|
(記録は記憶によったもので、上田さんがあらましを記し、小田さんが推敲したもの。参加者の確認をとったものではない。)
2013年3月16日(土)里仁篇
本日は、早川君、小田さん、成田君、上田さんの四人。里仁篇を音読。訓読と意味は小田さん。一揆では高津君が合流。
子の曰はく、位無きを患へず、立つ所以を患ふ。己を知ること莫きを患へず、知らる可きことを為すことを求む。
立つ所以は、其の位に立つ所以の者を謂ふ。知る可きは、以て知らる可きの實を謂ふ。○程子の曰く、君子は其の己に在る者を求むるのみ。
孔子が言われた、「地位の無いことを患うな。どうすれば地位を得る事が出来るかを患え。自分の知られていないことを患うな。知られるように努力をしなさい」と。
立つ理由とは、その地位に立つ理由のことである。知る可きとは、知られるべき実体をいう。○程子が言った、「君子は、自らのなかにひたすら己を求めるのみである」と。
小田:「立つ所以を患ふ」とは、どうしたら高い地位に付けるかということですかね。
成田:「所以」には、いくつかの意味があります。手段、理由、方法などです。手段、方法の意味とここで解釈すれば、言われるとおりの意味です。
小田:つまり、高い地位につけるための手段とか方法を考えて実行していないことが悪いのだ、反省せよというアドバイスなわけですか。
成田:だが理由の意味である、と取ると、位高い人が、どうしてそれほどの地位に立っているか、その理由をよく考えてみよ、ということになるでしょう。
上田:立たん所以は就職するというに限られますか。
早川:宋代になると、違った解釈が出てきました。人間たるもの、位に立つかどうかと人間としてどうかは別問題であり、君子は位があろうがなかろうがしかるべき人間として立っているべきことが大事なのだ、そうするための手段を考えよ、とこの条は言っているのだという解釈です。孔子の「三十にして立つ」と同じ意味なのだ、と解釈するわけです。地位にあくせくしない、立派な人格者となれというメセージなのだという、道学者的解釈です。だがそうすると、下の句とうまくつながらない問題が出てきます。だから一般的には、就職する者へのメッセージという意味で解釈せざるをえない。
成田:君子は位なんぞどうでもよいことで人間として一本立ちすればよいのである、と朱子なんかも本当は読みたかったのでしょうが、下と繋がらないから位に立つために己を磨け、という解釈になっています。
早川:上だけなら道徳として読むことができるが、「知らる可きことを為す」ですから就職する方法を言っている条なのだと全体を取るしかない。
小田:つまり、弟子たちに対して君たち効果的な就職活動していないだろう、だからどうすれば就職できるかよく考えてみろと、諭した章なのでしょうか。奥深さが全然ないですね。
早川:だが現代っぽくていいですね。
成田:知られるべきことをせよ、ということですが、いわば今風に言えば就職のために英検を受けるとかエントリーシートをどうするかといった手段を追うよりも、修身克己して己の身を修めてゆけばしぜんと声がかかるものだという意味でしょうかね。
小田:漢代とかの選挙ならば、修身して仁徳の人であるという評判が上がれば、やがて郷里の上役が役人に推薦してくれる道が開けたでしょうね。しかし、科挙が導入された以降では、仁徳が高かろうが試験に受からないと就職なんかできなくなった。仁徳だけではどうにもならない。
成田:孔子の弟子たちは、きっとエントリーシートを書くのはうまいような連中が多かったでしょう。そんな試験秀才たちが就職できないでカリカリしているとき、たまには論語でも読んで人間性を高めなさい、と諭すみたいなものでしょうか。
小田:いまどきの採用試験では、面接官は応募者のフェイスブックとかツイッターとかまで閲覧して、過去の素行も見ます。たとえ面接で格好のいいことを言ったとしても、フェイスブックとかツイッターに見える普段の行いや言動が劣悪だったならば、採用しないでしょう。今の時代の就職の秘訣は、普段から日ごろの言動を慎み、日ごろの行いをよく高めて総合的に使える人材だと見られることに気をつけなさい、ということになりました。だから、孔子の言葉はごく最近の時代になって、再び的外れではなくなりました。
成田:現代社会が当時に近づいている。
小田:大学一年生の頃から業績を作っておかないと、就活になってからにわかに取り繕っても認めてはくれない。もっとも、これが就職の秘訣となった時代には、いかに大学一年から表面を取り繕うべきか、という対策がまた現れるのですが。
早川:孔子の弟子も、就職するには先生に認められることが必要でした。澹臺滅明みたいに、孔子が注目せずとも自分で仕事をみつけてくるような人もいましたが。
小田:先生、就職の口を聞いてくださいと弟子が集まってくる。しかし、人格が善くないと先生は推薦しなかった。そうやって、孔子は就職をせびる弟子たちの尻尾を掴んで善導しようとしたのでしょうかね。
成田:そのような孔子の弟子たちへの教育方法を、荀子も受け継いでいます。荀子は、君子たるもの口先ではなく徳行を高めて国の人材となれ、と強調しています。
早川:荀子は、「人の性は悪なり。その善は偽なり」と言いました。「偽」とはこしらえものであり、人間の本性でなくて後天的に身につけたもの、という意味です。ニセモノという意味ではありません。人間は本質的に悪であるが、学んで善を身につける存在なのであるから努力しなければ君子になれない、ということです。荀子の性悪説は孟子の性善説への反論として展開されているのですが、君子は善となれと薦める点では両者同じであり、結論は両者ともほとんど変わりません。
次にゆきますか。
子の曰はく、參か、吾が道は一以て之を貫せり。曾子の曰く、唯。子出ず。門人問ひて曰く、何と謂ふことぞ。曾子の曰く、夫子の道は、忠恕のみ。
參は所金の反。唯は上聲。○參乎は、曾子の名を呼びて之に告ぐ。貫は通なり。唯は、應ずること速やかにして疑ふこと無き者なり。聖人の心は、渾然たる一理にして泛應曲當、用各々同じからず。曾子其の用處に於て、蓋し已に事に隨ひて精察して力めて之を行ふ。但に未だ其の體の一なるを知らざるのみ。夫子其の眞に力を積むこと久しくして、將に得る所有らんとするを知る。是を以て呼びて之に告ぐ。曾子果たして能く其の指を默契す。?ち應ずること速やかにして疑ふこと無し。己を盡くすを之忠と謂ひ、己を推すを之恕と謂ふ。而已矣は、竭(つ)き盡(つく)して餘すこと無きの辭なり。夫子の一理渾然にして泛應曲當、譬へば則ち天地の至誠息むこと無くして、萬物各々其の所を得るがごときなり。此より外、固に餘法無くして亦推すことを待つこと無し。曾子此に見ること有りて、之を言ひ難し。故に學者己を盡くし己を推すの目(もく)を借り、以て之を著明にす。人の曉り易からんことを欲す。蓋し至誠息むこと無きは、道の體なり。萬殊の一本なる所以なり。萬物各々其の所を得るは、道の用なり。一本の萬殊なるの所以なり。此を以て之を觀れば、一以て之を貫くの實、見る可し。或ひと曰く、中心を忠と爲し、如心を恕と爲す。義に於て亦通ず。○程子の曰く、己を以て物に及ぼすは仁なり。己を推して物に及ぼすは恕なり。道を違ふこと遠からず、是れなり。忠恕一以て之を貫く。忠は天道、恕は人道。忠は無妄、恕は忠を行ふ所以なり。忠は體、恕は用。大本達道なり。此れ道を違ること遠からずと異なる者は、動くに天を以てするのみ。又曰く、維天の命、於(ああ)穆として已まざるは、忠なり。乾道變化して、各々性命を正すは、恕なり。又曰く、聖人人を敎ふるは、各々其の才に因る。吾が道一以て之を貫くは、惟曾子のみ能く此を達せんと爲す。孔子の之に告ぐる所以なり。曾子門人に告げて曰く、夫子の道、忠恕のみ。亦猶夫子の曾子に告ぐるがごときなり。中庸に所謂忠恕道に違ふこと遠からず、斯れ乃ち下學、上達の義。
孔子が言われた、「參よ、私の道は一つのことで貫かれている」と。曾子が応えた、「はい」と。孔子が外に出られた。門人が質問して言った、「どういうことですか?」と。曾子が言った、「先生の道は、ひたすら忠恕のみである」と。
參は所・金の反切。唯は上聲。○「參乎」は、曾子の名を呼んで告げようとしているのである。「貫」は通ることである。「唯」は、返答が速やかで迷いがないことである。聖人の心とは、分離できない一つの理でありながら臨機応変であり、その応用は各々同じものではない。曾子はその応用においては、物事に従って詳しく観察してつとめて行うことがよくできる。だが、まだその本質が一つであることが分かっていない。だが先生は、まさに曾子が力を積みあげること久しくして、もう理解することが出来ると知っておられた。だから曾子を呼びつけて、告げたのである。曾子は見事にそれを察して、暗黙に了解した。だからただちに返答し、ためらいもなかったのである。己を尽くすことを忠といい、己を推しすすめることを恕という。「而已矣」とは、とにかく尽くして尽くして余りが無いという言葉である。先生は一理渾然でありなおかつ臨機応変である。譬えるならば、天地の至誠が止むことなく、萬物各々がしかるべき位置を得るようなものである。この他には、もとより余すところの方法なく、また他に推すことなどもない。(忠恕のみで、これ以外にはない、唯一無二のもの)。曾子はこれを見ることが出来たが、言うことが難しかった。だから学ぶ者は己を尽くし己を推すという徳目をかりて、これを明らかにした。人が悟りやすくさせようとしたのである。つまり、至誠が止むこと無いことは、道の本体である。あらゆることの根本が一つであることの理由である。万物がそれぞれその位置を得るのは、道の応用である。一つの根本からあらゆることが派生する理由である。そういうことで、一でもって貫く実体を見ることができる。或る人がこう言っている、「中心を忠と爲し、如心を恕と爲す。その意味においてまた通じる」と。○程子が言っている、「自ら物に及ぼすことは、仁である。自らを推して物に及ぼすことは、恕である。道から去ることが遠くないのは、これである。忠恕、一を以てこれを貫く。忠は天道であり、恕は人道である。忠は無妄(天道による)であり、恕は忠を行うゆえんである。忠は本体であり、恕は応用である。大本達道である(一つの根本、基点が色々な道に通じている)。これが道から去ることが遠くないことと異なるのは、動かすのが天であることのみである(動く大本は天にある)。また、こうも言う。『維天の命、ああ、よきものにしてやまない』。これが、忠である。乾道(天道)が変化して、各々性命を正すことが、恕である。またこうも言う。聖人が人を教えるのは、それぞれのその才による。『吾が道一を以てこれを貫く』とは、ただ曾子のみが見事に達せんとしていたからである。孔子が曾子に告げたゆえんである。曾子は門人に告げて言った。『夫子の道、忠恕のみ』と。それはまた、先生が曾子に告げた、その両者の応答に類比すべきものである。中庸にいうところの『忠恕道に違ふこと遠からず』とは、まさしく下学して上達するという意味である」と。
小田:長い!
成田:大論文ですね。読むだけで一仕事した感に襲われます。
小田:「曾子曰く」は、「そうしのいはく」と読むのですか。曾子の場合は「のたまはく」ではないのでしょうか?
早川:そう読む場合もあります。
成田:三段階あります。「~がいはく」が一番下であり、それより上が「~のいはく」であり、一番上が「~ののたまはく」です。曾子は、孔子ほどに格が高くない。
小田:衛霊公篇3に「子の曰はく、賜、女、予を以て多に學びてこれを識る者と為すか。對へて曰く、然り。非ざるか。曰はく、非ざるなり、予は一にして以てこれを貫けり」。また、同24に「子貢、問ひて曰く、一言にして以て終身行ふべき者有るか、子の曰はく、其れ恕か、己が欲さざる所人に施すこと勿かれ」とあります。これらの条での朱子注を先走りして読んでみたのですが、朱子は子貢より曾子を格上とみなしています。子貢は、曾子にまで至らない格下であると。
早川:「曾子」とわざわざ敬称で呼ばれていますからね。ただの字(あざな)の子貢とは、呼び方だけで格の違いが表現されています。
小田:いつから、曾子の格が上がったのでしょうか?
成田:孟子の時点でしょう。孟子は、すでに曾子と尊称しています。曾子は、後世に続く弟子がいた。子貢の後継者といえば、しかしよくわからない。弟子がどれだけいて、それが儒家の主流となったかどうかで源流が持ち上げられます。子貢は弟子をとって教育するタイプではなかった。
小田:朱子は徳のランクとして、子貢より曾子が上としているわけですが。孔子―曾子―子貢だと。しかし、この解釈は妥当でしょうかね。
成田:だが同じ敬称つきでも、有子は朱子にそこまで評価されていません。曾子は、『孝経』を書いたとされます。
早川:『大学』も曾子による、といわれることがありますが、これは古い説ではない。
小田:しかし、四書に比べると『孝経』は朱子によってそれほど高く評価されていないように見えます。
早川:唐代には、孝経は玄宗皇帝に喜ばれて、大層流行したものです。
成田:孔子の弟子たちの中で、儒教のテキストで「経」と名付けられた書を書いたとみなされたのは、彼だけです。
小田:さて本文に戻りますが、ここでいう門人は、曾子の門人ですしょうか。それとも孔子の門人でしょうか。
早川:曾子は孔子より46歳若いので、孔子の晩年では29歳以下でした。その彼に弟子がいる、というのは僭越でしょう。だから孔子の門人でいいのでは。
成田:孔子と曾子のこの対話は、うまくできすぎていると思います。
小田:問答のかみ合い方が、いかにも文学的です。
成田:ここまでうまくかみ合っている問答は、むしろ作為を感じます。
早川:いわば拈華微笑(ねんげみしょう)の境地ですね。お釈迦さまが、レンゲの花を手でひねっていた。何も言わず、ただそれだけであった。並居る弟子たちの中で、摩訶迦葉(まかかしょう)だけが理解して、微笑した。言葉でなく、師と弟子が分かり合った。孔子と曾子のこの対話は、そんな境地に見えます。
上田:何が分かったのですか。
小田:それは、言葉で言うことができない。不立文字(ふりゅうもんじ)です。
早川:不立文字ですから、言葉にされていない。以心伝心です。こうして仏教の奥義が摩訶迦葉に伝わり、遠い時と空間を隔てて達磨に伝わった。これが、禅宗の大本の話です。
小田:しかし、衛霊公篇での孔子と子貢は、この条と同じテーマをはっきりとした問答で展開しています。子貢に対して、孔子がお前は俺のことを誤解してるだろう、とブーたれて難癖を付けた。だったら先生の一をもって貫くとはなんなのですか、と子貢が聞けば、孔子は自ら「そりゃあ、恕だよ」と明言した。こちらの問答のほうが、文学的ではないですがリアリティがあるように見えます。孔子と曾子は、歳が離れすぎています。曾子あたりの若手の弟子たちは、きっと先生と心を通わすような師弟関係まではいかなかったでしょう。これは、想像です。この対話は、孔子が若い弟子たちに言った謎めいた言葉に対して、曾子だけが分かったと答えた。子張あたりの若い弟子は、先生の真意がわからない。それで曾子に聞いたら、彼はズバッと答えた。それで若手たちが、曾参さんスゲーぜ、と賞賛した。そんなエピソードが大元だったのかな、などと思ったりします。その後ろで、先進の子貢あたりは若手どもの会話を後ろでニヤニヤしながら見ていた風景なんか、どうでしょうかね。いやあ、あのオッサンはなあ、君らの想像とは違うお人なんだぜ?とか考えながら(笑)。
成田:曾子は子路や子貢や宰我のように、孔子に突っ込みを入れたり、孔子に突っ込まれたりするようなことはない。教える者と学ぶ者という、通常の師匠と学生の関係だったでしょう。子路や子貢は諸国放浪を共にした、むしろ孔子の仲間だった。通常の師弟関係からは、彼ら先進は外れていたことでしょう。
小田:半ば同志ですね。
成田:死線を共に潜り抜けてきた。
小田:曾子は、孔子の放浪に付いて行ったのでしょうか?
成田:どうでしょうねえ。ないんじゃないか。
早川:もし付いていったとすれば、年齢からすれば10歳頃ですから。
小田:親父さんに連れまわされていた、とか?
成田:だが、親父さんがいつ孔子の弟子となったのかも、はっきりしない。
早川:息子を弟子入りさせるついでに親父も弟子入りした、という可能性もあるのでは?
小田:以前ご紹介した武内義雄先生は、戦前に『論語の研究』を出されました。先生の考証をなぞると、論語の上篇は学而篇と郷党篇を除いておおむね魯の曾子学派の伝承である。論拠は、まず第一にこれらの篇の言葉は曾子学派の末裔である孟子の引用と重なるものが多いことと、次に曾子が大活躍することです。いっぽう下篇は、上篇よりも雑多な学説が混入しているものの、その核心は子貢から始まる斉学派の伝承であるのではないか、と見ておられる。論拠は、まず第一に子貢に関する引用が多く、子貢を賞賛していること。第二に曾子が貶められていることです。(詳しくは2011年8月27日参照)。里仁篇では曾子が孔子を理解し、衛霊公篇では子貢が孔子を理解する役目を与えられています。これらは、武内先生の考証に従うならば、編集者の立場を反映しているのではないか。つまり、この里仁篇あたりを編集した魯学派としては、源流の曾子を賞賛しなければいけない。実際は、この条のような言葉を孔子は全ての弟子に言っていたのではないでしょうか?いわば弟子への謎かけであり、「予は一をもって貫いているのである。その一は何であるかが、今日の宿題だ。明日までに考えておけ」あたりですかね。
早川:問題の出し方として悪くない。
小田:子張なんぞは、一は禄でしょうかね、それとも利でしょうかね、などと言ったのかもしれない。
早川:たった一言だけで孔子が去る。この条は、文学的要素が高い。
成田:孔子が出て行った。果たして、本当の答えがそうであったか。
小田:だが衛霊公篇では、孔子自ら「恕」と断言しています。
成田:本当に孔子にとって、正解が一つであったのか。
小田:渾然一理ということですか。孔子が言いたかったことは、言葉にすれば嘘になるというか、、、
早川:この条の構成は、孔子は根本を一であると言った。それを曾子が言葉で分析したとき、忠恕の二文字になった。この構成が、哲学的展開を誘っているかのようです。
成田:本当は、仁というべきであったかもしれない。しかし仁の一字では、発展がない。それを曾子が忠と恕と必ずしも一致しない意味の二文字で展開した。朱子の解釈は、言葉にならざる真理を言葉にするとき多様に展開されていくという哲学的ストーリーに沿っています。
小田:衛霊公篇では「恕」としか言いません。だがこれでは発展がないですね。
成田:孔子が意図していた一は、恕だけにとどまらなかった。それで、恕と違う忠を付け加えた。
早川:テレビドラマのタイトルは、「恕の人、孔子」でしたね。
成田:製作者が、「仁の人、孔子」では理解しがたいので、もっと絞った意味の恕を採用したのではないでしょうか。
小田:とすると、現代中国語でも「恕」の一字はすぐ理解できるのでしょうか。日本語ではこの字はめったに使われないので、ニュアンスが思いつきません。
成田:「恕」の字は、今でも頻繁に使われています。饒恕、寛恕、とか。寛恕だと、どうかおゆるしください、ということです。見逃す、許すという意味があります。だがこのニュアンスは孔子の使った恕の用法と同じかといえば、そうでもない。
小田:では、現代中国語のニュアンスでは、「忠恕」は真心からゆるす、というイメージでしょうか。
上田:忠というのは自分が自分自身を生きる、しかし、自分を生きることしか考えなく、他人のことがわからないでは困る、他の生き方も受け容れることができねば困る。それが恕じゃないですか。
成田:言われているのは、そのまんま朱子の解釈に沿っています。
早川:思うに、孔子は晩年に忠恕と理解したのでしょう。
成田:この条の言うことは、まるで六十にして耳順う、七十にして心の欲するところに従えども矩を踰えず、という孔子の心境のときに発した言葉ならば分かります。しかし子貢とかなら分かっているでしょうが、孔子が若い時は恕の人とはいえなかったのでは?
時間となりました。一揆では高津君が合流。税申告の期間が終わりやっと解放されたということでしょう。
2013年3月23日(土)孟子梁恵王章句下
本日は、小田さん、上田さんの二人。士心で行い、その後、店長と店員さんとも交流。4月6日に備える。
魯の平公將に出でんとす。嬖人(へいじん)臧倉(ぞうそう)といふ者請ひて曰く、他日君出でれは、則ち必ず有司に之く所を命ず。今乘輿已に駕す。有司未だ之く所を知らず。敢へて請ふ。公の曰く、將に孟子に見んとす。曰く、何ぞや、君の為る所、身を輕んじて以て匹夫に先んずは、以て賢と爲るか。禮義は賢者より出づ。而るに孟子の後の喪、前(さき)の喪に踰へたり。君見ること無かれ。公曰く、諾。樂正子入りて見(まみ)へて曰く、君奚爲(なんすれ)ぞ孟軻を見ず。曰く、或ひと寡人に告げて曰く、孟子の後の喪、前の喪に踰へたり。是を以て往きて見ざる。曰く、何ぞや、君の謂ふ所の踰へるとは、前には士を以てし、後には大夫を以てす、前には三鼎を以てし、後には五鼎を以てするや。曰く、否。棺槨衣衾の美を謂ふ。曰く、謂ふ所の踰へるに非ず。貧富同じからざればなり。樂正子孟子を見て曰く、克、君に告(まう)す。君爲に來り見るなり。嬖人臧倉なる者有り。君を沮(とど)む。君是を以て來ることを果たさず。曰く、行くも之をせしむること或り、止まるも之を尼(とど)むる或り。行止は人の能くする所に非ず。吾がこれ魯侯に遇はざるは、天なり。臧氏が子、焉んぞ能く予をして遇はざらしめん。
魯の平公がちょうど出かけようとしていた。お気に入りの家臣の臧倉が質問した、「慣例では、我が君がお出かけの場合、必ず役人に行く先を命じておられます。今我が君はすでに車にお乗りになっていますが、役人は行く先を聞かされていません。敢えてお伺いします(どちらに行かれるのでしょうか?)」と。魯公が言った、「孟子に会おうと思っている」と。臧倉が言った、「何ということを我が君はなさるのですか。我が身を軽くして、庶民の所にでかけようとされています。それで賢と言えるでしょうか?礼義とは賢者より出るものです。ところが孟子の母の葬儀は父の葬儀を越えていました。我が君は会うべきではありません」と。魯公が言った、「そうだな」と。樂正子が入ってきて、魯公に見(まみ)えて言った、「我が君よ、どうして孟軻を謁見されませんか?」と。魯公が言った、「ある人がそれがしに告げてこう言った、『孟子の母の葬儀は、父の葬儀に越えていた』と。これによって、出かけて会う事をやめた」と。樂正子が言った、「何ということをおっしゃる。我が君の言われる『越えていた』とは、父には士の礼を以てし、母には大夫の礼を以てしたことであり、父には三鼎を以てし、母には五鼎を以てしたことですか」と。魯公が言った、「そうでない。棺(柩)槨(柩を容れる)衣(肌に付ける)衾(衣に付ける)の華やかさを言っているのだ」と。樂正子が言った、「それは越えていることにはなりません。(父と母では孟子の)貧富が違っていたからです」と。樂正子は孟子に会見して言った、「克(それがし)が我が君に申して、我が君は会見しようとされていました。ところが、お気に入りの家臣の臧倉という者がおり、我が君を止めてしまいました。我が君はそのために来ることができませんでした」と。孟子が言った、「(人たるもの)行くも行かせるものがあり、止まるも止めるものがある。行くこと止まることは、人が能くできることではない。私が魯侯に遇うことがないのは、天がすることである。臧家の子せがれに、どうして私を遇わさせないことができようか?」と。
小田:孟子は、おそらく斉を出た後は宋、滕、魯の順で動いたのでしょう。ここでは「匹夫」とありますから、つまり何の役にもついていなかったことが分かります。おそらく孟子の遊説活動は、魯で終わったと思われます。孔子の晩年には弟子たちが各地で役職に就いていたように、孟子の晩年には樂正子が魯で役職に就いていました。孟子の弟子で出世した人物で分かっているのはこの樂正子くらいのもので、しかも落ち目の魯に仕えたくらいでした。孟子には、孔子のような出世した弟子が多くいなかったようです。
上田:行或使之止或尼之ですが、之とは代名詞ですか、動詞ですか。
小田:代名詞でよいのでは。もっとも之(ゆく)と読んでも、意味は大きく変わらないでしょう。
上田:こういう格言でもありましたか?
小田:どうですかね。文法的にはおかしくない。使を単独で「させる」と読ませるのは、ちょっとイレギュラーですが。
上田:何故「尼」の字をここに使いますか?
小田:趙岐の注に尼は止と読むとしており、伝統的にそう読んで来たのでしょう。
上田:尼はníで僧、あま、nìでは泥、渋滞す、また安んず、和す意味がある。行は現代中国語ではよろしい、支障なしです。或を有ると読ませている。或は~することもあれば~することもあるで決定的な言い方ではない。行或使之とは、うまくゆけば行かしめる。止或尼之は行くことを安んず、ぐずぐずさせ、やめさせることもあるみたいな読みができませんか。
小田:行くも之をせしむること或り、止まるも之を尼(とど)むる或り、で いいんじゃないですか。「或」を用いているのは二句を並列させたからで、「尼」の原義はおっしゃる通りやめさせる、とどめるという意味でしょう。「あま」の意味は、仏教の比丘尼(びくに)を略して「尼」と呼んだところから始まるわけで、後世に始まった新しい用法です。
上田:魯公に会う事がないのは天の采配、朱熹も大いにそうとしているが、とってつけたようで、それほどのことですかね。
小田:孟子は公孫丑章句の末尾近くの章で、「夫れ天、未だ天下を平治せんと欲せず。如し天下を平治せんとせば、今の世に當りて、我を舍いて其れ誰ぞ」の言葉があります。また尽心章句の末尾でも、同様に私の言っていることは正しい、だが時代が間違っていると怒る章を置いています。この梁恵王章句の末尾の章も、きっと同じ意図なのでしょう。孟子が遊説したが成果を修めることができないのは、孟子の主張が間違っていたのでは断じてない。まだ天が天下に安寧をもたらそうと望んでいないから正しい孟子の主張が広まらないのだ、これは天の意志なんだ、と言って自己を正当化して終わっているのです。
上田:孟子はそう言うとしても、当時の人はそんな風には思わない。
小田:孟子は斉でも宋でも私の主張を容れたならば天下の王となる、と大見得を切ったわけで、しかし実際はそんなことはなかった。しかし自分の言っていることは絶対に間違いが無いという自信があり、天の巡りが悪いだけのことであると言い切るのです。儒家の親玉として、言い切らなければならなかった。
上田:気持ちは分からないでもないが、大袈裟。
小田:私は絶対間違っていない、という悲痛の叫びが聞こえますがね。
上田:孟子が滕に行った頃は薛に孟嘗君が居り、斉の宣王は孟子ばかりか、合従策を唱える蘇秦、連衡策を唱える張儀など諸子百家の論客に会っている。各国が生き残るために、内政外交に携わっていた人々が、孟子の言を聞いて、その通り、政策は間違っていない、天の巡りが悪い、と同意したとは思えない。
小田:前にも申し上げたように、孟子は政策を考える政治家というよりは思想家であり、儒家として王道を説きました。列国の王たちも、天下の王となるためには軍事力や経済力だけでは不足であることは、認識していたはずです。足りないものは、正義のお墨付きでした。だから孟子の言う王道政治のイデオロギーは、王たちにとっても必要であるとして受け取られたはずです。だから、孟子が召抱えられたのです。外交とか政策の立案者としてではなく、むしろ思想の卸元としてです。遡って孔子の集団は、その中に儒家だけでなくて法家や縦横家の萌芽的考えまで含んだ政治家たちを含んでいました。しかし孟子の頃には、それぞれが専門化して一家を成し、相対立するようになっていた。孟子は、墨家や道家や法家や縦横家を批判して、儒家集団の存在意義を主張しなければならなかった。孟子の時代の儒家に、何が残っていたでしょうか?それは、周代の政治が何がなんでも正しいという復古思想だけであり、具体的には宮廷の礼楽儀式と、古の王たちが依存した正統性の思想でした。だから孟子は、縦横家や法家のごとき時代に即した政策を主張するのではなく、ただ古のことを賛美することに特化した。特化せざるをえなかった、というべきでしょう。
上田:その点は、おっしゃるように、孔子と孟子を見る場合に大きな相違点となる。現代世界にあっても、日本が生き残るために、王道を貫け、そのことでたとえ核ミサイルをブチ込まれようと必ず将来その善政により王者が現れよう、私は絶対間違っていない、天の巡りが悪いだけだ、で納得しますかね。
小田:そりゃあ、しないでしょう。時代の現実に対処すべき柔軟なアイディアが、どうしても別に必要となるでしょう。これからの章で孟子の井田法が出てきますが、孟子は周公の制度だからこれを復古して導入しなさい、と薦めました。しかし、井田法はいわば原始共産制の復活であり、未開素朴な時代であれば有効であったかもしれないが、経済が発達した戦国時代には到底実現性がなかった。孟子は、これを儒家の具体的な政策として思想とセットで売り込んだわけで、周公の制度だから正しいのだ、ということを正統性の根拠にして売り込んだのです。
上田:成程、周公の制度ですか。民を安んずという考え方が基本にあるといいながら、其れを制度的に組み込むことはなかった。孟子の政策に関しては、滕文公章句で検討できればいいのかなと思います。
小田:孟子は、幸いにも(?)彼の言う儒家の経済政策が大国で採用されて、結果を見ることがなかった。滕では井田法が実施されたかもしれませんが、その結末は分からない。儒家が天下を取った漢代になれば、その時代の儒者たちは井田法などにもはやこだわりませんでした。民の利益を損なわないように国は規制したり税をかけたりすることを極力控えるべきだ、とか言うようになりました。この経済政策は、もはや道家的というべきです。儒者たちも、実際に国政に参加する立場ともなれば、このように柔軟に主張を変えていったのです。それを周代の制度に無理やり戻そうとした王莽は、無残に失敗して滅びました。こうして、孟子の言うような周公の復古政策は間違いであることが、具体的に実施して分かったわけです。そもそもが、『孟子』は唐代に韓愈が道統論を立てるまでは、さほど重要なテキストとみなされていませんでした。『孟子』は『荀子』などと並んで、孔子以降の儒家のテキスト群のひとつとして伝承されたに過ぎなかった。それが、韓愈によって孔子の後を継ぐ唯一の正統的後継者として称揚されることになり、後世に孟子が爆上げされて荀子が凋落するきっかけを作りました。この韓愈の評価の根拠は、純粋に思想的な評価です。韓愈以降は、『孟子』を戦国時代の政策論として読むことはなくなり、時代を超えた思想書として読まれることが決定しました。だから、具体的な孟子の外交とか経済政策とかは、問題にしない読み方が正統となったのです。
上田:そうですか、韓愈までは孟子は評価されていなかったんですか。
小田:荀子などと、差はありませんでした。だが宋代には、両者の価値は比較にならないほど広がりました。
上田:現代も孟子が生きた時代と同じく、高度に専門化した世界で、専門的な裏付けのない話はど素人のたわごとになる。その中で全体を見渡せる思想が必要ということですが、諸子百家を生みだした中国が今後どういう思想を取り入れるのか。
小田:中国は、いまだ貧しい層が大量にいる現状ですが、沿岸部などでは一定の所得水準を得る層がすでに生じ始めています。いわば中進国段階に入っているわけであり、この段階になれば人々は飢えなければよい、明日生きていればよい、といった欲求だけでは済まなくなるでしょう。インターネットの検閲とか、自由の抑圧とかに、今後の二十年間にまだ我慢できるのだろうか。孟子の言葉を借りるならば、民を尊しとなし、君を軽くするです。民の欲求が飢えなければよい、という水準ならば不自由でも許されたでしょうが、今後は抑圧に耐えられなくなった階層の声を聞かなければ、統治が危うくなるのではないでしょうか。また、中進国の段階に進んだということは、国際競争の面から見たならば、低賃金の魅力が失せてしまうことになります。経済に、創意工夫が必要となる段階であり、それがなければより低賃金で規制の少ない東南アジアに海外企業が向かうだけであり、現に向かいつつあります。創意工夫の経済に向かうためには、民度を上げる政策を取り、より自発性を高める教育を行い、そして非能率で腐敗した行政を改めならないでしょう。民の欲求の変化に対処し、経済の変化に対処する課題は、鄧小平からこのかた20年の政策とは異質の手段を用いる必要があるのではないでしょうか。
上田:鄧小平以降の20年は、突出した政治家がいたわけではないように見えます。しかし、きっと後世には成功した時代と呼ばれるのでしょう。ともかくも世界第二位の経済大国になったのですから、後世の評価は高くなるでしょう。ところが今を生きている我々は、何がよかったのかが判然としませんし、共産党幹部や役人は農民を搾取してひどい格差を生んでおり、ほめられたものではないし、素晴らしい思想にもとづいているとも思えない。時の勢いというか、それに皆がのっかっていったわけです。それからはずれると何を言ってもはじまらない。
小田:おっしゃるとおり、たとえば日本の60年代70年代の政治家たちが、他の時代の政治家より優れていたかといえば、それほどでもなかったでしょう。しかし、あの時代の日本は大いに進歩した黄金時代でした。いわば、天の時が味方していたので誰が政治家であってもうまくいった時代であった、とも言えるでしょう。それに比べれば、今の時代の日本は天の巡り合わせがよろしいとは言えない。そんな時代に生きるとなすすべがないのかといえば、私は決してそうではない、と思います。ローマでもイギリスでも、黄金時代を過ぎた後はある時期に大変に混乱しながらも、結果的にその状況に合わせ政策を行う立案者たちが登場することによって、あるいは次善の安定時代を実現したり、力を後退させながら別の国際的枠組みを演出して国を維持したりなどを行っていました。天の時が順調な時代よりも課題が大きい時代であるからこそ、より賢明な政策が必要であると言えるのではないでしょうか。
ということで、士心のビールを傾け延長戦となりました。
2013年3月30日(土)里仁篇
本日は、早川君、小田さん、成田君、上田さんの四人。小学校の桜も満開。今年は開花が早かった。里仁篇を早川君のリードで音読。訓読と意味は小田さん。
子の曰はく、君子は義に喩(さと)る。小人は利に喩る。
喩は猶曉のごとし。義は、天理の宜しき所。利は、人情の欲する所。○程子の曰く、君子の義に於るは、猶小人の利に於るがごとし。惟其れ深く喩る、是を以て篤く好む。楊氏が曰く、君子、生を舍て義を取る者有り。利を以て之を言はば、則ち人の欲する所、生より甚だしきは無く、惡む所、死より甚だしきは無し。孰か肯へて生を舍て義を取らんや。其の喩る所は義のみ。利の利爲るを知らざるが故なり。小人は是に反す。
孔子が言われた、「君子は義をよく理解し(分かり)、小人は利をよく理解する(分かる)」。
喩は曉(さと)ること。義は、天理の宜しき所である。利は、人情の欲する所である。○程子が言った、「君子の義に対するあり方は、小人の利に対するようなものである。ただ深く理解し、これを篤く好む」と。楊氏が言う、「君子には、生を捨てても義を取る者がいる。利の観点でみれば、人の欲するものとして生より強いものはなく、嫌うものとして死より大きなものはない。どうしてそれなのに、あえて生を捨てて義を取るのであろうか?君子のさとる所が義のみだからである(反応するのは義である所にすぎない)。だから君子は、利が利であることを知らないのだ(利益が利益にみえない)。小人はこの逆である」と。
小田:徂徠は例によって全く朱子とは違う解釈を取っています。義とは先王の古義であると言います。つまり、いにしえの王が定めた礼楽刑政の意義ということです。徂徠は、君子が利を望まないはずがあろうか、と批判します。政治を行う君子たるもの、統治される小人の利を理解しないと、政治を行うことはできない。君子と庶民とは、役割分担が違うにすぎない。庶民は利益を追求するが、君子はいにしえの王が定めたルールに従って政治を行う。孔子の言葉はこのことを言っているのであって、朱子が言うような君子と小人とで人格のレベルが違う、という解釈は誤りであると徂徠は批判しています。
早川:中国でも近代に近づくにつれて、徂徠のような解釈が台頭してきました。たとえば清の兪樾がそうです。朱熹は君子と小人を人品、品格から論じる。後世になると、君子と小人を階級の差としてとらえる考え方が現れました。明代清代は経済発展があって商工業が台頭し、利というものを排斥することが非現実的になったのが、解釈の変化の背景にあるのかもしれません。
小田:君子と小人を役割分担として捉える解釈が後世に台頭したと。そんな例、前にもありましたね。
早川:「利に放(よ)りて行はば、怨多し」ですかね。
小田:(むしろ一つ前の、「君子は德を懷(おも)ふ。小人は土を懷ふ。君子は刑を懷ふ。小人は惠を懷ふ」です。)後世になると、朱子とは違う読み方が発展していった。
早川:新しい解釈は、明清代に経済発展していた江南の人から出ています。実感として、利を排斥できなかった。
成田:商業の利益が簡単に得られない時代だと、利だけに依存するわけにはいかなったでしょう。今年は収穫が多かったとしても、来年はどうなるか分からない。そんなときに今年の余剰を貸し付けて利を貪ろうとしても、そううまくゆかない。そんな生産性の低い時代では、利に依存してやってゆくことはできない。やっぱり周囲との関係を保ち、善によってやってゆかなくちゃとなるでしょう。
早川:持ちつ持たれつの考え方の時代。
小田:明清代には利を追求しても目論見通りに成功できる時代的条件があったでしょう。しかし孔子の時代には、まだそんな余剰がある時代ではなく、商業はさほど発展してはいなかったはずです。当時の庶民は、今日明日を生きるに精一杯であったことでしょう。
成田:だから、かえってそんな時代の小人は、利によって簡単に落とされたとも言えるでしょう。食わせてやる、という利をちらつかせれば、小人たちを操作できた。むしろ、利に飛びついたでしょう。
早川:子路が貧しい人に粥を残した。孔子はそのやり方をよくないとした。子路は個人的に恩恵を施し、子路に個人的信望が集まるであろうが、それは政治の秩序を乱す行為であった。恩恵は政治がすべきことであり、子路の行為は政治のするべきことを乱した、と孔子は批判しました。
成田:貧者にも渡るように、税制をきちんとすべきだ、というのが孔子の意図だった。
小田:そのエピソードは、論語ではないですね。家語でしょうか?
早川:どうだったかな。孟子もまた、子産が冬の川を渡るのに難渋していた民を憐れんで自分の舟に載せてやったという美談を批判して、むしろ民を動員して橋を架けるのが政治家のすべきことだ、と言いました。
成田:子産は孟子から見れば政治家として小さい、というわけですかね。
小田:小人は、日々を生きることしか考える余裕がない。だからケダモノ同然であり、生き延びるという利にしか反応できない。だが君子は人間として判断しなければいけない。孔子の時代であれば、こちらのほうが説得力ある解釈だったでしょうね。
早川:孔子の時代に遡って考えたならば、やっぱり朱子の解釈のほうが正しいように見えます。陸九淵(象山)は朱子の良きライバルでしたが、彼がこの句を講義したとき、名講義として感動して泣き出すものがあった話があります。九淵と朱子は同時代人で、二人で直接会って論じ合い、ついに互いを理解できたという「鵝湖の会」のエピソードがあります。今の江西省に、天下四大書院の一つであった白鹿洞書院があり、これは朱子が復興したものでした。その白鹿洞書院に招かれて陸九淵が講演したのであるが、聴講者は涙を流して感動したと言います。
小田:講義の内容は、朱子の解釈と違っていたのでしょうか?
早川:いや、おおむね朱子と同じような方向での講義でした。しかし、どこに涙を流すほど感動したのでしょうかね。
小田:南宋代には貿易が盛んで、商業が栄えていました。思うに、商人が羽振りがよいのを横目で見ながら、誇り高い読書人たちはいまいましいと思っていたのでしょうか。そこで、陸九淵が君子は義に喩るのだ、諸君は君子だから利に喩る小人とは違うのだ、と言ったのでしょうかね。それで、一同そうだそうだと感動した。こんなところだったのかな。
早川:利で君子と小人が判別できる。君子が義に喩るは、君子たる努力をしている。小人は習によって利に喩る。
上田:覚、悟でなく何故「喩」を使っているのか。
成田:現在では比喩の「喩」ですが、古い時代には「喩」の字は「論(さとす)」の意味として用いられていたと思われます。論(さとす)と読むと、君子は義で論され理解する。
小田:そういえば、昨日中国・ベトナムでビジネスを手掛けている方と、話をしました。その方が言われるには、日本人と中国人とのビジネスのやり方は、両国の城の作りと同じである、と。日本の城は外堀・内堀を作り櫓を組み合わせ、城の中に入らせないように工夫しています。しかし中国の城は四方に門があり、三方を頑丈に作って一方だけをわざと開けておく。そうして、敵を城中に誘い込んで出られなくしてから、袋叩きにする戦法を取ります。これと同じで、日本人のビジネスのやり方は、ガードを固めてなかなか本丸の「契約」にたどり着かせない。相手の出方を見て、コミュニケーションを積み上げて行き、信頼できる関係を築いてからようやく契約をします。しかし、中国人のビジネスはまず最初に利益を取る、という結論からいきなり始めます。だから、この事業には「利」がある、儲かるということを愛想よく振りまき、まず契約から始めようとします。契約してしまったら、何が何でも「利」を取りに来て、その後に過程で生じたトラブルや計算違いなどを日本側が申し立てても、調整に乗らない。甘い「利」に釣られて城中に入ってしまった日本人は、ゆっくり料理されてしまうとか。このお話を今日の論語の言葉に当てはめるならば、日本人のビジネスは相手にいわば「義」を求めようとしているのではないでしょうか。信頼関係を作って、お互いに譲り合い調整する関係を作ろうとする。しかし中国人のビジネスは「利」を求めようとするのであって、儲かることが全てであり、大変に甘い儲けの話を持ち込む。そして、中途で起こった見込み違いについて、信頼関係から互いに調整しよう、と言っても受け付けない。ある意味、中国人のビジネスはドライで、わかりやすいとも言えるでしょうか。義とか信頼とか、無形の関係を求める日本人とはちょっと違うようです。
成田:中国人でも、日本人的な考えでいきたい、と思っている人はいるでしょう。ただ、それでは中国で成功しないので、成功者たちは結局利を望む人たちで占められるのかもしません。
早川:中国の経営者たちは、60ぐらいになると「義」とかを強調するようになる人が多いです。自分の人生が「義」によって貫かれていた、と本気で信じているようです。
成田:六十になって、「耳順ごう」となったのかもしれないですな。中国の全ての大学に建物を寄付したりしている人もいます。どこの大学に行っても、その人を記念した建造物がある。そのような成功した人が社会に還元することは中国であるし、西洋でも普通です。しかし、日本ではあまり目立たないです。
子の曰はく、賢を見ては齊(ひとし)からんことを思ひ、不賢を見ては内に自ら省みる。
省は悉井の反。○齊を思ふは、己も亦是の善有らんことを冀(ねが)ふなり。内に自ら省みるは、己も亦是の惡有らんことを恐る。○胡氏の曰く、人の善惡の同じからざるを見て、諸の身に反せざる無ければ、則ち徒に人を羨みて自棄すること甘んぜず、徒に人を責めて自責することを忘れず。
孔子が言われた、「賢い人を見たら、その人と等しくなりたいと思いなさい。賢くない人を見たら、自分にもないかと心中を反省しなさい」と。
省は悉と井の反切。○等しくなりたいということは、自分もあのように善でありたいとこいねがうことである。内に自ら省みるとは、自分にも同じ悪があるのではないか恐れることである。○胡氏が言った、「人の善悪が一様でないことを見て、わが身に反省しないことがないなら(常に反省していれば)、いたずらに人を羨んで自分はダメだと甘んじることはなく(自己の向上を怠らない)、いたずらに人を責めて自分を責めることを忘れることもない」と。
成田:「賢」は現代語では知能が高い意味ですが、もとの意味は知能のことではなくて、人より優れていることです。日本語の「かしこし」も、本来の意味は位が高い、という意味でした。
上田:仁でも義でもなく、賢としたのは何故ですか。
成田:仁や義は絶対的なもので、他との比較ではない。不仁、不義は比較して劣っているという意味ではなくて、絶対的な悪として用いられます。他方、賢は自分よりすぐれていることであり、比較して相対的な位置を示しています。不賢とは、自分よりも劣っているという意味です。
上田:比較が可能ということですね。
成田:「子貢問ふ。師(子張)と商(子夏)や孰か賢れる(先進篇)」の賢です。他と比べて上となる。
上田:賢の反対は愚でなく不賢。
小田:しかし、愚では劣っているという意味にはならないでしょう。
成田:賢の反対概念は、古くは「不肖」でした。賢不肖、と用います。賢の反対概念として愚が使われるようになるのは、もっと後の世のことです。
小田:愚はのろいとか、鈍いとかいう意味でしょう。
成田:「柴や愚、參や魯、師や辟、由や喭(先進篇)」とある。
小田:愚と魯の意味は、違いがあるのでしょうか。
成田:だいたい同じですね。愚鈍とも魯鈍とも言いますから。
子の曰はく、父母に事るに幾(やうや)く諫む。志の從はざるを見ては、又敬して違はず、勞して怨みず。
此の章、内則の言と相表裏す。幾は微なり。微諫は、所謂父母過有らば、氣を下し色を怡ばし、聲を柔らかに以て諫るなり。志の從はざるを見ては、又敬して違はず。所謂諫めて若し入られずんば、敬を起し孝を起し、悦べば則ち復諫るなり。勞して怨みずは、所謂其の罪を郷黨州閭に得んよりは、寧ろ熟して諫む。父母怒りて悦ばずして之を撻ち血流すも、敢へて疾怨せず、敬を起こし孝を起こすなり。
孔子が言われた、「父母に仕えるには、ゆるゆると諫めるものだ。自らの意図に従ってくれないのを見たら、また敬愛してそむいてはいけない。汗かいて働いても、怨まない」と。
この章は、礼記内則篇の言葉と表裏一体である。幾は微(かすか)なことである。微かに諫めるとは、(内則篇に)言うところの、父母に過失があれば、不満を顔に出さずにこにこして、声色を柔らかにして諫めることである。もし父母が自分の意図に従ってくれないならば、また敬愛してそむいてはいけない。諫めてもし入られないならば、敬愛を起して孝心を起して、父母が喜べば、また諫めるのだ。労して怨まないとは、(内則篇に)言うところの、父母がその罪を郷党や州閭(しゅうりょ)で得るよりは、むしろ繰り返して諫めることである。父母が怒って悦ばず、鞭打って流血の事態となったとしても、あえて怒って怨むこともせず、敬愛を起こして孝心を起こすものである。
成田:「労して怨みず」は、自分が苦労しても怨まない、のではなくて、むしろ父母のために汗をかいて労働しても怨まない、という意味だと思うのですが、朱子の解釈を見るとそうではないように見える。ぶん殴られる苦労をしても怨まない、と言っているわけで、これは父母からひどい目に会わされても怨まないことだと朱子は読んでいるということです。
早川:この朱子の注は、礼記内則篇の引用で成り立っています。「父母有過、下氣怡色、柔聲以諫。諫若不入、起敬起孝、説則復諫;不説、與其得罪於郷黨州閭、寧孰諫。父母怒、不説、而撻之流血、不敢疾怨、起敬起孝(礼記;内則)」
成田:朱子はこの章を内則篇で書かれていることだと解釈したのですが、この条はそのように読むべきかどうか。
早川:この倫理観は、現代人には受け入れられないでしょう。
小田:何があっても、親に敬と孝を起こすべし、とこうして礼記に書いているわけです。孝は中国人にとって無条件服従の掟と化してしまったわけで、陳独秀が孝を中国人を堕落させた害悪として糾弾したわけです。
早川:虚心坦懐に読んでみても、中国の孝は血にからむ。二十四孝といい、列女伝といい、書かれている内容は結構血なまぐさくて凄惨です。人間倫理を説いたものが、どういうわけか非人間的な世界となっている。
成田:説教では、極端なことを言っておくぐらいで丁度よい、ということでしょうか。偉人伝みたいなもので、野口英世の超人的人生を美談として説くが、誰もが野口英世みたいな人生を送れるはずがない。それと同じでしょうかね。
早川:貝原益軒の「女大学」は、女が読むから許せるのだと言います。女が読むから、書かれている極端なことでも受け入れて適当に調整できる。しかしこれを男が読んで、女に書いてあることを要求するのは、間違いというものです。
小田:子供に対して、最初から極端な例を挙げてしつけておけば、心にしみつくという教育的効果でしょうか?
早川:しかし、そのやり方が初等教育としてふさわしいかどうか?
小田:二十四孝なんかは、読書人が真面目に読む代物ではないでしょう。むしろ大衆本であり、わかりやすくしかもショッキングであるから受けたのでしょう。
成田:普通人でもできる孝行話では、本にしても誰も読まないでしょうね。
早川:だから、極端な例を出す。
上田:内則によると、子は早起きして、身支度を整え、仕事の用意をし、用具を整え、履をはきそして父母に仕えるという世界。新入社員がいきなり社長に仕えるようなもので、諌めるどころではない。そのなかでゆるゆる諌めるなど、諌めることにはならない。孔子自身若くして両親をなくしており、孝行をするということはなかったのではないか。
早川:家語の付録として孔子年表があり、それによると母親は孔子が二十四歳で亡くなったとされています。だから、家語の年表によるならば、少なくとも母親には仕える機会がないとは言えなかった、ということになるでしょう。
小田:史記列伝では、孔子の母親が死んだのは十代となっていませんでしたか?
早川:そうなっていますね。どちらが正しいのかは、わからない。しかし孔子は父親であったわけで、自分の息子との関係は明確にありました。息子に対しては、孝を教えなければならなかったのではないでしょうか?
成田:どうかな。放浪時代などは、息子は魯に置きっぱなしだったのでは?
小田:孟子は、君子は自分の子を教えることはしないのだ、と言っていました。子に正義を教えなければならないが、親が言っている正義に従っていないならば、子から言ってることとお父さんがやってることが違うとツッこまれる。これでは親子の情愛が台無しになるから、子を教えることはしないのだ、というのです。(離婁上、十八)孟子は、親子の間で情愛と建前の正義とは相反する、と気づいていました。孔子も、自分の子には建前を説教できなかったんじゃないか、と私は思います。むしろ、この条の言葉は、弟子たちに向けたものでしょう。弟子たちには父母がいて、子もいるのですから。
成田:今とは違い、この時代はだいたい子が親の仕事を継ぐものでした。子がある程度育てば仕事仲間となるわけで、親と子は常に一家で関係を持たなければならなかた。だから、互いの軋轢もまた避けられないものだった。だから、孝を言わなければならなかった。
早川:親子の不和はおおきな問題となる。
小田:口酸っぱくしても不和を抑え込まないと、一家離散となって家が滅亡してしまう。孝は、だから生存上必要であったとも言えるでしょう。
早川:古代の孝は、今流の言葉でいうと、なんとかコンプレックスの状態に見えます。親孝行コンプレックスというか、強迫観念のように孝を追及している。そこが、現代人に違和感があります。
成田:福祉国家でないので、孝は老後の生活保障という社会政策的意義もありました。
小田:結局、古代の孝は経済的必要性に裏打ちされていたから強固に守らなければならなかった、ということでしょうね。だから、コンプレックスのように見える。西洋でも、プロテスタントが広まった地域とカトリックに留まった地域では、家族構成が違っていたという研究を読んだことがあります。カトリック地域は大家族で、家族内での協力が経済的に必要だった。だから、家族道徳を重んじるカトリックに留まった。プロテスタント地域は独立家族であり、子は育てばもう親と対等の関係になって独立する。親は子が育ったら、育てた費用を請求するぐらいです。ここでは、孝の倫理は完全に解体している。
早川:そこまでいくと、かえって違和感を感じます。
時間となりました。後は、一揆にて。
2013年4月6日 士心にて学而篇
士心のブログを参照ください。
2013年4月13日(土)孟子滕文公章句上
本日は、小田さん、上田さんの二人。本日部分を音読。訓読と意味は小田さん。
滕の文公世子爲り。將に楚に之かんとして、宋に過つ。孟子を見る。孟子、性は善と道(い)ふ、言へば必ず堯舜を稱す。世子、楚より反りて、復孟子を見る。孟子の曰く、世子吾が言を疑ふか。夫れ道は一のみ。成覵(せいけん)、齊の景公に謂ひて曰く、彼も丈夫なり、我も丈夫なり。吾何ぞ彼を畏れんや。顏淵の曰く、舜は何人ぞ、予は何人ぞ。為(す)ること有る者は亦是の若し。公明儀曰く、文王は我が師なり。周公豈我を欺(あざむ)かんや。今滕長きを絶ちて短きを補はば、將に五十里ならんとす。猶以て善國爲る可し。書に曰く、若し藥瞑眩せざれば、厥の疾瘳(いへ)ず。
滕の文公が世子、つまり皇太子の時のことである。楚に行こうとして、宋を過ぎたとき、孟子に会った。孟子は世子に、性善を説いた。発言すれば、必ず堯舜のことをほめた。世子が楚より戻るときに、再び孟子に会った。孟子はこう言った、「世子は私の言葉を疑うのか。道は一つである。成覵は、齊の景公にこう言いました、『彼も立派な男であり、私も立派な男である。私がどうして彼を恐れようか』と。顏淵はこう言いました、『舜は何者であろう。私は何者であろう』と。何かをなそうとする者は、なべてこのようなものです。公明儀はまたこう言いました、『(周公は言った、)文王は我が師である、と。周公がどうして私を欺くだろうか?』と。今、滕は国の長短を整えれば、五十里四方ぐらいはあります。これだけあれば、善をなす国となりえます。書経にこうあります、『もし薬を飲んで、くらっとするくらいでなければ、病をなおすことはできない』と」。
上田:成覵が「彼も丈夫なり、我も丈夫なり」としていますが、丈夫とは。
小田:安井息軒は段玉裁の説を引用しながら、たぶん景公が誰かの勇者を称えたことに対して成覵が自分は彼に決して劣らない勇者だ、と言ったのだと推測しています。その上で、朱子が成覵の言ったことは聖賢と自分を比べたのだ、と解説していることを必ずしもそうとはいえないのではないか、成覵が倫理的にすぐれた人かどうかはどうでもよくて彼は自分が勇者であることを誇っただけではないか、と疑問を呈しています。では相手の勇者とは誰であるかは、よく分かりません。ともかく、自分はその勇者に物怖じなどしないと言ったのであり、このぐらい気後れするな、と文公に発破をかけたのでしょう。
上田:「文王は我が師」の我とは誰ですか。
小田:周公でしょう。彼が「文王は我が師」と言ったということです。その周公の言葉を引用して、公明儀もまた学んで文王に近づけるのだ、と言ったのだと。だから、これもまた文公に向けて、貴方もその心がけを持ちなさいと孟子が言ったのです。
上田:文公が太子のとき、楚に行った。当時は、斉、楚、秦間で外交の駆け引きが行われており、滕などの小国はどうすれば生き残れるかに苦慮しており、斉の客卿であった孟子が宋に居るということで、聞いてみると、性善を説いた。太子は感銘をしたのであるが、楚で過ごしてみると、孟子の言うことで果たしていいのかと疑問を拭えず、帰途にまた寄った。性善とは。
小田:朱子は、注の中でこれこそ後の告子章句で展開される性善説を説いたのだ、とみなしています。しかし、私はそんな思想学説を説いたのではないだろう、と思います。むしろ、いつもの孟子の持論として、人間だれでも善を心に持っているのだ、だから努力すれば堯舜に近づけるのです、堯舜のように天下の主となる道すら開けるのですよ、ということを語ったのでしょう。文公が楚から帰ってきてまた孟子に会ったのは、孟子が言っていることに納得できなかったからです。しかし、孟子のことなどどうでもよいと思ったならば、また会いに行くようなことはしない。孟子の説には頭でどうも腑に落ちないが、心で孟子のカリスマにすっかり圧倒されてしまったのではないか。だから、若い文公はまた会いに行った。それほど魅了されてしまったのでしょう。自分の言に耳をかすよい信者ができたと、さぞかし孟子は喜んだことでしょう。
上田:五十里四方の国と「若し藥瞑眩せざれば、厥の疾瘳ず」とは何の関係がありますか。
小田:私の説を全部採用して、徹底的に政治改革をやりなさい、とてつもなく辛い道であるが、それをやりなさい、と言っているのです。斉王は、自分の説を採用できなかった。あなたは断固としてやりなさい、周囲の者は反対するでしょうが、耳を貸してはいけない、と文公をけしかけたのです。若い文公は、自分のような極小国では、どうせ何をやっても駄目だと萎縮していた。それに対して、しっかりせい、成覵だって「我も丈夫」と言っているではないか。あんただってやればできるはずだ、だが道は辛いぞ、辛い道を覚悟するくらいでないと駄目だ、と言っているのです。
上田:顔淵が「舜は何人ぞ、予は何人ぞ」なんと言い方をしますか。
小田:少なくとも論語においては、こんな言葉を放つ顔淵は出てきませんね。論語では顔淵は物静かで、先生の言う事をじっと聞いているというイメージで作られています。しかし、実は顔淵には別の顔があったのかもしれません。むしろもっと積極的でバイタリティのある面も持っていたのかもしれず、だから孔子の高弟であったのかもしれない。しかし、論語の中の弟子伝説ではそういう顔淵は語り継がれることはなかった。ここは、孟子が顔淵を引用した数少ない部分の一つです。孟子は孔子学派の直系であるから、彼が継承していた顔淵の言葉は重要で、論語の言葉とは違う誇り高い顔淵の実像が伝えられていたのかもしれない。
上田:公明儀が文王と周公を持ち出したのは。
小田:周公は、文王の道に従って国を治めた。公明儀もまた、周公にならって政治を行おうとした。このように文王の道は、後世の者がならうことができるのだ、と文公に言ったのです。だから、文公もまたやらなければならない、と孟子は言ったわけですね。
上田:五十里四方と薬とは何の関係がありますか。
小田:殷の湯王も周の文王も、わずかな領地から国を興したという言い伝えがありました。つまり、彼らは小国から天下を取ったと。それを今の時代に持ち出して、湯王や文王もまた小国から天下を取ったわけだから、同じぐらいの大きさの滕国でも未来はあるのだ、と励ましたのです。はっきり言って、とんでもない時代錯誤ですが。いにしえの時代ならいざ知らず、戦国時代にはこんな小国に全く未来はないのですが。そのために三年の喪とか井田法のような孟子推奨の経済政治政策を取りなさい、それは頭がくらっとくるような薬のようなもので、それぐらい思い切ってやらないといけないのだ、と。実際に国の中で猛反対に会うが、私の言う事は絶対正しい、どんな反対をも押し切ってやりなさい。いわば脅しみたいなものです。
上田:貝塚先生の年表によれば、孟子が斉を後にしたのが前312年、宋の滞在が前311年、文公の父、滕の定公の没年が前307年ですから、太子が即位するのが前306年あたり、この後に三年の喪を孟子は太子に勧めますね。三年の喪は実際は25カ月とか27カ月とされますが、喪中に文公と孟子が政治改革の話をするというのはおかしなことになりませんか。
小田:貝塚先生の年代の根拠がどこにあるのかは、よく分かりません。滕に何年いたのかは、明確ではないのでは?まあ、そんなに長くいたとは思えませんが。
上田:三年は親のやり方を変えてはいけないというのが儒家。文公が政治改革を行うことは出来ないのでは。
小田:喪中は政治改革のために孟子の言葉を聞いているだけで、喪が明けてからやりなさいということであったかもしれません。
上田:貝塚先生の年表では孟子は前305年くらいには滕を去っている。この年表が正しければ、孟子は、三年の喪や三年父の道を改めずを自ら破って、文公にやらせようとしているように見える。
小田:まあ、そこは方便というわけでして。孟子に言わせれば、先代までの喪礼は間違っていた。だから、間違いは即刻改めて三年の喪礼にしたほうが、親への哀悼の意を示すことができて亡き親にとってもよいのだから、親の時代の制度になんぞこだわる必要はない、と薦めたのかもしれません。孟子にとっても、儒家推奨の喪礼を実際に披露する機会が巡ってきたのだから、やりなさいと薦めたのでしょう。文公が死んだときにやるのでは、遅すぎるでしょう。
上田:当時、斉と楚と秦をめぐっては、蘇秦の合従策や張儀の連衡策に揺れ、312年頃には、楚が張儀の謀略に引っ掛かり、斉との同盟を解消し、大敗し屈原が楚王を諌めたとか、薛に孟嘗君がやってくるとかいう時代でしたね。そういう中で文公は、孟子の王道政治を聞いても疑問があり、それでも孟子に従ってみようとした。
小田:この時代に、滕のような極小国が生き残れる策を、どの諸子百家が出すことができたでしょうか?法家ならば、こんな小国では法の拘束力の根源である「勢」を持つことができないから、改革できないと匙を投げるでしょう。縦横家ならば、各国に策を打つから資金をよこせ、と言うでしょう。しかし、滕に莫大な工作資金など出せるわけがない。そんなところで孟子が、よく分からないがやればできる、と断言した。だから、文公は飛びついたのでしょう。本音のところでは、孟子はこの時期には君主に天下取りをさせる道は、あきらめていたのかもしれない。それに近づいたのは斉の時代であり、孟子は斉でうまくいかなかった。斉を去った後は、むしろ後世に儒家の業績を残すことが主たる使命である、と考えていたのではないか。自分の言う事を忠実に行おうとした文公の記録を大きく残したのは、儒家の政策を国にあてはめた実例がこれであるという実験材料として滕国を見ていた面が、意地悪な言い方ですがあったのではないでしょうか?
上田:孟子は自分の政策で滕が生き残れると思っていたのですか。
小田:春秋時代は、まだ小国でもそのままに残す、という社会制度でした。だから、小国でも生き残る道がありました。しかし戦国時代になると、小国は併合して県として、中央から官吏を派遣して統治する中央集権制度が現れました。この時代になると、小国はどしどし滅ぼされています。滕がとりあえず生き残っているのは、ただただ斉と楚の間にあって、両者の力の緩衝地帯となっているにすぎません。だから斉が南下して宋を滅ぼし、それへのカウンターアタックを受けて斉が没落した後、力の空白地帯となった魯地方には速やかに楚が北上して、魯は滅亡します。滕もまた、この辺までで終わったことでしょう。これが当時の実情であり、孟子としても文公にはあなたの代で天下取りは無理だ、と言ったのです。あなたの代ではひたすら後世につなぐきっかけを作ることしかできない、それができればもしかしたら子孫が繁栄するかもしれませんが、成功はあなたの代では無理ですよ、と言ったのです。実情を見れば、そう言うしかないですね。孟子ですら、滕の現状はどうしようもないということだったのです。
上田:それはいかがなものか。それを言わずに、王道だ、三年喪や井田法などなど文公にさせる、まるで、憲法九条に準じておれば国が滅びても後に聖王が現れるみたいなことをやらせて、実際は無理だと分かっている。それに、前305年に滕を去っているというのが正しければ、やらせっぱなしのままで、さようならということになる。
小田:孟子を擁護する推測を考えました。最初から、たとえば二年契約で顧問となってもらったのかもしれません。孟子を雇うということは、背後にいる儒家の大集団もまとめて面倒を見るということです。そのための経費を斉や魏のような大国なら持つことができるが、滕では無理である。だから、二年くらいお弟子さんたちの面倒を見ますから、その間顧問となっていただけますか、と契約したんじゃないですか。孟子もまた、弟子やその家族を養わねばならないという事情があったから、呼ばれて行ったのでしょう。だから、呼ばれた間は顧問になって文公にあれこれアドバイスをした。もとより、その国に殉じる気はなかったのでしょう。
上田:まだ読み始めで私には分かりませんが、貝塚先生の年表によれば、孟子の言う事、やっていることは矛盾に満ちている。本気で文公に王道を説いたのか、孟子の意志で早々に滕を去ったのか、家臣の反対にあっておられなくなったのか疑問だらけであり、そういうことを考えながら、この先を読んでゆきたい。
小田:最後に付け加えますと、この章の朱子注にある程子の言葉は、『中庸』によるものです。朱子は、この章に初めて「性善」の文字が表れることを重視して、思想的意義を見ているわけです。
2013年4月27日(土)孟子滕文公章句上
本日は、小田さん、上田さんの二人。本日部分を音読。訓読と意味は小田さん。
滕の定公薨ず。世子然友に謂りて曰く、昔者(むかし)孟子嘗て我と宋に言ふ、心に於て終に忘れず。今不幸にして大故に至れり。吾子をして孟子に問はしめて、然して後に事を行はむとす。然友鄒に之きて孟子に問ふ。孟子曰く、亦善からずや。親喪は固り自ら盡くす所なり。曾子曰く、生くるには之に事るに禮を以てし、死すれば之を葬むるに禮を以てし、之を祭るに禮を以てす。孝と謂ふ可し。諸侯の禮、吾未だ之を學ばず。然りと雖も、吾嘗て之を聞けり。三年の喪、齊疏(しそ)の服、飦粥(せんじゅく)の食(し)、天子より庶人に達す。三代之を共にす。然友反命す。定めて、三年の喪を為す。父兄百官皆欲せずして、曰く。吾が宗國魯の先君も之を行ふこと莫し。吾が先君も亦之を行ふこと莫し。子が身に至りて之を反せば、不可、且つ志に曰く、喪祭は先祖に從ふ。曰く、吾之を受くる所有り。然友に謂りて曰く、吾他日未だ嘗て學問せず、好みて馬を馳せ劍を試む。今や父兄百官、我を足れりとせず。恐るらくは其れ大事を盡くすこと能はざることを。子我が爲に孟子に問へ。然友復た鄒に之きて孟子に問ふ。孟子曰く、然り。以て他に求む可からざる者なり。孔子の曰はく、君薨ずれば、冢宰に聽かしむ。粥を歠(すす)つて、面㴱(深)墨し、位に即きて哭す。百官有司、敢へて哀せざる莫し。之に先んずればなり。上(かみ)好む者有れば、下(しも)必ず焉より甚だしき者有り。君子の德は風なり。小人の德は艸(草)なり。艸之に風を尚(くわ)はれば必ず偃(ふ)す。是れ世子在り。然友反命す。世子曰く、然り。是れ誠我に在り。五月廬に居り、未だ命戒有らず。百官族人可とし、謂りて知れりと曰ふ。葬に至るに及びて、四方來りて之を觀る。顏色の戚(いたみ)、哭泣の哀しみ、弔する者大きに悦ぶ。
滕の定公が亡くなられた。世子(太子、文公)がお守役の然友に言った、「昔、孟子がかつて宋で私に言葉を下さった。それが心の中にずっと残っている。今、不幸にして父の死を迎えた。私は、あなたに孟子に質問してもらい、それから後で葬儀のことを行おうと思う」と。然友は鄒に行き孟子に質問した。孟子が言った、「それは善いことである。親の喪は出来る限り尽くすべきものである。曾子がこう言っている(論語では孔子の言葉になっている)、『親が生きているときは仕えるに礼を以てし、親が死ねば葬儀を行うに礼を以てし、親を祭るには礼を以てす。これを孝と言うべきである』と。諸侯の礼については、私はこれまで学んでいないが、私はこう聞いている。喪は三年、粗末で荒い布の服を着て、粗末なお粥を食す。この礼は、天子より庶人に至るまでおなじであり、夏殷周の三代で同じであった」と。然友が、世子のところに戻り報告した。世子は決意して、三年の喪を行おうとした。ところが世子の年長者や百官たちは誰もそれを望まず、こう言った、「吾が宗国の魯の先君もこれを行ったことはない。吾が国の先君もまたこれを行ったことがない。世子の代になってこれを覆すことはできません。そのうえ記録にもこうあります、『喪祭のことは先祖に従うものである』と」と。世子が言った、「私が言っているのは、ある方から伝授されたものである」と。世子は然友に言った、「私はこれまで学問をせず、馬を駆けたり剣術を試みることを好んだ。今や年長者や官吏達が、私を不十分としている。こんなことでは葬儀という大事を尽くすことはできない。あなたにもう一度私のために孟子に聞いてもらいたい」と。然友は再び鄒に行き、孟子に聞いた。孟子が言った、「そうでしょうね。しかしこのことは他人に頼むことはできません。孔子はこうおっしゃった、『君主がみまかられば、政治の一切は配下にまかせ、自分は粥をすすり、暗い顔つきで、喪主の席につき哭の礼を行うだけである。百官有司は、これを見て哀しまないものはない。なぜならば君主みずから率先してやるからである』と。人の上に立つ者が好んで行えば、下の者は輪をかけてますます模倣して行うものである。君子の徳は、風である。小人の徳は、草である。草に風が加われば必ずひれ伏すものです。だから、世子がそれをやらねばならない」と。然友が戻って報告をした。世子が言った、「そうだ!これこそ私のなすべきことである」と。こうして五ケ月あばら家に住み、一切命令も訓戒もしなかった。百官や一族の者は彼を認め、知者とみなした。葬の礼を行うと、四方の国々から人々がやってきてその礼を見た。世子の顏色の哀み入りと、哭泣に哀しむ姿を見て、弔問する者たちは大いに感服した。
小田:父兄百官は、三年の喪に反対しました。なんで前例を変えるのか、そんなものは聞いたことが無いと。そりゃそうでしょうね。
上田:朱熹はそうじゃない、周公の時にはやっていたものが失われたと反論している。
小田:ところで、孟子は万章章句下の二で不思議なことを言っています。北宮錡が周の爵位について尋ねると、「其の詳らかなること得て聞く可からず。諸侯其の己を害することを惡んで、皆其の籍を去(す)つ。然れども軻、嘗て其の略を聞けり」などとと説明しています。周代の爵位の制の記録を、後世の諸侯が自分たちに都合が悪いから捨てた。だから、現在に記録が残っていない、と言うのです。しかし、諸侯はたくさんいたというのに、すべての諸侯が捨ててしまって、記録がすっかりなくなったというのでしょうか?私は、孟子の言葉にかなり疑問を持っています。こういった周代の爵位とか、あるいはここで言う喪礼についても、じつは後世に儒家たちが分散的な古記録を参照して、そこから過去の制度を類推して再構成したものなのかもしれない、と私は思うところです。儒家は、いにしえの三代の制度はすばらしいものであったと賞賛して、その制度への復古を推奨します。しかしながら、孔子自身もまた、「夏の禮、吾能くこれを言ふ。杞、徴すに足らず。殷の禮、吾能くこれを言ふ。宋、徴すに足らず。文献、足らざるが故なり」と言っているところです。後世の国においては、夏や殷の礼に関する文献が足りない。だから、孔子が再構成をしてこのようなものだ、と言ったというものです。このように、儒家は孟子も加えて、周王朝の秩序はこうだったはずだということを再構成して主張していた面があったのではないか。しかしそれを裏付ける証拠の記録は、儒家たちもついに十分に見つけることができなかったのではないか。だから、三年の喪の制度も、私は本当のところはどこまで広くいにしえの時代に行われていたのかは、分からないと言うしかありません。少なくとも戦国時代には、誰も三年の喪などしていなかったとうことで、諸侯もまたやっていなかった。そのうえ、過去の各国の歴史で三年の喪をしていたという記録もまた、残っていなかった。孟子自身、諸侯の礼については学んだことはないと言い、しかし周の王室がやっていたことを、諸侯もやっていたと聞いている、と言います。だが孟子の推測が間違っていて周の王室のみがやっていただけで、魯などの諸侯は三年の喪など行っていなかったのではないか、とも考えることができます。だから、記録がないのは致し方ない。
上田:礼記は何時頃編集されていますか。三年問に色々記されていますが。
小田:現行の礼記は、漢代に礼関係の古いテキストから編集されたと言います。
上田:三年は、「子生れて三年、然る後に父母の懷(ふところ)を免(はな)る」を根拠としてますね。
小田:天子から庶人まで三年の喪ということです。
上田:三年問では、三年といっても二十五カ月、一年、九か月、五か月、三か月と色々の喪が記されており、三年ひとつではない。
小田:結局、孟子が文公に実際にやらせたのは、三年を五カ月に短縮していたのかもしれません。
上田:「五月廬に居り」としており、結局は三年ではなかったということでしょう。
小田:三年間、文公が何もせずにそれから後孟子から政治の意見を聞いた、というのはちょっと考えにくいです。そこまで孟子と文公が付き合った時間は、長くないはずです。何もしなかったのは、たぶん五カ月だけでしょう。
上田:そう思えます。そうであったと考えるほうが話が合います。それを文公が三年の喪を行ったとするのは、どうもいただけない。
小田:孟子としては、この喪を儒家推奨の礼の実例として、宣伝にしたかったのではないでしょうか。今文公にやらせるチャンスであり、それが実現した、本当は三年やらせたかったのではないでしょうか。しかしこの戦国時代、そんな悠長なことはしていられない。だから、五ヶ月にしたのかもしれません。
上田:していないのにしたというのが、いただけない。
小田:三年やるのが理想であったとしても、父兄百官の言うことが当時の常識であり、先例にもなかった。先例にないことをしてはいけないと言うのは、当然だったでしょう。
上田:三年父のやり方を変えてはいけないということにも合致していない。
小田:文公は孟子に従い、三年の喪に入り、五か月は何もせず喪に服したといいます。その心がけが、父兄百官に伝わったと。また四方の国から葬儀を見てみようとして弔問者がやって来て感服したと。少なくとも、文公のやっていることを諸国に知らせる宣伝効果はあったのでしょう。
上田:父兄を年長者とされましたが、どういうことですか。
小田:叔父とか年上の従兄のようなものでしょう。
上田:朱熹は、「父兄は同姓の老臣なり。滕と魯とは倶に文王の後にして、而して魯の祖、周公長たり。兄弟之を宗とす」としてます。
小田:文公は若くて、同族の年長者で家臣であった人たちが大勢いたのでしょう。だから、代替わりしたばかりの若い君主の立場は弱かった。孟子は、文公の行為が父兄百官を感化して、弔問の者たちを感服させた、と最後に付け足しています。これは、「君子の徳は風、小人の徳は草」の理論に呼応させたもので、上がやれば下がなびくという実例となったのだ、と主張したいのです。しかし、実際に感化されて感服したのどうか。残念ながら、怪しいと思いますね。
上田:私も怪しいと思っている。貝塚先生の年表では、孟子は滕を前305年に辞任して魯に向かったとしておられる。定公が薨じたのが前307年ですから、父兄百官の反対にゆりもどされて、文公も腰砕けになり、孟子も滕に居れなくなくなったのではないかと思っている。
小田:前回にも申しましたが孟子率いる儒家教団を召し抱えるには莫大な経費がかかり、滕のような小国ではずっと孟子にいてもらうのは、予算が許さなかったのかもしれませんね。だから、二年程度いてもらうに留めたのかもしれない。しかし、孟子が文公に薦めた復古制度の数々ですが、たとえば明治維新のとき、いにしえの官職とか制度を復興させようと最初はやりました。主観的にはこれが日本古来の制度なのだ、と考えて制定したわけですが、そんな制度は幕藩体制を生きていた当時の人々にとっては、全くの珍奇なものでしかありませんでした。それと同じで、孟子の薦めたいにしえの制度もまた、同時代人から見れば突拍子のない改革に見えたに違いありません。それで、父兄百官も先君もやってない、記録にもないと猛反対をした。この記録は孟子側の主張ですから、自分に都合のいいように書いている。宣伝のために、この喪の試みは成功して下々に感化の効果があったのだ、と主張としたのでしょう。
上田:三年の喪が、周王室のみで、諸侯の実例がなかったということかもしれませんが、孔子の死に際しては行われたことは確かでしょう。
小田:儒家集団は、復古思想の中で行ったはずです。
上田:上は象を天にとる、三年の喪は、人道の至文、としており三年の喪は王たるものかくあるべし、という思いもあったのでしょう。
小田:尽心章句上39に、「齊の宣王喪を短くせんと欲す。公孫丑曰く、朞(期、近親の喪一年)の喪をするは、猶已(や)むに愈(まさ)れるか」とあります。つまり、斉の宣王が一年以上の喪を短くしたいと言って、公孫丑が一年にしてもしないよりましではありませんかと孟子に聞いた。孟子は、孝道を教えればそういう質問はしなくなるものだ、と答えた。つまり、斉の宣王は、少なくとも一年以上の喪をせよと儒家に薦められて、それでは長すぎる、と渋ったということです。これは三年の喪をせよと薦められた、と解釈されています。だとすると、斉は諸侯でなくて周と同じ王として三年の喪をするべきだ、と孟子は考えていたのでしょうか。それとも、諸侯は原則全て三年の喪をするべきだと考えていたのでしょうか。文公は短い五月の喪を行った、とするならば、文公は王でなく公で周王室の家臣であるから、短い喪でかまわない、と考えていたのでしょうか。しかし、孟子はすでに有名無実の周王朝を復古させて秩序を復活させようと望んでいたとは、ちょっと思えないのですが。むしろ、新しい斉とか魏の王でも、仁義の政治で天下の主になるべきだ、と考えていたと思います。だとすると、たとえ弱小国の滕でも、王並みに三年の喪を行うべきだ、と薦めたとも考えられます。
上田:そんな話があったのですか。ところで、朱注に、林氏の言葉に、「人心の同じく然りとする所の者、我より之を發すを以て、彼が心悦びて誠服す。亦然るを期せずして然る者有り」とはどういうことですか。
小田:親を哀悼する情は、他人のために行うのではなくて、自分の心中から率先してやるものだ。それが他人を結果的に感服させる。このように他人を感服させようと思ってやったのではないのに、他人がなびいて感服してしまう。これが風に草がなびくことだ、ということでしょう。
上田:大いに悦ぶとはどういうことですか。
小田:文公の姿をみて、感服したということでしょう。孟子はこのように、君主の徳が民をひきつけて徳になびくように秩序に従わせる、という説を前の梁恵王章句でも述べていました。だが、荀子はそんなことで秩序はできない、と批判しました。先に君主が礼とか法を作って、下々にあてはめる。人はこうすべきであるという規範を作り、信賞必罰のガイドを示して、初めて秩序は作られる。なぜならば人の性は「悪」、つまり単なる利欲を求める存在にすぎず、それが君主の徳だけで感化されてよくなるはずがあろうか、むしろ礼や法で信賞必罰を行って初めて社会はよくなるのだ、と言いました。孟子は、いわば昔の大らかな村社会で通用するような、長老の徳に村人が自ずから従う、といった素朴な国家像を理想としていました。ところが、このような国家像は、戦国時代の発達した社会からは現実離れしたところがありました。だから、孟子の説は後世荀子により批判されて、荀子はより現実に即した理想社会を提示しました。
上田:今日はこんなところですかね。
一揆では、過去のアルバイト君が連休で旧交を改めるためにやってきたとのこと。なつかしや。最近の北朝鮮情勢、文化力について杯を傾ける。
2013年5月11日14:00~16:00 論語読書会in士心
参加者:上田、成田、早川、北澤、小田、桐畑孝佑 士心での記録者:小田
学而篇二(読み下しは、中村惕斎に従う。)
有子の曰く、其の人と爲りや孝弟にして、上を犯すことを好む者鮮し、上を犯すことを好まずして、亂を作(おこ)すことを好む者は、未だこれ有らず、君子は本を務む、本立ちて道生(な)る、孝弟は其れ仁を爲(おこな)うの本か。
《読み下しのポイント》
・
現在では使われませんが、江戸時代の読み下しに使われていた記号が出てきます。まず「メ」の字から右下の出っ張りを削ったような字。これで、「して」と読みます。次に、かぎカッコの"「"を左右にひっくり返したような字。これで、「こと」と読みます。
・
「矣」は助字です。断定を表しますが、ここでは読みません。
・
「未」は再読文字といいます。まず「いまだ」と読んでから下に進み、下の「一」に至って戻り「ず」ともう一回読みます。このような再読文字は、漢文でいくつかあります。おいおい、他の例も出てきます。
・ 「與」は疑問の助字です。「か」と読みます。
《James
Leggeの英訳》
①
The
philosopher Yew said, "They are few who, being filial and
fraternal, are fond of offending against their superiors.
There have been none, who, not liking to offend against
their superiors have been fond of stirring up confusion."
②
"The supeior man bends his attention to what is radical.
That being established, all practical courses naturally grow
up. Filial piety and fraternal submission! Are they not the
root of all benevolent
actions?"
(日本語訳例)
①
哲学者である有子が言った、「子として親を愛し、年少者として兄姉に従う人となりでありながら、目上の者に好んで逆らう者は、ほとんどいない。目上の者に好んで逆らわない人となりで、混乱を起こすことを好むものは、いまだかっていない。②すぐれた人(=君子)は、自らの関心を何が根本的であるのかということに向ける。根本が確立されれば、全ての実践的な道が生育する。子としての情愛、そして年少者としての服従心!この二つは、あらゆる慈善的行為(=仁を為す)の基礎ではなかろうか?」
(英訳について)
小田:この言葉を発したのは、有子(有若)です。孔子の弟子です。このように、論語には孔子の弟子たちの言葉もたくさん出てきます。レッグは「哲学者である有子」と言っています。
桐畑:哲学者ということは、ギリシャの哲学者みたいなものだということですか。
小田:孔子は、「The
Master(先生)」と訳されています。ソクラテスとその弟子の哲学者たちのサークルみたいなものを、孔子と弟子たちのサークルに想定していたんじゃないでしょうか。
早川:有子は孔子より十三歳年下の弟子で、姿かたちが孔子にそっくりであったと言われています。それで、孔子の死後に弟子たちが孔子学校の次期総代に有子を選ぼうという提案が行われましたが、別の弟子の曾子とかが反対して、彼は斥けられました。論語の中で、有子みたいに「子」を付けて先生として敬われているのは、他に曾子など四名(?)しかいません。この「子」を付けられている弟子たちが、論語の編集者であるという説もあります。
小田:次に、「孝」「弟」「仁を為す」について、それぞれは「filial
piety」「fraternal
submission」「benevolent
actions」と訳されています。ここではだいたいこの訳のようなことを言っているのですが、「仁」については、すぐ次の章で別の訳し方をしています。孔子は「仁」の字を使うときいろいろな意味合いを持たせているので、訳もいろいろとなるわけです。次に「君子」について、レッグは「The
superior
man」と訳しています。ところがこれもまた、一つ前の章では別の訳(man
of complete
virtue)を採用しています。「君子」の語も意味は一定していないということが、英訳から透けて見えてきます。
(討論)
小田:この章は、前の章が学問のすすめとして個人への呼びかけであったことに対して、社会の理想的なシステムを述べた内容となっています。このように、論語には二つの視点があります。一つは、個人としていかに生きるべきか、という倫理的内容。もう一つは、理想の社会とはどのようであるべきか、という社会思想的内容です。
成田:この章で有子が言っていることは、たぶん孔子の死後に彼が主張したことではないかと思います。孔子じしんは、このように社会のシステムについて明確に述べることはありません。
小田:有子はまず、システムの基盤として、家族を据えています。家族の中で子供が親に愛情をもって仕え、年少者が兄と姉に一歩譲ることで、家庭の秩序が保たれる。この基盤となる家族の安定は、目下の者が目上の者に従順に従うことによって実現される。これを積み上げていけば、国家全体の秩序が乱されず安定するのだ。こういう理想社会を、有子さんは主張しているのです。
成田:ですが、安定が本当に理想の社会であるのか、という疑問があります。目下の者が目上の者に何も言えずに黙っているのが、本当に目上の人のためになるのか。親や兄姉が間違っていたら、見て見ぬふりをして従うのか。それでは、いじけた社会が出来上がってしまい、社会が腐ってしまわないか。
小田:会社でいえば、年功序列でよいのか、ということでしょう。小泉総理時代以降、日本の年功序列制度はほとんど崩れ去ってしまいました。実力が実力どおり評価されることがよい社会なのだ、という主張が支配するようになってしまいました。年功序列よりも、成果給というわけです。
北澤:私の勤めていた会社でも、20年ほど成果給を採用していたのです。ところが、これがうまくいかない。それで、最近は見直しが進められています。成果給を導入した最初の頃は、皆張り切って頑張ろうという意欲が強かったので、成果目標を高く掲げていました。ところが年数が経つにつれて、目標が達成できないことによる減点をだんだん恐れるようになって、職場で掲げる成果目標がどんどん低くなっていったのです。成果だけで評価するようになると、数字ばかり気にしてチームワークがおろそかになってしまいます。成果主義というのは、思ったよりうまくいかないものです。
桐畑:忠、孝とセットで言われますよね。日本では、儒教の忠孝がどのぐらい歴史に影響を及ぼしたのでしょうか。
小田:そうですね。日本では、とりわけ「忠」が強く意識されてきました。しかし、論語の中では、主君に忠誠を尽くすという意味で「忠」の字が使われることは、じつはないのです。「忠」の字のもともとの意味は、「まごごろから行うこと」に過ぎません。まごころから主君に仕えたならばそれもまた「忠」ですが、ほんとうは「忠」はそれだけに限らないのです。
早川:だから、「子に忠」という言葉すらあります。
小田:だいたいが、論語の中ではこの有子の言葉のように「孝」が一番大事であるという主張は強くありますが、主君への「忠」が大事であるというような主張はないのです。孔子から150年ほど後に現れた儒家の孟子などは、悪政を行う君主は殺してもかまわない、とまで言います。中国の家臣たちは、暴君が現れたり、朝廷の政治がヤバくなったら、退職して逃げるのが賢明だという考え方が、特に恥ずかしいとも思われていません。中国では忠誠を尽くすのはあくまで家族であって、国や皇帝への関係は日本人よりもずっと割り切ってドライに距離を置いているようです。
早川:日本人は、全ての家系を辿ると、結局ぜんぶ天皇に行き着いてしまう。日本全体が一つの家族である、という考えに容易に行き着きます。だから、個々の家への孝よりも国と天皇への忠が優先されるという意見が勝ちます。中国は多民族の集まりであって、家と国とは重ならない。
小田:本当は日本だって単一民族ではないのですが、国全体が一つの家族である、という考えが、ほとんど無意識レベルで支配しています。今、沖縄の人々が主権回復の日に反対するなど、本土に対して異論を提出しています。それは、今言ったような日本人が一つの家族である、という考えに対して彼らが感じる違和感に由来しているはずです。
桐畑:幕末の志士たちは、忠孝の考えで明治維新を起こしたのでしょうか?
成田:あの時代の思想は、「尊皇攘夷」です。日本人の主君である天皇を尊び、日本の敵である外国を撃退する。この考えが幕末になって主流となったのですが、江戸時代初期から中期までは、「忠」を誓う相手は徳川幕府でした。天皇は、ほとんど忘れられていました。しかし、国学者などが、じつは日本の本当の君主は天皇であり、徳川幕府などはその家臣にすぎないのだという説を立て始めて、江戸時代後期になるとだんだん賛同者が増えていきました。それで、幕末になって外国の圧力に屈してうろたえる幕府を見て、たかが家臣が日本を支配するな、天皇こそ日本の支配者のはずだ、という考えが志士たちの間に広がりました。「忠」の相手が変わったのです。
では、次にいきましょう。
子の曰く、言を巧(よ)くし色を令(よ)くするは鮮(すくな)いかな仁。
《James
Leggeの英訳》
The
Master said, "Fine words and an insinuating appearance are
seldom associated with true
virtue."
(日本語訳例)
先生が言われた。「きれいな言葉と媚びるような見かけは、めったに真の徳とむすびつかない。」
(英訳について)
成田:この章では仁を「true
virtue」つまり真の徳と訳しています。前の章は「仁を為す」と行動を言っているわけで、こちらは徳そのものを指しています。その違いが、訳の違いとなっているのです。
早川:巧言が「fine
words」であるのは皮肉あるニュアンスですね。
(討論)
成田:せっかくだから、惕斎の解説も読んでみましょう。
小田:では、やってみましょう。
(大意訳)
巧言令色とは、言語顔色を取り繕って、あたかも徳ある者のように見せかけることを言う。人の心は一つしかないのあるが、理に根ざして現れるのは、本心の作用。気にひかれて起こるのは、私意の欲である。天理と人欲は、つねに心の中で勝負をなしている。人は、よく心の内に向かって、心を保ち養うならば天理が支配して、人欲が消えてなくなり、本心の徳が完成するのだ。これがすなわち、仁である。だがもし巧言令色によってもっぱら外見を飾るならば、人欲がほしいままに跋扈して本心の徳は滅ぶ。聖人孔子の言葉は、おだやかゆるやかである。彼が「すくなし」とおっしゃられるさいには、その真意は絶対いないのだ、ということなのだ。それを思い知るべし。
○人の一身に表れる言語・動作は、みな心のありどころ次第なのである。ゆえに、君子は容貌や言葉の調子を治めて整えるときには、心の内に向かって工夫を用いるのだ。これすなわち、心を保ち養うということである。小人どもが他人のかくしごとを暴き立てて、これが正直な行為だと言えば、一見彼は巧言ではないのと似ている。また顔色をいかめしく作り、しかし内面はふにゃふにゃであれば、一見彼は令色でないのと似ている。だが、これらはみな外面に従って情を曲げ、偽りを飾っている。だからこれらは実は最大の巧言令色の輩なのである。およそ孔子一門の学は、仁を求めるのをもって要点とする。この論語の書は、冒頭に「時に習う」を置いて、学問に励む義務を説く。次に「孝弟」を置いて、仁を求める本を立てる。次に「巧言令色」を置いて、仁を損なうことへの戒めを述べる。これは、編集者が心を用いているところである。
小田:惕斎は朱子の注を当時の日本語で分かりやすく解説しています。だから、同じことが朱子の注にも書かれています。
成田:この逆さまの言葉も、論語にあります。「剛毅朴訥は仁に近し」です。
桐畑:幕末の志士たちも、こういった儒教の言葉に影響されていたのでしょうか?
小田:幕末の志士たちにとっては、論語は当たり前の教養書でした。西郷隆盛とかは、じつの性格は陽気でおしゃべりな人だったとか言いますね。しかし、薩摩武士たちを指揮する立場に立ったとき、彼らのトップとしては巧言令色でないほうが信頼される。それで、あまり多くを語らない人になったとか。
成田:儒学の一派である陽明学は、幕末の思想に大きな影響を与えました。
早川:逆に中国人が、それまで大して評価されていなかった陽明学が日本人にここまで大きな影響を与えていることに驚き、本国で再評価するようになったぐらいです。
小田:陽明学は、血の気の多い人にぴったりの思想です。
成田:人間の心には良知良能がある。だから、心即行で心の良心に従って行動しろと。大塩平八郎です。
小田:だが朱子学は、おとなしい学問の思想で、秩序重視です。それで、徳川家康は下克上の時代を終わらせるために、武士たちに朱子学を必修学問と定めた。信長は光秀に倒され、秀吉に政権を乗っ取られた。その秀吉政権は、家康によってまた乗っ取られた。後からやって来た家康は前の二人が下克上でやられた(自分もやった)のを見ていたから、今後はそれを防ぐために朱子学で武士をおとなしく秩序に従うよう、洗脳したのです。これは見事に当って、江戸幕府は250年間安泰でした。だけど、その一方で陽明学も輸入されて、広く読まれるようになった。日本の儒学は科挙の試験勉強と結びついていなかったので、純粋な知的好奇心からいろいろな説を研究するようになりました。
桐畑:日本人が儒教に影響を受けたのは、いつからでしょうか?
小田:まあ、江戸時代以降です。それより前には、仏教の思想が人々を動かしていました。親鸞の念仏教とは、善人なおもて往生を遂ぐ、いわんや悪人をや、と説いて、社会の下層で見下されている百姓たちに対して君たちこそ救われるのだ、と呼びかけて大いに反応を受けました。加賀国で大名を倒してしまい、百姓国家を作ったりしました。しかし江戸時代に入ると仏教は力を失い、代わりに儒教が日本人に影響を与えるようになりました。
桐畑:禅は、儒教と関係があるのでしょうか?
小田:そこに写真が掲げてある山岡鉄舟さんなどは、禅に傾倒した武士ですね。私は、禅と儒教に関係がある、というよりも、使い分けられていたというべきではないか、と思います。禅は、常在戦場の心境を養う道であり、いつなんどきでも迷わずに行動できる心構えを持つために、武士が求めた。儒教は、もっと理論的に、何が正義であり何が不義であるかを明らかにするガイドとして、求められた。普段は儒教により理論を持ち、いざ緊急事態が起これば禅の心によって的確に判断行動する。そんな受け止め方だったのじゃないかな、と私は思います。
西陣小学校の読書会では、高津君が参加、早川君、小田さん、上田さんの四人。論語はお休み。高津君爆発。一揆にても噴火やまず。余韻でしょうか、①「強竜闘不過地頭蛇」②「上有政策、下有対策」③「山高皇帝遠」とメールがきました。早川君の解説によれば、
① 強い龍が戦っても、地主の蛇には勝てない。我が國の「泣く子と、地頭には勝てない」に似ていますね。
② 官は「政策」、民は「対策」。これは傑作です。「策」の字の重出が、180度違う文脈のなかで生かされており、ユーモアを醸し出しています。いちばん好きですね。
③ 「山が高く、皇帝の権威も達しない」という意味であり、朝廷の法律の届かぬ状態の比喩です。五言絶句の形式であり、元末の方國珍が反乱を起こしたときののスローガンとして伝わっており、「樹旗謡」と題されます。最初に記録されるのは、明代の黄溥の著した『
閒中今古録』であり、詩の全体を示せば以下のようになります。
山高皇帝遠 山高くして皇帝遠く
民少相公多 民少くして相公多し
一日三遍打 一日、三遍打たる
不反待如何 反せずして待つこと如何?
山は高く、皇帝は遙かかなた、民衆は少なく、大臣が多い。一日に、何度も殴打され、反乱を起こさずに、どうするのだ?
押韻は「多」「何」で整っていますが、転句の「遍」の字のみ平仄が違っており、作詩の規範に違反しています。
惜しいですね。
「一日三遍打 一日、三遍打たる」とは税金の滞納などにより「杖――棒打ち」や「策――むち打ち」の刑罰を被ることを指すでしょう。
いわゆる「官逼民反――官逼りて民反す」の状態ですね、ということだそうです。
高津君、今度は論語で噴火しますよとのこと。
2013年5月18日(土)里仁篇
本日は、早川君、小田さん、上田さんの三人。早川君のリードで里仁篇を音読。訓読と意味は小田さん。
子の曰はく、父母在せば、遠く遊ばず。遊ぶこと必ず方有り。
遠く遊ぶこと、則ち親を去ること遠くして、日爲ること久し。定省曠(むな)しくして音問疎し。惟だ己の親を思ひて置かざるのみにあらず、亦親の我を念ひて忘れんことを恐る。遊ぶこと必ず方有りは、已に告げて東へ之けと云はば、則ち敢へて更に西に適かざるが如し。親の必ず己の在る所を知りて憂ひ無く、己を召せば則ち必ず至りて失ふこと無きを欲するなり。范氏曰く、子能く父母の心を以て心と爲れば、則ち孝なり。
孔子が言われた、「父母がいらっしゃる間は、遠く旅行をしない。旅行するときにはどの方向に行くかを決めて告げておくものだ」と。
遠く旅行すれば親から遠く離れ、何日も離れることになる。定省(昏定宸省[こんていしんせい]。夜に親の布団を敷き、朝に親の安否を気遣うこと)することができず、ご機嫌伺いをすることもできなくなる。ただ自分が親を思って捨て置かないだけではない。むしろまた、親が自分を思って忘れておかないことを恐れるのだ。「遊ぶこと必ず方あり」とは、はじめに東に行くと告げておいてから、その後勝手に西に行ったりしないことである。親は必ず子のいる所を知って憂いがなく、子を呼べば必ずやってきていなくならないことを望む。范氏が言う、「子がよく父母の心を慮れば、孝である」と。
小田:朱子はここでずいぶんとやさしいことを言っていますね。前の章で引用された礼記のえげつない世界と、全く違います。つまり「父母怒りて悦ばずして之を撻ち血流すも、敢へて疾怨せず、敬を起こし孝を起こすなり」ですが、この親の暴力に耐え忍ぶのが孝であるという礼記の古代的であからさまな親子関係のくだりを、あえて朱子は引用した。なのに、次のこの条では、むしろ近代的な親子関係といいますか、親もまた子のことを心配しているのだから、気苦労させてはイカンと思いやるのが孝なのだ、とか言います。朱子は、むしろこちらが親子関係の理想としての本音だったのかな。
早川:これは現代にも通じます。確かに「撻ち血流す」よりやわらかい。
小田:古注で鄭玄は、「方」のことを「常」のことであると言います。
早川:この場合の「常」は五常の「常」で、つまり踏み行うべき道ということです。
小田:それは、旅行する時には、行く所を決めるということでしょうか。
早川:それは新注の解釈です。古注では、旅行するときにはルールを守るということであり、つまり旅の恥はかき捨てなどをしてはならない、ということです。
小田:すると、旅行心得みたいなことですか?
早川:旅行することがあれば、両親に心配させてはいけない。
小田:しかし、古注の「常」の線では、前後がつながらないのではないでしょうか?遠く旅行をしない、旅行するならルールを守れ、という教えであれば、それは孝の心得というよりも、旅行の心得になってしまいます。この前後の条は孝のことを続けて言っているわけで、この条も孝がテーマのはずです。古注では、そこがぼやけてしまいませんか?
早川:ルールを守ることが、両親に心配させないことではないでしょうか。むしろ「方」を「方角」とみなして「東へ之けと云はば、則ち敢へて更に西に適かざる」と解釈する朱子は果たして正しいか、疑問です。「方」の解釈については、鄭玄の読み方に軍配が上がると思います。ところで朱子の注を見ますと、やはり後世の人の見方であるな、と感じさせます。古代社会、西に行くといいながら東に行くみたいに自由に道筋を変えることができたか?史記仲尼弟子列伝に、商瞿がいい年となっても子がないため、母が室(妻)を取ろうとしたが、孔子は瞿を斉に派遣することを心配する母に対して「瞿は四十を過ぎれば五人の子持ちとなるから心配ない」と諭し、果してそうなった、という話があります。つまり斉に行くだけで死ぬかもしれないと心配するような時代に、旅行で自由な道筋が取れるとはちょっと思いがたい。むしろ、ルールを守って行くと読んだ方がよいと思います。朱子の南宋時代にもなれば、道路も整備されて、船便もありました。朱子は、意識せずに後世の開けた時代を前提とした読み方をしていると思います。
小田:なるほど、古代には思いつきで行く場所を変える条件などなかったと。
早川:斉にゆくだけでもめている。そんな時代だったことを考えるべきでしょう。
小田:李氏朝鮮でも、ふと思いついて金剛山に登ってみる、なんて風流のエピソードがあります。それができたのは、交通網が整備された時代だからできたことです。朱子もまたフラリと各地に遊ぶことだって、あったのでしょう。
早川:朱子は南宋の各地に旅行していました。ただ南北分裂時代なので孔子の生誕地には、行けなかった。行きたかったでしょうね。
上田:孔子は諸国を放浪してどこに居るかわからないどころか、命を危険さらしている。「君子は・・・居安きこと求むること無く」ともしており、これと合わない。どういうつもりで言われたことなのか。
早川:孔子は早くに両親を亡くしていますから、両親に心配をかけることはなかった。この条の言葉は、どういう状況で、弟子のだれに言われたと思われますか?
上田:それが分からない。
小田:思いますに、これは孔子学校の生徒に向けた、外交官の心得みたいなものではないですかね。孔子学校が就職塾だったことは、明らかなことです。それで、もし君命で外国へ行くことを命じられたとき、おのれの出世の事だけを考えて受けたならば、それは両親をほったらかしにして外国へ行くことになる。そうすると、郷里で親不孝の批判を受けて、自分の評判を落とすことになるリスクがあるから気を付けなさい、ということを孔子は説いたのではないでしょうか。呉起は衛の人ですが、母親に出世するまで帰らないと言い残して、魯の曾子(曾参)の門を叩いた。だが、母親が郷里で死んだという知らせを受けたにも関わらず、まだ出世していないから帰らなかった。曾子は、その呉起を責めて、破門にしてしまいました。出世しないうちは帰らないということは母親もおそらく了解済みだったことで、たぶん呉起は心にやましいことだとは思っていなかったでしょう。だが、世間は許さなかった。本人たちが了解していても、社会常識にひっかかると指弾を受けて、失脚のもとにもなる。孔子は、その危うさを弟子に言いたかったのでは?
早川:四書大全のこの条を見ると、君命で遠くに派遣させられるとき、親をどうするかという話があります。論語を読んでいる人は、遠隔地への派遣を命じられたときに、どう感じたでしょうかね。
小田:僻地は、ものすごく遠いですからね。誰だったかな、北京から新疆に向かおうとした役人が、いったん船で日本に来て、それからロシアに渡って、シベリア鉄道を経由して新疆に行ったとか。そちらの方が、北京から国内を通って新疆に行くよりも速かったと。中国の遠隔地は、そのぐらい遠いですからね。
(後注:呉藹宸(ごあいしん)です。民国時代に、新疆で活動した役人です。司馬遼太郎氏がこの人について興味深く言及していたので、頭の片隅に残っていましたが、名前まで覚えていませんでした。司馬遼太郎氏の叙述を借りると、彼はウルムチの新疆省政府に自らを売り込みに行こうとした。そのために北京から船で神戸に行き、敦賀に出て、敦賀からナホトカにまた船で行って、シベリア鉄道経由で新疆に入ったということです。当時はそのくらい北京から新疆までの内陸交通はほとんど整備されていなかった、ということです。)
早川:そんな時代に孔子があれほど諸国を歩いたのは、前代未聞にして新鮮ですらあった。
小田:晋の文公とかは、大旅行しましたが。
早川:諸侯階級では、国同士の人間交流もあり、旅行もありました。しかし諸侯でもない孔子が、君命でもなく大旅行をした。こんな例は、それまでにありません。周の穆王は、どこまで行ったんでしょうね?(穆王は八頭の駿馬をもっていた。「絶地;土を踏まないほど速い」「翻羽;鳥を追い越す」「奔霄:日に千里走る」「越影:自分の影を追い越す」「踰輝:輝を踰える」「超光:光を超える」「謄霧:雲に乗る」「挟翼:翼がある」)。小田さんの外交官の説は、なかなか面白いです。私もまた、考えてみました。孔子の周遊は当時珍しい事業でしたから、一緒に行きたいと思う弟子が多かったでしょう。しかし、希望者全員連れて行くわけにはいかず、人数を絞り込まねばならない。そこで、この言葉を出して選別した。遠くに行くには親に心配をかけてはいけないし、行くにはルールを守らないといけない、と一般論を述べておいて、真意は両親が健在な弟子は連れて行かないという宣言であった。こういうのは、どうでしょうか。
小田:先進篇で、孔子といっしょに陳、蔡に行った者は出世のチャンスを逃がした、という言葉がありますね。長くつらい旅行だった。
早川:その条の「門」の解釈は、いま言われた解釈とは別にもう一つありまして、自分の門下にはいない、という解釈もあります。つまり、陳、蔡に行った弟子はもう自分の門下にいない。全て卒業して就職したか、死んでしまったかになってしまった。孔子が両親のいない人限定で連れて行ったとするならば、皆年配者だったことでしょう。だから、後世には死んでしまった人も多かった。
小田:しかし曾参みたいに親子で参加したら、孔子の選別も効果ありませんね。
早川:あれは、予想外だったでしょうね。
上田:孔子は何故こんなことを言ったのですかね。
早川:具体的な「孝」を説いている。ここの一連は好きな個所です。父母の年齢を記憶しておくなどこまかいところを具体的にのべておりしっくりする。
上田:どれも孔子にはあてはまらない。
小田:社会常識であり、こういうことをきちんとしておかないと足元をすくわれるぞ。軽んじると仕事ができても、後ろ指をさされるぞと。さっきの私の解釈ならば、孔子の官僚としての体験談と言えないでしょうかね。
早川:徂徠は、古い格言とみています。父母の年の句もまとまりがよく格言であったかもしれません。
小田:津田左右吉氏は、論語の中の言葉は一般的な格言が多く、孔子の独自の言葉は非常に少ない、と考証されています。それが正しいとするならば、当時出回っている格言を孔子塾で取り上げて、孔子がその説明をあれこれと加えて講義した。だが、その孔子の説明部分はたいてい切り捨てられて本文だけが残った、というところでしょうか。
早川:格言だけを弟子が残した。
小田:孔子が格言について説明した部分は、おおかた記憶にも記録にも残らなかったのかもしれません。今論語を読みながらあれこれと話をしていますが、その話の部分はオリジナルであっても、本文は全く別人が作成したテキストです。孔子塾の授業もまた、大本は既成の格言を今風の教訓として読み替える作業だったのではないでしょうか。
子の曰はく、三年父の道を改むること無きを、孝と謂ふ可し。
胡氏が曰く、已に首篇に見えたり。此に蓋し復出して、其の半を逸んず。
孔子が言われた、「三年父の道を改めることをしない。これを孝と謂うべきである」と。
胡氏が言うに、「すでに学而篇に見える。ここに重複して収録され、前半分を抜かしているのだ」と。
早川:この条のように重複する場合は、飛ばしますか?
小田:徂徠は、重出ではないと言っています。「論語の載する所、皆孔子の言なるにはあらず。蓋し『父在則観其志、父没則観其行』、古言なり。『三年無改於父道、可謂孝矣』、また古言なり。孔子或いは並びに引き、或いは単誦す。複出にあらざるなり。」つまり、学而篇は二つの古言を並べ、里仁篇はその一つだけを取り出した。両者は、ニュアンスが違う。「並びに引く所以の者は、以て学の博を貴ぶを見はす。」つまり学而篇は父から多くを学ぶ姿勢について述べている。「門人のまた其の単なるを録する所以の者は、以て孔子の古言を用ふるの方を見はす。」里仁篇では、孔子は片方の古言だけを取り上げた。思うに、ここで一連の「孝」のルールを述べているわけで、その流れの中でこの古言が取り上げられている、ということでしょう。
早川:そう意味づけることも可能でしょうが・・・
小田:武内先生ならば、学而篇と里仁篇は編集者が違うのだとみなすでしょう。つまり里仁篇は曾子から始まる魯スクールが編纂した、わりかし早い時期の成立である。いっぽう学而篇は戦国時代中期以降に編纂されたものであろう。私はよく分からないのですが、学而篇は文法的に後の時代のものが見える、と言われています。
早川:文法が新しいのかどうかは分かりませんが、徂徠の説より、武内先生の説が分かり易い。
上田:孝のベーシックなことを三つ並べている。親に心配をかけてはいけない。親が育ててくれた恩をわすれてはいけない。親の長寿を気遣う。誰でも分かるが、実際に行うことはむつかしい。
早川:孝行の息子は、父が亡くなればあまりの哀しみにとてもそんな(父の道を改める)ことはできない。喪中では哀戚思慕、情があふれて、道を改めるようなことは思いつかない、と。学而篇の注は孔安国、里仁篇での注は鄭玄です。この条のことですが、綱吉の遺言であった「生類憐れみの令」について、後を継いだ家宣はこれを直ちに廃止した。このとき、この条のルールをどう考えるのか、という問題にぶち当たった。
小田:廃止することを進言したのが、儒者の新井白石でした。悪法を改める事は民のためであり、躊躇してはならないと。だが家宣は、綱吉の遺言をむげにひっくり返すことにためらった。
早川:綱吉は後世悪君のイメージが定着していて、生類憐れみの令はその代表のように言われていますが、それほど悪い政治であったのか。当時は、経済的繁栄の時代でした。
小田:まず、生類憐れみの令がどこまで徹底して守られていたのか、という問題があります。尾張藩御畳奉行朝日重章の『鸚鵡籠中記』は同時代資料として重要ですが、それを見ると平気で魚釣りをして食べている。
早川:江戸では、少なくとも犬の保護は行われていました。
小田:綱吉の時代によって、犬や猫をペットとして可愛がる視点が日本人に生まれたといえます。犬なんかは、大陸や半島の影響で日本では食料と見なされていた。しかし、綱吉時代以降、日本人は犬を食べなくなりました。
早川:生類憐れみの令は、動物愛護という視点を日本人に導入した功績があったと思われます。
小田:むしろ、生類憐れみの令への民の怨みは、犬を食えないという不満にあったのでは?
早川:本人の意図は、どこにあったのでしょうか。大僧正隆光が、上様は戌年だから犬を大切にすれば世継ぎが生まれるだろうとか吹き込んで生類憐れみの令となった、という噂がまことしやかに流れていましたが。だが綱吉は学問を重視するところがありました。湯島聖堂で、『大学』の講義をしています。
小田:綱吉は、正室が京都の公家から入ったこともあり、治世時代には江戸に京文化が紹介され、自らも能を好みました。彼は、太平の時代にふさわしく、武断でなく文治によって国を治める政治的意図があったように思われます。綱吉以前の時代には、まだ殺伐とした戦国の遺風がありました。島原の乱が起こり、由井正雪の変もありました。由井正雪の変などは、成功していたら戦国時代に逆戻りしかねない。そんな時代を終えて、文治で統治する転換が必要でした。それが綱吉時代であり、生類憐れみの令もその観点から見直さなければいけないと思います。
早川:綱吉時代は大名を潰していながら、乱が起きていない。統治が巧みでした。
小田:清朝の三藩平定時代は、だいたい綱吉時代と重なりますね。くしくも日本と中国の両方で、同じ時代に武断から文治への転換がありました。
早川:康熙帝から乾隆帝の時代ですね。歴代の中華王朝は、武で統一した後にすみやかに文治政治に転換するものです。中国では短い期間でそうなるのですが、日本では文治に移行するまでに時間がかかりました。
小田:日本と中国で、何か同時代性があったのではないか、と思うのですが。経済ではないでしょうか。
生類憐れみの令から、脱線してしまいました。
子の曰はく、父母の年をば、知らずんばある可からず。一つは則ち以て喜び、一つは則ち以て懼る。
知は猶記憶のごとし。常に父母の年を知れば、則ち既に其の壽を喜び、又其の衰ふることを懼れて、日を愛しむの誠に於て、自(おのづか)ら已むこと能はざる者あり。
孔子が言われた、「父母の年は、知っておかねばならない。一つは歳を重ねたことを喜び、一つは歳を重ねたことを怖れるからだ」と。
「知」は、記憶しておくことである。常に父母の年を記憶しておれば、いつでも長寿を喜び、又その衰えることを懼れて、日を惜しんで(孝を行う)誠実さにおいて、しぜんとやめることができなくなるものがあるのだ。
早川:朱子注の「日を愛(お)しむ」には、典拠があります。前漢の楊雄が論語に模して著した『法言』の孝至篇に、「孝子愛日」とあり、これが典拠です。日々時間を惜しみ孝行をするという意味です。楊雄の別の著作で、易経に模した著作を『太玄経』といいます。このテキストは当時の数学的知見が含まれていて、興味深い内容となっています。だが難解であり、現代の学者たちは手を付けることがなかなかできずにいます。楊雄は大学者であり、唐の韓愈、北宋の司馬光や王安石とかは、楊雄の業績を高く評価していました。しかし朱熹は、彼の二君に仕えた無節操を『通鑑綱目』で批判して、以降は彼の評判は落ちてしまいました。楊雄は、時代が悪かった。時代は前漢末期で、王莽の簒奪劇にぶち当たってしまいました。楊雄は王莽の功徳を称して古の伊尹・周公になぞらえたり、「秦をそしり、新をたたえる」という文章を作り、王莽を賞賛しました。これが、二君に仕えたという批判となりました。だが王莽は次第に猜疑心を募らせて、重用していた楊雄を疎んじるようになりました。楊雄の門人が罪に問われた時に、楊雄の名が挙がりました。それで取り調べの使者がやってきた時に、楊雄は逮捕されると早合点をして、楼閣から飛び降り自殺を図りました。大怪我をしたのですが命をとりとめ、けっきょく天寿を全うしました。楊雄は、こうして飛び降り自殺未遂の典型となってしまい、後世に飛び降り自殺未遂が起こると、いつも引き合いに出されます。
小田:朱子はそうやって楊雄を批判するのに、こうして引用する。他の箇所でも引用していました。矛盾するようですが。
早川:朱子は、楊雄の言葉だと気づかずに、引用していたのではないでしょうか。そのぐらい、朱子以前には彼の功績は認められていたのです。
時間となりました。後は、一揆にて終電まで。早川君大変ですなあ・・・
2013年5月25日(土)滕文公章句
本日は、小田さん、上田さんの二人。本日分を音読。訓読と意味は小田さん。
滕の文公國を爲(をさ)めんことを問ふ。孟子の曰く、民の事として緩(ゆる)がせにす可からず。詩に云く、晝は爾を于(ゆ)いて茅(ちか)れ、宵(よる)は爾を索(なは)綯(な)へ。亟(すみ)やかに其れ屋に乘れ。其れ始めて百穀を播(ま)かん。民の道や爲る、恆の産有る者は恆の心有り、恆の産無き者は恆の心無し。苟も恆の心無ければ、放辟邪侈(ほうへきじゃし)にして、為せざること無きのみ。罪に陷るに及びて、然して後に從って之を刑す。是れ民を罔するなり。焉んぞ仁人位に在る有りて、民を罔することす可けんや。是の故に賢君は必ず恭儉、下(しも)を禮して、民に取ること制有り。陽虎が曰く、富をすれば仁ならず、仁をすれば富まず。夏后氏は五十にして貢す。殷人は七十にして助す。周人は百畝にして徹す。其の實は皆什が一なり。徹は、徹なり。助は、藉(しゃ)なり。龍子が曰く、地を治むる助より善きは莫し。貢より善からざるは莫し。貢は數歳の中を校(かむが)へて以て常とす。樂歳(らくさい)には粒米狼戻(りゅうまいろうれい)、多く之を取りて虐(ぎゃく)せざるに、則ち寡なく之を取る。凶年には其の田に糞(つちか)ふして足らず。則ち必ず取り盈(み)つ。民の父母と爲して、民をして盻盻(げいげい)然とせしめ、將た歳を終へるまで勤めて動(はたら)きて、以て其の父母を養うことを得しめず。又稱(あ)げ貸して之を益し、老稚をして溝壑に轉びしむ。惡(いづくん)ぞ、其の民の父母爲るに在らむ。夫れ祿を世々にすることは、滕固より之を行う。詩に云く、我が公田に雨らして、遂に我が私に及べと。惟助、公田有りとす。此に由りて之を觀れば、周と雖も亦助すると。庠序學校を設(まう)け爲(な)して以て之を敎ふ。庠は養なり。校は敎なり。序は射なり。夏に校と曰ふ。殷に序と曰ふ。周に庠と曰ふ。學は則ち三代之を共にす。皆人倫を明らかにする所以なり。人倫上(かみ)に明らかにして、小民下(しも)に親しむ。王者起こること有らば、必ず來りて法を取らん。是れ王者の師爲り。詩に云く、周は舊邦なりと雖も、其の命惟れ新たなりとは、文王を謂ふなり。子力(つと)めて之を行はば、亦以て子が國を新たにせん。
滕の文公が国の統治法を聞いた。孟子が言った、「人民のことは、いいかげんに考えてはいけません。詩に言います、『昼には、お前は茅を刈れ。宵には、お前は縄をなえ。さっさと屋根にあがって修理しろ。それが終わったら、ようやく種もみを播け』と。いったいにして、民の性情たるや、常の収入のある者は安定した心を持つが、常の収入の無い者は安定した心を持たないものです。いやしくも安定した心を持たなければ、やりたい放題で驕り高ぶり無軌道に何でもしてしまう。そうして人民が罪を犯してから、罪に応じて刑罰を与える。これでは、人民をわなにかけるようなものです。どうして仁人がしかるべき位にあって、人民をわなにかけていいものでしょうか。だから、賢君は必ず恭儉で、部下を礼をもって遇し、人民から税を取り立てるときには規則に従って徴収するのです。陽虎がこう言いました、『富を蓄えれば仁でなくなり、仁であれば富が蓄えられない』と。夏は(一人当たり)五十(畝?)で、貢(課税)しました。殷人は七十で助(課税)しました。周人は百畝で徹(課税)しました。すべて十分の一税です。周の徹は撤収することで、殷の助は借りるという意味です。龍子が言いました、『土地統治法としては助が最善であり、貢が最悪である』と。貢は数年の収穫高を比べて、その平均量を定量税とする制度です。この徴税法は、豊作の年には収穫の米がありあまるので、多くを取っても虐政ではなく、むしろ取り足りません。だが凶年にはどんなに田に肥料を加えても収量が足りず、だから取り過ぎになります。人民の父母となっていて、人民をあくせく働かして、年が終るまで勤労させて、それでその父母を養うことができない。そのうえ人民に賃貸しして利子をとり、老人や幼児に溝に転げ落ちる苦しみを与える。これでどうして、その民の父母となれるでしょう。「そもそも代々祿をとることは、滕はすでに行っている」(この部分を小林先生は錯簡とされている)。詩経にこうあります、『我が公田に雨がふり、ついに私田に至る』と。これはきっと助の課税であり、だから公田と言っているのでしょう。ここからみるなら、周王朝もまた助を行っていたはずです。庠序学校を設立して人民を教化します。庠は養うこと、校は教えること、序は射礼を学ぶことです。夏では校と言いました。殷では序と言い、周に庠と言いました。学は夏殷周の三代おなじものです。これらは皆人倫を明らかにするためです。人倫が上に明らかになれば、小民は下で互いに親しみ合います。王者が起こることが有れば、必ず滕の国にやってきて制度を参考にするでしょう。これは王者の先生となるということです。詩経にこうあります、『周は古い国であるが、天命は新しい』と。これは、文王の言葉です。あなたが努力して実行すれば、貴方の国を一新することとなるでしょう。」
小田:私、ここのところはあまり真剣に読む気になれません。このような土地政策が、本当に夏殷周で行われていたとは、思えません。この孟子の歴史観は、孟子の時代の社会現実が投影されたものだろうと思います。つまり、中央集権国家が成立して、文字と度量衡が広域で統一され、徴税・司法を実施する官僚組織が成立して、初めて実施される税制ではないか。それが可能となる時代背景は、ようやく戦国時代に完備したはずです。ですから夏殷周の税制だと孟子が主張している制度は、儒家が詩その他の古代テキストの断片的な記述を拾い上げて、それを目の前にある戦国時代の整った国家システムを無批判に過去に当てはめて、想像したものにすぎないのでないか。ここで孟子が進言している農地政策は、近代ソ連のコルホーズとかの社会主義的農業管理法と、原理的に一緒のものです。貧富をなくすことを目的として農民を土地にしばりつけて、現物徴収で収奪するシステムです。耕作者の自由な開墾も移動も認めず、コミュニティーに縛り付ける。社会主義の理想ですが、現実は地上の牢獄です。
上田:貢や徹のなかで助を最善としますが、どれも収穫ではなく区画にこだわりますね。ある区画を決めてそこの収穫を税とする。孟子は正確に区画を決めればあとは座してもうまくゆくとしていますが、正確に区画を決定することは簡単なことではない。
小田:測量が出来ねばなりません。
上田:どうのように測量をしましたか。
小田:検地する役人が必要ですし、収量を検査する役人も必要です。さらに、農民のトラブルを裁定する役人も必要です。戦国時代に中央集権国家ができるまで、そういう条件は整っていなかったはずです。さらに言えばこの制度は、土地に善し悪しがあり、しかも農民の改良により土地の収量は大幅に上昇するという観点がないと思われます。機械的に土地を割り振るだけでは、ぜったい平等な制度とはなりません。きわめて古い時代においては、行政制度などはほとんど存在せず、当然収量の多寡が農民ごとに起こったことでしょう。しかしたとえ起こったとしても、村の中で祝い事とか行事の際に余分に放出したりして調整をはかって平等化するような、おおらかな自治の時代であったはずです。自治に逆らう者は、村から追い出されるまでです。井田法がまるで三代でも完成していたかのように孟子は言うわけですが、そんなことあるはずない、と私は思います。
上田:貢は区画を10に分けて1区画を税にする、これには問題があり、助では皆で1区画を耕作して税にする、周は郊外では助、都市部は貢のアイデアでやっているとしている。夏も殷も数百年続いており、耕す人、野人が居なければ、為政者、君子は養えないとしており、税制がなければ運営はできないでしょう。
小田:とうぜん農村から税として収奪していたでしょうが、井田法のような整然とした農政ではなかったはずで、村ごとへの貢物の義務を割り当てて、村の父老たちに責任をかぶせて一括納付させるようなものだったのではないか。井田法は儒家にとって理想の農政のように言われますが、このようなシステムが成立する前提として戦国時代に勃興した法家的官僚国家があり、裏口から法家思想を持ち込んでいるといえます。ここで言われている「貢」の税制ですが、これは江戸時代に採用されていた定免法(じょうめんほう)のことです。もう一つ検見取法(けみどりほう)があって、これは毎年の収穫を見て税を徴収する法です。(後注:勉強会では、逆のことを言っていました。江戸時代初期は検見取法だったのですが、これを実施するためには役人の数が不足で、行政制度が徴税法に追いつかない。だから享保の改革で定免法に改定して、行政負担を減らして、加えて幕府が安定収入を得る策を取ったということです。このように、ずっと後世の江戸時代でさえ、税を徴収する役人の数は不十分でした。それを、はるか古代の三代でどうやってできるでしょうか?)このような税制に関する議論は、ずっと後世になって始まったものです。
上田:龍子が助が最善で、貢が最悪としていますが、彼は衛の霊公の大夫、公叔戍と親しいとあり、孔子と同時代の人です。鄭の子産も土地制度を導入し農民の猛反対にあうが三年たつと効果があり子産のおかげと喜んだという話がある。
小田:おっしゃるとおり、春秋末期に子産らの政治家たちが、税制改革を始めたのでしょう。その時期になって、税制を施行できるだけの行政システムを国家が持つことができた。そのような条件がまだない時代では、整然とした税を徴収することはできなかった。村ごとに割り当てた貢物のような、荒っぽい収奪だったでしょう。
上田:国家無くして税が有るという事は無い。夏、殷は数百年続いた国家です。
小田:殷はともあれ、たとえ夏が実在していたとしても、その時代において後世に言う国家としての体裁を持っていたかどうか?もっとプリミティブな部族連合の段階ですら、支配者への貢納という形で、税はありえます。歴史学的に見れば、儒家が主張するような整然とした国家制度が三代であったということは、ありえないはずです。孟子は、目の前の発達した社会の現実をそのまま過去の三代に当てはめて、それらの時代には理想の国家制度があったと想定し、それらの国家制度からいいとこ取りをせよ、と勧めたのでしょう。孟子は、実際には戦国時代の制度の改良を薦めていたのですが、それを過去への回帰という言葉で薦めたのです。
上田:孟子は井田法は正確に区切ればあとは簡単だとした。
小田:国有の土地を共同で耕させて収穫を国が吸い上げるシステムであるならば、それはコルホーズなのですが、コミュニティ内の農民にとっては働らこうが働くまいが所得は同じなので、生産性は低かった。それで確かフルシチョフの時代に自留地を認めて、そこでは各農民がマーケットに出して収入を得てもよいとした。それは社会主義の理想から後退した農民への妥協であって、農地面積的にはわずかなものでした。しかしブレジネフ時代になると、自留地からの出荷が大きな割合を占めるようになった。農民は、利で働くのです。
上田:圭田というのはそういうものではありませんか。
小田:圭田が私有地として永久保有を許すのであるならば、農民は肥料をつぎ込み必死に耕作するでしょう。その結果、年を経ると必ず貧農と富農の分離が起こります。ロシアで19世紀半ばに農奴解放が行われたときには、それまで農地の私有が認められなかった農民に、農地が割り当てられました。その後、農村は富農と貧農に分かれていきました。一方は土地を購入してますます富農化し、一方は土地を手放してますます貧農化していきました。土地の私有を認めると、必ずそうなります。それで、スターリンは富農を階級的に絶滅することを実施しました。
上田:夏の貢の不具合を改めることで助が採用され、その不具合を改めるに徹が採用された。
小田:こんな議論が、古い時代に成立していたとはとても思えません。後世の視点から、議論しているのです。魏の曹操が導入した屯田法は、たしかに井田法を参考にしています。この時代人口が激減して、土地が余っていました。それで兵士に均等に土地を割り振って、平時は自作農として自給させる制度を採用しました。これは、当時の社会状況に合っていたから、成功したのです。北魏の孝文帝は、改良して均田法を導入しました。一般農民を戸籍に編入して一律に土地を配分し、税を現物で納めさせました。魏晋南北朝時代のような乱世を乗り切るには、このような農民管理法は有効でした。しかしながら、唐代になって経済が回復すると、農民を戸籍で緊縛して税を徴収するシステムでは税収が思うように上がらなくなりました。それで、唐代後期以降は銭納に移行しました。
上田:税制は国家の基本ですからね。
小田:スターリンの発想も同じようなものだったから、農民管理制度が孟子と似ているのです。貧しくて国家権力が強い時には、井田法のような方法が有効である。しかし、だんだんと経済の実情に農民管理制度がついてゆけず、税収が上がらなくなるものです。それを抑圧しようとすると、また国家権力に頼るようになります。
上田:農業のみでは片肺で物品、市場に関する税が必要でしょう。
小田:戦国時代では、市場税と関所税を取っていたことでしょう。市場税といっても商品に課税することはむつかしいので、場所代として店舗にかける税でした。商人に課税する制度は、古代ではこのぐらいしかできなかったでしょう。漢代などでは、売官売爵によって富商から富を吸い上げることも行われていました。爵位を買うことには実利があって、罪を得たら爵位を返上することと引き換えに実刑を免れる効果があります。刑罰への保険になるわけです。商業というのは、農民と違って国家が把捉することが難しい存在です。だから、商人は国家運営者からは良く思われない。為政者からすれば、不気味なところがあったのでしょう。
上田:富国となれば交易が重要になるんではありませんか。
小田:とはいうものの、古代社会では国力の源泉はあくまでも農業です。農地を増やし、人口を増やして税収を上げることが、富国強兵の目標でした。ゆえに各国は運河を掘って灌漑を行い、新田を拓きました。商業はそこから税を取ることも難しく、国家の育成対称とは見られなかったでしょう。重商主義とか言い始めるのは、ずっと後世の社会のことです。
上田:孟子の税制の議論は、農業偏重であり、当時においても批判があったのではありませんか。
小田:儒者は国家の観点からものを申すので、当時の社会水準では農業重視であるのはいたしかたありません。商業を称える「商家」という諸子百家などいませんでしたが、他の産業とともに商業も弁護する立場であるならば、道家でしょうかね。道家は、国家の諸産業への介入が有害である、という自由放任主義経済思想ですから。儒者は経書に書かれた古い伝承を重視する立場であり、理想の制度を君主に進言するさいには、理想の制度がいにしえの三代に存在していたから復古せよ、と言います。実際には後の時代の実情を前提とした改革案であるのに、復古主義の立場を取るから昔の時代を美化するのです。これと全く対照的であったのが秦の商鞅です。彼は秦に新法を導入する際に、古い制度が正しいという考え方を捨てて新しい法を採用することを宣言しました。国人たちは聞いたことがない制度を導入することに反対しましたが、古い制度が正しいという必然性はない、と押し切りました。彼は、新しい制度を新しい制度として隠さず進言したのです。実は新しい制度なのに古きよき制度の復古なのだ、とねじれた進言をした儒家との違いです。
上田:結局孟子の税制では間に合わなく、秦が統一を果した。それが現実だったのでしょう。
小田:孟子と商鞅はだいたい同時代ですが、当時の人々にとってどちらが耳に心地よかったか、と言えば、たぶん孟子のほうだったでしょう。人間というものは、新しい制度よりも昔の制度と言われたほうが、正しそうに思う保守性があるからです。孟子はこうして復古の建前で改革案を提示したわけですが、そこには人間の性は善であり上が善であれば下もなびいて善になる、といった、当時の社会の実情をよく見ない甘い見通しがありました。荀子はそれを批判して、統治術はそのような君主の善とかではなくて、礼と法の運用によらなければいけない、と言いました。彼は儒家ですが、秦の統治を称えています。荀子の統治術は、法家とほとんど変わりません。儒家の改革案も突き詰めれば、法家の改革案と同じようなものだったのです。荀子は「形名」を正すことを主張します。形とは刑のことでもあり、形名とは言葉や法令の定義を明確にすることです。論語で、孔子が衛の政治改革として「名を正す」ことから始めたい、と言いました。これはいっぱんに名分を正しくすることだ、と解釈をされています。だが、私は違うと思うのです。孔子が言いたかったことは、荀子の形名を正すことだったのではないだろうか。度量衡や法令用語の定義を行うことによって、行政が正しく運営されるようにすること。孔子は、そういうことが言いたかったのではありませんか。国家が出す法令の用語をきちんと定義し、有司の権限の範囲を定め、信賞必罰をマギレないルールに従って行う。春秋時代末期になれば社会が複雑になって、以前のおおらかな時代のままの行政運用ではいっぱい齟齬が表れて、役人の恣意がはびこっていたのではないか。孔子は実務経験が長かったから、その不合理を分かっていたはずです。だから形名を正すことは、上の者の横暴を抑えることでもあり、民にとっても好ましいものであり、国を強くするための有効な策であった。子路はその有効さがよく見えなかったから、「先生はなんと迂遠なのだ」と言ったのです。しかし、秦が強国となった理由は、形名を正したところにありました。荀子は、だから秦を評価したのだと思います。
上田:そういうことはあるでしょう。今日はこのくらいにしておきましょう。
2013年6月1日14:00~16:00 論語読書会in士心
参加者:上田、早川、小田、桐畑孝佑、河村美歩
士心での記録者:小田
学而篇四(読み下しは、中村惕斎に従う。)
曾子の曰く、吾れ日に三たび吾が身を省(かへりみ)る。人の爲めに謀りて忠あらざるか。朋友と交はって信あらざるか。傳へて習はざるかと。
《読み下しのポイント》
「與」の字は現代新字体では「与」に当ります。いくつかの読み方がありますが、ここでは並列の助字であり、「と」と読みます。前の二に出てきた用法では疑問の助字として、「か」と読むこともあります。他に、比較の助字として「より」と読むこともあります。これらは文脈によって読み方を判断するしかありません。
《James
Leggeの英訳》
The
philosopher Tsang said, "I daily examine myself on three
points:-whether, in transacting business for others, I may
have been not faithful; - whether, in intercourse with
friends, I may have been not sincere; - whether I may have
not mastered and practiced the instructions of my
teacher."
(日本語訳例)
哲学者である曾子が言った、「私は毎日三つのことを反省する。他人と仕事をしていたとき、私はまごころから実行してなかったかどうか。友人と交流していたとき、私は誠実でなかったかどうか。私の先生(孔子のこと)の教えを学んでおさらいしなかったかどうか。」
(英訳について)
小田:河村さんは、読み下しも英語訳も、お見事ですね。これは曾子(姓は曾、名は参[しん])の言葉です。曾子は孔子のかなり若い世代の弟子で、年は孔子の46歳下、彼のお父さんも孔子の弟子でした。ちょっと後の章で、孔子の別の弟子の子夏(しか)の言葉が出ています。しかし、レッグは子夏のことを"Tsze-hea"と訳して、曾子や前の二で出てきた有子のように"The
philosopher"を付けていません。これは、曾子、有子という言い方が、姓である「曾」「有」の後に尊称である「子」を付けていることを考慮に入れて、訳し分けているのだと思います。いっぽう「子夏」という言い方は、字(あざな)です。(この人の姓は卜[ぼく]、名は商[しょう]です。「あざな」とは、中国の慣習で普段友人や同僚が呼びかけるときに用いる通称のようなものです。)現代日本語でたとえるのは難しいですが、「曾子」という言い方はいわば「桐畑先生」と呼びかけるようなもので、「子夏」という言い方は「孝佑さん」と呼びかけることに、あるいは近いかもしれません。(実際は、中国の慣習では名で呼びかけるのは大変に失礼なことであるとして、普段は使われません。だから、呼びかけ用の通称としての「あざな」が用いられるのです。)とりわけ曾子は、顔回(がんかい)と並んで孔子の弟子たちの中でも別格の存在として、後世見なされるようになりました。孔子は後世神様扱いされるようになったわけですが、顔回と曾子は神様に仕える高位の使徒のような存在になりました。論語には、曾子の言葉が多数収録されています。
(討論)
河村:この言葉は、否定が三つ続いています。どうして、肯定する言葉にしないのでしょうか?
早川:よいご指摘です。キリスト教と論語を比較したとき、キリスト教ではなすべきことを肯定的に教える内容が、論語ではなすべきでないことを否定的に教える内容にひっくり返されています。キリスト教では「あなたがしてほしいと思うことを隣人にしなさい」であるのが、論語では「己の欲せざるところを他人に施すなかれ」になります。論語で人の道を教えるときには、してはいけないことを戒める、という方向が見えます。
|

|
小田:実際には、「人の爲めに謀りて忠あらざるか。朋友と交はって信あらざるか。」は、「人の爲めに謀りて忠たるか。朋友と交はって信たるか。」と肯定的に言っても、同じ意味となるでしょう。最後の「傳へて習はざるか」だけは、否定にするしかない。だから、語調を整えるために前の二つも否定にした、と言えるかもしれない。曾子は孔子とずいぶん歳が離れた弟子で、父親も孔子の弟子でした。このようなポジションでは、先生が雲の上のような存在となって、自分で何か創作するというよりも、雲の上の先生の教えを忠実に後世に伝えることを自分の役目とするより、他はなかったのではないでしょうか。最後の「傳へて習はざるか」に、その意識が見えているように私には思えます。この「傳へて習はざるか」については、「習はざるを傳ふるか」という読み方もあります。このように読むと、「先生から学ばなかった内容を弟子たちに伝えたのではないか」という意味になるでしょう。曾子は、儒家の本流の学派の始まりとなりました。曾子の後に孔子の孫の子思(しし)が続き、その子思の後に孟子が続きます。
|
桐畑:孔子の弟子たちは、どうやって生計を立てていたのでしょうか?
早川:各国で高い位に昇った人が、多くいました。弟子の子路(しろ)は、魯の隣の国である衛の国で大夫(たいふ)となり、政争に巻き込まれて命を落としました。また冉求(ぜんきゅう)という弟子は、魯の国を実質的に支配していた大貴族の季氏(きし)の家宰(執事)に就きました。他に、子貢(しこう)という弟子は商才が豊かで、投機で大儲けして財を成したりもしました。
小田:子貢も、衛と魯の宰相に昇っています。儲けた金を資金源にして、位を取ったのでしょうね。孔子の学校というのは純粋に学問をしていたのだ、というのが後世のキレイな見方です。ところが、よく論語を読んでみると、孔子の弟子たちの本当の目当ては、学問を習得して各国で就職することにあったのです。孔子の学校で専門知識を得れば、各国の君主とか貴族とかが重宝して雇ってくれるようになりました。それで、孔子の学校は時間が経つにつれて、弟子がどんどん集まるようになりました。当時の就活塾とでもいうべき存在だったのです。
早川:孔子の弟子たちは純粋に学問を望んで集まった、というのは、日本人の論語に対する誤解の一つです。
小田:後世の朱子学が、そのように読ませたのです。朱子学は、科挙の試験問題で丸暗記しなければ合格できない、試験のための学問となってしまいました。試験に受かることが目的だから、教科書の内容なんてキレイな建前を連ねていればよい。その朱子学の描いた美化された孔子学校の世界が、日本では長く信じられて来ました。
早川:漆雕開(しつちょうかい)という弟子が、すでに仕官できるにも関わらず、「私はまだ学問に自信がないです」と言ってまだ学校に残りたい、と言いました。孔子は、この言葉を喜んだと言います。つまりは、彼のように就職を断ってまで学問を続けたいと望むような弟子は、珍しかったということです。
小田:他の弟子たちは、こんな殊勝じゃなかった。
早川:孔子の時代は、前の時代に見られなかった、学問次第で各国に仕官できる時代となりました。それまでの時代は貴族は貴族、平民は平民であり、平民が仕官するような道はありませんでした。そこに風穴を開けたのが、孔子の学校でした。孔子もまた、低い身分から学問で高位にのし上がった人でした。孔子が始めて、弟子たちが後に続いたのでした。
小田:実力本位、下克上の時代の始まりですね。だから、案外今の時代に近いところがあったのです。
桐畑:そのような時代は、いつまで続いたのでしょうか?
小田:続く戦国時代になると、実力次第、金次第で各国の高位に昇る、ということが当たり前となりました。呂不韋(りょふい)という人は大金持ちの商人でしたが、この金を使って秦の朝廷に工作を行い、超大国の秦の宰相にまで昇りました。この辺が、実力本位の時代のピークだったでしょうね。
上田:権力で搾取する側に回って、泥棒の中の元締めの大泥棒になろうとしたということですな。
河村:ところで、「謀」(はかる)という字が使われていますが、これはここではよい意味になっているようです。私のイメージでは、この字は悪い意味なのですが。謀略とか、陰謀とか。
小田:「無謀」「深謀遠慮」という言葉は今でも使われますが、これらの言葉では「謀」はよい意味で使われています。もともとこの字は、「慎重に考える」という意味であり、悪い意味とは限りません。
早川:猶(猷)という字は、現代中国語では"yóu"と読み、これはよい意味限定で「はかる・はかりごと」という意味です。「謀」の字は同じく現代中国語で"móu"と読み、この二つの字の発音は近いです。おそらく非常に古い時代には「かんがえる」とか「はかる」という意味を持った一つの発音があって、それが後世に二つの音と漢字に分かれたのではないか。時代を古く遡ると、今の時代では別の漢字に分かれている区別があいまいになって、一つの字でいろいろな意味に使っている例が、他にもたくさんあります。
小田:さて、ここで「忠」の字が出てきます。先月、桐畑さんが日本に「忠孝」が入ってきたのは儒教起源なのか、というご質問がありましたが、この曾子の言葉では、「人の爲めに謀りて忠」というわけで、他人一般に対して「忠」であるべきだ、という使い方をしています。だいたいが「忠」の字の本来の意味は、「まごころから行う」という意味です。対象は、一般人でもあり、友人でもあり、主君でもありえます。主君とか天皇とか会社とか、目上の存在に対して滅私奉公する、という日本での意味は、「忠」の意味を狭く捉えているのです。
早川:現代中国語では、「忠」の意味を本来のとおり広い意味で使います。妻に「忠」などと使われます。
小田:だけれども、支配者の側から見れば、主君に無条件に「忠」であることが、最も都合がよい。論語の時代では「忠」の意味は相手を限定していませんでしたが、時代が下るにつれて、中国思想では主君と国家に「忠」でなければいけない、国家が成り立たない、という主張が大きくなっていきました。日本には、後世の思想である主君と国家への「忠」が輸入されて、定着しました。それで、「忠臣蔵」とかになるわけです。だから、主君とか国家とかへの「忠」という思想は、後世の儒教の影響はもちろんありますが、論語本来の思想とはちょっとずれがあります。
河村:この言葉は、普通に人生訓みたいな内容ですね。経営者の人たちには論語を読んでいる人が多いということですが、こういった言葉から影響されているのでしょうか。全部通して読むというよりも、拾い読みができる?
早川:論語は短い言葉の集まりで、前後の関係を考えなくても拾い読みできるところがあります。渋沢栄一のように、「論語と算盤」と言って経営の指針にすることもできます。
河村:この言葉とかは、政治とは関係がない。日常生活に活用できそうです。
小田:次の章とかは、政治のことを言っています。とはいえ、論語は政治のことばかり書かれているわけではありません。
では、次にいきましょう。桐畑さん、お願いします。
学而篇五(読み下しは、中村惕斎に従う。)
子の曰はく、千乗の國を道(おさむ)るには、事を敬(つつし)んで信あり、用を節して人を愛し、民を使ふに時を以(もっ)てす。
《James
Leggeの英訳》
The
Master said, "To rule a country of thousand chariots, there
must be reverent attention to business, and sincerity;
economy in expenditure, and love for all men; and the
employment of the people at the proper
time."
(日本語訳例)
先生が言われた。「戦車千台の国を統治するためには、仕事に敬心を持って注力し、かつ誠実でなければいけない。支出を節約して、すべての人を愛しなければいけない。そして、人々を使役するときには適切な季節に行わなければならない。」
(英訳について)
小田:戦車といっても、現代の砲塔のついた車ではなくて、馬に引かせて敵陣に突撃する古代の戦車です。馬と車と乗員を揃えなければならず、費用がかかる兵器であり、これを多く揃えることは国力を示すシンボルでありました。「千乗の国」という言葉は当時の決まり文句で、戦車千台を動員できるほどの大きな国、という意味です。これが次の戦国時代になると「万乗の国」という言葉が現れて、国の規模がさらに大きくなります。「適切な季節」というのは、人々は農民なわけですから、種まきや収穫の農繁期を避けて、冬の農閑期に運河の溝さらえとか城壁の補修とかの土木工事に動員しなさい、という意味です。
早川:日本でも、かつて天皇のことを「一天万乗の君」と言ったりしました。
河村:「用」という言葉が、"expenditure"の意味になるのでしょうか?
早川:「費用」の「用」です。その意味があります。
(討論)
河村:普通に、経営のお手本になりそうな言葉ですね。
小田:言うのは簡単だけれども、実行するのは難しいでしょう。この時代はまだ貨幣経済が浸透する前の時代ですので、税収は穀物とか布とか家畜とかの、現物徴収だったでしょう。それらからまず役人たちに現物給与として与え、残りは土木工事のための給与、外国からの物品の購入、それから軍事支出に用いたことでしょう。その中で最も支出拡大に動きやすかったのは、軍備の増強だったことでしょう。軍備を充実させなければ他国からの侵略を招き、また他国への介入ができなくなる。だから軍備を増強させようとするでしょうが、それによって役人への給与を削ったり、また増税したりするならば、やがて国が転覆するでしょう。だが、政治を行っている当事者は、雑音に惑わされてこの言葉のような原則が見えなくなるものです。
上田:経営するときには、無謀な投資を行わず、従業員を細やかに配慮しなければいけない。これを怠ると、ホリエモンみたいになる。
小田:私は、堀江氏の言っていることは、一つの見解であると思っています。欲望のままに金を儲けることは、悪でない。国の制約などは無用であって、天皇など必要ない。結局この道を推し進めることは日本という国の解体につながるのですが、個人が先にあって国が先にあるのではない、という考えは、一つの見解であると思います。それが正しいと思うか思わないかは、各人が判断するべきだと私は思います。
桐畑:孔子の学校への授業料は、金銭ではなかったのでしょうか?
小田:現物だったでしょうね。まだ、貨幣が普段の生活で出回る時代ではない。
桐畑:貨幣が出回る時代になるのは、いつからでしょうか?
小田:さきほど話があった弟子の子貢が、投機で大儲けしたということであり、彼のような投機で儲ける人間がちょうどこの頃初めて出てきました。子貢がその時に投機で蓄えたのは、黄金とか絹布とかのどの国でも高価で通用する品だったのではないでしょうか。次の戦国時代になると、各国が銭を鋳造するようになり、さきほどの呂不韋(りょふい)のように金の力で国の宰相にまで昇るような時代となりました。しかし、このように貨幣経済が発達した時代というのは、社会が壊れている時代です。金を通じないで助け合いで生活できる農村のコミュニティが壊れて、貧富の差が大きくなり、人どうしが信頼できなくなる、そんな時代が戦国時代であったでしょう。(古代の貨幣経済についてのもっと詳しい説明は、山田勝芳『貨幣の中国古代史』朝日選書を参照。)
河村:孔子の学校には、入学試験はあったのでしょうか?
早川:いや、「束脩(干し肉の一束)を持ってきたものから以上は、私はどんな人でも教えなかったということはない。」(述而篇、七)とありまして、礼儀上最も軽い手土産であった干し肉一束を持って来たら、誰でも入門を許すということでした。また、互郷(ごきょう)という、人々があまり近寄りたがらない集落の若者が孔子に会見を求めてきて、弟子たちが怪しんだにも関わらず孔子は会ってあげた、という話もあります。(同じく述而篇、二八)孔子学校は、来る者を拒みませんでした。その互郷というのが、どうして差別されていたのか、古い時代のことでよく分かりません。現代日本の被差別部落に相当するような集落だったのか、、、
小田:私は、異民族だったのではないか、と思いますが。
上田:孔子が政治について語る際に、「礼」に従っているかどうかを、最も注意しました。孔子が若い頃に、陽虎という魯の家臣が魯の三桓氏(さんかんし)という大貴族たちの支配を転覆するクーデターを起こして、一時期魯の政治を握りました。その陽虎は、孔子のことを自分の同士だとみなして、クーデター政権に参加するように求めました。孔子は承諾するようなことを言いながら、結局断りました。その陽虎のクーデター政権は結局崩壊して、元の三桓氏の支配が魯に戻りました。その孔子は、後に魯で出世したとき、やはり三桓氏の力を抑えて魯の殿様の権力を復活させようと試みて、やはり三桓氏の反対に合って失脚しました。孔子もまた、家臣が力を持ちすぎていると国の秩序が乱れることを懸念していた。「礼」というのは国のあるべき秩序の姿です。上に立つ者は秩序に従って、下の民を愛さなければならない。
小田:日本の江戸時代に、どうして儒教がすんなりと受け入れられたか。その理由は、江戸時代の幕府、大名、武士という封建秩序が、論語などに書かれている理想の「礼」の社会に近かったので、違和感なく受け入れられたからではなかったか、と私は思うのです。論語に書かれている政治の理想は、殿様が目に見える範囲内の領域と民を細やかに統治して、殿様と家臣とが近い関係で秩序の中で協力し合う、そのようなものです。これは、それほど大きくない各藩の領域の中で、整然とした身分秩序の範囲内で国を運営する、という江戸時代の社会事情と、きわめてよく合ったものでした。江戸時代には、最初朱子学、つまり南宋の朱熹の解釈した儒教が入りました。しかし、朱子学は導入されて100年ぐらい経ったら、日本の学者によって完膚なきまでに批判されてしまい、そこから後は日本独自の論語の読み方が流行しました。朱子学は、中央集権王朝の実情に都合がよい学問でした。試験にさえ受かれば、誰でもエリートになれる。だから、人は誰でもエリートを目指して超人的に努力して、人間性を高めなければいけない。(具体的には、科挙の試験に受からなければいけない。)このような朱子学の教えは、しかし江戸時代の封建制度と矛盾していました。ある人は、日本人が朱子学を体現した国家を作ったのは、実は明治政府であったと言います。明治政府は、身分秩序を撤廃し、試験にさえ受かれば誰でも国家官僚になれる。国民は、すべからくエリートなることを目指すべきであり、そして全ての国民が超人的に努力して、お国のために尽くさなければいけない。論語の世界は、朱子学のようにも読むことができるし、江戸時代の学者たちが読んだように身分社会の「礼」を薦めた書であるように読むこともできる。いろいろな読み方ができる書というのは、それができた当時の一筋縄ではいかない複雑な社会事情を反映した結果であると思われて、論語が優れた古典であることの証明であると、私は思います。(朱子学と明治国家の関係については、小倉紀蔵『朱子学化する日本近代』藤原書店を参照。江戸時代儒学の歴史については、丸山真男『近世儒教の発展における徂徠学の特質並にその国学との関連』に詳しい。)
もう少し時間があります。次にいきましょう。再び河村さん、お願いします。
学而篇六(読み下しは、中村惕斎に従う。)
子の曰はく、弟子入りては則ち孝あり、出ては則ち弟あり、謹んで信(まこと)あり、汎く衆を愛して仁あるに親(ちかづ)き、行って餘力有るときは、則ち以(もちひ)て文を学ぶ。
《James
Leggeの英訳》
The
Master said, "A youth, when at home, should be filial, and
abroad, respectful to his elders. He should be earnest and
trustful. He should overflow in love to all, and cultivate
the friendship of the good. When he has time and
opportunity, after the performance of these things, he
should employ them in polite studies."
(日本語訳例)
先生が言われた。「若者よ。家の中にいるときは、親孝行しなさい。家の外に出たと
きは、年長者を敬いなさい。熱心であれ、そして人を信頼しなさい。万人への愛で心を満たし、よい人たちとの友情を育みなさい。これらのこ
とを行った後、まだ時間と機会があるならば、その時間と機会で高級な学問に進みなさい。」
(英訳について)
早川:"
cultivate the friendship of the
good"は、かなり意訳していますね。
小田:「filial」は、親孝行という意味です。
(討論)
小田:孔子の学校が就活塾だ、ということは、さっき申したとおりです。だから、放っておいても専門知識については、皆勉強したことでしょう。しかし、その学長の孔子は、生徒たちに向けてこんなことを言っていた。専門知識よりも先に、社会人として常識ができあがっていないといけないぞ、と。まず社会人として立派な存在となり、専門知識を身につけるのはその後だ。
河村:大学の先生もまた、そう言っています。
小田:今日はもう読む時間がありませんが、この言葉は次の子夏の言葉と、表裏になっているのです。子夏の言葉は、社会人としての常識ができているならば、たとえ専門知識を学んでいなくても、私はその人が学のある人だとみなすのだ、と言います。学のあるなしよりも、社会人としての立派さのほうが格が上なのだ、と。日本の経営者が好きそうな言葉です。ここの言葉に限って言うと、「孝」「弟(悌)」を守れ、という教えがあります。目上の者に服従しなさい、という教えであって、戦後の日本では評判が悪い教えです。アメリカ式に、年齢の区別など抜きにして、対等のフレンドリーな関係がよいのだ、という教えのほうが、流行りです。私は、それはそれで貫徹できたならば、よい社会を作ることができるだろう、と思います。しかしながら、日本の社会にアメリカ式の人間関係が合っているかどうか、という問題に関しては、私はいささか疑問を持つところです。私も以前役所の組織で働いていたことがあり、その世界は年功序列の慣習が強くありました。年功序列には、若い者から見たら不合理な点があります。年が若いというだけで、我慢しなければいけないことがあります。若い上司が年上の部下を使うときには、ものすごく気を使わなければなりません。しかし、組織がその慣習で全体としてうまく動くならば、尊重するしかない。
桐畑:幕末時代、日本を共和国に作り変えよう、という主張はなかったのでしょうか。
小田:思想としては、あったと言えるでしょう。横井小楠という優れた学者は、アメリカの大統領制を「堯舜の世」と絶賛して、理想とみなしていました。それで、危険思想家として暗殺されてしまいました。また、死ぬ間際の吉田松陰の思想は、天皇そのものの否定までは行かなくても既存の朝廷・幕府・各藩の体制を全否定して、民衆主導の革命の呼びかけへと傾いていきました。アメリカを理想国家とみなす考えは、結構多くの開明的な志士たちが持っていたところです。
桐畑:その人たちは、論語を読んでいたのでしょうか。
早川:むしろ、暗記していたでしょうね。
(小田後注:明治維新の直後に、明治政府の高官たちが大挙して欧米各国を訪問して、不平等条約の撤廃を交渉し、また欧米に国づくりを学ぶ旅に出ました。いわゆる「岩倉使節団」です。このとき、ちょうど欧州ではプロイセンがフランスを破って、ドイツ帝国が成立した直後でした。使節団は、ドイツ宰相ビスマルクと会見して、強い感銘を受けたということです。
使節団はイギリス政府と談判のさい、専制政治と自由政治はイギリスで実験したが、「遂ニ自由の大利を知リシナリ」と、日本の人民の言論・出版・思想・信仰の自由を保障するよう要望せられたが、大久保(利通)などは、米英仏の文明は日本よりも数段上で、日本がいくらまねをしも「およばざること万々なり」とし、「普・魯(プロシャとロシア)の両国にはかならず(日本の)標準たるべきこと多からんと思考」して、後輩にもこの両国の研究をすすめていた、、、大久保が帰国後、日本のビスマルクを気取り、かれのなき後をついだ伊藤(博文)もまたビスマルク気取りでいたことは、有名な話である。(井上清『日本の歴史20明治維新』中公文庫より)
こうして、維新の元勲たちは、遅れた日本の国情に最もふさわしいモデル国家としてドイツ帝国を選び、民主制国家よりも強権的国家に日本が向かうことになりました。大日本憲法は、ドイツ帝国憲法がモデルでした。)
2013年6月8日(土)里仁篇
本日は、早川君、小田さん、上田さんの三人。里仁篇を早川君のリードで音読。訓読と意味は小田さん。
子の曰はく、古者(いにしへ)言を出さざるは、躬の逮(およ)ばざるを恥ずなり。
古者と言ひて、以て今の然らざるを見(あら)はすなり。逮は及なり。行、言に及ばざれば、恥ず可きの甚だしきなり。古者其の言を出さざる所以は、此が爲にして故なり。○范氏が曰く、君子の言に於るや、已むことを得ずして後之を出す。之を言ふこと難きに非らず、之を行ふこと難し。人惟其れ行はず。是を以て輕く之を言ふ。之を言ふこと其の行ふ所の如く、之を行ふこと其の言ふ所の如くせば、則ち諸を其の口より出すこと、必ず易からず。
孔子が言われた、「昔の人が言葉をあまり多く発しなかったのは、行動が及ばないのを恥じたからである」と。
昔に言及するのは、今の時代がそうでないことを明らかにしようとしているのである。「逮」は及ぶということである。行いが発言に及ばないことは、最も恥ずべきことである。昔には言葉をあまり多く発しなかった理由は、このためなのである。○范氏が言った、「君子たるもの、言葉はやむをえない事情があってから発言するものである。それは、発言することが難しいのではない。発言したことを行うことが難しいのである。人というものは、行動しないものである。だから、軽々しく言葉を発するのだ。だが発言が行動に合うように、行動が発言に合うようにするならば、言葉を発するのは容易なことではなくなる」と。
早川:「惟其(ただそれ)」は、その意味を取るのがなかなかに難しい語でして、この語について論じた論文があるくらいです。
小田:この言い回しは、朱子の時代特有のものなのでしょうか?
早川:いや、左伝でも見られる古い表現を、あえて後世に模倣して使っているのです。古代の口語的表現というべきであり、後世から読み取りにくいニュアンスがあります。「惟其」以下のことを際立たせる表現です。ここでは、「人というものは行動しないものだ」ということを強調して、だから軽々しく言うものだ、とつなげているのです。「惟其」が出てくると、文中で著者が一番言いたいことを表しています。
小田:ここから数条は、君子の言葉についての話となります。里仁篇は、全体として君子論を語っている篇であると思うのですが、ここはそのまとめのようなものでしょうか。君子の発言は、こうあらねばならないと。
早川:ここまで親孝行の話題があって、ここから自分に対する反省に移ります。次の次の朱子注で引用される胡氏の言葉で、「吾が道一貫より此に至るまで十章、疑ふらく、皆曾子門人の記す所ならん」とあります。吾が道一貫の条から十条は、まとまりがある同一の者の記録であり、おそらく曾子の門人であろう、ということです。
小田:私が思いますに、里仁篇は本来「德は孤(こ)ならず、必ず鄰有り」で終わっていたのではないか。この条で終わると、君子論が引き締まります。仁の説明から始まって、君子の進退、忠恕の精神、孝の行為、言葉への注意と続いて、最後に「だから君子は孤立することがないのだ」とまとめて、君子道を称揚する。しかし、最後の子游の言葉は蛇足的な付け足しに見えてしまいます。疑うに、この条は子游の弟子が置かせたのではないでしょうか。ひょっとすると里仁篇は、子游の弟子が編纂したのではないかとも思うのですが。里仁篇はひた押しに孔子の言葉を繋げていながら、最後だけ子游の単独発言であって、全体から浮いてしまっている。これは、編集者の師の言葉を最後に挿入したのかもしれない。
早川:だが、もし子游の弟子が編纂したのなら、もっと子游の言葉があってよいでしょうね。それはないと思います。
小田:この条についてですが、「古者」というときに想定していたのは、歴史的時代の人々というよりも、むしろ孔子の若い時代の大人たちの雰囲気を思い出して、孔子が今どきの時代と前の世代の時代との落差を言っていたのかもしれないと思うところです。孔子の時代、しだいに言葉の遊戯のために言葉を使う、「しゃべり」が人々に多く見られるようになったのではないでしょうか。子貢などは孔子と近い世代ですが、彼にはすでに言葉を過剰に操るところがあった。「子貢、人を方す。子の曰く、賜や賢なるかな、夫れ我れは則ち暇あらず(憲問篇)」というやり取りがあった。子貢は、会ったこともない他人について、あれこれと評論家の言葉を費やした。孔子は、子貢のその評論家風情に対して、「ずいぶん賢明なんだな。君はいったい何様のつもりなんだよ?」と皮肉を言ったのではないでしょうか。他人の悪口を言ったことを責めたというよりも、当事者でない子貢が、あれこれと人物批評をしたことに、孔子はカチンと来たのかもしれません。そのような「しゃべり」は、昔の世代にはなかった。子貢は、後の子張とか子夏とかの新しい世代の「さきがけ」みたいなものだったのでしょう。孔子に共感して付き従った面々といえば、たいていが言葉巧みな知恵者たちでした。だいたい孔子自体が、言葉と文化で評判を得た人であり、新しい世代の開拓者だった。最も高い知性の秀才たちが孔子の下に慕って集まったという事実が、孔子が時代の最先端を行っていた証拠だと思います。しかし孔子としては、自らが時代の破壊者であったにも関わらず、古い時代のよさを感じ取っていて、古い時代が壊れていくことを自覚していたのではないでしょうか。孔子は、だから矛盾の人というべきでした。
早川:言葉に対する危機感は、あったでしょう。「其の位にあらざれば其の政を謀らず(憲問篇)」の意味は、位にあって責任の範囲外のことを発言することへの戒めであったでしょう。
小田:職分から外れた発言は、災厄を招くおそれがある。
早川:時代が下って明清あたりの時代になると、口語表現の文章化も発達して、言葉が氾濫するようになります。そのような時代になると、古代人の言葉に対してもつ危惧というものが、分からなくなってしまったことでしょう。
上田:言葉と行動の話で、言葉は心に思う事が口に出たもの、それと行動の関係ですが、現代人は心に思うことが本当に自分が思っていることか怪しく思いますが、この頃は、どうなんですか。
小田:(現代人が「内面」が存在しているという思い込みは、現代人特有の現象なのであり、)言葉が貧弱な時代においては言葉は全て過去の伝統から受け継がれたものであって、「私はこう思う」というような表現はなかなか成り立たない。しかし、孔子の時代くらいになると、伝統的表現に対して「これはどうしてこのように言われているのか?」「この言葉はどうして正しいのであるか?」というような自覚的吟味が行われて、主体的に言葉を選んで扱う習慣がだんだん発達していったのだと思います。
早川:古代では名と実、つまり言葉と物が乖離すると調和が乱れるという感覚がありました。
小田:春秋戦国時代というのは、社会が不安定となった時代です。安定した伝統的社会というものは、「位」と「富」と「徳」とが一致しているものです。村では長老が最も尊敬され、最も富を占め、そして村のために最も徳をもって村人のために公正に再分配を行うということが当たり前である。王朝もそうであって、貴族が尊く、富を独占し、そして国のために公正に再分配を行うというのが当たり前のことであった。それが、春秋時代になると社会が不安定となり、「富」と「位」と「徳」とが必ずしも一致しなくなる。貨幣経済が次第に侵入して、位なくして富を得る者が現れる。社会が一枚岩でなくなった結果、位ある者たちが責任を果たさなくなり、しかるべき徳を持っていないのではないかという批判が現れる。その反射として、むしろ位も富もなくても徳を持つ者が君子である、という考えが生まれてくる。孔子がことさらにほめた顔回などは、位も富もないが徳を持っている存在のモデルとして孔子にほめられたと言えるくらいではないか。孔子が思想を始めたことには、春秋時代の社会の不安定化が背景にあるはずです。偉い者が自明の理でなくなった。だから、社会の不公正に対して「なぜ?」という疑問が発する。このとき同時に、言葉を伝統どおりに受け取らず、吟味する意識も生まれたのだと思います。
上田:言葉は誰が使うかで随分変化する。神託みたいなものと王が使う場合、諸侯や大夫が使う場合、士レベルとなると言葉の使い方も意味も違ってくる。
早川:易、繋辞伝に「子曰く、書は言を尽くさず、言は意を尽くさず」とあります。心に思う事は、言葉に十分表すことができない。そして言葉は十分に文字に表せない。繋辞伝は伝統的に孔子が書いたものであるとみなされているのですが、たとえ後世漢代あたりの作であったとしても、古代人にとって意と言葉と文章との間にギャップがあるということは、すでに自覚されていたことが分かります。
小田:漢文では、三者のギャップが痛烈に感じられることでしょうね。ギリシャ語などの西洋語であるとディテールを分析的に表現することが可能なので、三者のギャップはむしろないようにするのが正しい文章なのだ、という信念が支配します。だが漢文では、とりわけ話し言葉と書き言葉のギャップが非常に大きい。ところで、徂徠の『論語徴』の刊本を見ると、この条と二つ後の条の注がありません。落丁でなければ、徂徠はこれらの条を飛ばしたということでしょう。
早川:他の条も飛ばしているのでしょうか。
小田:ここまででは、そういうことが見当たりません。飛ばしているならば、意図的でしょう。徂徠は、雄弁の人です。言に言を連ねる人です。もしかして徂徠は、これらの条の言葉にギクリとして、注釈できなかったのではないか。
早川:意味深ですね。
上田:甲骨文字の時代の言葉は天帝の意を伺うもの、金文は王の盟約を刻したものと言葉と行為が厳しく一致していたが、この時代になると言葉は政治を記録したり、政治を論じたりで随分変化した。
小田:それだけ、言葉を操作することがうまい人が増えたということです。時代が変化したということです。
早川:日本の中世から近世に至るまでの講義録に興味があって、読んでみたことがあります。そこで使われているの言葉を見ると、室町時代の清原家とかの講義は、単に古典の言葉の引用を羅列しているだけで、内容の検討というものがありません。それが江戸時代中期以降の石門心学の講義になると、テーマを表から裏からいろいろな喩え話を用いて解説しようと試みています。言葉遣いもまた、噺家のような口語的な講義録となっています。明治になるとさらに言語の技術が上がります。時代が下るにつれて、講義の言葉遣いが変わってきます。室町時代は単に伝承をそのまま伝えるだけだったのが、石門心学になると内容を多方向から理解しようと試みるようになりました。孔子の言葉は2500年前のものですが、その時代であるにも関わらず今に読んでも思想的内容があるのは、言葉から意味を読み取ろうとする視座があったからでしょう。西洋のソクラテスも孔子とほぼ同時代を生きましたが、あの時代は西でも東でも人類における言葉の発展があった。孔子以前の時代、晏子や管仲が孔子のような意味を吟味した言葉を残すことができたかどうか、疑問とするところです。
小田:思いますに、思想あるところには、同時に貨幣経済が現れます。両者は、社会が崩れ始めた時代に現れるものです。2500年前、東の中国と西のギリシャで、同時代的に不安定な社会が発生した。「富」と「位」と「徳」が一致することが自明でなくなってしまった社会が、発生した。その時代に生きる者は、どうして社会が不安定なのかを考え始めた。貨幣経済の浸透の結果、「位」なくして「富」を得る者が出てくる。社会が崩れ始めた結果、「位」と「徳」とが同じ人間に宿る、ということが自明でなくなる。ここに思想が始まり、言葉の吟味が始まったはずです。
早川:中世の講義は、単に右から左に引用を移し変えるだけです。孔子は「述べて作らず」と言ったわけですが、孔子は右から左に引用を移し変えていただけに留まらなかった。
小田:たとえ素材は昔の言葉であったとしても、選択して編集する作業において、解釈が入ります。孔子が語った言葉はたいていが古語の引用であったとしても、それをどのような文脈で用いたかに、オリジナルな思想が入ります。
上田:孔子が春秋に注をしたようなもの。孔子は述べて作らずというが、詩や書を教えるときに当時の言葉で説明しますからね。
早川:春秋は孔子が編集したかどうかは論争のあるところですが、春秋の編集のやり方は、孔子的であったといえるのではないでしょうか。一文字ごとに意味を凝縮して選択する、という筆法は、孔子の編集意識としてふさわしいと言えるでしょう。後世の漢文の規範となりました。それを注釈した左伝が左丘明の作であるという説は怪しいですが、注釈者の意思として孔子の編集方針を受け継いでいると言えるでしょう。
小田:左伝は、前漢末に劉歆が漢の書庫から左丘明の注釈書を発見した、と発表したところから始まったわけですが、後漢時代には従来の注釈書であった公羊伝・穀梁伝に左伝を加えるべきかどうか大論争があって、鄭玄の頃にようやく公式経典として認められたいきさつがあります。以降はむしろ左伝が最も尊重すべき注釈書として権威が高められるようになりました。だが、このようにちょっと出自があやしいテキストです。
早川:後漢代には、批判派が左伝の膏肓の病と言う批判書を出せば、鍼で治療するという反批判書を出したりされました。近年は劉歆の偽作説が流行しているのですが、最近戦国時代の竹簡から当時の左伝テキストが発見された、とニュースになって、定説が覆されたと大騒ぎになりました。ところが、検討した結果それが偽物と判定されて、また大騒ぎになりました。また、『大学』の「治国・平天下」のくだりは後世の概念であるはずで、だから『大学』は後世の偽作であるという説が広く流行していたのですが、前秦時代の出土物にすでに同様の表現があることが判明して、これも定説が覆ってしまいました。古代思想史は、いま現在成立年代がどんどん古くなっていて、前の時代のなんでも漢代まで新しくしてしまう流行からの逆転現象が起こっています。
小田:私が読んだ左伝の解説書では、劉歆の偽作説は言い過ぎであって、おそらく戦国時代の三晋、なかでも魏・韓の歴史家(左氏)の編纂であったのではないか、という主張がなされていました。その理由は、魯斉の出来事中心に書かれている『春秋』本文に比べて、左伝は晋関係の記事が大量に収録されていることです。劉歆は、もともと『春秋』と無関係の年代記であったテキストを、年度ごとに記事を分割してこれを左丘明の『春秋』注釈書だとみなして発表したのではないか、という疑義でした。
中国は、ヘーゲルやマルクスの影響で、メソポタミアやエジプトと同質の専制文明である、と見なされ続けています。マルクスの言う、「アジア的生産様式」(Asiatische
Produktionsweise)です。私は、秦始皇帝の統一以降の中華王朝は、おおむねマルクスのように分類されても致し方ないと思います。しかしながら、こと春秋戦国時代に限って中国の歴史を見ると、オリエントの諸文明とは明確に違う点が、二点あります。一つは、思想が発生したことです。もう一つは、貨幣経済が浸透したことです。エジプトもメソポタミアも、あれだけ大きな建築物を作り、発達した灌漑農業を築いたにも関わらず、(後世の意味における)貨幣がありませんでした。(正確に言えば、外国貿易の決済としての貴金属[決済手段としての貨幣]や、神殿へのお布施や罰金の支払いのための貨幣[支払手段としての貨幣]はありました。だが、商品の全目的的な対価として流通する貨幣[交換手段としての貨幣]は、見られませんでした。)これは、現物経済で社会が十分安定的に運営できたからであり、「富」と「位」と「徳」を全て持った存在が村にも(長老)王朝にも(王と貴族)揺るぎ無く存在し続けて、動揺がなかったからです。そのような安定した社会であったから、思想もなかったのです。
ところが、中国の春秋戦国時代は、この両者がありました。これは、オリエントの諸文明と、決定的に違う点であったと、私は思うのです。社会が不安定になるから、貨幣経済が勢いを得て、子貢のように無位無官のぶんざいで巨富を積んで社会的に制裁を受けない時代が現れました(安定的な社会では、子貢のような存在は直ちに国家から追放されるはずです。)そして、社会が不安定になるから、正義が自明の理でなくなり、人々が「なぜ?」を問わずにはいられないようになりました。思想の始まりです。
だから、私は春秋戦国時代、そしてその基盤を作った周王朝というのは、マルクスの分類に当てはまらない中国史で特殊な時代であったのではないか、と思うのです。ここからは想像ですが、周に先行する殷王朝は、メソポタミアやエジプトと同様の、中央集権的専制国家だったのではないか。(もっと特定するならば、首都での戦争捕虜の生贄の祭りによって国家を統合する点においては、アメリカ大陸のアズテク王朝や西アフリカのダホメ王朝と同質の国家運営方針であったように思えます。儀式的大量殺人が権威を作る専制王朝の例は、時代と地域を越えて世界的に存在します。)それを、文化的にははるかに劣る西方の蛮族であった姫氏の周が侵入して、殷王朝を倒したのではないだろうか。姫氏の周は蛮族であったが戦士集団であり、日本の武士のように同族の間の人間関係が濃厚であった(一族の恥となれば直ちに死に、上に立つ者は一族全体のために生きなければならない)。だから、自分たちが滅ぼした殷王朝の中央集権システムを維持できるだけのノウハウを持たなかったが、代わりに信頼できる一族を中国各地に派遣して、人間のネットワークで分権的に支配する体制を、やむをえず取ったのではないだろうか。それが、周王朝の「封建制」だったのではないか、と思うのです。このシステムは、始めはうまくいった。だが、時代が下るに連れて同族の連帯が形骸化して、各国でてんでばらばらに割拠する時代が現れてしまった。それが、春秋戦国時代ではなかったか、と私は思うのです。始皇帝の統一は、いわば殷王朝への先祖返りであって、中国史で特殊な時代であった周王朝時代から中国の本来の統治原理への復興というべきものではなかったか。勝手なアイディアを申して恐縮ですが、そのように思うところです。(春秋時代の六芸には、戦士集団の技能が濃厚に含まれています。これは、姫氏の周王朝が本来持っていたエートスの名残だったのではないでしょうか。そしてその六芸が後世の中華王朝時代で全く放棄されたことは、周王朝時代が中国の歴史で特殊な時代であったことの、一つの傍証かもしれません。)
早川:柳宗元が、周時代の封建制の中国史における特殊性を指摘しています。西洋で貨幣が現れたのは、いつの時代でしょうか。
小田:小アジアのリディアにおいて、紀元前6世紀のことです。ちょうどバビロン捕囚の時代です。
早川:乱世の時代であった。
小田:この時期になって、オリエントの辺境で貨幣が現れた。そのさらに辺境にギリシャがありました。ユダヤ人もこの時期にとつぜん集団で強制移住させられた時から、特異なユダヤ教が始まりました。(そして、外国でいったん生活せざるをえなかった彼らは、その後に農業を捨てて商業民族となりました。)「なぜ?」を問う思想は、不安定な社会から起こるものだと、私は思います。そして不安定な社会では、貨幣経済が侵入します。
子の曰はく、約を以て之を失する者は鮮し。
鮮は上聲。○謝氏が曰く、侈然(しぜん)として以て自ら放(ままに)せず、之を約と謂ふ。尹氏曰く、凡そ事約なれば則ち失鮮し。止(ただ)に儉約を謂ふのみに非ず。
小田:朱子注に近づけて訳します。
孔子が言われた、「自制して失敗する者は少ない」と。
鮮は上聲。○謝氏が言うに、「驕り高ぶり自ら放縦にならないことを『約』というのだ」と。尹氏が言うに、「およそ物事に『約』であれば失敗は少ない。単に倹約のことを言っているだけではない」と。
小田:尹氏は孔安国の注(倶に中を得ず、奢は則ち驕、佚は禍を招く、儉約は憂患無し)について批判しているのでしょう。単なる生活上の倹約だけではなくて、自制のことだと。
早川:「之謂約」は韓愈がよく使うフレーズです。朱熹は韓愈を評価しますのでそれを取り込んだのでしょう。
小田:「約」の解釈ですが、貝塚・金谷両氏の日本語訳は朱子注を採用していますが、宮崎市定氏の日本語訳は徂徠注をあえて採用しています。つまり、孟子の「憂患に生き、安逸に死す」がこの条の意味であると。徂徠には珍しく、孟子を引用しています。
早川:つまり、人間は困難とともに発展がある。しかし安逸には発展がない。
小田:徂徠が言うに、「古単に約と言ふ者、困約と約束とのみ。孔安国・朱子ともに之を失す。」こう言って、徂徠は「約」は困約の意味だと断じているのです。
早川:宮崎先生の訳は?
小田:「子曰く、逆境におかれたために大失敗することは滅多にない。」
早川:宮崎先生には、何があったのでしょうか?
小田:どうでしょうね。今どきの学生たちに向けたメッセージとして、「ぬくぬくと生きていると、大成しないよ」と呼びかけたのでしょうか。徂徠は、父親が江戸所払いの罰を受けて九十九里浜の田舎で少年時代を過ごしました。そんな辺境でどうやって勉強したのか、謎です。逆境から学者生活を始めたので、この注となったのかもしれません。
早川:江戸に帰ってきて塾を開いたが、最初は困窮して隣の豆腐屋にお情けでおからをもらって生活した。講談になっています。
小田:あれは、出世してからどういうオチでしたっけ。
早川:当時の恩を覚えていて、豆腐屋に数倍返ししたということだったはずです。
小田:しかし、私は古注・朱子注を支持します。前後と比較したとき、困窮では流れから浮いてしまいます。ここは、言葉と行動の自制がよい結果を生む、という流れで読んだほうがすっきりするのではないかと思います。
早川:私もそう思います。徂徠の言うことは必ずしも当てはまらないのではないか。「我を博むに文を以てし、我を約すに禮を以てす(子罕篇)」とあるように、約の用法は論語でも自己抑制の意味を持たせています。この条の約を困約の意味として提起したのは、徂徠が最初です。宮崎先生は、それをあえて採用した。注釈には、その人の生活経験が反映しているのでしょうか。為政篇の「父母は唯其の疾を之憂ふ」について、加地伸行先生は「父母に対して、病気ではあるまいか〔と健康状態を〕ただただ心配することだ」と解釈をされた。先生は、両親を早くに亡くされた。その経験が、この解釈になっているようです。
小田:この条は、他に解釈はあるでしょうか。
早川:約を約束と解釈し、「約束を破る人は少ない」と読む人がいます。
小田:「失う」を約束を破ると読むのですか。
早川:しかし、やはり朱子や古注の解釈の方が妥当と思います。八佾篇の「禮は其の奢(おご)らんよりは寧ろ儉せよ」と同様のことを言っているのだと思います。孔安国の注は、そういうことです。読み手の生活実感によって論語の解釈が変わるというのは、面白いことです。徳川家康が論語の郷党篇を読んだとき、「厩焚けたり」の条の解釈がおかしいのではないかと林羅山に聞いた。武士の実感としては、馬は最も大事である。馬がどうなったかを気にしなかったというのは合点がいかず、ここは「人を傷(そこな)えるか。不。」と切って、その後「馬を問う。」と読むべきではないか、つまり人と馬を心配したのではないか、と質問した。林羅山は、さすがにその読み方はできないと否定したということです。
小田:もう過ぎた八佾篇に戻ってしまいますが、宮崎市定氏は、「曾(かつ)て泰山、林放に如かずと謂(おも)へんか」の条について、興味深い解釈を述べています。従来この条は林放を低くみた解釈が取られているが、氏はむしろ「曾て泰山を謂うこと、林放の如くならざりしか」と読むべきであると言います。林放は伝記がないので後世の学者によってつまらない弟子としてあしらわれてしまっている。しかしそれは後世の者の勝手な偏見ではないか。この条はむしろ、「冉有、以前お前は泰山の神聖さについて、林放と意見が一致していたではないか」という意味となるはずだ。つまりは林放の意見を孔子は高く評価していたのであり、林放は実は孔子の高弟であったと解釈すれば、この条が自然に読めてくる、と言っています。宮崎氏は、今読んでいるレッグの英訳を高く評価して、自らの論語解釈でレッグ訳を採用しているところが多くあります。宮崎氏は、中国語の論文の多くが非論理的であることに頭を抱え、それよりはずいぶんましである日本語の論文ですらあいまいな点が多いと指摘し、しかし西洋の中国関係の論文は彼らにとって全くの外国文化である漢文を彼らにとって意味を持つように明確に解釈しようと試みるので、我々から見ても目を開かされる解釈が多いと言います。なので、中国古典学者はもっと英語やドイツ語の訳を読むべきだ、と主張しています。
早川:中国語の論文では、古典をそのまま引用して現代語訳を付けない。なので、意味を吟味せず素通りしてしまいます。日本語の論文では、少なくとも読み下しすることで日本語訳として解釈され、さらには現代語訳まで付けられることがあります。もっと徹底するのが英語論文であって、当然ながら英語訳が必須となるわけで、彼らは原文の意味を完全に外国語に解釈します。私たちも、なるたけ英語の論文を読むように、と指導されています。
2013年6月15日(土)里仁篇
本日は、早川君、小田さん、高津君、上田さんの四人。里仁篇を早川君のリードで音読。訓読と意味は小田さん。
子の曰はく、君子は言に訥(とつ)として行に敏(さと)からんことを欲す。
行は去聲。○謝氏が曰く、言を放つは易し、故に訥を欲す。行を力めるは難し、故に敏からんことを欲す。○胡氏が曰く、吾が道一貫より此に至るまで十章、疑ふらく、皆曾子門人の記(しる)す所ならん。
孔子が言われた「君子たるもの言葉は少なく、行動に敏速でありたい」と。
行は去聲。○謝氏が言った、「言を放つのは簡単であり、ゆえに言葉は少なくありたい。努力して行動することは難しい。ゆえに敏速でありたい」と。○胡氏が言った、「曾子の『道一貫』の章よりこの章に至るまでの十章は、すべて曾子の門人の記したところと思われる」と。
上田:言葉は少なく、行動に敏速とは実際どういう行為ですか。
小田:学而篇14「事に敏にして言に愼み」などと一緒のことではないですか。
早川:前の「言を出さざるは、躬の逮(およ)ばざるを恥ずなり」と一連しているのでは。言葉と行いの対比の続きで、まとまっていると思います。
小田:前回も申しましたが、孔子の学校には雄弁な人が大勢集まって来ました。孔子自身が、言葉を操るタイプの人でした。しかし、言葉がどんどん増えていく時代に直面して、前の世代がそうではなかったことを回顧して、危機感をまた持ち合わせていたのも孔子だったのではないでしょうか。これらの言葉は、孔子の自戒を込めた言葉だったのではないでしょうか。
早川:衛霊公篇に「群居して終日言ひ義に及ばず、好んで小慧を行ふ、難いかな」とあります。言葉でいろいろ討論することは、楽しいものがあります。孔子は、議論のための議論の遊びだけで一日が終わってしまうことを、ここで戒めとしています。行動しないで言葉を発することの虚しさを、言っています。詩経の「白珪(玉)の欠けたるは、猶ほ磨くべきなり。この言の欠けたるは、おさむべからざるなり(白玉が欠けたときは磨き直せても、一度出した言葉はどうしようもない)」のごとくです。子貢は孔子一門の中でも雄弁ではトップであると思いますが、その子貢ですら子張篇で「君子は一言以て知と為す。一言以て不知と為す。言慎しまずんばある可らざる」と言っています。彼ですら言葉に慎重でなくてはならないと言い、言葉に対する畏れがありました。
小田:子貢は「文飾なんぞいらない、実質があればよい」と言った論者に対して、それはまちがいである、と反論していました。顔淵篇の「駟(四頭馬車)も舌に及ばず。文猶質なり、質猶文なり」のところです。これは雍也篇の「質、文に勝れば則ち野、文、質に勝れば則ち史、文質、彬彬として然る後に君子」のことを想定して言った言葉だと思われます。子張篇の言葉だけでは、子貢の真意は分からないのではないですか。
早川:どっちも揃ってこそです。
小田:ニュースで読んだのですが、25年前から来日しているマレーシアのジャーナリストが、最近の日本人はおかしくなっていると言っていました。そのおかしくなっている最大の点として、言葉の乱れを挙げていました。一昔前の時代、政治家の言葉も一般人の言葉も、折り目正しく丁寧であった。だが、今の時代はテレビで野卑な言葉が平気で流されるようになり、政治家も一般人も言葉が大変に乱れている、と一昔前の日本人と今の日本人を比較して言うのです。
高津:基本的に私もマレーシアのジャーナリストと同じ意見です、ただ、以前ビートたけしのテレビ番組を見たのですが、「ひらがな」は、かつて女の人が私的な表現のために積極的に使い始めたものが、後世に広まって日本語の表現を変えてしまった。こんな例があるように、今の時代に乱れていると眉をひそめられる表現でも後世にはそれが新しい表現を切り開くかもしない。間違っているとは必ずしも言えないのではないでしょうか。
小田:言葉は、歴史の流れのなかで変化していきます。前の時代に変な表現であると非難される言葉が、後世には日本語のメインストリームに入ってしまい、それによって日本語が変化する。その積み重ねです。だから新しい表現が必ずしも悪いとはいえず、しかし新しい表現が言葉の乱れとして同時代人をイラっとさせるのも、致し方のないことです。(今の若い女の子たちでもきちんとしている子は、大人に対応するときに使うキレイな言葉と、仲間内で使うチョーヤバゲナくだけた言葉を明確に使い分けられると思います。)
高津:武士が漢字と仮名を融合させたと言っていました。
早川:そういうところがあります。漢文を読み下すときに、日本語化する。そのプロセスで、公的な表現形式が漢字かな混じりで作られていきました。
小田:古代の中国でも、言葉の変化はありました。論語の文章と孟子の文章を比べると、後者は飛躍的に複雑になっています。孔子から孟子までの150年間で表現が発達して、複雑な議論ができるようになった。古い世代の人からすれば、後世の言葉は表現過剰であり、批判することでしょう。昔のように短い言葉で表現し尽くすのがよいのか、どちらがよいのか。
高津:私は、ジブリのファンです。「千と千尋の神隠し」では、言葉は強い意味を持っているのだ、というメッセージがあります。宮崎監督は、言葉がだんだん軽々しくなっていることについて、危惧がある。言葉を使う人が、それにどのぐら意志を込めて伝えることができるか、が大事で、言葉の長短ではなく、例えば「麻冕は礼なり、今や純なるは倹なり、吾は衆に従う」(子罕第九、3)とありますように、表面よりも内容が大事ということではないのでしょうか。ただ、今の私はマレーシアのジャーナリストの意見に賛成です。
上田:漢文では日本人の心が表現できず、仮名を交えることで表現できたということです。中村先生は西欧の五線譜では自分の心を表現できないところがあり、それを表現できる文法を考えているとおっしゃっている。鑑真のオペラなどの創作をされてますから欧風では表現できないところがあるのでしょう。
高津:中村先生の君子と小人の対比には、大いに影響を受けました。中村先生の考え方は、非常におもしろい。気持ちを伝えることは、千尋もそうです。千尋は責任をもって、気持ちをこめて、「働かせて下さい」と言いました。そうしないと生きて行けない、という気持ちを込めて、言いました。上田さんは宮崎監督は好きではないようですが、是非とも観てもらいたいものです。
上田:NHKで擬態語で製品開発をする取り組みがありました。樹脂で金属感を出すのですがうまくゆかない。二つ並べて「ぴかぴか」とか「すべすべ」とか感じる擬態語から両者の差をあきらかにして、その感覚に近づけることで開発ができたそうです。ロボットにも「ガンガン」「ふにゃふにゃ」とかいう言葉で動きを制御する試みもあるようです。
小田:日本語は擬態語が極めて多く、しかも現在進行形ですごい勢いで増殖しています。日本人は擬態語が大好きですが、欧米人は嫌います。欧米人が日本語の擬態語に接したとき、それはどういう意味であるのか分析的に説明することを求めます。だが、日本人はそれに答えられない。説明ができない。欧米では、明確に翻訳説明できない言葉は嫌われます。
早川:だがラテン語は、擬態的表現がそのまま単語になったりすることができる言葉で、造語力があります。
小田:古代語には、それだけ自由さがあったということでしょう。
早川:韓国語にも擬態語があるのではないでしょうか。あちら側での造語力は、どうなのでしょうか?
小田:そうですね。擬態語は、日本語と韓国語で共通の特徴です。韓国語の歌にも、使われたりします。だが、韓国語の擬態語がどのくらい造語力があるのかは、残念ながら私にはよく分かりません。日本語や韓国語の擬態語の起源は、おそらく古代中国語の「~~然」「~~如」「~~乎」などの表現と同根であると思われます。(マレー語にも同様の表現があるので、東アジアの古層にある共通表現なのかもしれません。)これが近代欧米語では、造語力が大きく制限される方向に向かいました。フランスでは近代以降アカデミーフランセーズがフランス語の単語を公的にコントロールしています。アカデミーが認めた単語以外はフランス語として認めない、という強い言語統制です。自由な造語は禁じられています。
高津:欧米人はどうするんですか。
小田:結局のところ、理性的な表現を連ねて、なんとか感じたことを説明的に表現しようとする。そうするしかないでしょう。(下の詩などは、俳句の五七五で表現できるのではないでしょうか?)
|
"September"
Der Garten trauert,
kuehl sinkt in die Blumen der Regen.
Der Sommer schauert
still seinem Ende entgegen.
Golden tropft Blatt um Blatt
nieder vom hohen Akazienbaum.
Sommer laechelt erstaunt und matt
in den sterbenden Gartentraum.
|
-
庭は泣きすすり、
雨は花の上に冷ややかに沈みゆく。
終わりを迎えようとする夏は
静かに、ぶるっと身震いする。
- 黄金(きん)の葉の上に、また葉が降る降る
高いアカシアの木から、落ちていく。
夏は、死にゆく庭の夢の上に
驚き、疲れ果てながら、微笑みかける。
(ヘッセ『九月』より、小田光男訳)
|
早川:日本語は、漢文を訓読で読むこと、これが表現の発達に寄与したと思われます。原文の漢文は孤立語(各単語が語尾の活用を持たず、それぞれが孤立している言語)ですが、日本語でこれを訓読すると長ったらしくなる。訓読することによって、それ自体でもとの漢文にはない独特のニュアンスを日本人は読み込んでしまいます。日本人が訓読して読んでいる漢文と、中国人がそのまま読んでいる漢文とでは、読み手のニュアンスが相当に違ってしまいます。
高津:「不可」を日本語で「~べからず」と読みますと、改まった禁止の表現に聞こえます。しかし中国語で「不可」と言えば、これは当たり前の禁止表現であって、改まった意味は出てきません。
早川:二重否定も、ニュアンスに差があります。「不可不」を訓読すれば、「~せざるべからず」です。こう言うと、何やら理性的にすべきことを説得しているようなニュアンスに日本語では聞こえます。しかし中国語で「不可不」はこれもまた慣用表現であり、しかも強い強制のニュアンスを伴った表現です。「絶対やりなさい」という強い意味となり、日中で古典を読むときに相互誤解が生じるもととなります。
小田:つまり「父母の年をば知らざるべからず(不可不知)」を中国人が読めば、「父母の年は絶対に知っておけ!」という脅迫的な命令文に聞こえるわけですか。日本語だと、先生のお小言みたいに聞こえますがね。
高津:ちょっと戻ってしまいますが、為政篇13の「先行其言而後従之」ですが、これは普通「先行其言、而後従之」と切られます。こう切って読んだとき、私は「先に発言を行って、その後でこれに従う」と読める、これで正しいのだろうか、と以前の読書会で疑問に出したと思います。そのとき確か成田さんだったと思いますが、通常はそのように解釈するのではなくて、「先に発言すべきことを行い、それから言葉を従わせる」という意味だ、と言われていました。今の章と比べて、どちらが正しい読みなのでしょうか。もし言葉が後ならば「先行」で切って、「其言而後従之」としたほうが私には分かりやすいです。確かその時は成田さんからは文の構成上「先行其言」としたほうがきれいみたいなことが言っておられたかと思います。うろおぼえなので、成田さんには責任がありません。
小田:私は、普通の読み方(朱子注の読み方)のほうが、四字+四字となって形が整っていると思います。金谷治先生は朱子注のとおりに切っていますが、宮崎市定先生は成田さんの読み方を採用していますね。つまり、「先行、其言而後従之」と切っています。
早川:その二とおりの読み方は、すでに伝統的に提出されている二説です。宋代以降は、むしろ「先行、其言而後従之」の読み方を支持する説が多くなっています。
高津:とはいうものの、「先に行動して、言葉はそれから後に従う」のやり方にも問題があると思います。行ったことを、後付けで言葉で言い訳することを許してしまうことになりかねない。「先に発言を行って、その後でこれに従う」のやり方ならば、発言に責任が伴うことになります。こちらのやり方のほうが、言葉に責任を持つべき重大さをよく表していると思います。
早川:それは、新しい読み方です。清代にもその読みがあります。高津さんの言われることにも、一理があります。民主党のマニフェストにあった子供手当なんかは、結局うやむやになってわけがわからなくなってしまいましたが、それを思い出したりします。
高津:言葉は重要です、責任が生じます。
早川:不用意に言を発すると、それが行動に制約を与えて、縛られてしまうことになります。前に言った言葉に縛られて、やりたいことができなくなりかねない。
高津:今の時代は、言葉をむやみに使いすぎる。そのことについての危惧を、宮崎監督と孔子は共に持っているのではないか。両者は似ています。上田さん、宮崎監督をぜひ観てくださいね。
上田:相手の言い分を聞き、自分の気持ちを確かめていると、タイミングを失い、なかなかうまく言えない。しかし、云い分を聞いているから、着地点は予想でき、すぐに行動にでることができるということではないですか。
早川:面白い解釈です、人生経験ですね。顔淵篇の「吾と囘、終日言りて違はざること愚なるが如し」、聴く一方の顔回を思い出します。
高津:宮崎映画の『もののけ姫』の話です。タタラバは本来、主人公にとって自分の敵となる集団ですが、そこでアシタカが見たのは、ここの男性は威張らない、女でも人間扱いしてくれるから辛くてもいきいきと働いている女性たち。その傍らで彼女たちによって生きる場を奪われている集団(生命)もあります。宮崎監督は、全ての人々と集団がそれぞれの理由をもって生きることを描き、人々と集団は生きていることによって互いにぶつかるのですが、どちらも生きてはいけない理由はないと考えます。その挟間にあってひとりでその問題をかかえこむ主人公を描きます。それぞれが生きたいと思っていて、それで対立し、両者を共存させなければならないが、それが不可能だと分かっていながら、両者共存のために行動せずにはいられなかった。これは、孔子にも当てはまることだと思います(是知其不可而為之者與/憲問第十四・41)。「ローマ・クラブ」をご存知ですか。「成長の限界」という本があります。欲望に生きる人間はどこかで停止しなければならない、と「ローマ・クラブ」は言います。「もののけ姫」では最後はもろともに崩壊してゼロから再度復活するのですが、これが宮崎先生の現代への最終的解決として見通しているかのようです。
小田:対立する双方に生きる理由があって、単純に勧善懲悪の図式に当てはまらない。宮崎監督の単純な勧善懲悪の図式を拒絶するストーリーは、黒澤明監督のストーリーを受け継いでいる、とも言えるでしょう。たとえば『七人の侍』で、村人たちは表だっては自分たちが野盗に虐待されていることを侍に訴え、義侠心から立ち上がった侍たちに感謝します。しかしながら村人は裏に回れば狡猾であり、富を蓄えることが第一の目的であり、侍たちを体よく利用しているにすぎないともいえる。それを、百姓出身の侍の一人が指摘します。侍たちはそれを分かって、それでも飲み込んで戦います。守るべき対象が絶対善ではなくて灰色の存在でしかないという認識は、単純な勧善懲悪のストーリーを超えています。
高津:日本の作品はハリウッドの正義と悪がはっきりした作品でなく、善悪をはっきりさせないのがいい。日本では八百万の神々がいて、どの存在にも存在理由があって白黒つけられない、という感覚があると思います。ハリウッドでも『アバター』なんかは、宮崎監督のパクリじゃないか。あれなんかを観ると、アメリカ映画も最近随分と変わってきたように思えます。『スパイダーマン』とか、主人公が悪に捉われた存在であるという設定で、自分自身と葛藤して戦います。
小田:『スター・ウォーズ』シリーズなんかも、最初の3話は単純な勧善懲悪物語で、たわいもないものでした。次の3話は前の3話で悪役であったダース・ヴェイダーの前半生がテーマとなり、主人公となります。もともと善人であった主人公が悪に陥った過程を描くわけです。
高津:日本のアニメや漫画は優れている。岩明均の漫画で『寄生獣』をご存知ですか?寄生獣は、人間の身体に寄生して人間を食います。だから人間にとっては悪なのですが、寄生獣の立場から言えば、寄生獣は人間という宿主が必要であり、人間が滅びれば彼らも滅びる。人間だって地球に寄生している存在ではないか、と寄生獣に反論されます。それで、主人公は、最初は最後の寄生獣にとどめを差さず、生きるか滅びるか、自然に任そうとします。しかし最後の最後で主人公は自分が人間である、という立場に戻って、最後の寄生獣を結局殺すのです。日本のアニメには、共存意識があると思います。日本のアニメや漫画は深いテーマを捉えていると、私は思います。
小田:まあ日本のアニメや漫画は、くだらないものは猛烈にくだらない、と思いますがね。日本のアニメは、作り手も消費者も、裾野がとても広いのです。それだけ、多くの人が参入しているジャンルなのです。だから玉石混交で、素晴らしい作品もくだらない作品もあるのだと、私は思います。古代中国の詩でも、そうですよ。一方で大雅小雅のような、朝廷で演奏する高級な作品もありました。他方で鄭声のような、真面目くさった人間たちが真っ赤になって怒るような今風の歌もありました。私は、高級な作品だけを見ていては、ジャンル全体の活力が見えないと思います。どんなに宮崎監督のようなハイレベルの作品を政府が育成しようとしても、くだらない内容に好き好んで集まる裾野があることを忘れたならば、アニメも漫画もおしまいだと思います。
高津:ところで、最近観たテレビ番組で思ったことですが、もしかしたら『老子』を書いたのは顔回ではないかと。『老子』のいう「無為自然」は、何もしないことではない。むしろ、黒子に徹して見せないことだ。『論語』で「位になければ政をしない」とかの言葉がありますが、こういう原理は『老子』と共通するのではないか。『老子』は、政治を全く否定するものではない、と思います。かつて読書会で林先生は老子について、これは孔子への批判のために書かれた書物であって孔子以降の著作である、と言われました。これもうろおぼえで定かではないのですが・・・
小田:その林先生の見方は、正しいと思います。『論語』の後半にはとくに、『老子』に展開されているような発想が見えるところです。私は、少なくとも『老子』の主張は孔子の活動時代より後であるはずだ、と思います。
早川:陽貨篇に「予(わ)れ言ふこと無からんと欲す。子貢が曰く、子如し言はずんば則ち小子何をか述べん。子の曰はく、天何をか言ふや。四時行はれ百物生ず。天何をか言ふや」とあり、物しゃべらない孔子です。
小田:しゃべるのがウザくなった、てめえ言葉だけで俺を理解できると思うなよ、という吐き捨てるような発言は、『老子』を準備した発言ともいえるし、しかし反発を生むのは必至であり、その反発が曾子とか孟子とかの「先生の意図を言葉で俺たちは継承しているのだ」という連中を生み出したのかもしれません。
高津:顔回の陋巷での生活なんかは、老子風です。
小田:孔子も、秀才の弟子たちに「出世して、よい官僚になれ」とか説教していたわけですが、本当は地位も名誉も富も求めず、「皆からデクノボウと言われ、誉められもせず、苦にもされず、そういう者に私はなりたい」(宮澤賢治)という理想を、ひそかに持っていたのかもしれませんね。だから、顔回を一番に誉めた。顔回が『老子』の作者かどうかは分かりませんが、『老子』で展開されている発想はとりわけ『論語』後半で見られるものと通じるものがある、と思います。
(高津後記)
皆さん
こんばんは、先ほどはありがとうございました。
いつも勉強せずにでたらめに言う私、今日の孔子の言葉は本当に胸に「刺さります」。
それでも暴走致しますので、暫くお付き合いいただければ幸いです。
顔淵老子説その①
http://kanbun.info/shibu02/roushi20.html(老子 道経 異俗第二十)原文を読んでもいまいちわからない私ですが・・・何となく、論語、雍也第六(11)賢哉回也~の生活スタイルそっくり?子貢の施しへの怒り説(小田談)も加味してひとり頷く顔淵老子説。
顔淵老子説その②
論語、子罕第九(11)顔淵喟然歎曰~の文章をみてると、顔淵の対比しながらの表現はとても老子の章句の使い方と似ているのでは・・・きっと知識人なら誰でもかけた文書の書き方のひとつであったのだろう、が、気になって仕方ない顔淵老子説。
何となくパートⅡ、老子は儒教を批判しているかもしれませんが、孔子の考え方とは表裏一体に感じるのは、やはり賢哉回也=孔子絶賛、顔淵の聞一以知十だからこそ体得できたのであろう、孔子の真意をまとめた顔淵老子説。
まぁ、私は学会?学界?だの、教授だのの力及ばん所の野次馬でありますので、無根拠で不勉強で好きに言っているだけですが、悪しからずに今後ともよろしくお願いいたします。
【その他いろいろ】
* 宮崎駿 『本へのとびら』(岩波新書)、岩明均 『寄生獣』全十巻(講談社)、無料レンタル致します。
* 宮崎駿(千と千尋の神隠し)・・・言葉は力である。千尋の迷い込んだ世界は、言葉を発することは取り返すのつかない重さを持っている・・・大部分
割愛・・・今日、言葉は限りなく軽く、どうとでもいえるアブクのようなものと受け取られているが、それは現実がうつろになっているにすぎない。言葉は力で
あることは、今も真実である。力のない空虚な言葉が、無意味に溢れているだけなのだ。宮崎駿日本人版孔子説一押し。
* ドラッカー・・・根本的な資質=真摯(Integrity)さである。
2013年6月22日(土)里仁篇
本日は、早川君、小田さん、上田さんの三人。里仁篇を早川君のリードで音読。訓読と意味は小田さん。
子の曰はく、德は孤(こ)ならず、必ず鄰有り。
鄰は猶親のごとし。德は孤立せず、必ず類を以て應ず。故に德有る者は、必ず其の類有りて之に從ふこと、居に鄰有るが如し。
孔子が言われた、「徳は孤立しない。必ず隣ができる」と。
「鄰」とは、親しむようなことである。徳は孤立しない。必ず同類をもって呼応する。ゆえに徳ある者には必ずその同類があって、従い相集まるのである。それは、住居には隣があるようなものである。
早川:古言を引いている印象がします。徂徠先生はどう言っておられますか。
小田:古言とは指摘していません。
早川:「徳不孤」の語は、周易にもあります。おそらく古代には「人口に膾炙(かいしゃ)」していた言葉だったのでしょう。
小田:膾は「なます」、刺身のことです。炙は焼き肉のことです。古代人にとってのご馳走はこの二つだった。だから「人口に膾炙する」という言葉が生まれました。皆が好んで用いる言葉、という意味です。
早川:孔子の工夫があるとすれば、その後に「必有隣」を付けたところだったでしょうか。あるいはここは孔子のオリジナルだったかもしれません。
上田:隣のイメージとはどんなものですか。
早川:朱熹は「鄰」は親と同じことである、としています。親友とか親密とかの語があるとおり、「鄰」には密接にくっついているイメージがあります。徳が存在すると、それに呼応した者どうしが密接となる。徳に共鳴する人がやってくる。ここで孔子は、徳についてそれは人間の中に内在しているものであると、みなしているのでしょうか。人間の中には徳があるから、一人の人に徳があれば、各人の内在する徳に連鎖反応が起こる、というイメージで孔子は語っているのでしょうか。舜の徳を皆が慕って群がった、という伝説がありますが。
小田:舜が一年いる所は村落となり、二年で邑となり、三年で都となったという話ですね。
早川:その伝説を思い出します。
小田:先週にも申し上げたところですが、私はこの後に続く子游の言葉は、後からの余計な付け足しではないか、と思うところです。つまり、本来の里仁篇は、この条で終わっていたのではないか?と疑うところです。そう読めば、この条は次の公冶長篇の前置きと読むこともできます。里仁篇は、君子はかくあるべきという理想論を展開します。諸君は仁徳者となれ。修練を積んで君子となれ。それがテーマです。そのような修練を積んだ君子たちが、具体的に孔子の周りに集まってきたのだ。孔子という有徳者は、孤立せず同士を得た。それが、次の公冶長篇のテーマである。そのように橋渡しをする意味がこの条にありはしないか、と思うところです。
伝統に無批判に従う古い人間たちの中から、自覚して修練を積む新しい人間存在たちが現れた。彼ら君子は、ややもすれば郷里の世間から浮き上がって、あらぬ非難を受けることもある。時には、犯罪者として投獄される憂き目にも会う。次の篇の冒頭で出てくる公冶長は、司直の手によって犯罪者と見なされた。だが、孔子の目から見れば、彼は同志である。世間や国家の目から見れば指弾されても、覚醒した存在である君子たちはいわば新しい共同体の中に生きているのであって、君子どうし分かり合えるのだ。イエス・キリストは弟子たちに対して、地上の人間関係をいったん断ち切って、新たな信仰の共同体を作るように求めました。私は、孔子の下に集まった集団は、イエス・キリストの教団と相通じる連帯意識があったのではないか、とすら思うところです。両者ともに、すでに世間の掟を超越した仲間であり、我々こそが天下を変えることができる先覚者であると。
次回読むところを先回りしてしまいますが、公冶長には鳥語が理解できた、という奇怪な言い伝えがあります。理性的な論者はこれを荒唐無稽な作り話として顧みませんが、私はあえてこだわってみたいと思うところです。彼のように動物と会話ができる人、というフォークロアは、日本にもあるし世界中にはいっぱいあります。それらのお話は、異世界の非人間的な魔物とコミュニケーションが取れる人間にまつわる話です。そのようなお話の根源を訊ねるならば、それはムラ社会の外部と接触ができてコミュニケーションが取れる人間について、それを神話的に解釈した話であると言うことができます。外部とコミュニケーションすることによって、そのような人間はにわかに富を得たり、高度な知識を得たりします。ムラ社会の住民から見れば、どうやって彼がそのような力を得たのか理解できず、だから動物とか悪霊とかの力を得たに違いない、とみなすわけです。村人たちは、そういう人間を恐れて村八分にしたり、時にはムラ社会の平穏を取り戻すために抹殺します。ムラ社会にとって理解不可能な外界の人間と連絡が取れる存在は、不気味なのです。
公冶長の伝説に何らかの根拠があったとするならば、私は彼が異文化の人間集団とコミュニケーションができる存在だったのではないか。その集団はムラ社会にとって不気味な存在であり、それを「鳥」として表象したのではないか、と推察するところです。ムラ社会は、「鳥」=異文化集団とコミュニケーションできる異能の存在をなんとしてでも罪に落し込み、共同体から排除しようとします。だから、彼は投獄されたのではないか。しかし、孔子はそもそもがムラ社会からはみ出した集団のリーダーであり、よって彼を罪ある者として忌むことはなかった。むしろ、同志として姻戚関係を結んだ。日本でも、在日外国人、被差別部落、あるいは左翼系のコミュニティーは、国家権力に100%従わず、横の連帯をもって国家によって罪に落された者を救助しようとします。だが、国家共同体から見れば、このような集団は秩序に従わない敵であり、隙あらば弾圧しようとするものです。
孔子の集団が各国を巡遊していたとき、時々襲撃を受けた。後世に祭り上げられた孔子像の視点から見れば、匡人とか桓魋とかは聖人に仇なす極悪人となるでしょうが、彼らの主観的意識としては、むしろ怪しい新興宗教集団を成敗する共同体の正義感に満ち満ちていたのかもしれません。むしろそのほうが、当時の実感として正しいのではないか。孔子の集団は、怪しい異能者揃いでした。子貢が大もうけできたのは、きっと共同体の外部と連絡を取り合える、特殊なネットワークを持っていたのが原因だったのではないでしょうか。伝記にはありませんが、公冶長も「鳥」とのネットワークで、富を積んでいたのかもしれません。そして彼を獄から救ったのも、「鳥」の集団が影で奔走したのかもしれません。孔子の集団は、そのような共同体にとって排除されるべき異能の人間たちを、どんどん引き寄せていったのではないでしょうか。
早川:孔子が鴟夷子皮(しいしひ)を田常の門前に掛けた、という話が伝わっています。白川静先生の「孔子伝」によれば、それは呪いのお札であった。つまり孔子は権力者を呪って国外退去したということです。もしこんなことを本当にしていたとすれば、各国で嫌われて当然だったでしょうが。公冶長の鳥の話を聞いて私が連想したのは、左伝です(昭公十七年)。鳥官氏の王は、鳥の名で構成されていた。それらは古い時代の氏族とのつながりを持った集団であり、それら怪しげな鳥官氏の言葉か習俗に通じていた者がいた(孔子は郯子からそれを学んだ)。あるいはそのような者たちが、共同体から排斥されたのかもしれません。
小田:孔子は、彼の生きていた時代、間違いなく異端者であったことでしょう。そうでなければ、大旅行をするという発想など出てきません。
早川:しかし、有力者の子弟たちまで、孔子の門を叩きました。不思議なのは、三桓氏と敵対したにも関わらず、孔子が殺されなかったことです。普通は、殺されます。孔子には、何か三桓氏ですら逆らえないバックがあったのでしょうか。三桓氏に殺されることもなく、堂々と国外に出国して、留守の家族も別段なんら害されてはいません。
小田:私は、孔子が会見した互郷の童子の出身は、やはり異族ではなかったかと思います。体制側の共同体にいる人間たちにとっては、関わってはいけないアンタッチャブルの集落だったのではないか。孔子は、そういう者とも平気で会見することができたのではないか。これは、既存の因習から自由な精神を持った人間でないと、成し得ないことです。そんなことができるのは、普通の人間ではない。日本では天皇は秩序を超えた王であり、だから賤民ともつながりを持つことができた。
早川:だから孔子は、階級や秩序を越える「素王」であるのかもしれない。
小田:イエス・キリストもまた、賤民の出自であった。そこから地上の掟を相対化して、人間の支配者、王として信仰されるようになった。両者の違いは、イエスは地上の掟の破壊者であったから殺されましたが、孔子はともかく天寿を全うできたところです。
早川:東洋の聖人は天寿を全うする。天寿を全うするのはコチラ東洋で、殺されてしまうのはアチラ西洋だ、と梅原先生はおっしゃる。東洋では、不幸にして死んだ者は神になります。聖人にはなれません。
小田:神として、手の届かないあっちの世界に祭り上げるわけですね。聖人は人間の手本であり、信者もまた見習わなければいけません。西洋では聖人が続々殺されてしまいますので、信者たるもの聖人たちを見習って命を捨ててかかれ、という信仰に導かれます。それで、殉教者が後を絶ちません。だが東洋では、聖人孔子ですら命を永らえたのであるから、こんな中途半端で死んでたまるか、天命尽きるまで生き抜いてやる、ということになるわけでしょうかね。
早川:儒教には、もともと殉教はありませんでした。殉教が出始めたのは、明代以降の新しい時代の儒教になってからです。
小田:文天祥などは、むしろナショナリストというべきでしょうね。儒教の教義に従ったというよりは。
早川:日本人は朱子学の一部だけを取り出して、主君や国家のために殉死するのが儒教の道だ、とか言うわけですが、朱子の著作の全体を見れば、殉死殉教を肯定する考えなどどこにもありません。ところで山縣有朋の邸宅「無隣庵」は、この条の「必有隣」から明らかに取っていますね。私には徳が無いからというユーモアです。
小田:山縣の京都邸宅は、他に今は二条の「がんこ苑」になっている建物もあります。
早川:藤井有隣館もあり、京都には色々ありますね。
上田:徳は孤とはどういうことですか。
早川:孔子の実感としては、徳は孤高であり、世間から孤立してしまう。だが孔子には、他方で若い弟子たちが集まって来た。それで、いにしえの言葉はやはり正しかったのだ、と自ら納得した発言だったのでしょうか。
小田:私はむしろ、弟子の集団に向けた言葉ではなかったか、と思います。自覚した修養者は、周囲から孤立するものだ。だが、必ず同じく自覚した同士がいるから、めげてはならないぞ、というメッセージではないでしょうか。
早川:孔子はすべてに好かれるようではいけない。悪しき人には嫌がられ、善き人には好かれる。集ってくる人のレベルに応じて反応する。類は友を呼ぶ。徳は孤ならず、どのような徳か。徳には美徳、悪徳、荒徳、悪い意味での人間性の意味もある。
上田:悪徳は悪徳を集めるですか。
早川:悪徳も隣がある。
小田:私は、ここの言葉の「徳」をもっと広い「得」の意味にも読んでみたいものです。つまり、道徳に限らず、何らかの奇妙で独特な能力を持っていたり、何かを偏愛して好んで打ち込むことができたりするとする。そのような人間はとかく親とか先生とかの大人から理解されず冷ややかに扱われるものであるが、広い世界には必ず自分と同じ同好の士がいて、自分の能力や好みを理解し合える仲間がいるものだ。周囲から理解されなくても、孤立することはないのだ。石森章太郎とか藤子不二夫とか、田舎で大人たちに理解されない漫画好きたちが、東京に集まると同好の士を見出した。有名なトキワ荘伝説ですが、その同好の士たちの集まりから、日本の漫画文化が大きく飛躍しました。そのように、「得」は決して孤立せず、大きな輪を作る可能性を秘めているのだ。そのように私は読みたいですね。
上田:孔子は、顔回を失ったとき、天我を亡ぼせりと言いました。それでも隣はありますか。
早川:「徳は弧ならず必ず隣あり」のとおり、顔回だってやってきた。しかし「天我を亡ぼせり」は強い失望の言葉であり、この二つの言葉は違うシチュエーションで発せられたと言えるでしょう。両者に統一した視点がるとはいえないでしょう。
小田:顔回は、孔子の母方の顔家出身だったのではないでしょうか。ならば、彼は孔子の親戚筋で唯一の弟子だったのではないでしょうか。父方の孔家からは、誰も弟子がいなかったようですが。だから顔回は身内の中で唯一の理解者であり、特別の弟子であった。それを失ったときの孔子のダメージは、大きかったのではないでしょうか。
上田:必ず隣ありは、善いようでも悪いようでもとれますが。
早川:どっちにも使ったのでしょう。
子游が曰く、君に事(つかうま)つるに數(しばしば)すれば、斯れ辱しめらる。朋友に數すれば、斯れ疏(うと)んぜらる。
數は色角の反。○程子の曰く、數(さく)は煩數(はんさく)なり。胡氏が曰く、君に事りて諫めて行はれずんば、則ち當に去るべし。友を導きて善納られずんば、則ち當に止むべし。煩?(はんとく)するに至れば、則ち言う者輕く、聽く者厭ふ。是を以て榮を求めて反りて辱しめられ、親を求めて反りて疏んぜらる。范氏が曰く、君臣・朋友は皆義を以て合ふ。故に其の事同じ。
子游が言った、「君に仕えて何度も諌めると、恥辱を受ける。朋友を何度も諌めると、疎んじられる」と。
數は色角の反。○程子が言った、「数は煩数(わずらわしいほど回数が多いこと)である」と。胡氏が言った、「主君に仕えて諫めて用いられないならば、去るべきである。友を導いて善であるのに受け容れられないならば、止めるべきである。うっとおしいまでに繰り返すと発言が軽くなり、聽く者も飽きる。ゆえに、栄誉を求めてかえって辱しめられ、親しみを求めてかえって疎んじられる」と。范氏が言った、「君臣と朋友はみな義をもって合うものだ。だから、両者の事情は同じである」と。
早川:どうして子游の言葉が、最後にあるのか。何か意図があるのか。あるいは「子曰」だったのが誤って「子游曰」となってしまったのか。もし意図的に子游の言葉がここに挟まれているとするならば、それは論語の編纂事情に関わることでしょう。
上田:後の自由闊達な議論をする時代になると曾子の言葉はうっとおしく思われるようなことがあり、子游の弟子がこういうことを言ったのではありませんか。
早川:つまり、曾子の一門が編集したとされるここより前の各条の後に子游の言葉が置かれたのには、意図があると思われるわけですね。
上田:強いて意味をみるならばですが。
早川:数ですが、古注では動詞で「数える」、君に仕えて「数えたてる」、つまり自分の自慢話しをすることだ、と鄭玄の注にあります。朱子の注では一方「しばしば」諌めるという解釈です。両者の差は、時代の差でしょうか。古代の段階ではまだ国家が中小企業程度の規模であって、君主に自慢話をすることもできた。しかし宋代にもなれば政府の組織が完備されて、そのような組織の中では主君に自慢話をすることは現実味がない。それで、宋代になれば新しい読み方が必要になったのでしょう。梁の武帝が注釈を残していて、この条について家臣が功労を述べて数え立てることだ、とみなしています。君主から見て、苦笑するしかなかったのでしょう。「数」の解釈ですが、ここでは僭越の「僭」と通じる意味であり、相手の領域を越えるとか、余計なことをするという意味になります。ここでの「数」の読みは通常とは違って、「サク」と読まなければいけません。現代中国でも違う発音です。(shŭ数える shù数、名詞 shuòしばしば)。
小田:「数」を、君に仕える回数と考えるのはどうでしょうか?
早川:二君に仕えるはいいのですが、朋友ではどうなりますか。
小田:朋友の数が多いと、関係が広く浅くなる。それでは朋友でなくなり、疎遠な関係になる。こんな解釈はどうでしょう。「疏んぜらる」を受動態でなく能動態として「疏し」と読み、同じく「辱しめらる」を「辱なり」と読む。すなわち「何度も主君を変えるのは辱であり、朋友の数が多いのは疎遠である」という解釈は、果たして文法的に可能でしょうか?
早川:「数」には「数多ければ」の意味があり、文法的には完全にそう読むことが可能です。
小田:つまりは、あんまり頻繁に仕える主君を取り替えたり、無闇に交友の輪を広げるな、という人間関係を処世の手段として弄ぶことへの警告として読んでもよいかもしれない。
早川:時代性、解釈する人の生き方が反映されますね。後世に小田光男なる論者がこのように解釈しているが、それはどういう時代的背景と人間的背景があったのであろうか、などと詮索されるかもしれませんね。朱子注では、「君臣・朋友皆義を以て合ふ」とみなしています。両者は同じく他人同士の関係であるから、相通じると。これも、時代背景が言わせたのでしょうか。
小田:君臣にも友人も、「親」の関係ではない。他人であるという区別でしょうか。
早川:ここではそこまで強い親類の「親」ではなく、「親しみ」という意味でしょう。ここの朱子注は、前の「父母に事るに幾(やうや)く諫む。志の從はざるを見ては、又敬して違はず、勞して怨みず」とひっかけているようにも見えますが、ちょっと二つが離れ過ぎています。
小田:氏族社会では、無条件で協力する関係にあるのは親族であり、友人といえどもいざとなったら親族を最も大事にするはずであり、だから過大な期待をかけてはいけない。せいぜいは、義の関係にすぎない。朱子注が「朋友は義」と言っているのは、宋代社会が氏族関係中心に動いていたという実情を反映していたといえるでしょうか。
早川:おそらく、そうでしょう。孔子の職業は「巫」、つまり葬式稼業でした。「赤い霊柩車」というTVシリーズを実家で見たのですが、そこで葬儀会社の人が事件を解決する。葬儀に来る人の態度から、糸口をつかみ事件を解決します。孔子も幼いころから葬儀の真似ごとなどをしたぐらいで、家業の上で葬儀に集まる人間たちの態度や表情をいろいろ観察できたことでしょう。そのとき、やはり親族には哀しみが現れている。しかし朋友は哀しんでいるとはいえ、親族とは嘆き方が違う。主君への弔問の際には形式通り哭泣するが、どうも泣き方に情が籠もっておらず形式的である。そんな人々の態度を見て、孔子は人間関係の親疎の度合いを掴んだのかもしれません。心から哀しむのは、血のつながりのある者だけだと。君臣・朋友は義であるという視点は、孔子の巫の職業経験から得た実感があるのではないでしょうか。
小田:巫覡は、中国社会では卑しい職業とされていましたね。
早川:いっぱんに、葬儀に係わる人は卑しいと思われていました。
小田:孔子は、その賤しい集団の一人であった。一般人にとって、近寄りたくない集団の出自だったということです。
早川:「我若くしていやしかりき」と孔子は言いましたが、白川静先生は孔子を卑しい身分の出と見なしています。それでいながら頭角を現し、国の重職を得て、若い人の心をつかんだ。生前から聖なるというか、常人ではない印象を与えていたことでしょう。
上田:次の公冶長篇で、南宮子容が孔子の兄の子と結婚しています。南宮子容は孟孫氏ですから、孔子は非常に高位の貴族と姻戚関係となったということです。どうしてこんな身分を越える関係を結べたのでしょうか。
早川:おっしゃっているのは、公冶長篇の南容と孟孫氏の南宮子容を同一人物とみなす説に立っておられるわけですが、この両者は少なくとも前漢代には別人とみなされていたと思われます。つまり漢書の人物表には、両者が別人として記載されているのです。これが同一説に傾いたのは、後漢代であると思われます。礼の内容などについても、前漢代などはまだ混乱していて諸説乱れていたように見られます。『礼記』には相矛盾する内容が並列しています。これらをなんとか折衷して一貫した説にしようとする作業が、後漢代に行われたと思われます。
小田:始皇帝が、帝王の業として泰山で封禅を行おうとして、魯から儒家の各派を集めました。ところが各派は儀式の内容についててんでばらばらな意見を述べて、統一がぜんぜんなかった。それで始皇帝はあきれて、独自のやり方で儀式を編み出したといいます。それ以降、始皇帝の儒家に対する評価が落ちてしまいました。当時の儒家ですら、礼についてはまちまちな意見に分かれてしまっていたということでしょう。
早川:封禅は、記録の残る歴史時代に誰もやったことがなかったから、意見がばらばらとなったのは致し方なかったでしょう。漢代武帝の封禅は詳しく資料が残されていて、それは始皇帝の儀式を継承したものであったから、始皇帝の封禅の内容はあらかた推測が付きます。
上田:封禅は、始皇帝より前からあったことでしょう。
早川:いちおう、伝説上ではやったことになっています。始皇帝は、伝説の帝王の儀式を統一後に再現しようとしたのです。
小田:始皇帝の中国巡幸も、周代の王が中国各地を巡幸したという伝説を受けて、全国統一の帝王の事業として「復活」させたものでした。
早川:始皇帝の巡歴を見ると広大な領域に広がっていて、あれは後世の拡張した中華世界の現実に合わせて後付けで作られた伝説に則って行ったと思われます。封禅の儀の呪縛は歴代中華王朝で続きましたが、宋代神宗を最後に、とうとう伝統が終わりました。
小田:山に登るのが、いいかげん面倒くさくなったのでしょう(笑)。いにしえの儀式というのはどうも胡散臭いものが多くて、たとえば儒家の「三年の喪」とかも、孔子から150年後の孟子の代になると、魯でも滕でも言い伝えですら聞いたことがない、と滕文公の家臣たちが猛反対したぐらいでした。少なくとも戦国時代になると、「三年の喪」などは伝統でも何でもない、初耳であった。
早川:「三年の喪」はさすがに国家運営の支障になるわけでして、前漢の文帝が「年を日に替えよ」という詔を出して、三年を三日に縮めてしまいました。論者の中には、「三年の喪」は孔子が捏造したものである、という主張をする人もいるぐらいです。
小田:捏造は言い過ぎではないかな、と私は思いますが、考えられることは、孔子の時代には国の中下層までも上層階級の文化を模倣する機運が現れたのかもしれない。「三年の喪」は、上層階級の文化であって、孔子たち中下層には魅力的であって孔子も積極的に普及させようとしたのではないか。ところがその時代すでに上層階級では古い儀式がすたれていて、もはや「三年の喪」も行われなくなっていた。そんなギャップがあったのではないでしょうか。
早川:すでに上層階級ではすたれていた文化が中下層階級によって復興され、上層階級に逆輸入された、という逆転現象すらあったのかもしれませんね。
本日にて、里仁篇が終了しました。
2013年6月29日(土)滕文公章句上
本日は、小田さん、上田さんの二人。本日分を音読。訓読と意味は小田さん。
畢戰(ひつせん)をして井地(せいち)を問はしむ。孟子の曰く、子(畢戰)が君(きみ:文公)將(まさ)に仁政を行はんとして、選び擇して子を使はす。子必ず之を勉めよ。夫れ仁政は、必ず經界より始まる。經界正しからずんば、井地均しからず、穀祿平かならず。是の故に暴君?吏(ぼうくんおり)は必ず其の經界を慢(まん)す。經界?に正しければ、田を分ち祿を制すること坐して定む可し。夫れ滕は壤地褊小、將(はた)君子爲り。將、野人爲り。君子無くんば野人を治むこと莫し。野人無くんば君子を養ふこと莫し。請ふ、野は九が一にして助し、國中は什が一にして自賦せしめん。卿以下は必ず圭田有り。圭田は五十畝。餘夫は二十五畝。死徙(しし)郷を出づること無し、郷田井を同じふす。出入相友(ともな)ひ、守望相助け、疾病相扶持すれば、則ち百姓親睦す。方里にして井(せい)す。井すは九百畝、其の中を公田とす。八家皆百畝を私にして、同じく公田を養ふ。公事畢はりて、然して後に敢へて私事を治む。野人を別つ所以なり。此れ其の大略なり。若し夫れ之を潤澤するは、則ち君と子とに在り。
文公が家臣の畢戰に命じて井田法を質問させた。孟子が答えた、「あなたの主君は、今まさに仁政を行おうとしてあなたを選び、私のもとへ派遣した。だから、あなたは必ず努力して学ばなければなりませんぞ。そもそも仁政は、必ず境界を定める事から始まります。境界が正しくなければ、井田法の土地は不均等になって収穫も秩禄も不平等になります。だから暴君や汚れた役人は、必ずその境界を乱すのです。境界が正しくなっていれば、田畑を分けて秩禄を制御することは座りながらにしてできるでしょう。そもそも滕は土地が狭く小さいが、政治家もいれば農民もいます。政治家がいなければ農民を治めることはできず、農民がいなければ政治家を養うことができません。以下のようにしなさい。すなわち、都の遠方においては九分の一税を敷き、助法を行ってください。都の近辺は十分の一税にして農民に自発的に税を納めさせてください。卿以下の政治家には必ず祭祀用の無税の圭田を国の権限で与えるように。圭田は五十畝であり、庶流の者には二十五畝を与えるように。各戸の当主が死んだり移住したりしても、郷の戸籍から出ることはありません。郷の田は井田として八家に分けて共同耕作をして、公田への出入を協力させ、郷里を助け合って守り、疾病者があれば助け合う。こうするならば、庶民は親睦するでしょう。一里四方が一井田で、井田は九百畝、その九分の一を公田とします。八家がみな百畝づつ私田を持ち、共同で公田を耕し国費を養う。最初に公田を耕作させて、その後で私田を耕作させる。これは、政治家と農民の区別をつけるためであります(つまり、お上の公田の耕作が私事よりも優先する決まりとすることで、農民に分際をわきまえさせるのです)。これが井田法のおおよそです。この内容の詳細を潤澤に補強するのは、主君とあなたがなすべきことです」と。
上田:ここでは境界をきちんと測量することを非常に重要視しているが、きちんと測量ができたのですかね。
小田:ここでの孟子の発言は、あらかた「礼記」に書かれた内容をそのまま繰り返しています。「礼記」の井田法の記述は、おそらく古い何らかの記録に基づいていたことでしょう。だがこのような測量に基づいた区画割りで田地を割り振ることがもし周代で実際に行われていたとするならば、新規に開拓された処女地の場合でしかありえなかったのではないか、と私は思います。もし井田法が周代でも行われていたとするならば、それは国が主導で開墾して水を引き、捕虜とか奴隷とかを入植させて拓いた新規の開拓地において行われていた、と考えたほうが自然です。そして、そのような開拓地はむしろ周代の農村においてはマージナルな存在であり、圧倒的多数は昔ながらの農民が邑(ゆう)を中心にして築いた自然農村だったのではないか。昔ながらの農村において、国家が測量をして土地を再配分することなど、およそ不可能なことです。ここで孟子が「國中」つまり都の周辺に対しては年貢を自発的に納めさせる制度を取れ、と言っていますが、これこそが自然に邑の周囲に形成された農村であって、土地を再配分することなどできないからこうしたのでしょう。孟子はさも郊外に行われたと伝えられている井田法が周代の主流の制度であったかのように主張しているわけですが、孟子は周代の主流の制度とマージナルな制度とを転倒して理解いるのではないか、と私は思います。
上田:日本ではどうでしたか。
小田:日本の奈良時代以降、条里制に基づいた村落が全国で見られました。これこそが班田収授法の成果であるとみなされてきたわけですが、近年の分析によれば条里制によって作られた村落は、荘園において新規に開墾された土地に対して実行されたようだということが分かってきました。寺社とか藤原氏とかが、開墾地に農民や蝦夷とかを強制的に入植させて増やした農地では、まず均等に各人に田畑を割り振るところから始めたわけです。もし孟子が井田法による土地の均等配分を既存の農村においても実行するべきだと考えていたとするならば、彼は錯覚していたと言うしかありません。実際に漢の王莽が井田法を実行しようと試みたのですが、大地主が既得権をもつ土地を国家が強制的に再配分することには大反対が起こり、失敗に終わりました。孟子は、農民に均等に土地を配分する井田法の趣旨を理想的に解釈したのでしょう。だが、自然の農村に対して国家が平等主義に従って改造する、という孟子の農政は、スターリンやポルポトの農政と同じです。大変な暴力を伴い、そして何一つよい結果を生みませんでした。
上田:太閤検地はどうですか。
小田:太閤検地は、各農民が保有する田畑の総量を確定して、税収を確保することが目的でした。そのために隠し田は厳しく摘発されましたが、土地を平等主義的に再配分したわけではありません。
上田:公田の耕作は、前にもあったがコルホーズや大躍進の農地の耕作同様なかなか生産性があがらない。公田を区切って耕作させる方式ではどうもうまくゆかないようですが。
小田:中国以外の古代国家における農政は、どうだったでしょうか。たとえばインカ帝国では農村の土地は四つに区切られました。一つは農民のもの、一つは村の村長の取り分、一つは皇帝への貢納分、もう一つを神(神殿)に納めさせる分、というシステムでした。農村を運営してゆくには、村の行事などで村長の役割が大きく、祭りや行事などの費用として村長の取り分は吐き出すようになっています。自然に作られた農村には、そのような暗黙の了解としての富の偏在と再配分があったと思われます。その上に後から帝国が征服者として覆いかぶさり、皇帝と神への取り分を割り込ませたのが、インカ帝国の農村だったはずです。皇帝と神殿もまた、公共事業や首都における祭りによって大々的に再配分を行うための原資として、農村に取り分を課したのです。ところが、孟子の言う井田法を見ると、村の取り部分がない。井田法は、国と農村とが直結した制度となっています。インカ帝国の場合は、村の部分と皇帝・神殿部分との折り合いがありましたが、孟子の井田法は村の自治会費的なものが考慮されていません。これは、奇妙なことです。村の取り分がないのはなぜかと考えたならば、おそらく国家が直接に新田開拓を行って入植させた土地だったからではないでしょうか。すなわち、直営農地です。直営農地ならば、村の村長が税を集めて代理納入するようなシステムとは、別の形になったのでしょう。
上田:非常に合理的な考え方とは思いますね。孟子は実際に農業をしたことはなさそうであり、朱子は社倉の運用など農政に携わり成果をあげており、井田制についてもう少し実際的な考察が出来なかったのですかね。
小田:朱子の時代には井田制は非現実的なものとなっており、朱子は彼の時代に孟子の主張する制度を活用することができるとは、考えていなかったのではないでしょうか。
上田:朱子は孟子を高く評価しており、井田法にも好意的に思える。江戸時代には米切手など、債権化して売買が行われており、米の先物取引が行われていたようで、中国より結構先進的ですが。
小田:言われるとおり、江戸時代の大坂北浜で、米切手の売買が行われていました。幕藩体制の税収は、米による現物徴収です。しかし年貢の米を武士たちがそのまま食うわけではなくて、必ず大坂で米を換金して、それを財政に充てていたわけです。そのとき、米切手が切られました。江戸時代中期以降になると各藩は財政が逼迫して財源不足となり、秋の収穫を担保にして年のはじめに米切手を切って先に金を受け取る、もっと逼迫すれば二年後三年後の収穫を担保にして金を受け取る、というようなことまで行われていました。こうして将来の収穫を当てにした各藩の米切手が流通するわけで、収穫を前もって金に換える事が当たり前となりました。ここが先物相場変動の源となったわけで、秋の収穫が不作であることが見込まれたときには切手の価値が上がり、豊作だと価値が下がる。こうして、毎年の豊凶の予測に応じて米切手の思惑売買が行われるようになり、世界最初の先物相場が江戸時代の大坂北浜で成立したのです。そのため大坂には、日本各地の豊凶の情報を素早く集めるネットワークが作られていました。中国より先進的かどうかというよりは、貨幣経済が同時代の中国朝鮮より非常に深く浸透していたのが江戸時代であったというべきでしょう。
上田:孟子の議論は荒っぽい、公田のみで税がまかなえたとは思えない。
小田:孟子が井田法を理想とみなした理由は、税収確保というよりは、次の二つの点ではなかったでしょうか。一つはこの制度の下で農民の不平等がなくなること。もう一つは国家が農村を管理統制するのにふさわしい制度であること。水平的には平等で、垂直的には統制が主眼にある。孟子は、周代の古文献にある井田法を見て、これが農村の統制に最もふさわしい制度であり、それが理想とする周代にあったと考えて推奨したのでしょう。孟子のイデオロギー的視点によって井田法は理想の制度に祭り上げられたわけで、しかし実情は先に申したとおり、これが周代に普遍的な制度であり、周代には農村を国家が統制していたと孟子がみなした通りであったどうか、私は非常にあやしいと思います。
上田:税収を増やすにはどうしましたか。
小田:孟子の時代の諸国は、原野に運河を引いて開墾し、入植させて新田を開きました。こうして税収の増加を各国は目指しました。この時代に鉄器が農具として普及したことが、運河の開削にも土地の開墾にも飛躍的に大きな役割を果たしたはずです。各国が開墾した新田では、孟子の井田法のような直営農地が広がっていたのではないでしょうか。
上田:滕ではそういうことができましたか。
小田:滕は狭くて小さく、新規開拓できるような土地があったかどうか?だが孟子の言葉を信じて既存の農村の土地を再配分しようとしたならば、農民の怨みを買うに決まっています。孟子は井田法を理想の税制と信じて疑わなかったようですが、最後まで信じていたということは、たぶん彼の生前には現実的に実施された機会がなかったからでしょう。もし実施していれば、王莽みたいにこの制度が空想的であることを分かったはずです。
上田:王莽がそれを証明してくれた。日本では荘園化してゆきましたが、中国ではどうですか。
小田:基本的には、歴代王朝ともに地主が農村を支配する体制で、その点だけ見れば日本と同様ですが、詳細は異なる点があると思います。中国では科挙の制度が完成した宋代以降では、世襲貴族はいなくなり、科挙に受かった士大夫官僚が一代限りで富と権威を得る、官僚制度となりました。科挙は建前として全ての人民に開かれた試験であり、たまに貧しい家から秀才が現れて地元の有力者の庇護を受けて学問を積み、科挙に受かって出世する美談が現れます。だが、大方は裕福な地主階層の子弟が恵まれた環境で科挙の試験勉強をして受かるケースが圧倒的多数でした。だから、士大夫と地主階層とは、大方重なっていました。日本では、鎌倉幕府以降の幕府はほとんど土地紛争を裁定することが主要な役割のようになり、幕府は農村の土地争いを裁定するという需要を満たすことで発展していったともいえます。このように日本では政府が土地争いの調停者として重要な機能を果たし続けていくようになりましたが、中国の政府はそこまで農村の土地争いに介入するようなことはなかったようです。中国は広大であり、官僚の数はそれに比べるとあまりにも少ない。だから中央政府としては、目が届かない農村には介入せず地方任せであり、年貢も唐代末期以降には金納が普及して、農地を細かく政府が管理せずとも金さえ入ってくればいいわけで、日本の幕府のように細かい行政の介入は行わず、成り行き任せであったようです。中国では中央政府がする仕事は軍事と治水であり、農村の土地争いまで負担するようなものではなかった。年貢を払えないと、やがては土地を失って小作農になり、果ては雇われ農民となります。そうやって成り行き任せのまま地主は肥え太り、貧農は食うにもことかかなくなっていく。その果てに、暴動が起こる。暴動が農村を席巻すると、地主は殺されるか逃亡するかして、それまでの土地の所有関係が白紙に戻る。白紙に戻った土地を貧農が取り合いして殺し合いして、人口がうんと減った後には土地がまた余るようになって土地争いも貧富の差も鎮まる。中国の農村は、その繰り返しです。だから、王朝ごとに農村も断絶がある、と考えたほうがよいと思います。明末清初の大乱で農村は更新され、19世紀の太平天国の乱でまた更新され、そして20世紀に毛沢東が地主を粛清してまた更新されました。日本では政権が代わっても、上層の支配者は変わるが農村は時代を越えて継続していたように思われます。中国では、王朝の交代ごとに農村も更新されるのが普通だというべきだと思います。日本では農村に継続性があるから、土地争いは放置せずに政府が裁定する。中国では王朝ごとに農村が断絶することによって土地関係が更新されて、また一からスタートする、という違いがおおまかに言ってあるのではないか、と思います。
上田:明治時代には地租として、江戸時代の沽券を地券とし、地価を定め、土地の売買を自由にした。米切手などを運用していた人々は土地所有権の売買など十分理解していたのでしょう。高利貸しが土地を集積して地主に売ることが可能になりました。中国ではどうですかね。
小田:庄屋とかの上層農民は、貨幣経済について十分理解していたことでしょう。一般農民は、それに引きずられるしかなかったのでは。現代中国は、共産主義の建前上土地の所有権を認めていません。よって、土地の売買はないはずです。土地を開発するために、国が土地を簡単に取り上げることもできます。中国は、いまだ本籍主義です。地方から都会にやってきても、住民票を農村から都市に簡単に移すことはできない。そういう都市に本籍を持たない人は、都市の行政サービスを受ける事ができず、不利をこうむります。農民を農村に縛り付ける制度は孟子の時代に終わったことではなく、共産主義諸国は普通に行っていた統制であり、現代中国でも消えているわけではありません。
ということで、孟子の井田法については終了。
2013年7月6日(土)公冶長篇
本日は、小田さん、早川君、上田さんの三人。早川君のリードで公冶長篇を音読。訓読と意味は小田さん。
此の篇は、皆古今の人物の賢否得失を論ず。蓋し格物窮理の一端なり。凡て二十七章。胡氏以爲らく、疑うらくは子貢の徒の記す所多しと云う。
この篇は、すべて古今の人物の賢否得失を論じている。つまりそれは、格物窮理の端緒なのである。すべてで二十七章。胡氏が言うに、「思うに子貢の弟子の記録したものが多い」と。
子、公冶長を謂はく、妻(めあ)はす可し。縲絏(るいせつ)の中に在りと雖も、其の罪に非ずと。其の子を以て之に妻す。
孔子が、公冶長のことについて言われた、「(自分の娘を)妻(めあ)わしてよい。捕縛されていたとはいえ、罪ではなかった」と。その子(娘)を、公冶長の妻とした。
妻は去聲、下も同じ。縲は力追の反。絏は息列の反。○公冶長は孔子の弟子。妻は之が妻とするなり。縲は黑き索なり。絏は攣(れん:ひく)なり。古は獄中黑き索を以て罪人を拘攣(こうれん、捕え縛る)す。長が爲人(ひととなり)や、考なる所無し。而れども夫子其れ妻す可しと稱せば其れ必ず以て之を取ること有らん。又言ふ、其の人嘗て縲絏の中に陷ると雖も、其の罪に非ざれば、則ち固より妻す可きに害無し。夫れ罪有り罪無きは、我に在るのみ。豈に外より至る者を以て、榮辱と爲さんや。
妻は去聲、下も同じ。縲は力追の反。絏は息列の反。○公冶長は孔子の弟子である。「妻」とは妻とするということである。縲は黒縄である。絏は攣、つなぎとめることである。いにしえには獄中において黒縄で罪人を拘束していた。公冶長の人となりは、伝記がない。しかしながら、孔子が娘を嫁がせてよいと言っている以上、必ずや取りえがあったということである。又言うに、その人がかつて獄中にあったとはいえ、その罪ではなかったのであり、もともと嫁がせるにさしさわりはない。そもそも、罪の有る無しは、その人の中にあるのみである。どうして外から与えられるもので、栄辱とすべきであろうか。
上田:公冶長の伝記はなかったのですか。
早川:彼の業績についての伝記は、ありません。史記の弟子列伝でも、「齊の人、字は子長」とあるのみです。魯の人という説(孔安国)もあります。孔子が娘を嫁がせたのですが、これ以上のことが分からない。それが興味をひきます。
小田:鳥語を解するという伝説は、皇侃からということですが。そこでは、『論釋』が出典ということですが。
早川:范甯(はんねい)の説と、『論釋』があります。皇侃は論釋を引いた。
小田:ところが、朱子はその話を取り上げていませんね。朱子が一切取り上げなかったのは、信憑性に欠けると判断したのでしょうか。
早川:皇侃の『義疏』は、朱熹の頃には散逸していたようです。義疏が残されていたのは日本のみでしたからね。
小田:つまり、朱子が観ることが出来たか怪しいということですか。
早川:宋代までは、少なくとも文献目録にはあった。つまり、宋代までは何とか残っていたのかもしれません。しかしながら、宋代の学者は誰も鳥伝説に触れませんでした。もし目に触れるまで出回っていたとすれば、誰かが取り上げたはずです。
小田:つまり、宋代の学者は皇侃の説を知らなかった可能性が高いということですか。
早川:朱熹は科学的な人だから、たとえこの説を知っていたとしても取り上げたかどうか?
小田:しかしながら、唐代までは鳥伝説が出回っていたようですね。
早川:初唐の人、沈佺期の『燕語詩』に、「不如知、黄鳥語 能免冶長災」とあります。また有名な白楽天の『烏鵲贈答詩序』には、「余非冶長、不能通其意」とあります。いずれも公冶長の鳥伝説について触れた句です。
小田:つまり唐代までは鳥伝説は有名な話であった。それが、宋代には分からなくなってしまったと。
早川:だから、後世の中国人は、唐代のこれらの詩人が公冶長の何について言及しているのか、分からなくなったはずです。だが今の中国ではかえって人気のある話になっていて、公冶長が二羽の鳥の声に耳を傾ける姿が切手にもなっています。
小田:なるほど。面白い話ですからね。孔子一門のことを描いた同人漫画を私は購入したことがあるのですが、そこで公冶長が出てきました。陳蔡の間で一行が行く場を失ったとき、公冶長が出てきて、脱出するための味方として鳥を動員したりしました。
早川:鳥の声は分かったとして、味方につけるのは飛躍ですね。
上田:前回小田さんは異文化集団のコミュニケーション能力とか言っておられたようですが。
小田:冶長は、もしかしたら当時の社会からはみ出した集団とのパイプを持っていたのかもしれない。それが「鳥」として表象された。不気味な存在であるために疑われて、捕えられたのかもしれない。しかし孔子は彼を自分の一族に招き入れることまでした。ここに、孔子もまたはぐれ者であり、孔子一門は時代のはぐれ者集団であった可能性を見たいと思います。初期のキリスト教団と似たような、既存のコミュニティからはぐれた集団だったのではないか、などと考えてみたいところです。
早川:左伝、昭公十七年に郯子がこう言っています。「昔黄帝氏は雲を以て紀す。故に雲師を爲して雲もて名づく。炎帝氏は火を以て紀す。故に火師を爲して火もて名づく。共工氏は水を以て紀す。故に水師を爲して水もて名づく。大皞氏は龍を以て紀す。故に龍師を爲して龍もて名づく。我が高祖少皞摯(しょうこうし)の立つや、鳳鳥適に至れり。故に鳥に紀して、鳥師を爲して鳥もて名づく。鳳鳥氏は、歷正なり。玄鳥氏は、分を司る者なり。伯趙氏は、至を司る者なり。靑鳥氏は、啓を司る者なり。丹鳥氏は、閉を司る者なり。祝鳩氏は、司徒なり。鴡鳩氏(しょきゅうし)は、司馬なり。爽鳩氏は、司寇なり。五鳩は民を鳩(あつ)むる者なり。器用を利し、度量を正して、民を夷(たい)らかにする者なり。九扈(きゅうこ)を九農正と爲す。民を扈(とど)めて淫すること無からしむる者なり」とあります。すべて鳥の名がついている集団があった。二十八歳の孔子が、その郯子に師事して、いにしえの教えを受けたという。
小田:すでにメインの社会では伝承が途絶えたいにしえの伝承を、アブノーマルな集団がなぜか伝えていた。それを、孔子がわざわざ聞きに行ったという。孔子の異常性を伝える話です。
上田:龍師とか鳥師とか、そういう集団の言葉が通じなくなっていたが郯子はそのことを知っていたのでは。
早川:それにしてもよく分からないのは、孔子の時代の記録において、互いの言葉が通じなかった、という話が見えないことです。唐宋以後には、言語が違って通じないという話は出てきます。しかし春秋や戦国時代でも地域によって言葉が違っていたはずですが、通じなかったという記録はない。孔子が楚の国で言葉が通じずに困ったという話もない。孟子にもそういう話はない。それが、不思議なところです。
小田:孟子は、楚の言葉を南蛮鴃舌と言っています。また子供の守役に斉人を選ぶか楚人を選ぶか、という話の中で斉人を選べば優雅な斉語を子は習得するが、楚人を選ぶと変な言葉になる、と言っています。孟子は、明らかに斉の言葉と楚の言葉は違っていることを話の前提としています。もっとも、地の言葉は各地で違っていても、ラテン語とかギリシア語みたいな共通語が中国全土で成立していた可能性はあると思います。
早川:「雅言」が当時の共通語という解釈を取るわけですね。
小田:もうひとつの考えとしては、とても古い時代には言葉は地方によって大きな差がなかった、という可能性もあります。言葉が地方ごとに分岐するのはより新しい時代のことであって、孔子の時代まではあまり差がなくて孟子の時代以降になって言葉の地域差が現れた、という可能性もあるかもしれません。
早川:湯島聖堂では、毎年の釋奠(せきてん。孔子を祀る日)に、一人の著名学者が講演をします。私が聞きに言った日は早稲田大学の村山吉廣先生が講義されて、今日のところがテーマでした。熱がこもっていました。孔子は人の言葉に迷わされずに、自分が正しいと思ったことを貫いたということであり、今でも冤罪で苦しむ人がいるが、この孔子の行為は彼が冤罪を受けた人でも受け入れた、と読み取ることができる。この条については、気になることがあります。いったいどういうシチュエーションでこの言葉が発せられたのでしょうか。孔子は、なぜわざわざ公冶長を選んだのか。孔子が、冤罪を受けた者をわざわざ選ぶ必要はない。ぼくが孔子なら、子貢を選びますがね?
小田:娘の器量が悪かったとか、歳を取りすぎていたとかの事情かな?それで誰も他に娶る者がおらず、公冶長だけが手を挙げた、、、?
早川:私は、ひょっとしたらこれは恋愛結婚ではなかったか、と思います。周囲の者が「あれは縲絏の中にあった」と言うと、孔子は「縲絏の中に在りと雖も、其の罪に非ず」とピシリと言った。娘の気持ちをよく知る父親であったと。
小田:なんにせよ、このエピソードからは異常な感じがします。
早川:なので、注釈者たちも解釈に困った。朱子もまた、何か必ずとるべき所があったに違いない、と苦しい推測をしています。
上田:次ともかかわるのですが、この順序によれば、自分の娘をすでに公冶長に嫁がせておれば、南容の時に兄の子を嫁がせてで別段どういうこともない。次では、南容にはどっちでも嫁がせることができたかのごとき議論になっている。それなら順番を逆にしなければいけないのではないか。
早川:注釈者は兄の娘をいい方に、自分の娘を悪い方にみたいな感がありますね。
子の南容を謂はく、邦道有れば廢(すて)られず。邦道無んば刑戮(けいりく)を免ると。其の兄の子を以て之妻(めあ)はす。
孔子が南容について言った、「国がよく治まっておれば、位を失う事はないだろう。国が治まっていなくとも、刑罰を免れるだろう」と。こうして、自らの兄の子を南容に嫁がせた。
南容、孔子の弟子、南宮に居る。名は縚、又名は适、字は子容、諡は敬叔。孟懿子が兄なり。廢られずは、言ふは、必ず用いらるるなり。其の言行を謹むを以て、故に能く治朝に用いられ、禍を亂世に免る。事は又第十一篇に見へたり。○或ひと日く、公冶長の賢、南容に及ばず。故に聖人其の子を以て長に妻として、而して兄の子を以て容に妻す。蓋し兄に厚くして、己に薄きなり。程子が曰く、此れ己の私心を以て聖人を窺ふなり。凡そ人の嫌を避く者は、皆内足らざればなり。聖人は至公より、何ぞ嫌を避くることが有らん。況や女(むすめ)を嫁(とつが)するは必ず其の才を量りて配を求む。尤も當に避くる所有るべからず。孔子の事の若きは、則ち其の年の長幼、時(こ)れから先後、皆知る可からず。惟以て嫌を避くるは、則ち大きに可からず。嫌を避くる事、賢者且爲さず。況や聖人をや。
南容は、孔子の弟子であり、南宮に居住した。名は縚、又名は适、字は子容、諡は敬叔。孟懿子の兄である。「廢られず」とは、必ず登用されるということである。その言行が謹直であるがゆえにに治っておれば朝庭に登用され、乱世にあっても禍を免れる。この事はまた第十一篇にも見える。○ある人は、「公冶長の賢明さは、南容に及ばない。だから聖人孔子は自分の子を公冶長の妻とし、兄の子を南容に嫁がせた。つまり、兄に厚くして、己に薄くした」と言っている。しかし程子は言った、「この人の言葉は、己の私心で聖人孔子の心を窺っているにすぎない。だいたい人が評判を気にするのは、すべて内面の徳に足らないものがあるからだ。聖人はおのずから公正の極みであり、どうして評判を気にすることがあろうか。ましてや娘を嫁がせるときには、必ずやその才を推量して配偶者を求めるであろう。どうして、評判を気にすることがあり得ようか。孔子が行ったこれらのことについては、両者の年の長幼も、どちらが前後であるかについても、全く知ることができない。ただ評判を気にしたなどということは、断じてありえない。評判を気にすることは、賢者すら行わない。まして聖人孔子が行うはずもない」と。
早川:『漢書』の古今人物評によれば、南容と南宮敬叔は別人であり、南容は上の下、3位であり、南宮敬叔は中の上、4位にランクされています。宮崎市定先生が、これを発見されました。
小田:つまり、後漢初期までは少なくとも二人は別人とみなされていた、と。
ここで時間となりました。
2013年7月13日(土)公冶長篇
本日は、小田さん、早川君、上田さんの三人。早川君のリードで公冶長篇を音読。
先週読んだところの続きから。
上田:「縲lĖiは力lì追zhuīの反切」というのは、読みと合わないのではないですか。
早川:朱子の注は、隋代の音韻書である陸法言の『切韻』に基本的に則っています。以降、現代音に至るまでに激しい発音の変化が起こっているため、『切韻』の中古音は現代音からずいぶん離れています。ここは縲lĖiではなくléiであったようです。日本語では「縲(ルイ)」と読み、これが「力(リョク)と追(ツイ)の反切」と説明されたならば、音がかえって合っています。日本語は唐代の発音を保存しているからです。「追」も唐代には『切韻』のように発音されていたのでしょう。中国人が現代発音で古典を読む傾向が生まれたのは、せいぜいこの二、三十年のことです。それまでは古い音韻のとおりに読まれたり、地方ごとに読み方が異なっていたりしました。かつての中国の学者たちにとって、自国の古典は聞いても何を言っているのか分かりづらい、過去にすたれた発音で読まれたテキストでした。
先週の鳥語のことですが、『周禮』の秋官に、「夷隷掌、役牧人 養牛馬 與鳥言 貉隷掌…掌與獣言」とありました。「夷隷掌は牧人を役し、牛馬を養い、鳥と言(ものい)う。貉隷掌は、、、獣と言うを掌(つかさど)る。」つまり、周代の制度には鳥と語ったり獣と語る役目の官職があったということです。夷隷掌という官職には「夷(えびす)」の字が付いています。当時の感覚では蛮族は動物と人間の中間である、というものでした。だから、動物と話すことは蛮族と交渉することとわりかし連続性を持って意識されていたのかもしれません。
小田:後世の中国文化の感覚では、禽獣と人間とは隔絶しているとみなしがちです。しかしながら、とても古い時代には生き物もまた固有の魂をもち、何らかのメッセージを発しているのだ、という感覚を持っていたとしても不思議ではなかったでしょう。動物と人間との間に連続性を見る感覚です。牛馬や鳥が騒いだならば、それは何らかの天変地異のきざしであり、君主の不徳の結果ではないか、そのように捉える感覚は、必ず存在していたと思います。
早川:前回小田さんが鳥の言葉を解するということを、公冶長が異族とコミュニケーションが取れたということではないか、と言われましたが、そういうこともあったのでしょう。左伝にも、牛の言葉が分かる人とか石がしゃべったりとか、迷信満載なことが書かれていて後世の読者の悩みの種となっています。左伝、僖公二十九年条に、介葛盧(介は国名で葛盧が人名)という東夷の人が、牛の鳴き声を聞いて三匹の子が生まれると予言すると、果たして三匹生まれたということが書かれています。つまり、動物の言葉が理解できたと。
上田:黄帝の涿鹿の戦いでは神と人間と動物が入り乱れて戦っており、庖羲や女媧は人面蛇身であり、人間と神と動物がきっちり分かれていないし、天上と天下の往来もひんぱんであったという伝承があった。
小田:左伝はおそらく戦国時代に編集されたものと思われますが、記事そのものは春秋時代から継承されたものであったことでしょう。古代中国の感覚は、合理性一本ではなかったと思います。戦国時代の論者あたりから、迷信を斥けて合理的に思考する傾向が顕著となりました。それ以前の時代には、迷信的な思考がむしろ支配していたはずです。中国は時代を遡れば、東夷・南蛮・西戎・北狄が中原に混在していたはずです。孔子の時代には、すぐ隣に異文化の邑があったぐらいだったと思われます。そのような異文化の人々はたとえば動物と話が出来る、といった恐れて遠ざけるべき人々として表象されたことでしょう。おそらく孔子の弟子の中にも、結構夷狄出身の人が多かったのではないでしょうか?
早川:姓をみると変わったものがありますね。公冶とか、当て字っぽく見えます。
小田:弟子たちの中には、自分の出身地の言葉で、固有の姓名を持っていたのかもしれません。それを漢字で当て字にしたとき、変わった姓を名乗ったのかもしれません。
早川:春秋時代には、それまでの時代に見えなかった、変わった姓の人物が多数現れます。
上田:周は多くの民族を糾合して殷を討ったといいます。
早川:主に羌人で、西方の民を糾合して殷に勝ったといいます。
小田:羌人は、殷王朝と対抗していました。
早川:殷墟の出土物を解読すると、恐るべき抗争があったことが分かります。
小田:私の会社の中国語スタッフさんの夫君は、中国籍で彝(イ)族です。彝族はもともと「夷族」と書かれていたのですが、悪い字なので改めているのです。彼らは古代の羌人の子孫である、と自称しています。現在、主に四川省・雲南省・貴州省の山間部に住んでいます。彼らのユニークな点は、独自の文字を持っていることです(Yi
Script)。しかも、その由来は漢字とは異なり、相当に古い時代の由来である可能性があります。(少なくとも、近代の創作ではないようです。)彼らの文字は、古代の羌人の文字を受け継いでいるのだ、と言うのです。
早川:その辺は、学会でもめるところです。文字の由来は民族のアイデンティティーに関わりますから。
上田:三星堆には文字がありましたか。
小田:その方が言うに、三星堆の遺跡に残されている記号は、Yi
Scriptで完全に解読できるとか。その研究をしている学者もいるということです。つまりは、三星堆は古代の羌人の築いた文明であり、その子孫である彝族が四川省に住んでいるのは当然の連続性であると。
早川:文字なのか、文様なのか判別が難しい。だが現代人の文字感覚とはちがったものがあったとすれば、文様も文字の役割を果たしていたかもしれません。
上田:三苗との関連はどうなりますか。
小田:古代文献の三苗は、現代の貴州省周辺に居住する苗(ミャオ)族の祖先であるという説があります。彼らは、かつて中原に広く住んでいた。それが堯や舜によって追い出されて、辺地に落ち延びたという説です。
早川:大和朝廷と出雲の関係のようなものですが、証明が難しい。
上田:堯が二人の娘を嬀水に下ろすとか、都広が天下の中心とか、山海経にありますが、中原ではなく南西方が中心であったように思えます。
早川:二人の娘は娥皇と女英のことですね。この伝説は、中原の『詩経』などには見えない。なのに屈原の楚辞・九歌の「湘夫人」、「湘君」は、おそらく彼女たちの伝説のことを言っていると思われます。すると、伝説の起源は南方にあった、ということとなるでしょう。
小田:思うに、古代中国とは、一つではなく複数の文化が合流して生まれたものだったはずです。つまりは、中原とは東夷・南蛮・西戎・北狄の諸文化が交流して、その複合体として発達したのではないだろうか。様々な集団を統治してゆく中で、共通の制度や倫理を打ち立てる普遍的な文明が成長し、中華のテリトリーが成立した。中華が成立したら、そこの者たちはかえって周囲の四つの文化と自らを隔てて、華夷意識を持つようになったのではないでしょうか。だから、中華の由来は周辺の夷狄にあったと私はみなしたいです。
早川:ある方のちょっときつい言葉ですが、中国の制度は縦に追ってゆけるが、その制度を運営する担い手は、異民族が次々に強姦することにより混合してきたと言います。
小田:匈奴、鮮卑、キタイ、女真など、古来から中国を支配した諸民族は、ことごとく消えてしまいました。一番新しい満州族も、今となってはもはや見つかりません。
早川:中国では、支配民族の吸収が百年に一回くらい起こります。今では純粋な満州語がしゃべれる人は片手で数えることができるくらいになりました。立命館大学アジア太平洋大学の愛新覚羅先生がそうです。
小田:新疆ウイグル自治区のシボ族も、満州語を話します。
早川:だが、正統の満州語から外れています。
小田:彼らは乾隆帝の時代に征服地への押さえとして辺境に連れて行かれて、そのまま置き去りとなってしまった。それが奇跡的に満州語を保存して生き残ったのが、シボ族です。
早川:むしろ、都会化して洗練された正統満州語よりも、本来の言葉に近いのかもしれません。周辺の辺境に文化が残るという例はよくあります。ところで私が中国の先生に漢詩を贈ったら、「礼が滅んで夷に残る」と返答されました。喜んでよいのか、どうなのか?褒められたのか貶されたのか?まあ仲のよい先生なので、冗談なのですがね。論語では夷ではなく「野に在り」とか言いますが。
では、このあたりで南容にゆきますか。
小田:公冶長と南容のエピソードは、セットになっていると思います。
早川:そうですね。
小田:先回りしてしまいますが、私は次の子賎と子貢のエピソードも、やはりセットになっていると思います。
早川:公冶長と南容は結婚話で、関係が強いのは確かです。
小田:いっぱんに公冶長篇は、複数の弟子や歴史上の人物を並列して、それぞれの長短を示すという編集方針があるのではないか、と私は思うところです。
早川:この篇は、編集意図を感じさせる。朱子注では冒頭にこの篇は「子貢の徒の記す所多し」とあります。子貢は、人物評価が好きだったんでしょうかね。
上田:こういう集団が集まれば、人物評価は格好の話題でしょう。私もよくやりました。
小田:子賎と子貢ですが、私はここの二人のくだりを読んだとき想起したのが、先進篇の「先進は野人、後進は君子」のくだりです。ここで孔子が子賎のことを「君子だ」として賞賛しているわけですが、私はここで孔子が弟子を評した「君子」という言葉は、朱熹の注のような「道徳にすぐれた立派な人」という意味とは違うのではなかったか、と読んで思いました。むしろ、「君子」の本来の意味である、「政治家、政治ができる統治者」という意味で、弟子の子賎を孔子は誉めたのではないでしょうか。孔子は子賎のことを、「大した政治家だな、この人は!」と感嘆したのではないでしょうか。それで私は先進篇の「野人、君子」の区別もまた、政治をそつなくこなす後進の弟子と、どうも垢抜けない先進の弟子とを対比させた言葉であったのではないか、と捉えてみたいです。なぜならば、子賎のエピソードは論語にはなくて『史記』や『呂氏春秋』にあるのですが、それらを読むと彼は単なる道徳の人ではない。『呂氏春秋』の審応覧篇のエピソードなどを見ると、むしろ、自分の置かれた政治的状況を的確に読んで巧妙に立ち回る、策略を持った政治家と言うべきです。(『呂子春秋』審応覧篇の概略:子賎が魯の哀公から単父の統治を任されたとき、哀公から任地に派遣された役人を、難癖を付けて追い返した。哀公は役人たちの復命を聞いたとき、自分が子賎の統治に役人を通じて介入していることを諫めているのだと気づき、今後単父の統治者は子賎であるとみなす、と一切の統治を一任した。果たして単父はよく治まった。孔子が弟子の巫馬旗をひそかに派遣して単父の統治を観察したところ、漁民は夜に小魚を放流していた。小魚は放流するように、という法令のゆえであった。漁民は、夜の闇の中でも傍らに法があるかのように、子賎の政治に従っていた。)これが「君子」であるならば、子賎は政治家としての資質があるから孔子が称えたのではないか、と私は思ったところです。そして、後進の弟子たちを孔子が「君子」と称したとき、それは孔子が名を挙げてから入門した新しい弟子たちは上流階級の子弟が中心であって、そういう新来の弟子たちは生まれ育った時から統治者階級の空気を吸ってきたわけで、名利にガツガツするところがなく、庶民との適正な距離感を持ち、そして朝廷での出処進退を体で知っていた。つまりは、生まれながらの貴族たちであった。いっぽう、孔子が無名の時代からつき従ってきた子貢とか子路とかの先進の弟子は、個性豊かであるが上昇志向を隠すことができず、朝廷や庶民の中にあって上手に出処進退ができない。いわば百姓の子弟たちであり、ゆえに野人である。孔子は、「野人、君子」と言ったとき、育った環境が違い、資質が違っていることを指摘したのではないでしょうか。子貢は、いくら才気があったとしても、育ちが良くなくて上昇志向を隠すことができない。だから、野暮天であり政治家として洗練されていない。子賎は子貢とほぼ年齢が同じですが、私はおそらく子賎は孔子が有名になってから弟子になった、上流階級の子弟だったのではないかな、と思います。その子賎を孔子が「君子」と称えた。子貢は同年代でしかも後から入門した子賎を孔子が称えたのを聞いて、腹を立てた。それで、「じゃあ私は何ですか?」と聞いた。孔子は、近しい弟子のことであるから、ついつい「お前は、器だ。(君子=政治家としてはダメダナ。)」と軽口を叩いてしまった。その後に言い過ぎたことを反省して、「しかし、最高の器だ。(スタッフとしてならば、最高の働きをする。)」とフォローしたのではないか?私は、この一連の子賎と子貢のくだりを、孔子が親しい弟子にうっかり言ってしまった暴言に、とっさにフォローを入れた微笑ましいエピソードして読んでみたい、と思うところです。
早川:子賎は孔子より四十九歳下、子貢は三十一歳下で、年が離れていますが?
小田:仲尼弟子列伝では、子賎は孔子より三十歳下と書かれていますね。ならば、子貢とほぼ同世代となりますが。
早川:別の出典があるか、史記でも書写の系統が違うのかもしれません。しかし、子賎が子貢よりもずっと年下であったほうがむしろ後進グループとして妥当性があるし、子貢が自分よりずっと年少者を孔子が君子と称えたことに腹を立てた、ということになって、より問答がリアルとなるでしょうね。私は、「宓不斉の単父(ぜんぽ)を治むるや、鳴琴を弾じ、身は堂を下らずして、而も単父は治まりぬ」という子賎のエピソードが好きです。徳のある立派な人であり、ゆえに政治手腕に優れた人というべきです。大人物の感じですね。
小田:孔子は、どうして子賎のような人物が出てきたのか、と感嘆したのではないでしょうか。子賎を評価するとき、彼の出自である魯の上層階級の文化もまた評価せざるをえない。子貢などはイモくさく見えたのでしょう。
上田:そういうことはあったのでしょう。
小田:『呂氏春秋』や『史記』のエピソードを見ると、朝廷や人民を頭から信用せず、かといって力に訴えることもない。生まれながらの上層階級だから、上手な距離感をとって政治ができたのではないでしょうか。
早川:子賎という名の関連ですが、高貴な人ほど己を謙遜していやしく言うものであり、もしかしたら彼の字(あざな)は、上流階級ゆえだったかもしれませんね。いっぽう子貢の「貢」は富貴の字であり、貧乏人の出自の者ほど金持ちに見せたいのかもしれません。子賎は「鳴琴を弾じ、身は堂を下らずして」治まった。孔子みたいな人は、そこまで大胆な行動はとれない。となれば、宓不斉の家の格がすごいことになります。宓不斉名家説ですか。小田さん以前にそんなことを言った人がいますかね?
小田:孔子は、三桓氏を常々批判していた。それで、魯の上流階級たちのことを低く評価していた。だが、晩年になってそこからの出自の「君子」たちが弟子として加わるようになり、彼ら御曹司たちの実力を見るにつけて、魯の上流階級のことを見直さずにはいられなくなった。子賎を評価した孔子の言葉は、そのような孔子の晩年の言葉ではなかったでしょうか。子貢などの野人とはモノが違う、と改めて思わずにはいられなかったのではないでしょうか。しかし、「吾は先進に従わん」であり、孔子は自らと同じ出自である野人たちに、それでも心情的シンパシーを持っていたのではないでしょうか。
上田:子賎は自らは動かず人を登用して政治をする舜タイプに描かれている。しかし、そのような政治は当時では行い得なかったスタイル。現実の政治においては子貢のなした仕事の方がはるかに大きな効果をもたらした。ただ、子貢は孔子あってと本尊を立てる、自分がトップになろうとしない、そこを器としたのでしょう。子賎は自ら立つ人。
小田:子賎は、孔子に弟子入りする必要はなかったのではないでしょうかね。自分の力でも、政治家として一本立ちできた。
早川:宓さんか密さんを左伝から見つける必要がありますね。名家を見つけ出さねば。伏生の祖先が宓不斉ともいいます。
南容の話に戻しましょう。
小田:後漢以前には南容二人説ということでしたね。後漢以降は一人説となったのでしょうか。
早川:いつからそうなったかは分かりません。
小田:朱熹は、少なくとも同一説です。
早川:先進篇の「南容、三たび白圭を復す。孔子以て其の兄の子をこれに妻す」と大雅を引いて、孔子がほめたのが南容です。また憲問篇に、「南宮适、孔子に問ひて曰く、羿射を善くし、奡舟を盪(うご)かす。倶に其の死然るを得ず。禹と稷、躬ら稼して天下を有つ。夫子、答へず。南宮适、出ず。子の曰はく、君子なるかな若き人。德を尚ぶかな若き人」とあるのが、孔子と一緒に周へ行った南宮敬叔で、これは別人という。これが、南容二人説です。
キンコンカーンと鳴りました、時間です。
2013年7月20日(土)孟子滕文公章句
本日は、小田さん、上田さんの二人。本日分を音読。訓読と意味は小田さん。
神農の言を爲(おさ)む者、許行有り。楚より滕に之きて、門に踵(いた)つて文公に告げて曰く、遠方の人、君の仁政を行ふを聞く。願はくは一廛(てん)を受けて氓(たみ)爲(た)らん。文公、之に處を與ふ。其の徒數十人、皆褐(かつ)を衣(き)たり、屨(くつ)を捆(う)ち席(むしろ)を織りて以て食とす。陳良が徒陳相、其の弟辛と、耒耜(らいし)を負ふて宋より滕に之きて曰く、君聖人の政を行ふと聞く。是れ亦聖人なり。願はくば聖人の氓爲らん。陳相、許行を見て大きに悦び、盡く其の學を棄て學ぶ。陳相、孟子を見て、許行が言を道(い)ふて曰く、滕の君は則ち誠に賢君なり。然りと雖も未だ道を聞かず。賢者は民と並び耕し、食の饔飧(ようそん)して治む。今、滕、倉廩(そうりん)府庫(ふこ)有れば、則ち是れ民を厲(や)ましめて以て自ら養ふなり。惡んぞ賢を得ん。孟子曰く、許子は必ず粟を種(う)へて而して後に食らふか。曰く、然り。許子は必ず布を織りて而して後に衣るか。曰く、否。許子は褐を衣たり。許子は冠(かんむり)するか。曰く、冠す。曰く、奚(なに)を冠す。曰く、素を冠す。曰く、自ら之を織るか。曰く、否。粟を以て之に易(か)ふ。曰く、許子は奚爲(なんす)れぞ自ら織らざる。曰く、耕に害す。曰く、許子は釜甑(ふそう)を以て爨(かし)ぎ、鐵を以て耕へすか。曰く、然り。自ら之を爲るか。曰く、否。粟を以て之に易ふ。粟を以て械器に易ふるは、陶冶を厲(や)ましむと為さず。陶冶も亦其の械器を以て粟に易ふるは、豈に農夫を厲ましむと為(せ)しや。且つ許子何ぞ陶冶を為して、舍(や)めて皆諸を其の宮中に取りて之を用ひざる、何爲(なんす)れぞ紛紛然として百工と交易する。何ぞ許子が煩(わずらは)しきを憚(はばから)らざる。曰く、百工の事、固(もと)より耕へして且つす可からず。然らば則ち天下を治むること獨り耕へして且つ為す可けんや。大人の事有り、小人の事有り。且つ一人の身にして、百工の為す所備はる。如し必ず自ら爲して後に之を用ひば、是れ天下を率いて路(みち)するなり。故に曰く、或は心を勞し、或は力を勞す。心を勞す者は人を治む。力を勞す者は人に治めらる。人に治めらる者は人を食(やしな)ふ。人を治む者は人に食はる、天下の通義なり。
神農の説を唱える、許行という者がいた。楚より滕にやってきて、宮門に来て文公にこう言った。「遠方の人は、あなたが仁政を行うと言っております。どうか住居を一つをもらいうけて、貴国の民にしてください」と。文公は、許行に住む場所を与えた。その信徒は数十人、すべてぼろぼろの毛布の服を着て、クツを造りムシロを織って食いつないでいた。楚の儒者陳良の信徒であった陳相とその弟陳辛とが、鋤をかついで宋より滕にやって来て文公に言った。「我が君は聖人の政治を行っていると聞いています。ならばまさに聖人です。どうか聖人の民に加えてください」と。陳相は、許行に会って大いに悦んだ。自らの儒学をすべて棄てて、許行に学んだ。陳相は孟子に会って、許行の説を唱えた。「滕の殿様は誠に賢君であるが、まだ正しい道を受け入れていない。賢者は人民と並んで耕し働いて食を得、自炊して政治をします。今、滕の国には穀物倉庫や財貨を蓄える倉庫があり、人民を働かせて自らを養っているということです。どうして賢君といえようか」と。孟子が言った。「許先生は必ず穀物を植えて、後に収穫して食べるのか」。陳相が応えた。「そうです」。孟子が言った。「許先生は、必ず自分で布を織ってその着物を着るのか」。陳相が応えた。「ちがう。許先生はぼろの毛布を着ている」。孟子が言った。「許先生は冠をしているか」。陳相が応えた。「冠しています」。孟子が言った。「何を冠しているのか」。陳相が応えた。「色なしの絹を冠している」。孟子が言った。「自分でそれを織るのか」。陳相が応えた。「ちがう。穀物と交換している」。孟子が言った。「許先生はどうして自分で織らないのか」。陳相が応えた。「耕作の妨げとなる」。孟子が言った。「許先生は釜や甑(こしき)で煮たて、鉄の鋤で田畑を耕しているのか」。陳相が応えた。「そうだ」。孟子が言った。「それらを自分で作っているのか」。陳相が応えた。「ちがう。穀物と交換している」。孟子が言った。「穀物で道具と交換交易することは、陶工や製鉄業者を働かせているのではないか。陶工や製鉄業者もまた、道具で穀物と交換するのは、農夫を働かせているのではないか。ところで、許先生はどうして自分で土器や鉄を作り、必要な物を全部自分家に貯えて使うことをしないのか。どうして、こせこせと諸々の職人と交易するのか。どうして、許先生はこせこせして交易することを煩わしいとしないのか」。陳相が応えた。「職人の仕事をしては、そもそも耕作することができないので一緒にすべきではない」。孟子が言った。「だったら、天下を治めることも、耕作して一緒になすべきことでありえようか。統治者の仕事があり、統治される者の仕事がある。その上、人間一人の身体を考えても、諸々の職人の作ったものを装備している。もし必ず自分で全部作ってからそれを用いるとするなら、これは天下を指導してすべての人を疲れさせているだけである。だから昔の言葉にこうある。『ある者は心を労し、ある者は力を労す』と。心を労す者とは人を治める者であり、力を労す者とは人に治められる者である。人に治められる者は統治する者を養い、統治する者は人民に養われる。これが、天下の普遍的真理である」と。
小田:孔子の弟子の樊遅が農業を習いたいというと、孔子がすげなく断ったエピソードがありましたね(子路篇)。この孟子の反論は、孔子のあの辺の意見を、長大にまくし立てたものです。しかし、孔子が言うと説得力があります。孔子は若い頃は貧しくて、いろいろな職業を経験してきた苦労人であり、だから弟子に対して「いずくんぞ稼を用いん」と言って統治者はいちいち農民のまねごとなどしなくてよろしい、もっとするべきことがある、と言った言葉には、社会の上も下も体で知ってきた経験の重みがあります。しかし、孟子はどうだったでしょうか。単に、統治階級のための思想である儒家の主張をしゃべりまくっているだけで、経験に裏打ちされた議論の臭いがどうも薄いように思えてなりません。説得力に欠けるように思います。
上田:許行は神農をたてているのですが、どういう思想家だったんですか。
小田:許行の説については、『孟子』の中の記述以外のことは、よく分かりません。大事なことは、『孟子』は彼らをやりこめて嘲笑うのが目的でありますから、彼らを一方的に愚か者として扱っていることです。その説は、きっとゆがめられて描かれています。実際は、こんな粗雑な主張ではなかったでしょう。
上田:農業をしっかり行う事、価格を一定にすることを言ってますね。
小田:そうですね。価格を国家が公定して市場のなすがままに変動させず、品質を考慮に入れず産物は全て公定価格で取引させること。これを孟子は批判していますが、農村保護政策として見たならば、これは反自由化政策として一理ある主張です。産物が市場価格に翻弄されると、農村が崩壊する原因のもととなりかねない。許行たちの説はよく分からないので想像に過ぎませんが、彼らがまっとうな社会思想を主張していたとするならば、その視点は農村の保護にあったのではないでしょうか。農村は、社会の基本にあり、最も自然なコミュニティである。国家の統治階級は、農村から搾取するだけの有害無益な寄生者である。市場経済の浸透は、狡猾な商人によって農村が食い物にされて疲弊する害悪である。統治階級と市場経済は、ゆえに農村の敵である。私は、許行の思想は、きっと江戸時代の安藤昌益の主張に近いものだったのではないかな、と思います。昌益は、武士階級は搾取者であると批判し、彼ら統治階級の存在を正当化する孔子らの儒教も有害であり、捨てるべきであると主張しました。商人もまた、農村を疲弊させる敵とみなしました。農業のみが自然から直接生命を養う人間の正しい営みであり、人間は全て農業を行うべきと主張しました。昌益は八戸藩の疲弊した農村の実情から思想を展開し、農民を苦しめていた藩政府と商人を批判しました。許行の説は、陳相ら儒家をも転ばせたほどの説得力がある思想であったはずです。その思想は残されていないが、私は昌益のような農村からの目線で社会を批判した思想なのではなかったかな、と想像するところです。
上田:孟子も市場経済をよしとはしていない。許行とそう対立するものではなさそうだが。
小田:孟子もまた、商人の存在を積極的に評価しているとは、とても思えません。孟子と許行との違いは、孟子はあくまで統治者階級の存在意義を正当化しようとするところです。許行のように統治者階級の存在を批判する者を、孟子は論破しようとします。
上田:孟子は、許行はなんでも自分ですべきという点で徹底していないし、それは間違っていると批判している。しかし、許行は粟と械器の交換を認め、自らクツやムシロとの交換を行っており、分業を否定しているものではない。
小田:市場を経由しない公定価格を通じた、最低限の必需品の交換を認めるという立場でしょう。許行の徒は、おそらく農村の維持が思想の中心にあると思われますので、農村の維持のために必要な物品に限って公定価格で交易することを理想としたのでしょう。これは、農村の実情に基づいた思想であったのかもしれません。いっぽう孟子の議論は、どこまで農村の実情に基づいていたでしょうか?ただただ書経などの古代テキストに書かれていた内容をいにしえの聖王の制度であると無批判に称揚し、これを現代に復活させるべきだと主張する。それはまるで、マルクスのテキストで書かれていることが絶対真理であるとみなして現実との落差を認識せず、公式から現実を批判する教条主義マルクシストのようなものではないですか。孔子は貧しい出自から身を起こし、下級役人のやることも体験していて、庶民の実情を知る機会が十分にあったと思います。孟子には、そのような下積み時代が欠けていたのかもしれません。最初から学者一本であり、現実の生活者との接点に乏しかったのではないか。陳相兄弟が許行に簡単に転んだのは、許行の思想が儒家の思想よりも説得力があると彼らが悟ったからに違いない。ここでは孟子が陳相をやっつけたかのように記述されていますが、果たして陳相が儒家に戻ったでしょうか?やっつけられたのではなく、物別れに終わったのではないでしょうか。そんな簡単に論破されたとは、私はとても思えません。
上田:許行は、文公が倉廩、府庫を有することを、民を搾取しているとみなしていた。
小田:農村目線から見れば、統治者はいらない、市場経済もいらないという主張でしょう。自分たちで作ったものを、信頼できるコミュニティーとの間で交換し、自給自足に近い社会を維持していく。今の日本にも、物品、サーヴィス、さらには教育も国家や市場を経由せずにコミュニティーで自足させることを追求している人たちが大勢います。国家と市場を経由せずに自然社会を運営するという理想は、ある意味美しいものです。しかし私は、彼らの主張に全面的に賛同できかねます。国家がないと外部の暴力からの防衛ができず、市場経済の魅力はそう簡単に断ち切ることはできないと思います。
上田:孟子の批判は許行の説とかみあっていない。
小田:孟子は許行に対して、なぜ全部自分で作る、いわば原始人の状態に戻らないのか、という極論をぶつけています。しかし許行は、最低限の衣服は認めているようです。冠を着けています。当時の中国では、これを着けないと文化的に許容されない。だから、冠は着ける。しかし、冠のファッションにはこだわらない。農村の維持のために必要な需要だけを満たすことを優先して、贅沢やファッションを追求しない。そのようなことを許行は主張していたのでしょう。おそらく、陳相はここで書かれていることよりももっと孟子に反論していたことでしょう。もっと痛いところを突いていたんじゃないでしょうかね。
上田:孟先生、お説の井田法は成果を上げておりますかなどなど。
小田:孟子の農業政策などは空理空論であり、実行してみたらおそらく失敗していたことでしょう。さらに孟子は以前に斉で戦争を起こした張本人であり、斉と燕の両国を混乱させた前科がある。陳相は、その辺を突いて反論したのではないでしょうか?堯や舜がかつて行ったことなどを理想として掲げるが、今の時代の農村の実情をどれだけ孟子は分かっていたでしょうか。実際の農村の事情をふまえた許行の説に、陳相らはコロッと転んだのではないでしょうか。孟子は学のある人間は君子として朝廷で高い位に付き、贅沢に暮らし、人民を支配する権利があると弁護をします。こうして、統治者階級の自己弁護に終始しています。次の時代の儒家である荀子もまた、君子が高い禄を受けるのは社会秩序のあり方として自然である、と弁護して孟子と同じ線を行きます。かつての古い時代には、殿様と百姓との間で贅沢さに差があるのは当然のことであると誰も疑問を持たなかったことでしょう。しかしこの戦国時代になると、許行のように疑問を投げかける主張をする者が現れてきた。墨家もまた、統治者階級の贅沢さにノーを突きつけて、むしろ統治者は誰よりも人一倍働く義務があると主張した思想家でした。孟子は、それら統治者階級の存在意義に対する疑問を投げかけた思想に対して、統治者階級の存在を天下普遍の真理であると反批判する立場でした。
上田:利潤という考え方はどうなってましたか。
小田:前に成田さんが、諸子百家はあったが商家はとうとう現れなかった、と言っておられました。戦国時代といえども、商人道徳は現れなかったということです。東アジアで商人道徳が現れたのは、江戸時代の石門心学あたりが最初であったでしょう。商業活動が天道に適った道であり、適正な利潤は善であるという思想は、それまで根付くことはありませんでした。この許行のように、市場経済反対の思想はありました。むしろ東アジアにおいて国家の役目は、市場経済が農村に浸透することを防ぐところにあったといえるでしょう。
上田:ある男が市場の小高い丘から全体を眺めて、安く買って、高い所で売るという話がありました。
小田:前にあった「壟断」の故事です。孟子は、商人のことを十分理解していたとは思えません。孟子の思想は学者の思想であり、彼の思想は農民や商人の生活実情に即した思想ではない。孟子は亜聖公と称揚され、東アジアにおいては学者が上からの目線で社会を統治する思想が、国家公認の思想となりました。そのため、農民や商人などの生活者の実感から積み上げた思想の芽が、摘み取られてしまいました。不幸なことです。
上田:子貢は交易の利潤について分かっていたのではないですか。
小田:子貢のやったことは、投機です。おそらく彼は国によって物資の価格差があることに目を付けて、国の間で物資を動かすことによって巨利を得たのであろうと思われます。これは、継続的な交易活動というよりは、機会を見てシステムの間隙を突いて利益を得る、まさに「投機」であって、交易活動から適正利潤を得る、という考えとは違うでしょう。
上田:心学から何故利潤という考え方がでましたか。
小田:石田梅岩は町人であり、町人としての生活の後に学者になりました。その生活の実感に裏打ちされていたから、石門心学がありました。中国でも宋明代には商業活動が盛んで、裕福な商人は大勢いました。しかしながら、中国社会は官僚たちの文化である読書人の文化が圧倒的にステイタスが高く、商人たちといえども読書人の文化を規範としました。庶民の実感から思想を練り上げる、という考えは、根付くことがなかったと思われます。日本の儒教は江戸時代以降の輸入学問であり、底が浅くて根が浅い。それが逆にアレンジを利かせる気軽さを産む素地となり、町人あがりの学者が独自の思想を展開させて受け入れられることを可能としたと思われます。中国や李氏朝鮮では、そうはいかなかった。
上田:古代における富は農業ということですが、交易による利はエジプト、メソポタミアの時代からあるでしょうし、平清盛、足利義満、織田信長なども交易に力を入れた。
小田:エジプトやメソポタミアにおいては、交易による利は国家の管理下にあり、自由な商業活動とはいえません。日本史の中で交易からの利益に目を付けた政治家は確かに時代ごとに現れましたが、彼らの統治法が継続したかといえば、そうではない。清盛とか義満とか信長とかは確かに一時代を作り上げましたが、その後に続いたのはいずれも農業重視、商業抑制の安定志向の統治体制でした。交易が華やかであった信長・秀吉政権は長く続かず、その後を継いだ徳川政権は農村コミュニティーの維持に心を砕いた政権であり、商業はマージナルな存在として枠をはめ込み、その体制こそが長続きすることができました。産業革命以前の人間社会では、コミュニティーの維持が社会の至上命題であり続けました。正義とはコミュニティーの必要な需要を満たして継続させることにあるとみなされ、アリストテレスもまたそのように主張して自由な商業活動の意義を認めなかったところです。人間社会がコミュニティーを壊しつつ経済成長し続け、社会がそれを許容するような時代は、産業革命以降に産業資本が自立的に回転し始めた時代以降のことです。それはたかだか200年しか経過しておらず、人間の歴史としては新しいものです。それまでの時代は、コミュニティーの安定的維持を善とした停滞的社会がずっと続いていたのであり、その中で緩慢に成長が続いてきたのでした。石器時代、人間は農業とか船とか車とか、後の農業社会時代のテクノロジーをたいてい開発していました。ところが、人間は数万年の間それを発展させず、停滞の中で安定していました。それが、産業革命以前の社会の本来のあり方だったのです。
上田:中国には適正利潤という考え方はありますか。
小田:適正利潤という考えは、そもそも産業革命以前にはなかったと思われます。商業活動が正義であるという考えから適正利潤という考えが導出されるのですが、商業活動が正義であるという考えは、人類の歴史では非常に特殊で新しい考え方です。中国においては、鄧小平以降利益の追求が全面的に肯定され、今に至っています。これまでの中国経済は、低賃金を搾取元として利益を挙げ続けてきました。しかしながら、すでに今年ぐらいから低賃金の推進力は失われています。ここから先は商品の開発力や営業力といった正攻法の商業活動で稼ぐより他はないはずであり、それを行うには持続的な商業活動を目指した商道徳のセンスが必要と思われます。だが今の中国で、商道徳のセンスがどこまで育っているかは、ちょっと怪しい。中国経済は、今後が試されているところです。
久方ぶりに一揆に。サプライズ、稲垣夫妻に出会いました。
2013年7月27日(土)孟子滕文公章句
本日は、小田さん、上田さんの二人。本日分を音読。訓読と意味は小田さん。
堯の時に當りて、天下猶未だ平かならず、洪水橫流して、天下に氾濫す。草木暢茂(ちょうも)し、禽獸繁殖し、五穀登(な)らず、禽獸人に偪(せま)る。獸蹄鳥跡(じゅうていちょうせき)の道、中國に交はる。堯獨り之を憂へて、舜を舉げて敷き治む。舜、益(えき)をして火を掌らしむ。益、山澤を烈(せん)して之を焚(や)く。禽獸逃れ匿る。禹、九河を疏(とほ)し、濟・漯(せいとう)を㵸(とほ)し、諸海に注ぐ。汝・漢を決(さく)り、淮・泗を排(ひら)いて、之を江に注ぐ。然して後に中國得て食す可し。是の時に當りて、禹、外に八年、三たび其の門を過(よぎ)れども而も入らず。耕へんと欲すと雖も得んや。后稷民に稼穡を敎へ、五穀を樹藝す。五穀熟して民人育す。人の道有るや、飽食、煖衣、逸居して、敎へ無ければ、則ち禽獸に近し。聖人之を憂ふること有りて、契(せつ)をして司徒爲らしむ。敎ふるに人倫を以てす。父子親有り、君臣義有り、夫婦別有り、長幼序有り、朋友信有り。放勳曰く、之を勞し、之を來し、之を匡(ただ)し、之を直(なをら)し、之を輔け、之を翼(たす)けて、自ら之を得せしめて、又從ふて振(ふる)つてこれを德(めぐ)むと。聖人の民を憂ふること此の如し。而して耕へすに暇あらんや。堯は舜を得ざるを以て己が憂ひとす。舜は禹・皐陶を得ざるを以て己が憂ひとす。夫れ百畝の易(をさ)まらざるを以て己が憂ひとする者は、農夫なり。人に分かつに財を以てする、之を惠と謂ふ。人に敎ふるに善を以てす、之を忠と謂ふ。天下の爲に人を得るは、之を仁と謂ふ。是の故に天下を以て人に與ふるは易く、天下の爲に人を得るは難し。孔子の曰はく、大なるかな堯の君(きみ)爲る。惟(ただ)天のみ大なりとす。惟堯のみ之に則(のつと)る。蕩蕩(とうとう)乎たり、民能く名づくること無し。君なるかな舜。巍巍(ぎぎ)乎たり、天下を有(たも)つて與(あづか)らず。堯舜の天下を治むること、豈に其の心を用うる所無からんや。亦耕すに用ひざるのみ。
(孟子の言葉の続き)
「堯の時代になって、天下は未だ平かでなかった。洪水が暴れて、天下に氾濫していた。草木は伸び茂り、禽獸が繁殖し、五穀は実らず、禽獸が人の住処まで近寄り、獸や鳥の通り道が中国に交錯していた。ひとり堯のみがこれを憂えて、舜を登用して統治をさせた。舜は、益を用いて火を使わせた。益は、山沢を燃やして焼き払った。禽獸は逃れて隠れた。禹は、九つの河を治水し、濟水・漯水の川底をさらってそれぞれを海に注がせた。汝水・漢水を開削し、淮水・泗水を排水して長江に注いだ。こうした後に、中国は食を得ることができるようになった。この時において禹は八年間外遊し、三度自宅の門を通り過ぎたが立ち寄ることはなかった。耕作しようとしても、どうしてできただろうか。后稷は民に農業を教え、五穀を植え付けさせた。五穀が実って、人民が育った。だが人の道として(人の性格として)、飽食、煖衣、逸居して、教えがなければ、禽獸に近い。聖人はこれを憂えて、契に命じて司徒に就かせ、人倫を民に教えさせた。父子に親が有り、君臣に義が有り、夫婦に別が有り、長幼に序が有り、朋友に信が有る、と。放勳曰く、(放勳は堯のこと。趙岐はこの以下のくだりを堯の言葉でなくて業績であると解釈している。この場合、「曰」の字は「日」の間違いであると思われ、ゆえに小林先生は"日ごとに"と読んでおられる。朱熹は「曰く」と取っており、つまり以下は堯が言ったことであるとみなしている)『人民を働かせ、人民を集め、人民の邪を正し、人民を直にし、人民を助けて、自分の力で行うことができるようにしむけ、人民に奉仕してめぐんでやろう』と。聖人が人民を憂えるのはこれほどまでである。なのに、耕作するような暇がどうしてあろうか。堯は舜を得ることができないことを己の憂いとした。舜は禹や皐陶を得ることができないことを己の憂いとした。だいたい百畝の田畑の耕作がうまくできない、とかいうことを己の憂いとするのは、農夫である。人に分与するに財産をもってする、これを惠という。人に教えるに善をもってする、これを忠という。天下のために人を得ること、これを仁という。このゆえに、天下をもって人に与えることは簡単であり、天下のために人を得ることは難しいのである。孔子が言われた。『堯の君主ぶりは何と偉大なことか。ただ天だけを偉大とした。ただ堯だけが天の道に則り、ゆったりとしていた。人民は堯の統治を名づけることができなかった。舜は何と偉大な君主であろうか。高らかに立派で、天下を保有していながらも関与しなかった』と。堯や舜が天下を治めるときに、どうして心を用うることがなかったであろう。単に耕作に使わなかったのみである。」
上田:孟子の「父子親有り、君臣義有り、夫婦別有り、長幼序有り、朋友信有り」は、『書経』皋陶謨には、「父は義、母は慈、兄は友、弟は恭、子は孝」とある。孟子は論語風、どっちが古い認識ですか。
小田:『書経』を参照するときには、注意が必要です。『書経』の伝承は漢代に『古文尚書』と『今文尚書』の二系統があった。現行の『書経』は『古文尚書』であるとみなされてきたのですが、これは現在『偽古文尚書』と呼ばれます。本来の『古文尚書』は前漢代に孔子の旧宅の壁から出てきたテキストから編まれたものであったはずですが、西晋代に散逸してしまった。それが東晋代に梅賾(ばいさく)が『古文尚書』の完全なテキストが発見されたと主張したものが、現行の『古文尚書』であり、『書経』です。それは、漢代に伏生が口承していた『今文尚書』のテキストよりも大幅に篇数が増やされていました。以降、梅賾の提出したテキストが本物の『書経』と信じられていましたが、宋代ぐらいから朱熹などが疑問を呈するようになった。そして、清代に梅賾のテキストは捏造であると論証されてしまいました。だから『偽古文尚書』で水増しされた篇は、今のところ後世の捏造であると判断したほうがよいです。皋陶謨篇は、どっちだったかな、、、今は覚えていません。(後注:皋陶謨篇は『今文尚書』にすでにあった篇なので、捏造ではないと思われます。)
上田:孟子の方が古いということですか。
小田:少なくとも、より古い戦国時代のテキストの一バリエーションであったことは、確かです。いっぱんに人倫を五行説と絡めて五つに整理して、それぞれを一文字で表すことは、当時よくある整理法だったのではないか。しかしそれぞれの内容は、論者によって違っていたのでしょう。
上田:中国ではもろもろの古代の王により人間が動物とちがった人間らしい社会生活をするようになったという伝承がある。
小田:孟子は、このように聖人が治水を行い、聖人が土地を整備し、そしてモラルを教えないと人民は生活すらできなかった、と言うのです。つまり、統治階級がいなければ人民はモラルがないどころではなく、生活すら成り立たないと考えます。許行は、耕す農民があればそれで十分であり、統治階級はいらないと考えます。しかし儒家は、統治階級がいなければ社会は存在すらできない、とみなします。
上田:許行は神農をたてておりますが、人間らしい生活をさせることに功のあった一人であり、堯・舜もその一部。
小田:言い伝えの神農は、耕作を開始し、役に立つ草を選んで薬草をもたらしたということです。いわばはるか昔の時代の文化英雄であり、その点では堯舜も同じです。孟子は現在の社会のことを言っているわけです。今の時代もまた、堯舜のような統治者階級が絶対必要であり、それらは農夫のような耕作ごときやる必要はなく、むしろ農夫に養われるのが当然であると。孟子の統治者階級弁護の口調は、しかしながらどうにも私には違和感があります。だいたい中国の気候条件から言って、統治者階級が社会の必須条件であるという思想が、どうして出てきたのか。メソポタミアやエジプトは、砂漠気候です。チグリス・ユーフラテス川やナイル川の水を農村に分配しなければ、人間は生存することすらできない気候です。だから、これらの水を管理し、灌漑システムを維持する国家権力が社会の大前提となり、強力な王権が生まれる基礎となりました。このような気候条件に生まれた文明では、孟子のような統治者階級必須論は、わりかし納得がいきます。しかし中国華北は降水量は比較的少ないとはいえ温帯気候に属し、古来から天水農業、つまり雨水に頼る農業を行っていたはずです。天水農業ならば、王権による河川の水の管理は特別必要ではなかったはずです。より湿潤な華中華南ならば、なおさらのことです。このような気候条件の中国で、なぜ孟子が言うような統治者階級が人民の生活を作り上げたのだ、という神話が登場したのか、どうも私には腑に落ちません。オリエントと違って、統治者階級などは中国の農村の生存に必須であったとは思えません。
上田:天地を支える柱が折れたとか、西南に傾いたとか、洪水も堯の時だけではなかったようだ。
小田:洪水伝説は、世界中にあります。おそらく先史時代に地球レベルでの洪水があり、その記憶が形を変えて各地の伝説として残ったのではないでしょうか。
上田:聖王伝説をみれば様々な古王の工夫により、長い時間をかけて人間らしい生活を獲得し、社会を築くようになるという考え方は許行にしろ、孟子にしろ変わりはない、根底にあるのではないか。
小田:許行は、楚から来た人です。南方の湿潤な気候では、農村が自然に発生して先行し、政治は後から搾取者として乗っかって来た、という考えのほうが実感的だったのではないでしょうか。孟子の育った華北地方では、逆に政治が人民を指導して、そこから初めて人民の生活が成り立つという発想があるようです。しかし政治がないと生活が成立しない、という発想は日本人にはピンとこないと思います。
上田:そうでしょう。
小田:日本人は、おそらく政治などがなくても生活してゆける、と思っているはずです。政治家をなめたところがあります。しかし中国では、もしかしたら孟子の発想のほうがしっくり来るのかもしれない。すなわち政治がないと、国家は崩壊する。人民だけでは何もできない、国家が型をはめこまないと崩れ去ってしまう、という考えが優位なのかもしれません。そこに、中国と日本の発想の違いがあるのかもしれません。今週、埼玉県の浦和で朝のラッシュ時に女性が電車とホームの間に挟まれた事故がありました。そこで駅員らは音頭をとって車両から乗客全員を下ろし、乗客に協力を求めて、車両を皆で持ち上げて浮かせて、女性を助け出しました。この事故は日本では大したニュースになりませんでしたが、海外に紹介されて大変な反響を呼びました。イギリスで、ロシアで、アメリカで、中国で、驚きをもって報道されました。こんなことは日本人にしかできない業績だ、自分たちの国では乗客が自発的に協力して仕事をすることなどありえない、と。どうやら日本人には、人民の力で即座に秩序を作って事を成し遂げる力があるようです。政治あっての人民ではなく、人民が秩序をつくることができる。だがこの力は、どうやら日本人以外も持っているわけではないようです。孟子の考え方のほうが、グローバル・スタンダードなのかもしれません。政治がなければ、人民は何もできないという考え。しかし、日本人はたぶんそこから外れています。
上田:日本では武力による天下統一、暦や度量衡の管理、徳をもって王朝がはじまるという発想は無い。
小田:思想とか技術とかは輸入すればよい、という考えがあるからかもしれませんね。かつては中国から、明治以降は欧米から。時代ごとに発達した文明から、完成した形のものを導入すればよい。だから、自前で造り出さなければならないという意識が薄いのかもしれません。中国では、王朝が変われば制度が一変します。それは政治が制度を一から作り直す、という意識が働いているのかもしれない。いっぽう日本では幕府が変わっても、制度は大きく変わりません。変わるのは、大化の改新、明治維新、昭和戦後と進んだ制度をまるごと輸入するときです。
上田:ここでは孟子の書経からの引用が多い。孟子は孔子のように述べて作らずか、それとも孟子流にアレンジしているのか、そのあたりはどうなんですか。
小田:『書経』に限らず、六経など儒家のテキストは、孟子の活躍した戦国時代の斉国に集まった稷下の学士たちが手を入れていた可能性が高い、と私は思います。おそらく孟子自身も、深く関与していたのではないか。儒家は古い制度の復古を主張していたので、当然古来の伝承の伝承整理を重視しました。その他の諸子百家は、儒家ほど古来の伝承保存を重要に思っていなかったことでしょう。後の万章章句で、万章たち孟子の弟子がいにしえの聖人賢人たちの色々な異説を取り上げて、孟子にその真偽を質問しています。おそらく『書経』にあらわれたような説話にも、当時は色々な伝承が並行してあったのでしょう。そのうちから儒家にとって都合のよい伝承を正統とみなし、そうでない伝承は除外したと思われます。たとえば、殷の伊尹が料理人となって湯王に取り入ったという話があります。これは韓非子難言篇にも取り上げられていて、当時は広く信じられていた伝承です。韓非子が言うに、伊尹は賢者であったが湯王に七十度説いても聞くところとならなかった。それで料理人に身をやつして湯王に取り入り、ようやく湯王が聞き入れる機会を得たと。韓非子は聖人湯王と賢者伊尹とであっても、政治の場ではこのぐらい君主が家臣の進言を容れるのは難しいのだ、と説くわけです。だが万章はこの伝承は本当なのかと孟子に問い、孟子は伊尹がそんなことをするはずがないと却下しました。
上田:「人に分かつに財を以てする、之を惠と謂ふ。人に敎ふるに善を以てす、之を忠と謂ふ。天下の爲に人を得るは、之を仁と謂ふ。」これは、論語の忠や仁とはいささか異なる、当時あった言葉ですか、それとも孟子の言ですか。
小田:その後の「是の故に天下を以て人に與ふるは易く、天下の爲に人を得るは難し」の結論を導くためにある言葉でしょう。この言葉、孟子の他の章で出てくる持論と一致しています。公孫丑章句下での「故に將(まさ)に大いにすること有らんとする君は、必ず召さざる所の臣有り。謀ること有らんと欲すは、則ち之に就く。其の德を尊び道を樂しむこと、是の如くならずば、與にすること有るに足らず」と同じことです。志大きな君主は、家臣に大きな人材が何としても必要である。君主は、大きな人材である家臣を呼びつけるようなことはしないのだ、と斉の宣王に言い放ちました。そのぐらい、人材は重要である。堯は舜を得るために至れり尽くせりを行い、孟子はこの両者こそが真の友人関係であると言いました。まあ、要するに孟子は自分をそのように尊重せよ、と時の君主たちに言いたかったのですが。ここでの忠や仁の説明は、孟子の結論に沿って言われたものでしょう。
上田:孔子の曰はく以下の孔子の言葉は、論語ではどうですか。
小田:泰伯篇の最後の部分とほぼ一致します。「子の曰はく、巍巍乎かな、舜禹の天下有つなり。而して與らず」「子の曰はく、大なるかな堯の君と爲るなり。巍巍乎として唯だ天大と爲す。唯だ堯これに則る。蕩蕩乎として民能く名づくる無し。巍巍乎として其の成功有るなり。煥乎として其の文章有り」。孟子は同じ原典からわずかに異なる文を引用したはずです。このくだりは、しかしどうも道家思想の臭いがします。無為の統治術を最上とするわけです。孟子は、君臨すれども具体的な仕事を行わなかったという堯舜の統治を儒家流に解釈して、仁の心によって有能な家臣をなつかせて働かせたのが彼らの偉大な統治者としての徳であったとみなすのです。君主自らが働くことは、ありません。そこから仁を取り去って無為の統治にすれば、道家思想になります。論語泰伯篇の統治論は、道家思想と紙一重です。
上田:「民能く名づくること無し」とはどういうことですか。
小田:あまりに偉大なので、人民には形容のしようがないということでしょう。
上田:太陽のようなもので当たり前のもので格別に意識にのぼらない。書経とか古い伝承のなかでは、いろいろの要素が混在していたのではないですか。
小田:孟子が泰伯篇の言葉をあえて引用した理由は、許行の徒への攻撃のみならず、墨家の主張への攻撃の意図もあったはずです。墨家は、禹を理想の君主とみなしました。禹は脛の毛が擦り切れるほどに天下のために働いたと伝えられる聖人です。墨家はこのように統治者は率先して天下のために働くべきことを、主張しました。儒家と道家は、共にこのような墨家の君主像を批判しました。君主は具体的に働く必要はない、と。その点においては、儒家と道家は一致していました。
上田:許行は神農、墨家は禹というところをとりあげる。
小田:儒家は堯・舜であり、道家は黄帝です。それぞれ、神話上の人物を理想の君主として仮託し、それぞれの統治論を肉付けしていったのです。前の泰伯篇では堯舜と並んで禹も称えられていますが、孟子の引用からは禹が削られています。きっとこれは、墨家のアイドルである禹を儒家のアイドルである堯舜と並べることを避けたのでしょう。たわいもないことです。
2013年8月3日14:00~16:00 論語読書会in士心
参加者:上田、成田、小田、桐畑孝佑 記録者:小田
学而篇七(読み下しは、中村愓斎に従う。)
子夏の曰く、賢を賢として色に易(か)へ、父母に事(つかふまつ)って能(よ)く其の力を竭(つく)し、君に事(つかふまつ)って其の身を致し、朋友と交はり、言(ものい)って信(まこと)有らば、いまだ學びずと曰(い)ふというとも、吾は必ず之を學びたりと謂(い)はん。
《James
Leggeの英訳》
Tsze-hea
said, "If a man withdraws his mind from the love of beauty,
and applies it as sincerely to the love of the virtuous; if,
in serving his parents, he can exert his utmost strength;
if, in serving his prince, he can devote his life; if, in
his intercourse with his friends, his words are sincere:-
although men say that he has not learned, I will certainly
say that he has."
(日本語訳例)
子夏(しか)が言った、「もし人がその美人への愛から心を自制して、心を同じくらいの真剣さで賢人への愛に捧げたならば― もし人が両親に仕えるときに自分の最大限の力を用いたならば― もし人が諸侯に仕えるときに全生命を捧げたならば― もし人が友人と交わるときに言葉に誠実であったならば― たとえ世の人々がこの人のことを無学であると言ったとしても、私は断じて彼のことを学のある人だと言うであろう。」
(英訳について)
小田:桐畑さん、ありがとうございました。この英語は、かなり難しいです。4つの「もし」を重ねて、この4つの条件を備えているならばという条件文が続いて、ようやく最後の主文になります。"the
love of beauty"
という訳は、おそらく美女とか美人を想定した訳だと思います。"as
sincerely"は、"as
sincerely (as the love of
beauty)"
が隠れているわけで、「美人への愛と同じくらいの真剣さで」という意味です。"prince"は一般の意味では「皇太子」ですが、もともとの意味は王様に次ぐ位の君主を指す言葉です。(イギリス皇太子の正式名称は"Prince
of
Wales"ですが、これはイギリスの一地方であるウェールズを治める小君主、という意味です。)孔子の時代は周王朝でしたが、周王朝は力を失って配下の数多くある諸侯たちが覇権を競っていた時代でした。日本の戦国時代みたいな状況でした。だから、レッグはそのような諸侯に仕えることを想定して、"king"ではなくて"prince"の語を用いたのでしょう。"Tsze-hea"は孔子の弟子、子夏のことです。ところで三つ前の章を見てください。ここの発言者である曾子(そうし)は同じく孔子の弟子ですが、"The
philosopher
Tsang"と訳されています。両者は格が違うことを、レッグは意識して訳し分けているのです。「子夏」という呼び名は、字(あざな)です。彼の姓名は、卜商(ぼく・しょう)です。いっぽう「曾子」という言い方は、「曾先生」というニュアンスを持つ尊称です。真の姓名は、曾參(そう・しん)です。彼の字は子輿(しよ)です。姓・名・字・尊称の関係は、以下のとおりとなります。
曾參 姓+名。昔の中国では、他人を姓+名で呼ぶことは失礼であるとみなされた。
曾子 姓+尊称。弟子が先生を呼ぶときにはこのように呼ばれた。
子輿 字。対等の同僚が呼びかけるときには、もう一つの名前である字で呼びかける。
昔の中国では、他人の名を呼ぶことが許されるシチュエーションは、三つありました。一つは家庭内の目上が呼ぶとき。曾參の家の両親や祖父母、兄姉、叔父さんたちなどは「參」と名を呼んでもよい。二つは社会上の目上が呼ぶとき。孔子は師であるから、弟子のことを「曾參」と呼んでもよい。また漢の皇帝は、「劉備」と呼んでもよい。三つは敵が相手を罵るとき。曹操は「劉備」と呼んで敵として罵ります。しかし曹操も劉備も同じく漢の家臣として仕えていた時期には、曹操といえども名で呼ぶことは許されません。「劉予州」とか、役職で呼びかけたりします。
ここで卜商のことを「子夏」と字で表記しているということは、いわば「子夏さん」と対等の同僚として表記しているわけです。いっぽう曾參のことは「曾子」、つまり「曾先生」と尊称しているわけです。なので、論語のこの学而篇のあたりは、おそらく曾子の弟子の系統が編集したものであろう、という推測が成り立つわけです。卜商の弟子が編集したならば、「卜子(ぼくし)」と尊称されているはずです。
|

|
成田:子夏は、孔門十哲の一人に数えられる高弟です。多くの弟子がいたことでしょう。ところが曾參は十哲に入っていない。
小田:孔門十哲が出てくるのは、論語後半の先進篇です。なので、論語の前半と後半は編集者が違うのではないか、という推測もあります。
成田:孔子が死んだ後に、弟子たちはそれぞれに一門を立てて孫弟子を持つようになりました。子夏の一門を別の若い弟子たちが「孔子の教えと違う」と非難したりしました。孔子の死後、それぞれの弟子たちの主張の違いがあらわとなって、学派が分裂していきました。
|
(討論)
小田:桐畑さん、この章の意味は、分かるでしょうか?
桐畑:大筋理解できますが、「學ぶ」というのは何を学ぶことを想定しているのでしょうか?
成田:子夏の「學ぶ」に対する考えと、世間一般の「學ぶ」に対する考えとには違いがあったようです。子夏の「學ぶ」とは、日常生活の上で誠実に実行することを習得する、ということであり、世間一般の「學ぶ」とは知識の多さを競うものだったのでしょう。
小田:知識の多さよりも、道徳というわけですか。今の学校で、そのような教育がなされているのでしょうか?
桐畑:道徳の科目に五段階評価を導入する、という議論があって、しかし道徳の科目に点数評価は合わないという批判もあります。
小田:少なくとも私の通っていた高校では、勉強とは偏差値が全てだとばかり言っていましたね。道徳教育なんぞ、完全に無視されていました。
成田:人の道としての道徳は、小中の義務教育で教わってそれで十分。高校以上は専門知識があればよい、ということでしょうかね。
小田:しかし、礼儀とか社会常識とかは、いずれ将来社会に出たときに評価されて出世するための武器になるのだから、よく学んでおけと高等教育で教えるのは有益ではないかな、とも思うのですが。今の時代では、学校で道徳を学んでも目立った利益がよく見えないので、おろそかになりがちです。漢代とかの中国では、親孝行だとか村で評判がよいとかの評価が上がれば、朝廷に就職口を推薦されました。こういう目だったメリットがあれば、道徳に励むでしょうが。
成田:ところが実際は、有力者に近い人間だけが選ばれました。コネ社会を助長しただけでした。それで後世になると科挙が導入されて、筆記試験の成績で道徳を測ることになった。道徳の筆記試験となれば、論語をどれだけ丸暗記しているかが「學ぶ」の大小とみなされることになりました。
小田:さて、「賢賢易色」ですが、オーソドックスな解釈はレッグのように「美人への愛から賢者への愛に心を向け替えよ」というものです。しかし、これには異説があります。高名な中国史研究家の宮崎市定氏は、「賢賢たるかな、易(とかげ)の色や」と読み下し、これは古いことわざの引用である、と解釈します。「易」は通常占いの意味ですが、その原義は動物のトカゲのことです。トカゲはカメレオンが一番わかりやすい例ですが、周囲の環境に応じて体の色を素早く変える特徴があります。そこから「易」の字には「かえる、かわる」という意味が派生し、運命の変化を示す占いの意味もまた派生しました。宮崎氏は、「易」の字を原義のトカゲの意味であると捉えました。そして、この章が意味することは、古語の言うとおりトカゲは巧みに色を変える、そしてトカゲのように会う人(両親、諸侯、友人)に応じて付き合い方を巧みに変える人は賢明であり、それは学のある人間なのだ、と子夏が批評した、というのです。
桐畑:そう読むと、意味がぜんぜん変わってきます。
成田:しかし、宮崎氏の説はちょっと苦しいのではないかと思います。「色」のもっとも古い意味はセックス、性行為そのもののことです。これが論語の時代になると、「顔色・表情」という別の意味が付け加わりました。この「顔色」という意味が先行して、そこからさらに派生して一般的な「色・色あい」という意味が生まれました。しかし論語の時代において一般的な「色・色あい」という意味で「色」の字が使われたという宮崎氏の解釈は、考証的にかなり苦しいと思います。むしろ、「賢賢易色」は「賢者を賢者として尊重するように、顔色を変えよ」という解釈も成り立つわけで、私はむしろこの読み方を支持したいです。賢者に対面したら尊重する表情を作れ、ということです。
小田:「賢賢易色」には他にも解釈があります。別の高名な中国史研究家の貝塚茂樹氏は、「賢を賢とすること、色(おんな)の易(ごと)くせよ」と読んでいます。つまり、「賢者を賢者として尊重することを、女色を好むことのように行え」という解釈であり、性欲肯定です。貝塚氏がこの解釈を出したのは70年代学生運動の時代であって、時代らしい解釈です。
上田:中村愓斎の注が、よく分からない。「其人みづから色を好むの意にかへて、賢をたつとぶと云にあらず」とはどういう意味ですか?
成田:色を好む心と賢者を尊ぶ心は別であって、色を好む心をそのまま賢者に向けて賢者を愛するのではないぞ、ということでしょう。もし向ければ男色なってしまう。
では、次にいきましょう。桐畑さん、続いてお願いします。
学而篇八(読み下しは、中村愓斎に従う。)
子の曰はく、君子重からざれば則ち威あらず、學も則ち固からず、忠信を主とし、己れに如かざる者を友とする無かれ、過つときは則ち改むるに憚ること勿(なか)れ。
《James
Leggeの英訳》
The
Master said, "If the scholar be not grave, he will not call
forth any veneration, and his learning will not be solid.
②"Hold faithfulness and sincerity as first
principles."③"Have no friends not equal to
yourselves."④"When you have faults, do not fear to abandon
them,"
(日本語訳例)
先生が言われた。「もし学者が重々しくなければ、尊敬の念をさっぱり起こさせることができず、その学問は確固たるものにならないであろう。」②「信頼と誠実さを第一の原理とせよ。」③「君たち自身と対等以下の友人は、持ってはならない。」④「間違いを犯したときには、それを捨て去ることを恐れてはならない。」
(英訳について)
小田:この章は、4つの異なる言葉をつなげている、とレッグは解釈しているわけです。
(討論)
小田:「君たち自身と対等以下の友人は、持ってはならない。」という言葉は、きついと思いませんか?
桐畑:対等以上となれば、上司でしょうか。
成田:しかし上司の側から見れば、目下は対等でないから友人となりえない。結局、対等の同僚しか友人になりえない、ということになるでしょう。
小田:この言葉は、身分関係の上下だけを指し示したのではないと思います。友人というのは、相手を尊重する関係である。尊重するためには、相手に何がしか自分より勝っている点が必要だ。たとえば知識では私のほうが上だが、決断力では友人の方が勝っていることを認める、という関係です。それが、全ての点において相手よりも自分が勝っているならば、それで友人関係となることは難しい。師匠と弟子、あるいは親分と子分の関係ならばよいが、心中で相手を尊重できず見下しているのに対等の友人関係を築くことはできない、という考えであると私は思うところです。
成田:思うに、孔子の弟子たちが朝廷で職を得たとき、同僚には身分の高さだけで職を得ている人間たちもいたはずです。実力で雇われた孔子の弟子たちは、そのようなコネで役職を得た人間たちと共に仕事をしなければならない。このような相手は実力では自分たちと対等ではないのだから、そのような人間たちと友人関係になどなってはならず、なる必要もない、というアドバイスであったかもしれません。
小田:会社の従業員というものは、しょせん雇われた雇用関係にすぎない。しかし日本の会社組織にはウェットな人間関係がつきまとい、チーム意識を維持しようとし、付き合いたくも無いのに過剰なまでに友人みたいな職場関係を作ろうとする空気もあります。このような空気があるから、自分の仕事が終わったら退社、というドライな行動を取りづらくして、サービス残業の温床になっています。現在企業の側は従業員の保護をやめて資本の論理をむき出しにしているわけで、他方で従業員の側はドライな雇用関係を作れておらず、一方的に不利な拘束を受けている。これがブラック企業を生み出す原因だと思うわけです。本来の友人関係とは、職場の中での付き合いとは区別するべきです。この辺、中国人などは職場でドライに付き合える技を持っているのではないですか?
成田:表面上は穏やかに付き合う術は、巧みですね。
小田:水面下では激しく争っても、表面は君子として穏やかであるわけですか。さすがは孔子以来の年季が入っている。
上田:「過つときは則ち改むるに憚ること勿(なか)れ」は、自分が過ったときだけでないのではないか。主君が過ったときに、直ちに修正させなければならない、という意味があると思います。
桐畑:「重からず」というのは、具体的にはどういう行為なのでしょうか。
小田:現代では、分かりづらくなっている行為です。たとえば江戸時代の武士たちは、軽々しく会話しなかった。動作はあわてたりせず、沈着であることが求められた。これは、武士の威厳を保つためにそうすべきと教えられていたからでした。
上田:中村愓斎の注釈の最後に、この章を田の管理になぞらえています。これは、どういう意味でしょうか。
小田:このたとえ話は、なんだか的を外しているという印象ですね。言っていることは分かるが、このたとえは上手とはいいがたい。ところでさきほどの章と同じく、この章にも異なる読み方があります。「學も則ち固からず」を、「學べば則ち固からず」と読んで、意味は「学問を積めば固執しなくなり、臨機応変に対応できるようになる」とみなすわけです。つまり、前の「君子重からざれば則ち威あらず」と「學べば則ち固からず」はつながっておらず、それぞれ君子の別々の行為を指しているのだ、という解釈です。私はこちらの解釈のほうが、好みです。
桐畑:論語の「學」は、実用的知識が中心のようです。シチュエーションに応じて、具体的な論議を行っている。私は最近『老子』を読んだのですが、両者はずいぶん違っています。
小田:伝説では、老子は孔子の同時代人、ということになっていますが、私は先に孔子の論語があって、『老子』は後から編集されたのであろうと推測します。古い時代の知識は、論語の中に出てくるような実用的知識であった。それが時代が進むに連れて抽象的な議論が発達し、『老子』のような思想が現れたのでしょう。
桐畑:孔子の弟子たちが学んでいた「學」の内容は、どうだったのでしょうか。
小田:「礼」が中心です。礼は学ばなければ得られない宮廷作法の知識であり、学ぶことによって宮廷に職を得る機会がありました。当時の礼の中には、法律もまた含まれていました。つまり、儀式から立法行政まで、政治に必要な知識の体系全てでした。
成田:孔子の学校に入門すれば礼を学ぶことができて、職を得ることができた。なので、弟子たちはそれ目当てに入門してきました。孔子は弟子たちに向けて、しかし専門知識だけでは君子とはなれない、礼の形式だけではなくて礼の精神も学ばなければならない、と説いたのです。
桐畑:私は経済学専攻ですが、経済学には主流の学派とは別にエコロジー経済学や人間の幸福度を指標とする議論があります。そのような議論では、仏教や老子の思想を参考にしているところがあります。経済学もまた、倫理的規範からの視点を持たせることができる、と思います。今の経済学では、倫理的規範の議論はほとんどありませんが。
小田:かつては近代経済学とマルクス経済学の両派があり、両者は同じ経済現象を違う倫理観から捉えて対立していた、と言うことができるでしょう。先日参議院に当選した某社長さんなどにとっては、自由な営利活動は倫理的善である。しかし従業員の立場から見れば、過酷な競争は従業員から人間的な生活を奪う倫理的悪である。近代経済学とマルクス経済学は、両者の異なる視点に立って、激しく対立していた。経済学にもまた規範的(normative)な視点は当然あるわけで、単なる技術の学問ではないはずです。社会の幸福をどのように捉えるか、という倫理的視点において、孔子の主張は老子や仏教とは、違う視点に立っています。それを理解して是非を吟味することも、大切なことだと思います。
2013年8月21日(水)送別と成婚の集い
|

|

|
|
まずは童君夫妻と鄭さんの近況。
8月10日頃に一緒に台湾での学会に参加されたとのこと。
台北の街を散歩している時、ある写真コンテストの題材を探している台湾大学の大学生の請求でモデルをされたのが上の写真。
右は、鄭墡謨兄と家内と小犬とありますが、子犬のようにかわいい息子ということでしょうかね。それともなにか特別の意味でもあるのでしょうか。
鄭さんも早くご子孫を。
|
8月21日(水) 19-22、士心。送別とご成婚、門出を祝して乾杯。久方ぶりにメンバーが揃って旧交を温めることができました。 早川君は九月から北京へ、北澤さんも九月から燕山へ。高井君と岸本さんは、25日の挙式直前に、万障繰り上げて、参加をいただきありがとうございました。稲垣君にはMCをおつとめいただき円滑に会が進行いたしました。
小田さんより、送別の詩あり。
|
海濱太平轉擾亂
寛政奇士憂慮多
光陰重代意不變
電網繋國心偏頗
英州凱男嘗駁説
千載後日風浪過
從之畢竟盡死已
無爲將奈難局何
百花多忙海東界
君遊燕地離鴨河
河南雖愚勸子敬
熱魂冷頭資切磋
復欲阮籍酒中歌
癸巳七月
河南殷人
|
(読み下し)
海濱の太平 轉(うたた)擾亂
寛政の奇士 憂慮多し
光陰 代を重ねて 意 變らず
電網 國を繋げて 心 偏頗なり
英州の凱男(がいだん) 嘗(かつ)て駁説す
千載後日風浪過 千載の後日 風浪過ぎん
之に從はば 畢竟 盡(ことごと)く死するのみ
無爲にして將(まさ)に難局を奈何(いかん)せんと
百花 多忙なる 海東界
君は燕地に遊びて 鴨河を離る
河南 愚(おろか)と雖(いへど)も 子敬に勸む
熱魂冷頭 切磋に資せん
復(ま)た 阮籍の酒中歌を欲す
|
|
|
[大意]
(かつて) 海浜の太平は次第に擾乱と化し
寛政の奇人、林子平の憂慮は多かった。
時は世代を重ねたが、その頃と意志は変わっていない。
インターネットが国を繋いだが、人心は偏頗(かたよる)である。
英国のケインズ(凱恩斯)男爵は、かつて論駁した。
「千年の後日には、風も浪も過ぎ去るであろうという説があるが
この説に従ったならば、結局皆死んでしまうだけだ。
無為であっては、この難局をどうすることもできないだろう」と。(註)
海東のこの日本では、議論の花が咲き乱れ、大変に忙しい。
そんな中で君は、燕地(えんち=北京)に遊学し、鴨川を離れていく。
河南(小田の雅号です)は愚かであるが、子敬に勧めよう。
熱い魂と冷たい頭が 勉学向上の糧となるでありましょう、と。
また、阮籍が酒中で奏でたあの歌を、聞かせてください。
(註)But
this long run is a misleading guide to current
affairs. In the long run we are all dead.
Economists set themselves too easy, too useless a
task if in tempestuous seasons they can only tell
us that when the storm is long past the ocean is
flat again.
|
成田君解説ありがとうございました。「酒狂」 伝阮籍作の演奏、2012年10月13日の演奏(読書会)が思い起こされます。成田君より、早川君に手彫りの落款印と申しますか雅号印が贈られ、早速、これを用いて、同じ字で韻を踏んだ返答の詩あり。
|
平成癸巳、八月二十一日、離宴の席上、河南先生、我に賜うに七古の大作を以てす。瑶均(※)に次し奉る。(※)均=韻
|
|
秋蝉 客を送る 洛陽の道
西を望めば 奈(いかんともする)無く 憂念多し
和漢の二邦は 本(もと)より唇歯
恰(あたか)も 相如(しょうじょ)と廉頗(れんぱ)に似たり
趙宋の詩文は 情味有り
燈前 巻を開けば 時の過ぐるを惜しむ
平生 最も仰ぐは 黄山谷(こうざんこく)
才は襪線(べっせん)の如くして 奈何(いかん)せんと欲す
願わくは雅琴を帯びて 五嶽に遊び
懐(ふところ)に詩筆を携えて黄河に対せん
燕京の学堂は 彦士(げんし)多し
朋友 講習 玉磋(みが)く可し
|
(大意)
秋の蝉が客を送る、洛陽の道
西方を望むと、何とすることもままならず、憂いの心が多い
日本と中国とは、もとより唇と歯のような親密な関係であり
それはあたかも戦国時代の藺相如(りんしょうじょ)と廉頗(れんぱ)のようなものだ
趙氏宋王朝の詩文は、情味がある
ともしびの前で本を開けば、いたずらに時が過ぎてゆく
日常の私が最も仰ぐ詩人は、黄山谷(黄庭堅)である
だが私の才は足袋の糸のように短小であり、近づくこともできない
願わくは雅やかな琴を帯びて、中国の五嶽に遊び
詩筆を携帯して、黄河に相対したいものだ
燕京(=北京)の学堂には、立派な士が多い
朋友関係に学校の講習。玉を磋(みが)かなければならない
|
|
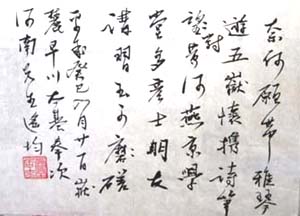
|
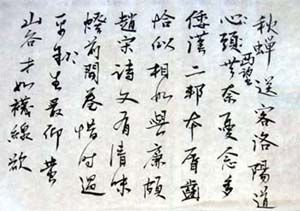
|
かような詩のやりとりは、中華では行われることがなくなり、東夷において生きているようです。文化の果つるところに文化発つ。論語なんぞもさようなものです。北澤さんによれば、中国での日本語教師が不足しているようです。当地にゆかれましたら、また、実情を教示ください。
高津君、川那辺さん、大川さん、駆けつけの安澤さん、電話参加の鄭さん、皆さんご多用のところありがとうございました。
2013年8月25日(土)孟子滕文公章句
本日は、小田さん、上田さんの二人。本日分を音読。訓読と意味は小田さん。
吾聞く、夏を用ひて夷を變ずる者を。未だ夷に變ずる者を聞かず。陳良は、楚の産なり。周公・仲尼の道を悦びて、北中國に學ぶ。北方の學者、未だ之より先きんずること或ること能はず。彼は所謂豪傑の士なり。子が兄弟之に事ふること數十年、師死して遂に之に倍(そむ)く。昔(むかし)は孔子沒して、三年の外、門人任を治めて將に歸らんとし、入りて子貢を揖(ゆう)す。相嚮(むか)つて哭し、皆失聲して、然して後に歸る。子貢反りて、室を場に築いて、獨り居ること三年、然して後に歸る。他日子夏・子張・子游、有若が聖人に似たるを以て、孔子に事(つこふま)つる所を以て之に事へんと欲して、曾子に彊(し)いん。曾子曰く、不可。江漢以て之を濯(あ)らひ、秋陽以て之を暴(さら)す。皜皜(こうこう)乎として尚(くわ)ふ可からざるのみ。今や南蠻鴃舌(げきぜつ)の人、先王の道に非ず。子、子が師に倍(そむ)きて之を學ぶ、亦曾子に異(い)なり。吾聞く、幽谷を出でて喬木に遷る者を。未だ喬木を下つて幽谷に入る者を聞かず。魯頌に曰く、戎狄是れ膺(う)ち、荊舒是れ懲らす。周公、方に且つ之を膺つ。子、是を之學ぶ。亦善く變ぜずとす。
許子が道に從はば、則ち市の賈(あたひ)貳(ふた)つならず、國中僞り無けん。五尺の童をして市に適かしむと雖も、之を欺くこと或ること莫けん。布帛(ふはく)長短同じくは、則ち賈(あたひ)相ひ若(し)かん。麻縷絲絮(まるしじょ)輕重同じくば、則ち賈相ひ若し、五穀の多寡同じくば、則ち賈相ひ若し、屨(くつ)の大小同じくば、則ち賈相ひ若かん。曰く、夫れ物の齊(ひと)しからざる、物の情(せい)なり。或は相ひ倍蓰(ばいし)し、或は相ひ什伯し、或は相ひ千萬す。子比(つ)いで之を同じふせば、是れ天下を亂るなり。巨屨小屨賈を同じふせば、人豈に之をせんや。許子が道に從はば、相率(ひき)いて僞りをせん者なり。惡んぞ能く國家を治めん。
(孟子の言葉つづき)「私は中華の文化に蛮族が変化するのを聞いたことはあるが、いまだに蛮族の文化に変化するのを聞いたことがない。陳良は楚の生れであり、周公・仲尼(孔子)の道を悦び、北に中国に学んだ。北方の学者といえども、陳良を越える者は現れなかった。彼はいわゆる豪傑の士である。お前たち兄弟は数十年間陳良に仕え、いざ師が死んだら彼に背いた。昔、孔子が沒して三年のたった後、門人は喪の任を終えて帰ろうとして、子貢のところへゆき挨拶をした。相対して哭礼を行い、皆声を枯らして帰った。だが子貢だけは戻って一室を墓に築き、独りで居ること三年、それから後に帰った。後日、子夏・子張・子游は有若が聖人(孔子)に似ているので、かつて孔子に仕えた作法で仕えようとして、曾子にそれを強要した。だが曾子は言った『それはできない。長江や漢水で布を濯(あ)らい、秋の陽差しで布をさらし、こうして布がピカピカに白く光る。これほどまで孔子はすぐれており、誰がこれに比肩することができようか』と。今、南蛮の鳥のようなわけのわからない言葉を話す輩が、先王の道を非としている。お前は、お前の師に背いて奴に学んだ。なんとまた曾子と違うことか。私(孟子)は、暗い谷を出でて高い木に移る者のことは聞いたことがあるが、いまだに高い木を降りて暗い谷に入る者を聞いたことがない。詩経の魯頌にこうある、『戎狄は是れを撃ち、荊舒は是れを懲らしめる』と。周公はまさにこれら蛮族どもを撃ったのだ。お前はこのことを学んでおりながら、その変節がよいことといえるだろうか」と。
(陳相が言った)「許子の道に従えば、市場の値段が統一され、国の中で詐欺がなくなるだろう。背丈五尺の小さな子を買い物に市場に行かせたとしても、誰もこの子を欺くことができなくなるだろう。布帛は長さが同じなら、値段はどれも等しくなるだろう。麻・縷・絲・絮(麻、絹などの糸の総称)は重さが同じならば、値段はどれも等しくなるだろう。五穀は量が同じならば、値段はどれも等しくなるだろう。屨の大きさが同じならば、値段はどれも等しくなるだろう」と。
(孟子が)言った、「そもそも物の価値は均一ではないのが、物の性質である。あるいは二倍・五倍し、あるいは十倍・百倍し、あるいは千倍・万倍する。お前はそれらをひっくるめて同じ値段にすると言う。それは天下を乱すことになるだろう。巨屨(粗い廉価な靴)と小屨(精緻で高価な靴)の値段を同じにすれば、誰が高価な屨を作るだろう?許子の道に従うなら、すべての人を偽りに導くことになり、どうして国家を治めることが出来ようか?」と。
小田:こうして孟子が論争に勝ったかのようにまとめて終わっているわけです。当然ながら、孟子側の勝利した主張しか書かれていません。
上田:許子の主張が孟子の述べるとおりとは思えない。
小田:前も申しましたが、許子はおそらく価格統制を経済政策として主張していたのでしょう。つまり、市場ごとに自由に価格を設定させていれば、市場ごとに価格差が発生する。それがあると、物資を右から左に流すだけで巨利を得られることになり、投機商人の格好の餌食となります。しまいには生産をないがしろにしても商人が投機に群がるようになり、買占め売り惜しみを通じて市場価格を操作して生産者から富を吸い上げるようになります。これを国が公定価格を決めて市場ではその価格以外では取引させないように統制すれば、投機の余地はなくなる。そうやって農村を商人が食い物にしないようにする。許子の主張は『孟子』以外では残されていないのですが、私は、そういう風なものではなかったかと思っています。この政策は、古代から現代まで繰り返し提唱されている、投機抑制策ですので。
上田:孟子は許子が何もかも長さ、重さ、量が同じなら同じ価格にせよと言っているかのごとき言い分であるが、孟子が捻じ曲げているのではないか。
小田:私は、許子本来の主張にも程度の差はあれ言われるような内容が含まれていたのではないか、と思っています。農村の生活を維持するために価格を市場を無視して公定することは、今だって行われていることです。農村が商品経済に巻き込まれて没落者が出ないように、農村を解体させない価格を設定して奢侈品の生産売買を禁止するという主張があったのではないか。許子が農村保護の実践的思想を持っていたとすれば、大いにありうることだと思います。
上田:班田収受においてすら、田に上、中、下の区別があり、絹布でも精粗に等級があり、そういうものは税として納める基準にもなっており、なにもかもいっしょくたというのは現実的ではない。
小田:思想ですから。戦国時代は前の時代に比べて、おそらく貧富の差が大きくなり、農村は疲弊していたことでしょう。価格統制と奢侈品抑制により貧富の差を押さえ、時代の贅沢に対する批判を行う思想だったのではないでしょうか。同時代の墨家もまた、贅沢を批判する視点を持っていました。それに比べて、儒家は身分相応の贅沢な生活は当然のことである、と富貴に寛容なところがあります。
上田:陳良は当代一の儒家と孟子は評しており陳相兄弟もそこそこの儒者であり、それが弟子となるくらいであり許子も相当の学者であり、租税や市場に関する理解があったと思いますが。
小田:陳相らは、すでに陳良のような儒家の下では時代の問題解決にならない、と思っていたから、すんなりと許子に従ったのではないでしょうか。この時代の儒家は堯舜とか文王とか大時代的な理想を述べるばかりで、社会の現実が見えていなかったのではないでしょうか。陳相兄弟はすでに師の下にいた頃から儒家の限界を感じており、だからあっさり儒家を捨てたのではないでしょうか。おそらく、この時代に儒家から脱落したのは彼らばかりでなく、後を絶たなかったことでしょう。儒家は、滅亡の危機にあったことでしょう。そんな中で儒家の親玉である孟子としては、自軍を守るために「君たちの言うことにも一理はある」などとは口が裂けても言うことができなかった。敵を認めればそこで負けであり、儒家は衰退崩壊する。だから、できることは声を張り上げて敵を全否定して罵ることであり、全力を持って叩き潰すことに拳を振り上げた。それが、孟子だったのでしょう。
上田:布は俸給でもあり貨幣の役割も果したもので、どの布も一緒とすれば交換が成立しなくなる。そういうレベルまで許子がブチ壊すようなことをしたとは思えない。
小田:許子の主張は、『孟子』に書かれていることを通じるしかなく、孟子は歪めて載せているはずです。許子の本当の主張は、知る由もない。墨家はテキストを残していますので、儒家による墨家の批判と墨家による儒家の批判の双方を比較すれば、意見の相違を見て取ることができます。意地悪な視点を取るならば、孟子が文公を落とした滕国は、儒家の弟子たちにとって小さいながらも確保された就職先である。儒家が開拓したこのテリトリーに、許子が割って入り、陳相のような裏切り者も現れた。孟子にすれば、こちらが開拓した就職先を守るために、後からやってきた許子を追い払うことに努力したという点もあったのでしょうね。孟子は宋にも行っていますが、これもまた儒家の就職先の開拓が主要な目的のひとつであったのではないでしょうか。もっとも、孟子死後において儒家の得意先は、相変わらず斉でありました。後世の荀子は、斉の稷下を拠点としました。荀子は荀子で、趙に行ったり秦に行ったりして、儒家のための新規開拓先を物色したところです。
上田:許子は文化大革命の毛沢東みたいな話に聞こえる。なんでも自給せよ、農村で自ら鉄を作り、粗雑な鉄で役に立たず、自給もならず、結局経済はガタガタになった。
小田:毛沢東はゲリラ時代には英雄でしたが、統治者時代には災厄でした。彼はそのキャリアにおいて、どうも農村の実情によく理解が及ばなかったようです。なので、農業を実際にやった経験があれば荒唐無稽であることが分かりそうな無謀な増産計画を立てて、国家の頂点にいる彼の主張に誰も疑問を差し挟むことができず、実行に移された。結果は大飢饉による大量死でした。しかしながら許子は、少なくとも農村を知った上で思想を立てたのではないでしょうかね。彼の思想は、たぶん安藤昌益のようなものではなかったかと思います。
上田:許子のことは分からないとして、農家はどうなんですか。農家といえば、神農が思い出されますが、彼は太陽が南中する時に市を設け、物々交換をさせ、生業(なりわい)を生みだしたと称される。いわゆる分業のことで、許子がそれまで否定するとは思えない。戦国時代ともなれば、矢や矛や盾を大量に備えねばならなく食糧や物資も大量に備蓄しなければならない、許子や孟子では対応ができない。法家などはどうみてましたか。
小田:農家の主張は、なにぶん文献が足らずよく分かりません。法家であるならば、『韓非子』では儒家と墨家を当世流行の邪説であると批判しています。『韓非子』のテキストは韓非子が書いたのでなければ前漢代の法家が書いたと思われます。この頃に勢いがあったのが、儒家と墨家であったわけです。当時の為政者たちが採用した思想を見れば、当時流行の思想が分かります。秦の始皇帝は、ご存知のとおり法家に依拠しました。それを継いだ漢の劉邦は個人的には儒家を好まなかったが、宮廷儀式のために儒家を採用しました。次の文帝は黄老思想を好み、次の景帝は法刑を好み、次の武帝に至って儒家を国教としました。儒家・道家・法家が、秦漢代に勢いのあった統治思想でありました。文帝の時代は、秦末漢初の動乱の結果人口が激減し、国が疲弊していました。この時代に最もふさわしい統治術として、法を厳格に適用せず、民のなすがままに任せて民力回復を待つという黄老思想が採用されました。時代が下って国力が回復したならば、法による国家統制が強化されました。この時代には、法家が前面に出ました。儒家はといえば、法家は道徳はさておいて法術で統治する立場でしたが、儒家は道徳と法術の二本立てで統治する立場でした。道徳面の統治術としては徳行ある者を官吏に採用し、村落の年長者に爵位を与えて権威を持たせたりする政策が進められました。かといって、法が漢代にないがしろにされたわけではなく、秦律を受け継いだ漢律は酷刑をいくぶん緩和されながらも、引き続き適用されていました。儒家の統治術は法刑を否定するわけではなく、法刑による統制と道徳による統制を併用するところにありました。
上田:平成の日本は巨額の財政赤字をかかえている。そうなるとこれをどう解決するのかという議論が起こる。古代の議論からヒントを得るべき。
小田:古代の経済と現代の経済は、思想と違って同列に論じることはできないと思いますが、、、財政議論は、古くからありました。漢の武帝の時代、匈奴等と対外戦争を大いに行い、それにより国家財政が危うくなりました。財政再建のために、塩と鉄の専売に関する議論が起こりました。その議論が『塩鉄論』として現代に残されていて、古代の財政議論として貴重な文献です。当時の学者たちはすでに皆儒家なのですが、その中でも法家的な傾向を持った論者とそれに反対する論者に分かれていました。一方は、財政を補填するために専売はやむを得ないと論じました。他方は、専売により高い商品を買わせることは人民への圧迫であり、為政者としてなすべきでない、と論じました。結局専売論者の策が採用されて、一時的に国家財政を救ったわけですが。塩と鉄の専売は、歴代王朝にも人気がある税収アップ策となりました。ただ現代経済においては、ケインズ主義的総需要管理政策、サプライサイド政策、貿易政策を組み合わせた結果として財政再建を論じなければならず、単に増税すれば事足りるというわけではありません。
上田:現代でも油田がみつかったということで国が豊かになる。
小田:非工業国家ならば、天然資源で財政が潤うということはあるでしょう。秦が強大になった原因の一つには、蜀を征服して特産品の鉄と塩を手に入れたことがありました。蜀の塩井は、後世まで有名です。劉備や諸葛公明が蜀で建国し、まがりなりにもしばらく国が保ったのは、蜀の資源が強みとしてあったゆえでした。だが戦国時代から漢代にかけては、灌漑の開削による新田増加により農地と人口を増やして税収アップにつなげる策が、より大規模に各国で取られました。漢代は初期には処女地が余っていたので農地を増やすことができましたが、末期になると頭打ちとなって税源に苦しむようになりました。人口の増減が財政の基礎にある、という議論であるならば、現代でも形を変えて通じるところがあります。
上田: 今日はそんなところですか。
2013年8月31日(土)孟子滕文公章句
本日は、小田さん、上田さんの二人。本日分を音読。訓読と意味は小田さん。
墨者夷之(いし)、徐辟(じょへき)に因りて孟子を見んことを求む。孟子曰く、吾固(もと)より見ることを願ふ。今吾尚ほ病めり。病愈へば、我且(まさ)に往きて見んとす。夷子は來らざれ。他日又孟子を見んことを求む。孟子曰く、吾今は則ち以て見る可し。直(ただし)からずんば則ち道見(あらは)れず。我且つ之を直ふせん。吾聞く、夷子は墨者と。墨が喪を治むること、薄きを以て其の道とす。夷子以て天下を易へんことを思ふ。豈に以て是に非ずとして貴びざらんや。然れども夷子其の親を葬(は)ふること厚きは、則ち是れ賤しむ所を以て親に事ふ。徐子以て夷子に告ぐ。夷子が曰く、儒者の道、古の人赤子を保んずるが若しと。此の言(こと)何と謂ふことぞ。之は則ち以爲(おも)へらく、愛に差等無し。施すこと親より始む。徐子以て孟子に告ぐ。孟子曰く、夫の夷子信(まこと)に以爲へらく、人の其の兄の子を親(しん)すること、其の鄰の赤子を親するが若しとするか。彼取る有りて爾(しか)る。赤子匍匐(ほふく)して將に井に入らんとす、赤子の罪に非ず。且つ天の物を生(な)す、之をして本を一つにせしむ。而して夷子は本を二つにするが故なり。蓋し上世嘗て其の親を葬らざる者有り。其の親死すれば、則ち舉げて之を壑(たに)に委(す)つ。他日之を過(よぎ)る。狐狸之を食らひ、蠅蚋姑(ようぜいこ)之を?(く)らふ。其の?(ひたい)泚(せい)たること有り、睨(にらみ)て視ず。夫の泚たること、人の爲に泚たるに非ず。中心より面目に達す。蓋し歸りて??(るいり)を反(こぼ)して之を掩ふ。之を掩ふこと誠に是ならば、則ち孝子仁人の其の親を掩ふこと、亦必ず道有り。徐子以て夷子に告ぐ。夷子憮然として爲閒(しばらくあり)て曰く、之を命(をし)ふ。
墨者の夷之は、徐辟を通じて孟子と会見しようとした。孟子が言った、「私はかねてから会いたいとと思っていた。だが、今私は病気がまだ治っていない。病気が治れば、こちらから出かけて会いたい。夷子が来ることはない」と。後日、また(夷之が)孟子に会う事を求めた。孟子が言った、「今なら会見できる。思想が正しくなければ、道が現れることはない。私が、彼に正しい道を教えてやろう。私が聞くところでは、夷子は墨者である。墨家の喪礼は、薄葬を道としている。(つまりは)夷子は薄葬で天下を変えようと望んでいるということだ。どうして薄葬が間違っていると思いながら、それを貴ぶことがあろうか?(薄葬が正しいと信じているのだから、彼はそれを貴んでいるのであろう?)だのに、夷子は自分の親を厚く葬った。これは、墨家として賤しむべき方法で親に仕えたのではないか?」と。徐子はそのことを夷子に告げた。夷子が言った、「儒家の道では、『いにしえの人は(人民全体を)赤子を保んずるように取り扱った』という。これはどういうことかというと、私が思うに、愛には差別が無いということである。ただ、私は施すことを親から始めたまでである」と。徐子はそのことを孟子に告げた。孟子が言った、「かの夷子は、本当に『人が自分の兄の子をいつくしむことは、自分の鄰家の赤子をいつくしむことと等しい』と思っているのであろうか?(『いにしえの人は(人民全体を)赤子を保んずるように取り扱った』といにしえの人が考えたのは、)しかるべき理由があるから、そう考えたのである。赤子がはいはいして井戸に落ちようとするのは、赤子の罪ではない。(いにしえの人は無知な人民を赤子のように慎重に取り扱った。この言葉は、そういう意味にすぎないのだ。)かつ、天が物を生ずるにあたり、万物それぞれにおいて本源を一つに定めた。なのに、夷子は本源を二つにしている。思うに太古にあっては、自分の親を葬らない者がいた。自分の親が死ぬと、持ち上げて谷底に捨てた。後日そこを通り過ぎると、狐狸が死体を食べ、はえやぶよが死体をしゃぶっていた。それを視て自分の額に汗がでてきて、直視することができなかった。そのように汗がでることは、人のために汗が出たのではない。心の中心が動いて、顔に表れたのである。だからこの者は帰って、もっこやすきで親の死体を土で覆ったのである。死体を覆うことが誠にこのように心中から湧き出た情のなせるわざであるならば、孝行息子や仁人が自分の親を土で覆う事は、道にかなっていることだ」と。徐子はそのことを夷子に告げた。夷子はしょげかえって、しばらくしてから言った、「よくぞ教えてくださいました」と。
上田:「豈に以て是に非ずとして貴びざらんや」とはどういうことですか。
小田:どうして薄葬が正しくないと思いながら、尊重しないことがあろうか。つまり、薄葬が正しいと思っているから、それを尊んでいるのであろう。なのに、親を厚く葬ったのはどういうわけか、と言っているのです。
上田:「之をして本を一つにせしむ。而して夷子は本を二つにする」とはどういうことですか。
小田:根源にあることは一つであり、それを夷子は二つにしていると言うのです。すべての人間が等しく大事である、という一つの根源があり、であるのに親を厚く葬ったという行動を起こさせた根源がもう一つある。夷子はダブルスタンダードなのではないか、と孟子は批判した。夷子は、いやダブルスタンダードではなくて、単に身近な親から始めただけだ、と言い訳をしたということでしょう。
上田:小林先生の見解はそれとは違いますね。
小田:ああ、そのようですね。こちらのほうが具体的で、より本来の考えに近いのかな。孟子は人間の根源は父母であり、ひとつしかないのが天の道であると言う。しかし、夷子によれば自分の父母が二つも、三つもあることになる。それを批判したと。
上田:孟子が本を一とし、夷子がそれを二つにするという批判はピンとこない。
小田:これは、墨家を批判したのです。ここで、墨家の教えに忠実でなかった夷子を取り上げた。墨家の思想に忠実であるならば、自分の親も赤の他人も等しく薄葬しなければならない。なのに夷子は自分の親を厚く葬った。孟子はそのダブルスタンダードを突いて、彼を動揺させようとしたのです。
上田:それだけのことなんですかね。
小田:それだけでしょう。夷子は墨家でありながら、儒家の主張に理解を示し、ついに儒家に屈服した。まれにみる儒家の大勝利のケースであり、だから勝利の記録として大書して取り上げたのです。敵をこき下ろすためには、わずか一人の転向であってもデカデカと取り上げて、敵の致命的敗北のように宣伝する。
上田:つまらない話ですね。
小田:葬礼は厚くするにも薄くするにも、それぞれ理由を言うことができます。この問題に絶対正義などはないでしょう。墨家は孟子の時代以降も相変わらず隆盛であり、半世紀後の荀子も目の敵にして攻撃しています。墨家が孟子の時代に論破されて衰えた証拠は、ありません。孟子は、墨家でありながら儒家に転んだ例外のケースを取り上げて、宣伝したのです。夷子は墨家でありながら、親への人情があったのでしょうね。
上田:親と他人は違うということですが、産みの親と育ての親とか、貸し腹とか親と他人とは簡単には分けられない。
小田:孟子は、墨家の兼愛説を攻撃しているのです。墨家はすべて間違っていると攻撃することが、儒家である孟子の立場でした。親と隣の人を同列に取り扱うことを、間違いであると主張しました。
上田:それを根本が一つを墨家が根本を二つに分けると批判するのはピンとこない。
小田:孟子は儒家として、古来の中国社会の原則である祖先尊重の孝の原理を絶対正義として、親の厚葬を天の道として正当化しました。しかしながら、これは人類普遍の原理であるかといえば、とんでもない。インドには、墓はありません。死んだらカルマが転生して、次の生を受けることになります。死んだ親は今頃どこかで赤子として生まれ変わっているかもしれず、あるいは犬かミジンコにでも転生しているかもしれない。ここから殺生を禁じるインド思想が生まれるのであり、同時に死体を尊んで子孫が礼拝することはありません。またゾロアスター教では、鳥葬が行われます。死体は山に捨て、鳥に食わせるに任せるのです。インド以西の思想においては、死体と魂は別物であって、死体は物質にすぎないと考えるものが見られます。だが中国では、肉体と魂は一体であり、手厚く葬ります。儒家は財産を傾けてでも葬礼や墓を立派にせよと言います。それで後世の為政者たちは、人民を搾取しても大きな墓を造る行き過ぎを行うようになり、儒教はこれを否定することができません。先祖のばかでかい墓を作る風習は日本にも影響を与えて、仏教が入る前の時代には天皇豪族が巨大な墓を造っていました。しかし仏教伝来以降は、中国でも日本でも墓は小さくなっていきました。これは、仏教の思想が影響したものと思われます。中国では、曹操の時代に薄葬令が出されました。この時期の中国は人口が激減して国力が衰え、墓を造営するために人や物資を大量動員する余裕などなく、ゆえに禁じられたのです。以降中国では、仏教に特徴されるような家族を超越した慈悲の思想と儒教に特徴されるような家族中心の孝の思想との間で、揺れ動いているように見えます。
上田:夷子は赤子を安んじると同じで親からはじめて他人を愛すとするが、親の死体と他人の死体では、他人の死体はほおっておけるが自分の親はほおっておけまいとする話を聞いて納得したということでしょうが、釈然としない話。
小田:夷子は、もとから墨家思想を信奉しきれず、動揺していたのでしょう。孟子の主張は、儒家の主張する差別愛の原理です。梁恵王章句から、一貫しています。中国の氏族中心社会の構造に適合した愛の原理を儒家は述べているわけです。いっぽう墨家の兼愛思想は、氏族中心社会を壊して血縁によらない新しい共同体を作ろうとする思想です。
上田:「直(ただし)からずんば則ち道見(あらは)れず。我且つ之を直ふせん」。正さねば、道が現れない。だから正すと述べている。
小田:夷子は正されましたが、墨家全体は正されていません。『墨子』の中では儒家が逆に攻撃され、正されています。墨家から見た儒家は無償で天下のために働く奉仕の精神に欠けており、見返りがなければ行動しない機会主義であり、身内びいきであり、利己主義であると批判されています。『墨子』だけを読めば、儒家は歪んだ思想の信奉者にすぎなくなり、『孟子』と逆転します。
上田:赤子の解釈において、孟子が、赤子を安んじるように愛せではなく、赤子は何も知らないから、これを教え導くことが為政者のなすべきことという見解は納得ができるが、それ以外は強引な決め付けでピンとこない。
小田:このあたりの章は、孟子が論敵を打ち破った武勇伝として置かれています。後世の我々から見れば両者ともに水掛け論であり、孟子が思想的に勝利したとはとても見えない。ここでは、墨家から儒家に転んだ転向者を取り上げて、鬼の首を取ったように大きく取り上げているのです。
2013年9月7日14:00~16:00 論語読書会in士心
参加者:上田、小田、桐畑孝佑、石河誉行 記録者:小田
学而篇九(読み下しは、中村愓斎に従う。)
曾子の曰く、終りを愼しみ遠きを追へば、民の德厚きに歸(おもむ)く。
《James
Leggeの英訳》
The philosopher Tsang said, "Let there be a careful
attention to perform the funeral rites to parents, and let
them be followed when long gone with the ceremonies of
sacrifice;- then the virtue of the people will resume its
proper
excellence."
(日本語訳例)
哲学者である曾子が言った、「両親の葬礼を行うことに、注意を向けさせよ。そして両親たちが亡くなって長く経ったときに、犠牲の祭りを行って彼らを追慕させよ。そうすれば、人々の徳は再び正しき素晴らしさを取り戻すであろう」と。
(英訳について)
小田:今日は、同志社文学部から石河さんが初参加いただきました。石河さんは人間の第二言語修得過程を主研究分野としてご希望である(ゼミは違う研究内容ということですが)、ということです。日本人にとっての漢文は、日本人にとっての英語とはかなり文化的位置が違います。日本語は漢文から膨大な語彙を取り入れ、かつ日本は中国思想の考え方を文化の根本レベルで摂取しています。だから、日本人にとって漢文は完全に第二言語とは言いがたい。しかしながら、日本語と漢文および中国思想の間には、微妙であるがしかし決定的な差異があると思われます。今回論語を読むに当たって、その点についてヒントを得る機会をお持ちになることができたならば、私たちとしても幸いなとろです。さて、石河さんに今訳していただきましたが、分からない点はあるでしょうか?
石河:内容が、どうもピンと来ないですね。葬式をやったら、人々が正しい道に進むというのは、現実味に乏しいように思われます。
小田:内容の吟味に進む前に、この言葉を理解するためには古代中国の葬祭礼についての知識が必要です。日本人は、親が亡くなったら葬儀を行い、四十九日や命日に皆で集まって先祖を供養しますよね。実はこれは、古代中国の葬祭礼が形を変えて入っているのです。日本の葬祭礼は仏教に基づいて行われますが、その仏教は中国文化の影響を受けたものです。古代中国では、両親が亡くなったら子が葬儀を行いました。そして、年が経った後には、両親の霊を祀るための祭礼を定期的に行いました。この祭礼においては、牛・豚・羊を犠牲として殺し、その血と首を霊前に捧げました。だからレッグの訳においては、"
with the ceremonies of
sacrifice"が本文にない補足的説明として追加されているのです。仏教化された日本の命日では豚を殺したりしませんが、今でも中国とか韓国では先祖の祭りにおいて殺した肉を霊前に捧げる風習が受け継がれています。
(討論)
石河:ここの言葉は、生と死を区切らず、親を親として常に大事にしなければならない、という曾子のひたむきな思いが表れているように思えます。私は去年祖母が亡くなって四十九日に出席したとき、祖母や、あるいは自分の祖先たちのことをどれだけ大事に祭ることができているのか、と疑問に思うことがありました。
上田:曾子がこのように言っているのは、当時の人々が実際には祖先を手厚く祭っていなかったという現実があったからです。自分の親や祖先を祭らずして、民の徳をとりもどすなど議論してもはじまらないと反省を促したのでしょう。
桐畑:なるほど、それで"resume"の意味が分かりました。今の時代には存在していないから、取り戻すのだと。
上田:父や先祖とのつながりを自覚することによって、その末裔であるという自己の大切さが身にしみるようになる。親や先祖を手厚く祭ることは、血のつながりの先にある自分という存在を大事にする、ということにもつながるのです。
小田:石河さんも言われるように、今の日本は自分は自分で完結していて親や祖先とはつながりがない、という考えが広がりすぎています。これは極端でありますが、もともと日本人は中国人ほど祖先からの系譜を大事にしない文化でした。中国人になると、それこそ数千年前の祖先からつながる一族の自覚を持ちます。日本人は、たいていの人は曽祖父母ぐらいになると名前すらよく知らない人のほうが多いと思います。この日本人の血統意識の希薄さは、一方では上田さんの言われるような血のつながりの中の自分の大事さという自覚を持ちにくくして、人間を孤立させる面があります。しかしながら、他方で家や一族のしがらみから解放されて行動できるという身軽さの面もあります。中国では、「九世の仇を討つ」という言葉があります。自分の九代前の遠い祖先が受けた屈辱は、九代後の子孫ですら必ず晴らさなければならない、という意味です。これは過去の人間に現在の人間が縛られ、一族の掟に個人が縛られるという、血統社会の悪い側面を表しています。結局、その中間ぐらいが程よいのでしょう。
では、次にいきましょう。
石河さん、続いてお願いします。
学而篇十(読み下しは、中村愓斎に従う。)
子禽、子貢に問ふて曰く、夫子是の邦に至れるときに、必ず其の政(まつりごと)を聞く。之を求むるか、抑(そもそも)之を與(あた)ふるか。子貢の曰く、夫子温良恭儉讓以て之を得(う)。夫子の之を求むるは其諸(それ)人の之を求むるに異るか。
小田:石河さんは、通常に読み下しができますね。お上手です。「與」の字は、新字体では「与」です。「與」の字をよく見ると、真ん中に「与」が見えますよね?戦前は、日本でもこの旧字体を使っていました。しかし戦後改革で難しい漢字は学習のさまたげになると簡単な新字体に改められました。その結果が「与」の字です。大陸中国でも共産党政権が簡体字を採用しましたが、日本と調整することなく別個に行われました。その結果、日本の新字体と中国の簡体字はまるで互換性がありません。(「与」の字に限っては、たまたま簡体字でもこの字が採用されています。)しかしながら台湾や香港などでは今でも旧字体(繁体字)が用いられていて、かの地で「与」の字は見当たりませんが「與」の字は通用します。(後記:読書会ではシンガポールもそうだ、と発言しましたが、これは誤解のようです。台湾と香港は小田が2000年代に実際に行ったことがあるので、間違いないと言うことができます。)旧字体のままの漢文を学ぶ効能といっては何ですが、旧字体を書けなくても読めるようになれば、旧字体を採用している諸国の新聞やテレビを理解することの助けになります、
《James
Leggeの英訳》
①Tsze-ki'in
asked Tsze-kung, saying, "When our Master comes to any
country, he does not fail to learn all about its government.
Does he ask his information? Or is it given to
him?"
②Tsze-kung
said, "Our Master is benign, upright, courteous, temperate,
and complaisant, and thus he gets his information. The
Master's mode of asking information! -Is it not different
form that of other
men?"
(日本語訳例)
①子禽が子貢にこのように質問した、「我らの夫子はどの国に赴いても、必ずその政府について学び取ります。夫子は、自ら情報を問い合わせているのでしょうか?それとも、情報が夫子に与えられているのでしょうか?」②子貢が答えた、「我らの夫子は、温和で、正直で、礼儀正しく、控えめで、しかも従順である。夫子の情報を問い合わせるやり方は、他の人のやり方と違わないのであろうか?」
(討論)
小田:この章は、困った章です。何を言いたいのか、定説がありません。子貢というのは孔子の弟子で、切れ者で有名です。子禽には二説あって、孔子の弟子という説と、子貢の弟子という説があります。そして、この章の問答を理解するためには、孔子の時代と彼の行跡をざっと知っておく必要があります。孔子は、現在の山東省西部に当たる魯の出身であり、低い身分から学問で評価を高め、魯で法務大臣にまで昇りました。彼はそこで落ち目の祖国を立て直すために政治改革を試みましたが、短期間で反対勢力に阻止されて失脚しました。通常ならばこれで引退して学問に専念するところですが、彼はそうしなかった。当時の中国は斉、燕、晋、楚など大小多くの国に分かれていました。中国大陸はヨーロッパほどの大きさがあるので、小国に分かれていてもおかしくありませんでした。孔子は弟子と共に魯を去って、自分の理想とした政治を諸国に売り込む旅に出ました。そうして、多くの国を長年かけて回り、ついにどこからも相手にされず、晩年になって魯に戻り、ようやく学問と弟子の育成に専念するようになって生涯を終えました。この章の問答は、孔子が弟子と共に長年多くの諸国を回ったという事実が前提となっています。孔子は、どの国を訪問してもいつのまにか各国の重要な情報を得ていた。国の世継ぎを誰にするかで宮中が割れたお家騒動のこととか、本来は国家機密であるべき事態についても、孔子は情報を得て自分の進退を的確に判断したように思われるエピソードが、論語の中には他にもあります。どうやって、これを得たのであろうか?
桐畑:孔子は温和であったから情報収集ができた、ということですが、温和であれば必然的に情報を得ることができたというのは、疑問に思います。孔子の情報収集力の高さは、他に原因があったのではないですか。
上田:子貢は切れ者で、彼ならば賄賂を使ってでも情報収集をしたことでしょう。子禽は何か特別なことをしたのではないかと思った。しかし孔子は何も特別なことをしないのに情報を得た。西欧人は譲の概念が理解しづらく、レッグは"complaisant"つまり相手が喜んで言いたくなるように接して情報を得ることができた、と捉えている。
石河:おのずから情報を言いたくなるような人徳があったのでしょうか。
上田:孔子は注意力が高い人間であり、周辺情報から勘を働かせて本質を突き、相手も実はと意見を求めたのかもしれません。
小田:ちょっと斜に構えた解釈をすると、実際は子貢が賄賂とかスパイ活動とかの汚れた手段を使って国家情報を収集して、先生に伝えていたのかもしれません。しかし他の弟子たちには、そのような汚れ仕事の真相を言わなかった。それで子貢は、「孔子は温和だから情報が集まってくるんじゃないの?」とか言って誤魔化したのが、この章の真相なのかもしれません。ま、これは邪推です。
石河:この章が論語に入っているからには、何か教訓があったということですね?
小田:そのはずです。論語は、孔子の死後に孔子と直弟子たちの重要な言葉を集めて編集し、後世の弟子たちが暗誦するために作られたテキストです。当然ながら、後世の弟子たちが行動指針とするべき内容が、ここに集められていたはずです。教訓であるならば、孔子が温和で従順であったことが情報を集める理由となった、だから人の上に立つためには温和で従順でありなさい、という行動指針を薦めたものでしょう。孔子は政治家としては大した実績を残しませんでしたが、教育者としては優秀な弟子を多数集めて従わせることに成功しました。孔子の弟子にはこの子貢のような頭の切れる者がいたり、あるいは武人であったのが孔子に魅せられて弟子となった者がいたり、あるいは出世主義者で出世したいから孔子の弟子になった者がいたり、またあるいは顔回のように特に取りえはないが人徳だけは優れていた者がいたり、多種多様な能力を持った弟子たちを纏め上げていた手腕がありました。リーダーとして、優れていました。孔子のリーダー像は、三国志の劉備とか日本の徳川家康とかに見られるような、自分は静的で動かず、周囲に有能な部下を集めて組織で実績を挙げるタイプでしょう。こういったリーダー像は東洋では好まれますが、西洋ではナポレオンとかアメリカ大統領のように、自らの卓越した能力とビジョンにより率先して動き、部下をリードしていく動的なリーダー像が圧倒的に好まれます。日本ならば、織田信長タイプですね。皆さんは、どちらのタイプを理想としますか?
石河:私は、吉野山活性化プロジェクトのリーダーをやっています。チームで子供たちを教える仕事なのですが、私じしんよりも周囲の人々がよく動いてくれます。そのまとめ役としての自分から言えば、自分は家康型のリーダーに近いのであろうと思いますし、そちらのタイプにより親近感を持ちます。
桐畑:私は、両者の中間でしょうか。結構、自分で仕事をやっちゃいます。
石河:今の中国では、どちらのタイプが好まれるのでしょうか?多民族国家であり、リーダーシップが必要だと思うのですが?
小田:毛沢東は、孔子タイプではありませんね。一般的に言わせていただければ、太平の世ならば孔子タイプが好まれるでしょう。乱世であれば、もっとアクティブなタイプでなければいけないでしょう。今の中国人が、現在を太平であるか、乱世であるか、どちらであるのかという自己イメージによるのではないか、と思います。
上田:この章の最後の疑問は、結局どちらなのでしょうか。孔子のやり方は、人と違うのであろうか、それとも同じなのであろうか。レッグ訳は、明らかに同じだと取っています。
石河:やり方は他人と同じであっても、それでうまく情報収集ができるのであれば、結果的には違っているのではないでしょうか。普通は温和では情報収集できない。
桐畑:やり方が同じだったら、結果は同じになるはずです。孔子は、レベルが違うのでしょう。温良恭儉讓で情報収集できたと言いますが、一般人はこれで成功できない。テクニックが違うのであれば、これは一般的な教えとは言えないはずです。
小田:孔子は、「聖人」とみなされます。この「聖人」は、しかしキリスト教の「聖人」と違います。キリスト教の「聖人」は、神から超自然的な恩寵を受けて超自然的な業績を成し遂げた人間であって、普通の人間から断絶しています。しかし孔子が「聖人」と呼ばれるゆえんは、人間ならば本来誰でも見に付けることができるはずの徳を、その極限まで実現した人間として「聖人」なのです。普通の人間は潜在力を誰でも持っているにも関わらず、怠惰や欲望が邪魔をして「聖人」になれない。あくまでも孔子はただの人間であり、「聖人」と普通の人間は連続していると考えます。だから、孔子が情報を収集できた秘密は彼が超人だからなのではなく、人間の当たり前の能力を完璧に使いこなした結果なのだ、と捉えているはずです。
石河:中国には、西洋の神のような考えはなかったのでしょうか。中国思想は、神なしで述べられているのではないでしょうか。
小田:「天命」という言葉が中国思想にはあります。人間の寿命とか逆境とか、人間の努力ではどうにもならない領域の運命について、これは「天命」である、と考えます。なので、人間を越えた力としての「天」は、中国思想でも想定されています。しかしながら聖書やコーランの神が人間に詳細な掟を命令する、もの言う人格神であるのに対して、中国思想の「天」は、人間に具体的な命令の言葉を下したりはしません。あくまで人間の側から、ばくぜんと予感するまでです。中国思想は、西洋思想よりも人間世界の善悪で完結させる要素が強くあります。
では、次にいきましょう。
次は桐畑さんにお願いします。
学而篇十一(読み下しは、中村愓斎に従う。)
子の曰はく、父在(いま)すときは其の志を觀、父沒(おは)るときは其の行を觀る。三年父の道を改むること無きを孝と謂ふ可し。
《James
Leggeの英訳》
The
Master said, "While a man's father is alive, look at the
bent of his will; when his father is dead, look at his
conduct. If for three years he does not alter from the way
of his father, he may be called filial."
(日本語訳例)
孔子が言った、「人たるもの父親が生存中は、親の意向を見習え。父親の死後は、親の行跡を見習え。もし(死後)三年間父親の道から外れなかったら、その人は親孝行者であると言ってよいだろう。」
(討論)
上田:中村愓斎は、レッグとは違う解釈をしています。
小田:そうですね。「父います時は、子たる者、心のままに事を行ふことを得ず、されど其志のむかふ所につきてみれば、其善悪しるるなり、父をはりて後は、子の行実、明にみゆるなり。」つまり、父親が生存中は、子は父親の意向に絶対服従であり、心のままに行動できない。だから、この時期には子が父に従って悪事を行わざるをえなかったとしても、それでその子の善悪を知ることはできず、本心はどう思っているかで善悪を見なければならない。だが父親の死後は子の判断で行動できるのだから、その行為はそのままその人の善悪であると。そして三年父の道を変えない、というのは父の道が善事であるならば三年のみならずそれ以降も変える必要はなく、だが父の道が悪事であるならば本当はすぐにでも改めなければならないが亡き父を尊重して三年ぐらいは待てという解釈を取っています。中村?斎は江戸時代の人であり、この時代には家長である父親の意向は家の中で絶対であった、という事情があったこと、そして父親といえども悪事の人生を行った人であれば見習う必要などないではないか、という他方で開けた時代の倫理観があって、父親の道に死後も絶対服従せよという読み方を取らせなかったというべきでしょう。
上田:三年間父の道を変えない、という考えは現代人にはついていけない。儒家は、三年の喪を言う。つまり親の死後三年間は、ひたすら何もしない。子は三歳になるまで親の完全な庇護の下にあるのだから、その恩を感じて死後三年間ぐらいは悲しくて悲しくて何もすることができないはずだ、そうに違いない、というのが根拠である。それで孔子は三年の喪を当然とみなした。弟子の子貢などは、親でなく師の孔子が死んだ後、三年に三年を加えて六年間の喪に服した。働き盛りの年に三年も何もしない、というのはしかし現代人にはピンと来ないことです。この章の言う三年は、孔子の薦める三年の喪と抱き合わせで考えられています。
桐畑:本当に、三年の喪を皆がやっていたのでしょうか?
上田:孔子の弟子ですら、もっと短くするべきだという意見を孔子にした者がありました。
小田:漢代になって、さすがに三年の喪は三日に短縮されました。(後記:勉強会では三月と言ったと思いますが、誤りです。)匈奴と戦争状態で、内外に問題が山積みである時代に三年も皇帝が何もしないなどというのは、許されるわけありませんね。もし三年の喪という制度が本当にはるかな古代にあったとすれば、素朴で悠長な時代だったからできたというべきでしょう。
桐畑:この章の孔子の言葉は、より古代の実情に則した発言だったのではないでしょうか。たとえ親が間違っていても、従わなければならないという掟が古代には必要であったのではないか。秩序が乱れていたから、親の言うことを聞かなければならないという掟を制定して、秩序を作ろうとしたのではないでしょうか。
小田:儒教が薦める孝の倫理は、ただの倫理ではなくて童子に法秩序的意義と経済政策的意義がありました。法秩序的意義は、おっしゃるように家の秩序を守るために法律で親孝行の義務を固定化したことです。経済政策的意義は、年老いた親を子供が養う義務を課して家庭内で高齢者介護を行わせたことです。国家が保護するのは孤児や子のない高齢者に限られ、それ以外は家庭内で面倒を見るのが、昔の社会の原則でした。今でも自民党とかはこちらの方が福祉国家よりも好ましいというスタンスを取っていますがね。
桐畑:孔子は法務大臣であったということですが、法秩序の重要性も理解していたのではないでしょうか。単にお説教だけで社会が治まると考えていたとは、ちょっと思えませんが。
小田:孔子の後継者には、二派がありました。一つが孟子の学派であり、もう一つが荀子の学派です。孟子の学派は、統治者が正しい心を持てば社会はよく治まる、だから統治者はひたすら人格を高めよ、という考えに立ちました。荀子の学派は、統治者がなすべきことは理にかなった法律を立案して社会に当てはめることだ、という考えに立ちました。この両者は並存して重視されていたのですが、宋代になって荀子の説は邪説であるとして排斥され、孟子の説だけが孔子の正しい教えの解説であるとみなされてしまいました。以降の儒教においては、自分が正しくあれば周囲の人間が正しくなり、周囲の人間が正しくなれば社会が正しくなり、国家も世界も、さらに宇宙の気象すら正しくなるという楽観的な主観的倫理が主流になりました。かつての時代のように法律の側面にも目を向けていた儒教から、この面では後退したともいえます。しかし孔子その人においては、彼はそもそも学派の創始者であって、孟子的な考えも荀子的な考えも共に持っていたはずだ、と私は思います。だからこそ孟子も荀子も自分の説こそが孔子の正しい考えなのだ、と主張したはずです。荀子の弟子からは、韓非子と李斯が出ました。李斯は秦始皇帝の丞相(首相)になって、始皇帝の政策をもっぱら立案した人物です。韓非子も李斯も法家であり、荀子の儒家の発展として法家があったことは、見逃すべきではありません。
桐畑:環境問題にしても、個人が正しくあることが普及すれば自ずから問題は解決するはずだという考えと、政府が法律を作って強制しなければ解決しないという考えがあります。私の親は生活保護関係について仕事上よく関わっているのですが、生活保護申請はちょっとでも欠格要因があると申請は受理されません。それで申請者のところに調査に行くのですが、たいていは怒鳴られて追い返されるそうです。情として救ってあげたいと思ったとしても、それを認めてしまえば誰もかれもが生活保護を受給することになって財政が破綻する。一人一人の個人の行いだけではどうにもならず、社会全体のために法で調整しなければならないこともあります。
小田:私も、もと役人でしたから言われることはよく分かります。役人は、個人の判断で法を曲げて市民に恩恵を与えてはならない。それをしてよいのは、大局的な判断を行う政治家だけだ。これが原則でしたね。そろそろ時間となりましたが、初参加の石河さん、ご感想はいかがでしたか?
石河:自分の拠って立つ思想文化の根源は何だろうか、この社会でのリーダーのあり方は何だろうか、と問うときに自国の思想を理解しなければならないと考えています。日本は儒教の国であり、文化の根幹にある考え方の理解を、今後より進めたいと思うところです。
2013年9月21日(土)孟子滕文公章句
本日は、小田さん、上田さんの二人。本日分を音読。訓読と意味は小田さん。
陳代が曰く、諸侯を見ざるは、宜しく小きなるが若く然るべし。今一たび之に見るは、大きなるは則ち以て王たらん。小きなるは則ち以て霸たらん。且つ志に曰く、尺を枉げて尋を直(の)ぶと。宜しく為す可きが若くなるなり。孟子の曰く、昔齊の景公田(かり)す。虞人を招くに旌を以てす。至らず。將に之を殺さんとす。志士は溝壑に在るを忘れず、勇士は其の元(かうべ)を喪ふことを忘れず。孔子奚(なに)をか取れる。其の招きに非ざれば往かざるを取れり。如し其の招くを待たずして往くは、何ぞや。且つ夫れ尺を枉げて尋を直ぶことは、利を以て言ふ。如し利を以てせば、則ち尋を枉げ尺を直べて利なるは、亦す可けんか。昔者(むかし)趙簡子王良をして嬖奚(へいけい)と乘らしむ。終日にして一禽を獲ず。嬖奚反命して曰く、天下の賤工なり。或ひと以て王良に告ぐ。良が曰く、請ふ、之を復(また)せん。彊(し)ひて後に可(き)く。一朝にして十禽を獲たり。嬖奚反命して曰く、天下の良工なり。簡子が曰く、我女(なんぢ)と乘ることを掌らしめん。王良に謂ふ。良可(き)かずして、曰く、吾之が爲に範して我馳驅(ちく)すれば、終日に一を獲ず。之が爲に詭遇(きぐう)すれば、一朝にして十を獲たり。詩に云く、其の馳(は)することを失はず、矢を舍(はな)つて破が如し。我小人と乘ることを貫(ならは)ず。請ふ、辭せん。御者且つ射者と比することを羞ず。比して禽獸を得ること、丘陵の若しと雖もせず。如し道を枉げて彼に從わば、何ぞや。且つ子過てり。己を枉ぐる者は未だ能く人を直する者有らず。
弟子の陳代が言った、「先生が諸侯に謁見されないのは、度量が小さいように思われます。一度諸侯に会われれば、大きな諸侯は天下の王になり、小さな諸侯でも天下の覇者となるでしょう。また、古文献にこう言います、『一尺を曲げて一尋(八尺)を正しくする』と。どうかこのようにしてください」と。孟子が言った、「昔、齊の景公が狩りをした。虞人(狩り場の管理人)を旌の旗で招こうとしたが、来なかったので、この虞人を誅殺しようとした。(孔子は言われた、)『志士はいつも溝の中に落ちていることを忘れず、勇士は自分の首がいつでも無くなることを忘れない』と。孔子は虞人について、どこを褒めたのであろうか。それは、礼にかなった招き方でないと行かなかったことを褒めたのである。もし招かれないのに行ったならば、許されることであろうか?そのうえ、そもそも一尺を曲げて一尋を真直ぐにするというのは、利によって言っていることだ。もし利によって行うのであれば、一尋を曲げて一尺を真直ぐにすることに利があったとするならば、それをするべきであろうか?(してはいけないだろう。)昔、晋の趙簡子が御者の王良に対して、嬖奚という家臣と同乗させた。嬖奚は、終日にして鳥一羽すら獲れなかった。嬖奚は復命して言った、『王良は天下一の下手くその御者です』と。ある人が、そのことを王良に告げた。王良が言った、『どうかもう一度やらせて下さい』と。強く要請して、その後にようやく聴き届けられた。嬖奚は、一朝で鳥十羽を獲ることができた。嬖奚は復命して言った、『王良は天下一の良い御者です』と。趙簡子が言った、『私はお前を嬖奚の御者にしようと思う』と。こう王良に言うと、王良はうなずかず、こう言った、『私が彼のために規範に従って馬車を走らせると、終日に一羽も獲ませんでした。だが彼のために規範に外れた御し方をすれば、一朝で十羽を獲ました。詩にこうあります、〈馬車が正しい駆け方を失わなければ、矢を放てば的を破るように必ず当たるがごとし〉と。私は小人と乗ることに慣れていません。どうか、辞退させてください』と。御者ですら、射者におもねることを恥じる。おもねって禽獸を得ることが丘陵のように沢山であったとしても、そうはしないのだ。もし道を曲げて諸侯に従うなら、許されることであろうか?(やってはいけない。)かつまた、君は間違っている。己を曲げた者で未だかつて人を正しくすることが出来た者はいないのだ」と。
小田:「志士は溝壑に在るを忘れず、勇士は其の元(かうべ)を喪ふことを忘れず」は幕末の志士たちが愛好した言葉であり、出典はここです。だが、この章全体は、志士たちの使い方とぜんぜん違った論議をしています。それでこの章ですが、良い面をあえて申すとすれば、孟子の民主的思想といいますか、諸侯の権力に屈従しない反骨の思想の面がよく出ていると思います。虞人や王良は、身分の低い人です。それが景公や趙簡子に対して、一歩も引きません。それを孔子が褒め、孟子も褒めた。孟子は、諸侯にこちらから頭を下げては会いに行かない。向こうから正しい招き方で腰を低くして頼みに来ない限り、権力者の下にはせ参じることはない。孟子の、そのような権力におもねらない意気を示した章の一つと言えるでしょう。孟子の中に流れる、ある意味民主主義的な思想がここにも無きにしもあらずというところでしょうか。
上田:「如し利を以てせば、則ち尋を枉げ尺を直べて利なるは、亦す可けんか」とはどういうことですか。
小田:九割道を曲げて一割正しいことをしても、そこに利益があるならばやるべきか?ということです。
上田:一尺を曲げて八尺を正すが八尺を曲げて一尺を正すとは飛躍がすぎませんか。
小田:ここは、弟子の引用に対して引用を逆さまにして、レトリックで反論したところです。言いたいことは、諸侯に対して頭を下げてたまるか。こちらから少しでもおもねってゆけば、全部曲げることになるぞ。ということでしょう。後の万章章句とかでも、なんで孟子は諸侯に仕えないのか、という同様なテーマが繰り返されます。孔子は、諸侯に仕えないのはなぜか、というテーマはさほど重要ではありません。しかし、孟子はこれを繰り返し取り上げます。両者の違いです。
上田:それは時代の差ですか、性格の差ですか。
小田:論語為政篇で、「或ひと孔子に謂ひて曰く、子奚ぞ政をせざる。子の曰はく、書に孝を云へりや。惟れ孝に、兄弟に友に、政有るに施すと。是れ亦政をするなり。奚(なん)ぞ其れ政をするとせん」とあります。ここは孔子が政治をしない理由を述べたところですが、おそらく孔子晩年時代の言葉でしょう。さきほど申し上げたとおり、孟子は弟子としばしば諸侯に仕えない理由について問答をするのですが、これらの問答は孟子の遊説時代の前に行われたのか、それとも遊説時代を終えて魯で引退した後の時代の問答であるのか。どちらであるか、判断がつきません。
上田:滕文公篇にあることがその位置になりませんか。
小田:滕文公篇は、最初については確かに孟子が斉を去って宋を経由して滕にやって来た時代のエピソードです。だが、篇の全体は色々な時代からエピソードを取っています。この章については、孟子が引退した時代なのかもしれないし、梁恵王に会いに行く前の時代かもしれません。これは私の個人的な印象なのですが、私はこの章とか万章章句などの同様の章の問答は、梁恵王に遊説する前の時代に行われたのではなかったか、と思っています。まず第一に、弟子の陳代の孟子への期待の言葉は、公孫丑が斉で孟子に期待した言葉と同じ内容ものです(公孫丑章句上の冒頭)。もし孟子が各国を回って思うような結果を出せなかった後の問答であるならば、弟子がこのような期待の言葉を言うことはおかしいのではないか?という点です。第二に、孟子は弟子の言葉に対して、かたくなに反論しています。遊説時代を終えた後であればもう最晩年であり、自分も理想には遠かったが一仕事を終えた後の時期であるならば、もう少し述懐とかを交えて枯れた言い方をしたのではなかったか。しかしこの章などは、弟子に対して世に出ない理由を力一杯反論しています。これは、孟子が遊説に出馬する前、魯で儒家集団を細々と守っていた時代の問答だったんじゃないかな、と私は想像します。その時代、どんどん時代に取り残されている儒家を何とかしてくださいと、弟子たちの突き上げに孟子は会っていたのではないか。しかし、孟子はまだ当世流行りの遊説に踏み出すふんぎりがつかなかった。まだ、成功する自信がなかった。そんな時代の問答だったのかもしれません。
上田:陳代という弟子からどの時代か分からりませんか。
小田:陳代は、ここにしか出てきません。孟子の弟子は、孟子の中に出てくる以外には、おおむね他の文献でのエピソードがありません。孟子の弟子は、大した活躍もしなかった二流の人物ばかりです。むしろ、荀子の弟子の方に一流がいました。だから、弟子によって時代を類推することは難しいです。孟子はこの章では諸侯に会わない理由を述べているのですが、50代になってようやく遊説に乗り出しました。孟子の前半生は、不明です。次の章には、張儀と公孫衍が出てきます。張儀、公孫衍と蘇秦を合わせて史記張儀列伝でまとめられていて、当時を代表する縦横家たちであり、諸侯を遊説して派手な活躍をしました。だが、孟子は彼らを厳しく批判しています。彼らが、いわば孟子の言う己を曲げた連中であり、二章を合わせて読めば、孟子はいくら活躍していてもこのような遊説家を評価してはならない、正しい道でなければ遊説してはならない、と説いたという展開です。
上田:王良がおもねらない、己を曲げないは分かるが、それが「己を枉ぐる者は未だ能く人を直する者有らず」となるのは無理がある。
小田:確かに、孟子の言葉には飛躍がありますね。後世の読者には、変に見える。孟子は公孫丑章句でも常々言っていることですが、天下の原則により諸侯を説き伏せ、天下の王にさせるのが自分の役目であり、それ以外の道は取らないのだというのは彼の持論です。
上田:それなら、梁恵王篇や公孫丑篇の前に、この話を出せば読者には分かりがいい。
小田:まずは、孟子の華々しい活躍からつかみを始めなければ、書物としてはいけなかったのでしょう。活動していない時代の言い訳から、書物を始める訳にはいかないです。しかしながら後の儒家は、これを諸侯に見せて儒家の道を示したはずです。その中に、この章のように儒家は簡単に諸侯に頭を下げない、と宣言している。見せられた諸侯も、困ったことでしょう。漢代以降体制側の思想となった後の解釈者たちは、孟子に散見されるこのような反抗的な部分については、無視するしかなかった。
上田:吉田松陰先生はどうみておられますか。
小田:調べてみますが、孟子の心意気に学ぶべしということでしょう。(後注:『講孟剳記』のこの章の講義で松陰は「志士は溝壑に在るを忘れず、勇士は其の元を喪ふことを忘れず」と「己を枉ぐる者は未だ能く人を直する者有らず」の二つの言葉を取り上げて、武士のあるべき姿としてこれらの言葉への解説を行っています。松陰の講義はこの章の解説というよりは、この二つの強い言葉に賛同して一般論を展開しています。孟子がどうして諸侯に会見しないのか?という理由に踏み込んだ解説は、されていません。)
上田:陳代はまず曲げて諸侯に会って、実績をあげればいいではないかとするのを、己を曲げる者は人を正しくすることはできないとするのは、どうも無理やりの決め付けで頭がついてゆかない。
小田:後の万章章句で、伊尹と湯王の話があります。伊尹は、出馬を要請した湯王を最初は追い返します。だが王が何度も何度も頭を下げてきたので、伊尹はようやくその心意気を買って出馬しました。一旦出馬すれば、国の為に全精力を尽くしたと言います。孟子は、自分のことを現代の伊尹であると考えていたことでしょう。伊尹のように王が誠心誠意をもって招かなければ、のこのこ仕えに行ったりはしないと考えていたのでしょうね。
上田:王良という御者は相当有名な御者で星座にもなっていたと思う。王良は結局は己を曲げなかったとするが(一旦は、嬖奚に合せた)、己を曲げないが諸侯に会わないとは、合致しない。
小田:虞人は、左伝に出てくるようです。王良は御者としては本物のプロで、下手な弓使いの嬖奚でも彼に調子を合わせれば十羽を取らせることができた。孟子は、自己評価としては政治のプロであり、諸侯を王者・覇者とすることぐらい掌を返すように簡単なことだと自信があった。だが今の時代は、遊説家が諸侯に取り入って出世することが大流行している。自分も遊説に出かける前の孟子は、おもねって出世する時代の風潮に腹を立てていた時代があったのでしょう。
上田:ここを遊説前の孟子とされたことには、頷けるところがある。梁恵王篇、公孫丑篇を前提とすると、ここでの議論はちぐはぐになるし、気負いがあり、強引な論法であり、後期のものとは思い難い。
小田:ところで孔子が虞人を褒めたということですが、孟子的には低い身分でありながらも己を枉げなかった心意気を孔子が称えたのだ、という解釈を取っています。だが思いますに、もしかしたらここでの孔子の賞賛には、別の含意があったのではないか。孔子は、もしかしたら虞人の行為を法家思想的な意味で賞賛したのかもしれない。虞人は、正規の手続きによらない召集命令に対して、たとえそれが君命であっても従わなかった。狩りというものは、軍事訓練の場でもあります。軍規のマニュアルでは、召集の旗が出て初めて担当者は動く。旗が出ていないのに動くことが許されれば、軍隊統率ができなくなります。孔子は、虞人の命を張ってでも軍規に従った行為について、これを役人の鑑であると賞賛したのかもしれません。国家や組織を法秩序によって制御する法家思想から見れば、確かに虞人の行為は正解です。組織とは、たとえ内容がよくても、決裁命令系統を外れた手続きを取ることは悪です。自衛隊などは、とりわけ行動するときの手続きを重視しているはずです。孔子は法家的考えも持ち合わせていたでしょうから、虞人の行為を軍規マニュアルを遵守した役人としての正解である、という意味で賞賛したのかもしれません。だが孟子は、少なくともそのような解釈を取っていません。
上田:これが遊説前の問答と思ったきっかけは何ですか。
小田:墨子を読んでいた時に感じたものです。墨家は、儒家は利があるとみなせば動くが、そうでないと動かないと批判します。墨家はそういう計算をせず、善を見ればすぐに行動を起こす、と対比させます。墨家から見れば儒家は天下のために働く積極性がないと批判され、じっさい儒家にはそのような面が多分にあったのではないか。孟子が繰り返し出馬しない理由を弟子からの質問に対して答えているところを見ると、孟子時代の儒家にも行動に消極的な傾向があったのではないかな、と私は思いました。じっさい孟子の前半生は何をしていたか不明であり、おそらく魯で弟子たちとの狭いサークルの中で逼塞していたのではないか。それではいかんと決意し、ようやく諸侯を説得する術を身に付けて、50代から行動を起こしたのではないでしょうか。儒家の存亡の危機にやむにやまれず行動した面が、孟子にはあったのかもしれません。
2013年10月5日(土)孟子滕文公章句
本日は、小田さん、上田さんの二人。本日分を音読。訓読と意味は小田さん。
景春が曰く、公孫衍・張儀は豈誠の大丈夫ならずや。一たび怒りて諸侯懼る。安居して天下熄(や)む。孟子の曰く、是れ焉んぞ大丈夫爲ることを得んや。子未だ禮を學ばずや。丈夫の冠するや、父之に命ず。女子の嫁するや、母之に命ず。往きて之を門に送り、之を戒めて曰く、往きて女(なんじ)が家に之き、必ず敬(つつし)み必ず戒め、夫子に違ふこと無かれ。順を以て正とするは、妾婦の道なり。天下の廣居に居り、天下の正位に立ち、天下の大道を行ふ。志を得れば民と之に由り、志を得ずんば獨り其の道を行ふ。富貴も淫すること能はず、貧賤も移すこと能はず、威武も屈すること能はず。此之を大丈夫と謂ふ。
縦横家の景春が言った、「公孫衍・張儀は、実に大人物と言えるのではないか。一たび彼らが怒ると諸侯が懼れる。彼らがじっとしていると、天下が静かになる」と。孟子が言った、「彼らがなんで大人物であろうか?あなたは、まだ礼を学んだことがないのか。男児が加冠の礼を行うとき、父はその子に男児の道を命ずる。また女子が嫁ぐときには、母がその子に女子の道を命ずる。母は家から出てその子を門から送りだすときに、この子に戒めてこう言うだろう、『家を出てお前の婚家に嫁いだならば、必ず嫁ぎ先の家人を敬い、必ず身をつつしみ、嫁ぎ先の男性たちに逆らってはならない』と。従順を正しいとするのは、妾婦の道である。だが、天下という広々とした所に居て、天下の正しい位置に立ち、天下の偉大な道を行うこと、(これが大人物の道である)。大人物とは志を得れば人民と共に大道に由り、志を得なければ独りで正しい道を行う。富貴もまた彼の心を乱すことができず、貧賤も彼の心を変えることができず、威圧も武力も彼の心を曲げることができない。これこそを大人物というのだ」と。
上田:小田さんは前回の対話を孟子の遊説前のものと言われていた。そう読むと、確かに非常に話が通じ易くなる。卓見と思う。
小田:梁の恵王は、全盛時には天下の覇者を自称して飛ぶ鳥を落とす勢いでした。当然、天下から才能ある士を集めようとしていたはずです。魯の儒家集団のリーダーでもあった孟子にも、早くから誘いの話があったのではないか、と思うところです。次に出てくる周霄は魏(梁)人ですが、その招きに対して行こうとしなかった。その後、恵王は斉と秦に敗れて落ち目となりました。その頃になって、孟子は梁に行きました。次の周霄の対話とかは、私はやはり梁の恵王と会見する前の時代、孟子がまだ遊説を始める前の時代であり、かたくなに諸侯からの誘いを断っていた時期があったのではないか、と推測するわけです。その時代は、孟子の伝記において伏せられているのですが。
上田:なるほど。
小田:この章で景春は公孫衍・張儀を高く評価した。孟子は彼らを諸侯にへつらう妾婦の道と貶めた。孟子は諸侯に仕えない理由として、正しい道が行われていないからだ、と弁明しました。
上田:いわゆる大言壮語。
小田:天下に居て、正しい位に立ち、偉大な道を行うのが大丈夫であるという。大丈夫は志を得れば天下に打って出るが、今は志を得られないから一人で道を行っているのだ。これは、孟子の自画像であるようにも聞こえます。孟子はなぜ仕官しないかの理由を、これから後の章でも繰り返し取り上げます。おそらく孟子は、天下に出られなかった時期があったのでしょう。孟子の弁明は、自分の置かれた境遇を正当化しているのではないでしょうか。張儀がなぜ批判されるのかについて、前に成田さんは張儀のやり方では最終的な解決にならない、その時代は乗り切れるが究極の解決策ではない、しかし儒家は究極の解決策を提案できるのが理由であろう、と言っておられた。司馬遷もまた張儀を厳しく批判しているところです。分裂している中国をかき乱したにすぎない、と。
上田:後の人はそう言える。
小田:戦国を秦の始皇帝が統一し、劉邦が後を継いで漢の世になった時代から見れば、張儀をけなすことは簡単なことです。張儀のような権謀術数では、天下の統一を導くことはできない。それはまあそうなのですが、戦国時代の真っ只中において、まだ統一など夢物語であった時代においては、国を運営するために合従あり連衡ありの外交策を使って、一時しのぎを続けるより他はなかったというのが現実だったはずです。およそ今の時代においてすら、国の運営などというものは、一時しのぎの外交策の連続ではないか。私は一概に張儀を批判することはできないと思います。張儀みたいな政治家は、今の時代にはちょっと見当たらないですね。少し昔であるならば、ドイツのビスマルクなんかがわりかし近いでしょうか。ビスマルクは巧妙な合従連衡の外交策を用いて、30年の間ドイツを中心とした平和を保ちました。もっとも彼の引退後にはドイツの外交策は破綻して第一次世界大戦を起こして国は滅亡したわけですが。だからビスマルクの策は根本的な平和をもたらさなかったと言えば確かにそうですが、それで彼が一時代の安定をもたらした功績を軽視するのは、外交の現実を見ようとしない極論であると私は思うところです。孟子の言葉は、ビスマルクを称える論者に対してコミュニズムだけが根本的解決であると批判する、マルクス主義者みたいです。孟子は実際斉にいた時代に国政に携わり、軍事行動まで国に起こさせたのです。そして、大失敗に終わった。孟子がこの経験で国政や外交というものがいかに複雑で困難なものであるかを理解しなければ、愚かというべきでしょう。ここでの縦横家たちへの一方的な批判の口調は、まだ現実の政治に手をつけたことがない時代の孟子の言葉であったほうが、分かりよいと思います。
上田:いずれにせよ、公孫衍・張儀は孟子の遊説にでる前のことで、遊説前の対話と想定される。
小田:孔子の弟子の子夏は、孔子の死後に魏(梁)に行って重用されました。孟子の時代にも、子夏の後継の儒家がきっと重用されていたはずです。斉でもまた、孟子の当時儒家集団が勢いを持っていました。これは、最後に斉を拠点とした子貢の後継者であったと思われます。この当時、曾参の後継であった本家・魯の儒家集団はむしろ勢いがなかったのでしょうが、孟子はそこで頭角をあらわしていた。斉王も梁王も、お抱えの儒家たちから孟子のことは聞いていたのではないか。だから誘いがあったけれど、孟子は当初断っていた。ある時になってからにわかに動き、梁に行き、斉にも行った。もしこの推測が正しいとするならば、孟子にいったいどういう心境の変化があったのでしょうか。
上田:当時孟子が何をしていたかは分からないのですか。
小田:孔子については、生涯全体について詳しい記録があるわけですが、孟子は遊説を始めた時期から以降しか分かりません。遊説を始めたのは老年に入ってからであり、それまでの時代に彼が何をしていたかを考証した研究は、私はあまり見たことがありません。
周霄(しゅうしょう)問ひて曰く、古の君子仕ふるか。孟子曰く、仕ふ。傳に曰く、孔子、三月君無んば、則ち皇皇如たり。疆(さかい)を出れば、必ず質を載す。公明儀が曰く、古の人三月君無んば則ち弔す。三月君無ければ則ち弔す。以(はなは)だ急(すみ)やかならずや。曰く、士の位を失ふは、猶諸侯の國家を失へるがごとし。禮に曰く、諸侯耕助して、以て粢盛(しせい)に供す、夫人蠶?(さんそう)して、以て衣服を爲(つく)る。犧牲成らず、粢盛潔(きよ)からず、衣服備はずんば、敢て以て祭らず。惟士田無くんば、則ち亦祭らず。牲殺器皿(きべん)衣服備はらず。敢て以て祭らずんば、則ち敢て以て宴せず。亦弔するに足らずや。疆を出れば必ず質を載するは、何ぞ。曰く、士の仕ふるや、猶農夫の耕へすがごとし。農夫豈疆を出るが爲に其の耒耜(らいし)を舍(す)てんや。曰く、晉國も亦仕國なり。未だ嘗て仕ふこと此の如く其れ急なることを聞かず。仕ふこと此の如く其れ急なり。君子の仕へ難きは何ぞ。曰く、丈夫生まれて之が爲に室有らんことを願ふ。女子生まれて之が爲に家有らんことを願ふ。父母の心、人皆之れ有り。父母の命、媒妁の言を待たず、穴隙(けつげき)を鑽(き)りて相窺ひ、牆(しょう)を踰へて相從はば、則ち父母國人(たみ)皆之を賤む。古の人未だ嘗て仕ふことを欲せずんばあらず。又、其の道に由らざることを惡む。其の道に由らずして往く者は、穴隙を鑽るのと類なり。
周霄が質問をした、「古の君子は仕官したのでしょうか?」と。孟子が言った、「仕官した。言い伝えによれば、『孔子は三ケ月君主が無ければ、そわそわとされた。国境を出る時には、必ず(諸侯への)進物を(車に)載せた』という。また公明儀はこう言った、『古の人は三ケ月君主が無ければ弔問の見舞が来る』と。(周霄が言った、)「三ケ月君主が無ければ弔問の見舞が来るとは、何とせっかちなことではありませんか」と。(孟子が)言った、「士が位を失うことは、諸侯が国家を失うようなものである。礼記に言う、『諸侯が耕助の礼を行い、作物を皿に盛って供える。諸侯の夫人は蚕の糸を紡ぎ衣服を作る』と。今、犧牲が生育せず、お供えが清潔でなく、衣服が揃わないなら、あえて祭ることはしなかった。また、士には給田が無ければ、祭ることはできない。犠牲の動物、器や皿、そして衣服が揃わず、あえて祭ることをしなければ、あえて宴会をすることもない。これはまた、弔問するのに十分ではないか(十分である)」と。(周霄が言った、)「国境を出れば必ず進物を載せるとは、どういうことですか」と。(孟子が)言った、「士が仕官するというのは、あたかも農夫が耕作するようなものである。農夫が国境を出るときに、どうして鋤や鍬を捨てるだろうか?」と。(周霄が)言った、「晉(魏つまり梁のこと。梁恵王章句においても、恵王は自国のことを晉と自称していた)の国もまた、仕官に足る国です。しかしいまだかつて、仕官することをこれほどまでに急ぐということは聞いたことがありません。仕官することをそれほどまでに急ぐのであるなら、君子(孟子のことを指している)が仕官しようとしないのはどうしてですか?」と。(孟子が)言った、「男子たるもの、生まれれば家人はこの子に配偶者のできることを願う。女子が生まれれば、この子のために嫁ぎ先ができることを願う。父母の心には、誰でも皆この願いがあるのだ。しかし、父母の命も媒妁人の言葉も待たず、塀に穴をあけ逢い引きし、垣を乗り越えて落ち合うなら、父母も国の人々も皆これをさげすむであろう。古の人は、いまだかつて仕官することを思わないことはなかった。だが、正しい道によらないことを憎んだ。正しい道によらず仕えに行く者は、塀に穴をあける者と同類である」と。
小田:ならば、梁王と斉王には正しい道で仕えるために行ったことになります。どこが正しいと孟子は思っていたのか?そこが難しい。
上田:あれだけ大言壮語して、道に非ずば、と言ってましたからね。
小田:この章は、思いますに梁の家臣である周霄が孟子を誘いに来たのでしょう。恵王が天下から人材を欲しているので、先生も梁にお越しになってくださいよ、などと。それを正しい道でなければ仕えない、と言って一時は断っていた孟子であった。どういう心境の変化で梁に行ったのだろうか?断ったことも正しいし、行ったことも正しいというのが孟子の主張であり、こうしてここに記述を残した。うがった推測をするならば、断った時期には、孟子はまだ時期尚早であると踏んでいたのかもしれません。梁には、子夏の弟子筋の儒家たちがいた。彼らに勝てないと、思っていたのかもしれない。斉には、子貢の弟子筋がいた。断った時期の孟子は、彼らに取り込まれることを恐れていたのかもしれない。孟子としては、各国の儒家たちの頂点に自分を置く遊説ツアーを行わなければならず、梁や斉の儒家たちを配下に置く策を立てなければならない。孟子は、行って儒家内の権力闘争に勝利するメドをつけてから行ったのかもしれません。
上田:あり得ることです。
小田:斉には、公孫丑がいました。彼は斉人です。孟子は公孫丑に、お前は管仲・晏子しか知らない、管仲・晏子などは曾西ですら比較されることに憮然とした、と叱りとばしました。公孫丑はいわば子貢から始まる斉学派の末裔であり、孟子はそれを完全に論破して組み敷いています。このとき、孟子は斉学派を屈服させていたのでしょう。孟子は繰り返し繰り返し、なぜ自分が出馬しないかを述べます。彼にとっては、重要なテーマであったのです。おそらくこれは墨家の「儒家は善行を出し惜しみする」という批判への言い訳であり、かつ孟子自身の消極的な前半生に対する批判への言い訳でもあったのではないでしょうか。
上田:諸侯への進物を積み込むことは、農夫が鋤鍬を持つのと一緒、進物は商売道具といわんばかり、あったりまえのことだった。
小田:孔子の時代とかであれば、国を出る士は次の諸侯にふさわしい進物を用意するのが常識だったのでしょう。採用されなければ生活の道が絶たれるわけですから。孔子の引用された言葉は、たぶん魯を去って諸国を巡っていた時代のことではないでしょうか。大勢の弟子たちを連れて三ヶ月食い扶持なしでい続けたら、それは焦ってそわそわすることでしょう。
上田:孟子は正式の招請があれば行くとしていた。この時は、周霄はまだ恵王の招請ではなく、人材発掘に当たっていたのではないか。非常に不遜なことを言う儒家であるが、一度招請してみてはどうか、ということになったのではないか。
小田:どうでしょうかね。私は、恵王の招請はこの周霄の時にもあったんじゃないか、と思います。しかし、孟子はこのとき動かなかった。当初恵王は覇王であることを公言していましたが、斉や秦に敗れて落ち目になった。孟子は、恵王が落ち目になった頃に会見に行きました。これも計算のうちだったかもしれません。失意の君主であれば、説得に聞く耳を持つであろうと。そうして梁で経験を積んで、次には当時の最強国である斉の若い宣王を説得に向かった。後の告子章句において、孟子は君子が仕官する条件について三つを挙げています。一つは道が行われる目処があるとき。二つは道は行われそうにないが君主に世話になったとき。三つは経済的に困ったときであると。孟子はこのとき、少なくとも困窮してはいなかったのでしょうね。
上田:次の彭更の場合には諸侯に伝食とあり、車数十台、従者数百人の時で、後年のことと思う。この頃には現実的判断をしているが、周霄に対しては非常に気負った対応をしており、恵王に会う前という考えに賛成できる。
小田:周霄と会見した頃は、孟子の弟子はそんなに多くなかったのではないでしょうか。孟子は梁へ行き子夏の後の儒家を組み込み、斉へ行き子貢の後の儒家を吸収し、その結果数百人規模の集団となったのではないでしょうかね。
上田:合理的な解釈だと思います。遊説前の対話という見方は非常に有効だと思う。
2013年10月19日14:00~16:00 論語読書会in士心
参加者:上田、小田、成田、桐畑孝佑
学而篇十二(読み下しは、中村愓斎に従う。) 記録者:小田
有子の曰く、禮の用和することを貴しと爲す、先王の道斯れ美(よ)しと爲して、小大之に由る、行はれざる所有り、和を知りて和するのみにして禮を以て之を節せざれば、亦た行はるべからず。
《James
Leggeの英訳》
①The
philosopher Yew said, "In practicing the rules of propriety,
a natural ease is to be prized. In the ways prescribed by
the ancient kings, this is the excellent quality, in things
small and great we follow them.②"Yet
it is not to be observed in all cases. If one, knowing how
such ease should be prized, manifests it, without regulating
it by the rules of propriety, this likewise is not to be
done."
(日本語訳例)
①哲学者である有子が言った、「礼儀の規則を実践するにあたって、自然なくつろぎが賞賛されるべきだ。古代の王たちにより指示されたやり方において、これ(礼儀の実践において自然なくつろぎを保つこと)は最高の価値が与えられていた。そして大きなことから小さなことまで、我々はこれに従う。②だがしかし、すべての場合において、自然なくつろぎが見られるわけではない。もし人がどれだけこのようなくつろぎが賞賛されるべきであるかを知っていながら、礼儀の規則によってこれを制御せずして実行するならば、こういった効果は表れないであろう」と。
(討論)
小田:有子とは、孔子の弟子有若(ゆうじゃく)のことです。学而篇の最初から二つ目の条にも、彼の言葉がありました。前の言葉といい、この言葉といい、理論的な叙述を行っています。彼は、どうも理論に長けていたようです。そして、その内容は難解です。まず、「禮(礼)」という言葉の意味が、現代日本語の意味より大きな概念を指しています。現代日本語で「礼」という字はお辞儀とか丁寧な言葉づかいとか、対人関係での配慮の意味しか持っていません。しかしながら、有子の言う「礼」は古代中国の用法であり、そこには法・刑罰・道徳まで含んだ政治全般の統治術の意味が含まれています。古代中国では、「士大夫以上は礼、庶人は刑」のルールが適用される掟がありました。すなわち、諸侯の朝廷に参内して政治に関わる最低ランクの士大夫以上に対しては、庶民に適用する刑罰で統治せず、もっとソフトで文化的な礼のルールを適用して統治することが原則でありました。庶民と上流階級と間には適用される法刑に区別があったのです。ここで有子が言う「礼」とは、だから上流階級を統治するためのルール全般であると考えなければなりません。日本でも江戸時代においては、武士に適用する法度(はっと)は庶民に適用する刑法と明確に区別されていました。悪事を行ったら磔にされるのは、庶民です。武士は、武士として許されない失態を犯したと判断されたならば、切腹しました。切腹とは、形式上は死刑ではありません。家と主君の名誉を汚した恥を悔いて、命を自ら断つ自殺であると位置づけられました。こうして武士には名誉を重んじる道徳のルールが適用され、庶民には名誉などを求めず刑罰を適用していました。古代中国の「礼」は、江戸時代の武士のルールとやや通じるものがあると私は思います。もとより現代社会では全ての人間は平等に法の下で統治されますので、有子の「礼」は現代に引き寄せて考えるときには法・刑罰・道徳の全体に渡る統治術、ぐらいに考えればよいと思います。そこに「和」が必要であるという。レッグはこれを"natural
ease"と訳しています。だがこの訳は、ちょっと的をはずしているんじゃないかな。おそらく西洋人のレッグは、「和」がなんで政治に必要なのか、その意味がよく理解できなかったように思うのですが、、、
上田:レッグは"natural
ease"で何を想定していたのでしょうか。ピンと来ない。
小田:レッグは、「礼」を"the
rules of
propriety"と訳しています。直訳すれば、「礼儀正しさの規則」です。英語でこう訳してしまうと、礼服の着こなしとか式典やパーティーでのエチケットとか、そんな意味に限定されてしまいます。そして、西洋社会ではそれらのエチケットは上流社会と下層社会とを区別する文化的差異として認識されますが、それが政治にとって重要だという理解など、ありません。イギリスみたいな階級社会であれば少しは文化的意義を認めるでしょうが(レッグはイギリス人です)、ロシアとかアメリカなどは礼儀じたいを冷笑すらする社会で、全く理解できないでしょうね。レッグは、おそらくここで言う「礼」を単なる文化的優雅さや厳粛さの意味に捉えているのでしょう。そんな中で、「和」を"natural
ease"と訳した。たとえば式典とかパーティーとかの席で、気の効いたジョークを言うのは、偉い政治家のたしなみと見なされます。堅苦しい式典の場を和ませる効果がある。たぶん、レッグはそんなことを想定していたんじゃないでしょうかね。
上田:なるほど、それは分かりやすい。
小田:しかし、レッグがそのような想定をしていたとすれば、それは「礼」と「和」の本来の意味を捉えたとは言えません。「礼」と「和」の射程は、もっと大きい。
上田:「和を貴しと為す」などと言うのは、論語で有子しかいません。先王を引き合いにしたり、大小これによると正当性を補ったのでしょう。不和な気持ちで親に孝、兄に悌を行おうとしても、うまくいかない。だから、礼を具体的に行うときには、上下の和の心が重要である。しかし、なんでもかんでも和せばいいものではない、親子、兄弟、先生生徒のけじめがなくなり、礼にならない。礼には元来、敬とか和が前提となっており、和をとりたてていうのはどういうことですかね。
成田:古代では「和」の意味は①音楽の調和、あるいは②料理の味の調和、という意味で用いられます。つまりは、異なる要素が互いに正しい配置で調和している様子が「和」の本義です。「礼の用和することを貴しと為す」は、たぶん古い格言であったのではないかと思います。有子は、古い格言に対して解説の言葉を付け加えた。それが、この条であると思われます。
小田:音楽の和音は、音の上下の区別がある。それらを一斉に鳴らすと、快く響く関係がある。政治も同じことで、上下に身分の区別があり、家庭には尊卑の区別がある。それらが正しい配置で調和していることが、礼すなわち統治の要点である。そのような意味でしょうか。
成田:思うに、有子の当時失敗した例があったのではないでしょうか。有子の時代、政治において和ばかりが追及された結果、かえって統治がうまくいかないことが多く見られた。だから、礼で制御しなければいけないのだ、という戒めの言葉を有子は言ったのではないでしょうか。
小田:有子の言葉は、孔子の言葉が具体的であるのに比べて、理論倒れのところがあります。後世の儒家はますます理論倒れの傾向を強めていきましたが、有子あたりにその起源があったように思われます。
桐畑:ここの有子の言葉に比べて、孔子の言葉はどのように具体的なのでしょうか?ちょっと分からない。
小田:孔子は、弟子と問答したり、君主から質問を受けたりするとときに、おおむね具体的に答えます。「どうすれば民がよく治まるのか?」と聞かれたら、「正しい家臣を登用して、それによって曲がった家臣を矯正しなさい」と答えます。それに比べて有子の言葉は、「礼」「和」という概念を操作して、統治論を抽象的に展開しています。そこには、大きな差があると私は思います。
成田:有子の言葉は、まるで学校の校長先生の訓示のように聞こえます。味わいがない。もし論語が有子の言葉ばかりで埋め尽くされていたならば、ぜんぜん魅力がなくなっていたことでしょう。
上田:「和を知りて和する」の意味は、なんでしょうか?どんなことを想定しているのか?
成田:よく分からないですが、結果的に和が達成されるのが正しい姿であるのに、最初から意図的に和を目指して統治を試みるならば馴れ合いとなってうまくいかない、といった意味でしょうか。
小田:この有子の言葉は、聖徳太子の十七条憲法「和をもって貴しとなす」に直接に影響を及ぼしているはずです。
成田:そのはずです。豪族の寄り合い所帯であった古代日本において、豪族どうしが和して共に朝廷を支えていくのが理想である、という考えのもとで引用されたのでしょう。
小田:なお、宮崎市定氏は、「和」を大胆に「妥協性」と解しています。つまり、前半を「礼を実行するには妥協性が大切だ。三代の政治が立派だというのも、こういう点で最高であったからだ。物事を一から十まで礼の規則づくめでやろうとすれば、行きづまることが出てくるためだ。」と訳しています。前半は礼の堅苦しさに固執せず妥協せよ、後半はしかし妥協するだけではうまくいかない、と解しています。
桐畑:ずいぶんと、分かりやすい解釈です。
小田:しかし、これが正しい解釈かというと、さあどうでしょうかね。
では、次にいきましょう。
桐畑さん、続いてお願いします。
学而篇十三(読み下しは、中村愓斎に従う。)
有子の曰く、信義に近づくときは、言(こと)復(ふ)んづべし、恭禮に近づくときは、恥辱に遠ざかる、因(よ)ること其の親(したし)むべきを失はざるときは亦た宗(そう)としつべし。
成田:中村愓斎の詠み下しでは、動詞+「つ(づ)」という用法がよく見られます。これは江戸時代に普通であった用法です。
《James
Leggeの英訳》
The
philosopher Yew said, "When agreements are made according to
what it right, wheat is spoken can be made good. When
respect is shown according to what is proper, one keeps far
from shame and disgrace. When the parties upon whom a man
leans are proper persons to be intimate with, he can make
them his guides and masters."
(日本語訳例)
哲学者である有子が言った、「正しさにしたがって合意がなされるならば、話されることは実現されうるであろう。礼儀正しさにしたがって尊敬がなされるならば、人は恥と不名誉から遠く離れ続けるであろう。人は、彼が寄りかかっている集団が親しむに値する正しい人々であるとき、彼はその人々を自分の導き手かつ師とすることができるであろう」と。
(討論)
小田:このレッグの訳は、もっぱら南宋の朱子が打った「新注」に従っています。しかしながら、この条の有子の言葉は朱子とは全く違った解釈が提出されてきました。その例として、江戸時代の儒学者である伊藤仁斎と荻生徂徠の解釈をレジメに書いておきました。
伊藤仁斎:他人の交際において親しみに依存(因)すれば、尊敬(宗)される。(古注、孔安国注に依拠した解釈)
荻生徂徠:妻の家族(因=姻)よりも自分の生家(親)を大事にする者は、一族の主(宗)となることができる。(陳書王元規伝にある引用から導き出した解釈)
この条は、朱子の注に従って読んだならば、「因(よ)ること其の、、」の前と後との間で、言っていることにつながりが見えない。仁斎と徂徠は、それぞれ別のやり方で前後を一貫して解釈する読み方を試みました。仁斎は、前半の二句は人が個人で達成できる道徳について述べている。最後の一句は、人が他人との付き合いにおいて気をつけるべきこと=親しみに依存すること、について述べて、人間として完成するべき道を有子は言っているのだ、と解釈するわけです。いっぽう徂徠はぜんぜん違って、この有子の言葉はすべて人が従うべきルールについて述べているのだと解釈します。まず前半二句は家庭の外では「義」と「礼」に従うべきこと、最後の句は家庭の中で姻族より親族を重視するという掟を述べていると。桐畑さん、しかし、姻族より親族を重視する、ということの意味は理解できるでしょうか?
桐畑:そういうこだわりが、当時にはあったのでしょうか?
成田:そんな例が本当にどれだけあったのか、ちょっと分からないですね。
小田:徂徠は、史書にここの言葉が引用されていることを見つけ出して、根拠としています。その例では、貧しい家の子弟が地元の豪族の娘と結婚したが、生家の親族を忘れたりはしない、という意味で用いられています。
成田:それは、もしかしたら論語の言葉の意味を変えて、あえて引用したのかもしれません。論語とかの中にある有名な言葉は、意味を取り替えて用いることが、よく行われます。
小田:漢代ごろの注釈は「古注」と呼ばれます。古注は朱子の読み方とはまた違っています。朱子は「信義に近づくときは、、、」「恭禮に近づくときは、、、」と条件節として読んでいますが、古注は「信は義に近し」「恭は禮に近し」として、「AはBである」と完結させて結んでいます。つまり訳せば、「信は義と同じではないが、近い概念である。なぜならば、両者ともに言葉を実行させる力があるからだ。また恭は禮と同じではないが、やはり近い概念である。なぜならば、両者ともに恥辱から遠ざける力があるからだ。」となります。私はむしろ、このほうがよく意味を取れるとすら思うのですが。
成田:だがそうなると、最後の句もまた完結させる形で読まないと統一が取れないと思います。しかし「因ることは、其の親とすべきを失わず」では、意味がよく分からない。
上田:信は友との間の約束事で、悪友もおり不義な約束も多い。だから義にかなうような約束をするように。恭は上司に仕えるときのことだが、なんでもかんでも従っていると、逆にピシャリとやられ恥をかかされることがある、礼にかなっていないなら孔子は拒否してよいとした。義と礼に親しむことを失なわなければ、宗、まあトップの人となれるということではないですかね。
成田:ここでの「親」を親族として解釈するならば、「因ること親を失う」という例がやはりかつてはよくありえた時代があったのかもしれません。ついつい、親族でない者を頼ってしまう。しかし人として最も重視するべきやはり親族であって、それを忘れてはならないと。
小田:孔子の時代あたりは、後世の中国社会ほど家族制度が厳格でなかったのではないでしょうか?江戸時代の日本社会では婿養子が当たり前に行われていましたが、かつての中国も後世より家系の血統維持の掟が厳格でなく、だからこそ有子のような儒家がそれではイカン、血統を守って祖先の祭りを厳格に行え、と当時に主張したのではないでしょうか。その主張が、後世の中国社会の規範となった。
成田:少なくとも孔子は、母方の顔氏に育てられたと思われます。孔子の母方の家への依存は大きかった。
小田:孔子の弟子には、父方の孔家の弟子はいない。しかし母方の顔家からは顔回など重要な弟子が出ている。孔子にとっては、母方の家系のほうが影響が大きかったはずです。
桐畑:この条では、「信」「義」「禮」といった、たった一文字で複雑な概念を説明しようとしています。細かい説明なしに漢字一文字で論証しようとしているので、解釈するのがとても難しく感じます。「信」は、信じることの意味でしょうか?
成田:むしろ、約束を果たすこと、経済用語における「信用」の意味です。
まだ時間があります。次にいきましょう。
続けて桐畑さんにお願いします。
学而篇十四(読み下しは、中村愓斎に従う。)
子の曰はく、君子は食飽かんと求むること無く居安からんと求むること無く、事(わざ)を敏(と)くして言を愼(つつ)しみ、有道に就いて正す、學好むと謂(い)いつべからくのみ。
《James
Leggeの英訳》
The
Master said, "He who aims to be a man of complete virtue, in
his food does not seek to gratify his appetite, not in his
dwelling-place does he seek the appliances of ease; he is
earnest in what he is doing, and careful in his speech; he
frequents the company of men of principle that he may be
rectified: - such a person may be said indeed to love to
learn."
(日本語訳例)
孔子が言った、「君子を目指す者は、食事において自分の食欲を満足させることを求めず、住居において安楽への安住を求めず、自分が行うことに熱心であり、自分の言葉に慎重であり、そして彼が正されてしかるべき原則を持った人々を仲間として、しきりに訪れる。このような人間は、学ぶことを愛好する者と言ってよい。」
(討論)
小田:前の難解な二つに続いて、ようやく理解しやすい言葉が出てきました。
桐畑:前半はよく分かりますが、しかし「有道に就いて」以下は、わかりにくいです。
小田:有道とはいわば道徳のある人のことです。レッグは"
the
company of men of
principle"と訳しています。「原則を持った人々である仲間」、そのような仲間をしきりに訪れる、交際する。そうやって自らの誤りを正し続ける。そのような人間は向上心ある人であり、前の部分の志と併せて学を好む人であるというわけです。
成田:「有道に就いて正す」のレッグの解釈は、中村愓斎の解釈と違っています。
小田:中村愓斎は、「有道とは、道徳ある人を云、上に云如くに、道を求ることをつとめて、得る所あれども、なを自是(ぜ)なりとせず、又必有道の人につきて、其の是非をとひただすなり」。つまり、自分だけで満足せずに、道徳ある人に就いてさらに是非を問いただす。修正するのは、自分からの発意という解釈です。しかしレッグは"may
be
rectified"と訳して、道徳ある人に自分を正してもらうことと解釈しています。自分ひとりでは正しくあることはできない、と見るわけです。
桐畑:前半は禁欲的なことが書いていますが、儒教は禁欲的なのでしょうか。
小田:キリスト教に比べると、儒教は欲望にわりかし寛容です。たとえば、儒教は裕福な暮らしをすることを非難しません。キリスト経では、財産を持つことは天国に入ることへの妨げとなる、という考えがあります。古代の聖人などには、高い柱の上に登ってそこで寝起きして暮らし、下からの信者からの差し入れだけで生きた禁欲者などが大勢現れました。儒教はしかし、こういった世俗の欲望から逃れることを薦めるわけではありません。
成田:裕福であるということは、それだけ高い地位にいて高い禄をもらっているということでず。そのような人は、自らの家をしっかり経営して立派な家長となることが責務とみなされます。家族は小さな社会であり、大きな社会同様に重要なものです。
上田:孔子自身は食い物にうるさく、住居も悪くありません。それに安住してはいけないということです。
成田:レッグの訳では、「君子を目指す者」となっています。つまり食欲や安住を求めない時期がある。それは、君子を目指して努力している時期である。レッグは、いざ君子となればそのような禁欲は不要だと考えていたのでしょうか?
小田:レッグ自体香港に駐在していて、中国人の君子たる役人たちを見る機会があったでしょう。彼らを見ると、到底禁欲的に見えなかったのではないでしょうか。禁欲的であるのは、役人になるための受験勉強中の者であると。
成田:しかし、私は食欲や安住に満足することをしないのは、君子になってからもまた同様である、と思います。それが孔子の本意だったのではないか。君子は常に、生活に安楽してはならない。志を持ち続けなければならない、と。
桐畑:今日は礼、和、義といった概念が出るところを読んだわけですが、このような勉強をする機会は大学ではありません。だから、かえって新鮮に感じるところです。こういった勉強は、どのようなときに役立つでしょうか?
小田:大学生が今学ばなければならないとこは、何でしょうか。
桐畑:今の学生ならば、まず英語力、論理的思考力、コミュニケーション能力。これらを身に着けることが就職のために絶対必要だと言われますね。
小田:私が思いますに、それらは就職し、社会に出るときに必要な、社会への入門の技術だと思います。社会に出てから後、人生で成功するためには、しかし別の学問が必要ではないかと思います。礼、和、義といったことは、実際仕事を継続させるときに大変重要なことです。私なども遠く離れた外国人とビジネスをしていますが、信義を守ることとか丁寧なレターを送ることとかは、決定的に重要であると感じています。社会に出てからいかに生きるのがよい結果を得るか、という学問は、今の時代にはどうもおろそかになっているのではないでしょうかね。
|
