|
�i�L�^�͋L���ɂ�������̂ŁA��c������܂����L���A���c�����Ȃ������́B�Q���҂̊m�F���Ƃ������̂ł͂Ȃ��B�j
2024�N8��10���i�y�j��w�͋变
�{���́A���{����A�۔������A���c����A��c����̎l�l
��w�͋变
���c����� ���W��
�A
�u�`�O���͂����� youtube
�۔��F�푈�ɕ����Ĉȍ~�����������Ƃ��̂ċ������悤�Ɏv���B�@�Ɋ�Â��Ă���悢�A����ŒN���ӔC���Ƃ�Ȃ��B
���c�F���{�����@�ł́A�@������͍̂���c���ł��B���̍���c���͍������I���őI�ԁB������������@������Ă���Ȃ�A�I���œ���ւ���悢�B���ꂪ�����`�A�@�����Ƃ̌����ł���A�悢����c����I�ڂ��Ɛ^���ɍl���邱�Ƃ������ɁA���{�������ƃu�[�����B����͋��ʂ�Ȃ����낤.�A�������g�����̑Ӗ���ҏȂ��Ȃ����B���ꂪ���̌��O�Ȃ̂ł����A�ǂ���炻�̌��O�ǂ���ƂȂ��Ă��Ȃ��B
�۔��F���������܂����̂ł�������̂ł����B
���c�F�I���A��O�̋��ȏ���n�œh��Ԃ����B�C�g�̉Ȗڂ͊��S�ɔp������܂����BGHQ�́A���̋���œ��{�͊Ԉ�����A�Ƃ��ē��{�l���������ׂ������`�����č����̎��o�����߂��B����͂���ŋ͒ʂ��Ă���̂ł����A���{�l�͂���ɏ����ł��Ă��Ȃ��B
�۔��F�a��h��Ȃǂ͐l�ԓI�傫��������܂����B��w�ɂ���{������A�����������{�̂Ȃ��ŁA���[���b�p�̂悢�����̂����邱�Ƃ��ł��܂����B�����`�̑����������m�Ȑl���������߂�A�悢���̂��ׂ���Ă��܂��܂��B
���c�F��l��l�����o�������āA�c����I�Ԃ��Ƃ��ł�����̂ł����A�����Ȃ��Ă��Ȃ��B
�۔��F�q���̂Ƃ����炫����Ƌ����Ă��܂���B
���c�F�a��h��̂悤�ȍ]�ˎ���ɋ�������l�����́A�q���̎������w���w��ł����B���R�̂��ƂƂ��āA��������{�ɂ���܂��B���̎�w���A����GHQ�ɂ��Ƃǂ߂��h���ꂽ�Ƃ����ׂ��ł��傤���B
�۔��F�]�ˎ���ł͏�����M�������ϋ��̐��x�����āA���X�Ŕ�펞�̂��߂̐ςݗ��Ă��s���A�a��h��̍��ɂ͂��ꂪ�������܂��Ă���A�F�X�Ȃ��Ƃɂ����p���邱�Ƃ��ł����悤�ł��B�a��h��͂���������Ď��Ƃ��������Ƃ��ł��܂����B�����ېV�̐l�B�͂����𗧂Ă��悤�ł��B���̓��{�ł͊O���l����R�����Ă��āA�X�[�p�[�Ȃǂł͓X��������O���l�ŁA�����~�b�N�X�W���[�X�݂����ɂȂ��Ă��܂����B
���c�F���{�ł͖����`���炪�s���Ă��܂������A�S�̒�ɂ́A��ɗ��҂́A�������~�ōs���Ă͂����Ȃ��A�Ƃ����C�������c���Ă���B
���{�F�a��h��͗��ʂ������ɔ̔�����.�d�������Ă������l�ł����B�����v�Z�����Ĕ̔����s���Ă��܂����B��L�̂��Ƃ��������Ă��܂����̂ŁA�����̕�����L�������ł��܂����B
�۔��F�_��Ƃ����B�����ƌo�c����ɂȂ��Ă��܂����B
�R��ōց@�S�H��
���c����� ���W��
�A�u�`�㔼�͂�����
youtube
�۔��F��O�́A�����͂܂�ł����B�Ō�܂œY�������邪������O�Ƃ������Ƃ��{�ɂ���܂����B��q�w�I���z��`�������ɂ������A�����ł͎E������A�ł�����A���{�ł͍l�����Ȃ��悤�Ȏc�s�Ȃ��Ƃ�����A��ɂƂ�ł��Ȃ��l������A����ŎE����Ă��ǂ��Ƃ���ȂNjɒ[�Ȃ��Ƃ����ݓn���Ă܂��B���{�ł́A����������ɂ��܂��A����͖����ł���A�ƑΏ����܂��B
���c�F��q�́u�����ʊӍj�ځv���܂������A���j�ɑ����q�̔�]�͐h煂ŁA�قƂ�ǂ̗��j��̐l���͂悭�ĕs�\���A�����Ă͈��l�Ƃ��Ĕᔻ���܂��B����Ȓ����̌����ł������A���̒��Ŏ������~���̂ĂđP�ł���ׂ����Ɛ�����q�w�́A���Ȃ��Ƃ����O�Ƃ��Ă����Ƒ��d����܂����B��������Y�v���ɂ���āA�̂ċ����Ă��܂��܂����B
�۔��F���{�ł́A���s�A�ޗǁA���A�������X�e���Ő��藧���Ă���悤�ɁA���������������`�̒��Ő��͑������N�����Ă���Ǝv���Ă����̂ł����A���ꂪ����Ă���ƋC�t���܂����B�S���قȂ閯���̐������o���オ���Ă���A�������ɂ����̂͊��Ɩ����炢�̂��̂ŁA���͈���Ă���̂ł��ˁB�����Ȃ�܂��ƑO�̕����͂�����������ɂ��̂ċ����܂��B���{�ł͓V�c�Ƃ����������ɂȂ��Ă������ێ����邱�Ƃ��Ȃ���A���Ƃ��ĘA�шӎ������蕶�����ۂ���Ă��܂����B��������Ƃ݂�̂͊ԈႢ�ƋC�t�����̂ł��B���ƍ����m�̐킢���J��Ԃ���Ă����悤�Ȃ��̂Ȃ̂ł��ˁB
���{�F���[���b�p���ʁX�̍��ƂȂ��Ă���̂͋��R�̂��Ƃł��B�t�����X�A�h�C�c�A�C�^���A�Ȃǂ͈�̍��ł��悩�����B
���c�F�t�����X�A�h�C�c�A�C�^���A�Ȃǂ͒����ł͐_�����[�}�鍑�ł���Ǝv���Ă����B�㐢�ɕʁX�ɕ����ꂽ�B
�۔��F���͒����ł͑v�オ�D���ł��B�v�̓g���R�n�ł��ˁB�v�̍H�|�̑f���炵���Ƃ���̓g���R�̉e���������Ă��܂��B
���c�F�@�Ⓜ���ٖ����������Ƃ������邱�Ƃ�����܂����A���̕��ނ͂��������Ǝv���܂��B�m�����@���̍c���͑N�ڑ��̌����ł���܂������A�������������Ƃ����ӎ��͌�̐��Ɏn�܂������̂ł��B�u���v�Ƃ����͖̂����ł͂Ȃ��BꟁE�w�̎��ォ�瑱���Ƃ����O�Ԍܗς�����Ă��邩�ǂ����A���ł����āA�@���͏o���͂ǂ��ł��ꒆ�̗ϗ��ƕ����d���Ă����B�Ȃ̂ł���炪�ٖ��������Ƃ����̂͌ꕾ������Ǝv���܂��B
�۔��F���̋��ʍ����d�������Ƃ������ƂłˁB
���c�F�����Ɣ��̋�ʂ��ӎ����ꂽ��̂́A�v��ȍ~�̂��Ƃł��B�����S���Ƃ����B���Ƃ��́A���̕����d�����Ɏ��������̕����������ɉ����t���悤�Ƃ����B�`���M�X�n���̍��A�����S���l�͉ؖk�̒����l���F�E���ɂ��ėr�������悢�ƌ������Ƃ����B�ؖk�͗V�q�̓K�n�ł���A�����̃����S���l�͒��̕�����ϗ���S�����d���Ă��Ȃ������̂ł��B�F�E���ƂȂ�Ȃ������̂́A�_�O�l�̋M���ł������뗥�^�ށi���������j�ł������B�ނ́A�E�������ł�������ق��������ł���ƃ����S���l�ɗ@�i���Ɓj�����Ƃ������Ƃł��B�뗥�^�ނ̌_�O�����Ƃ̓����S���n�ł������A���N��������������Ă������ʒ��ؕ����d����悤�ɂȂ��Ă��܂����B�������������̓`���d���Ȃ������S���Ȃǂɒ��ʂ���������A�����Ɣ��̍��ʂ��ӎ�����邱�ƂɂȂ����B���ňꎞ���������肻���ɂȂ������\�R�Ȃǂ́A�o���̓C�����l�ł����B�C�����l���i���s���܂������j���ʂ��Ē��̍c��ɂȂ邱�Ƃ��A����ł���Ώ\�����肦�邱�Ƃł����B
�۔��F���̒����̎p�͌��X�����������ł������Ƃ������Ƃł��ˁB�F�X�̍������荞�݁A���ł͊����łȂ����Ă���B
���c�F�h��v���Ő������|�ꂽ�B������p�������ؖ����́A�����i�V���i���Y����ł��o�����B���͊J���ꂽ�����ł��薯���ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ă̌����́A�����Ɏ̂ċ����܂����B���������ӂ̔����x�z���ē��R�A�Ƃ������ƂɂȂ����B����ɋ��Y�v���ɂ���āA��q�w���̂ċ���ꂽ�B���{�l�͎O�����`���D���ł����A�O�����Y�͂���Ɏ�q�w�̎v�z�ŏ�����Ă��܂��B�����͐������������ɑ��āA�Ɛb�Ƃ��Ă�����x����ł��Ȃ��A�������Ď������~���ނ��o���ɂ��ęӒD����ދɈ��l�ł���B�t�ɏ����E���́A�X�����������A������p�������㏬��冊������ɑ��āA�������~���̂ĂĒ��߂��т����B�O�����Y�͑�����l��A�����E�����̂���B����ɓ��{�l�͍��ł��u�������o����B����́A��q�w�̍l���Ɏ^�����Ă���Ƃ������Ƃł��B�����▾���ېV�̍��̓��{�l�́A��q�̒����ǂ�Œ����⒩�N�͎��������Ɠ����ϗ��ς������Ă���̂��ƐM�����B����������{�̗����ւ̓����������N����A��������̍��܂�����̂ł������B������{�l�͂����ɒ����l�E���N�l�ƈႤ�̂��Ƃ������Ƃ��������Ƃ����s���Ă��܂����A���������̍��͂��̋t�ŁA������q�w�ɐ��`�������铯�m�����ϗ��ς������Ă���Ǝv���Ă��܂����B
�۔��F�C�I�����[���ɍs���Ă����̂ł����A�����l���䂪����ł��B
���{�F20�N�O�͓��{�l�������������Ă��܂����B�~�̗͂œk�}��g��ŐF�X�p�����������Ƃ����Ă��܂����B�������̖��b�̋L�^������A�����ł͖��̖��x�����Ȃ�Ⴂ�ƋL���Ă��܂��B
���c�F���{�ł́A�_���⒬�l�ɂ����{������A�Ȃ����o�c���ł��Ă��܂����B�����ł͉ȋ������ɂ��g�b�v�G���[�g�͗D�G�������B�������c��̈��|�I�����́A�ق����炩���ł������B�����̓��{�ƒ����̍��́A�����S�̂̕��ϒl�ł������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���{�F�������Y�}�́A�������C�ɂ��ċ���ɗ͂����Ă���Ƃ��낪����Ǝv���܂��B
�۔��F���{�͊�i�܂�j�ȍ��ł��ˁB�ǂ��ɍs�������l����Ƃ���ɂ��Ȃ����̂�����B
���c�F�]�ˎ���A�������ł܂��čL���������ʂł��傤�B
�۔��F���E�̐l�X�������Ă��āA���{�̂܂ꂳ���������Ă��܂��B
���{�F���ɐN�����ꂽ���Ƃ̗��Ԃ��̑v���ł����B�۔�����A�H�|������Ŋ��������̂ł����H�g���R���ۂ��̂ł����H
���c�F���Ɛ��́A���������̕����𒆍��ɉ����t�����B����Ȃ��Ƃ́A����܂ł̒��ؐ��E�ł͂Ȃ��������Ƃł����B����܂ł̒����ł́A�����ɑт̑����ł����B���ꂪ���B���̐��́A���̖т�㐔��A�����͌ӕ��ƌĂ�邢����`���C�i�h���X�ɃY�{�����������܂����B���NJ��������B�̕�����������Ă��܂��A���݂ł������̐����͌ӕ��̃o���G�[�V�����ł��钷�߂ɃY�{���ł��B
���{�F���_���ł̓A�C�f���e�B�e�B�[�͈ꏏ�ł����A��`�I�ɂ͈قȂ�悤�ł��B
2024�N9��14���i�y�j��w�͋变
�{���́A���{����A�Z�c����A���䂳��A�۔�����A���c����A��c����̘Z�l
���c����̃��W��
��w�͋��i��-06.pdf�j�̍u�`�͂������@youtube
�۔��F�t�H�퍑�A���̏t�H�Ƃ����A�ǂ�����n�܂�܂����B
���c�F�t�H�o�Ɛ퍑�炫�܂��B�t�H�o�͍E�q���Ҏ[�������̂ŁA�t�H����͋I���O770�N������E�q�̌�̍��܂łł��B���ꂩ��I���O221�N�`���V���ꂷ��܂ł��퍑����ŁA�e��������ȂĔe������������a�����߂�v�z������A�e���ɂ����邳�܂��܂Ȍ����A����A����𗫌����Ҏ[�������̂ł��B
�۔��F�o�Ƃ����̂�
���c�F�e�L�X�g�Ƃ����Ӗ��ł��B
��c�F�e���Ɏj��������L�^������܂��B�E�q�͂����Ҏ[�������́B
���c�F�퍑��͂ǂ̂悤�ȍ����Ő푈���������A��v�������̐����ƁA���R�A�V���Ƃ��ǂ̂悤�ȍ�����p���������L���Ă��܂��B�t�H�͎���̗�������E�q�̔ӔN�A�E�q�͗p�����邱�Ƃ��Ȃ��A�ӔN�ɐ��𐳂��Ӗ������߂āA�㐢�̂��߂ɗ��j��Ҏ[�����Ƃ���܂��B
�۔��F�����A�����Ƃ́H�������ƈٖ����Ƃ������������Ƃ͊W���܂��B
���c�F�����Ƃ��������@�ȑO�A��k���̓쒩�A���{�͓쒩�ƌ��Ղ��쒩�̉��������ł��B�k���͑N�ڂ������Ă���A���ɂȂ��ēs���Ɉڂ������Ŏg��ꂽ���������B������A�����҂͂���܂ł̉��̓��[�J���Ȃ��̂Œ����̉����g�����ƂɂȂ����̂ł����A�����E����җ�Ȕ���������A���{�ł͕��p����邱�ƂɂȂ�܂����B
�۔��F���͌����̕����_�炩���Ă��������ŁA�k�̕��̉����c�ɕ��ɕ������܂��B�A�������������̂̉����c���Ă���B
�����F�����ɂȂ��ē��������S�ƂȂ�A�m���ɒ��S�ł͌��t���ω������Ă䂫�܂��B�������A���[�ł͐̂̂��̂��c��܂��B���k�ł͊��q����̂��̂��c���Ă���A�F�{�̕��ł͂��܂���~���g����������h�Ƃ����܂��B�Ƃ���ŁA�V�Ƃ��A�N�Ƃ��A�ς��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ��A�V�Ɉӎu������Ƃ݂�̂��A���R���ۂ̂Ȃ��ł݂�̂��A���̂�����͂ǂ��Ȃ��Ă��܂����B
���c�F�����͂ނ������B�u��ɂ����̂ڂ�ƁA�V�邪�ӎu�������A�V�̈ӎu���l�Ԃɉ���Ƃ����ϔO�����łɂ���܂����B���������オ����Ўq�ɂȂ�ƁA�A�V�͉����\�����A�V�̈ӎu�͖��̓����ɕ\���A�ƌ����B�����ł͎��オ����ɂ�āA�V�����m�Ȉӎu�������݂Ƃ����ϔO����ނ��A�V�͉��炩�̈ӎu�������Ă���͂��ł��邪����͂킩��Ȃ��i�E�q�j�A�V�̈ӎu�͂킩��Ȃ����A���̎x�������邩�ۂ��œǂݎ�邱�Ƃ��ł���i�Ўq�j�A�V�͎��R���ۂł���@�������蒁�������鑶�݂ŁA�l�Ԃ͂���������I�ɗ��p�����낵���i䤎q�j�A�ƒE�_�b�����Ă����܂��B
�����F�����̐l�ԂƓV�Ƃ��a���ƂȂ�܂��B���Đ肢�����Ă��̌��ʂœ����Ƃ������Ƃ�����܂������t�H����Œf�₵�Ă��܂����B
���c�F�퍑�������ɂȂ�ƁA�V�E�n�E�l���Γ��̑��݂ł���Ƃ����c�_���N����B�V�ƒn�͖@��������A����͌b�݂������炷���݂ł���B�c��ۑ�́A�l����������邱�Ƃł���B�l����������荇���I�ȉ^�c���s���V�X�e��������A�l���N��͓V�n�ɕ��ԑ��݂ƂȂ�傢�Ȃ�K����n��ɂ����炷�ł��낤�A�A�A
�����F�i�t�H�퍑���牤�����]�X�Ƃ���̂ł����j�����ɈӖ�������̂��B��҂ɓ���������̂��B���ʂ������̂�������Ȃ��B
���c�F��w�̌����������s�����Ƃ���ŁA���ۂ͕���邩�ǂ����͂킩��Ȃ��B���̕s���͏����Ȃ��킯�ł���܂��āA�䂦�ɕ����͌����͋����̂ł��获������ׂ��łȂ��A�Ƌ����Ďx�����L�߂��B�����Ɏ�q�������������킯�ł����A��q�͐������̐�ΑP�ɏ]�����Ƃ������l�Ԃ̖ړI���`���ł���ƌ����B�l�̍K���Ƃ������Ƃ��͎����ł���A���̗��Q�ōs������͈̂��ł���Ɣᔻ���܂����B
�����F�@������Ă悢���ʂɂȂ邩������Ȃ��B�����������ƂɂȂ�܂��B
���c�F��q�́A�����ɂ����Ė����ł��邩�ǂ����͖��ł͂Ȃ��A�l�̈ӎu���z�������ɏ]�����Ƃ������l�Ԃ̖ړI���`���ł���B�l�̍K����x�O�������l���ł���A���Ɍ����������ł��B
�۔��F�ؔ�q�Ȃǂ�ǂނƁA�܂�Ō���݂����Ȃ��Ƃ��łĂ��܂��B���̎���͑����ɐl�̐S�����G�ɂȂ��Ă����̂ł��傤�B���̒��ōE�q���^�ǂ������c�����Ƃ������Ƃł����B
���c�F��w�́A�m���Ɋ���ȍ~�̓����ɂ͓s���̂悢�����ŁA���Ƃ�������ҏW���ĕی삵�܂����B�����|���u��ǂނƁA�n�c��̕������������ɂ�������炸�A����̏��ɂɂ͑����̏��Ђ��c����Ă������Ƃ��킩��܂��B�������A�����|���u�ɋL�^���ꂽ���Ђ̒��ŁA����܂œ`����Ă�����̂͂����킸����������܂���B�������́A���ゲ��ɂ����������̒��ŁA�^�悭�����c�����ق�̈ꕔ�̏�����ǂ�ł���̂ł��B
�۔��F�Ñ㒆���̔��z�͂������Ǝv���܂��B���{�͂����Ƃ�������������܂��ł��ˁB
�R��ōւɂ��āB
���c����̃��W���i��w�͋�ߘa�Z�N�㌎.pdf�j���c����̍u�`�@youtube
�۔��F�ߎS�Șb����ł��ˁB
���c�F�����ƁA���̗��v�Ƃ������Ƃ����������ł��B
�����F���{�̒����A�J�n������1192�N��1180�N�ƕω����Ă��܂������A��̌��͂���d�ł�������̂ł����A�V�c������A���m�����ł͏��R�Ƒ喼�ȂǎO�d�\���ł͂ǂ��Ή��������̂��B���v�̗��Ō㒹�H��c�͓������A��Ɛl�����ɋ�B�ɂ�������s���h�����ꓙ�X�ǂ�ɏ]���̂��������̂��A���G�ɂȂ��Ă����B�X�y�C���̃J�^���[�j�A�ł͒P�ꖯ���łȂ�������������ł���A�X�y�C�������������Ȃ̂��Ɨ��Ȃ̂��A���G�Ȍ`�Ԃł���A�ǂ���������̂��B�����ȌN��ɒ���s�����Ƃ������ȒP�ɂ͂䂩�Ȃ��B�R��ōւ͂ǂ�����Ɖ]���܂����B
���c�F�܂��ɓ���B�ōւ̒�q�����܂����B�ōւ͑喼�Ƃ��W���������l�ŁA�V�c�ɂ��Ă͂��܂葽�������Ȃ��B���Ƃł���A�N���ɕK���d���Ă���B��]�͂͂����肵�Ă��āA����̎�𗠐��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ��������ł������肷��B���ꂪ�_���E���l�ɂȂ�ƁA�ǂ��ł��邩�B�ނ�͏��R�ɂ��喼�ɂ��d���Ă���킯�ł͂Ȃ��B�e�ɂ͎d���Ă��邪�A�Љ�I�Ɍ���A�ŏI�I�ɂ͓��{�̌N��Ɏd����Ƃ������ƂƂȂ�A����͌��ǓV�c�ł���Ƃ������ƂɂȂ�B�����A�E�˘Q�l������A�܂��_���E���l����u�m���y�o�����B�ނ�́A���m�ɓ��{�̌N��͒N���Ƃ����₢���ӎ��ɋ������B��������ƁA����͓V�c�ł���A���R�͓V�c�̈ӌ��ɏ]��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B�ނ炠���肩��A���D�ւ̎v�z�������͂����悤�ɂȂ������Ƃł��傤�B
�۔��F�퍑����͏��҂ɕt���B�����łȂ��Ɩ��c�Ȃ��ƂɂȂ�܂��B�V�c�Ƃł͐₦�����ɂȂ�ƁA�n�}��H��H���ĂȂ��čs���B�V����~���Ă������̂ł͂Ȃ��B�͕̂v�w�Ƃ����Ă��A������������Ɩ����e�����߂��Ƃ���B�Ŏ�����̎���ł����B
�����F�]�ˎ���̉Ƒ����x�͂��Ȃ莩�R�ʼn�������𗣉������B�Ƒ����x���K�`�K�`�ɂȂ����͖̂����ɂȂ��Ă���̂��ƁB�����̒j�����ڂ��������܂ꂽ�B
�Z�c�F�V�̑������͎���ɂ��ς��B�Ђ⏃�����Ď�q�w�ƂȂ����B���܂�Ƃ���͓V�ӂ����Ȃ��Ȃ����B
��c�F�E�q�ł́A�b�͌N�Ɂu���v�ł����A�N���u��v�Ɋ�Â��Ắu���v�ŁA�N���u��v�ɊO��Ă���ΐb���N��ς��Ăn�j�ƂȂ�B�]���ĘD���łĊe�n�ɌN�����߂��B�b���������ǂ܂�Ĉȍ~�A�n��̒�́A�V�̏��̒��q�A���̎q���Ƃ���A�n��̒�͍s�����N�����ɐ肢�����ď��̋��������߂˂Ȃ�Ȃ������i�n��̒�ɂ͎��R�ӎu�͂Ȃ��j�B���͂��̌n����œ|�������߁A���炽�Ȑ�����������������Ȃ��Ȃ����B�V�͖��Ɉ��J��^�����i���̂���j�҂ɐV���ɖ����~�낵���Ƃ����咣�����o���o�Ő�`�����i�܂��A�����͔��T��Z�\�l�T�ɂ��A�V�ӂ�ސ��ł�����̂Ƃ����j�B�`�������������ꟁA�F�̌����̏w�A�^������S�y�������e�A�����V�����Ƃ���b�Ɏd�グ�A������p�����Ƃ����B���o��j�L�ł́A���łɕ����Ɂu���v������Ă���A�����͕����̂��߂ɐ�������鏀�������A�������u�����̖��v����@�Ƃ̐킢���n�߂��Ƃ��Ă����i�ڂ����́u�������v�ɋL���Ă���܂��j�B
2024�N10��5���i�y�j��w�͋变�A�₹�䖝�̐�
�{���́A���䂳��A�۔�����A���c����A��c����̎l�l
��w�͋变
���c�����
���W�� �A�u�`�O���͂�����
youtube
�@
�����̏��̕�����ǂޑO�ɁA�����Ǝ�q�w�̐��E�ς̈Ⴂ��}�����B���c�͕�������I�Ɍ����������Ƃ��Ȃ��̂ŁA�p��̐����Ȃǂɕs�������邩������܂��A�����͂��������������B
�����́A�O�E�����l�Ԃ̈ӎ���p�́A���ׂė։��]������Ɓi�J���}�j���N�������z�ł���ƍl���܂��B�ƁA�����悤�Ƃ���ӖړI�Ȉӎu�ł���A�ЂƂ̌̂�����Ŗł�ł��A�Ƃ͎��̐����ɗ։��]������B�l�Ԃ͎��˂ΘZ���ƌĂ��Z�̓��̂����ꂩ�ɓ]������B�{�����ɗ����邩�����ꂸ�A�C�����ň��S�����ƂȂ邩�����ꂸ�A�܂��l�Ԃ̐Ԃ�V�ɓ]�����邩������Ȃ��B����́A�ߋ����疢���։��X�ƌp�������B���ׂĐ����悤�Ƃ���Ƃ��Ȃ��邱�ƂŁA�Ƃɂ���Đl�Ԃ͈ӎ��������A�~�]�������A�~�]�͌����Ė�������Ȃ��B�����琶���邱�Ƃ͋�ł���Ƃ����B�l�����ɂ̖ړI�́A���̋Ƃ��Ȃ��ӎ��Ɨ~�]����A���z�ł�����̂��Ȃ����Ƃ�m�邱�Ƃł���A�O�E�ւ̎������̂ĂĈ��������߂邱�Ƃł���ƁB�����畧���ł́A�O�E��ے�I�ɂƂ炦�āA������̂Ă邱�Ƃ�E�߂܂��B
���Ƃ��̂āA���E���̂āA�Ƒ����̂Ă�B�����̌���f�āB
��q�w�́A���̕����̐��E�ς�O��I�ɔᔻ���܂��B�����̐��E�ς́A�����̊O�ɍL����O�E���u�l�ԂɂƂ��Ă͂Ȃ��ق����悢�A�������Ȃ��ق����悢�v�Ɗ��߂�B���̊ؖ��́A���������̂悤�ɑE�߂č��ƂƉƑ��ɐӔC���������A�ӔC���瓦��悤�Ƃ��邱�Ƃ������Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ɣᔻ���܂����B�ؖ������̑���Ɏ����Ă������E�ς́A�w��w�x�̏C�g�ĉƎ������V���A�ł��B�l�Ԃ̖ڕW�́A�܂�������ϗ��I�ɂ悭���邱�Ƃł���B�������ϗ��I�ɂ悭����A���͂̉ƒ���ƂƂ̂��邱�Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ɂ��̊O�ɂ��鍑�Ƃ��悭���邱�Ƃɒ��͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ꂪw�������A�E�q�Ўq�����������ؐ��E�̐��������ł���ƁB�����⓹���́A��������邽�߂ɂ��낢��Ɠ���N�w�����˂���܂킷���A���̌��ʎЉ�ւ̐ӔC�͂���Ȃ��A�̂Ă�ƌ����B���ꂱ�����Ƃ̓G�ł���A���ł���A���ؐ��E���獪�₵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ܂Ō����܂����B
��q�w�́A���̊ؖ��̕����ᔻ���āA�O�E�Ǝ��ȂƂ̊W��l�Ԃ̋`���Ƃ��Ĉʒu�t����v�z�I�\�z���s���܂����B�ȑO�̎��̍u�`�ŁA�u��q�w�̓��e�[�[�v�ƌĂт܂����B��́A�u���͑������Ȃ�v�ł��B��q�w�͕����ɑR���āA�l�Ԃ̑��݂͓V������^����ꂽ��ΓI�P���j�S�ɂ���A�ƌ����܂��B�V�����l�Ԃɗ^������ΓI�P�A���ꂪ�u���v�ł���A�Ўq�������u���P�v�ł���B����Ől�Ԃ̐l�����l�K�e�B�u�ɑ����镧���⓹����ނ���B�����đ��e�[�[�A�u�S�͐��E��ׂ�v������܂��B�V�����l�Ԃɗ^����u���v����ΓI�P�ł���Ȃ�A�����̐l�Ԃ��P�łȂ��̂͂ǂ����ĂȂ̂��B����́A�l�ԑ��݂́u�{�R�̐��v�Ɓu�C���̐��v�̓�ʂ������Ă��邩�炾�B�u�{�R�̐��v�́A���邱�Ƃ��G�邱�Ƃ��ł��Ȃ����A�l�Ԃ̒��Ɋm���ɑ��݂��Ă���A�s���̑P�ł���B�u�C���̐��v�́A�l�Ԃ���̓I�ȓ��̂������ĕ����Ƃ��Đ��܂�Ă��邱�Ƃɂ��A���̕����������N�������̂ł���B�u�{�R�̐��v���u�C���̐��v�Ɗ�������ƁA�l�Ԃ̐S�Ɂu��v�����܂��B�u��v�͒��f��I�ׂΑP�A�ߕs�y�ł���Έ��B�قƂ�ǂ̐l�Ԃ̓i�}�́u��v�ł͉ߕs�y�ł���A���������Ă悭�ĕs���S�A�����ėȏ��l�ł����Ȃ��B�Ȃ̂ŐS��b���āA�u��v�𒆗f�ɏ�ɕۂH�v�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�S��b������@���A��q�w�ł͋��h���{�A�Ƃ����p����g���܂��B���f��I�ю�邱�Ƃ͂���߂ē�����A�l�ԂȂ�ΐ��ݓI�ɒN�ł��ł��邱�Ƃł���B�����Đl�Ԃ̋��ɂ̖ړI�́A���Ȃ��C�߂Ă悭���邱�Ƃł���A�i��ŊO�E�ɑP���y�ڂ����Ƃł���B��w�̂����C�g�ĉƎ������V���A�ł��B�������Ď�q�w�͐l�Ԃ̑��݂�P�ƂƂ炦�A���̑P���Ȃ���O�E�ɋy�ڂ����Ƃ��l�Ԃ̋��ɂ̖ړI�ł���`���ł���A�ƌ����āA���������̊O�E�ے�_��ᔻ���đނ���̂ł��B
�Ўq�̎��ɂ���ē�����������r�₦���A�Ƃ����̂͊ؖ��̐��ł��B�ؖ��͖Ўq�𐳓��ȍE�q�̌�p�҂ƈʒu�Â��A�������퍑����Ɋ���������Ƃ�䤎q�͍E�q�̋����𐳂����`���Ă��Ȃ��ƈʒu�t�����B���̈ʒu�Â����v��ȍ~�ɒ蒅���āA�Ўq�͎�w�̐����A䤎q�͎�w�ْ̈[�Ƃ��������ŌŒ肳��Ă��܂��܂����B���̈ӌ��Ƃ��ẮA䤎q�͌����Ď�w�ْ̈[�ł͂Ȃ��A�Ўq�̘_�c�̑e�G�ȓ_������Ȃ錤����ςݏd�˂ĕ�����l�Ƃ����ׂ��ł��B�L���Ȑ��������A�Ўq�̂悤�ɐl�Ԃ��ŏ�����P�ł���ƌŒ�I�ɑ����ẮA�����̎Љ������ł��Ȃ��B�Ȃ̂ł܂��ŏ��Ƀi�}�̐l�Ԃ͂��傤���Ȃ����݂ŗ~�Â��߂ő�������ł���Ƃ������Ƃ�F�߂āA��������l�H�I�ɐ��䂷��p���l���邱�Ƃɂ���Đl�Ԃ��悭�Ȃ邵�Љ�����Ȃ����ł���̂��A�Ƃ������͂��s�����l�ł����B䤎q�̂��Ƃ͌����o���Ǝ��Ƃ��ăL�����Ȃ��̂ŁA�����͂���ȏ��߂Ƃ��܂��B������邱�Ƃ́A䤎q�͌��������ł��B�Ўq�͗��z��_����ł��B�~���������A�V����l�Ԃɉۂ���q�w���ǂ����I�Ԃ̂��͖��m�ł��傤�B�܂�䤎q�͍��Ƃɂ��l�Ԃ̓��������߂܂��B�Ўq�͓ǂ߂킩��܂����l�̎����ԌX���������B���������G���[�g���鎩�����������̎m��v�����ɂƂ��āA�ǂ��炪�S��ł̂������炩�ł��傤�B
�������Ď�q�͊���ȍ~�̎�w�͎}�t���߂���œ������Ȃ��A�Ɣᔻ���܂��B�����n�Z�A���Ƃ������P�e�w�҂����߂�^���Ȃ���A�_��̈Ӗ��͌㐢�ł悭�킩��Ȃ��Ȃ��Ă������Ƃł��傤�B�n�Z�A���͌㊿�̐l�ŁA�܂��t�H�퍑���ォ��̓`�����Q�Ƃł��鎞��ɂ����B�㊿�ȍ~����ȓ`�����ł�ł��܂����̂ŁA�ނ�̒��߂��Ȃ���Θ_����Ўq���܌o���Ӗ����悭�킩�炸�A�������傭��q�w�������ł��Ȃ������ł��傤�B�����Č����A��q�͊���͂܂��l�X�̒��ɓ������c���Ă�������ł������A�ƌ����܂��B鰐W��k���Ƃ��@����͂����������߂��Ⴍ����ŁA���̎�����͌Ñ�ɋ߂��Đl�X�̐S���܂��ł������ƕ]���܂����B
�����F�E�q�ȍ~�@���ɐ��ނ������͕����邪�E�E�E
�۔��F���t���������B������ǂ��Ă�����������Ȃ��B
���c�F�������ւ̍]�ˎ���̖{�ł��̂ŁA�������Â炢�Ƃ���͂���܂��B
�۔��F�]�˂̐l�B�͕��ʂɓǂ߂��̂ł��傤���A�������������ł��ˁB
���c�F���ւ̖{�͍L���ǂ܂�Ă���A���{��Ŏ�q�����������������Ƃ�������Ă���Ƃ��낪�d��܂����B
�����F��q�w�������������ɗ������Ă����Ƃ������Ƃ͕�����܂����E�E�E
���c�F�v�z�j�Ƃ��ďd�v�B�Ўq�œr�₦�A����A����ƒ�����Ă������̂���q�������������Ƃ��Ă���B�ɓ��m�ւ≬���h�q���͎�q�w��ᔻ���Ă܂������B
�����F�E�q�̍��Ɗ���ł͌��t�̈Ӗ����e���قȂ�ł��傤���A�t�H���犿��܂Ŏ��ԓI�ɂЂ炫������܂��B�|�Ȃ�؊Ȃ��������Ă����R�������ď������킩��Ȃ��Ȃ�����A���ɂ���Ċ����̎��̂��������Ă����B
��c�F�E�q�̍��̕����̏��̂͋����ŁA����͐`��̗ꏑ�ŏ��̂��قȂ��Ă���B���t�̈Ӗ����ϑJ���Ă���B
�����F�`�̎n�c��̕����B��ŕ������ꂽ���A����ɂȂ��ďo�Ă����B
���c�F�O����A�D�����E�q�̉��~�����Ƃ������A�ǂ̓��������ʂ̌Õ��̒|�Ȃ��łĂ����B���m�ɂ������ǂ������Ƃ���A����͎�w�̃e�L�X�g�ł��肨���炭�E�q�̎q��������������ĕǂ̓��ɉB�������̂ł��낤�A�Ƃ������Ƃł������B���̊����̏��̂́A�����g���Ă������̂Ƃ͈قȂ��Ă����B���̕ǂ���o���e�L�X�g�́A�㐢�Õ��ƌĂ�܂��B�ʂɁA�n�c��̕����̌�ł��O����ɂ͌��`�Ŏ�Ƃ̃e�L�X�g���o���Ă���҂������B����́A���̐l���Ă�Ō�点�A�����M�L�����B����������ƌĂт܂��B����܂Ŏc���w�̃e�L�X�g�́A�Õ��E�����̗������Q�Ƃ��ĕҎ[���ꂽ�Ǝv���܂��B
�۔��F�ǂ̉����ł��������g���̂ł����A�������̉����͊��Ɩ����炢�ŁA���̑��͉������Ƃ������Ȃ��Ƃ��܂����B
���c�F�i���m�Ɋ����łȂ��A�Ǝ��o���Ċ������x�z�����̂͌��Ɛ��ł��B�@���͊m���ɑN�ڑ��̒�����c�����o�ꂵ�܂������A�����͊����Ɣ��̋�ʂ͂Ȃ���Ă��炸�A������p���ė��߂Ɨ�������ē������Ă�����A����͒��؉����ł����B�v���⋧�������̋^�������邵�A���̎錳�������Ċ����Ə��^���ƖÑ������Z���ĕ������J��Ԃ��Ă������J�Ȃ̏o�g�ł���A�c��܂ŏ����Ɋ����ł��������ǂ������₵���B�j
��c�F�b���̕����͍b�������şu��̂��́B���͕����������܂���ł����̂ōb��������p���A����ɂ͎��`��Ӗ����ω��������Ə̂���A���̎��̂̂��̂��E�q�̎���ɗp�����Ă����B�㊿�̋��T�������ȍ~�̗l�X�ȏ��̂ƌ���W�߁A�ꌹ�A�g�p��������ɂ����B�n�Z��A�����̊����������ăe�L�X�g�ƒ��߂���������Ă������B
���c�F⽏��Ɨꏑ�̓G�W�v�g�ł����q�G���O���t�ƃf���e�B�b�N�݂����Ȃ��̂ł��B
�����F���ւ̋L���Ă��邱�Ƃ͍]�˂̐l�̏펯�Ȃ̂ł��傤�B�i�n�J������Ƃ͌����߂��ł��傤�B�ނ͗��j���̑n�ݎ҂ł��B
��c�F�����ɂ��Ă����̌����͎����ǂ����Ǝv���B��q�w�̂悤�ɉ��߂���͎̂�q�̓����̎Љ��f������̂Ǝv����B��q�͑T���D��ł����̂ł��蕧�����������Ă����B���オ�Ⴆ�A������Ή��ɂȂ����̂ł͂Ȃ����B
�����F�O����@�̖@�����܂����B
���c�F�����e���̔w�i�Ƃ��āA���������łƒ�������̌����ƂȂ��Ă����Ƃ��낪����܂����B����ɓ���Α��E�Ƃ͖����ł���̂Ŗ��ŁB�E���͂ł��Ȃ��̂ŕ����Ȃ��ł����B����͂Ƃ��ɒ����ȍ~�A�ߓx�g���e�n�Ŗ\��ē����Ԃł����B�ߓx�g�����͎���̂��߂ɏd�łƕ������ۂ��A��������邽�߂ɒ�����d�łƕ������ۂ��B����ŁA���O�ɂ͏d�����S�ƂȂ�܂����B���ꂩ�瓦��邽�߂ɁA���ɋ삯����őm�ƂȂ�҂����o�����B���ɔF�߂��Ȃ��Ă��䔯���Ď��x�m�ƂȂ�A�łƕ������瓦���҂��������Ă��܂����B�ؖ��́A����m�_�H���̕ʂɕ��������āA�Љ�Z�K�w�ƂȂ��Ă���B�_�͌܂̊K�w��H�킳�Ȃ���Ȃ炸�A���̂��߂ɔ_�Ƃ��敾���Ă���̂��Ɣᔻ���܂����B
�����F��������̑�̓h���}������Ă܂����A�����ɂ��Ă��l���̏I���ɋ߂Â��Əo�Ƃ���B�����A�ϗ��A�E�E�E�����ɖ߂�Ƌ~�����Ȃ����ƂɋC�t���B���q�⎺���̎���ł������������Ƃ�����B
�۔��F�V�c�Ƃł��o�Ƃ�����܂��ˁB
�����F�l���ɕs��������A�o�Ƃ���B
�۔��F�������o�ƁA�V�c�Ƃ��o�ƁA�V�c�Ƃł͒����̐l�����Ȃ��B
�����F�����Ƃ̃������Ƃ��Ă͎A�l�̂�����ƂȂ�ƕ����B
�۔��F���{�l�ɓ���݈Ղ��B
���c�F鰐W��k���A�헐�̎��A�~�����Ȃ��悤�Ȗ����ɂȂ�ƕ������L�܂�B
�۔��F�S�̍s���������ƂȂ�B
���c�F�����ɂ͍��x�̓N�w������܂�����w�ɂ͂��ꂪ����܂���ł����B��q�͕��������C�o�������A���̂܂܂ł͂��Ȃ��܂���̂ŁA���_���������܂����B
�����F�̗��z�A�����̎��A��Ƒ��̒��̂Ȃ���Ƃ��Ă̕�������~���A�Ƒ��̂Ȃ���Ŏ��߂�B���ꂪ�H���ƂȂ�Ɓu��v�Ŏ��߂�B�Ԃ̑��l�̐��ƂȂ�Ɓu�@�v�Ŏ��߂�B�̕��q�̈��A�q�������ގЉ����Ă䂯�Ȃ��Ȃ�B
�۔��F�˂Ȃ�Ȃ��̐��E�B�ł������Ղ͕�̑r�ɋ����ɋA��O�N�̑r�ɕ����Ă���A�̂̂��Ƃ��e�����Ă��܂��B
���c�F�N�b�ƕ��q�A���q�̃��������D�悳��A�N�b�̋`���Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�Ɛb���e���h���A�e���S���Ȃ�̋��őr�ɕ����Ƃ����Ύ~�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����o�������ɂ��邱�Ƃ�����܂����B
�₹�䖝�̐�
���c����� ���W��
�A�u�`�㔼�͂�����
youtube
�����́A����@�g�́wዉ䖝�̐��x�����グ�����Ǝv���܂��B�R��ōւ̎v�z������܂Ŏ��グ�Ă��܂����B���ꂩ������D�ցA���������A�I�R����Ƃ������ō֊w�h�̐l�����̎v�z�ɂ��āA���グ�Ă��������Ǝv���܂��B�����͍]�ˎ��ォ�炿����Ɨ���āA��q�w�̑ɂɂ���͂��̖����̕��V�@�g�̘_�����グ�����Ǝv���܂��B���V�͔���q�w�ł���͂��ł����A���C�M�Ɖ|�{���g����N�Ɏd���A�]�˖��{���I���Ζ������{�Ɏd���Ē��y�������Ȃ��l�ɁA���Ƃ̊�@���������܂����B���V�̐�����A���x�����Y���ƃR�~���j�^���A�j�Y���̐���������̕����ōl������Ǝv���A�����グ�����Ǝv���܂��B
�������N�@�w�����_�V�T���x
�����\�N�@����푈
�������N�@����{�鍑���@���z
������O�N�@����J�݁E���璺��
������l�N�܌��\����@��Î���
������l�N�܌��@�|�{���g�O����b�i�`��ܔN�����j
������l�N�\�ꌎ�w?�䖝�̐��x�E�e�@���C�M�A�|�{���g�A�ؑ��H�M�A�I�{���_�A���엊�ϓ��Ɍ�����
���������Ȃ��痬�z���ēǂ܂�A�]���ƂȂ�
�����O�l�N�ꌎ����w�����V��x�Ɂw?�䖝�̐��x������
���N�����\�O���@���x�h��w?�䖝�̐���ǂށx
���N������ܓ��@�����V��ɂāwዉ䖝�̐��ɑ���]�_�ɏA�āx���\
ዉ䖝�̐��́A���V��������\�l�N�Ɍ��������ɒm�l�����Ɍ������_�]�ł��B
������\�l�N�Ƃ����A����{�鍑���@�����z���ꂽ�̂���\��N�A����J�݂����̗��N�̓�\�O�N�ł����B���̎����̓��{���{�́A����푈������������̂̎��͍���ʼn�X�ɂ�����������Ɨv�����鎩�R�����^���̓˂��グ�ɒ��ʂ��܂����B���������@���z�ƍ���J�݂ŏ���A���ۓI�ɂ͕s�����������̂��߂ɗƌ��𑱂��܂������Ȃ��Ȃ��O�i���Ȃ��A���̂悤�Ȏ���ł����B
������\�l�N�ɂ́A�����������V�A�c���q�����ꌧ�̑�Âŏ���������ĕ�����������Î������N����A���{���ɏՌ�������܂����B���卑���V�A�̍c���q��V�������{�̌x�����P�������A�Ƃ��������́A�����������V�A�Ƃ̐푈�̌����ɂȂ肩�˂Ȃ��B�����ɑ�����{�̐��{�Ǝi�@�Ƃ̑Ή��ɂ��Ă͏ȗ����܂����A�Ƃ����ꂱ�̎������ĊO����b�͎��C���āA�|�{���g�Ɍ�サ�܂����B
�|�{�͂��̑O�̎����ɂ͕�����b�����߂Ă��āA��C�푈�ł̔s�҂ł���Ȃ��疾�����{�ł߂��߂��o�����Ă��܂����B�wዉ䖝�̐��x�́A����Ȏ����ɉ|�{�⓯�������b�̏��C�M�̐i�ނɂ��ċꌾ��悵���_�ł����B
�����͎��Ȃ���ɔ�Ȃ�
ዉ䖝�̐��́A���̈ꕶ����n�܂�܂��B�����������Ƃ́A�����������ƂƂ������̂͐l�ޑS�̂��猩��Ύ��I�ȗ̈�������Đ��E�̓y�n���敪�������āA����Ō݂��ɓG�������Ă���A�N�w�I�Ɍ���Ύ����ǂ����̑����ɂ����Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B���̗���́A����̗p��ł������x�����X�g�ł��镟�V�̊�{�I���E�ςƂ����ׂ����̂ł��B�܂����V�́A���x�����X�g�̗��ꂩ��A���Ƃɒ����𐾂��č��Ƃɖ�������A�G���Ƒ����ΈӒn�ł��킢�����A�Ƃ�������i�V���i���Y���̂��Ƃ��A�v�z�I�Ɍ���A�z�炵���A�����̐��E�ł���ƒႭ����킯�ł��B���̌����́A����̐�i���̍����ɂƂ��ẮA���͂�嗬�ł��傤�B
���N�������̖����ȂĂ��č����ŏ�̔������̂��邱���s�v�c�Ȃ�A�̂ɒ��N�����̕����i���j�͓N�w���ɉ�����Ώ�������l�ނ̎���Ȃ�ǂ�
���̂悤�ɕ��V�͌����̂ł����A����ɑ����āA
�����܂ł̐��E�̎���ɉ��Ă͔V���̂��Ĕ����Ɖ]�킴����A�����N�w�̎���͗����̌����ɂ���
�������āA�N�w�I�ɂ͂������Ȏ����ł���Ȃ���A���E�̎���ɂ����Ă͒��N�����͔����ƌ��������Ȃ��A�ƑO����|���̂ł��B���̘_�́A���V���������N�ɏ������w�����_�V�T���x�Ɠ����ł���A�����ŕ��V�͕����̋���Ƃ͓������������Ⴂ���̖��ł͂Ȃ��A���̍\�����邨�̂��̂̐l�Ԃ������ǂꂾ���m�͂�i�߁A�o�ϊ�����i�߁A�����������Ȃ����ɂ������Ă���̂��A�ƌ����B���������̍Ō�̏͂ɂ����āA�������{�����ɒm�͂ƌo�ϊ����̑��i��i�߂�̂́A���{���Ɨ���ۂ��߂Ȃ̂ł���A���{�l���͂�t���Ȃ���ΐ��m�ɂ����A�C���h�Ⓦ��A�W�A�̂悤�ɂȂ��Ă��܂��̂��A�Ƃ����h�q�̍�ł��邱�Ƃ��q�ׂďI���܂��B���V�́A���x�����Y���̗��O���猩��ΐl�Ԃ̊�b�͌l�̊����ł���A���Ƃւ̒����Ȃǂ͐�ΓI�ł���ƍl����ׂ��ł͂Ȃ��B�����������̐��E�ɂ����Ă͍��Ƃ����݂��A�Ȃ������V�̎���ł͐��m�̗����ƂƂ��Ĕm�̎㍑�����Ă��̖���z��Ƃ��Ă��錻����B����ɓ��{���ׂ邱�Ƃ�h�����߂ɂ́A���{���܂��l�̗͂�t���邵���Ȃ��̂��A�Ƃ����B����Η\�h�I�[�u�Ƃ��č��Ƃ̓Ɨ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�ƌ����̂ł��B���V�̘_�́A���O�Ƃ��Ă͐l�Ԃ̊����������č��Ƃ͂���Ȃ��A�������������Ƃ��č��Ƃ̓Ɨ������Ȃ�������Ȃ��A�Ƃ�����d�̘_�ɂȂ��Ă��܂��B�Ȃ̂ŁA���R���郊�x�����Y���ɂȂ肫���Ă���킯�ł͂Ȃ��A���Ƃ����Ď�q�w�̂悤�Ɏ������̂Ăč��̂��߂ɐ�����A�Ƃ���Ŏ�����̓����ł��Ȃ��B���V���A�P�X���I�̐A���n����ɂ����Đ��m���̃��x�����Y���Ɋ��S�ɋA�˂���킯�ɂ͂����Ȃ����B���V�̎���̎���́A�Q�P���I�̌���ł�������ǂ��납�S���ς���Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ǝ��͎v���܂��B
�����ɍ݂Ă͍�������䅓���Ȃ���嫂������̕ϑJ�ɏ]�č��̐����Ȃ����A�������ɋy��ł�牁i�Ƃāj�����Ƃ̒n���ێ�����ɑ��炸�p�ł̐����ɖ��Ȃ��嫂��A��������̙F��������ċ����邱�Ƃ��ׂ����A���ۂɗ͐s���đR���ɝ˂��͐����l��̑R�炵�ނ鏊�ɂ��āA�����g���ĉ]���A����̑�a�ɉ̖]�Ȃ��Ƃ͒m��Ȃ�����A���ۂ̗ՏI�Ɏ���܂ň��̎蓖��ӂ炴�邪�@���A
���́A�����������Ƃ��ɂ���ł������x���A�s�F�Z���ł����Ă��Ō�̉\�����̂Ă���蔲���A���̂��Ƃ��V�́uዉ䖝�v�ƌ����܂��B�����̕���̕a�̂�����́A���V�͑v�̕��V�˂̓`�L������p�����̂ł��傤�B���D�ւ́w�����⌾�x�̕��V�˂̊��ɂ����ē��l�̌��t���o�Ă��܂����A�w�����⌾�x�͖����̃x�X�g�Z���[�{�ł���A���V���S�ʓI�ɋ��������Ƃ͎v���܂��K���ڂ�ʂ��Ă����͂��ł��B
��v�̑厖���ɋ���S��K�s�͌ł��^�����ɂ��炸�A�J��p��E��ň�����⎁���J�𑶂����邱�����v�Ȃ�Ɏ�����ǂ��A�㐢�̍�������҂��o�d���d�Ďm�C��{���Ƃ���ɂ͛\�a�_�҂̌Ƒ���r���Ď��_�҂�ዉ䖝����炴��炸�A���������҂����Ɏ���܂ŏL�F�̖�����ɂ��鏊�ȂȂ���A
�����ŕ��V�́A��v�̗��j���Ђ��Ƃ��܂��B��v�͍ŏ��k����U�߂Ă������i����j�Ɏ�s���ח��������A�ؖk���̂���A�h�����čc���⎁�̎q����ő��ʂ����Đ������܂����B���̂Ƃ��v�R�͓�������ꂸ�A�e�n�Œ������鏫�R���߂��߂��ɋ��̐N�U��H���~�߂Ă���ł����B�����ŋ��ɕߗ��ƂȂ��ĉ�����ꂽ�`�w����ɋA�҂��āA�����̎������������B�`�w�͋��ɉ����͂܂��ꂽ���A����Ƃ��ア��v�ł͋��Ɛ키���Ƃ͖������Ɣ��f�������A���͋��ƍu�a���邱�Ƃ�����B���ۋ��R���쒆���ł̐퓬�͕s���ŁA���]���čU�ߐ邱�Ƃ��ł����ɂ����B�������O���Ő���Ă��鏫�R�̊x��͍u�a�ɖҔ��œO��R����咣�����B���ʂ͂悭�m���Ă���Ƃ���A�x��͑ނ����ĎE���ꂽ�B�㐢�A�����ł͊x��͋~���̉p�Y�Ƃ��Đ_���J���A�_�ƂȂ����x��̑O�Ő`�w�͔����Ђ��܂����ċ��������������Ă��܂��B���l�̂��Ƃ���v�̍Ō�ŋN����A��v�̍c��̓����S���̐N���ɍ��y���r�炳��邱�ƂɔE�т��A�t�r���C�ɍ~�����ċ���������B���������V�˂͍~�������ɁA�v���̈⎙�𐄑Ղ��āA�v�����S�ɖłт�܂ōR�킵���B�L�F�Ƃ́A�L���ɂ����Ƃ悢�ɂ����̈Ӗ��ł��B���V�́A���j�I�ɂ͕����錋�ʂƂȂ����Ƃ��Ă��A�㐢�ɏ̂�����̂͊x�V�˂ł���A�`�w�͔l���邱�ƂɂȂ������Ƃ��w���܂��B
��������A���C�M�ᔻ�Ɉڂ�܂��Bዉ䖝�̐��Ŕᔻ�����_�́A��ł��B��́A���C�M���R��ł����ɂ�������炸�A���v�Ȑ�������Ƃ����ړI�������č]�˂������������Ƃł��B����ɂ���Ċm���Ɉꎞ�̂��ƂƂ��Đl���͏����������A�����ƒ������Ԃɑ����ׂ��m�������Ȃ�ꂽ�Ɣᔻ����B���V�́A���̎m���Ȃ������~���������Ƃ��A����������{���ǂ����̍��̐N���ɍ������Ƃ��A�܂����l������邽�߂ƐN�����ɖ����~�����͂��Ȃ����A�ƌ��O����̂ł��B
������́A����͏��ɉ����ĉ|�{�ɑ���ᔻ�ł����A��l�͖��{�I�����̑啨�ł���A���͍]�˂𖾂��n���A�|�{�͖��{�c�}�𗦂��Ĕ��قŔs�k���A����������{���I��点�Ă��܂����ɂ�������炸�A�Ȃ�ŐV�����������{�ő���U���Ċ������Ă���̂��B�|�{�Ȃǂ́A����?�䖝�̐��������ꂽ�Ƃ��A���{�̊O����b�܂ł���Ă��܂����B��q�w�ł́A��N�Ɏd���邱�Ƃ͍Œ�ڗ�̍s�ׂł���Ɣᔻ�����B�R��ōւ���D�ւ������Ƃ���A�N�b�̋`�͎���������̗ϗ��ł���A��N�ɂ͗��炸�����܂ŕt�������A��N���|�ꂽ�Ƃ��ɂ͂���ɏ}���Ĉꐶ��r�ɕ����̂�����ׂ����B��������Ɖ|�{�́A���Ďd�������{�Ȃǂ����Y�ꂽ�Ƃ����悤�ɁA�������{�Ŋ������Ă���B���V�́A�������b�ł���Ȃ��疋�{�ŖS��͖������{�ɏo�d������s���Ƃ��ĕ�炵�Ă����I�{���_�ɂ���ዉ䖝�̐��������āA�傢�Ɏ^�����Ƃ������Ƃł��B
���V�̓��x�����X�g�ł���܂������A���Ƃ����Ď�N�⍑���ȒP�Ɍ��̂Ăď�芷���郂�����ɑ��āA��@�����������ɂ͂����Ȃ������B���̂ւA���V�����S�Ȃ郊�x�����Y���A���S�Ȃ鐢�E�s���ƂȂ�Ȃ������Ƃ���ł��B���V�́w�����_�V�T���x�Ŏ�q�w�������҂ǂ��ᔻ���Ă��܂��B�ł����A���́w?�䖝�̐��x��ዉ䖝�͂܂�ʂ��Ƃ�������Ȃ������ɂƂ��ĂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�ƌ��킴������܂���ł����B��q�w�Ƃ����̂́A�����̗��v�ɂȂ邩��Ƃ����ĉƑ����N�����ւ��邱�ƂȂǂ͂��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�����ɕs���ł�ዉ䖝���Ď���A�Ƃ��������ł��B
�����F�I�풼��̐e���̎�����v���o���B
�۔��F���l�ς��ς��܂����B����@�g�̓��x�����X�g�̍l���������鏭�Ȃ��l�B�t�Ƃ����l�����܂����B
���c�F����͑��̓K�m�ŗ��w���w�сA�����̏���ǂ�ł���A�����̎v�z�𑁂����猤�����Ă��܂����B
�۔��F����̐l�ł͂Ȃ��A�����̎v�z���w��ł����Ƃ������Ƃł��ˁB
���c�F�A�����J�̎��R��`�̎v�z�ŁA�������������ł����B���m�̗ϗ������_�ł͂Ȃ��A�X�l���m�͂����߁A�l�Ƃ��Ď������邱�ƂŁA���̓Ɨ��𐬂����Ƃ�ڎw�����̂ŁASelf-help�i�����j�̓����ł��B�A�����J�����߂Ŏ��R���̎���B�ێ�̊����Ԃ�������A���璺��ƂȂ�܂����B
�۔��F����@�g��ǂ��Ƃ�����܂����A�o���Ă���̂͂ЂƂ����A�l�͈ꐶ�����邱�Ƃ�v���Ƃ������Ƃł����B
�����F�Ⴂ���ɂ́A�u�V�͐l�̏�ɐl�����炸�A�l�̉��ɐl�����炸�v���L���ł����ˁB�v���e�X�^���g�I�ŁA�W�����E�X�`���A�[�g�E�~���̎��R��`�B�Љ�_��I�ȍl����������A�x�z�҂Ɛl���̌_��W�ɂ����āA���͂�|�������I���R������B���V�Ƃ��ẮA�v���e�X�^���g���\�T�G�e�B�i���Ё��Љ�j�����悤�ɁA��l��l���Ɨ�������ŎЉ���x���Ă������Ƃ��������ƂƂƂ炦�Ă����̂ł��傤�B
�۔��F�A�C�f���e�B�e�B�[�A�l�̓Ɨ���厖�ɂ����B
�����F���̗͂������č��Ƃ����藧�B�����V���{�ɂ͐l�ނ��R�����A�i�|�{�����������j���{�̖�l�ŗL�\�ł��������̂����Ȃ���A�����̍��Ƃ͐��藧���Ȃ������B
�۔��F���C�M�ɋ߂��R���S�M�ł����A�ނƂȂ�Έꏏ�Ɏ��ɂ����v����ʂ̐l�ŁA��q�ɐɂ��܂�ĖS���Ȃ����B�]�ˏ閳���J��𐼋�����ƌ������͓̂S�M�ł����A�����������ɂ����Ă䂩�ꂽ�Ƃ���A���C�M���Ă��������l���Ǝv���܂����B
�����F�X�쐴�b�ŏ��������ƌ��������ƂɂȂ��Ă���B���������l�����邪�A���������Ă����B
���c�F����@�g�͖������{�ɂ͏o�d���Ȃ������B�uዉ䖝�̐��v�͐e�����l�̊Ԃɔz�z���ꂽ���̂ł����A���b�ł����ē������������{�ւ̏o�d��f��W���[�i���X�g�ƂȂ��Ă����I�{���_�i������Ƃ��傤����j�̑E�߂Ŏ����V��Ɍf�ڂ��ꓯ�Ђ���o�ł���܂����B����ɐ�ď��C�M�Ɖ|�{���g�ɑ��e�𑗂��Ă��܂��B������́A�c�_�����������������Ȃ����A�ʗ_�͑��l�̂��邱�ƂŎ����̂��Â���m����̂ł͂Ȃ��ƕԓ������������A�|�{����́u���̂����ԓ�����v�Ƃ������܂ܕ��S���Ȃ�܂����B
2024�N11��2���i�y�j��w�͋变�A�����⌾
�{���́A���{����A���䂳��A�۔�����A���c����A��c����̌ܐl
���c����̃��W��
��w�͋�i��-08.pdf�j�̍u�`�͂�����@youtube
����Ǝ���́A��w�͋变�̖����ƂȂ�܂��B�Ўq���v������A���̓������p���҂͐₦���B���̌�̓e�L�X�g�͎c�������A������ϗ��Ƃ��Ď��H���A���������ɏ]���ĉ^�c���邱�Ƃ́A�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B����ɉh�����͔̂��������͂⎌�����������̋Z�\�A���������Ƃ������N�w�͍��������ۂ̗ϗ��ɉ��̉v���Ȃ������A�Z�p�����œ������Ȃ��e��Z�\�̕S�Ƃ����A����炪�ɉh���鎞��A��q���猩������̎���ł������B
���ɓ��͖ŖS���A�ܑ�\���ƌĂ�闐���������I�������B���̖ŖS�̌o�߂͂��Ɏ������~�̏X�����̂ŁA��S���͉����̗�������������̌��b�ł������͂��Ȃ̂ɁA���̓��̍Ō�̍c���ވʂ����ęӒD���A�Ō�̍c��Ƌ��b�������F�E���ɂ��Ă��܂����B����Ȃ��Ƃ́A鰂̑����e�q������Ȃ������B���̎�S���͑��ʂ����ɂ�������炸����S���ł����A���q�ɔ������N������āA�h���E����Ē�ʂ�D��ꂽ�B�ȍ~�ؖk�ʼn����͌ܓx��サ�����n�������ǂ܂�ŒZ���ł������B�������q�͌܋G�̐����ƌĂ�ł��܂��B��q����ʂ͏���Ɏ��ւ��Ă͂����Ȃ��A�ƒ�̒����͐������Ȃ���Ȃ�Ȃ��A����������������҂͎������~��D�悳���Ă͂����Ȃ��A�ƌ����̂́A�O�ܑ̌オ���܂�ɗ���Ă������Ƃւ̔��Ȃł��������Ƃ�����ł��傤�B
��q�́A�V�^�������čĂёv���͓�������ɂȂ����A�Ə����Ă��܂��B��������́A�v�̗̓y���g�債���Ƃ��A�v�̍c�������N�����ł���A�Ƃ����̂��Ă���̂ł͌����Ă���܂���B��q�������Ă�������̑v�͓�v�ŁA�k�����͋��ɐ�������Ď����A�̂߂ǂ͎�q�̐��U�����Ƃ��Ȃ������B���̍c����A���̉����ɔ�ׂē��i�D��Ă����킯�ł��Ȃ��B��q���̂��Ă���̂́A���̑v��Ɏ�w�����������A�Ƃ������Ƃł��B�����͈ꎞ�̂��Ƃł���A�v�z�͉i�����đ����B��q�́A�v�z�̌ւ炵���������đI��Ŏ����グ���̂ł����B�����̑v�̐����I�Ɛт��������Ă���킯�ł͂���܂���B
���ہA�v��̒m���l�����̊����͉����ł����B�k�v�ł́A����q�⒣��������q�ɂȂ���v�w��W�J���܂����B���j���ł͉��z���Ǝi�n�����������A�i�n���̎����ʊӂ́A�ҔN�̂Ƃ������q�@�ł��B����܂ł̗��j���͋I�`�̂ƌĂ�āA���j��̏d�v�l���������ꊪ����`�ɂ��ď����Ă����B�i�n�J�̎j�L����\�ł��B����͎i�n�J�̂悤�ɏ��ȏ����肪�����ΐl���̓`�L��i�Ƃ��Ėʔ����̂ł����A���j�̗��ꂪ�悭�킩��Ȃ��B�����ʊӂ̕ҔN�̂́A�ߋ��̒����̗��j����N���Ƃɏ��������̂ł��B���N�̏d�v�Ȏ�����ǂ��ė��j�̗����ǂݎ�邱�Ƃ��ł���悤�ɍ���Ă��āA����̗��j���ɂȂ������I�ȍ�i�ł����B�����ʊӂ́A��q�ɂ��傫�ȉe����^���܂����B��ɏo�Ă���\�݂�A�V�@�̉����A�h�g�E�h�Q�̌Z�킽���͓��v����Ƃɐ������āA���l�łȂ��������ł����B���̎���̊��������́A�����ɓ����ő�̒m���l�ł�����A�X�[�p�[�G���[�g�����ł����B�ȋ��Ŋ������̗p����悤�ɂȂ������ʂł����B���̃X�[�p�[�G���[�g�����ł����Ă��A�v�̖ŖS��H���~�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ������̂ł����B���{�ł͑喼�������ő�̒m���l�ł�������́A����܂���B���{�ł͐����Ƃƒm���l�́A�������Ƃ������̕����������Ċ������Ă��܂��B���݂̒����͂�����ƈႤ�悤�ł����A���Ă̒��������ł͐����Ƃƒm���l�̓C�R�[���ł����B
�����Ŏ�q�͓���q���w��w�x�̉��l���Ĕ����������Ƃ������܂��B�w��w�x�́A���Ɓw��L�x�̈�тł����B���̍�҂ɂ��ẮA�N�����������Ƃ����L�^����������܂���B�w���f�x�͎q�v���������A�Ƃ����L�^�͂���܂��B�w�_��x�́A�E�q�����������̂ł͂���܂���B�������E�q�̎���Ɏ�Ƃ̐l���������Ԃ������Ă܂Ƃ߂Ă��������Ƃ͖��炩�ł��B�w�Ўq�x�͖Ўq����q�Ƃ�������ɂ܂Ƃ߂��A�Ƃ����L��������܂��B�������w��w�x�ɂ́A���̂悤�ȋL�^�͉�������܂���B����܂ł́A���ʂɒ��ڂ���Ă������ł͂���܂���ł����B
�ؖ����A�͂��߂āw��w�x�̏C�g�ĉƎ������V���A�̗ϗ������̐��������ł���Ǝ��グ�Č������܂����B�v��ɂȂ�ƁA���́w��w�x���ϗ����Ƃ��ėD��Ă���A�Ƃ����ӌ����L�͂Ȋw�҂����ɂ���đ����Ă����܂����B
�ȋ��ɋy�悵���V�K�̐i�m�ɑ��āA�c�邪�����ɐȂŌ䏑�w��w�x�w���f�x�w��L��s�сx���������銵��B
���v����Ƃ̑\�݂��A�u�w��w�x�w���o�^�͕сx�́A�����̍��{�ł���ƌ������B
�i�n�����A��w���͂��߂ĒP�Ƃ̏��Ƃ��Č������A����t�����B
����q�Ƃ́A����[����]�E����[�ɐ�]�̌Z��ŁA�k�v�̐l�ł��B������Ɋw�т܂����B����[����]�͔ނ�̂��Ƃ������ɓ�����w�҂ŁA����q�ƕ���Ŏ�q�w�̗��_�I�N����������l�ł����B���̓���q�́A��w�ɂ��Ă����݂Ȃ��܂����B
- �w��w�x�͍E�q�̈⏑�ł���A�_��Ўq�ɕC�G���鐹�T�ł���B
�u��w�͐��l�̊����Ȃ�v
- �w��w�x�́A�ŏ��Ɋw�Ȃ�������Ȃ��B�u���ɓ���̖�͑�w�ɔ@�i���j�͂Ȃ��A���̑��͘_�Ђɔ@���͂Ȃ�
- �w��w�x�ɂ͍��ȒE�R������A�C�����K�v�ł���B
��q�́A���̌������p�����܂��B
���̃y�[�W�ɁA��q�̌����̗v�_���܂Ƃ߂܂����B
��@�����͐퍑����̖Ўq����A�v��Ɏp���ꂽ�B
�ؖ��́Aw�̓����͍E�q�Ўq�Ɏp����āA�����ŏI������ƌ����܂����B��q�͂��̌���Ȃ��܂��B�Ўq�̎���ɁA��O�Z�Z�N�ԓ����͒f�₵�Ă����B�����Ɏ�����A����q��������āA�������Ĕ��������B����q�̋��͎҂ł��钣�ڂƂƂ��ɁA�ނ�̋������Ĕ������ꂽ�����ł���B�E�q�Ўq�̐������ǂݕ��͔ނ�̊w�ł���A�㐢�̎҂͔ނ�̒T���𖾂炩�ɂ��āA�����ǂ��Ċw�яC�{����̂��B������́A��q����������܂łقƂ�ǖY����Ă��܂����B�������q�͓���q�̎t�Ƃ��Č������A�ߎv�^�ɂ��̌�^�����^���A��q�ȍ~�͎�q�w�̑c�Ƃ��đ��d�����悤�ɂȂ�܂����B�O�ɂ��\���܂������A�؍��̍����͎�����̎v�z�Ɋ�Â��Ă��܂��B��q�͓���q�����Ċw�ԁA�Ƃ�������ł������A��q����Ɍ��ЂƂȂ�����́A����������q�ȍ~�ɉ����ꂽ�B����q�Ɋw�k���������ɉ���A���]�F���������B���]�F�ɁA��q�̕��̎鏼�Ɨ�?���w�B��q�͗c�����ɕ����狳�����������N����ɕ��Ǝ��ɕʂ�A���l���Ă��痛?�Ɋw��Œ��q�̊w���p�����B�������Ď�q�Ɏ��铹����������悤�ɂȂ�܂����B
���@�w��w�x�͍E�q�̈⏑��\�q�Ɩ�l�������L�������ł���B
����́A���q�������o�������Ƃł��B�����͂���܂���B��w�͍E�q�̈⏑�ł���Ƃ݂Ȃ����o�Ƒ\�q�̉���Ƃ݂Ȃ����`�ɕ������܂����A���q�͌o�ɂ��āA����قǂ̌��t�͍E�q�ł����c�����Ƃ��ł��Ȃ��A�Ƃ��������܂���B�`�ɂ��ẮA���̓��e�����f�E�Ўq�ƈ�v���Ă��邱�ƁA���ɑ\�q�̌��t�����p����Ă���Ƃ��납��A�\�q�Ƃ��̖�l�̍�ł��邱�ƂɊԈႢ�Ȃ��A�ƌ����Ă��܂��B��������������A����������܂���B����ł���q�͒��q�����̏�����ʑ��d�������Ƃ����S�Ɏ���āA��w���l���Ɉ����グ�܂����B
�O�A�w�Ԏ҂́w��w�x�w�_��x�w�Ўq�x�w���f�x�̎l�����w��Ŏ��H���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
��q�́A�l����K�ǂ̏��Ƃ��Ďw�肵�āA�܌o�̏�ɒu���܂����B�l���́A���̑S�Ă�ʂ��ė������Ȃ���A�Ǐ��������ƂɂȂ�Ȃ��B�_�ꂾ���ǂނ��Ƃ��A��q�͋֎~���Ă��܂��B�܂���w��ǂ�ŁA�w��̍��i��m��Ȃ�������Ȃ��B���i�̂��Ƃ��u�K�́v�ƌ����܂��B�_���Ўq�́A���l���ɉ����Ĕ��������t�ł���B�Ȃ̂ł����ǂނ����ł́A���̉��ɂǂ̂悤�Ȋw��̍��i������̂����킩��Ȃ��B��w�͒Z���Ȃ���A�w��̍��i���S�đ����Ă���B�܂���w���悭�ǂ�ŁA�E�q�Ўq�̓��Ƃ͂����ڎw�����Ƃ��Ă����̂ł���A���̉���M����{��l�����Ɍ����āA���Ȃ������͂����ڎw���Ȃ����A�ƌ������Ƃ��Ă����̂��B����𗝉��������Ę_����E���ǂ݂��āA�����E�q�̂��Ƃ��킩�������̂悤�ɍ��_����̂́A�ד��ł����Ď�q�͂��������ɔF�߂Ȃ��B�������邵����������܂��A��q�͎l�������̂悤�ɑS�̂œǂނ��Ƃ����߂܂��B
�l�A
�w��w�x�w�_��x�w�Ўq�x�w���f�x�̎l���́A�����u���v������Ă���B�i�_�Ј�v�j
�����ŁA�_��ƖЎq�͓������Ƃ������Ă���A��w���f�������ł���A�Ƃ�����q�̌������o����܂��B�_�Ј�v�ł��B�Ȃ̂Ŏ�q�́A�_��̌��t��Ўq�̌��t�ʼn��߂��܂��B�t�������ł��B�E�q�ƖЎq�ƁA���ꂩ��\�q�Ǝq�v�̐������u���v�͂��ׂē����Ȃ̂ł��邩��A�������Ă͂����Ȃ����R�͂Ȃ��B�������A����͎v�z�j���猩��Ƃ��������B������q�͎v�z����j�Ƃ��Č����ɁA���̎n�܂肩�瑱���s���́u���v��ǂݎ�낤�Ƃ��Ă���̂�����A����ł悢�Ƃ����킯�ł��B
������ƕt�������܂��ƁA��q���Ȃ��w�̓����͂邩�㐢�̏t�H�퍑����܂ŕς�炸�Ɍp�����ꂽ�ƌ�����̂��B���̍������A��q�͎l���̒��f�͋变�ŏ����Ă��܂��B�_���H�тɁAꟂ��w���u��i�܂��Ɓj�ɂ��̒�������v�Ɩ������Ƃ���B�����ďw���܂��Z�ɖ������A�Ƃ���B��q�́A���́u���v�����f�ł����āA�E�q�����A�E�q�̑��̎q�v�����̈Ӌ`���₦�邱�Ƃ�����āu���f�v���������̂��A�ƌ����B���f��w�Z���玞����u�ĂčE�q�A�q�v�ɂ������肻�̂܂p���ꂽ�A�Ƃ����킯�ł��B�_��ɂ͏w���Z�ɖ��������t���ȗ�����Ă��܂����A���o���Z敕тɂ͏ȗ������ɏ�����Ă���B���̌��t���A��q�͒��f�͋变�Ɉ��p���Ă��܂��B�Ƃ��낪�A���̏��o���Z敕т́A�㐢�̍l�̌��ʌÑ�̏����ł͂Ȃ��ĎO������ȍ~�ɝs�����ꂽ�U�����ł��邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B��q�́A�U�������w�̌��t���Ƃ݂Ȃ��đ�^�ʖڂɒ��f�͋变�Ɉ��p�������ƂɂȂ�B�s�����ꂽ���t���Ñ�̐����̌��t�Ǝv������Ř_�������q�w�͂��͂₱��܂ł��A�Ɣᔻ�̎�ɂ���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��܂����B
�܁A�w��w�x�ɂ͍��ȒE�R������A�C����������B
����͒��q�̌�������q���p�������̂Ȃ̂ł����A�㐢�ɔᔻ�ɂ��炳��܂����B���̉��z���́A���q���q�̍�Ƃ͂��������A��w�͂��Ƃ̎p�Ŋ������Ă���̂��A�ƌ����܂����B�̂̏����͒|�̂ӂ��ł���Ȃ��Ȃ߂���ŒԂ������̂ŁA�E�q�͔ӔN�ɈՂɖv�����āA�Ղ�ǂ݉߂��ĂȂ߂��炪�O��ꂽ�A�Ƃ����G�s�\�[�h���j�L�ɏ����Ă��܂��B�������Ĕ�̂Ђ��������ꂽ��A�Ȃ����ɂȂ��Ă��܂��B���Ԃ���������o���Ă���l�����Ȃ��Ȃ�ƁA���ԈႢ���o�Ă���B�܂��Ȃ̉��������������Ă܂��ƁA���̊Ԃ̕������ł��܂��B����ɖ{���͒��߂̂���ʼn��Ƀ������Ă��������̂��A�㐢�̐l���ԈႦ�Ė{���ɓ���Ă��܂��B�܂��������̒f�Ђ��Ȃ��Č��̏��̎p�ɖ߂����Ƃ����Ƃ��A���������d�Ȃ��Ă��܂����肷��B�̂̒|�Ɣ�Ђ��̏��́A�����������Ƃ��N�����Ă��܂����B����ŁA���q�͑�w�ɂ����ꂪ�������ɈႢ�Ȃ��A�ƍl�����̂ł����B���R�́A��w�͗��H���R�Ǝn�߂���I���܂Ř_���W�J����Ă���͂��Ȃ̂ɁA�����Ȃ��Ă��Ȃ��B��������ג����Č������ӏ�������K�v������̂��A�Ƃ������Ƃł��B
��q�́A���̂��߂ɗ�L�̑�w����ג����A����Ɍ����Ă���Ƃ݂Ȃ����ӏ��ɉ��M���܂����B���ꂪ�A���̃y�[�W�̕\�ł��B��w�͋�͒P�Ȃ钍�ł͂Ȃ��āA��q�������낵�̕����������Ă���̂ł��B��q�̌��t���A�u�^�i���ꂪ���j�A��{�ɉ����ėp�H�r�������B�_�E�ЁE���f�́A�p���ė͂��₳���v�i��q��ށA��w��@�j�̂��j�Ƃ���܂��B��q���l���W���̒��ŁA������͂��₵���͎̂��͑�w�͋�ł����āA�_��E�Ўq�E���f�̒��͂���ɔ�ׂ���債����Ƃł͂Ȃ������A�Əq�����Ă���̂ł��B
��i���݁j�ɂ��Ă̘b�ɂȂ�܂����B��͎��̋����ł��B�{���N�Y����o�����Ƃ������Ƃł��B���z�̔Q�荇������ł��{���N�Y�ƖԂ̃{���N�Y���ϋl�߂����̂���o�������̂ŕz�ɋ߂����́B�A�����̑@�ۂ��ޗ��ɂ��č����̂ŁA�㊿�����(�������)������105�N�ɏ��߂č�����ƌ����Ă���B
�|�Ȃ��q���ł�����͎̂���R�ł͂Ȃ��v�i����j�ł������B�v�͓����̔炩��т���苎��A�A�����������́B
�M���V�A�ł͐܂肽���ݎ��̘X�i�낤��j���p����ꂽ�B�X�̕\�ʂւ̏������݂́A��M�i�X�^�C���X�j�ƌĂ���̂Ƃ����������g���čs�����B�����������������ɂ͉����^�������Ȃւ�̂悤�ȓ�����g���č�藎�Ƃ����B�����ȕ����̓p�s���X�ɋL���ꂽ�A�p�s���X�͈ꖇ�ꖇ���Ƃō��̂ő�ʐ��Y���ł��Ȃ��B�C�������Ă��Ȃ��y�n�ł͏��݂₷���J�r�ȂǂɐN����₷���A��ɂ͗r�玆�i�r�̔�Ɍ���Ȃ��j���p����ꂽ�B�����Ȃǂ͗r�玆�ɋL���ꂽ�B
�����F�v��������]�����Ă�����B������⋧���i���傤���傢��j�ł����A���̎��͒�����Q�i���傤�����j�ł��̌n���Ŗk�v���܂ő����A��v�Œ�̌n������Z�̌n���ɂȂ�܂�����`�������炢�����������̂ł͂Ȃ��ł����B�i�k�v���̑��@�����v����̍��@�܂ŁA�⋧���̒�̌n���B��v���̍F�@�����⋧���̎q���̌n���ƂȂ��j
���{�F��v�͑��̌n���ƂȂ�B
�����F�S�������̎��ɖ߂�B�i�ܑ㗝�@���狧���̒��j�̌n���ƂȂ��j
���{�F��v���炷��Ό��ɂ��ǂ����B
�����F�����ł́A�ٖ��������Ē��؉����Ă����Ƃ����l��������B������������x�����āA���邩���ɏo�Ȃ��B
���c�F�t�r���C�̎���A��v�̈�b�̑����͌��Ɏd�����B�����������Ȃ���A��ག̍c��ɂ͎d���Ȃ��Ƌ��ۂ����҂������B�������������ł͐������̂��₵���������������Ƃ��A�����܂Œ��̍c�邾���𐳂����Ƃ��Đ�Ώo�d���Ȃ��h�ƁA����������Ėk���̍c��ɏo�d����h�ɕ�����܂��B
����F��v�̉�����q�V�i���傤�������G���ƊG��ɗD��A��v�̉@�̉�ɑ��ĕ��l��������A�����l��Ƃւ̋��n���������B��v��łڂ�����ག̌��Ɏd�����j�Ƃ������ƂŁA����ȍ~�A�j���p���A����҂Ƃ��Ă������܂ꂽ�B�j�����܂��B���Ƃ��Ă��v�̊������E���ƍs�����o���Ȃ��Ȃ�܂��B
�۔��F�����v�̂��̂�~���܂����B�v�̂��̂͑f���炵���B
�����F�V�q���͌����I�ŁA�V���w�␔�w�Ȃǂ���荞�B
���c�F�t�r���C�̓`���M�X�n���ƈقȂ蒆�ؕ����d���Ă��܂��B�`���M�X�n���͐����������E�����̋��̂ł���ؖk�̒����l���F�E���ɂ��Ė��l�̑����Ƃ��āA�V�q���悤�A�ƍl�����B����ɑ��Č_�O�l�̑��ߖ뗥�^�ނ́A�ނ��됶�����Đł��Ƃ����ق������ł���Ɛi�������Ƃ����܂��B�`���M�X�n���̎���͂���Ȃӂ��ɒ����̂��Ƃ����Ƃ��v���Ă��܂���ł������A���̃t�r���C�͌��݂̖k���ɂȂ����s��z���A���������Ɋ�Â��đs��ȃv������������B�t�r���C�͓�v�̈�b�ɂ��U���������āA�d���邱�Ƃ����߂܂����B���̗U���ɕ��V�ˁi�Ԃ�Ă傤�j�ƎӞc���i����ڂ��Ƃ��j�͋��ۂ��܂����B
�۔��F���Yest�Ƃ��Ȃ��ЂƂ������B
���{�F��{�����ł��B
�۔��F�{��搶�̖{��ǂ�őv�̂��Ƃ��w��ł��܂��B�v�̕����͑f���炵���B
���c�F�v�͒��ł����A���͌��������S���Ń`�x�b�g�����A���}���k�ł��B�`�x�b�g�����́A�`�x�b�g�E�����S���E���F�̏@���ŁA����ȍ~�̓_���C�E���}���ō����ЂƂȂ����B�k���ɂ͋���ȃ`�x�b�g�����̎��@������܂����A����͐����̍c�邪�_���C�E���}�̎{��ł����Ċ�i�������̂ł��B�����E�����̍c��́A�k�������̃n�[���ł���A�k���������M����_���C�E���}�͍c��ƃ��[�}���c�Ƃ̊W�̂悤�Ȃ��̂ŁA����d���邱�ƂŖk�������̃n�[���Ƃ��Ă̐������Ă����B�����̍c��ɑ��Ă͐�ΌN��ł���܂������A����Ƃ͈Ⴄ�������������B����̒����̂�₱�����Ƃ���́A���̓�̐��E�̌N��ł����������̔Ő}���A�������Ƃ��߂��Čp�����Ă��邱�Ƃł��B�����S���E�`�x�b�g�E���F�ɂƂ��āA�����������x�����闝�R�͂Ȃ��B���������āA�������{�̓_���C�E���}���Β����ɓ���Ȃ��B
�����F����Ƀ_���C�E���}�̐��܂�ς������B
�۔��F�{���ɗ։Ă���Ȃ炷�������Ƃł��ˁB
�����F�؍��ƒ����̗��j�ӎ����قȂ�B�����́A���]����k���N�����⒆���̗̓y�ł������A�����j�̕Ӌ��Ƃ��A�؍��͒��N�����̗̓y�Ƃ��܂��B
��c�F����N�̗̓y�Ǝ咣����A�����̕��w���ŏA�E���邱�Ƃ͏o���Ȃ��Ȃ�B
�����F�o���J�������ł�������肪�N���Ă���B�M���V�A�̏o�y��������A�M���V�A�̂Ƃ���B�i�V���i���Y�������ނƑ�ςȂ��ƂɂȂ�B
���{�F�}�P�h�j�A�ɂ�����܂��ˁB
�����F�A���S�X����|���g�X�ɂ́A�w���h�g�X���L�����M���V�A�l�̉����B�����������̌Ñ�̏Z���̓g���L�A�l�ł����āA�M���V�A���b���Ă������{���̃M���V�A�l�Ƃ͂����Ȃ��B
���{�F�A���N�T���_�[�̃}�P�h�j�A�́A����̃}�P�h�j�A�Ƃ͈Ⴄ�i����̃}�P�h�j�A�l�́A�u���K���A�l�ɋ߂��B�X���u�l�ƃg���R�l�̍����ŁA�X���u���b���B�`�g�[�����̃u���K���A�ƌ��ʂ����ă��[�S�X���r�A�A�M�ɏ����ӎ���^���邽�߂ɁA�u���[�S�X���r�A�A�M�̃}�P�h�j�A�l�v�Ƃ����A�C�f���e�B�e�B��^�����B�P�X�X�O�N��̓Ɨ���A�Ɨ��}�P�h�j�A�ł͎��������̓A���L�T���_�[�剤�̌Ñ�}�P�h�j�A�l�̖���ł���Ƌ��ȏ��ŋ����ČÑ�}�P�h�j�A���i�V���i���Y���ɗ��p���āA�M���V�������{�������B�j
�����F�}�P�h�j�A�̓I�����s�A�ɂ͎Q���ł����B�M���V�A���b���M���V�A�l�ł������B
���c����̃��W��
�����⌾�i��w�͋�ߘa�Z�N�\�ꌎ.pdf�j�̍u�`�͂�����@youtube
�����F�������E���͓��{�ł��l�C������܂����A������������{�ōL�܂�܂������B�]�˂̌㔼�ł����H
���c�F���D�ցi1652�`1712�j�͎�҂Ƃ��Ēm���Ă����B����I�ɂȂ����͍̂]�ˎ������Ɉ���{���o����Ă���ł��傤�B�i�V���������u1781�`1800�v���З��ʎs�ꂪ�����n�߂��j
�����F��҂����łȂ��O���u�́A�]�ˎ���O���ł��ӊO�ɒm���Ă����B���䉉�Y�A�ŋ��ł����邩������Ȃ��B�����������̂����{�ɂ������Ă��Ă��܂������H
���c�F������Ȃ��ł����A�̕���̋N���͖��炩�ɒ����̋����ł��B�����̉��ڂƂ��āA���肠���肩��L�܂��Ēm���Ă����\���͂���܂��B���y�̑�\�I�l�`�ɍE��������܂��B�m�I�Ȓj���̐l�`�ł��B���\����ɂ́A���Ȃ��Ƃ����y�̌���҂����͒m���Ă����ł��傤�B�ߏ�������Ȃǂ́A�����ʊӍj�ڂ��炢�ǂ�ł����͂��B�����ʊӍj�ڂł͗����E�����̂����A�����i�n�@����Ă��܂��B�����ꍇ��Ȃǂ́A�����j�̊�{�m���������ď����ꂽ���̂ł��B��ʐl�����\����ɂǂ��܂Œm���Ă������́A������܂���B
�����F�u�O���u�v�̒��҂̒��͕��G�Ȑl�B冂̐l�ŁA鰉��A�����Ƃ͑Η�����B�i�n��鰂̖����Ɏ����������A(���̑��̎i�n�����T���ŐW�̍c��ƂȂ�)�B鰁A�W�ɂ��z�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B
���c�F冊���鰂ɖłڂ���Ă���A������鰂͐W�Ɍ�サ�܂����B�Ȃ̂Œ��ɂƂ��Ă͏I���������Ƃ��ď������Ƃ��ł����̂ł��傤�B���́A冊��̐l���ɂ���鰂𐳓��Ƃ�����j���ɂ��Ă͈ٗ�ȂقǂɎ����グ�Ă��܂��B�قƂ��鰁E冂͑Γ��̂悤�ł��B���͂��܂����x�ł��B
��c�F���́A���������̐l�Ƃ���A�i�n�J�̎j�L�̂悤�Ȓ����̗��j�̕Ҏ[���A����̒n�������njłɎh�����A�b��冂̒n���̗��j�ɋ������������B冁A���A鰂̗��j�ɒʂ��Ă���A�W�ɂȂ��āA���i���傤���j�Ɍ��o����A�O���u�̕Ҏ[�ɗp����ꂽ�B�������N���ʂ̓������s���A�������ē��Γ`���Ҏ[���Ă���B�������Ŕږ�Ă̂��Ƃ�������B
���{�F鰎u�`�l�`�ł��ˁB
���c�F�����⌾�ł́A�ӒD�����Ɏd���邱�Ƃ͕s���ł��邪���ڂɂȂ�Ǝd���邱�Ƃ����`�ƂȂ�悤�Ȃ�������Ȏ��Ԃ�z�肹����܂���B���D�ւ͓��{�ł͓V�c�������Ă���A���̂悤�Ȗ��͋N����Ȃ��Ƃ��܂����B�����͌��̍c��ɂ͎d���܂���ł����B�����S���̍c��͒��̍c��ł͂Ȃ��Ǝd�������B�R��ōւ̒�q�̂����A���������͍]�˂ɏo�܂����B���������D�ւ͗����ȗ����Ɛ����͓V�c�̙ӒD�҂ł���Ƃ������������āA�]�˂𓌕��ƌĂ�ŁA����𓌓s�ƌĂԂȂƌ������B���̎���͙ӒD�҂�����������Ă��邢��̂ŁA�����Ȃ�˂���̗U���ɂ��������A���s���o�܂���ł����B�������k���������������A�����S���ƈꏏ�Ƃ�����ł��B���������͓����_��_���A���������͂��������Ɣᔻ����ꕔ�̎҂̐���ᔻ���āA�T�������������l�͎��Ƃ��čs���̂��A�����ᔻ����͍̂E�q�Ўq�����l�ƔF�߂�����ᔻ���邱�Ƃł����āA�s������܂�Ȃ��ƌ����܂����B����ɑ��Đ̒�q�̎�ы��ւ́A�t���̐��Ɍ��{���܂����B���l�łȂ����݂͂��̂悤�Ȃ��Ƃ���ؘ_���Ă͂Ȃ�Ȃ��A����Ȃ��Ƃ�_���邩��ӒD�ւ̓����J����̂ł���ƁB���̂��Ƃ́A����ɘ_���܂��B
�����F���v�̗��͂��������A�u�ρv�Ƃ��Ȃ���ΐ����_���炷����������Ȃ�B���͗L�镐�m���V�c�𓇗����ɂ���Ƃ����������D���邱�Ƃ͋�����Ȃ��B
���c�F���D�ւ͔ޓ����u���v�Ƃ��܂����B
�����F�������A���a�V�c�܂ş��ΐ��a�����A�����V�c�̎q�����]���������B
���c�F�]�˖��{�́A�j�g�����肩�疾�m�ɍc�����d�̎p�������܂����B���Ղ�������������܂����B�̂悤�Ȕᔻ�ɑ��āA�]�˖��{�̙͐̂ӒD�҂����Ƃ͈Ⴂ�A�c���d���A���̏�ōc���ɂ͂ł��Ȃ������̐������s�\���グ�Ă���̂��A�ƁB����ŗ��R�z�͖k�������͂��������ƒ@���܂���܂����A�]�˖��{�͍c�����̐b�Ƃ��Ĉ��肵���������s���Ă���̂Ő������̂��A�ƕٌ삵�Ă��܂��B�]�˖��{�́A�j�g�ȍ~�͎��������̐��������c����������o�����ƂɋC��z���Ă��܂����B
�����F�ƍN���֒����Ɍ��Ə��@�x���o�����Ƃ��́A�V�c����Ɍx�����Ă��܂����B
���c�F���C���́A�R�Ȃ̕E�����Ǖ��ŁA�O��勴�Ɍ��������ƎR�Ȃ��畚���A���A�����A���V�����ŏI���������܂����B�O�҂����C���\�O���ł����A����͑喼���g�����Ƃ��ւ��܂����B�����̑喼�́A��₩�狞�s��ʂ炸��ÂɌ��������C���\������ʂ邱�Ƃ𖽂����܂����B�]�˖��{������Ƒ喼�Ƃ����т����Ƃ��A�ɓx�Ɍx���������߂ł��B�����j�����̂������̓��Ëv���ŁA�F������R���𗦂��ċ��s�s���ɓ��X�Ɠ������B���{�͂���𗯂߂邱�Ƃ��ł����A��͏��R���܂����狞�s�ɓ����ď��喼�ɑR���A��͓��Âق��L�͑�𐭎��ɏ�������āA�ߌ��Ȓ��B�ɑR���邱�Ƃ�����������Ȃ��Ȃ�܂����B
2024�N12��14���i�y�j��w�͋变
�{���́A���䂳��A�Z�c����A��_����A�۔������A���c����A��c����̘Z�l�A�Y�N��ɐ��{����A����
����ő�w�͋变���I���܂��B���牽��ǂނ��ɂ��đ�w�̖{���Ƃ��邩�A���f�͋��ǂނ��̉���B
��w�͋变
���c����̃��W���A
�u�`�͂�����youtube
�R���Č�ɌÎҁi���ɂ��ցj��{�ɂ��Đl���͂ӂ�̖@�A���S���B�̎w�i�ނˁj�A��R�i����j�Ƃ��ĕ��i�܂��j���ɖ��i�����炩�j�Ȃ�B
���S�́A�E�q�̂�݂��ւ��܂��S��́A���B�́A�]�q��i�Ȃ�сj�ɑ��̖嗬�̍���B�\�́B�w�́A�|��B��R�́A���Ȃ�ᤁi�������j�Ȃ�B����ɁA�S�ƙB�Ƃ́A��q�͂��߂Ă�����킩�Ă�B���q�̎��܂ł́A�����S�B�̂킯�Ȃ��肯��ǁA�ɐ�̉��{�̑�w�A�S���p���̂܂܂ɂāA�B���݂̂�����A�S���̎���ɂ��āA�����ꂵ���A���łɑ��̕����i�Ԃ�ׂ�j�̒[�i�͂��j����̂ɁA�������ւ�Ȃ�ׂ��B
���i���j���s�q�i�ӂт�j���ȁi�����āj����嫁i���ցj�ǂ��A�����K�i�����́j�ЂɎ��i���āA�������ƗL����o�i���Áj�����B
����薖�܂ł́A��q���̏��̏͋����̂��Ƃ���B�s�q�Ƃ́A�Ƃ���ʂȂ�B��q�t�ɛ����āA�Ȃ����i�ւ肭���j�鎌�Ȃ�B���i�Ƃ́A���́A�Ђ��ނ�`�B�i�́A�P�Ȃ�B��N�̓����A�l���Ђ��߂Ƃ�āA�킪�g���悭����Ɖ]�ӂȂ�B�Ўq�́A�E�q�̖�ɁA�y����ǂ��A��ɑ��̋���l�ɂƂ�āA�݂Â��炨���߂�Ɖ]���Ƃ��A���i�Ƃ��ւ�ɂ��āA��q�����q�̑�w�̐����ɁA���Â��蓾���邱�Ƃ��A�������ւ�Ȃ�B
���F
��q�̖��B����p����͔̂ڏ̂ł����āA���̂���E�ꑰ�̔N���҂��Ăю̂Ăɂ���E�t����q���ĂԁE�c�邪�b�����ĂԁA����ȊO�͎g���Ă͂Ȃ�Ȃ��B
���i�F
���ډ�Ȃ��t�����Ċw�Ԃ��ƁB���q�Ǝ�q�͎l�`����Ă���B
���̏�ਁi���j����ځi���ւ�j�݂�ɁA�P�𐜁i�����j�Ԃ��������B���i�����j���Ȃđ��̌�蛁i���낤�j��Y��āA�сi�Ƃ�j�ĔV���S�i���j�߁A��i�܂܁j����ↁi�Ђ����j�Ɍȁi���́j���ӂ��āA����荗��i����₭�j���ӁB�ȂČ�̌N�q��ցi�܁j�B
��ਂ�Ƃ́A�����[�i�Ă��j���炭���]�B���Ƃ́A��⑽�����]���i���ӂ��Ƃj�B���ɂ�قǂƉ]�`�Ȃ�B���́A�͂ȂB�݂���Ă��ł��邱�Ƃ��]�B���́A�����ȂӁB�����Ăق�т��邱�Ƃ��]�B��蛂́A�F���₵�Ƃ�ށB�ł́A�ʂ�����ӁB蛂́A�m���̂����ӁB荂́A��������B���̏��̂��܂��S���炴�邱�Ƃ��]�B���́A���낻���Ȃ�B���̐��̂��܂����Ȃ͂炴�邱�Ƃ��]�B�]�Ӂi���ӂ�����j�́A���q�����̑�w�̏����݂�A�Ȃ�����̏������ɁA�݂Â��炽�ւ��˂āA�킪��蛂Ȃ邱�Ƃ�Y��A���q�̐����Ƃ肠�߁A�����̊Ԃɂ́A�Ȃ��ӂ����āA���̏���荗����A��Ђ����ƂȂ�B���i����j�͋����`�Ȃ�B�W�i�������j��q�͋�̑�w�́A�ɐ�̉��{�ɂ��āA�X�əB���̂��ł����炽�߁A���q�i�v�̐����Ƃ�āA��͂�荕����ӁB�����P�̒��A�����͎��Ƃ̈ӂɏo����B����ǂ������̏��Ȃ�A���đ��̋`���߂����āA��̌N�q�́A�����ߐ������Ƃ�҂Ɩ�i�Ȃ�j�B
�Ɂi���́j�߂Ēm��G���i�����j���āA�߂i�̂��j��鏊�������Ƃ��B�R�i������j�ǂ����Ƃ̖��������A���i���傭�j�𐬂��̈ӁA�{�҂̌Ȃ����߁A�l�����ނ�̕��i�݂��j�ɉ��ẮA���������K��������������i�����j�ȂЖ������炶�Ɖ]�ӁB
�ɒm�Ƃ́A�ӂ�������ӂȂ�B�G�́A�ЂƂ���ӁB������������`�Ȃ�B���́A�z��邼�B���Ȃ�����邱�Ƃ��]�B���Ƃ́A�v�ƂȂ�B�����Ɖ]���@���B�����������𐬂��Ƃ́A�l�����������āA�悫�������Ȃ����Ƃ��]�B���́A�@�Ȃ�B���̒i�́A��q���ނ̎��Ȃ�B����ǂ����̏͋�A���ɓV���̋����A�w�҂̛��C�ɕ�Ђ��邱�ƁA���������ɂ��炸�B�̍E�q�t�H�����A��S�P�N�̓V�q�ܔ��̞܂��悹�āA�S���̑�@�����Ă������ʂӂ��Ƃ��A�݂Â���]���Ă̂��܂͂��A���m��҂́A���ꂽ���t�H���A����߂���҂́A���ꂽ���t�H���ƁB��q�̍��̌��i���Ɓj�A���̈ӂƂ��̂Â��炠�Ђ���B
���ȁF �K�B�ʊK�A���ہB
�~���i����j�ȓсi�������j�b�q�i�����j�A�V���̎��������B
�~���́A�v�̍F�v�̔N���B�ȓт͑��̏\���N�Ȃ�B��q�̖{���́A�]���̋J�B�i�����イ�j�Ȃ�ǂ��A���̒n��̎��A�V���S�Ȃ肯��ɂ��āA�ӂ邫���𑶂���ꂽ��B
�~���ȓсF ���� 1189
�N�B��q�ӔN�̌\��B��q�͎l���W���̎��M���l�\��ōs�������A��w�͋�͋�S�̍�œ�\�N�߂���ɂ悤�₭���������グ�Ē�{�Ƃ����B���������̌�������𑱂��A�Ō�̉����͂��̎��̋���O�ł������Ƃ����B
�V���̎����F ��q�̖{�т͋J�B�i�����イ)婺�����i�Ԃ���j�ŁA��q�̓����͐V���S�ɑ����Ă����B���݂͍]���Ȃɑ�����B��q�̑c��͑�X�J�B婺���ɋ��Z���Ă������A���̎鏼���i�m�ɋy�悵�ĕ����ɕ��C�A�����Ŗk�v�̕���ɒ��ʂ��Ă��̂܂ܕ��������Ɉ�Ƃŋ��Z�����B
�܂Ƃ�
���c��������W��
�ȏ�ŁA��w�͋变�͏I���ł��B��q�͒��q�̊w���p������A�Ƃ�������ŁA���q��������w�̃e�L�X�g�̕��ג����A�������Ă���͂��̉ӏ��ւ̉��M���s���܂����B��q������͙G�z�Ȃ��Ƃ��s�����̂Ō㐢�̔ᔻ��҂������A�Ƃ�������ł��邱�Ƃ������ŏq�ׂĂ��܂��B��������q�������ʼn��M�����i���v�m�̋c�_�́A�l���̒��f�ւ̉��߂ƕ���Ŏ�q�w�̖{�ۂƂȂ�A����ȍ~�Ɏ�q�w�����w�ƂȂ�����́A���S�Ȍ��Ђ̒���ƂȂ�܂����B����̉��z���A�]�ˎ���̈ɓ��m�ւ́A���̌��Ђɑ��ė����������Ĕᔻ���悤�Ƃ����҂����ł��B
��q�̐�������v����́A�܂���q�w�����w�ł͂Ȃ��A�������w�ƌĂꂽ�w��ɂ͂������̔h������܂����B�C�����͒���I�ȗ���ł���A���쌬�͏����̎�q�ɏՌ���^���Ĕނ̎v��������ɐi�߂錴���͂ƂȂ�A���ێR�͐S�w��W�J�����A�̉�Ŏ�q��ᔻ���鎍���Ԃ��āA�ނƌ����Ș_�����s���܂����B�܂����͘C�����̒�q�Ŏ����h�ƌĂ�āA���������̎��т���]�����܂����B�����h�́A�����͌o���ϖ��̎��тŕ]������ׂ��ł���A�����Ƃ̓�������ʂ��ŕ]������ׂ��ł͂Ȃ��A�Ƃ�������ł����B����͎�q�Ƒ�����Ȃ�����ł����B��q�͍E�Ђ̓����w�ԂƂ������Ƃ�w�ȗ��̐������ϗ����w�ԂƂ������Ƃł���A�������邪���ɂ���Ƃ������Ƃ͂܂������{���]�|�Ő������Ȃ����Ƃł����B��q�̃t�H�����[���A���ۂ̐�����������Ƃ̓�����D�悵�Ĕᔻ���s���悤�ɂȂ����̂́A��q�̎v�z��͕킵�����ʂł����B����Ŏ�q�w�҂͓��{�Łu���w�搶�v�ƌĂ�āA���������ߖʂ��Đ��̒��̂����鎖���Ƃ��召�̗L���l�Ƃ����P�V�J�����i�b�g�����Ɣᔻ�������̌��O�������`������Ő��̒����l�X�ł��邱�Ƃ����悤�Ƃ��Ȃ��l�A�Ƃ��ĝ�������܂��B��������q�͓�������ɑ��l�ȃ��C�o�����������ŁA����̌��i�ȗ�����т����܂łł����B���ꂪ���ЂƂȂ��Ă��܂����̂́A�㐢�̐����̌��ʂł��B
����ȍ~�A�ȋ��̏o��͎�q�w�ƂȂ�܂����B��q�w�́A�鍑�̉^�c�ɂ҂���Ɠ��Ă͂܂�D�s���ȋ��`�ł����B����́A��q�̎v�f���z���Č��ЂƂȂ�܂����B��q�w�́A����������҂ɓ��������߂܂��B����́A�ȋ��ɋy�悷�銯�������֎������������Ƃ��Ă܂��Ƃɓs�����悢�B��q�w�́A��q�̓��O�ȓw�͂̂��������āA�l���܌o�̂��ꂼ��̃e�L�X�g����̌����Ő��������邽�߂́A�_���̖Ԃ����菄�炳��Ă���B������w�ԂƎ�w�̃e�L�X�g����̌����Ő�������Ė������Ȃ��B�Ȃ̂ň٘_��ʌ������o�邱�Ƃ�����B����͎����w��Ƃ��čD�s���ł����B�t�Ɏ�q�w�͎�q�ɂ���Ă��܂�Ɋ������ꂷ�����̂ŁA��q�ȍ~�Ɋw���̔��W���ł��܂���ł����B����Ɏ�q�͎l���̒����������A�܌o���ꕔ�ɒ���t���A�c��͒�q������t���܂����B���̒��̓e�L�X�g�̈�͂��Ƃɕt�����Ă��āA������܂������̘_��Ƃ��ēs�����悢�B�ȋ��̐ݖ�́A�Ўq�Ƃ����f�Ƃ��̈ꕶ���o���āA����ɂ��ď����A�Ƃ������̂ł����B�ǂ̏��̂ǂ̏͂��甲���o�����͏�����܂���B���������āA�l���܌o�̌������ۈËL���Ă��Ȃ��҂́A�����Ńn�C�T���E�i���B������N���A�ł���҂́A���̈ꕶ�ɑ����q�����v���o���āA�l���܌o�̒��œW�J������q�̘_���ɏ]���č앶���A�����Ǝ��̌����͐�ɏo�����A���邱�Ƃ����߂��܂����B����Ŏ҂̊w�͂͑���ł���A�Ƃ������Ƃł��B�����⒩�N�ł͎�q�w�͂��̎v�z�̓��e�����A�ȋ��̎҂̊w�͂𑪂邽�߂̎����w��ƂȂ�܂����B
���{�̍]�ˎ���́A����Ⴂ�܂����B���{�͎�q�w�����サ�܂������A�킪���̕��Ƃ͐��P�̓����҂ł����āA�ȋ��͂Ȃ��A��q�w���w�ԕK�R��������܂���B���̂��ߍ]�ˎ���O���̕��Ƃ͕��D���ȏ��R��喼���w��A���邢�͍����Ȏ�҂������ē����̏p�����b���Ă��������͂���܂������A���Ƃ��Ђ낭��q�w���w�K����悤�ȋC�^�͂܂�����܂���ł����B�����h�q�����R�j�g���̊w�⓹�y�ɕt�������č]�ˏ�̏��������Ɏ�w���������肵�܂������A�ނ�͊w�ԋC������Ȃ��čŏ��͎��������r������͎���̂���߂ď���ɂ�点�Ď����͏���Ɏv�����Ă����A�Əq�����Ă��܂��B
�ނ���A�]�ˎ���Ɏ�q�w��^���Ɋw�ڂ��Ƃ����̂́A���l�����ł����B���l�����͐^�V�����A���w��ł����q�w���A�����ɑւ��f���炵�������Ƃ��Đ^���Ɏ��g�݂܂����B�������|�̒�q��������n�܂�A�R��ōւ̖剺�A�ɓ��m�ցA�����h�q�A����������l�ł�������A���Ƒm���ł�������A���邢�͖��ˑ̐��̉��ŕ��Ɛg������E�������l�����ł����B�]�ˎ���O���͂܂���q�w���A������Đ^���Ɋw��A��q�̒���ɌP�_���t�����ď�������܂����B�������ւ̉���́A�]�ˎ���O���̓w�͂̐��ʂ̈��ł��B�]�ˎ��㒆���ɂȂ�ƁA�R���f�s�A�ɓ��m�ցA�����h�q������q�w���悭�w�����҂�������A���x�͎�q�w�ᔻ�����o���܂����B���̒i�K���o�āA�]�ˎ������ɂȂ�Ə�����M�̊�������Ɋe�˂��ˍZ���J���A�����Ŏ�q�w���I�[�\�h�b�N�X�Ȏ�w�Ƃ��ċ�������悤�ɂȂ�܂����B���̒i�K�ł悤�₭��q�̎l���W����ߎv�^���A���Ƃ����ɂƂ��Ċ�b���{�Ƃ��Ď������i�K�ƂȂ�܂����B���̉������͒��l�ɂ���Đݗ����ꂽ�m�ł����A�����ŋ�����ꂽ�͎̂�q�w�ł����B�ȋ����Ȃ����{�Ő�������邱�Ƃ��ł��Ȃ����l���A�l�̓��Ƃ��Ď�q�w�𗘊Q���������Ŋw�̂ł����B���̉������Ŋw����|�R�⍲����ւ��A���x�͕��Ƃ����Ɏ�q�w�������邱�ƂɂȂ�܂����B������F�A�Éꐸ���A������ւ犰������̎�q�w�҂����́A���������ɑ��Ŋw��ł���]�˂̏����s�ɏ�����܂����B���{�ł͎�q�w�͎����w��ł͂Ȃ��A�����ɐV���������̋����Ƃ��āA��ɂ͒��l���w�Ԃׂ��l�̓��Ƃ��Ċw��āA�t�ɓ����҂̕��Ƃɋ����邱�ƂɂȂ����̂ł����B
�۔��F��w�̐��_�͍]�˂̂͂��߂��炠�����Ǝv���Ă����̂ł����B
���c�F�ŏ��͒��l����ŁA�]�˂̂͂��߂ɂ������͕̂��m���Ŏ�w�ł͂Ȃ������ł��傤�B
�۔��F�]�˂ł��������A�����͉e���͂������̂���V�c���o�Ƃ��ĖS���Ȃ�ȂǁA���������S�ł������B
���c�F���y���R����܂ł́A�����̉e���͂��傫�������B��q�w���w�������|���A���Ƃ͑m���ł����B�������|�����ꂩ��̓��{�Ɏ�q�w���L�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ɠw�͂����Ƃ������Ƃ́A�G�g�ƍN�̍���q�w�͂���L�܂��Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃ̗��Ԃ��ł��B
�۔��F�]�ˎ���ɕ�����_���͂ǂ������������͂����Ă��܂�����?
���c�F���{�͏@��ɌːЂ̊Ǘ��������܂����B�����͌��I�@�ւł��B���s�̎��Ɛ_�Ђ����Ŏc����Ă���A�Ƃ������Ƃ́A�]�ˎ����ʂ��Đl�X���������o���ďC�U�����Ă������ʂł��B�]�ˎ���͕������_����������܂��ŁA�l�X�͎����_�Ђ��������̂Ƃ��Ă��z�{�������B��w�͂���ɑ��āA�l�̓�����������̂ł����B�_���Ƃ╧�m�͎�ᔻ���āA�����l�͓�H���ĉ���Ă���Ƃ��A�����l�͓����l�Ƃ��Đ��߂Ă��邪�A�����͉Ă�łڂ������͟u��łڂ����A��N���E�߂���t�l�ł͂Ȃ����A�����Ȃǂ͂���������{�̒n�ɓ������瑦�n���c�P���A�Ƃ���排������Ă��܂����B�_���Ƃ͓��{�͈Ր��v���ȂǂȂ��A�V�c�������Ƒ������Ă���_�̍����Ǝ��掩�^���Ē����Ǝ�ᔻ���܂����B��ы��ւ͐��D�ւ̒�q�Ȃ̂ł����A�c�������܂ő������Ă���̂́A�c�����_�Ɏ���Ă�������ł��A���{���������N�����D��Ă��邩��ł��Ȃ��A�����̋��R�ɂ����Ȃ��ƌ����܂����B���R���{�ł͈Ր��v��������܂ŋN����Ȃ��������߂ɁA�N�b�̋`������Ȃ����ԂƂȂ��Ă��邱�ƂȂ���Ȃ�Ȃ��B����͋��R�ɂ������A�ߋ��ɂ����t�̓V�c�͂������A����c���͖{�莛�����͂Ȃ������Ă�����̂ɉ����_�̂�����Ȃ��̂��A����c�������I����Ă����������͂Ȃ��ƌx�����܂����B
��c�F�_���͎�q�w��ᔻ���Ă������ł��Ȃ��B����������Ε�������荞�݁A������Ύ���荞�ދg�c�_���������������Ƃ�����Ă���A�g�c�_���ł́A��q�w������������荞�ށA�g��ґ��́A�u�悵����v���u��������v�Ƃ���̂��A��q�̗��w����荞�݁A�ōւ�����ɋ������Ă܂��B
�۔��F�_���Ǝ�q�w�����т��Ă���B�����_���ł����B
��c�F�ōւ�g�쓙�͉ƌ��̎��ɁA���߂̕ۉȐ��V�Ɏ�藧�Ă��Ă���A���Ƒ��ƌP������`�������Ă���A���{�����ɂ�������Ă܂��B�V�c�Ə��R�̊W�ɂ��Ă����S�ł͈Ր��v���̂Ȃ����{�������ɏ���A���{�̎�͏��R�ł͂Ȃ��V�c�Ƃ��Ă���܂����A���{�ᔻ�ɂȂ���悤�Ȃ��Ƃ͂ł��Ȃ��ɂ������Ǝv���܂��B�ōւ͓��{�ňՐ��v�����N����Ȃ����Ƃ��A��q�w�̗��w�Ɋ�Â����{���I�A�Î��L�����߂��A���헧�����u�C�ł��藝�v�A�u���������̋C�v�Łu���̗����Âɓn��Ă���炸�v�Ƃ��܂����B����͎�q�w�̗��A�C�̊T�O����͂���܂��̂Ŏ�q�w�ɒ����Ȑl�͔����Ă���܂��B
���c�F�ōւ́A��q�w�҂Ɛ_���Ƃ̓�̊�������Ă��܂����B���������Ɛ��D�ւ͈ōւ����q�w�̗���͂̍��������܂��ꂽ����ł������A�ӔN�̈ōւ���q�w�̒�q���Ȃ�������ɂ��Đ_���̒�q�������Ђ������邱�Ƃɉ䖝�Ȃ炸�ꌾ��悵���B����Ƃ��ꂪ�t�̋t�ɐG�ꂽ�悤�ŁA�����͔j��ƂȂ��Ă��܂��܂����B���̂Ƃ�����Ő_���ɂ͗����������Ă����͂��̐��D�ւ��j�傳��Ă��܂��܂����i�D�ւ͈ȑO�ōւ̑�w�͋���߂���q�{���̎v�z����O��Ă���A�Ɣᔻ�������Ƃ�����A�ōւ͍��Ɏ����Ă����悤�ł��j�B�����ł́A�s�K�ɂ����l���Ր��v�����s���Ă��܂����B����Œ����ł͌N�b�̋`�������܂��ƂȂ�A��q�������N��ł����Ă��N�b�̋`���т��ď]���ׂ����i�S�H���ւ̎�q�̉��߂�����j�A����Ƃ����t�̌N��͂��łɈ�C�v�ɂ����Ȃ����炱���|���Ă��悢�Ɗv����F�߂�ׂ����i�Ўq�ւ̉��߂�����j�A�ǂ��������̌��t���c���܂����B���������{�ł͍K���ɂ��Ր��v�����Ȃ������̂ŁA�N�b�̋`���Ɏ��ׂ��f�n������A��q�̂悤�ȂԂ�͋N����Ȃ��B�������Ȃ���A�ō֊w�h�̐l�X�́A������n�͂��ł������\�������邱�Ƃ�F�����Ă��܂����B�ō֊w�h�̌I�R���N�́A�w�ی���L�x���̐e���Ɍ��悵�܂����B����́A�@�����ォ�痊���܂ł̗��j�����������̂ŁA���̎���̗��V�c��c�������ɗ��ϕs���ł���������ᔻ�������̂ŁA�����̓V�c��c�ɂ͌N��̎������������Ă���A����ňՐ��v�����N����Ȃ��������Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��A���������̂Ƃ����������̕��ƂɓV�c�̌��͂���������D��ꂽ���Ƃ́A�����̓V�c��c�����̈��t�Ȃӂ�܂��̓��R�̕ł������A�ƌ������ᔻ���Ă��܂��B�I�R�̏��́A���̐e���ɑ��āA���Ȃ��̑c��͂���Ȃɂ��N��̎��i�Ȃ����Ƃ��s���Ă����A�㐢�̂��Ȃ������c���́A�ߋ��̑c��Ȃ��ĐT�܂Ȃ�����x�����Ր��v���ƂȂ�܂���A�Ɖ��߂鏑�ł���܂����B�ō֊w���w�l�����́A�c���̐_�̂�����Ȃǂ͐M���Ȃ��B�ނ���c�����������邽�߂ɂ́A�ߋ���[�����Ȃ��Ē鉤�Ƃ��Ă̓����Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ�����@���������Ă��܂����B�����A�D���ւ̖����ɒ������O������܂����B�ނ͖����V�c�̗c�����Ɏ��u�ƂȂ�A�����Ɉڂ��ēV�c�Ɏ�q�w���������B�����͐����ɔs��ē�������Ǖ�����Ă��܂��܂������A�����V�c�̐N���ɂ́A�����ČF�{�̎�q�w�ҁA���c�i�t�����u�ƂȂ����B�ނ�́A�V�c�Ɏ�q�w�I�鉤�̂�����������܂����B���Ȃ킿�A�N�傽��҂͖��̍ő�̖͔͂łȂ���Ȃ�Ȃ��A�������~�͂��������ɋ����ꂸ�A���ɕ����ׂ����̋��t�łȂ���Ȃ�Ȃ��B�����������������̓����I�N��ςŖ����V�c�͌O������܂����B�悭������Ƃ����ׂ��ł��B
�۔��F�~�c�_�l�Ƃ́H
���c�F�~�c�_�l�͏��l�ˎm�ł��B��ы��ւ̖剺�ɁA�ዷ���l�ˎm�̎R���t���������B�t���ȍ~�A���l�˂͑S���̔˂ł͒������A�ō֊w��ˊw�Ƃ��܂����B�~�c�_�l�͂��̔ˊw����o�āA���c���������ĉ��A�����̑卖�ŕߔ��A��������A�Ԃ��Ȃ����S���܂����B
�۔��F�_�l�͋��ȏ��ɂ悭�o�Ă��܂��B�U�w�̋ւƂ́H
���c�F��v�ł̔h�������ł����A�����̐V�@�ɔ����鋌�@�h�Ƃ̑Η��ɂ͂��܂�܂��B���@�h�̏������������q�͋��@�h�ɓ�����A���q���̊w�͐V�@�h����ے肳�ꂽ�o�܂�����܂��B
�i��c�F�J�@�̎���̍ɑ���������i���傤���傮�j�ŁA�O�ʂ̊�侂�h�i�������イ�j�Ƃ̑Η��ł����A�J�@�ɋ߂�����ɂ�������侂�h���ɑ��l���ɂ܂Ō��o������ꉡ�Ԃ���A���ȂŊ��S��`�҂̎�q���ᔻ���܂����B�J�@�́u�����̌������Ƃ͌����ɍs�����Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ƃ������ƂŎ�����ᔻ����҂������A�����͎��u��Ƃ����A��������ɑ����X�R����܂����B��侂�h�͎m��v�Ԃɂ���������̉e���͂�}�����邽�߁A��q�w���U�w�Ƃ��ċ֎~���A�U�w�̓}�l�𒆉��̊��E����r�����܂����B�z�����ꂽ�҂�����܂������A��q�͐E�������܂����B�j
�۔��F�U�w�Ƃ��ꂽ��q�w���A���w�Ƃ��ꂽ�̂ł��ˁB
�������S���Ȃ�A��侂�h���ÎE����Č�A��c3�N�i1227�N�j�Ɏ����ɑ��t�E�M�����݈̎ʂ��Ǒ�����A�~�S���N�i1241�N�j1���A�E�q�_���牤�����r������������]�J����܂����B
��c�F���������{�Ŗ������ʂ����Ă���B���n�@���`�͓�T���̑m�ł����A�G�g�̎��A���N�Ƃ̊O���̍쐬�A�u�a���ɓ��������������̑m�i�Z�E���Ώ��[�G�������傤���傤�����j�̐����ŁA���얋�{�ł͊O������ՂɌg����Ă��܂��B���Ђ̍s���ɂ��W����Ă��܂��B�V��@�i���ʎ����j�̑m�V�C�͕����ɒʂ��]�˂̊X����A�S��A���S�储����܍s���ɍ��킹�ČܐF�̕s����ݒu���A�X���ɒʂ����ɏ���̎Ђ�ݒu���Ďח���A���̈ɐ��𐼏ƂƂ��A�����ɓ��Ƌ{��݂���Ȃǂ��܂��܂ȃA�C�f�A����Ă��܂��B�g�c�_���́A����܂Ō��Ƃ̔��쎁������̐_�_���Ƃ��Đ_�Ђ����Ă����̂ł����A���{���璺������o��������^�����A�_�Ђ̍ĕ҂��s���Ă��܂��B
���c�F�����̑T�m�͒m���l�ł����B�����E���N�Ƃ̌��ɂ́A����������Č������邱�Ƃ���@�ł����B���\�̖��̌�n���ŁA������g�҂����쉮��ɗ����B���������Ƃɂ͊����͂��납������������҂Ȃǂ���킯���Ȃ��B�����Ŋ����̖��l�Ƃ��ċ��s�ŗL���ɂȂ��Ă����������|���A���쉮��ɌĂ�܂����B�ނ̉ƍN���͂��߂Ƃ����喼�����ւ̒m���́A��������n�܂�܂��B�]�ˎ���A���͑����̊��Ђ������Ă��܂����B�ōւ��y���̑T���Ŏ�q�w���w��ł��܂��B�����h�q�͏㑍�̕Гc�ɂŐ������܂������A�ǂ���炻���ɂ����������Ȏ����������Ă������Ђ�ǂ����Ċw���i�߂��悤�ł��B
2025�N1��11���i�y�j��w�͋�
�{���́A���{����A�Z�c����A�۔�����A���c����A��c����̌ܐl
���c���W��
��w�͋�i�o-01.pdf�j�i��w�͋�ߘa���N�ꌎ.pdf�j
��w�͋�̍u�`�͂͂������@youtube
��L��w�тɎ�q���C�������������̂���w�͋�i��w�͋�ߘa���N�ꌎ.pdf�j�ł��B��q�͗�L��w�т���בւ��A���₵�܂����B�u�o�v���E�q�̈⏑�E�{���i�o�j�Ƃ����̓��e���O�j�́E�����ڂƂ��܂����B����ȉ����u�`�v�Ƃ��A�\�q�Ƃ��̒�q���A�O�j�́i�������A�V(�e)���A�~���P�j�Ƃ��A���ӁA���S�A���g�A�ĉƁA�����A���V���A�Ƃ��܂������A����Ɏ���ɂ́A�i���A�v�m�ł���˂Ȃ�Ȃ��Ƃ��A��q�����₵�����ڂƂ��܂����B�e�L�X�g�����֑�w�������p���܂��B�u�{���v�́u��L��w�ь����v+�u��q�̏������낵���v�A�u���v�́u�{���ɑ����q�̒��v�i�������ւ͏ȗ��A���W���ł͏����Œlj��j���Ă��܂��i�o-01.pdf�j�B
��q�Ɖ��z���̉��߂ɂ��ẮA�����͂����ƒʂ��܂����A��q�Ɖ��z���̑�w���߂̑Δ���܂Ƃ߂Ă����܂����i��w�͋�ߘa���N�ꌎ.pdf�j�B���z���͒��q�E��q�̊w��ɑΌ�����l�ł����A�ނ͂Ƃ��ɑ�w��ʂ̉��߂œǂނׂ��ł���Ǝ咣���āA�ނ̊w�̏d�v�ȕ���������Ă��܂��B���z���͒��q�E��q����w�ɂ͍��ȒE�R������Ƃ݂Ȃ��ĕ��בւ����₵�����Ƃ�ᔻ���āA��w�͊���̃e�L�X�g�̂܂܂œǂ߂ƌ����܂����B�܂���q�́u���ɐe���ށv�����߂āu����V�ɂ��v�Ɠǂނ��Ƃ�ᔻ���A�u���Ɛe���ށv�̓ǂ݂��т��܂��B�܂��i���v�m�̘_�͎�q�Ɗ��S�Ɉ�����ǂݕ������܂��B���z���͖Ўq�́u�ǒm�v��������āA�u�m��v���v���u�ǒm��v���v�Ɖ��߂��܂��B�i���́u���𐳁i�����j���v�Ɖ��߂��܂��B�S�����Ƒ�����Ƃ��A�K�����̂ɑ���ӎ��������Ă���B���̈ӎ����ǒm���͂��炩����Ƃ��A�P�͑P�Ƃ��ĕK���D�݁A���͈��Ƃ��ĕK�����i�ɂ��j�܂��ɂ͂����Ȃ��B�䂦�Ɋi���v�m�Ƃ͐S�ɔ�����Ă���ǒm��ΏۂɌ����āA���ꂪ�P�ł���ƐS�������Β����ɂ�����D��ōs�����A���ꂪ���ł���ƐS�������Β����ɂ��������Ő����A�Ƃ����m�s������w���Ă���̂ł���B�S�ɂ͐����ǒm��������Ă���A�u�S�������v�ł���̂�����A���ꂪ�ł���͂����B���ꂪ�ł��Ȃ��̂́A�����S�����~�ɓ܂炳��Ă��邩��Ȃ̂��ƁB��q�͊w��ōl���Ȃ���Η��͌����Ȃ��A�ƌ����܂��B���z���́A�����̍�����ł����~�������Η������łɐS�̒��ɂ��邱�Ƃ�m��A�ƌ����܂��B��q�́A�ʂĂ��Ȃ����ȂƓw�͂̐�ɐ��l�ւ̓���������Ƃ�������ł��B���z���́A�悫�S�ƂȂ邽�߂ɂ͓Ǐ��Ȃǂ͂���Ȃ��A�S���{���ɐ�������ΐS�͕K���������o���Ƃ�������ł��B��q�͍s������Ƃ��ɂ͂����������ꂪ���f�̗��ɉ����Ă���̂����Ȕ��Ȃ���A�Ƃ�������ł��B���z���́A�S�̗ǒm���u�Ԉ���Ă���v�ƌ����Ȃ�A�����ɍs�����ĊԈႢ���i�i���j���Ƃ�������ł��B��q�̓ǂݕ��́A���f�̋c�_�ɑ������Ă��܂��B���z���͓����l���ł��A�Ўq�̌��t���瑽��������Ă��܂��B�i�}�̐S�����܂�M�������A�w��Ŕ��Ȃ��Ȃ���ΐ����͌����Ȃ��Ǝv���l�́A��q�w�������Ă��܂��B�i�}�̐S�̐���M�����A�P���Ǝv���͑S�͂Ŏx���A�����Ǝv���Β����Ɏa���Ď̂ĂȂ���ΐl�Ԃł͂Ȃ��Ƃ����̂��������Ǝv���l�́A�z���w�������Ă���ł��傤�B�剖���ցA���������A�O���R�I�v���z���w�����D�����̂́A�悭�킩�邱�Ƃł��B
���c�F�۔�����ǂ�����D�܂�܂����H
�۔��F�z���w�̕��ł��ˁB
����������t�������܂��ƁA�Ԓ˒��i���������悵�j�搶�́A��w��䤎q�A�Ўq�A���f�̎v�z�����Ċ���O���ɐ��������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����\����V�ߊ�����n�̑�w����Ŏ�������Ă��܂��B��w�ɂ́A�m����䤎q�̎v�z�ɒʂ���Ƃ��낪���������܂��B��w�́u�����𖾂ɂ���v�u���P�Ɏ~��v�̕W��́A䤎q�̉���т̋c�_���i���Ƃ������̂ł͂Ȃ��̂��Ƌ^�������Ȃ�܂��B䤎q�́u�����Ɏ~�܂�v�ƌ����A�u�吴���v�ƌ����B���Ȃ킿����Ȋ������Ƃ̒��_�Ƃ��āA����ςɂƂ��ꂸ���X�N���鏔����Ջ@���ςɉ����ł���p�[�t�F�N�g�Ȕ��f�͂����������]�������Ƃ����ɂ̖ړI�ł���A�ƌ����B�����ǂ߂A���Ƃ̃G���[�g������̂�����ڎw���ׂ��Ȃ̂��A����肩���X�b�L�������ł���������܂��B�Ȃɂ��i���v�m�̋c�_�͍E�q�ɂ͂Ȃ����A�Ўq�ɂ�����܂���B����̂͂���䤎q�����ŁA������䤎q�̋c�_�͐퍑�v�z�̒��ł��ł�����łȂ����ł������Ȋi���v�m�̋c�_�ł��B䤎q�̂������������f�_���o�āA����̎�Ƃ����Ƃ̒��_�ɂ���ׂ��l�ނ͒m�͂Ɠ��͂��ǂ��i�߂�ׂ����̓W�]���������̂���w�ł͂Ȃ����A�Ƃ������ł���킯�ł��B�Ԓː搶�̎w�E�́A���͂��Ȃ萳�����Ǝv���Ă��܂��B��������Ƒ�w�͍E�q�̈⏑�Ƃ��]�q�̉���Ƃ��͂Ƃ�ł��Ȃ��A�ɓ��m�ւ��^�����Ƃ��肸���ƌ㐢�̏��ł���Ƃ������ƂɂȂ�B�����Ƃ�����������ł�������܂���B���Ƃ���w������̎v�z�ł������Ƃ��Ă��A��w��䤎q���o���Ñ��Ǝv�z�̍ł��������ꂽ�����ł���Ƃ������Ƃ��ł���ł��傤�B
�۔��F䤎q�̍l��������w�ɓ��荞��ł���A�Ƃ������ƂȂ̂ł��ˁB�ǂ����Ă������f�ł���̂ł����B
���c�F�p�ꂪ���Ă��܂��B�~�����Ǝ~���P�A�吴���Ɩ������B䤎q�͏������̃g�b�v�ƂȂ�l�Ԃ͐���ς��̂āA�����Ȕ��f�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƌ����B�������]�ɂ͊O�����画�f��f�킹��G���i���j�������Ă��܂��B����������A���_����ɏW������w�͂𑱂��Ȃ����B�������Ď~�����ƂȂ�Δ��f�͂͑吴���ƂȂ�A���S�Ȗ��ߎ҂ƂȂ邱�Ƃ��ł��邾�낤�B���ꂪ䤎q�̉���т̌����Ƃ���ł����A��w�̂����߂Ƒ������Ă��܂��B䤎q����w���A�l�̏�ɗ������ҁA���ߎ҂̐S���ł��B����Ɍ����A�u�i���v�m�v�̋c�_�͍E�q���Ўq������Ă��Ȃ��B����Ă���̂�䤎q�����ł���A����䤎q�̊i���v�m�_�͐�`�v�z�̒��ōł��傫���ł������Ȃ��̂ł��B��w�̔���ڂ̍ŏ��ɂǂ����Ċi���v�m�������Ă���̂��A�E�q�Ўq�̎v�z���猩��Εs�R�ł�������܂��A���ꂪ䤎q�̎v�z���o�R�����҂̍l���ł���ƍl�����Ȃ�A���ɂ悭�����ł��܂��B��������q�̉��߂ɂ́A䤎q�͍̗p����Ă��܂���A䤎q�͎q�v�ƖЎq��ᔻ����҂ł���A�������w��̗v�Ƃ���v���҂ɂƂ��Ăْ͈[�ł����Ȃ��B��q�̑�w���߂́A�Ўq�E���f�ɂ���Ă��܂��B
�۔��F䤎q���Ƃ肱�݊���ɑ�w���ł����Ƃ������Ƃł��ˁB
���c�F�����f�����鍪���͂���܂��A�������邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃł��B��Ǝv�z�͍E�q����q�v�Ўq���o�Ĕ��W���A䤎q�Ɏ���܂����B��������邲�ƂɎv�z����������đ̌n�����Ă����܂����B��w�͎�Ƃ̗ϗ����R���p�N�g�ɂ܂Ƃ߂Ă��܂��B���̂悤�Ȃ܂Ƃ߂��ł���n�_�́A�����炭�v�z���W�J����Đ������ꂫ�������Ȃ��̎���ł͂Ȃ����Ɛ����ł��܂��B����������䤎q�̌�������ĖЎq���f���������悤�Ƃ���@�^������������Ƃ���A����͂����炭�`�ォ�犿��O�����낾�����̂ł͂Ȃ����ƁB
�۔��F�ł��A䤎q�͕��ʂ̐l�ɂ͒m���Ă��܂���ˁB
���c�F䤎q�ْ͈[�Ƃ���Ă��܂��A�ȋ��̎����ɂ͏o�܂���B����œǂ܂�Ȃ��Ȃ�܂����B�܂�䤎q�͕��ʂ����������ɓ���ŁA�C�y�ɓǂ߂鏑�ł͂Ȃ��B���ʁA�����]�ˎ���̍D�w�̐l�����̏������߂���܂ŁA�قƂ�ǒ��ڂ���܂���ł����B
��c�F����Ɏ������Ƃ����B�c���q�ɒ鉤�w��������A�m��v�Ɋ��鍑�̂������O�ꂷ�邽�߂ɂ��R���p�N�g�ɂ܂Ƃ߂���̂�����ꂽ�̂ł��傤�B�������̓A���̍��͕�㺁E�_�_�E����EꟁE�w���p���Z�ⓒ���A�����̓��𖾓��Ƃ���悤�ȉ��߂������̂ł��傤���B
���������@�����_
���������́A���q�̐��D�ւƕ���Ŏt�̎R��ōւ����q�w�̗����̐[���Ō��܂��ꂽ����ł����B�������t���ӔN�A��q�w�̒�q���Ȃ�������ɂ��Đ_���̒�q�������Ђ�������ԓx�ɓ{���ċꌾ��悵���Ƃ���A�t�̋t�ɐG��Ĕj�傳��Ă��܂��܂����B�ōւ̎���́A�]�˂ɐi�o���܂����B�����ō]�˂̊e�˂ɏ�����Ď�q�w�̍u�`���s���A��w����Ă܂����B�ނ̌�ɂ͈�t�I�ցE�ٍe�q�������A���ɕ����̑�܂ňō֊w�̌n���͑����Ă����܂��B
��ы��ւ͐��D�ւɊw�сA�D�ւ̎���͋��s�ݏZ�̐l�X�ɋ����𑱂��邽�߂ɁA���s�䒬�ŏm���J���܂����B�䒬�̋��ւ̏m�͖]�팬�Ə̂��A�퐳����炢����̐��_���p���ŋΉ����ʂ������Ƃ_�I�x���Ƃ��Ă��܂����B�������̐Ւn�ɍs���Ă݂܂������A���̓}���V�����ƓX�ɂȂ��Ă��ĐΔ���ē�������܂���ł����B���U���s�ݏZ�ł������̂Œ����̂悤�ɍ]�˂̊e�˂Ƃ̂Ȃ���͂���܂���ł������A�����ዷ���l�˂̎R���t�����ނ̏m�Ɋw�сA�ȍ~���l�˂ł͈ō֊w���ˊw�ƂȂ�܂����B���̌n�����疋���ɔ~�c�_�l�E�L�n�V��������܂����B�_�l�͑������������āA�����̑卖�ŏ��Y����܂����B�V���͎F���ˎm�ŁA���Ëv���̏㗌�ɉ����ď㗌���āA���{�h�̌��ƂE����N�[�f�^�[���v�悵�܂����B���ꂪ�v���̓{����A�����̎��c���ňꖡ�Ƃ��ǂ��l������܂����B���c�������ł��B���̉_�l�E�V�����L���ł����A�������O�͏��N�����V�c�̎��u�ƂȂ�A�����Ɉڂ��ēV�c�Ɏ�q�w�������܂����B���O�͐����ɔs��ē���������܂������A���̌�ɓV�c�̎��u�ɒ������̂��F�{�̎�q�w�ҁA���c�i�t�ł����B�����V�c�͏��N����ɒ������O�A�N����ȍ~�Ɍ��c�i�t����e�����āA��q�w�I�鉤�̗ϗ��ς𐁂����܂�Đ��������̂ł����B��q�w�I�鉤�Ƃ́A�N��͖��̍ő�̖͔͂łȂ���Ȃ�Ȃ��A�����łȂ���ΌN��̎��i���Ȃ��A�Ƃ��������l�܂�悤�ȓ����I�N�呜�ł��B�����V�c�͗c�������狳�����āA�悭�������������Ƃ����ׂ��ł��傤�B
���ێO�N�i1718�j�A�ӔN�̍����������]�˂��狞�s�ɖ߂��Ă��܂����B�O��ւ̒�q��蒼�D�ɓ����_�����A���ւ�������L�^���āA�����Ƃ̈ӌ������̓��e�����J�����B
- �Ռo�Łu���������v�߁A�V�ɏ����Đl�ɉ����v�ƌ����A�Ўq�Łu�����͂���i�m�`�j��g�ɂ��v�ƌ����Ă���B��q�͒��f����Łu�����̕�������Ȃ�v�ƌ����Ă���B�����E�����̍s���́A�ᔻ���邱�Ƃ͕s�\�B
- ���l�͍ł����S�Ȃ����݂ł���A�퓹�ƌ����̗������s�����Ƃ��ł���B���l�͓V������ΑT�������������̂ł���B��������l�ɂ͐��l�̌�����͕킷�邱�Ƃ͂ł����A���l�̏퓹����邱�Ƃ���������Ȃ��܂łł���B
- ���l�͍ł����S�Ȃ����݂ł���A�퓹�ƌ����̗������s�����Ƃ��ł���B���l�͓V������ΑT�������������̂ł���B��������l�ɂ͐��l�̌�����͕킷�邱�Ƃ͂ł����A���l�̏퓹����邱�Ƃ���������Ȃ��܂łł���B
- �l�Ԃ��猩����@���͌N��ŕ����͉Ɛb�ł��邪�A�V�邩�猩����@���͉ƘV�ŕ����͗p�l�����B��l�̓V���ƘV���Ƃ𖽂����Ȃ�A�p�l�����͂���ɏ]����葼�͂Ȃ��B���Ώf�Ă͏퓹���畐�����|�߂��̂ł���A�V���疽���Č������s�킴������Ȃ����������Ƃ͗��ꂪ�Ⴄ�B
- ���������q�E���q�����ɗ��ĂȂ������͓̂V������������ł���A�����̑��ʂ��x�������Ƃ���ɓV����������Ă���B
- �_������̐_���Ƃǂ����A�����͓����̂��Ƃ��s���҂l�Ƃ����߂��������ł���Ɣᔻ���Ė�����n�̓��{���ō��Ǝ����グ��̂́A�����Ⴂ���͂Ȃ͂������B
���Ώf�Ă��|�߂��̂́A�����̐S��������̂��ƂŁA�����̌��t�����u�}�Y�}�^�����v�Ǝ~�߂��܂ł́u���v�ł������B���җ��ꂪ�Ⴄ��ł́A����������ł̂��ŋ��ł������A�ƌ����Ă���B��������Ɣ��Ώf�Ă͂��ŋ��Ŏ~�߂��ɂ�������炸�A�������������s������ɂ͂��̂��ŋ��ɏ}���Ď����ƂɂȂ�܂��B�����̂悤�Ȃ��Ƃ͖{������Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ��Ƃ������Ƃ��㐢�Ɏ������߂ɁA�����đ��Ȗ��������Ď��Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤���B���������ł���A�s��ł��B
�����́A���{�̎�������Ƃ���ɐ_�������Ē�����ؐH���̕s���҂Ɣl�铖���̐_���Ƃ������������A�����̌��������ՓI�ŕW���Ȃ̂ł����āA���{�̎���Ȃǂ͓c�Ɏ҂̈ӌ��ɂ����Ȃ��A�Ɣᔻ�����̂ł��B�����͒��q�̐��D�ւ̖����⌾���A�悭�Ȃ������Ɣᔻ���Ă��܂����B
���̂Ƃ����D�ւ͂��łɎ������Ă��āA��q�̎�ы��ւ������̓����_���Č������ᔻ���܂����B���ւ͎t���D�ւ��p���Ő_���ɂ��X�|���܂������A�_���Ƃ������Ǝ�w��ᔻ����ԓx�ɂ͗����������Ď�q�w��i�삵���l�ł����B
- �E�q�́u�����P��s�������v�ƌ����Ă���B���́u�����v����菜�����Ƃ͂ł��Ȃ��B�E�q�͂ǂ����ĕ����E�ה��������ƌ����A�����𖢂��P��s�������ƌ������̂��B
- �\�q�́w��w�x�ŕ������������p���ď̂��Aw�ł������ł��Ȃ��B�E�q�͔ӔN�ɒP�i�c��A�c���q�j�̐Č��U�t���āA�D���ɐē�����i�����A���ꂪ���Ȃ�ʐ�͗��b���q���߂Ɂw�t�H�x���������B���̍E�q�̈Ӑ}�͂ǂ��ɂ��������B
- �t����������������邻�̐S���́A�����������B���l�Ȃ�܂������A��炲�Ƃ����ǂ����ĕ��������ɏo�����Ƃ�������悤���B
- �t�������������A�퓹�Ȃǂƌ��̂́A�܂�Ől�̓��ɓ���邩�̂��Ƃ������ŁA�S�����s���ł���B����Ȃ��Ƃ�����Ă͂Ȃ�Ȃ��B
- �����̕����́A���l���s�K�ɂ�����������Ȃ��ɍ����ł������ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���{�ɂ���Âɞ{�@�ɗ��ʈ��N�͂������A�����킢�ɂ������̕s�K���Ȃ�������ՂȂ���Ȃ�Ȃ��B�i���ւ��܂��A�_���Ƃ������������Ȃ߂邱�Ƃ�ᔻ���Ă���B���ɂ����̎���̑f�p�Ȑ_���ł́A�i����̋����Ƃ��ĕs���ł���A��������̋����ł��钆���̎�w���K�v�ł���B�c�������������͓̂��{���_�Ɏ���Ă��邩��ł͂Ȃ��āA���܂��܂̊�Ղɂ����Ȃ��B�c�����_�Ɏ���Ă���̂ł���A�ǂ����č]�ˎ���̍��͖{�莛�����͂Ȃ��������Ă���̂��B�j
���̋c�_�A�ǂ����Ƃ����藧���܂��B�ǂ������������A�ǂ������Ԉ���Ă���Ƃ͂����Ȃ��B���ւ̒����ւ̔ᔻ�́A�����̐_������̐_���Ƃ����̓��{��^�_�Ƃ͈�����悵�Ă��܂��B�_���Ƃ����������̂��Ƃ�ؐH���ʼn���킵���Ɣl�邱�Ƃ��ᔻ���A���{�͊C���߂����狛��H�ׂĂ��邾���ł��낤���A�����͊C�������A����q���������͓�ȂȂǂ͊C���牓������Ă��āA��{�������ĉh�{�Ƃ��Ȃ�������Ȃ��������̂��ƌ����A����̎���Ŋ������Ă����_���Ƃ����̃f�^�����Ȕᔻ���꓁���f���Ă��܂��B
���������́A�]�˂Ŋ������āA���ۂɐ������͂������Ă����喼�����ɍu�`���s���Ă����l�ł��B�����炭�������猩��A���łɓ��{�͎�����Ր��v�����Ȃ���Ă��āA���s�̓V�c�͌N��Ƃ͌�����A�Ƃ����������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B��������ɍ]�˂ɂ��������h�q�́A���R�͕����ł���A�������V���̎O���̓��̗L���Ă����������ğu���������̂Ɠ������A�ƌ����Ă��܂��B�܂�V�c�͌`�����������Ă��邪�A�����͂������̌��͂��Ȃ��B�h�q�͓��삱�������{�̎����̉��ł���Ɩ������Ă��܂����B��͎������v����ē��삪���ʂ��邾���ł���ƁB
�����ۂ����ւ́A�t�̐��D�ւ̎v�z���p���ŁA���U���s�ɗ��܂�喼�Ɏd���邱�Ƃ����܂���ł����B�ނ�̗��ꂩ�猾���A��q�w�̌N�b�̗ϗ������S�Ȍ`�Ŏ��ʂ����Ƃ��ł���f�n���A���{�ɂ͊�ՓI�Ɏc���Ă���B����Ȃ�A���{�ł͌N�b�̗ϗ������o���Ď��ʂ����Ƃ��A��q�w�҂Ƃ��Ă̖��߂ł��낤�B�Ր��v���́A�����̐��l����炴������Ȃ������ɍ����ł������B����ɂ���āA�����ł͌N�b�̗ϗ��������܂��ƂȂ�A��q���͂����肵�����Ƃ������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B���{�̎�q�w�҂́A�N�b�̗ϗ���ʂ��f�n���c���Ă���ȏ�́A��ʂ��ēV�c���N��Ƃ��Đ�ɑ��d���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ւ̔��_�́A��q�w�҂̘_������o�����̂ł����B
�c�������܂ő������Ă���̂́A�c�����_�Ɏ���Ă�������ł��A���{���������N�����D��Ă��邩��ł��Ȃ��B�����̋��R�ɂ����Ȃ��B�������R���{�ł͈Ր��v��������܂ŋN����Ȃ��������߂ɁA�N�b�̋`������Ȃ����ԂƂȂ��Ă���̂��B�_�����͂�ꒆ���l�͓�H���ĉ���킵���A���{�l�͐H�����琴�炩���Ƃ��A��ꒆ���l�͓����̂悤�ȕs���҂𐒂߂Ă��₪��A���{�ł͓����Ȃǂ̓n���c�P���Ƃ��A��Y����Ȕ�排����������Ȃ��B�����ł͂Ȃ��āA��q�w�̘_���������ē��{���N�b�̋`�����������������ȗ���Ă��Ȃ���ՓI���j�������Ă��邱�Ƃ��̂��A�������������Ƃ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƌ����Ƃ���ɗD�ꂽ�Ƃ��낪����܂��B���Ղ̘_����p���āA���{��i�삵�Ă���̂ł��B
���ւ͎�q�w�҂Ƃ��āA���{�̊�ՂȂ���Ȃ�Ȃ��B����́A���ア�����čc�����Ր��v�������\���͂��肤��A�Ƃ������Ƃ�F�߂��c�_�ł��B�����c�����N��Ƃ��Ă̐Ӗ���Y��A�������~�ɑ���A���{�̖����ڂ݂Ȃ��Ȃ����Ȃ�A���̂Ƃ��V�����������킵���Ȃ�A���̂Ƃ��c���͂��ɏI���ł��낤�B���ɍ]�ˎ���ɂ͂قƂ�ǏI��肩���Ă����B�c���͂����Ȃ�Ȃ����߂ɁA�ߋ��̉@�����̋����ȓV�c��c������A����V�c�̂悤�ɉƐb�̈ӌ������ɂ߂�ڂ��Ȃ��N��ƂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̉��߂��A�ō֊w�̎�w���w�l�����ɂ͂���܂����B����́A���̉��߂𐬂����ō֊w�h�Ƃ��āA�I�R���N�����グ�����Ǝv���܂��B
�۔��F�c���͋����R���������Ă�����̂ł͂���܂��A�H�ׂ�ɂ�������ł͖��͂���Ƃ��A����������c����������������ĐH�ׂ邱�Ƃ��o�����Ƃ����b������܂��B
���c�F����͖������̂��Ƃł��ˁB��������̍��̍c���A��c�͋������͂������Ă��܂����B���̍��̓V�c��c�̏��Ƃ́A�������ɂ��N��̐Ӗ������o�������̂ł������Ƃ͂����Ȃ��B���q�̒������ڂ݂��A���ς̍s�ׂ��s���A�������~�Ő킢�����A�Ɛb�̑P���������������B���̕s���̌��ʂƂ��āA�������V�c���Ȃ�������ɂ��ĕ��Ɛ����𗧂Ă��B�I�R���N�́u�ی���L�v�ɂ����L���Ă��܂��B�I�R�́A�����܂ł���ĈՐ��v�����N����Ȃ��������Ƃ���Ԃׂ����A�ƌ����܂��B�����̊�ł����A�����̍��ɓV�c�Ƃ͈Ր��v������ē��R�ł������B�����V�c�̏��N���̎��u�ł������������O�͈ō֊w�h�̖����ŁA�c���V�c�Ɏ�q�w�I�N��̐S���������܂����B�����́u�ی���L�v��ǖ{�ɗp�����Ƃ������Ƃł��B�V�c�ɑ��āA����c�̏��ƂȂ��A�N��Ƃ��ē��̊ӂƂȂ薯�̋��t�ƂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƌ��������Ƃł��傤�B�����̌�������Ď��u�ƂȂ������c�i�t����q�w�҂ŁA�N���̓V�c�Ɏ�q�w�̗ϗ��ς�O��I�ɍu���܂����B
�۔��F���a�V�c�̓}�b�J�[�T�[�Ƃ̉�Ŏ��̐ӔC�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��]��ꂽ�̂ł��ˁB
���c�F�����V�c�ȗ��̌N�呜�Ƃ������̂��A�c���Ɍp������Ă���ƌ����ׂ��ł��傤�B
�۔��F�ӔC�͎��ɂ���E�E�E
��c�F�}�b�J�[�T�[�ɑ��āu�S�ӔC���ҁv�Ɖ]��ꂽ�B�i����{�鍑���@�̎匠�҂͓V�c�ł����j���a�V�c�͍c���q�̍��C�M���X��K�₵�W���[�W5������p���́u�N�Ղ���ǂ����������v�Ƃ����������w��ł���ꂽ�B
���c�F�C�M���X�ɂ̓m�u���X�E�I�u���[�W���̍l��������B���̍l�����A�����V�c�����N��ւ̋���Ɠ������u�ĂĐڋ߂��Ă����B���a�V�c���C�M���X�̉e�������f�n�ɂ́A�����V�c�̌N�呜���������Ǝv���܂��B�N��͓V�����Ă���̂ł��邩��v�����܂܂̂��Ƃ�����Ă悢�A����œ|�ꂽ�Ȃ�ΓV�����s�����܂ł��A�Ƃ����ꐧ�N��ς��ʂɂ���킯�ŁA���������������͓V�c�ɂ͍���Ȃ��������Ƃł��傤�B
�i��c�F�ʗ�V���ɂ�蕐�����@�������Ƃ���܂����A�i�n�J�́u�j�L�v�ł͂��̎��_�ł͕����ɓV���͍~��Ă��܂���B�����i�����j�ɍ~��Ă����Ƃ���܂��B�����A���������ɓV�����~��Ă������炻�̑��q���i�����j���@���ׂ��Ƃ��A�����̈ʔv�𗧂Ăďo�w���܂������͈����Ԃ��܂��B�����ɓV�����~��Ă��Ȃ��Ƃ��܂����B
�@���o�ł��@���̎��ɂ́A�����ɂ����ɂ��V�����~�肽�Ƃ͋L����Ă��܂���B���o�ɂ͕����ɓV�����~�肽�Ƒ�X�I�ɋL����܂����B�������@���̂́A���܂�̂Ђǂ��Ɂu�V�̔��v���s���Ƃ�����������������̂ł��B����͞{���������������Ɠ��l�u�V�̔��v�Ȃ����́u�v�C�i�߂���Ƃ��čȎq�܂ŎE���j�v�ł��B�����͓V�̖��Ȃ������@���������Ƃɕa�݂܂��B�������S�������ȂǎO���̗��ʂ��āu�����ɐӂ��L�邩�v��V�ɖ₢�A�ӂ������Ɛ肢�Ŕ������A�����~�肽�Ƃ��Ă��܂��B
�@�u�ɂ͖��q�Ƃ������l���c���Ă���A�����͓����̂������₢�A���q���Ă��Z���������Ƃ����u�^�͋��e�v���Ɏ����܂��B�����̋㌴���݂����Ȃ��̂ł��B����قǂ̌��l���u�Ɏc���Ă��Ȃ��牽�̕����ɓV�������肽�̂ł��傤�B���l�ɓV�����~���Ȃ�A������薥�q���Y�����܂��B
�@�{���͓V�̏��̎q���n��̒�ł���A���̎q���ȊO�ɓ������ς˂邱�Ƃ́A���q�W��r�₷��悤�Ȉُ펖�Ԃł��B���ٖ̋��ȕ��q�W�̒f����ɘa���邽�߁A�V�Ƃ������ۊT�O����������Ր��v�����N�����Ė��Ȃ��Ƃ���H�v���}��ꂽ�̂ł��傤�B
�@���������u�V���v�Ƃ����T�O�������ĕ������@�������𐳓������A���o�ɂ�蕶���́u�v���X�I�ɏ���Ɍ��`�i�v���p�K���_�j���܂����B������ɂ��K�p���A������u�V���v�ɂ��Ƃ��܂����B�u�V�̖��v�͖��߂̂悤�Ȃ��̂ł����A�u�V���v�ƂȂ�A�V�����ɕ����������炷�҂Ɂu�����̖��v���~�낷�Ƃ����悤�ȊT�O�ɂȂ�܂����B�����A���̐Ӗ����ʂ����˂A�u�V���v���������ƂɂȂ�܂��B��̉��ɂǂ��Ȃ�Ύ������A�����Ȃ�Ȃ����߂̋��P�̏��Ƃ��ď��o�i�����j���Ҏ[���ꂽ�悤�Ȃ��̂ł��B
�@��Ƃ́A�������ǂ�ȂɂЂǂ��d�ł����Ă��@���ɒ�����s�������A���P�̓��̐l�Ƃ��ď̗g���܂��B�������A���o��j�L�ł́A�����ƌ����I�ŁA�����́A�@���ɏ��������߂鍋���ȑ��蕨�̌��Ԃ�ɐ����̌��āA���^�A���{�A�˚��A邘�A����Ղ��̓y���g�����܂��B�����̂��A�@�x�����߁A��i����݁j�𐧂��A�����ʂ����A�����]���R�t�Ɍ}���A�����U�i����j��㍲�ɕt���A������m���̕㍲�A�L�����R�t�̕㍲�ɒu���܂��B���ׂ̈ɐ����D��Ƃ��̌�̏����𒅁X�Ƃ����߂Ă���܂����B�u�̑c�Ɂi�����j�͂�����낤���Ƃ݂āA�@���ɒ������܂������A�@���́A�V���͎����ɂ���A�����ɉ����o���悤�ƂƂ肠��Ȃ������ƋL���Ă��܂��B�j
2025�N2��1���i�y�j��w�͋�
�{���́A���䂳��A���{����A���c����A��c����̎l�l
���c��������W���i�o-02�j�A
�u�`�͂�����youtube�@
�ԑ厚�F��L��w�т̌���
�Ώ����F��q�̒�
�����F�������ւ̉��
|
��{�̓���
��{�Ƃ́A��l�̛{�Ȃ�
|
��w�Ƃ́A���̊w�p�傢�ɂ��āA�ْ[�Ȋw�̔䂷�ׂ��ɂ��炴��Ȃ�B��Ɖ]�́A���A���[���i�������������j�̋`�݂̂ɂ��炸�B�����̎��葸���̋Ɂi���͂܁j���`�������˂���B���̌̂ɁA�K�\�܈ȏ㐬�l�̌���A������w�ԁB���Ƃ́A?�i���Ɓj�������ނ�҂́A�R�i����j�ĂȂ��Ƃ���Ȃ�A�s���҂̓��̔@���B
|
�����𖾂ɂ���ɍ݂�A
���͔V�𖾂��ɂ���Ȃ�B�����Ƃ́A�l�̓V��蓾�鏊�ɂ��āA���ˁi����ꂢ�j�s���i�ӂ܂��j�A�ȂďO������i���ȁj���āA�ݎ��ɜ�i�����j����҂Ȃ�B�A�i�����j�A���g�i���Ђ�j�̍S�i�����j���鏊�A�l�~�̕��i�����j������ਁi�ȁj��A�������L��č��i����j���A�R��ǂ����̖{铁i�ق��j�̖��́A�������i���܁j�����i���j�đ��i��j�܂���җL��B�̂ɛ{�ҁi��������j�c�i�܂��j�ɑ���ᢂ��鏊�Ɉ���āA���ɔV�𖾂��ɂ��A�Ȃđ��̏��ɕ��i�����j��ׂ��Ȃ�B
|
�{�w�̓��Ƃ��鏊�A���̒[�i����j�O����B���̈�́A�����𖾂ɂ���ɂ���B���́A���i�Ƃ��j�̎��̋`�Ȃ�B�}�i����j�������̂����������Ȃ֓���ǂ��A�l���ݕ��ɂ�����āA�����i���Ƃ��j���͂߂Ė��Ȃ�̂ɖ����Ɖ]�B�l�����_�l�i��Ⴄ�₤�j����A�������i����j���ē��鏊����̂����Ɖ]�B�����́A�V��萶�꓾�āA�g�ɂ��Ȃւ���ҁA���͐S�̖{�̂�Ŗ��Â�����B����l�S�̕�����A?�ɂ��Č`�Ȃ��A��ɂ��Ă悭���ʁi����Â��j���A�V�����ݐ������ȂւāA�V���̖�?�i�j�ɜ䂸�B�����Ȃ邱�Ƃ����̔@���Ȃ�B�R��ǂ�������𖾂ɂ��Ɖ]�́A���������Ȃӂ邱�Ɛ��l�}�l���ƂȂ�˂ǂ��A����鏉���A�����̂ɂ���ɂ��ق͂�A����Č�ɏK���̂�����ɂ��݂āA�����Ȃ鏊�A����ނ��Ƃ���B����ǂ��{�̖̂��͂���鏊�Ȃ��A���ɂӂ�A?�i���Ɓj�ɂ���ᢌ��i�͂���j�����Ɖ]���ƂȂ��B�w�҂���ᢂ��鏊�ɂ��Ă���𐄂����͂߂āA�{�҂̑́i�����j�ɂ��ւ�A�����˂ɖ����ɂ��Ă���ނ��ƂȂ��炵�ށB�������𖾂ɂ��Ɖ]�Ȃ�B
�ȉ��u�`���e
�����Ƃ������t�́A���Z�̖��O�ɂ��Ȃ��Ă��܂��B�A���́u�����v�ƌ����B�E�n�B�i���悤���j�̌܌o���`�ł́u�Ȃ̌����̓��v�ƌ����B���o�E���o�ɂ������̌ꂪ�o�ė��āA�Â����t�ł��B�Ȃ�ƂȂ��l�Ԃ̋P���������A�ƍl���āA������Ė��炩�ɂ��悤�B������j�Ƃ��Ă͂���ł悢�̂ł͂Ȃ����A�Ƃ��v���܂��B䤎q�́u�吴���v�Ƃ����p���p���āA�l�Ԃ��]���̃|�e���V���������S�Ɉ����o���āA����ς���菜���Ċ��S�Ȕ��f�͂���ԁA�ƌ����܂��B�����Ƃ͂��̂悤�ȓ��]�������Ƃ�ڕW�Ƃ���B
䤎q�������A����Ă͂����Ȃ����ƁF
���̂��߂ł͂Ȃ������̌��͗~�Ő���������A���邢�̓��C�o���ւ̎��i�Ŕ\�͂���l���̎ז�������i�~���̕��j�B
�͂��܂�������ő債�����Ƃ͂Ȃ����낤�ƌy���l���A��̑厖���l�����ɕ��u����A���邢�͂��łɑ厖�͉߂��Ă��邱�Ƃ𗝉��ł����A���ʂȘJ�͂��₵�Ă��܂��i�n�I�̕��j�B
���\�Ȑg���������Ђ������ďd��Ȏd����������A�t�ɐe�����Ȃ��l���ɑ��Ă�����ƕ]�����Ȃ��i���߂̕��j�B
���s���ł���킯���킩�炸�A���邢�͂悭�m���Ă��邱�Ƃ��ƍ����������Čy���ɔ��f����i����̕��j�B
�w��ł���Ήߋ��ɓ������Ⴊ�������ɂ��ւ�炸�A���߂Ă̏o�������Ƌ����Č����̂Ȃ������炯�o���i�Í��̕��j�B
���������o�J�ȃ��[�_�[�ɁA�w�ԌN�����͂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B䤎q�̌��t�ɉ����Č������̂悤�ȋ����ƂȂ�ł��傤���B
��q�̉��߂́A�v���҂̓N�w�ɂ̂��Ƃ��Ă��܂��B�����ɁA�N�w�I���߂�^���Ă��܂��B���W���̐}�i���W���G��w�͋�ߘa���N�j�͈ȑO�̂��̂����ς������̂ł��B��q�̒��A�������ւ̉���̔w��ɂ́A���̂悤�ȉ��߂�����܂��B
���̉��߂͒��q�A��������̓N�w�����Ď�q���ł��o�������̂ł��B��w����́w���f�x�̗��_�A����сw�Ўq�x�̗��_�I���q�����p����܂��B�܂����̐��E���u�́v�Ɓu�p�v�̓�ɕ������āA���ې��E�̔w��ɖ{�����B����Ă���A�Ƃ������_��u���܂����A����͍E�q��Ўq�̌Ñ�v�z�ɂ͂���͂����Ȃ������B��������̓N�w�I�e�������炩�Ɍ��Ď��܂��B��q�����v���҂͕����ɑR���āA��w��N�w�I�Ɉ�{����������Ƃ����ۑ�Ɏ��g�݂܂����B����ł��̂悤�ȓN�w���u�����𖾂ɂ���v�̔w��ɒu�����̂ł����B��q�͎l���̂����w��w�x�Ɓw���f�x�𗝘_�I����Ƃ��čŏd�����܂����B�w�_��x�w�Ўq�x�́A���l���q�����̌��t��w��ɂ���N�w�I�̌n���甭����ꂽ���t�A�Ƃ��ĉ��߂��܂��B������G������ł��錻�ۂ̐��E�̌������ɂ���{���̐��E��T�낤�Ƃ���N�w���A�`����w�ƌĂт܂��B�ߑ㒆���N�w���J�������N���Y��metaphysics��|�����̂ł��B���͌`����Ƃ������t���A�Ռo������܂����B���̃q���g�́A���łɎ�q���Ռo�ɂ���`����Ƃ������t���w���āA���ꂱ���Ñォ��u���v�̐��E��_���Ă������̂ł���A�Ƃ݂Ȃ��ėp�����Ƃ���ɂ���܂����B�������A�Ռo�������ꂽ�Ñ�̎��_�ŁA��q�̂悤�Ȍ��ۂ̌������ɖ{��������͂����Ƃ����c�_���Ȃ���Ă����Ƃ́A����v���܂���B�Ñ�ɂ́A�鉤���]�����̂Ƃ��āu���v���_����ꂽ���Ƃ͊m���ł��B�鉤�͓V���ƒn���ƕ��ї��u���v�̎�Ɏ҂ł���ׂ��ŁA�V�ɖ@��������n�ɖ@��������悤�ɁA�l�Ԑ��E��@���������Ď��߂鑶�݂ł���ƁB�������u���v�̖{���͉����ɂ��āA��q�̂悤�ȑ̗p�_��p�����_�c�����ꂽ�`�Ղ͂���܂���B
��q�w�͌㐢�A�]������낵���Ȃ��ł��B��������������Z�Z�N�O�̎v�z�ł���ƍl�����Ƃ��A�l�ނ̗��j�I�ɏd�v�ȓ_������܂��B����́A��q�w�ł͐l�Ԃ͒N�ł��V����P�u���v��^�����Ă��āA���ݓI�ɂ́u�����v������Ă���̂ł���A���l���}�l���l�ԂƂ��đP�u���v������u�����v�����邱�Ƃ͓����ł����āA�Ⴂ�͂����w�͂��邩�ۂ��ɂ����Ȃ��̂��A�ƁB���̕����v�z�𐢊E�������̎���ɑł��o�����_�́A�̑�ȂƂ��낾�Ǝ��͍l���܂��B���̕����v�z���v��ɐ������āA�����Ɏ�Εn���̎q�ł����������ɂȂ��Ƃ����ȋ��̐����ƕ��s���Ă������Ƃ́A���R�ł͂���܂���B����������q������͖���ł����ł��Ȃ��Гc�ɂ̉Ƃ̏o�ŁA���e�̑�ɂ悤�₭�ȋ��ɋy�悵�Ēn����l�ƂȂ����Ƃł����B���̎q�̎�q�́A�v�����łƂт���̖���̏o�ł������C�����⒣�쌬�ƁA�Γ��̎v�z�I�F�l�Ƃ��ĕt�������Ă��܂����B�v��̎�҂����́A���̐l�̊w��ɂ���ĕt�������o���͖��Ȃ��C��������܂����B
�������̂悤�Ȑ��ݓI�����v�z�Ɨׂ荇�킹�ɁA�����̐l�ԂɊi��������͕̂s�����ł͂Ȃ��A�w�͂��������܂ꂽ�܂܂ŕ����Ă��邩�̍��ł���A�Ƃ������ʂ̕s�����R������v�z���Z�b�g�ƂȂ��Ă��܂��B�w�͂̕����͌��ljȋ��ɋy�悷�邩�ۂ��̈�_�����ɍi���A���l��E�l�̋Z�\�͉��˂ȐE�ƂƂ��ĕ]������Ȃ��Љ�ł��Ă��܂��܂����B��q�w���Z�������؍��̎Љ�ł͐E�l�⏤�l�̋Z�p�ԕ������Ȃ��A�ƌ�����̂͂��̂��߂ł��B�ȋ��ɋy�悷�邱�Ƃ��B��̉��l�Ƃ���镶���ł́A�ꐶ��E�l�Ƃ��ĕ�炵�ďI��邱�Ƃ͌ւ�ǂ��납�p�����������Ƃł���A���߂Ďq���ɂ͒p����������������E�p���đ��h����銯���ɂȂ点�����Ɩ]�ށA�ƌ���ꂽ�肵�܂��B����Ɍ����A��w�̋��������Ȃ���ག͐l�Ԃ̌`�����������Ɠ������A�Ƃ����������ʂ̍����ɂ��Ȃ��Ă��܂��܂����B��q�w�̈����ʂ��܂��A������킯�ɂ����Ȃ��ł��傤�B
���z���̉��߂��A�ȒP�ɏq�ׂĂ����܂��B
�u��l�i��������j�̊w�͉��������Ė����𖾂ɂ���ɍ݂��B��l�͓V�n�ݕ��������Ĉ�̂ƈׂ��҂Ȃ�A���̓V�������邱�ƂȂ���Ƃ̂��Ƃ��A�����͂Ȃ���l�̂��Ƃ��v�B
���z���ɂƂ��Ė����Ƃ́A��l���珬�l�܂őS�Ă������Ă���u��̂̐m�v�ł���B��������l�͎��~�ɂ���ĉ�ƔނƂ���ʂ���܂łł���A�����𖾂ɂ���ΓV�n���������ƂƂ݂Ȃ��Đm���قǂ����S�����炩�ƂȂ�̂ł���A�ƌ����܂��B���z���͐l�ޑS�̂͂��납�R�쑐�Ɏ���܂ʼn�ƈ�̂ł��肱���e���ސS�������ɂ��邱�Ƃ������𖾂ɂ��邱�Ƃł���A����͐S����ł����ɂ��ł��邱�Ƃł���A�Ȃ��Ȃ�Ζ����͑S�Ă̐l�Ԃɐ��܂��������Ă�����̂ł��邩��A�ƌ����܂��B���z���͎�q�ƈ���Ė�����m�I�w�͂ɂ���ē�����̂Ƃ͍l�����A�S�̏ɂ���Ĉ�C�Ɏ��߂��A�Ƃ�������ł��B�ǂ���ɂ��꒷��Z������Ǝv���܂��B��q�̕����́A�����̊O�E�̒��Ɂu���v�������Đ��������Ƃ�����̂ł��B���z���̕����́A�����̐S�̒��Ɂu���v�������Ă��̐��ɏ]�����Ƃ�����̂ł��B��q�͐��E�𗝉����ď���Ⳃ�^���悤�Ƃ����҂̂悤�ł���A���z���͐��E�̒ɂ݂������̒ɂ݂Ƃ��Ċ�������Ƃ��~�ς��悤�Ƃ���@���Ƃ̂悤�ł���܂��B
��c�F䤎q�̉���_�A�i���v�m�A�Ўq�̐��ӁE���S���ʒu�Â��āA��w���퍑�������犿��ɕҎ[���ꂽ�Ƃ����Ƃ���͂悩�����Ǝv���܂��B��q�̖������̉��߂́A�`����w�A�N�w�Ƃ��Ė����Ȃ��̂Ǝv���܂����A�����͈Ռo�̎��������Ă������̂ŁA�u�q���`�v�ɂ́A��㺎����u���œV�����ρA�낵�Ă͒n�����@���B���̌̂ɗH���̌̂�m��v�Ƃ���܂��B�X�����ۂ��ǂ̂悤�ɐ������W���邩���A�z�A���T�ɂ�藝�����A�l�Ԃ炵�������A�Љ���̂��肩�������܂����B�����_�_�≩�邪�X�ɔ��W�����Ă������Ƃ�����܂��B
�@�������A�n��ł͐l�A���l���b�A�b�̑����ɔ��_���l�A�_���������܂�A�V�n�����R�ƂȂ�܂����B����܂œV�n�̒ʍs���ł������̂��A�V�n�f�����邱�ƂɂȂ�܂����B�R���̓V�˂ł����鉩�邪�����𐧂��܂����A���肵���������s���ɂ́AꟂ̑��z�̂��Ƃ��N�ɂ��y�Ԍ����A�����A�w�̐e�ɎE���ꂻ���ɂȂ��Ă��e�ɐs�����F��K�v�Ƃ��܂����B��㺎�����̓`���������Ƃ���܂��B�������̎���10�̑��z������l�X�͝�鯂ɋꂵ�݂܂��B9�̑��z���˗�������ɖ߂�܂����A���x�͑�J���J�ő�^���ƂȂ�܂��B�Z����B������A�g�ɂ��āA�R�����A���H��A����C�ɂȂ��A�^����������܂��B�����āA��B�̓y�n�̒n������Y���ɂ��A�ł��߁A�����^�c�����b�����Ƃ��܂��B������������������������ɘ_���H�тł́AꟂ��w�Ɂu��������v�Ƃ����Ƃ���܂��B�ɒ[�Ȍ����E������F�ɂ͗\�����Ȃ����Q���N��܂��B�Ўq��䤎q�ȑO���炠�����������������܂��܂ȍl�������܂߂āA��q���N�w�I�ɐ������ꂽ���̂Ǝv���܂��B
�����F�����Љ�ł͏t�H�̍����琩�A���������W�c�ɂ��^�c����Ă���B�ȋ��̎���ł͗D�G�Ȋ��������ƂȂ���̂łȂ��A�����Ƃ��ďo�����Ĉꑰ���������ĂĂ䂭�B��q�������Ŋ����ɂȂ邽�߂Ɋw�сA�o�������B�����̑n�n�҂͂���������������͂��ꂽ�ҁA���̎錳���͈�_���̏o�B���̑��@���k���̏o�g�A�����̍c�@�͌Ӑl�̌����A���̍��d���_���ŏ����N���X�̏o�ŁA�����̃g�b�v�͐�������͂łȂ��B�ё͔_���Ƃ������L�͂Ȓn��A�o�g�W�c���炷��Έْ[�ҁB���̑n�n�҂������B�������ǂ��Ȃ̂��Ƃ����Ƃ���B
��q�̓N�w�ł����A���[���b�p�̓N�w�͍����_�A�o���_�ŁA�����Ɍo����ς�ł����Č`��������̂ł����A�����͐��܂�Ȃ���ɔ�����Ă���Ƃ��Ă���B��m�I�ł���A�m�ł��܂��䂭�̂��B�܂����{�ł͌����Љ�ł��������A���܂�m��K�v�Ƃ��Ȃ������B�m���Ƃ��ē����Ă��邪�A���g�o���ׂ̈Ɏg���悤�Ȃ��̂łȂ��B�����ł͈�ཁA�ؐl���������ꂽ����ǁB
���c�F���E���L�͕��Q�҂̂悤�Ȃ��̂ł����B�������o���鎞�ɂ́A������𗧂Ă�l�����o�Ă��ꂪ������ƁA���̉��ɐl�ނ��W�܂��Ă����܂������̌`���ł�������܂��B�����ł͂����������Ƃ�����I�ɋN��A�����_�I�Ȏd�|��������Ǝ��͊����Ă���Ƃ���ł��B���̎錳���́A���{�I�Ɍ������N�U�̐e���ł��B���C�o���̒��m���́A���l�ł��B�������̌���́A���N�U�Ə��l�̐킢�ł������B���̂��ꂼ��ɁA�m���l�����Ă��܂����B�����ł́A�������J���҂͓V���疽�����҂ł���A�l�Ԃ̗͂��y�Ȃ������������ď���B���������̉��Ő��x�����̂͊����ł���A����͐l�Ԃ̐��E�ł����Ēm���l�����B�����ł́A�����Ƃ��ёƂ��������ł����A�������ȏo���̃g�b�v�ł��V����I�ꂽ�炻���m���l�����Ղ���B�����̒m���l�͏�ɐ����I�ł���A�����ɎQ�悵�悤�Ƃ��܂��B�����ۂ����{�ł́A�m���l�Ɛ����Ƃ͐藣����Ă���B���{�̒m���l�́A�����Ɋւ�낤�ƌ����Ă��Ȃ��B�������傫�ȈႢ�ł��B
�����F���������A�O���u���`�␅���`��ǂ̂ł����A����������Ȃ����̍������W�܂�̐���Ƃ������Ƃɒ����̃o�C�^���e�B�[���������B�������A�����ɂ��뉤�z���ɂ��낻�������m���l���g�b�v�ɗ����Ƃ͂Ȃ��B
���c�F���̔��z�͂Ȃ��ł��ˁB�g�b�v�͓V���̍~�肽�ƌn�ł���A�l�Ԃ̂͂���m��̈�ł͂Ȃ��B�������̉��̍ɑ��܂ł͐l�Ԃ̓w�͂œo�邱�Ƃ��ł��āA�����������͌��͓����ʼn�ȑ������s���A�������ւ���������Ȃ��B�Ȃ����{�ɂ͂��ꂪ�Ȃ��̂����s�v�c�ł��B
�����F�������̕��́A�w�����������������܂�p����ꂸ�A�A���Ă��n�ʂ��Ⴍ�A���^���Ⴉ�����B
���{�F���^����Ȃ������̃|�P�b�g�}�l�[�B
���c�F���{�Љ�ł́A�������Ӑ}�I�ɑ���Ƃ������̂ł͂Ȃ��A���̂܂ɂ��o���Ă䂭�ƍl���Ă���߂�����܂��B�����ł́A�����͒m���l�������̂ł���B
�����F�M���V�A�ł̓f���|�C�̐_���Łu�����g��m��v������܂����A���Ƃ͖���������ł͂Ȃ��B
���{�F�\�N���e�X�ł����B
�����F�����͒����I�œ��{�ɂ͂Ȃ��B
���{�F�\�N���e�X�͂ǂ��]���Ă܂����B
�����F�v���g�����L���Ă܂����A����������Ɖe���ł���B�����݂�Ƃ܂Ԃ����ĉ����݂��Ȃ��B��X�����̂Ƃ݂Ă�����̂̓C�f�A�̉e�i�v���g���̃C�f�A�_�j�B������䤎q�̘b�͂悭������ʔ��������B䤎q�͒���������䂭�Љ�ɂ������B
���c�F����䂭�̂ł����A�܂��V���������̎n�܂�ł�����܂����B���̎���w�h�̌𗬂�����A�ʉ݂̗��ʁA�v�z�̗��ʂ��n�܂��Ă��܂����B���̐V��������I���Ƃ̒����̒��œ��ꍑ�Ǝv�z�����A���̒��ʼn����̌N��ƃX�^�b�t�͂ǂ̂悤�Ȋw���A���f�\�͂����ׂ������l�����܂����B
�����F�Ăł͍��s��
��淄���l��Ɋw�Z���J���A�e�n����w�҂��W�ߖ@�ƂȂǂ�y�o�����B
���c�F���z�͑^�̐l�ł����A䤎q�Ɋw�ѐ`�ɍs���C�s��Ɏd���܂����B䤎q����̐l�ł����ĂɗV�w���w���E���߂܂������A槌�����^�ɍs���A���z�����̖��@�������̂ł��B
�����F��w�̈��̐��i�t���͎���f���Ă���B�m���l���e����]�X�Ƃ���̂̓��l�b�T���X�̎���������B�s�s�̎s����I�ԂɁA������ۂɂ͊O���l��o�p���邱�Ƃ��s��ꂽ�B�~�P�����W�F���̓t�B�����c�F�̐��܂ꂾ�����F�l�c�B�A�A�{���[�j���A���[�}�ƁA���I�i���h�E�_�E�r���`�̓g�X�J�[�i�Ő��܂�t�B�����c�F�A�~���m�A���[�}�A�{���[�j���A���F�l�c�B�A�A�t�B�����c�F�A���@�`�J���Ɠ]�X�Ƃ��Ă���B
���c�F�����̓��̐Ă͌o�ϑ卑�ŁA�Ō�܂Ő`�ɒ�R�ł��鍑�͂�����܂����B�w��ł��l���̊w�҂�S��������W�߂āA�Ő�[�̎v�z�̒��S�n�ƂȂ�܂����B�������Ўq���ᔻ���Ă��܂������A�Ă̐����͌�����`�Ŏ�v�Ȑ����I�|�X�g�͉��Ƃ̓c��������肵�A�]���҂ɐ����������邱�Ƃ�����܂���ł����B�����ۂ����̐`�ł́A�O���l���ɑ��ƂȂ�܂����B���ׂ͉q����`�ɓ���A�豂�鰂���`�ɓ���A�C�s����₩��`�ɓ������B��������ɑ��ƂȂ��Đ`�������ɂ��܂����B�`�͊O���l����O�̂悤�ɗv�E�ɏA���āA�V���ꂵ���B�Ă͋����ł���w��ł͈�ԗD��Ă��܂������A�V������͂ł��܂���ł����B�����A�퍑����ł͂����������O���l�����R��ɑ��ƂȂ�Ƃɂ킩�ɋ����ɉ����グ����т𐬂��̂ł����A���̖��H�́A�삷�鉤�����݂̊Ԃ͉��v��i�߂�̂ł����A���̉����S���Ȃ�Ɠ���������ē{������ߍ���ł����M����������ĂɍU�����s���Ė��c�ɎE�����B���ꂪ�퍑���邠��ł����B
���{�F�c���ӎ��݂����Ȃ��̂ł��B
�����F���Z����ɁA�������A�S��������������Ƃ�����܂������A���ꂪ�悭������܂����B
���c�F�]�ˎ���ɂ��ꂪ�u�[���ɂȂ����̂́A�Ȃɂ����[�����̂�����Ǝv���A�v�ٓI�c�_�ɐV�N�Ȃ��̂��������̂ł��傤�B
���{�F�]�ˎ���ɂȂ��āA��҂����h�����悤�ɂȂ����B
2025�N3��1���i�y�j�����搶�u�`��
�{���́A���{����A�۔�����A���c����A��c����̎l�l
���c���W�� �@�u�`�̌�����J�ɂ���
�������A���{�Ř_��A���u����̑�����A���Ə�c����ōs���Ă܂���܂����B�������V�搶�������\�Ȃ���܂����B�e�[�}�́u�w�_��x�Ɓw���f�x�ɂ����闝�z�I�l�����Ƃ��̐����ւ̊ւ��v�ł����B
���W���Ȃǂ͂���܂���ł������A���̍u�`�̊T���������`���������Ǝv���܂��B
- ��q�͎l���Ƃ��Ę_��E�Ўq�E��w�E���f��I�сA�����ꂳ�ꂽ�v�z���q�ׂ������т����ϗ����Ƃ��ēǂ����Ƃ���B���̌X�����A���܂��ɑ����Ă���B�������Ȃ���A���̎l���͐����������オ�Ⴂ�A�z�肷��ǎ҂Ɨ��z�Ƃ��鐭�����قȂ��Ă���B
- �傫�������āA�_��E�Ўq�^��w�E���f�ɓł���B�O�҂̐����́A�퍑�����`�����ł���A�܂��������V�����ꂳ���O�̎����O��Ƃ��������ł���B��҂́i��q�͘_�Ђ̓�����ƌ����Ă���̂́A���Ԃ́j�`�鍑�ɂ�铝��̌�A����̐����Ƃ݂Ȃ����ق����悢�B��w�E���f�́A���炩�ɓ���鍑����������œV���̓����������ɍs���ׂ�����_�������ł���B������E�q�E�Ўq�̐�������������̌����Ƃ݂Ȃ����Ƃ͂ł��Ȃ��B
- ���f�ŗp�����Ă���p��͂���ƁA�@�n�c��̍��Ɍ����郌�g���b�N�����ς����Ɛ����ł���i�����`�Y���̎w�E�j�A�A�u�؊x�v�i�؎R�Ɗx�R�A蟐��ȁj�𒆍��̑�\�Ƃ��Ď��グ��B�E�q�Ўq�͌��݂̎R���Ȃ̐l�őR���\�Ƃ��邪�A���f�̍�҂��E�ЂƓ����n��Ŋ������Ă�����؊x���\�Ƃ���͂����Ȃ��A�B�p��ɕ�����E���یꂪ�����A�Ўq���㐢�̏��ł���ƍl������B
- �_��́A�t�H�����`�퍑�����̒��������h���鎞��A���[�_�[��⍲����l�ނ̗ϗ����q�ׂ����ł���B���̂Ƃ����[�_�[�͕K�����������Ȏ������̏���ł���Ƃ͌��炸�A�o�����̎��͎҂��e���e�n�Ŕe���������ēo�ꂵ�Ă����B�����Ɏd���Ă悫�⍲���Ƃ��Đ������s���҂̗ϗ������������̂ł���B�������e����ڎw���̂ł͂Ȃ��A�u���[���Ƃ��ă��[�_�[���x�z����s�W�ōs�����E���Ŋ��Ƃ��ē����C���[�W�B�ϗ��I�ɐ����ŁA�_���𗠐�Ȃ��B�E�q�͒Ⴂ�g���̏o�g�ŁA�`���I�ȉ��l�ςł͘D���̐����ɂ͌g��邱�Ƃ��ł��Ȃ��g���ł������B�ނ̉��ɏW�܂�����q�������A�G���ȊK�w�̏o���̎҂����ł������B�ނ炪�ڎw�������́A�������鎞��̒��ō����ϗ��ς�g�ɂ��Ď��͎҂̐����ȃX�^�b�t�ƂȂ邱�Ƃł������B���{�̗��j�Ō���������Ȃ�A�퍑����̎��͂���喼�̉��œ��p������킷�l�ނ�ڎw���悤�Ȃ��̂̂ŁA�喼�̏o���͂��͂���ƂȂ�Ȃ�����ł������B���̂悤�ɍ����搶�͂��Ƃ��Ă��܂����B
- �Ўq�́A�퍑�����ɔe����ڎw�����������x�Ɍł܂�������A���̑剤�����̎t�ƂȂ肱���V���̎�ɓ������Ƃ�ڎw�������ł���B�Ўq�͌N��̎t�ł����đ剤�����ɓ��������邱�Ƃ͂Ȃ��A�e���̐����ɑ��Ă��ӌ��͂��邪�ӔC�͎��Ȃ�����ł��邱�Ƃ���������B
- ��w�́A�V�����ꂪ����������ɁA�c�邠�邢�͍c��ɂȂ肤����ҁi���Ȃ킿�����̏���j���w�ԓ��i����������A�鉤�w�j�����������ł���Ǝv����B
- ���f�́A��������Ɂu�N�q�v�̓������������ł���Ǝv����B�u�N�q�v�Ƃ͍c��i�V�q�j�͏�����A�c��ɂȂ�\�������鏔��A���ꂩ�炻���Ɏd����m��v�܂Ŋ܂܂��B�N�q�͒��f�̓���I�сA�鍑�����̒��ʼn����Ȕ��f���s���Đ����邱�Ƃ����������B
���������́A�킽�������c�̌����ł��B�������́A���c���M�����䂵����ɊO�ʂ̘C���ꑰ�������ӒD��ԂƂȂ�܂����B�������C�@�̖v��ɃN�[�f�^�[���N���ė����������������A���̂Ƃ����M�̏��q�ł���㉤������Ƃ��ď�����A�ȍ~�͕���̌n�������͂܂ő����܂��B���̂Ƃ������̏��e�n�ɉ����Ƃ��ĕ�������Ă��܂����B����A�Â��i��̎���͂܂���Ƃ̗͂͋{��ŋ����Ȃ��A���̕���̎���ɓ������̐s�͂Ŏ��v�z�ł͑S�ʂɗ��悤�ɂȂ�܂������A�܂�����̓X�^�b�t�ɖ@�Ƃ̊������d�p���Ă����Ԃł����B�������̐������x�z����悤�ɂȂ�̂́A���鎀��̏���E���̎���ɍɑ��ƂȂ���跌��̎���ȍ~�̂��Ƃł��B
��w�E���f������ɐ��������Ƃ���Ȃ�A����͊����������ď���ɋ�����e�L�X�g�Ƃ��ď����ꂽ�Ƃ������́A������O�ɁA����E�i��E����Ɖ����̌p�������肵�����������v����āA�����̎�Ƃ����̓V������̎���ɂӂ��킵���N��ƌN�q�̗ϗ��͂����ł���A�Ƃ݂Ȃ��Ď���I�ɍ쐬�������̂ł���A�Ƃ������̂ł͂Ȃ������ł��傤���B���ꂪ����̂Б��̐��̎���ɂȂ��ė�L�̕тƂ��č̗p����A���ɍ��ƂƂ��Ċw�Ԃׂ��e�L�X�g�ɂ܂ŏ��i���ꂽ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����ƌ����A�i���ɋN���������^�����̗��܂ŁA���͑����̗͂������Ă��܂����B�����̏����͍c��ɏ�����V����s���A�����ʼn����̊�����I��Ŏ����Ŗ@�߂�����Ă��܂����B�����ꑰ�̌����́A�����̂̓��R�ŗ������g�����đK�𒒑����A�K�̗��U������ѐ������ƂŔ���ȗ��v���グ�Ă��܂����B���̎����̒����͓y�n���痣�ꂽ�������������݂��Ă��āA���ꂪ�`���̒����L�̗��̋N���܂ƂȂ����̂ł����A�����Ȃǂ̏��͂�����J���͂Ɏg���ēƗ������ł���܂ł̍��͂�~���Ă����̂ł����B���㏉���͐`�鍑���퍑������łڂ��������ŁA���𗫎��ɕς��čĂѐ퍑����̂悤�ȏ������ꂼ��̐������s�����Ƃւ̈������傫�������̂ł����B�i����A�����̗L�͂ȏ���𒆉��̒��삪�Ԃ����j�𗧂Ă��B���̂��ߌ����ق����̉����N�������̂����^�����̗��ł����B���������͗\�z�ɔ����Ă������Ȃ����肳��܂����B
����̌�̏��́A�Ӑ}�I�ɕ��������������ė͂𗎂Ƃ��A�����͒����̖@���̓������ɒu�����悤�ɂȂ�A������ȍ~�͒P�ɉ����ɐH�킹�Ă��炤���̃X�y�A�ɂ܂ŗ����܂����B����ٕ̈�Z�̒��R���������Ȃǂ́A���̋���ȕ悪���@����Ă����ւ�Ȃ������������Ă������ł��������Ƃ��킩��܂������A�L�^�ł͎��Ə��ɂӂ����ĉ������Ȃ������B����́A���������ɂ܂�Ă����Ԃ��ɂȂ邩������Ȃ��Ƌ���āA�����Ė��ׂł����悤�ł��B�^�ɍc�錠�͂��m�����A���z�ق��̎��Ӑ��͂ɗD�ʂ�������悤�ɂȂ�̂́A�i��ȍ~�A������ł��B���̎����ɂȂ��čc��Ƃ��̐��{�͓V���S�̂������Ό��͂������ƂɂȂ�A����͂ǂ�ǂ���������������āA��������Ă��ƂȂ�������悤�ɂȂ����B���̌��͂������ĕ���͙��z�ɔ������J�n���A���ӂɂ�����ɏo�����Ċ������̔Ő}�����{�ɂ��g�����邱�Ƃɐ������܂����B����͔���Ȑ����A���Ə��炠�����i�Œ��B���܂����B���ɂ͕K���i�̉��ƓS��ꔄ�Ƃ��āA������啝�Ɉ����グ�Ď����𑝂₵�܂����B�ł̎����ɂ́A�傫��������3�ʂ肠��܂��B��͌����łł��B�܂�N�v�ł��B�������A����͂��͒�������̂���ςŁA�W�߂ĉ^�ԕ��S�����ɑ傫���āA���ł̔\�����悭����܂���B��́A�J���ɂ��ŁA�����ł��B���̓y�n���k�삳����A�������Ƃɓ�������A�����̉^���𖽂���A���邢�͕������ۂ��B�̂��g�����[�łł���A�×����疯�̋ꂵ�݂ł����B�݂��ɑK�Ŕ[�t������łł��B����͕����̉^�����K�v�łȂ��A���Ƃ��K�v�ȘJ����ŋ��Ŕ������Ƃ��\�ƂȂ�A�ł��\���������łł��B�Ȃ̂ŁA���ƂƂ��Ă͂ł������Őł���肽���ƍl���܂��B�����K�̗��ʂ��s���͂��Ă���o�ςɌ����ĉ\�ŁA���j����̔��B�i�K���K�v�ł����B����́A�Ñ�ɂ����Đ��E�̒��Ŕ�r���Ă������ɓ��K�̗��ʂ����B��������ł����B�K�ɂ��[�ł̕��@�͊֏�������A�s�ꂩ����A�_���⏤�l�̎���������A�Ȃǂ���܂����A���ʓI�ȐłƂ��Č×����畨�i�ւ̉ېł�����܂����B����̌��t�Ō����A����łł��B����̎���A�K���i�̉��ƓS�̐��Y�����Ƃ��Ɛ肵�āA���̔̔����ɏ���ł������Đꔄ���܂����B������ɔ���Ȃ�������Ȃ��i�ڂȂ̂ŁA�ł�傫�������Ă��������オ��B���̐ꔄ�͂���������葁���Ŏ����グ���i�ł���A���̌�̗�㒆�������͉��̐ꔄ���D��ŗp�������܂����B���ǁA������Ė��������i�킳��邱�ƂɂȂ��ĕ��S�ƂȂ�̂ł��B����̉����́A���̋]���ɐꔄ�Ő푈�̐��ߍ��킹���̂ł��B
�S���̏���ɑ��ẮA�c��ɒ��R����ۂ̗畨��@���̍��J�̔�p�Ƃ��Ĕ���ȋ��i��[�������āA����̍����̋]���̏�ɒ����̍������U���鐭��𑱂��܂����B���������������I�ȍ��́A�i��̌�̕���̎���ɂȂ��ĉ\�ƂȂ����̂ł���A����䂦�ɕ���͋���ȑΊO�푈���s�����̂ł����B
���̂悤�Ȍ����ɑ��āA����̎v�z�ɂ͕��邩���̎���ɂ͎̓��������Ԃ���܂����B���Ȃ킿�c��͓V�q�Ƃ��ē����҂̓����������A����͐b���Ƃ��ē����������Ƃ����҂����悤�ɂȂ�A���Ƃ͗͂���ł͂Ȃ��ČN�b��̂̓������K�v�ł���ƔF������鎞��ƂȂ�܂����B�Ȃ̂ł�����w���f������f�������z��`�������Ƃ���Ȃ�A�i������߂���������ȍ~�̌����ɂ��傤�Ǎ��v����B����āA���̎���ɏ����ꂽ�̂������Ƃ��ӂ��킵����������܂���B����́A���̏���ȉ����ł��B
�ȏ�̂悤�ɁA�����搶�͒��f����ё�w��_��Ўq��萬��������x�����āA������V�����ꎞ��A������������ɐ������肳��Ă��܂����B�������A���_�������܂��B�ЂƂ́A�i�n�J�̎j�L�Ɂu�q�v�����f���������v�Ƃ����L�^�����邱�ƁA������ǂ���舵���̂��B���̓_�ɂ��Ď��͇@�i�n�J���A�k���Ă��ނ̕��̑ゲ��ȍ~�ɐ����������f�̍�҂ɂ��āA���Ⴂ���邱�Ƃ����肦��̂��낤���A�A�i�n�J�����y�������f�́A���݂ɓ`��钆�f�̃e�L�X�g�Ɠ����Ȃ̂��낤���A�Ɛ搶�Ɏ��₵�܂����B
�ӂ��́A1990�N��ɐ퍑����̑^�悪���@����āi�s�X�^��j�A��������u��L�]�ߕсv���قڊ��S�Ȍ`�ŏo�y�����B�u��L�]�ߕсv�͗�L���f�тق��ƕ���ŁA�q�v�q����̘^���ꂽ�Ƃ����ËL�^������i�@���j�B�u��L�]�ߕсv���퍑���㒆���i�����炭�Ўq�������j�̕�ł���Ƃ����l�Êw�I�l���������Ƃ���A��L���f�т��܂����Ȃ��Ƃ����̌��^���퍑����ɑ��݂��Ă����͂��A�Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��̂��B
����ɂ��ẮA���f�̒��Ԃɂ���ⓚ�����i�����ƍE�q�j����эE�q�̊i���W���I���W�i���̒��f�ł���A�O��̒��ۓI�v�������i��q�ɂƂ��čł��厖�ȉӏ��ł��j���邢�͒��f�̃e�[�}�ɉ������E�q�̌��t�̒lj��͊���̑���ł���A�ƍl���邱�Ƃ��\�ł��邩�Ǝ��͎v���܂��B�u��L�]�ߕсv�͂��ׂčE�q�̌��t�ɂȂ��炦���i���W�ŁA�I���W�i���̒��f���܂����̒��x�́A�_����͓��e���ڍׂƂȂ��Ă��邪�A���ݓ`����w���f�قǒ��ۓI�ł͂Ȃ��A�E�q�̌��t�ɂȂ��炦���i�����Ï��p�ɕ��ׂ��e�L�X�g�ł������̂�������܂���B�����搶�ɂ��Ύi�n�J�͊ԈႢ�𐔑����s���Ă���A�Ƃ������Ƃł����A������������i�n�J�́u���f�͎q�v�̍�v�Ƃ����`�����������グ�Ďj�L�ɏ������̂ł���A����̎�Ƃ����M�����u���f�v�啝����łɂ��Ă͓ǂ��Ƃ��Ȃ��A�����W�����Ȃ������̂�������Ȃ��B
�۔��G���f�̃e�L�X�g�ɐ̖�������������������ꂽ�Ƃ��A�r�b�b�N���ł��B���������l�����͐̂��炠�����̂ł����B
���c�F��q�w�ł́A�q�v�̏��������̂ł���ƒf�肳��܂��B��q�w�̐M��҂ɂƂ��Ă�����^���Ƃ͂Ƃ�ł��Ȃ��b�ł����A�^���l�͐̂��炢�܂����B�����`�Y�搶�́A�n�c����ȍ~�ł���ƍl���܂����B������1990�N��Ɋs�X�^�悩��u��L�]�ߕсv���o�Ă����B�u��L�]�ߕсv�́u���f�v�Ɠ������w�q�v�q�x������ꂽ�Ƃ����ËL�^������A�u��L�]�ߕсv���o�y�����^��͖Ўq�̓�����A�퍑���㒆���̕�ł���Ɛ��肳��܂����B����Ȃ�Β��f�����������̍����炠�����̂ł��낤�A�Ƃ������_�����藧�B�L����w�̖��i�搶�́A����Łu���f�v��퍑�����ł��낤�ƌ����Ă���Ƃ������Ƃł��B�����������搶�́A���ԕ��̌�^�W�Ɩⓚ�͌Â������̉\�������邪�A�O��̓N�w�I���q�����������s�̃e�L�X�g�͊���ɐ��������̂ł��낤�A�Ɛ��肵�Ă��܂��B
�۔��F�����������Ƃ��]����͍̂����搶���͂��߂Ăł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł����B
���c�F�q�v�̏��������̂Ƃ��邱�Ƃ��^�⎋���邱�Ƃ́A���{�̊w�҂���O���猾���Ă��܂��B
���{�F���͂قڒ���B
���c�F��U����ɂȂ����̂ł����A�^�悩��e�L�X�g���o�Ă��āA�܂�����܂����B���͂ǂ���璆���ł͐퍑�����Ō��肵�����̂悤�ȋ�C�ƂȂ��Ă���悤�ł����A�����搶�͂���ɞ������ӌ��Ƃ����킯�ł��B���ǂǂ���Ƃ��������˂��ԂƂȂ��Ă��܂��B
�۔��F�O��ƒ����قȂ�Ƃ������ƂɂȂ����B
���c�F�퍑����ɒ��f�̃e�L�X�g�̌��^���������\���͂���܂��B�����ƍE�q�̖ⓚ�̂悤�ȕ����́A�I���W�i�����f�Ƃ��ČÂ����炠�����̂�������Ȃ��B���������̑O��̕����ɂ͓N�w�I�ȍl����������A���x�ɒ��ۓI�ȗp�ꂪ�p�����Ă���B����͂��Ȃ莞�オ����\��������A�܂������̒��̒��f�Ƃ����A�V�����ꎞ��ɂӂ��킵���ϗ����W�J����Ă��āA�`����̑��₩������Ȃ��B
��c�F���f�̖`���Ɂu�V�̖����邱��𐫂ƈ����v�Ƃ���A���f�Ƃ͂��̐��̂܂܂ɐ�����Ƃ������ȓN�w�I�v�l�@�ƂȂ��Ă���B�����ƍE�q�̖ⓚ�����ł́A�������u���v�ɂ��Ė₤�ƍE�q�����o�⏑�o�����p���Đ���������B�����E�����́u���v��m�邱�Ƃ��o���邪���p�o���Ȃ�������Ȃ��B����ɂ͊��p�o����l���ɂȂ�Ȃ�������Ȃ��B���̂��߂ɂ͓����C�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��A����ɂ͐m�łȂ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������ȓW�J�B
���c�F�퍑����̒���ɂ͂悭���邱�Ƃł����A���̖ⓚ�͂����炭��҂������ƍE�q��o�ꂳ���āA�����̌����������Ƃ����킹��ⓚ��n�삵���̂ł��傤�B�v���g�����A�\�N���e�X��o�ꂳ���Ėⓚ������Ȃ��Ɏ������J�����̂Ɠ��������ł��B
��c�F���q�Ȃ��E�q��o�ꂳ���A������点�A����Ȃ��Ƃ����邩�琢�̒����������Ȃ�݂����Șb�����B�_��ɂ͈����Ƃ̖ⓚ�̂悤�ɁA���ǂ��ǂƐ�������悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B
�۔��F���f�͂���܂œǂ��Ƃ��Ȃ��̂Ŗ��͂��킩��Ȃ��̂ł����B
���c�F���f��m��Ȃ��Ă��A�L���ȓ�l���̏n�����{�l�͌��ɂ��܂��B�������^�i����ӂ��悤�j�͋��璺��ɂ��łĂ��܂����A�S�ɂ�������ƕ����Ў����킷��Ȃ����ƁB�{�k�i�����j�́u�����v�ŁA�{�k���m�ɗ����ׂ��炸�B���O�A�����A���̑��u���f�v�Ɓu��w�v�ɂ͗ϗ��E�����ł悭�g���錾�t����������܂��B
�۔��G�u���v�Ȃ������ł��ˁB�����͒��f�ɂ͂��߂ďo�Ă���̂ł����B
���c�F�m���������Ǝv���܂����A������Ɗm�M���Ă܂���B������q�́u���v�̌���Ђ�ς�Ɏg���܂��B����œ��{�l���g���悤�ɂȂ����B�����搶�́A���{�l�͒m��Ȃ������ɒ��f�I�ɂȂ��Ă���ƌ����Ă��܂����B���́A�ނ�����{�l�͒m��Ȃ������Ɏ�q�w�ɐ��܂��Ă���ƌ��������Ƃ���ł��B�]�ˎ���̐l�́A���f���w��K���ǂ݂܂����B�����▾���ېV�̐l�́A������Ƃ��̍l�����ɉ����悤�ɂȂ�A��������̍��_�ɓ���悤�ɂȂ����B�V�����ƁA�{���]�|�A�o�d�A�C�g�A���ꂩ�狳�璺��ɂ͌������^�B�����l���A�ϗ����l����Ƃ��ɁA���f��w����p������o���A���f��w�̘g�g�݂ōl�����B����͂Ƃ���Ȃ������A��q�w�̃��[���̏�ӎ��ɑ����Ă����Ƃ������Ƃł��B
��c�F�����搶�́A���f�͊���ɍc��ł͂Ȃ��l�X�ȏ����m��v��ΏۂƂ��ĕҎ[���ꂽ�Ƃ���w�E�ł��������̂��A���c���A���̎������A���^�����̗��ȍ~�A����̌S���������L�͂ȏ��Ȃ��Ȃ�A����ꋭ�̑剓����̔敾�������ƒ����𗧂Ē��������A����A���A����̎���Ɠ��肵�����Ƃ�����݂̂��B���̎��Ɍ��o�����V�q�Ə���A�m��v�̊W���Y������Ƃ����B
�܂��A�����搶���i�n�J�ɂ͌��\�ԈႢ�������A���f���q�v�̍�Ƃ���̂����ĂɂȂ�Ȃ��Ƃ��ꂽ�̂ɂ̓r�b�N�������B
���c�F�i�n�J���L���ȏ�͉����̎����ɂ���Ă���͂��ŁA���̒��f�̃e�L�X�g�Ƃ͈قȂ�Ƃ��Ă��A�����ƍE�q�̖ⓚ�̂悤�ȕ����̂��̂����邱�Ƃ�m���Ă����̂�������܂���B���ꂪ�q�v�̍�ł���A�Ƃ����`�����ċL�^�������A���s�̒��f�e�L�X�g�̑��݂͒m��Ȃ������̂�������܂���B
��c�F����̖��ɍE�q�̋���̕ǂ��異�������邽�߂ɉB���ꂽ�e�L�X�g���o�Ă����B���̒��Ɂu��L�v������Õ���131�т������Ƃ����B�O���̑Փ��i�����Ƃ��j�Ƃ��Ր����ĕ҂��āA���݂ɂȂ���Ƃ���A���f���w�A�����ƍE�q�̖ⓚ�����̒��ɂ���A�`�̎��ɉB����Ă���Ƃ������Ƃ́A����ȑO���炠�������ƂɂȂ�B
���c�F����ɑ��݂�����W�̃e�L�X�g���A�Փ���85�тɐ��������i���L�A���݂͈ꕔ�̂ݎc���j�B���̑Ր���49�тɕҎ[���A����49�т̂��̂����L�ŁA���݂́w��L�x�ɂȂ���܂��B�Ҏ[���ꂽ�͕̂���̂Б��A���̎���ł����B����������ł��A���̎���ɌÂ��`���Ƃ݂Ȃ��ꂽ�e�L�X�g��I�͂��ł���A�����ߔN�̍쐬���邢�͑��₪�������e�L�X�g�������������̂͂ǂ������킯�ł��낤���A�Ƃ����^�₪�c��܂��B
2025�N3��29���i�y�j��w�͋�
�{���́A�Z�c����A���{����A�۔�����A���c����A��c����̌ܐl
���c��������W���i�o-03�j�A
�u�`�͂�����youtube�@
|
�ԑ厚�F��L��w�т̌���
�Ώ����F��q�̒�
���厚�F��q�̏������낵��
���厚�F�������ւ̉��
|
|
����e�i���炽�j�ɂ���ɍ݂�A
���q�H���A�e���c�i�܂��j�ɐV�ɍ��ׂ��A�ƁB
�V�Ƃ͑����p�i�ӂ�j�����v�i���炽�j�ނ�̈��i�����j�Ȃ�B�����͊��Ɏ��瑴�̖����𖾂��ɂ���A���c�i�܂��j�ɐ����ĈȂĐl�ɋy�ڂ��A�V�����Ė��i�܂��j�L
�Ȃđ����p���i���イ����j�̉��i���j�����炵�ނׂ��A�ƂȂ�B
|
����͖���e�i����j�ɂ���ɂ���B���e�̎��͐V�i����j�ɍ�i����j�Č���ׂ��B���͑��l�Ȃ�B��w�̋ƁA�V�����ɂ���Ɏ���
�̈ʂ���l�ɛ����Ė��Ɖ]�Ȃ�B�����V�ɂ��Ƃ́A�l���K���ɂ��݁A�ӂ�т�����A���炽�߂āA�����炵���Ȃ����Ƃ��]�B������������
�ɂ���̂��ƂȂ�B�W�i�������j�l�́A�ݕ��̒��Ȃ�A�V�̉���̋y���鏊���A�ِ��㑊�i���������ق��Ⴄ�j���āA�������������ׂ��B
�}���Ȃ𐬂��A���𐬂����ƁA�F�V�ɂ�������E���ɂāA����鏊�Ȃ��҂Ȃ�B���̌̂ɂ݂Â��瑴�����𖾂ɂ��鎞�́A���i���Ȃ͂��j�l��
�����y�ڂ��āA���������������ɂ��ׂ��Ȃ�B
|
���P�i������j�Ɏ~�܂�ɍ݂�B
�~�Ƃ͕K�����i�����j�Ɏ���đJ�i���j�炴��̈ӁB���P�͑����������c�R�i�Ƃ�����j�̋ɂȂ�B�����́A�����𖾂��ɂ���Ɩ���V�i���炽�j�ɂ���Ƃ́A�F�c�i��
���j�Ɏ��P�̒n�Ɏ~�܂�đJ�炴��ׂ��A�W���K�����̈Ȃĕv�i���j�̓V���̋ɂ�ᶁi�j�����L��āA��|�i���������j���l�~�̎������A�ƁB���̎O�҂͑�{�̍j�̂Ȃ�B
|
����́A���P�Ɏ~��ɂ���B���P�́A�P�̎���A叓���i����j�c�R�i��������j�̋ɂ܂�鏈�A�����f�̒��Ȃ�B����Ɏ~��Ƃ́A叓�i���Ɓj
�̎��P������ݓ��i����j�A�K�i���Ȃ炸�j����Ɏ~��A���łɎ~�鎞�́A�����������邱�ƂȂ����]�B叓�i���Ɓj�̎��P�Ɏ~�鎞�S�ɂ�
���ẮA�V�������͂߂����āA�����������l�~�̎��Ȃ��B�}���V����叓�i���Ɓj�����V���̊O�ɂ��ł���A���P�Ɏ~��Ɖ]���A�����V�̏�
�ɂ��āA叓�X叓�X�i���Ƃ��Ƃ��Ƃ��Ɓj���P������݂āA����Ɏ~��Ȃ�B�ȏ�̎O�������āA��w�̓��̍j�̂Ƃ��B���i���́j���˂���
���Ɖ]���Ȃ����ƁA�ԁi���݁j�̒���j�i�ȁj�ɂ�����A�߁i���ʁj���ė́i����j���тɂ����@���B
|
�~�i�Ƃǁj�܂邱�Ƃ�m��Ď��i�������j���č@�i�̂��j�ɒ�܂�L��B��܂�Ď����č@�ɔ\�i��j���i���Â��j�Ȃ�B�ɂ��Ď����č@
�ɔ\�������B���č@�ɔ\�����i������ς��j��B���č@�ɔ\�����i���j�B
�@�́A��Ɠ����B��i�̂��j�����i����j�ɕ��i�Ȃ�j���B
�~�Ƃ́A�c�i�܂��j�Ɏ~�܂�ׂ����̒n�ɂ��āA卽�i���Ȃ�j�����P�i������j�݂̍鏊�Ȃ�B�V��m��A�����u�ɒ���i�Ă������j�L��B�́A�S�̖ϓ����������
���B���́A�|�i���j�鏊�ɂ��Ĉ���������B���́A����|�i����j����̐��ځi�������傤�j�Ȃ�������B���́A���̎~�܂鏊�i���j�������B
|
����艺�i�����j�ܒi�́A�}�����𖾂ɂ��A����V�ɂ��āA���P�Ɏ~��Ƃ�����ҁA�K�i���Ȃ炸�j�܂Ñ��̎~�鏊��m�鎞�́A���̂Â�
��₤�₭�ɐ��n�̐��Ɏ~�鏊��Ɖ]���Ƃ������B����ǂ��傲�Ƃ̎��A�@�̎��ɂ��āA�~�邱�Ƃ邱�Ƃ́A���₷���炴�邱�Ƃ�
�����Ȃ�B���~�̎��A�㕶�������Ƃ��ւǂ��A����叓�X�i���Ƃ��Ɓj�ɂ��̂��̎��P�̂��鏈�������A�Ƃǂ܂�ǂ���Ɖ]�`�Ȃ�B�����m
�邱�ƁA���₷���炸�B���m�͍s�̌��A���肽���ɁA�m�邱�Ƃ�Ȃ�B�����Ɏ���A���̒m�鏊�����Ȃ�̂ɁA�u���ނ��ӏ�����
�āA���Ȃ����Ȃ��܂ǂЂȂ��B���m�Ă悭���Ɏ���Ȃ�B
�@�@���̂Â���₤�₭�ɁF���i���̂����j��Q�i�悤�₭�j�ɁB
���͂ł���ƁB 2
�u�悭���Č�ɂ́A���̐S��ɂ��Â܂�āA�݂���ɓ������ƂȂ��B�W�i�������j�u���܂���炴�鎞�́A�S�Ȃ鎞���A�Z�R�i������j
����B�u���łɒ�鎞�́A�S�̓��������A�{�̂��͂�Ă����납���B���̌̂ɑ��̓������Ƃ݂���Ȃ炸�B����邪�[���҂Ȃ�B
�@�@�Z�R�F䩑R�Ɠ����B�ڂ��肵�Ă���B
�����Ƃ́A�悭�������āA�S���ƂȂ����Ƃ̂Ȃ��`�Ȃ�B�S����Ȃ鎞�́A�g�̋��鏈�A���t�݂Ȗ��ɂ܂����āA�䂭�Ƃ��Ĉ����Ɖ]
���Ȃ��B���Ȃ邪�A���҂Ȃ�B
�S����ɁA�g��Ɉ����鎞�́A叓�i���Ɓj�ɜ䂸�邱�ƁA�n�e�ՉɁi���傤�悤���j�ɂ��āA���̎v�Ђ͂��鏊�A���i���͂��j�����Ƃ���
�͂߁A�ځi�܂сj�炩�Ȃ邱�Ƃ��������Ɖ]���ƂȂ��A叓�W�z�i�Ă�ł�j����ɂ������ЂāA����ɜ䂸�邱�ƁA���悢��_�ςȂ�B��
��\������Ɖ]�B
�@�@�n�e�ՉɁF�������Ƃ��Ă��������Ȃ����ƁB
����́A�~�邱�Ƃ�Ȃ�B��i�X�̂��邵���ւ����ɂ́A�����Ɖ�ƁA�������āA��ɂȂ�A�}�����s���A叓�i���Ɓj�A�召�ƂȂ��A
�݂ȑ��̎��P�Ɏ~��A�����Ɖ]���ƂȂ��B�W�m�s�_�[�A�Ȃ�Ђ����ނƂ��ւǂ��A�~�邱�Ƃ�m��͐��i���́j�m��ɂ��āA���i���́j����
��������B���Έ����̎l�i�́A�݂ȐS�̏�ɂ����āA���邵�����邱�ƑQ�X�i����j�ɐ[���B�A�m���ȂāA�s�����ʁB���鎞�́A�s�А���
�āA�E���i������j����Ȃ�B
�@�@�E���F���R�Ƃ��Ȃ����A���̎��ƓǂB�E���́A�Â��p���o���Đ��܂�ς�邱�ƁB
���c��������W���i��w�͋�ߘa���N�l���j�A
�����́A�O�j�̂̑����ł��B���ǂ�ł���͎̂�q�̕��ނɏ]���u�o�v�ł��B��q�́A���́u�o�v�͍E�q�̈⏑�ł���A�ƌ����܂��B�u�o�v�͎O�j�́E����ڂ��q�ׂ��āA�l����w�ɐi��Ŋw�Ԃׂ��G�b�Z���X���W��Ă���̂��A�ƍl���܂��B�O��͎O�j�̂̈�A�u�������i�����𖾂ɂ���j�v�ł����B�O��̘b���J��Ԃ��ƁA�u�����v�̈Ӗ��ɂ��Ċ���̌Ò��́A�قƂ�lj����q�ׂĂ��܂���B����Ŏ�q�͑v���w�̓N�w�I�ȈӖ���ǂݎ��A�u�����v�Ƃ͂��Ȃ킿�l�Ԃ��V������u���v�A�C�R�[���u���v�ł���A�ƍl���܂��B���ׂĂ̐l�Ԃ͓V����u���v�^����đP�Ȃ�u���v��{���I�Ɏ����Ă���B�Ȃ̂ŁA�l�Ԃ͒N�ł��P�ɐi�ޗ͂������Ă���B���̐�ΑP�́u���v���A��q�w�ł́u�{�R�̐��v�ƌĂԁB�����������̐l�Ԃ͕����I���E�̒��Ő����Ă���B��q�w�̗p��Ō����u�C���̐��v�������Đ����Ă��āA�u�{�R�̐��v�́u�C���̐��v�Ɗ������āA�u��v�ƂȂ�A���́u��v�͑P�̂͂��܂�ƂȂ邪�A�����w�͂��Ȃ���Ήߕs�y�Ɋׂ�A�u���f�v���O��đP���ł��Ȃ��B�w�͂����u���f�v����O�ꂽ�҂͏��l�ł���A���������V����^����ꂽ�u���v��S���ł��������ȑ��݂ƂȂ�B�w�Ԏ҂́A�����b���ēw�͂��A�u��v���R���g���[�����āu���f�v�̓���I�ё����Ȃ�������Ȃ��B�s�f�ɓw�͂��āu���v��s�������Ƃ��A�N�q�E���l�Ɏ��铹�Ȃ̂ł���B���ꂪ��q�w�́u�����𖾂ɂ���v�̉��߂ł����B
�O��̎��́A��q�w�̉��߂Ƃ͕ʂ�䤎q�́u�吴���v���Љ�A䤎q�́u�吴���v����u�������v�����߂��Ă݂܂����B����́A��������҂̐S�̖ڕW�Ƃ��āA�]���ɑ��݂��锻�f����点�����ς�O�ꂵ�Ď�菜���A���������f���s���S�̏�ԂɎ��邱�Ƃ��w�������̂ł����B�܂����z���́u�������v�̉��߂��Љ�A���z���ɂƂ��āu�����v�Ƃ͓V�n������̂̐m�ł���A�l�Ԃ����܂�Ȃ���ɐS�ɔ�����Ă�����̂ł���B���l�͎��ȂƑ��҂���ʂ��邱�Ƃɂ���Ă��ꂪ�킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ł���A��l�͖����𖾂ɂ��Ď��ȂƑ��l�A����ɂ͎R�쑐�Ɏ���S�Ă̑��݂���̂̐m�ł����āA�����Ƃ��܂˂��e���ނ��Ƃ��ł��邵�A�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�m��̂ł���B���������قƂ�Ǐ@���I�ȋ��n���w���̂��A���z���́u�������v�̉��߂ł����B
�u����e�i���炽�j�ɂ��v�܂��́u���Ɛe�i�����j���ށv
�����́A�O�j�̂̂Â��A�u�e���v�ł��B����́A�Ò��̐��Ǝ�q�w�̐����Η����Ă��܂��B�������ւ͎�q�ɉ��������߂ŁA�u�e�v�́u�V�v�̌��Ƃ݂Ȃ��A�u����V�i���炽�j�ɂ��v�Ɠǂ݂܂��B���̉��߂́A���q�̂��̂��p�������̂ł��B�ǂ����Ē��q�́A�����������̂��B����́A��w�̌�̕����Łu�V���v�̌��t���o�Ă��邩��ł��B
|
�i�`��́j
���i�Ƃ��j�̔Ձi��j�̖��i�߂��j�ɞH�i����j���A䑁i�܂��Ɓj�ɓ��ɐV�i���炽�j�ɂ��A�����ɐV�ɁA�����ɐV�Ȃ�A�ƁB
�N�t�i���������j�ɞH���A�V�ɂ���̖�����i���j�����A�ƁB
���ɞH���A�����p�M�i���イ�ق��j��嫁i�����ǁj���A���̖��i�߂��j�ہi���j��V�Ȃ�A�ƁB
|
���q�Ǝ�q�́A�o�͍E�q�̈⏑�A�`�͍E�q�̈⏑���q�̑\�q������I�ɉ���������A�Ɖ��߂��܂��B����Čo�ɏo�Ă���u�e���v�ɂ��Ă��A�`�ʼn������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̉������̓`��͂ł���A�����Łu��V���i�V���Ȃ閯���삱���j�v�Ƃ���̂�����A�o�́u�V���v�łȂ���Ȃ�Ȃ��A�ƍl�����̂ł��B����ŁA��q�́u�����𖾂ɂ���v���u�����w�Ԑl�́A���ł���𑼐l�ɋy�ڂ��āA���܂��C���̐��ɑ����ď��l�̒�݂ɂ��閯���������Ĉ����グ�A����V�i���炽�j�ɍ��ς��邱�Ƃ�ڎw���̂��A�Ɖ��߂����̂ł��B�Ȃ̓��𖾂炩�ɂ��āA���ꂩ�瑼�l�����P����A�Ƃ����ؓ��ł���ƁB������Əォ��ڐ��Ȃ̂��C�ɂ�����܂����A�܂��������߂��Ă��Ӗ��͒ʂ�܂��B
��q�w�͂ǂ����Ă����Ɗ��͌����ł��薯�͋����ł���A���Ɗ��͖����������Ďw�����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A�Ƃ����l���������܂��B���ɂ͖��̂悳�������ď�̐l�ɂ͂킩��Ȃ����̂�����̂��A�Ƃ����l�����́A��q�w�ł͂��܂�o�Ă��܂���B�������̘����Ǝ��̂��A����Ƃ��I�ꂽ�D�G�Ȑl�͖����`���������A���̒�����D�G�Ȏ҂���Ɉ����グ�Ă��̂��m���ł���A�Ƃ����g�����𑣂������Ǝ��̂��B�@�Ǝv�z�ɂȂ�ƁA���͖��������邱�ƂȂǂł��Ȃ��Ɠ˂������܂��B���͐�����s�����߂ɖ@��p���ăr�V�o�V�����܂邱�Ƃ��������̂ł���A���̗͂邽�߂ɂ͗��v�Œނ��đ��삵�A�Y���ŋ����ď]�킹��̂��ŏ�ł���ƁB����ȏ�ɖ����������邱�ƂȂǍ��Ƃ͂��ׂ��łȂ����A������Ƃ���łǂ����ǂ����ʂȂǏo�Ȃ��ƌ����Ă��܂��܂��B�����̐����v�z�͌Ñォ�炱�̎�Ǝv�z�̕����Ɩ@�Ǝv�z�̕����Ƃ̑����ɂ���܂����B���������ʂ���_�́A���҂Ƃ���̐��{�������̂��̂ł���A�Ƃ������Ƃɋ^���������Ȃ��Ƃ���ł��B���̂ق������{�����̂��̂ł���A���{�Ƃ͖��֗̕��̂��߂Ɍ����T�[�r�X���ϑ����������̈�g�D�ɂ����Ȃ��A�Ƃ����l���͎��R�����̍l���̂��Ƃł��B���ƒ����Ɋւ��ẮA���j�ケ�̕����͈���Ƃ�����܂���ł����B�����͂��܂�ɍ��y���傫�����āA�l�Ԃ����푽�l������̂ŁA����炪���獑�Ƃ��Ă܂Ƃ܂�ȂǕs�\�ł���A�ォ��^���͂߂邵�����悤���Ȃ��A�Ƃ����������������̂��Ǝ��͍l���܂��B���R�ȍ��A����I�ȍ��Ƃ������̂ɂ̓T�C�Y�̏���l������A������z���Ď��R�Ŗ���I�ȎЉ����邱�Ƃ͐l�ގj�ŃA�����J���O�����炢������������Ƃ��Ȃ��A�Ƃ����̂����̊��z�ł��B
���āA���z���́u�e���v���u���Ɛe���ށv�̓ǂ݂ʼn��߂��܂��B��l�͎��ȂƑ��l�̋�ʂȂ��m���قǂ������Ƃɖڊo�߂����݂ł���A�Ȃ̐S�Ɉ�̂̐m�����邱�Ƃ�m��B�䂦�Ɏ���̉Ƒ���m���邱�Ƃ��y�ڂ��đ��l�̉Ƒ���m���A���ƓV���ɂ܂Őm���y�ڂ��B���ꂪ�u���Ɛe���ށv���Ƃł���ƌ����܂��B����̋��J���搶�E�Ԓ˒��搶���܂��A�u���Ɛe���ށv���������āA���q�E��q�̉��߂͎֑��ł���ƌ����Ă��܂��B����ɑ�O�̉��߂Ƃ��āA�u�������Đe�i�����j���܂��ށv�Ǝg���`�ɓǂމ��߂�����܂��B����������͂��܂����Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ��悤�ł��B
�u���P�Ɏ~��v
�O�j�̂̎O�߂ł��B��q�̒��ł́u�������c�i���j�R�v�u�V����ᶁi�s�j���v�u��|���l�~�̎������v�ƁA��q�w�̃L�[���[�h������Ă��܂��B�������ւ́A����Ɂu���f�̒��v�̃L�[���[�h�������Ă��܂��B�����́A����܂Ŏ�����q�w�̓N�w�ɂ��Đ����������Ƃł��B�l�Ԃ��{�������Ă���P�u���v�́A�ɂߐs�����C���̐��Ɉ�������ꂽ�l�~�̎����痣�ꋎ��A�V�u���v�ɏ]�������J���Ă���̂ł���A����́u���f�̒��v��w�͂��đI�ё����邱�ƂȂ̂��B���̋��n�Ɏ~�܂葱���ė���Ȃ����Ƃ��A�u���P�Ɏ~��v�ł���B���ꂪ��q�w�I���߂ł��B���̂��߂ɐl�͂ǂ��w�͂���悢�̂��A�Ƃ����_�ɂ��Ă���q�͖c��Ȍ��t���c���Ă��܂��B����͈ӎ��ȑO�̐S���ė���������u���h���{�v�A���ꂩ�玩���ƊO�E�̗����Ȃ킿���f���ǂ��ɂ��邩����ɍl���Ĕ��Ȃ�������u�i���v�m�v�A���ꂪ�L�[���[�h�ƂȂ�܂��B����������������̂͂���܂��c��ł���A���Ԃɂ͎�ɕ����Ȃ��Ƃ���ł��B�Ƃ肠���������ł́A�ӎ�����O�̒i�K�̐S�𗎂������āA�ӎ����Ă͒��f�̓_����Ɍ��o�����Ƃɒ��͂��Đ�����A�Ƃ��Ă��������Ǝv���܂��B��������Č����ƂقƂ�Ǖ����̑T�̏C�s�݂����ɕ������܂��B��q�͎����̊w�ƑT�͑S���Ⴄ���̂ł���A�ƌ����̂ł����A���̉e�����Ă���͖̂��炩�ł���A�v��̎v�z�ł͒v�����̂Ȃ����Ƃł����B
��q�E���z���E䤎q�́u�~�v
���A�����Łu�~�v�Ƃ͂ǂ��������n���w���̂��A�ɂ��đ��̎�Ǝv�z�̌��������킹�čl���Ă݂����Ǝv���܂��B���z���͖���̎�Ǝv�z�ƂŁA��q�w�̐��ɐ^��������Ό����܂����B���z���́u�S�����v�������A��q�w�́u�������v��ᔻ���܂����B�u�S�����v�̎v�z�́A�����̂ڂ�Ύ�q�̓�����̔ᔻ�҂ł��������ێR�̂��̂ł��B���z���͍ŏ���q�̊i���v�m�̊ώ@�@�ɖv�����āA����Ő��E�̐^�����������邱�Ƃ��ł��Ȃ������Ƃ����̌������܂����B��������C���̌��������z���͎�������q�ɋy�Ȃ��Ɣډ�����̂ł͂Ȃ��A��q�̕��@�ł͐S�̐^���͓����Ȃ��A�Ǝv�������A�������痤�ێR�̎v�z�������Ď�q�w��ᔻ��������ւƌ������܂����B�ނ̊w�́u�z���w�v�A���҂̗��ێR�Ƃ��킹�āu�����w�v�A���邢�͐S�݂̍���ɏW�������w��ł���̂Łu�����S�w�v�ƌĂꂽ�肵�܂��B
���z���͎�q�w��ᔻ����̂ł����A���̔ᔻ���@�͎�q���邢�͒��q������������w�E���f�E�_��E�Ўq�̎l�������グ�A�������q�E��q�̐��Ƃ͈Ⴄ�ǂݕ��������̂ł����B�_�̐i�ߕ��́u���v�u�̗p�v�̊T�O��p���Ď�q�w�I�ł���A���̏�Łu���v�u�̗p�v�̓��e��������������̂ł����B���z���͎l�����̂��̂ɂ��Ĕᔻ�����邱�Ƃ͂Ȃ��A�����T�Ƃ��Ȃ���A���̐��T�ɕʂ̓ǂݕ���^������̂ł����B�u�Ўq�v�u���f�v����q�E��q�Ƃ͕ʂ̓ǂݕ������܂����A�Ƃ�킯�u��w�v�̒��q�E��q�̉��߂�O��I�ɔᔻ���āA�Ǝ��̉��߂�^�����Ƃ��낪�ۗ����Ă��܂��B���̉��z�����u��w�v�֗^���������̐����q�ɊJ���������A�u��w��v�ł����B
���W���ɂ���̂́A�u��w��v�̎~���P�ւ̉��߂����������̂ł��B�����ʼn��z���́A��q�w���u�������v�Ə̂��āA���E�����ɑ��݂��Ă���͂��́u���v�𑨂���A�ƌ������Ƃ�ᔻ���A���̂������x������E���G���A�Ɛ˂��܂��B�S�̊O�̐��E�Ɂu���v�����߂��Ƃ���ŁA��炲���܂��ƂȂ����ŐS�͉������������Ȃ��B��������A�l�̐S�̒��ɂ͂��łɁu���v�����邱�Ƃ�m��ׂ��Ȃ̂ł���A�S�́u���v�𑨂��Ă�����A�������u���P�v���~�܂��ɂȂ�͂��Ȃ̂��A�ƁB
���z���́A��w�́u�����v���u�ǒm�v�̌�Ɍ��ѕt���܂��B�u�ǒm�v�Ƃ́A�Ўq���������p��ł��B���W���ɁA�Ўq�̗ǒm�̂������u���܂��B
���z���͂��́u�ǒm�v�����グ�āA����𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ���w�̌����u�������v�Ȃ̂ł���A�Ǝ咣���܂��B�S�ɂ́A�{���I�Ɋ��S�ȑP���ւ̔��f�͂�������Ă���B�l�����������f����@�͂������S��ł��邱�Ƃł���B��������o���A�����Ɏ~�܂�u���P�v�ł���B�������f�ɖ������Ƃ�����Ȃ�A����͎��S���ł�ł��Ȃ��̂ł���A�Ȃ̒��́u�����v���u�ǒm�v�ɂ܂œ͂��Ă��Ȃ����炾�A�ƌ����܂��B
���āA����܂ő�w�ɂ�䤎q�w�h�̉e��������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����������q�ׂ܂����B䤎q�̒��ŁA��w�̐��ƍł��ڋ߂��Ă���n�_�Ř_��W�J���Ă���ƍl������̂��A����тł��B����тɂ́A��w�ƑΔ�ł���p�ꂪ�o�Ă��܂��B�u�����v�͂���܂�����Ɂu�吴���v�̌ꂪ����A�u�~���P�v�́u�~�����v�̌�Ƃ��Ă�����A�u�~�܂�Ē�܂���v�́u����ɂ��ĐÁv�̌�Ƃ��Ă�����܂��B���܁A䤎q�̐���ǂ��Ă݂܂��傤�B
䤎q�͉���тŁA�א��҂���N�q�͂ǂ̂悤�ȐS�̏�Ԃ������Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���ڂ����q�ׂ܂��B䤎q�͌���p��Ō����Δ]�̋@�\���ɕ����āA������s���\�͂��u�_�v�A�O�����������肻���~�ς���L���@�\���u�h�v�ƌĂт܂��B�N�q�́A�]���́u�h�v�ɍ��ꍏ�O�E��������Ă�����ɑ��āA������ߋ��ɒ~�ς��ꂽ�L���������炷����ςɂЂ������邱�ƂȂ��A�u�_�v�̋@�\�ɂ���Ċ����ɔ��f���s���悤�ɂ���A�ƌ����܂��B䤎q�́A�ߋ��ɒ~�ς��ꂽ�L���������炷����ς��A�u���v�ƌĂт܂��B����т́A���́u���v����菜���āu�_�v�̋@�\�������ɒB�����A�u�吴���v�Ɏ���ׂ����Ƃ�����܂��B�����ɂ����ČN�q�̐S�́u����ɂ��ĐÁv�ƂȂ�܂��B�]���ɂ͂��łɁu���v���Ȃ��A�����Ȃ��O����������Ă��Ă��A����͋���ۂ̃������ɓ����ė����f�[�^�ł���A�u�_�v�����m�����ɏ���ł���̂ł���B���ꂪ�u����v�ł���A���f�ɂ̓u�����N���Ȃ��̂Łu�Áv�ƂȂ�B���̂悤��䤎q�͌N�q�̗��z�I�Ȕ]����Ԃ�������܂��B䤎q�ɂƂ��āu�吴���v�ƂȂ邱�Ƃ́A���Ȃ킿�����ƂƂ��Đ�����������s���A�������A�E�g�v�b�g���o�����Ƃł��B䤎q�͎�q�≤�z�������A�����Ǝ��p�I�ł���A����ȍ��Ƒg�D���^�c���閽�ߎ҂̎����I�ۑ�ւ̉����@���q�ׂ����̂ł��B�㐢�̎�q�≤�z���̂悤�ȁA�l�ԂƂ͉�����Ƃ���������`�I�Ȗ��́A���グ��ɂ�����܂���B䤎q�́A��������퍑������I��点�ė��z�̐��E���Ƃ����A���z�̐��E���{�ɕK�v�Ȗ��ߎ҂̎d���ɂ��ďq�ׂ����̂ł��B
������w��䤎q�w�h�̉e�����ď����ꂽ�Ȃ�A��w�͑����Ă��`��A�����炭����̐����ł��낤�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���q���q�������u��w�͍E�q�̈⏑�A�\�q�̉���v�Ƃ���������́A���Ɏ��オ�����Ă��܂��܂��B
�ȏ�A���W���̕\�ɎO�҂́u�~�v���r���܂����B�ǂ��Ɏ~�܂�Ƃ����̂��B��q�́A�����̓��ƊO�́u���v�Ɋi�i�����j��A�m��v���ď�ɒ��f�̓���i�ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ邱�Ƃ��u�~�v�̒n�_�ł��B����́A���E�̗���m��A���̂Ƃ���ɍs������Ƃ������Ƃł��B�������E�Ɛl�ԂɁu���v�����݂��Ă���̂ł���B���������ׂ��Ȃ̂ł��傤�B���ꂪ�ł���̂��ǂ����A�Ƃ����₢�����������Ȃ�܂����A��q�Ɍ��킹�����ȋ^��������͎̂u������Ȃ��Ƃ������Ƃł��傤�B
���z���́A���~��ł��āA�����̐S�ɖ{��������Ă���u�ǒm�v�ɏ]���A�O�E�̐�����i�i�����j�����Ƃ��u�~�v�̒n�_�ł��B����̗ǐS��M���āA�ǐS�̖�����܂܂ɊO�E�̐�����i���B����͍D�ސl�͍D�ޓ��ł��낤���Ƃ́A�킩��܂��B���{�ł��]�ˎ���ȍ~�����̗z���w�M��҂�������܂����B�剖�����Y�̂悤�ɁA���S�������Ă���ł��苖���������Ɗ������Ȃ�A���������ĖI�N����ׂ��ł���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���a��O�̋�C���z���w���D�Ƃ����̂��A�킩�邱�Ƃł��B�O���R�I�v�͍Ō�̑��w�L���̊C�x�̑�ɂ����āA��l���̌M���N�����̕s���ւ̕�����s���Ɉڂ����Ƃ�M�O�Ƃ��āA�����̃g�b�v�����̕ʑ��ɐ������Ďh���E���A������ؕ�����Ƃ����s��ȕ���������܂����B
䤎q�́A�����Ɣނ̐����������ɑ����āA�₪�ė��鐢�E���Ƃ̎w���҂����ׂ��S�̏�Ԃ��u�~�v�Ƃ��ĕ`���܂����B�u���v��]�������菜���āA�u�_�v�̔\�͂����S�ɓ�������A�����Ȕ��f�͂��������N�q�͑��݂ł��邵�A������琬���鋳����s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂悤�ȃg�b�v���w���҂Ƃ��ČN�Ղ��鐢�E���K���Ȃ̂��A�Ƃ����₢�́A�퍑����̔ߎS�ȑ������I��点�Ȃ�������Ȃ��Ƃ���䤎q�̓����̎v�z�I�ۑ�̑O�ł́A�������̂ł͂���܂���ł����B䤎q�́A�ŏI�I�ɂ́u��v�̊w�K���v�z�̑O�ʂɑł��o���A�Љ�����肳���镶�����u�ł���u��v���N����Ɛb�������w��Ŏ��H���邱�Ƃ�ʂ��āA�Љ�͉����ȉ^�c���ł���悤�ɂȂ邾�낤�Ƃ�������Ⳃ�^���邱�ƂɂȂ�܂����B�u��v�͉ߋ��̒���ȗ��j�̒��ō��ꂽ���ƒ����̌o���I�^�c�@�ł���A������w�сA���́u�`�v��ǂݎ���č��̎���ɉ��p���邱�Ƃ��A�����Ƃ������Ƃ��^�c����N�q�����ɂƂ��Ă�����L�v�Ȃ��Ƃł���A�ƌ��_�Â����̂ł��B��̋`�����킹�āu��`�v�ƌĂт܂��B�u��`�v�͊e�������ƂɈقȂ�A�e�����̗��j��ʂ��č��ꂽ�A������l�̐S�ɂ��h���邱�Ƃ�����ł��B
�ȏ�ŁA��w�́u�O�j�́v��ǂ݂܂����B
��c�F���Ƃ͟u�̓����ŔՂ͐��ʊ�A���x�ɍ������V���ȓ����}�����Ǝ������ꂽ�Ƃ������Ƃł��傤�B�N�Ƃ͎����U�̒�̍N�f�B�t�Ƃ͍��������A�u�̓����ɓ��������Ǐf����f�i�U�̌Z��j���U�ɋ^�O�������@���̎q�̕��M�\���Ƌ��ɗ����N�����A�U�͂���肵�A�N�f�ɓ����������܂��B�V���Ƃ͕������炷��Οu�̖����w���A��������邱�Ƃ̓���A�Ή�����S�\�����L����Ă��܂��B�u��V���v�Ƃ́A���̓����V���ɂ��u�̖������ē�������悤�ɂƗ@�������Ǝv���܂��B������X�V���ɋ�������Ɠǂނ��Ƃ͏o���܂����A�Ӗ�ł��B�V�l���A�l��V���ɂ���A�V�^���A�^��V���ɂ���A�V�����A����V���ɂ���Ɠǂނ悤�Ȃ��̂ň�a��������܂��B
���c�F���q�Ǝ�q�́A�o�͍E�q�̈⏑�A�`�͒�q�̑\�q�ɂ�����ł���ƌ����Ă܂��B�`��͂Ɂu��V���v�Ƃ���A�o�Ɠ`�͑Ή����ׂ��ł���A�o�́u�e���v�́u�V���v�ł���ׂ��ƌ����B�������͎��g�̐S�̖����𖾂炩�ɂ���A����ɋy�ڂ��A����V���ɂ���A�����āA���̐S�Ɏ~�܂�Ƃ������߂ɂȂ�܂��B�o���E�q�̈⏑�A�`��\�q�̉��߂Ƃ��鍪���͂���܂���A���q���q���������߂��Ă��邾���̂��Ƃł��B�N�q�����l����������Ƃ����A�ォ��ڐ��ł��B���z���́u���Ɛe���ށv�Ɠǂ݁A�N�q�����l���X�����ۂ��̐S�̂��Ƃ͐m�ł���A��ʖ����m�ł��邱�ƂƂ��܂��B�u���ɐe���ށv�Ƃ����ǂݕ��́A�Ԓ˒��搶�����ꂪ�������Ē��q��q�̉��߂͑Ó��łȂ��ƌ����܂��B�u�������Đe���܂��ށv�Ƃ����ǂݕ�������A���J���搶�͂�������̗p���Ă��܂��B�������ʐ��ł́A���z����Ԓː搶�̓ǂݕ����嗬�ƂȂ��Ă��܂��B
�۔��F������āE�E�E�����̎v�z�ł͏����ׁ̈A���O�ׂ̈Ƃ������͈̂�Ȃ��A�����`�Ƃ͐^�t�̐��E�A�ォ�疳�m�Ȗ����[�ւ���A�ォ��ڐ��̎v�z����Ƃ������Ƃł����B
���c�F�����̐����v�z�ł͎�ƂƖ@�ƁA�������s��������̂��̂ŁA���͖������̂��A���͉������ł������킩��Ȃ��̂ō����w������B�����̂��Ƃ���悤�ȍl�����͂Ȃ��B
�۔��F���͖��ׂ̈ɂ�����̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł����B
���c�F�Ўq���A���Ƃ͖����ł��厖�ł���A�ƌ����܂��B䤎q���A�N��͏M�Ŗ��͐��ł���ƌ����܂��B�������Ȃ���A���҂Ƃ��ɖ����̂��Ƃ͌����܂���B������������Ȃǂł��Ȃ��A���͗��Œނ�グ�A�Y�ŋ����A����ȊO�̂��Ƃ͖��ʂƂ���̂��@�Ƃł��B�����������A���{�����Ƃ����悤�ȍl�����͒����ł͐������܂���ł����B
��c�F���q�Ȃǂ́A�l�̖{���̂܂܂ɐ�����Ίy������点����̂��A�m�`�ł���Ɩ����Ȃ��Ƃ�l�ɋ����邩�琢�̒����������Ȃ�BꟂ��̏w���̋`��F�̌����݂����Ȑ������łȂ�Ƒ��ꂵ�����Ƃ��B����f�Ă��쎀����悤�Ȃ��ƂɂȂ����BꟂ����R�ɒ�ʂ����낤�Ƃ��܂������A���R�͎����̐S�g�𗐂��悤�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��A����J�Ȃ��Ƃ��Ƃ��ċ������Ƃ����悤�Șb������B���{���������悤�������炵��������Ƃ����悤�ȍl���͂���B
�۔��F���̒��ł͘_��������悤�ȏW�܂�͑�R����܂����A�V�����w�ԏW�܂�͂��܂蕷���܂���ˁB
���c�F�����́A���V�v�z���嗬�ł����B��Ǝv�z�͂��̌�ł��B�����́A����������������ȂǂƂ������Ƃ͂��Ă��܂���B���V�v�z�́A���̊����͋K�������ɒu���A�Ƃ����_�ł͘V���I�ł��B����ō��Ƃ̑̐����ێ����邱�Ƃ͕K�v�ł���A�Y���̌������͈����Ēu���A�Ƃ����_�ł͖@�ƓI�ł��B�V���̎v�z�ɖ@�Ƃ̎v�z�����������Ɖ^�c�p���A���V�v�z�ł��B���̌i��܂ł͂��̕��j�ł���܂������A���̌���p�������邪�吪�����s�����B���̐��B�̂��߁A�呝�łƂȂ����B���邪������p����������s������ɁA��Ǝv�z���䓪����悤�ɂȂ�܂����B
�۔��F�V���v�z�ł͎��߂���Ȃ��ƂȂ����Ƃ������Ƃł����B
���c�F�i��܂ł̎����͑ΊO�푈���T���A���̊����̂܂܂ɍs�킹�鐭��ł����B���̎����A���Ɛ���ɓ����͕s�v�ł����B����ȑO�̍D�i�C���A���邪�剓���s�ł�����b�ł����B���������邪����푈�Əd�łň���������́A��]���ĕs�i�C�ƂȂ����B���̎����ɂȂ�ƁA���Ƃ����ꂾ���̋]���������鑶�݂ł��邽�߂ɂ́A���������K�v�ƂȂ����B���Ƃɓ����͂���Ȃ��Ƃ������V�v�z��@�Ǝv�z�ł́A���Ƃ̐������������Ȃ��B����ŕ���̎���A�ނ�͎�Ƃɘ_���ŕ����Ă��܂��A���Ƃ̐����v�z�Ɏ�Ǝv�z�����荞�ނ悤�ɂȂ�܂����B���Ȃ킿�A���Ƃ̏�ɗ��҂́A�����I�ɗD�ꂽ�l���łȂ�������Ȃ��B�N��͖��̕���ł���A�������d�Ȃ�������Ȃ��B�����łȂ���A���ɕ��S�������鐳�������Ȃ��B���ǂ��̎v�z���������܂����B
�Z�c�F���̎���̍D�i�C�A�s�i�C�Ƃ͂ǂ��������Ƃł����B
���c�F���v���������킯�ł͂���܂��A���q�I�ɂ͎i�n�J�̉ݐB��`�ɑ����̕x���̃G�s�\�[�h��������Ă��܂��B�i�n�J�́A�n���������҂̌��t�͂ɖ������t�����A�x��z��x�҂͖����炢�W���B����͓��R�̂��Ƃł���A�Ƃ܂Ō����܂����B
��c�F�����肪��x���ɂȂ����B
���c�F�����Ƃł́A�S�E���E�K���x�T�̌��ƂȂ�܂����B���̎����A�_���͓S�̔_��K���i�ł����B���́A�����Ă䂭���߂ɐ�Δ�������̂ł��B�����́A�K�ł��玩�R�ɒ��������Ă��܂����B
�۔��F���ƓS�͐ꔄ�ł͂Ȃ������ł����B
���c�F����̎��ɐŎ��邽�߂ɐꔄ�ɂ��܂����B
�Z�c�F�ݕ��o�ς��Z�����Ă����Ƃ������Ƃ��B
���c�F�I���O�̎���A�Ñ㒆�������E�̒��ł��ˏo���ē��K�����ʂ��Ă��܂����B���[�}�鍑�͎�ɋ���̉ݕ��ł������A�����ł͎�v�ʉ݂Ƃ��ē��K�����ʂ��Ă���A���K����ƂȂ��Ă����B���K�͋���݂����͂邩�ɑ�ʂɗ��ʂł��܂����B
�Z�c�F�_�����܂߂ĉݕ��o�ςł������̂��A�_���ł͕ʂ̌`�Ԃł��������̂��B
���c�F�����A�ł͓��̔����K�ŕ����ׂ����Ƃ���߂��܂����B���̍ہA�����K�͒N����������̂��������Ė��Ȃ������B����ŁA��ʐl�����K������Ă��܂����B���͐ł�[�߂邽�߂ɔ����K�����Ƃ��Ă����Ȃ�������Ȃ������̂ŁA�ꋓ�ɔ����K�̗��ʂ��L�܂�܂����B
�Z�c�F�ł́A�v�z�̓]�@�ƂȂ����̂ł͂Ȃ����B�Ўq�̌㉺�ɂȂ������̂�200�N�キ�炢�ɕ��������B
���c�F��Ƃ͐`�̎���ł����āA�V���̐i�s�W�Ƃ��Ďd���Ă��܂����B���ɂȂ�Ǝ�Ƃ͌ÓT�̒m���l�Ƃ��āA�����ƂȂ����ÓT�������Ƃ��s���Ă��܂����B���̂悤�ɐ`������ł���Ƃ͊������Ă����̂ł����A�����v�z�Ƃ��đ䓪����͕̂���̎��ォ��ł��B
�Z�c�F���K��N�ł����ƂȂ�A�������Ȃ��̂��o�Ă���A�C���t�����N��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��������B
���{�F���ɂ͑f�ނƂ��Ẳ��l���������B
�Z�c�F���K�̏d����`�͓��ꂳ��Ȃ������̂��B
���c�F���́A�����K�Őł�[�߂邱�Ƃ𖽂��܂����B���ꂪ���R�����ł��������߁A�Z�����Ԃ̂����Ɍ����Ɍ��܂ő傫���������Ɍ��܂Ŕ����K�Ɏ���đ����܂����B���̌��ʁA�C���t���ƂȂ�܂����B������̌���K�́A�Ăэ��Ƃ���������Ɛ肵�A�ʉ݂̑f�ނƌ`����Œ肵�ĉ��l�����肳�������̂ł��B
�Z�c�F���̉��l�Ƃ͉��ł������̂��A���A��Ƃ͂ǂ��قȂ�̂��B
���c�F�����ł͋����ʉ݂ł���܂������A�ʏ�̎���Ƃ��Ă͓��K���p�����܂����B�퍑����A�e���̒ʉ݂͌`������Ă��܂����B���ƍ��Ƃ̌��ςł́A�����p�����܂����B�������́A���ނ̓��K��S���ŗ��ʂ����āA����s�����邱�Ƃɐ������܂����B����ȍ~�A���K�͋��ɑ����ė��ʒʉ݂ƂȂ�܂����B
��c�F���̏��l�̎�����͖c��œ��K�ł͌��ςł����˂܂��A�ǂ����Ă܂������B
���{�F�]�˂̌��\����ł͈בւ����Ă��܂��B
�۔��F�M�p������K�v�ł��ˁB
�Z�c�F�v�z�̓]�@���������̂ł͂Ȃ����B
���c�F�����̐l���́A2000���l��������Ă����B���H�Ɨ��M�̐푈�ŁA�l�����������Ă��܂����B���ꂪ�����ɂ�7000���l���炢�ɂȂ�܂����B
�Z�c�F�l���������āA�o�ϐ����������B
���{�F�_�Ƃ̐��Y�������サ�Ă����B
|
�Ǐ���Œ�N���ꂽ���Ƃɂ��ĒNjL
�j�L�́u�ݐB��`�v�ɂ��ā@
�����w�@�K�c�@�K�O�����@���Q�l�ɂ��āB
(a)�~�]�͌o�ϐ����̗^��
�@�o�ϊ������~���ɍs���ɂ͖������������̂�H������ɕ�炵�����Ƃ������~���ɂ䂾�˂邱�ƁB
�̂ɑP���͔V�i���̗~���j�Ɉ���A�i����őʖڂȂ�j���̎��͗��ŔV���i�݂��сj���A���̎��͔V�����q�i������������j�ق��Ȃ��A���̎��͔V����i��������j�ق��Ȃ��A�ł����i��j�͔V��ू��ɂȂ邱�ƂƂ��Ă���B
(b)�Љ�I���Ƃ̐���
�@�Y���͊e�n�ɂ��قȂ�A�ׂ��d�����قȂ�B�_�A���i�R�ыƁA���̎d���j�A�H�A�������ꂼ��ɍs���ׂ����̂ŁA���i�{�j����ᢒ������i�w���A�����A�����j�𖽂���ׂ����̂ł͂Ȃ��B���ꂼ�ꂪ�Ɩ��ɗ�݁A�y���݁A�����Ⴋ�ɗ����悤�ɋx�ݖ������ʂ��A�������ꂸ�ɕ��������肾�����Ƃ������ɍ���������s���ł���B
(c)�_�H����͍��x�̌���
�@�_�H���l���̐H�ƈ߂̂��ƁA���Ƃ��傫���ƕx�A�������ƕn�B���܂����҂��]�����肾���A�ւ��Ȏ҂ł͕s������B�u�q�H���i�݁j�����X�߂�m��A�ߐH����ĞĐJ��m��v�B
(d)�����̎��R������
�@�`��ł͓x�ʍt��ʉ݂̓���A�����W���̌S�����A���Ԑl�̎����������A�`�̊����ɂ��@�Ǝv�z�̂ݗ��ʂ�����Ƃ����������P�p����A�֏��⋴�̒ʍs�ŁA�R��̋ւȂǂ������ꂽ�B�u�x���哪���V���Ɏ������A���Ղ̕��A�ʂ�����͂Ȃ��A���̗~���鏊�v�A��������70�N�A�u���Ǝ������A�����̍Ђɋ����ɔ��A�������l�����Ƒ���B�s翂̜H庾�i�q�Ɂj�F�Ȗ����ĕ{�ɂ͉ݍ���]���B���t�̑K�͋�����݂ˁA�ы������i�L��]��j�Z�i�����j���ׂ��炸�i�������j�v�ƂȂ����B���ȗ��̔_��H���Ƃ����V�X�e������O�ꂽ�o�ϊ�������O�̍D�i�C�����炵���B
(e)�s��̖u��
�@�t�H�퍑����ȗ��̓s�s�ȊO�ł��A������l���̃Z���^�[�ƂȂ�n���s��ƂȂ����B�_�H����ȊO�̐V�����E�ƂɌg���҂����ꂽ�B
(f)�V���Y�Ƃ̔��W
�@�u�ߍI�Ȃ閖���v����܂ł܂Ƃ��Ȑl�����Ȃ������ׂȒp���ׂ����ƁA�����Ȃ��Ƃ����đ�x���ɂȂ�҂������B�ޓ��͎���������ɋ@�q�ł���A���@�Ń{���ׂ�������x��������B���łʼn҂��B�y�e���ɂ����ĕw�������ǂ킩���A�̎��o�D�ɂ���A��ʂ̂悢�w�l���M�l�E�x���ɛZ�т�A����̌�{�ɓ���A���݂����Ö�A��ғ����E�҂��d��铙�X�B�������O���Y�Ƃ��u�������B
�u�F�A�ݗW�i�݈ʂɂ�镕�W�j�A�i�N�傩��́j���R�A�M�@�i�@�̈��p�j�A�Ɗ��i�ƍ߁j�A�x�L�炸���āA��i���Ƃ��Ɓj�����A��Ŗ����A�o������i�����ɓK�X�Ή����j�A�������i���v�j���l�A�ȂĖ��ɍ���v���A�i���j�{��p���V�����B��ɕ����Ȃ��i�p�f���āj�A����p���V�������i�`�����X�����ށj�A�̉��ɊT�i���@�j�L��A�̂ɏp�ɑ���Ȃ�B�_�{�A�H���ɂɎ����i�������ɕׂ߂�j�����Ƃ��B���i�͂��j��ė����ׂ��Ȃĕx�𐬂��B��Ȃ�͌X�S�i�S�ɉe����^����j�A���Ȃ�͌X�p�A���Ȃ���X�����҂ƂȂ�A���i�����āj�ɂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��i��R����j�B
�v��㙚��i�T�܂�����l�߁j�ؗ��i�g�̂��g�����Ƃ��j�A�����̐����Ȃ�B���i�����j��ɕx�҂͕K�����i��j��p�����B�c�_�́A�@���i��Ԃ̂�����d���j�A����ɐ`�g�i�l���j�͈ȂĈ�B���i���j�W���i�����������j�B�@�n�i��̓��@�j�͊��i���j���Ȃ�A����ɓc�f�i�l���j�͈ȂċN�����B���E�i�q���j�͜��ƂȂ�B����Ɋ���i�l���j�͗p���ĕx�ށB�s���i�s���j�́A��v�i�j���j���ˍs�Ȃ�A�����贞ِ��i�l���j�͈Ȃ��`���i���肠�܂�j�B�̎��i������j�́A�J�|�i�p���������d���j�Ȃ�B�����贔��i�l���j�͐���Ȃ��B�̟��i�ʏ`�̔��j�͏��ƂȂ�B����ɒ����i�l�j�͐��݂��B�r���i�������j�͔��Z�i���ɑ���ʋZ�p�j�Ȃ�B�����郅���i�l�j�͓C�H�i������݂̍��ȐH���j���B�����i�ٕ����H�j�͊Ȕ��i�y���j���i�̂݁j�����C�����i�l�j�͋R�i�n�j��A�˂�B�n�͟Ǖ��i�j�ł�����A�����i�l���j�͏��������i�قǂ̑剮�~���\���Ă���j�B����F�A����̒v���i��S�ɍs���j���B���ɗR��V���V��ɁA�x�i��j�ɂ��S�i���܂����j�Ƃ͖����A�����݂ɏ�̎�Ƃ������̂������B�i�݂́j�\����҂��t���i���W�܂�j�A�s�ю҂������i���Ɂj���B����̉Ƃ͈�s�̌N�ɔ��i����ׁj���A���ݎ҂͔T�i���Ȃ킿�j���҂ƞق������B毂ɏ����u�f���i�����̏���j�v�҂ł͂Ȃ����A�����ł��Ȃ����B
�F��L�ݗW���R�M�@�Ɗ����x�CᶒŖ����A�C�o����C�l�����C�Ȗ��v���C�p�{��V�C�ȕ���C�p�����V�C�̉��L�T�C�̑��p��B�ᎊ�͔_�{�C�H���ɁC�מܗ��Ȑ��x�C��ҌX�S�C���ҌX�p�C���ҌX�����ҁC�s���ɁB
�v㙚��ؗ́C�����V������C���x�ҕK�p��B�c�_�C�@�ƁC���`�g�ȊW��B�B�@�n�C������C���c�f�ȋN�B���E�C���Ɩ�C����ᢗp�x�B�s�ɁC��v�ˍs��C��贞ِ����`�B�̎��C�J�|��C��贔�����B�̟��C���Ɩ�C���������݁B�r��C���Z��C��?���C�H�B�����C�Ȕ����C�����A�R�B�n�C�Ǖ��C���������B���F����V���v�B�R���V�V�C�x���S�ƁC���ݖ����C�\���t���C�s�юҊ����B����V�Ɣ��s�V�N�C���ݎҔT�o���ғ��فB每����u�f���v�ҎׁH���H
�@��N��\���K�̎��v����������́B
酤
�i���j���ԁA��醬
�i���Â���������j��瓨�i���߁j�A���i�ʏ`�j��甔�i�������߁j�A���r彘�i�j��j����������̐��A�̍����i�������蔄��j����A�d���i�܂��E���j��ԁA���邢�́A�D�̒�����䕪�A�i�ށj�ؐ�́A�|���i�����j�݁A����軺���i��l�ԁj�S���i��j�A���Ԑ�_�A�؊�髤���i����j�疇�A��������A�f�E�c��E��炧���i�����ˁj��A�n���E蹾�i����j��A���瑫�A�r彘��ԁA�I��w�i�z�X�j��A�E�p�E�O���i�C���j��ҁA������i���났�ʁj�P�i���ʂ킽�j�וz�����A�����i���€�ʁj��C�A�Εz�i�����e�z�j��v��A���i���邵�j��l�A糱���i�������j�d䜴�i�[���j��䧁A鲐�i�ӂ��j鯼�i�����j��ҁA黀�i�G���j��A��i����сj�����A���i�Ȃ߁j�I��̎O�V�i�O�{�j�A��貂�i�Ă�j���i����߁j���A��i���Ђ��j�r���A���i���イ����j�Ȑ��A�ljʍ��i�ʕ��E��j����A
�������̎萔���Ŕ���ҁA��т�݂��t���̗������Ƃ�҂���\���K�̎��v��������B
�@�����͍��ɂ�L���ɂ�����A�n�x�̊i�����g�債���B����͑剓���̌o���d�����߁A���A���A�S��ꔄ���A�ϗA���������ĕ����̗]���Ă���n������͔������A�s������n��ɔ����ė��v�i�ϗA�@�j�A�������Ⴂ���ɕ���������ĕ������������A���M�������ɔ����ė��v��i�����@�j���̗p�������߁A���R�o�ς��j�Q���ꂽ�B�܂��A�c�ŁA�l���ŁA���Y�ŁA���i�̔��ւ̉ېŁA�E�ł�h�~���邽�߂̖��������サ�����ƂŁA�u�ݐB��`�v�ł����Ƃ���̌o�ςɂƂ��Ă̍ʼn���i���{�̉���ɂ�鑈���j�A�ƂȂ荡�ʼn]���f�t���Ɋׂ����B���R�o�ςŊg�U��������}�ȗ~���̋K�������߂�ꂽ�̂ł��낤�B��Ƃ̓o�p�ƂȂ邪�A��Ƃɂ͌o�ϐ�������͂Ȃ����߁A���R�o�ς͏K�ߕ��������l�����������B
�ݕ��o���ɂ���
�@�`�̓����A�����K�ɂ��S���I�ȉݕ�����̐��x���͎n�c�O�\���N�ł��邪�A���̓���ݕ����x���S���ɕ��y���Ȃ������ɐ`�̕�����}�����B
�@�`��̔����K�͎����Ɩ��ڂ���v������̉ݕ��ł��������A�O�������̔��S�����A�l�S�������͎��������ڂɋy�ʖ��ډݕ��ł��荬���������A������̌ܓS�K�Ŏ��̉ݕ��w���A���邱�Ƃɂ��A�ݕ��o�ς͈�����Ƃ���ǂ����B
�����ݕ��������ݕ���r���������̂ł͂Ȃ��A�z�傪�K�̑�֎�i�Ƃ��Ďg�p����Ă����B
�i���c�̌����j
��������A�����K�Ől���ł�[�߂�ׂ����Ƃ����肳��A���̂Ƃ������Ė��Ԃł̑K�̒�����ٔF�����B���̌��ʁA�����o�ς͓���ʉ݂̓��K���ꋓ�ɕ��y���邱�ƂɂȂ�A�푈�����Ɣ_�ƋZ�p�̑��i�����܂��āA�ݕ��o�ς��������}�����B�㊿����ȍ~�A��Ƃ͂��̎���̖�����������N�Ƃ����@�s�ׂł���ƌ��߂��A�����̒ʉ݉��l�̖��ډ����C���t�������ł���ƒf����_���ƂȂ����B�������Ȃ���A���̂Ƃ��̖����ٔF�ɂ�铝�ꓺ�݂̕��y���A�C���t�����Ȃ�����o�ς̊����������炵���Ƃ����m��I���ʂ����邱�Ƃ��������Ă͂Ȃ�Ȃ��B������ȍ~����K�̍��Ƃɂ��Ɛ�I���s�ɂ��A�ʉ݉��l�̈��肪�͂���ꂽ�B��������͕�����ɍs��ꂽ�d�łƌo�ϊ����K����A���悩��̗A�����߂ɂ�鉩�����o�Ƒ��܂��āA����������ȍ~�͒����I�ȃf�t���o�ςɓ˓������i����̒ʉ݉��l�����́A�������������Ŏ��z�����肳���邱�Ƃ��ړI�ł������j�B���������͉��l�����肵�����K�ߍ���Ŏg��Ȃ��Ȃ�A�K�v�ȕ����͎��L�̑�_�n���璲�B����o�ςƂȂ�A���͎���Ɍ����Čo�ϊ����͓݉����Ă������B
�_�ƋZ�p�ɂ���
�@�퍑���㖖�`��̔_�@�́A�L����(����)�ɎU�d�d�킷����́B
�@�O��������苍�k��O��Ƃ��āA(�݂�)�ɔd�킷����d��@
�@�͈̉ȓ�̐���_�@�ł́A�k���Ӂi�����Ă��A���d���A���R�̑����������ĎG����}������j���̂ł��邪�A�㎿�̏��i�Ď��v�ɂ͉������Ȃ��B���ォ��͕Ă����i�����Ă���A���͎҂ɂ���Ĉ�삪���i����A�����Z��0����ڂ̐��ƕ�|�Ƃ����݂ɍ��A����ɓ�s���Z���Ԋu�œ_�d����W��I�_�@�A�ϑ��E����̑����n�_�@�ł��邪���ʂ̘J���͂�v�����i��ʂɂ͕��y���Ȃ��j�B
|
2025�N5��10���i�y�j��w�͋�
�{���́A�۔�����A�Z�c����A���䂳��A���c����A��c����̌ܐl�A���{����y���ō����A
���c��������W���i�o-04�j�A���W���i��w�͋�ߘa���N�܌��j
�u�`�͂�����youtube�@
|
�ԑ厚�F��L��w�т̌���
�Ώ����F��q�̒�
���厚�F��q�̏������낵��
���厚�F�������ւ̉��
|
|
�~�i�Ƃǁj�܂邱�Ƃ�m��Ď��i�������j���č@�i�̂��j�ɒ�܂�L��B��܂�Ď����č@�ɔ\�i��j���i���Â��j�Ȃ�B�ɂ��Ď����č@�ɔ\�������B���č@�ɔ\�����i������ς��j��B���č@�ɔ\�����i���j�B
|
|
���i���Ɓj�{���i�ق�j�L��A���i�킴�j�I�n�L��B
���𖾁i������j���ɂ����{��ਂ��A����V�i���炽�j�ɂ����ਂ��B�~�܂��m����n��ਂ��A�\�����i���j���I��ਂ��B�{�E�n�͐�鏊�ɂ��āA���E�I�͌�ɂ��鏊�Ȃ�B���͏㕶�̙_�߁i��傤���j�̈ӂ����ԁB
|
����艺��i�́A�㕶�����ׂނ���ŁA��w�̓����w�Ԏ҂ɁA����p��ƁB���̂��łɂ������ӂׂ��Ƃ́A��ӂ�������B���Ƃ́A�V�̐�����܂܂Ȃ�҂��]�B叓�i���Ɓj�Ƃ́A�l�̂��킴�ɂ��R��邱�Ƃ��]�B�����V���A�ȂƐl�Ƃ��ĉ]���́A�����ɂ��ČȂ͖{�i���Ɓj�Ȃ�A�l�͖��i�����j�Ȃ�B���̌̂ɕ��{������Ɖ]�B�~�邱�Ƃ�m��ƁB�~�邱�Ƃ�Ƃ́A��叓�ɂ��āA�m��͎n�Ȃ�A����͏I�Ȃ�B���̌̂Ɏ��I�n����Ɖ]�B
�u����p��v�F
���v�i���ӂ��A�J���t�[�j�͎�q�w�p��ŁA�C�s�@�̂��ƁB�����ł͂��̈Ӗ��Ō����Ă���Ǝv����B
|
���i���j���鏊��m��A�������ɋ߂��B
|
�{�i���Ɓj�Ǝn�i�͂��߁j�Ƃ��ɂ��A���i�����j�ƏI�i�����j�Ƃ���ɂ��邱�Ƃ�����A�����łɓ��ɂ��������B���i����j�m��́A���i���́j���킴�ɂ��đ��̂��ׂ�m�邱�ƂȂ�B�m�鏊�������Ƃ��ւǂ������̗���m��݂̂ɂ��炸�B���́A叓���c�R�i���Ԃ�������j�̓����Ȃ�B����͐l�Ȃɓ���ƁA�C�w����ɂ��ĉ]�B����ɋ߂��Ƃ́A�������߂����͂����āA���ɂ̙|�i�Ƃ���j�Ɏ��邱�Ƃ₷���ƂȂ�B
叓���c�R�i���Ԃ�������j�̓����F
��q�w�p��B�V�n�����ɂ͐�ΓI�E�q�ϓI����������A�l�Ԃ��܂��]���̂����R�ł��铹��������B�c�R�i���R�j�Ƃ́u�܂��ɂ�����ׂ��v�ŁA�����łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����Ӗ��B
|
�Ái���ɂ����j�̖����i�߂��Ƃ��j��V���ɖ��i������j���ɂ���Ɨ~����҂́A��i�܁j�����̚��i���Ɂj�����ށB
���͕��߁i�ւ������j�B��i�̂��j�����i����j�ɕ��i�Ȃ�j���B
������V���ɖ��i������j���ɂ��Ƃ́A�V���̐l�����ĊF�Ȃđ��̖����𖾂��ɂ��邱�ƗL�炵�ނ�Ȃ�B���i���j���鏊��m��A�������ɋ߂��B
|
|
���̚������߂�Ɨ~����҂́A�悸���̉Ƃ�ꎁi�ƂƂ́j���B
|
|
���̉Ƃ�ꎂ���Ɨ~����҂́A�悸���̐g�����i�����j�ށB
|
|
���̐g�����߂�Ɨ~����҂́A�悸���̐S�𐳂������B
�S�Ƃ́A�g�̎�Ƃ��鏊�Ȃ�B
|
���c����̃��W���i��w�͋�ߘa���N�܌��j
�O��܂ł́A�O�j�̂ł����B�O�j�̂Ƃ́A�u�����𖾂ɂ��v�u����V�i���炽�j�ɂ��v�u���P�Ɏ~��v�ł����B�u����V�ɂ��v�́A��q�͒��q�̐��ɓ��ӂ��Č����́u�e�v�����u�V�v�ɓǂݑւ��܂����B������x�O�j�̂��Ȃ���ƁA�܂��u�����𖾂ɂ��v�Ƃ́A�����̒��ɂ���͂��̈̑�ȓ����w��Ŗ��炩�ɂ��邱�Ƃ�ڎw���A�Ƃ������Ƃł��B�����̒��ɂ���̑�ȓ��Ƃ͉����A�ɂ��ẮA��q�̌���������A���z���̌���������A�܂�䤎q�ɉ��������������肦��A�Ǝ��͐\���܂����B��q�́A�V����^����ꂽ�u�P���v�ł���ƌ����܂��B���z���́A�V�n������̂̐m�ł���A�ǒm�ł���ƌ����܂��B��q�́A�w��Ŋw�ё�����A�������Ȃ��Ɓu�P���v�͋C���̐��ɕ����Ă��܂��A�Ɗw�Ԏ҂�����܂��B���z���́A�l�Ԃ͐��܂�Ȃ���ɖ�����̂̐m������ǒm������̂ł���A�������~��ł�������ɂł����炩�ɂȂ�̂ł���A�Ƒ������̏������o���܂��B���̂ǂ������邩�͐l�̍D�݂ł͂Ȃ����A�Ǝv���܂��B�������āA�u�����𖾂ɂ���v�B�Â��Ėڎw���̂́A���l���ǂ��ɂ����邱�Ƃł��B��q�́u����V�ɂ��v�Ɠǂ�ŁA�����𖾂ɂ���҂͂��܂����l�̏�Ԃɂ��鑼�l�ɓ��������āA��������ς���̂��ƌ����B���z���́A�V�n������̂̐m�ɖڊo�߂�����ɂ͂��̐��̑S�Ă̐l�ԂƐe���ނ��ƂɂȂ�̂��A�ƌ����B�Ō�Ɂu���P�Ɏ~��v�́A��q�I�ɂ͒��f�̓���I��ł����Ɏ~�܂葱���邱�Ƃł���ƌ����B���@�Ƃ��Ă͋��h���{�A�i�������ł���A�h�̐S����ɗ{�������A�����ɉ������ł��艽��������O��Ă��邩����ɍl���Đ�����ƌ����B���z���I�ɂ͓V�n������̂̐m��܂点���A�S�̗ǒm�̖�����܂܂ɊO�E�̑P�������Ĉ������炵�߂�̂ł���A�ƌ����B��q�A���z���̂�����̓ǂݕ����ł���ł��傤���A�ǂ������邩�͐l����ł��傤�B���z�����D�ސl�͑������܂������A���ɗz���w�̓ƑP���ߌ����ɂ��Ă����Ȃ��l���������܂����B
��w�̎��ɂ́A�{����オ����܂��B�O�j�̂́A�ڕW�ł��B���ꂪ�u����āA���̌�ɁA�����ɂ͏��������邱�Ƃ�����܂��B�܂��{���ɓw�͂��Ȃ�������Ȃ��B���͖{������������ꂽ��ŁA������ɋy��ł������̂ł���B���̏������A�w��w�x�Ƃ����{�̂�����ʔ����Ƃ���ł��B�w�Ўq�x�ɂ����l�̍l��������܂����A�w��w�x�̏��q������������ď�����Ă��܂��B
�������ւ̉���̒��ŁA�u����p��v�Ƃ���܂��B�u���v�Ƃ́A�����炭�u���v�i���ӂ��j�v�̂��Ƃł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���v�܂��͍H�v�́A��q���Ђ�ς�ɗp���錾�t�ł��B���Ƃ͕����p��ł���A���Ɏ��邽�߂̏C�s�̂������w�����̂ł����B���͕����̖ڕW�ł��邪�A��݂����ɖڎw���ׂ��ł͂Ȃ��B������ׂ��w�͂̂���������A���ꂪ�u���v�v�ł���B��q�͕����p����g���āA�w��ŌN�q�ƂȂ�ׂ��������u���v�v�ƌ����܂����B���́u���v�v��Kung-fu�ƒ�����œǂ݂܂��B������C�M���X�l�������āA�J���t�[�ƌ����܂����B�J���t�[�Ƃ͕������q�w�ɂ����ďC�s�@���������t�ł���܂����A�����ɂ����Ă����p�̒b�B�̂��Ƃ��J���t�[�ƌĂт܂����B���ꂪ�u���[�X���[�Ƃ��W���b�L�[�`�F���Ƃ��̉f��Ő��E���ɍL����A�J���t�[�Ƃ����Β������@�̂��ƂɂȂ��Ă��܂��܂����B�{���͏C�s�S�ʂ��w�����t�ł��B���{��́u���ӂ��v�ƃJ���t�[�́A���͂��Ƃ��Ɠ����Ӗ��ł��B
�w��w�x�ł́A�{�E��ɂ͍ł������ɋ߂��Ƃ��낪�u����āA���E��ɍs���ɂ��������Ď������痣�ꂽ�Ƃ��낪�u�����\���ƂȂ��Ă��܂��B���̔����ڂŏq�ׂ��邱�ƂɂȂ�܂����A�V�����Ƃ��ǂ�����������A�܂��g�߂Ȃ킪�ƒ��āi�ƂƂ́j����B���̂��߂ɂ́A�Ȃ̐g���C�߂�B���̂��߂ɂ́A�S�𐳂�������B�ӂ𐽂ɂ���B���̂��߂ɂ͒m��v���A�Ώۂ��悭�ώ@����A�ƂȂ��Ă��܂��B�������ւ́u���v�Ɂu���Ɓv�Ɠǂ݂��ӂ��Ă��܂����A�����ł́u���v�Ƃ̓��m�S�g�̂��Ƃ��w���Ă���̂ŁA����Ȃ��悤�Ɂu���Ɓv�Ɠǂ܂��Ă���̂��Ǝv���܂��B�Ȃ��ׂ��u���Ɓv�ɂ͖{��������B�Ȃ��Ă����u�킴�v�ɂ͐�オ����B���̏������킫�܂��ēw�͂��邱�Ƃ���q�w�I�Ɍ��������ł���A���̏����������Ƃ��҂́A��q�w�I�Ɍ����o�J���m�ł���A���l���悭��������킯���Ȃ��A�ƂȂ�܂��B�V�����Ƃ�吺�Ō��Ȃ���A�������g�̂��Ƃɂ��Ă͂��������Ńe�L�g�E�Ȕy�́A��q�w�I�Ɍ��������̃o�J���m�ł���A�l�������i�͂Ȃ��B�����Ɛ�ɂ�邱�Ƃ����邾�낤�B�܂��Ȃ̐S�𐽂ɂ��Đ����A���퐶�����I�ɐ����Ȃ����B�������Đg�߂ȉƒ��m�荇���Ƃ悫�W��z���Ȃ����B�V�����Ƃ���鎑�i������̂́A���ꂩ��ł���ƁB��q�w�I�ɂ́A�����������Ƃ��w�ł͊w�Ȃ�������Ȃ��B��w�Ŗ��̋Z�p���w��ł��A�{�ł��铹�����w��ł��Ȃ���A����͏��l�ł���B���l�́A�傫�ȐӔC�������l�̏�ɗ��ׂ����i�͂Ȃ��A���̐������s�����i�͂Ȃ��ƁB
�i���{�̊w�҂��������m�Əo������Ƃ��̍l���̕ω��ɂ��āj
�w��w�x�̂����́u�{�����v�̊T�O�́A��w���w�Ԑl�����̍l�����ɑ傫�ȉe����^���܂����B�l�̓������C�߂铹�����{�ł���A�V�����Ƃ����߂�Z�p�͖��ł���B���q�S�Ƃ̂悤�ȋZ�p�����������ē������Ȃ����́A�א��Ƃ��Ĕᔻ����܂��B�����ł́u���̐��p�v�Ƃ����A���{�ł́u�a���m�ˁv�ƌ����܂����B����́A���m�̗D�ꂽ�_�͉Ȋw�Z�p�����ł���A���{�⒆���͖{�̂����̂܂܂ɂ��Đ��m�̉Ȋw�Z�p�������������A���m�ɕ����邱�Ƃ͂Ȃ��A�Ƃ����l���ł����B��w�͓����Ƃ��Đ��m�̃L���X�g���ɔ�ׂď���Ƃ���邱�Ƃ͂Ȃ��A������ێ����Đ��m����Ȋw�Z�p���z�����邱�ƂŐ��m�ɔ�������ׂ��A�Ƃ����咣�ł����B�����ł͍N�L�ׂƂ��̕ێ�I�Ȋw�҂����̎咣�ł����B����ɑ��ĒƏG��D�v�Ƃ��̊v�V�h�́A�����������̎Љ�点�Ă��錳���ł���A��������S�Ɏ̂ĂȂ���Ζ��勤�a�̎Љ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A�Ǝ�������邱�Ƃ��咣���܂����B���̊v�V�h�̐�Ƀ}���N�X��`�҂��䓪���A�������Y�}�ƂȂ�A���ؐl�����a���ƂȂ�A������v���ƂȂ�A��є�E�Ƃ��������ƂɂȂ����B����������̒��ؐl�����a���͍E�q���̂��ĎI�ȉƑ������𐄏����Ă��āA�킯���킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
�]�ˎ���A���{�̎�w�҂����́A���m�ɐڂ��Ă�����ǂ��l�������B�V�䔒�́A�؉������Ɋw�т܂����B�؉������͓������|�̑���q�ɓ������҂ŁA���s����]�˂ɐi�o���Ă��̐V�䔒�A���邢�͎��̏��R�g�@�Ɏd�����������Ȃǂ������܂����B�V�䔒�̎�w�́A�����I�Ȏ�q�w�ł��B���̔����A���{�ɖ��������ĕ߂炦��ꂽ�鋳�t�V�h�b�`��q�₷�邱�Ƃ�����܂����B�V�h�b�`�́A���܉����ł��邩���ɕ������B������l��ʂ��ē�����ƁA�V�h�b�`�͑����獷�������̊p�x�𑪂�A�������猻�݂���]�˂̈ܓx���v�Z���A�����p�ӂ����I�����_���̐��E�n�}�̂ǂ̏ꏊ�ɍ]�˂����邩���R���p�X�Ő��m�Ɏw���������B���̌v�Z�����������m�ł������A�Ɣ��͏����c���Ă��܂��B�����Ƃ����́A�V�h�b�`���s�����v�Z�͎O�p�@��p�������̂ł����āA���{�̓V�������s���Ă��邱�ƂƓ����ł��邱�Ƃ𗝉����Ă����B�Ȃ̂Ōv�Z���̂��̂͋����Ȃ���������ǂ��A���̌v�Z�̑����Ɛ��m���ɂ͊��S���Ă��܂����Ə����Ă��܂��B����ŁA�����V�h�b�`�ɃL���X�g���̋��`�ɂ��Đq�₵���Ƃ���A�܂�Ŏq���̂悤�Șb������A�ƂĂ������l�Ԃ��b���Ă���Ƃ͎v���Ȃ��A�Ə����Ă��܂��B���́A���m�͌`�����̋Z�p�ɂ��Ă͗D�ꂽ�Ƃ��낪����A�������`����̖��ɂ��Ĕނ�̍l���͋��ł��艽���S����Ƃ��낪�Ȃ��A�Ƃ������z���c���Ă��܂��B���̎��_�ŁA���m�͋Z�p�͗D��Ă���Ƒ����Ă��܂����B���������͂��̌v�Z�̑����Ɛ��m���Ɋ��S���������ŁA���̋Z�p�͔��̗����͈͓̔��̂��̂ł����B�����ۂ��ނ�̃L���X�g���͔[���ł���Ƃ��낪�Ȃ��ċ��ł���A�Ƒ����Ă��܂����B
�����̎�҂����́A���m�ɑ��ċ������Ђ������Ă��܂������A�{���I�ɂ͔��Ɠ������_�ő����Ă��܂����B���䏬��́A�F�{�˂̎�҂ł��B�F�{�˂͎�q�w�̓Ǝ��̓`��������A�̂��ɖ����V�c�̎��u�ƂȂ������c�i�t���F�{�˂̏o�g�ł����B����͎�q�w��g�ɒ����Ȃ���A���m�̋Z�p�͂����m��芮�S�ɗD�ʂɂ��邱�Ƃ�F�߂Ă��܂����B����́A���m�ɂ́u�{�v�̓����͂Ȃ��āA�u���v�̋Z�p�����邾�����ƌ����B�������u���v�̋Z�p������߂Ĕ��B���������ʁA���C�@�ւƂ��ߑ�H�ƂƂ��������Ė��̕�炵�����コ���邱�Ƃɐ������Ă���B����͌��ʓI��w�̐����ł͂Ȃ����A���m�̎�q�w�҂����͐S�̂�����Ƃ������������Ƃ���_����W�J���Ă������A���ې����̌���ɉ����𗧂��Ă��Ȃ��̂Ƒ傫�ȈႢ���A�ƌ����܂����B�F�{�˂̎�w�͒��N��q�w�̉e�����傫���ƌ����A���N��q�w�͂Ƃ�킯��q�w�̗��C�_���ׂ����W�J�������B�����������ۓI�ⓚ�����ۂ̖��̐����̌���ɉ������ɗ��������A�Ɣ��Ȃ��Ă���킯�ł��B����́A���܂̐���w�������Ă�����A�Y�Ƃ������ēS����~�����͂��ł���ƌ����܂����B���ꂪ���̐�������ƂȂ邩��ł��B�ނ͎�w�́u�{�v�̗��z�͐������̂ł��邪�A�u���v�̋Z�p�ɂ��Đ��m�Ɋw�Ԃ��Ƃ��S�O���Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��A�ƌ�������ł����B
���������̍��v�ԏێR�́A��{���n�⏟�C�M��ɉe����^�����J���I��҂ł����B�ێR�́A�u���m�̌|�p�Ɠ��m�̓��������˂�v�ƌ����܂����B�����ł����|�p�Ƃ́A�Z�p�̂��Ƃł��B�ێR�͐��m�̌R���Z�p�╨���w�̌����ɔM�S�Ȑl�ł����B���̏ێR�́A�Z�p���w�Ԃ̂͂��₷���A�S���w�Ԃ̂͂������ē���A�ƌ����܂����B�ێR�͐��m�̋Z�p�ɂ��Ԃ�Ă��܂������A�̓����͑f���炵�����̂ł��̂܂��������Ȃ�������Ȃ��A�Ƃ����l���ł����B�ێR�͖����̐l�X�̒��ɂ����Ă͐��m���狑�ۂ��Ȃ��l�ł������A����ł��̓��������{�̗ϗ��Ƃ��Ă͍œK�ł���Ƃ����l���ɗ����Ă��܂����B
�������N�̕���@�g�ɂȂ�ƁA����ɘ_�����Ă��܂����B���V�́A��̍l����˂��܂��B��́A�̒��N�����Ƃ��̗ϗ��ɂ����݂��ē��m�����m�ɗ���Ă�����̂ł͂Ȃ��Ƃ����l���ł��B���V�́A���̓��m�͐��m�Ɋ��S�ɗ���Ă��邱�Ƃ�F�߂܂��B��́A���m�̓L���X�g�����D��Ă��邩�狭���̂ł����āA���{�͕����Ƃ��Ƃ�����߂č����S���L���X�g���ɉ��@����ׂ����A�Ƃ����l���ł��B���V�́A�����Ƃ������̂͌Ñ�ɖ�ȏ�Ԃ�}���邽�߂ɔ��B�������̂ł���A�L���X�g�������������Ñ�̎��_�œ����Ƃ��Ă͊������Ă��āA�����ɗD��͂Ȃ��ƌ����܂��B���V�́A�����ŃL���X�g���̓������Ɠ��l�Ɋ������Ă��邱�Ƃ�F�߂�킯�ł��B�������������N�ɑ������ꂽ���m���q�҂Ƃ͈�����悵�A���m�����m�ɗ���Ă���Ƃ���͏@���̂����ł͂Ȃ��A�Ɗ��j���܂��B���V�́A�����Ƃ́u�����v�Ɓu�q�b�v�̔��B�ł���ƌ����܂��B���m�͎����́u�����v�ɂƂǂ܂��Ă��āA�u�q�b�v�̔��B���Ȃ��B����͂ǂ����Ă��Ƃ����A���m�́u�q�b�v����l�̑�����������A���̐l���u�q�b�v���Љ�ɍL�߂銈����W���Ă��邩�炾�B�����ۂ����m�͐l���������āA���ꂪ�L�����Ĕ��W���邱�Ƃ�e�F���������Ă���Љ�ł���B�䂦�ɐ��m�ł͐l�́u�q�b�v���Љ�S�̂ɐςݏd�Ȃ��Ăǂ�ǂW���Ă����B���m�ɂ��u�q�b�v����l�͂��邪�l�̎����̗̈�ɉ������߂��āA�Љ���Ċ����ł��Ȃ����Ă���B���m�Ɠ��m�͂��̍��Ȃ̂ł���A�ƌ����܂��B���V�́A���N�����Ȃǂ͐l�Ԃ𒁏��̒��ɐ���l���ł����Ȃ��A������̂��Ă���Ԃ͓��m�͐��m�ɔs�������ł���Ɣᔻ���܂��B���V�́A�䂦�ɓ��{�ł͋���y���č����́u�q�b�v�̐��������߁A�l���������鎩�R���L�߂āu�q�b�v���\�S�Ɋ����ł����Ԃ����A�ƌ����܂����B
���{�̎́A�������傭�����̝|�Ƃ��Ē蒅���邱�Ƃ͂���܂���ł����B�Ȃ̂œ��{�͖̎����ȍ~�́u�E�q���v�ɕω����A�_������Ƃ��ēǂ݁A��������R���݂ɉ��߂���l�����L����܂����B���{�l�́A�w��L�x�Ƃ���������ǂ݂܂���B�w��L�x�����́A�ɂ����鐶���̝|���߂������ł��B�����E���N�̎́A�w��L�x�̎ł��B�����ɂ͎q�Ƃ��Ă̝|�A�ȂƂ��Ă̝|�A�N���҂Ƃ��Ă̝|���K�`�K�`�ɏ�����Ă���B�ƏG��D�v�́A�����炱�����̂ĂȂ��ƒ����ɖ��勤�a�͗��Ȃ��A�ƌ������̂ł����B���{�̎́A�|�����łȂ������̋����ł����āA����L���X�g���I�ł��B�����ۂ��������N�̎́A�|����邱�Ƃ���Ȃ̂ł����āA������_�������邢�̓C�X�������I�ł��B�����̈Ⴂ��m���Ă����K�v������̂��ȁA�Ǝ��͎v���܂��B
�۔��F��L�ɂ����鐶���̝|�ł����A�ݓ��̒��N�̕��̉ƒ�ł́A���q���x��������ƕ��e����̂��Ƃ��{���A���q������y�������Ďӂ���Ƃ���������������A�O���̐l�������Ă���ΓI�Ńr�b�N�����邭�炢�ł��B���{�ł́A�q��������������A�Â₩������̐e�q��������A�̒m��������A�~�b�N�X�W���[�X�݂����ɂȂ��Ă��܂��B�嗤�ł́A�S�������m��Ȃ��A�쐶�̂悤�Ȑl�������̂ł���A�|�Ƃ��ċ����邱�Ƃ�������Ȃ������Ƃ������Ƃł��傤���B�悭�͕�����܂��A�G���[�g�Ƃ��ẮA���������l�����������悤���Ȃ������B���m�̓������A�悭�͒m��܂��A�[�������̗��j������̂ł͂Ȃ��ł����B
���c�F�]�ˎ��ォ�疋���ł͐��m�̓�����Ⴍ�݂Ă��܂������A�����ɂȂ�ƃL���X�g�����D��Ă���̂Ő��m�͋����Ƃ��A���{�l���L���X�g���ɉ��@����ׂ��Ƃ̍l����������܂����B�������A����@�g�͂ǂ���̓������Â�����m�����ꂽ���̂ŗD��͂Ȃ��Ɣᔻ���܂����B���m�́u�m�b�v�́A�l�Ɏ~�܂炸�A�Љ�e��A���ꂪ���y����Ă䂭�Ƃ��낪�����Ȃ̂ł���ƁB
�����F�����̒����̑�w�ł́A�_�w�A�e�I���M�[�A�����S�ŃC�X�������E�����w����������A�_�w�ƈ�w���G���[�g�͊w�B�h�C�c�ł̓M���i�W�E���ŌÓT�⎩�R�Ȋw�ȂǑ���ɘj��G���[�g���w�ԁB�H�ȑ�w���ݗ�����Ă���B�����A���m���u���̋Z�p�v�Ƃ��邱�Ƃɂ͋^�₪����B
�۔��F�����̐S�̕������������Ă��Ȃ��B
�����F�ÓT�̋��{������B�C�M���X�̃p�u���b�N�X�N�[���ł́A���e������͂��ߌÓT��������邱�ƂȂ���G���[�g�Ƃ��Ă̐ӔC��K�������߂��A�E�G�[�o�[�̉]���Ƃ���̃G�g�X������B���ꂪ�Ȃ��Ɖ��v�J���͗��v��ӓ|�ɂȂ�B�����̎��{��`�́A�D�_���{��`�ł���Ɲ������ꂽ�B����́A�c�����������ׂ��̂��߂Ȃ�Ή��ł�����Ƃ������ł���A���m�̐����Ȍo�ϊ����ɂ͐����ȗ����Ƃ������{��`�̃G�g�X�����L���Ă��Ȃ��Ƃ����ᔻ�ł����B
�۔��F�h�C�c�ɋ������Ƃ�����܂����A�V���^�C�i�[����͂��炵�������B�������l�ԓI�ŁA�S�̋�������Ă��܂��B�S�̂܂܂Ɉ�Ă�Ƃ������̂ł��B���m�ɓ������Ȃ��A���������Ȃ��Ƃ����͓̂��Ă͂܂�Ȃ��B
�����F�����̊O���̐��E�ł́A�e���̃G���[�g���S����ł����A���ʂ���������̂�����܂����B��w�ŃM���V�A�E���[�}�ȗ��̃t�B���\�t�B�[�����L���Ă���A���ʂ̃��[��������܂����B�C�M���X�̊O���̃e�L�X�g�ł́A�u�⊶�v���O���ɉ�����ō��̔��_�Ƃ��A���������ƁA���ۖ@�̃��[������O���Ƃ��܂��B���������v���g�R�[���̏�ɊO�������藧���Ă���B��b�I�ȋ��{���Ȃ��ƁA��ؐl�̎��͍s�g�ƂȂ�B
�۔��F�o�ς�胂��������ɒu���B
�����F���{�l�̕���������Ă���B�Y�Ɗv���ŕx�𐬂������{�Ƃ͋M������̒n�����A���邢�͎݈ʂ����炤���Ƃ���Ƃ����B�C�M���X�̐��S���Ɖƃx�b�Z�}�[�́A�ӔN�Ƀi�C�g�݈̎ʂ����B���̎q���͑c�悪�݈ʂ����Ƃ��������邪�A�c�悪���S�Y�Ƃ̔��W�ɂ����炵�����т���낤�Ƃ��Ȃ������B
�۔��F���[���b�p�̋Z�p�̒��g�𗝉����Ă��܂�����
�����F�Z�p�͍̗p�������̂́A���̔w��ɂ��鋳�{�⓹���͌��Ă��Ȃ��B
���c�F�����Ő��m�v�z�����������悤�ɂȂ����̂́A���{�ւ̗��w�������������ł����B�����́A���m����ŐV�̊͑D�╺������낦�܂����B����ŁA�����̗����{�ɕ�����Ƃ͎v���Ă��Ȃ������B�����������푈�ŎS�s���A�u���̐��p�v�_�͑S���n�ɗ����Ă��܂����B�ڊo�܂������W���Ă������{�ɔނ�͒��ڂ��A�����ɗ��w�����W�܂�܂����B���̍��A���{�͂��łɐ��m�̋Z�p����łȂ��A�v�z�ɂ��Ă��������ێ悵�Ă��܂����B�ނ�͋��Y��`��}���N�X��`�������Ŋw��ŋA��܂����B
��c�F�����́u�i���v�m�v�͓V�́u���v��m�`��q�Ƃ��A�Ռo�ɂ�鎩�R�F���Ɏ~�܂����B�V���w�◥�w�Ȃǂɐ��k�ȍl�@�͂��������A���L���͂Ƃ������悤�Ȑ��m�l�����o�����p�������R�@���̕��ʂɂ͎���Ȃ������B
���c�F��q�͓V���⎩�R�ɂ��S���[���l�ł������A�ނ̎��R�_�͌��ǎl���܌o�������������Ă��邩��A�Ƃ�������i�߂Ă������Ƃ����ł��܂���ł����B�m���ɁA�Ñ㒆���̒m����Z�p�͗D�ꂽ���̂�����܂����B���̍��ɍ��ꂽ�A�z���A�܍s������q�͔����o�����Ƃ����Ȃ������B�A�z���A�܍s���Ŏ��R���ۂ͂������Đ����ł��Ă��܂��̂ŁA�ǂ�Ȃɍl���Ă�����ꂽ�g�̒��ł̎v�l�ł����B�����̓A���X�g�e���X�̑̌n���甲���o�����Ƃ��ł������A�����ł͎l���܌o�̑̌n���甲���o�����Ƃ��ł��Ȃ������B�����͉ߋ��ɂȂ܂������`������������ł��傤���B���{�͊�����w���w�т܂������A�I�����_�̉�U���̂ق����悭�����ł��Ă��邱�Ƃ�m��A������ɃX�b�p����芷�����B�ł������ł����O�łȂ��A���̑̌n�ŁA�������M���邱�Ƃ������s���悭�p����̂ŁA�s�����Ƃ݂Ȃ��Ύ̂ĂĂ��܂��B
�۔��F������w�́A���ł��܍s���ɂ��Ă͂߂�B�Ȃ�ł������������ɂȂ�̂��ƕ����A�̂��炱����������Ă���A�����������Ȃ��B����Ō˘f���B���d�s�v�c�Ȃ��ƁB
��c�F�����̘B���p�̍ޗ��A���@�̋L�q������Ύ��ɐ��k�Ńr�b�N������B
�����F���̒��ł͍��x�ɑ̌n������Ă��邪�v�ٓI�B��������Ƃ��낪�Ȃ��B�����ŁA�t�̂ŁA�s�V�s���A���₪�łł���ɂ�������炸�A���p����B
�۔��F��V���w��ł��܂����A���ɂ������Ă���G�l���M�[���������B
����F�o����`�ł�����A��������������Ă���B
�۔��F�A�t���J�ł̓G�C�Y�̎����ɐj�����g���A�l�������Ă���B�A�C�X�}���̓���n�̏��������Ǝ���Ƃ����̂�����܂��B
�����F���̌����������ł��˂Ȃ�Ȃ��B
�۔��F���Ă��ǂ��Ƃ���܂����A�M�̂��܂�l�ɂ́A���Ă͔M���Ă��点�邽�ߓłɂȂ�܂��B���Ă͒��ԁA�����肳��肪�Ȃ��B
���c�F�����̎v�z�ł́A�V�E�n�E�l�͊��S�ȑ��݂ł���ƍl���܂��B�V�n���z���Đs���Ȃ��悤�ɁA�l���܂��{���͏z���Č��N�ɐ���������̂ł���B�a�C�Ƃ͂��̏z�̂�ǂ݂ł���A��ǂޏ���ʂ��Ă��A�{���̗���ɗ����Ԃ�Ύ���B����͈�̎����ł���Ǝv���܂��B
�۔��F�l�̂ɂ́A�����͂�����B
���c�F�����l�́A���[���Ƃ���Ŋy�V�I�ł���Ǝv���܂��B�V���n���L���Ős�����A��������l�Ԃ����ɐ�����Ό��N�Œ����Ŏq���ɉh���Ď|�����̂��H����B�����͒n�啨���i�L��ŕ����L�x�j�̓y�n���ŁA�y�V�I�ɐ����Ă䂯��Ƃ������y���y�V�I�Ȏv�z���Y�̂ł��傤�B�C�M���X�������c��ɖf�Պg������肵����A�c��̓C�M���X�Ƃ̖f�Ղ͉��b�ł���A�킪���͒n�啨���A�C�M���X����~�������̂Ȃǂ͂Ȃ��A�Ɠ˂��ς˂܂����B���{�͒����ƈ���Ď��R�ЊQ������A�����ŏ��s����Ƃ��������ĔߊϓI�ɂȂ�̂������Ƃ��čD���ł����A������͒����ȏ�ɖL���ł���A���{�l�͕\�ʂ͔ߊϓI�ʼn���ɂ͉��Ƃ��Ȃ�Ƃ����y�ς�����Ǝv���Ă��܂��B���ꂪ���[���b�p�ɂȂ�ƋC���A�C�M���X�ł̓W���K�C�����炢�����܂Ƃ��Ɉ炽�Ȃ��B���̕��y�ł͔ߊϓI�ɂȂ�ł��傤�B
�����F�z���I�X�^�V�X�̍�p�����邩��g�̂̒��Ŏ����Ă䂭
���c�F�z���I�X�^�V�X�́A����p�łȂ����R�����͂Ɉˋ����Ď��Â���Ƃ����l���ł��B������w�̔��z�́A���������������̂ł��B
2025�N6��7���i�y�j��w�͋�
�{���́A�Z�c����A���c����A��c����̎O�l
���c��������W���i�o-05�j�A
�u�`�͂�����youtube�@
|
�ԑ厚�F��L��w�т̌���
�Ώ����F��q�̒�
���厚�F��q�̏������낵��
���厚�F�������ւ̉��
|
|
�Ái���ɂ����j�̖����i�߂��Ƃ��j��V���ɖ��i�����炩�j�ɂ��܂��~����҂́A��i�܁j�����̚��i���Ɂj�����ށB
���͕��߁i�ւ������j�B��i�̂��j�����i����j�ɕ��i�Ȃ�j���B
������V���ɖ��i������j���ɂ��Ƃ́A�V���̐l�����ĊF�Ȃđ��̖����𖾂��ɂ��邱�ƗL�炵�ނ�Ȃ�B
|
����艺���i�́A�Ðl�̊w�����鎟����܂т炩�ɂׂ̂āA��̍j�̒��̞��ڂ������A�V���̂��͂܂���A�������̂͂��߂܂ŁA�i�X���Ƃ�萄�����͂߂āA���̖{���͂��߁A�{���̓��ɂ������̂��̗p���̂��ł��邱�Ƃ�������B������V���ɖ��ɂ��Ƃ́A�V���̐l�̖������A�F���ɂ����ނ邱�Ƃ��]�B���̌�V���ɖ��������ƁA��ނׂ���`�Ȃ�A�������̎O���́A���H�v�i���ӂ��j�̖��ځi�݂Ⴄ�����j�ƂȂ�āA�����͌N�ɂ������A���ɂ����ʂȂ�B������͐��V���ɂ��邱�ƂȂ���A�����̔@���ɂ��Ђ��ւ���́A�V���̏���A�������܂ɐ��āA����V�ɂ��邱�Ƃ��A�킪�������̌��𐄂��Ђ�ނ����ɂāA��.�i�����j�ɂ��炴�邱�Ƃ������B�R��Ή��̍������߉Ƃ�ꎁi�ƂƂ̂Ӂj�邱�Ƃ��A���݂Ȗ������̐������Ȃ�ƒm����Ȃ�B
�H�v�F���v�Ɠ����B�w�͂Ƃ��̂����B
�������ނƂ́A����̏���A�����̖��X�܂ŁA�I�j�@�x�i�͂��Ɓj�A��X�i���������j�ɂ��Ă݂��ꂴ��₤�ɂ��邱�Ƃ��]�B�W�i�������j�V���̖{�͚��Ȃ�B
�� ��
�̓��悭�����܂�Č�A�����@���Ƃ��āA�����Ђ�ނ�A�V���A�i�Ђ�j���Ƃ��ւǂ�
�A�ꓝ���ĕ��ɂ��ׂ��B���̌̂ɁA�V���ɂ���Ƃ���ɂ́A�悸����������Ȃ�B
��X�F���R�Ɨ���Ȃ��l�B���X�B
|
���̚������߂܂��~����ҁA��Ñ��̉Ƃ�ꎁi�ƂƂ́j�ӁB
|
ꎂӂ�Ƃ́A��������ւāA�ЂƂ�������`�Ȃ�B�Ƃ̂�����j�������i�������傭�j���c���ځA�݂ȉ��`���������A�ϗ��𐳂����āA�e�i���̂��́j���̏�����͂��A���̕��Ɉ����߁A��ꎂɂ��Ă����Ђ߂Ȃ�������A�Ƃ��ƂƂ̂ӂ�Ɖ]�B�W���̖{�͉ƂȂ�B��Ƃ̓����A�悭�ƂƂ̂ւČセ�̐b�����A�Ђ������ȂւA���݂Ȃ���ɂȂ�Ђč������܂˂����܂�ׂ�
���B���̌̂ɍ������߂�Ƃ���ɂ́A�K�i���Ȃ炸�j�܂Ñ��̉Ƃ�ꎂӂ�Ȃ�B
|
���̉Ƃ�ꎂ���Ɨ~����҂́A�悸���̐g�����i�����j��
|
|
���̐g�����߂�Ɨ~����҂́A�悸���̐S�𐳂������B
�S�Ƃ́A�g�̎�Ƃ��鏊�Ȃ�B
|
|
���̐S�𐳂�������Ɨ~����҂́A�悸���̈ӂ𐽁i�܂��Ɓj�ɂ��B
���Ƃ́A���i���j�Ȃ�B�ӂƂ́A�S��ᢁi�͂��j���鏊�Ȃ�B���̐S��ᢂ��鏊�𛉂ɂ��A���̑P�Ɉ�ɂ��Ď���\�����Ɩ�����~����Ȃ�B
|
���c����̃��W���i��w�͋�ߘa���N�Z���j
�挎�́A�{�����ł����B�����́A�u�H�v�v�ł��锪���ڂɓ���܂��B�����ڂƂ́A�i���v�m���Ӑ��S���g�ĉƎ������V���ł��B�ŏI�ړI�ł���O�j�̂𐬂������邽�߂ɁA���̏�����œw�͂��Ȃ�������Ȃ��A�Ɛ�����܂��B�傫�ȖڕW���ǂ�ǂ�Â߂Ă����A���ɂ͎����̔]���̓����Ɏ���A�Ƃ����X�g�[���[�ł��B���̑�w�̂킸����߂���A��q�w�͋���ȗ��_��ςݏグ�Ă����܂����B
��w�̔����ڂɋߐڂ��錾�t�́A�w�Ўq�x�̒��Ɍ����܂��B�������w�Ўq�x�̒��ł́A���ɂ́u�����v�ł���A�ƂȂ��Ă��܂��B
|
�V���̖{�͍��ɍ݂�A���̖{�͉Ƃɍ݂�A�Ƃ̖{�͐g�ɍ݂�B�i���K�͋��j
�����ɂ��ē������ꂴ��҂́A���܂����ꂠ�炴��Ȃ�B�i���j
|
���ꂪ�A��w�ł͐��ӂ̑O�Ɋi���v�m���u����Ă���B������ɓ��m�ւ͕s�R�Ƃ��A��w�͍E�Ђ̋����𗝉����Ă��Ȃ��㐢�̎҂̍�ł���A�Ɣᔻ�����̂ł����B
��Ƃ̒��ŁA�i���v�m�ɂ��ēO��I�ɋc�_�����l�́A䤎q�ł����B�w䤎q�x�̉���т́A�S�������ς���菜���Ċ��S�Ȕ��f�͂邽�߂̕��@���_�����Ă��܂��B�����тł́A���t�ɏ�ʉ��ʂ̃J�e�S���[���ނ��s���A���t�Ɍ����Ȓ�`���s�����Ƃ��_�����Ă��܂��B���t�Ɍ����Ȓ�`���s�����Ƃ́A�c�_�������ɍs�����Ƃł���A���f�𐳊m�ɍs�����߂̒n�Ȃ炵�ł����B�퍑����̎v�z�ƂŁA䤎q�قNJi���v�m������������҂ɂƂ��ďd�v�ł��邱�Ƃ����������҂͂��܂���ł����B����ŁA�ߑ�̌����҂����́A��w��䤎q�w�h�̍�ł��邩�A���邢�͖Ўq�w�h��䤎q�w�h�̑����ł��낤�A�Ƃ������_���s�����̂ł����B��w���Ўq�w�h��䤎q�w�h�̑����ł���Ƃ���A���ꂪ�s��ꂽ�����͌Â��Ă��`��A�����炭�͑O����̂͂��ł��B
�����́A���V���A�����A�ĉƂ̂Ƃ���܂łƂ������Ǝv���܂��B�����܂ł͎����̊O�̐��E�ł���A���������͎����̒����ǂ����邩�̋c�_�ŁA�����ł������������ق����悢�Ǝv���܂��B
�w��w�x�͎�q�ȍ~�͎l���ɑI��āA��{���������N����Ɋw�Ƃ����悤�Ɉ�ʐl�̓����Ƃ��ēǂ܂��悤�ɂȂ�܂����B����ŁA�u�Ƃ�Ă��v�ƌ����A�e�Z��Ȏq���炢��z�肵�ēǂ܂��B����͂���œ����Ƃ��Đ��藧�̂ł����āA�����̋��璺������K�͂ȉƒ�̓������q�ׂĂ��܂��B�������Ȃ���A��w�̐������O����ł������Ƃ���Ȃ�A���̍c���ɂƂ��āu�Ƃ�Ă��v�ƌ����A���ƌ��͂̂��ׂĂ��������邱�ƂƓ����Ӗ��ł���A�Ƃ�Ă��Ȃ���������܂�Ȃ��Ƃ����̂́A�����̗��ł���܂����B���̒���́A���Ƃ̊����ƍc���̊������͂������ʂ���Ă��炸�A���Ƃ̊����͂܂��c���̎��I�ȉƐb�ł���Y���ƂȂ邱�Ƃ��o�R���Ă���C�p����邱�Ƃ��ʗ�ł����B�c���͋���ȍ��Y�E�y�������A���̂��߂̊���������܂����B�c���̎����͍��Ƃ̍��������Ƃقړ����K�͂ł���A�c���̍����Ƃ����ł����ɉۂ����A����̋��z�̉�����p�͍c����������P�o����܂����B�e���ɕ�������闫���̏���́A���Ƃ���Ƃ��đa���ł������Ƃ��Ă����ʂ̑c����J�铯���W�c�ł����B�����c���̊����A�c���̍��Y�A�c���̈ꑰ������u�Ă��v�͖̂c��Ȏd���ł���A�u�Ă��v���Ƃ����Ƃ��u���ށv�邱�ƂɂȂ���̂́A�ꑰ���w�������^�����̗�������Ζ��炩�Ȃ��Ƃł����B�Ȃ̂ŁA����́u�Ƃ�Ă��v�̈Ӗ��͌㐢�Ƃ̓X�P�[���������Ⴂ�Ȃ̂ł������A��{�����E���璺��̂悤�ɓǂނ��Ƃ��㐢�̃X�^���_�[�h�ƂȂ����̂ŁA���̂悤�ɓǂނق����������Ƃ��Ă͐������B�ƒ�̓������Љ�̊�b�ł���A���Ƃ̊�b�ł���A�Ƃ��������́A�ێ��`�҂��悭�g�����̂ł��B�w��w�x���A����͂�����̂悤�ɓǂ܂�܂��B�w�[�Q���̌����A�c���l�����R�ł���c��ȊO�̓h���C�ł���������ƁA���ׂĂ̐l���Љ���ێ�����͈͓��Ŏ��R�ł��鎞��Ƃł́A�����e�L�X�g�ł��ǂ܂��������Ă���͓̂��R�ł���A�ނ���ǂ���̎���ɂ��K�p����ĉ��߂ł���Ƃ��낪���ɂƂ��Ă͖ʔ����Ƃ���ł��B
��w�͖Ўq�̐���䤎q�̐��̑����Ȃ̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����b�������̂ŁA���������͖Ўq��䤎q�̍��ɂ��ď����q�ׂ����Ǝv���܂��B�Ўq�́A�퍑���㒆���̎v�z�Ƃł����B䤎q�́A�퍑�������̎v�z�Ƃł����B�Ўq�̎���̖��ӎ��́A����Ȍ��͂��������퍑����̉��������A�����ɑP�Ɍ����킹�邩�A�ł����B�퍑����̉������́A�O�̏t�H����̏����ɔ�ׂāA�z���Ɋ������]���A�̖�����ł��W�߁A�����W�߁A���Ȑ����Ƒ�K�͂Ȑ푈���s���͂�����܂����B�����p���ĉ䂱�������ؐ��E�̑n����ƂȂ�̂��A�Ƒ������Ă����B����ɑ��ĖЎq�́A�V���̉��ƂȂ�ɂ͐m�`�̐S�������āA��������͂ɐ����L���Ȃ�������Ȃ��A��������ΓV���̉��ƂȂ�̂͊ȒP�Ȃ̂ł���A�Ɖ������ɋ������̂ł����BꟂƂ��w�Ƃ������Ƃ��̓`���̐����̃G�s�\�[�h�����グ�āA�ނ�͐m�`������������V���̉��ƂȂꂽ�̂��A�Ɛ��������̂ł����B�Ўq��������헪�́A���͂̃g�b�v�̐S�������ւ��邱�Ƃł����B�Ўq�̎���́A����ʼn����������܂������A�Ɗy�ώ����Ă����B
�Ўq���Ă̑�b�ł������I���O315�N�A���̉��œ������N���܂����B���̉��͂��������ȕ�炵�������A����k�����Ƃ�]�Ɓw�ؔ�q�x�ɋL�^����Ă��܂��B�Ўq�̓������Ɋ������Ă����n�Ƃ̗V���Ƃ̉e�������̂ł͂Ȃ����A�Ɛ����������������܂��B����ʼn����́A�Ɛb�̎q�V�Ɉʂ������Ă��܂��܂����B�Ўq���̂���͂邩�̂�w�̑T���̔��k���A�퍑����Ɏ��ۂɂ�炩�����̂ł����B�n�Ƃ́A�Ўq��������ɐ�s�I�ɁA�����͗L�\�Ȑl�Ԃ����s���Ă͂����Ȃ����Ƃ��咣���Ă��܂����B
�T���̌��ʁA�������N����܂����B�����̌o�߂͂͂����܂����A���lj����̑��q�����ʂ��邱�ƂƂȂ�A�����̔�Q�҂��o���������̌��ʂɏI���܂����B���̎�������A�퍑����̎v�z�͕ω������Ƃ����܂��B����܂ł́A�u�N�傪�P�l�ł���A�����I�ɍ��͎��܂�v�ƍl�����Ă��܂����B�������q�V�̗��̌�́A�u�����͌N��̑P���ł͂Ȃ��A�����͒����̈���ł���v�Ƃ����l���ɕς��܂����B��������A�Ўq�̎��̐���̎v�z�Ƃ����́A���肵�������Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��邩�A�ɂ��čl�@��[�߂Ă����܂����B
���̍l�@�̖��ɁA䤎q���o�Ă��܂����B䤎q�́A�퍑����v�z�ɑ����܂��B�퍑����v�z�̓��B�_�́A�ЂƂ́u�N����͂���ɏW��������v�ł��B���͂����U����Ă�����A���͈ڏ��̃��[������܂��Ă��Ȃ��ƁA�K�������ƂȂ�B�N�傪��̌��͂��W�����A���̖��߉��ō��Ƃ̕x�ƌ��������z����Ȃ�������Ȃ��B���ꂪ�A���́u�N��̉��Ɂu���v�̍��Ƒg�D���\�z����v�ł��B�N��̌��͂𐭎��Ƃ��Ď��������邽�߂ɁA�N��̉��ɐ����E�����ɕ�����ꂽ�g�D�����B����炪���Ԃ̂悤�ɏォ��̖��߂����s���邱�Ƃɂ���āA���肵����������������̂ł���A�ƁB���̐퍑����v�z�̓����́A䤎q�����Ƃ���ł���A�ؔ�q�Ȃǖ@�Ǝv�z�������������Ă��܂��B
�����̌Ñ㕶�����A���̌Ñ㕶���ɔ�ׂāA�Ɠ��ȓ_���ЂƂ���܂��B����́A���Ƃ̊��ʊ��E�̐��x���ُ�ɔ��B���Ă���Ƃ���ł��B�Ñ㒆���̊��ʊ��E�́A�㉺�ɂ������ɂ��ُ�ɍׂ����v����Ă���B���ꂪ���{�ɂ��`����āA������v�Ƃ����厘�Y�Ƃ�������Ƃ��A���m�����͊��E�������L����Ė����悤�ɂȂ����B���ׂ̍��Ȋ��ʊ��E�́A�퍑�������̎v�z�Ƃ��������ƒ�����_���钆�Ŕ��B�������̂ł��B�ނ�퍑�������̎v�z�Ƃ����́A�N��̉��Ɂu���v�̍��Ƒg�D���\�z���邱�Ƃ��A�����̎�����ł���ƍl���Ă����B�퍑�������v�z�̖��ɂ�����䤎q�́A���Ƃ̊��E�\�̃v�����\���Ă��܂����B���ꂪ��q�̗��z�ɓ`���A�`�̊��E�ƂȂ�A���Ɉ����p����Ă������͂��ł��B�Ñ㒆���ُ̈�ɍׂ������ʊ��E�́A�퍑�������̎v�z�Ƃ����̗��z�����f���ꂽ���̂ł����B
�Ўq�͗��z�̌N���P�Ȃ鉤�ƒP���ɍl���Ă����̂ɑ��āA䤎q�͗��z�̌N��������g�D�̒��_�ɌN�Ղ��鑶�݂Ƃ��čl���Ă��܂����B���̒��_�̌N��ɑ��āA�ǂ����䤎q�͍ŏ��͔\�͂��ł��D�ꂽ���݂��ӂ��킵���A�ƍl���Ă����悤�ł��B�������A䤎q�͍ŏI�I�Ɂu��v�ɏ]���ׂ��ł��邱�Ƃ���������悤�ɂȂ�܂����B�\�͂��ł��D�ꂽ���݂��N��ł��邱�Ƃ́A�����̐����ł͂قڋN����܂���B�ނ���A�N��́u��v���w��ŌN��̈Ќ�������A�z���̊�����M�C���Ďd���̐��s��C��������ɓO����悢�A����u�N�Ղ���ǂ����������v���x�ŏ[���ł���A�ƍl����悤�ɂȂ����B�����Ƃ��z���̔\�͑P������������ڂ����́A䤎q�̌N��Ɉ₳�ꂽ�����ł���܂������B
䤎q�̌�A�O����̌��ِ��x���ǂ̂悤�Ȃ��̂ł������������āA�Ō�ɋ�̓I�ȃC���[�W�����������Ǝv���܂��B���W���̐}�́A���搶�����グ��A�؊Ȃɏ�����Ă������ٕ����̗���ł��B�I���O�Z��N�̋L�^�ŁA�O�����̎����ł��B���͗L�\�ȌN��Ƃ��Č㐢�ɂ��]������Ă��܂����A���̌��ق͉Ď��̓��Ɋ��R�ɋx�ɂ��o���Ƃ����ْ��ŁA�d�v�Ȗ��߂ł͂Ȃ��B����ł����ߐ��̌��O��A��̎��Ă͍c��̍ى����Ȃ�������܂���B����ʼn�����オ���Ă�����t���告�����p���A�����͍c��̔鏑���I������S���Ă�����j��v�����{�Ă������čc��ɍى������B�c�邪�������u�����ĞH���v�Ƃ́A�Ă̂Ƃ���ɂ���A�Ƃ������Ƃł��B������u�\�E�Z�C�v�ł���A���Ƃ����ǂ����̒��x�̈Ăɂ��Ă͉��̏�t�����̂܂܍ى����̂ł����B�c��́u�\�E�Z�C�v���o�ď��߂ďقƂȂ�A�@�ƂȂ�܂��B����ȊO�̉����̏���Ȕ��f�́A���߈ᔽ�ł���A�퍑����v�z�̃��[���ᔽ�ł���A�㐢�܂ŔF�߂��邱�Ƃ͂���܂���ł����B����̐ߓx�g�̂悤�ɒn�����ɍs�����ł̌�����^������́A���Ƃ̕��������ł����B
�ȏ�̂悤�Ȍ��ِ��x���@�\���Ă���A�c��͑������ނ�����Ȃ��Ă��A�z���̏告�ȉ��̊����j��v�̏�t�Ɂu�\�E�Z�C�v�ƌ����Ă������͉^�p�����B䤎q�̕`���Ă������x���������ƁA���̂悤�ł���Ƃ�����ł��傤�B
�����A�����̗��j�ɂ����ẮA�Ƃ�����u�\�E�Z�C�v�ŏI��点�Ȃ��N�傪�o�Ă��܂����B�`�̎n�c��A���̎錳���A����贐���́A�u�\�E�Z�C�v�ŏI��点�Ȃ������O�l�̍��N�ł����B���ߐ��̌��t���Ƃ��ẮA�N��̔��f���߂���̖@�ƂȂ�܂��B�Ȃ̂ōc�邪��t���ꂽ�ĂɃ_���o��������ƁA�z���͏]����葼�͂���܂���B�O����̌�j��v�̖����́A�㐢�̒��؉����ł͒����E�剺�E�����̎O�Ȃ��S���悤�ɂȂ�܂����B���̎錳���͂��̎O�Ȃ�p�~���A�c�邪�S�Ă̈Č��������̔��f�Ō��ق���V�X�e���ɂ��Ă��܂��܂����B�錳���͎c�s���L�\�ȌN��ŁA�ނȂ�Ή\�ł������B�������㐢�ɂ��̃V�X�e�����p�������Ă��܂������Ƃ����ł����B�L�\�������̂͑��q�̉i�y��܂łŁA���̌�͂悭�Ė}�f�A��͑ӑĂ����邢�͋��C�ɑ����N�傪�����܂����B�����̍c��̉e�ƂȂ��āA������̌��ق��s�����̂��A�����ł����B�����͛����ɂ���Ėłƌ�����̂́A���Ƃ��c��̌��قȂ��ł͉��������Ȃ����ߐ��x�ł���A�Ȃ������̍c�邪�܂Ƃ��Ȕ��f���s��Ȃ����߁A���̛͂������c��̖�����čD������ɖ��߂������悤�ɂȂ�������ł����B
��c�F�u�����͌N�ɂ������A���ɂ����ʂȂ�B�v�Ƃ͂ǂ��������Ƃł����B
���c�F�{���ŁA�����̑Ώۂ��N�▯�Ɍ��肵�Ă��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B
��c�F�ł͖������ΏۂƂ���̂͒N�A���ł����B
���c�F��ʓI�łȂ���Ȃ�Ȃ��B
��c�F�E�E�E���ւ̈Ӑ}��������܂���B����͂����āA����̍u�`�ł́A��w�ɉ�����u�Ɓv�͉�X���ʗ�z�肷��X�̉Ƃł͂Ȃ��A����A���ł͗��Ƃ�z�肷��悤�ȁu�Ɓv�Ƃ���l�������|�C���g�ƂȂ��Ă��܂����B��w�́A���������Ƃ̎҂ɑ��ĕҎ[���ꂽ���ƂȂ�܂��B��w�ɂ͖Ўq��䤎q�̍l�����������Ă���Ƃ������Ƃł����A䤎q�̍l��������������Ă���̂ł���A�u��v�Ɋ�Â������_����荞�܂�A������������ɂȂ�̂ł͂���܂��B�O�j�́A����ڂ͂����ς�S�̂�����ɐs���Ă��܂��B
���c�F���Ӑ��S�C�g�ĉƎ������V���̏����͖Ўq�Ƌ��ʂ��Ă��܂��B�������i���v�m�͖Ўq�ɂȂ��B�א��҂Ɋi���v�m���d�v�ł��邱�Ƃ����������҂Ƃ����A䤎q�ł��B��w������ɐ��������ƂȂ�A�����ǂޑΏۂ͍c��A���q�A���̑��ߓ��ƂȂ�鉤�w�̂悤�Ȃ��̂ŁA���̐S�̂����������Ă���ƍl�����܂��B
��c�F�����ɂ������悤�Ɏ�q�ɂ����ẮA�Ƃ́A����͂��Ƃ��A�b���A���A�N���́u�Ɓv���ΏۂɂȂ��Ă���A�Ђ�����Ԃ�����������A���V���̂Ȃ��悤���K�����ƕς�܂��B
���c�F����Ƒv��̈Ⴂ������ł��傤�B�v��͉ȋ����������Ă��܂����B�א��҂͖��̒�����I��Đ����^�c�Ɍg������B������������ł́A��w�́u�Ƃ�Ă��v�́A���ʂ̉ƂłȂ�������Ȃ��B����ł́u�Ƃ�Ă��v�̎w���Ƃ���͒鎺�ł���A�鎺�Ɋi���v�m������K�v�����������́A������Ƃ킩��Ȃ��B�ނ����L�̊w�L�тȂǂ́A�͂�����Ɗ����̐S���Ƃ��ď�����Ă��܂��B�����ł͎t�Ɋw�сA�w�F�Ō݂��ɋc�_���Đ��ۂ𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ̏d�v����������Ă��āA����͊i���v�m�Ƃ�����ł��傤�B
�Z�c�F�퍑����̑O���ƌ���̋��ڂɂȂ����u�q�V�̗��v�͂ǂ��������ʼn��̋N�������̂��B
���c�F�i����噲�̎��A�����ɑ��̎q�V�ɐ�����T���������ƂŁA�O�N�ō�����S��������������B���q�������q�V��œ|���镺�����������ƂȂ�G
����������
�B�j�j�L�ɂ��A�q�V�����������x�����Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B������w�`�������Ă͂₳��A�����͖n�Ƃ̎v�z�ɉe�����ꂽ�\��������܂��B�����́A���������ȕ�炵����������k�����Ƃ�]�Ɠ`������B�Ўq�Ɩn�Ƃ́A�N��ɗv������Ƃ��낪�Ⴂ�܂����B�Ўq�́A���͐m�`�̐S�������Ƃ��̗v�ŁA����ŗL�\�ȉƐb��S��������̂������ς�̖�ڂł���ƌ����܂����B�n�q�́A�N����Z�̂悤�ɂ��̐��ł�����L�\�ł������Ȃ�������Ȃ��A�ƌ����܂����B�Ўq���i��ŁA�L�\�Ȑl�����������s�Ȃ��ׂ��Ƃ����B�iꟂ͉��ʂ����҂̋��R��樂낤�Ƃ����̂ł����A���R�͎�����܂��B�������q�V�ɑT������Ƃ���A�q�V���邱�Ƃ͖����ł��傤�BꟂ̂悤�ȉ��A���̂���l���ɂȂ��ƕ�������A���������Ƃ���A�q�V���Ă��܂����j�B
�Z�c�F�q�V�͑P�ǂȕ����ł͂Ȃ������B���̎v���͑��q�ɂ͓`���Ȃ������B
���c�F�j�L�ł́A�q�V�͕������������x�����Ə�����Ă��܂����A����͏��҂̋L�^�ł����āA�s�҂����Ƃ��ď����Ă���B���Ԃ͂ǂ��ł��������͂킩��܂���B
�Z�c�F�u�q�V�̗��v�̕����͎j�L�݂̂��B
���c�F�Ўq�ɏڂ���������Ă��܂��i
�����N�͋剺
�j�B
�Z�c�F�Ўq�͉������ǂ��݂Ă����̂��B
���c�F�V�̖�����T���Ȃ�ΐ��������A������樂邱�Ƃ͔F�߂��Ȃ��B���̖��������ŋꂵ��ł���̂ŁA�Ă̐鉤�ɋ`�̌R���N�����Ƃ�i�����܂����B�鉤�͏o�����܂������A���Ă̊����̂��Ƃ�������ߐV�����N��𗧂ĂēP������悩�����B�������鉤�́A�������悤�Ƃ����B����ő��q�����𗦂��Ē�R���A�Ă͉��ɉ��݂����c���ēP�ނ��邱�ƂɂȂ����B�Ўq�͎��̌������Ƃ��Ȃ������鉤�������̂��A���͈����Ȃ��A�ƌ����Ă��܂����A�Ўq�����̒���ɐĂ��������̂͐ӔC�̈�[������Ƃ݂Ȃ��ꂽ����ł��傤�B
2025�N7��5���i�y�j��w�͋�
�{���́A�Z�c����A���{����A�۔�����A���c����A��c����̌ܐl
���c��������W���i�o-06�j�A
�u�`�͂�����youtube�@
|
�ԑ厚�F��L��w�т̌���
�Ώ����F��q�̒�
���厚�F��q�̏������낵��
���厚�F�������ւ̉��
|
|
���̉Ƃ�ꎂւ܂��~����ҁA��Ñ��̐g�����i�����j�ށB
|
���ނƂ́A�����ނ�Ȃ��A�����邱�Ƃ��]
�B���̐g�̈ЋV�����A叓
�i���Ɓj�ɜ䂶�A���ɐځi�܂��́j�邱�ƁA�݂Ȓ��������ɂ��āA����ނ��ƂȂ��A����邱�ƂȂ����A�g���C��Ɖ]
�B �W �i������ �j�Ƃ̖{�͐g�Ȃ� �A���̈�g���悭
����A�Ɛl�̒�{�ƂȂ�āA�݂Ȃ����͗߂�
�A�������͂��ނׂ����B���̌̂ɉƂ��ƁR�̂ւ�Ƃ���ɂ́A�K�i���Ȃ�j���܂Ñ��̐g�܂ŁA����ɖ{�𐄂����͂߂āA��i
�܂� �j������}�Ƃ��ׂ����Ƃ����ւ�B
���������F��q�w�p��
�B �S���O�� �Ɛڂ�����������������i�����j
��A���܂Ȃ����ӂ� �s���͂��Ă��� �B
�Ƃ̖{�͐g�Ȃ� �w �Ўq �x ���K�͋�� �u
�V���̖{�͍��ɍ݂�A���̖{�͉Ƃɍ݂�A�Ƃ̖{�͐g�ɍ݂�B
�v
|
���̐g�����߂܂��~����҂́A��Ñ��̐S�𐳂������B
�S�Ƃ́A�g�̎�Ƃ��鏊�Ȃ�B
|
���������Ƃ́A ���������Ȃ� �A �Ђ��݂Ȃ����邱�Ƃ� �] �B
�S�͑������Ȃ� �A �{�̒��a�ɂ��āA �������炸�Ɖ]���ƂȂ��B
����ǂ� �ϔO�G���ɂ��܂������鎞�͑��̗p�̍s�͂�� ��
�A���( �ւ�ρj ����āA�� �����炸�B�w�ҏ�ɑ��{�@
(����₤�������j�̍H�v��p��A�����݂Č�
�A���Ê���̊�(�������j��ɑ�(���́j�{�̂̐��������Ȃ͂��B
�W�S �͐g�̎�Ȃ�B�S��Â��ɂ͂ȂĂ鎞��
�A��g�S�̂����߂����ǂ�҂Ȃ��B���̌̂ɁA
�g�����߂�Ƃ���ɂ́A�K�܂� ���S�𐳂����炵�ނ�Ȃ�B
�����艺��
�A�݂����g�̍H�v�̓��ɂ��āA���i�����j���킫�Ă��ւ�B
���������A�� �����B
�s�����A�s�ύt�B
�S�͑������Ȃ�A�ȉ��l��
�w���f�x�̎�q�w�I���߂��q�ׂĂ���B
�S�̖{�̖{�R�̐��Ƃ����� �{���I�Ɋ��S�ł� ��A�����ł���A
��ɒ��f�E���a�ł��関���̒��B
���ꂪ�O�E�ɐڂ���Ƃ��A��p����������
�{�R�̐����C���̐���ʂ��Ď�������
�B���̍�p�͂��̂܂܂ł͉ߕs�y�ƂȂ�A���f����O��Ă��܂��B�H�v����ׂ��͐S�̍�p��
��������������悤�ɂ���Ƃ���ł���ߔ��̒��B���ꂪ
�u�����𖾂ɂ���v �Ƃ������Ƃł���B
��蘁A�������B
���� �킫�Ă��ւ��ƌ���Č����Ă���
�B
|
���̐S�𐳂������܂��~����҂́A��Ñ��̈ӂ𐽁i�܂��Ɓj�ɂ��B
���Ƃ́A���i���j�Ȃ�B�ӂƂ́A�S��ᢁi�͂��j���鏊�Ȃ�B���̐S��ᢂ��鏊�𛉂ɂ��A���̑P�Ɉ�ɂ��Ď���\�����Ɩ�����~����Ȃ�B
|
�ӂƂ́A�S�̂�����o�鏈 �B �}���O���̗ނ݂Ȑ� �Ȃ�B
����𐽂ɂ��Ƃ́A�l�̖{�S �A�P�����̂ݜ����ɂ��܂��Ɖ]��
���ƂȂ��B ����ǂ� ���~���̌`����萶 ���� �A
�ӔO�̊Ԃɂ܂��͂�̂� �A���̑P���ɂނ��ӏ�
�A�킪�{�S�̂܂܂Ȃ炸�A���ւ�đP�������ȂЁA�����܂����Ƃ���B
�Ȃ���R�P�����̂ݜ����ɂ��ޏ�����́A��₤�l���͂Â邪���߂ɂ��āA�킪�{�S��
���R��悭���邽�߂ɂ��炸�B
�����݂Â��炠���ނ��āA�ӂ܂��ƂȂ炸�� �]�B
�S�𐳂�����H�v�́A�ӂ𐽂ɂ�������A�X�Ɉ�d
�������イ�j�� �i���́j ���B
���̌̂ɁA�S�𐳂�����Ƃ���ɂ́A�K�܂ÔO���̒[�i�͂�
�j�ɂ��āA �Ȏ@�� ���i�������������j�̌���p�ЁA��
�����ނ������܂��ߐ� �i���� �j��
�A����������ɂ��ׂ��Ȃ�B�}�����l���͓͂��O�i�Ȃ��� �j��v
�Ȃ�B �C�g�̍H�v�� �A�������̏����ɂ��炸�B
���S���ӂ̂��ƁA�F�����ɂ���B���S���ӂ̍H�v������O���̊ԂɁA�Ƃ�킫�Ă���ɔB
�����g�̍H�v���A���ɂނ��ЂāA�}�Ȃ鏊�� ��ɂ��āA���邱��
�R �m��ׂ��B
��₤ �� �v �B
�������� �B
��₤ �l�� �l �� �͂Â邪 ���߂ɂ��� �A �ȉ� �` �Z�� �u
���l �� �� �� �� �s �P �� �ׂ� �v �� �_ �� �z�肵�Ă��� �B
���l �� �P �炵�����Ƃ� ����̂́A ���l �� �ڂ� �C�ɂ��Ă���
����ł���B ���l �͑��l �� ���Ȃ��Ƃ���ł� �K�� �s �P ��
�s�� �B ���� ���� �N �q �� �Ƃ� �ł��� �Ƃ��ɁA �� �� �T��
���� �ł���B
���O�i�Ȃ����j ���Ԃ� �� �� �́A ���� �� ���p �ǂ� ��
���킹�Ă��� �̂ł��낤 �� �v���� �B ���� �� �ǂ߂� �u
�_�C�K�C �v �ƂȂ�B ���� �� �u �i�C�K�C �v �́A ���� ��
���� �� �`�����|�� �ǂ� �B
���O��v ��q�w �p�� �B �S �� ���� �� �O�E �́A �{�� ���� �u
�� �v �� ��v���Ă��� �� �ł���A �S �� ���� �� �O�E �� �u
�� �v �� ��v ������悤 �H�v
���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���c��������W���i��w�͋�ߘa���N�����j
�挎�́A�����ƐĉƂ����܂����B�����́A�������g���S���ӂɐi�݂܂��B�u���S���Ӂv�Ƃ������t�͌���ł��Ђ�ς�Ɏg���āA����́w��w�x���R���Ȃ̂ł����A��w�ł́u���S���Ӂv�Ŏ�������Ă��܂��B
�Ўq�́A�u�V���̖{�͍��ɍ݂�A���̖{�͉Ƃɍ݂�A�Ƃ̖{�͐g�ɍ݂�v�Ƃ����܂��B�����ŁA�Ўq�̋����ɉ����ƁA�������߂ĉƂ�Ă��邽�߂ɂ́A�g�����߂邱�Ƃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����ł́u���g�i�C�g�j�v�́A��O�ł���Ίw�Z�ł̕K�{�Ȗڂł����B����ł́u�����v�̎��ƂƖ���ς��Ă��āA�F���ɗ͔��������e�ƂȂ��Ă��܂��B��������O�́u�C�g�v�́A���璺�ꂪ�����ł������悤�ɁA�Y�o���̐��_�ŏ�����Ă��܂����B�ƒ�̓����A�Љ�̓����A���ƂƓV�c�ւ̒������q�������ɋ������Ă��āA���̓��e�͂܂�������w�̐��Ӑ��S���g�������V���̋��`�ɉ��������̂ł���܂����B�������N�̍��́A���m�̋��ȏ���|�ċ��Ȃɗp���Ă����肵�āA�͌Â����̂Ƃ݂Ȃ���Ă��܂����B�������������{�͋�����j�����߁A���R�����^���ɂ�蔽���{����������ɂȂ�����ɒ��ʂ����Ƃ��A����ƌ��@��p�ӂ��邱�Ƃƈ��������ɋ���̍Ď���i�߂܂����B����́A���������ƂƓV�c�Ɉ����邽�߂̕��j�]���ł����B
�����ǂނƂ���ɕt����ꂽ�������ւ̉���́A��q�w�̋�����O��Ƃ��Ă��܂��B�ȑO�̃��W���̐}���A������x�o���܂����B
��q�w�́A���̐��E���u���v�Ɓu�C�v�i�`�C�j�̓�ɕ����܂��B�u�C�v�i�`�C�j�́A�G��Ċ�����邱�Ƃ��ł����̂��̂ł��B�����ƌ��������Ă��悢��������܂��A�����ƃG�l���M�[���܂߂������ƍL�����݂ł��B�����Ȃ�������͂����ƍl������S�_�⍰鮂��A�u�C�v�Ɋ܂܂�܂��B�u���v�͂��̑ΏƂŁA���邱�Ƃ��G��邱�Ƃ��ł��Ȃ����A���̐��E�Ɋm���ɑ��݂��Ă���Ƃ݂Ȃ��A���E�̓����A�F���̐ۗ��Ƃ����ׂ������ł��B����́u�C�v�̔w��ɕK���т���Ă��āA�u�C�v�𐳂����^���ɓ����̑�ȃi�j���m�J�ł��B�u�C�v�Ɓu���v�̊W�́A�n�ƌ�҂̊W���邢�͓d�Ԃƃ��[���̊W�A�����ԂƃJ�[�i�r�̊W�Ƃ����Ă��悢��������܂���B�u���v���Ȃ���A�u�C�v�͐������^�����ł��Ȃ��B���̐��E�������ł���悤�ɁA�l�Ԃ��܂��u���v�ɓ�����Ȃ���ΐ��������݂ɂȂ邱�Ƃ��ł��Ȃ��B����ŁA��q�w�̌����Ƃ��邱�Ƃ��A�������������Ă����Ǝv���܂��B��q�w�́u���v���ߑ�Ȋw�ƌ���I�Ɉ���Ă���_�́A��q�w�́u���v�͓V�̂̉^���A�l�G�̏z�A�����̐��������̖@���݂̂Ȃ炸�A�l�Ԃ̐��`�̌������܂��i���Ă��邱�Ƃł���A�Ȋw�Ɨϗ��w���ꏏ�ɂ��čl����Ƃ���ł��B
�u�g�����߂�v�u�S�𐳂��v�u�ӂ𐽂ɂ��v���Ƃ��A���ւ͎�q�w�p��ʼn�����Ă��܂��B������Ă��邱�Ƃ́A�l���́w���f�x�̋����ł��B��q�̐�B�ł����҂̒������́A�u�S�͐���ԁv�Ƃ������t���c���܂����B���̌��t����q�͒��ɐ�́u���͑������Ȃ�v�̌��t�ƕ��ׂāA�u�^�o�j�ꂸ�v�A�Ԃ��Ă����Ȃ��^���ł���ƌ����܂����B���̌��t�ւ̎�q�̉��߂́A�����ł��B�S�͓�d�̑��݂ł���B��́u���v�Ƃ��Ă̐S�ł���A�V���疜�l�ɓ������^����ꂽ�P�Ȃ鐫�B����͕s���Ő�ΓI�Ȑ��`�ł���A�u���v�ł���B�w���f�x�ł́u���i���イ�j�v�ƌĂ��B�w��w�x�ł́u�����v�ƌĂ��B��́A�u���v�Ƃ��Ă̐S���O�E�Ɛڂ��Ċ��������Ƃ��ɔ��������p�ł���A������u��v�ƌĂԁB�u��v�͑P�Ȃ鐫���������Ĕ����������̂ł��邩��A�P�Ȃ�l���A�P�Ȃ�s�ׂ̂��������ƂȂ�B�������Ȃ���A�����C�{���Ă��Ȃ��ƁA�u��v�͉ߕs�y�Ɋׂ�B�ߕs�y�Ɋׂ�ƁA�u��v�͕s�ύt�s���S�Ȃ��̂ƂȂ�A���̐��̈��l�Ƃ͂�������Ăł���B�܂����̐��̂قƂ�ǂ̐l�Ԃ́u��v�𐧌䂷��C�{�����Ȃ����l�ł���A���~�Ɉ��ݍ��܂�Ă��܂��B�����w�ԎҁA�N�q��ڎw���҂������A�C�{�ɂ��u��v�𐧌䂷��H�v���s���A�����̍l���ƍs�ׂ����ɒ��i�����j�邱�Ƃ�ڎw��������̂��B�w���f�x�́u���v�́A�l�Ԃ̐����s���́u���i���イ�j�v�ɂ���Ƃ����Ӗ��ƁA�O�E�Ɗ��������u��v�𒆂ɒ��i�����j�邱�Ƃ�ڎw���Ƃ����Ӗ��̓�������Ă���B���ꂪ�A�l���w���f�x�̎�q�w�I���߂ł��B�w��w�x�ł͂��̓w�͂����邱�Ƃ��u�����𖾂ɂ���v���Ƃł���Ɖ��߂����B����Ɏ�q�́A�w�_��x�̒��Ő�����Ꟃ��w�Ɏ������u��ɂ��̒�������v�̌��t���A�w���f�x�̋�������葱����Ƃ����`���ł������Ɖ��߂��܂��B��q�w�́A�����̒f�H�C�s�⑦�g�����̂悤�ȉ䂪�g���E���֗~��ے肵�܂��B���������f���O�ꂽ���ʂƂ��ċN����Ƃ݂Ȃ���鎄�~�͓O��I�ɔᔻ����A�S�̒����玄�~��Ǖ�����ƌ����܂��B���ǂ͋֗~�I�ƂȂ�܂����A�֗~�̗��R�͉䂪�g�����̐��E�́u���v�ɏ]�킹�����邽�߂ƂȂ�܂��B
�������āA��w�́u�g�����߂�v�u�S�𐳂��v�u�ӂ𐽂ɂ��v���Ƃ́A��q�w�ł́w���f�x�̉��߂������āA�S�̒����玄�~��Ǖ����āu���v�Ɏ�����]����A���Ȃ킿�䂪�ӂ��u���v�ɂ��āA�N���猾����܂ł��Ȃ�����]��Łu���v�ɏ]���悤�ɂ���B�������āu��v�𒆂ɒ��i�����j��悤�Ɏ���̐S�𐧌䂹��B�������ĐS�𐧌䂵�ĉ䂪�g�̍s���𐳂�������A�Ƃ������ʼn��߂���܂��B���͑O��A�w��w�x�͂����炭�O����ɏ����ꂽ���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����������q�ׂ܂����B�����������Ƃ���ƁA�O����Ɂu�g�����߂�v�u�S�𐳂��v�u�ӂ𐽂ɂ��v�̈Ӗ�����q�w�̂悤�Ɂw���f�x�̋����������Ȃ���N�w�I�ɉ��߂��Ă������Ƃ����A����Ȃ͂��͂Ȃ��B�����Ƒf�p�ɁA�������߂ĉƂ�Ă��邽�߂ɂ͉䂪�g���C�߂�A���̂��߂ɐS�𐳂��ӂ𐽂ɂ��Ȃ����A�ƖЎq�̌��t��������Ċi���I�Ɏg�����̂��Ǝv���܂��B����ł��������Ӗ��͒ʂ�B��q�w�͕����ɑR���đ傫�ȓN�w��W�J���鎞��̋C�^���������̂ŁA�����܂ŕ��G�ȍl�@�ƂȂ��Ă���̂ł��B�����́A���ۂ̔w��ɂ��čl�@���܂��B���ۂ̔w���[���[���T���Ă����ƁA�����ɂ́u���v������B����Ɂu���v�𐬂藧�����Ă�����̂��l����ƁA����̓J���}�A�u�Ɓv�ł���ƁB����͌��邽�߂̃v���Z�X�Ȃ̂ł����A��q�w�͂��̓N�w���炫���ƃq���g�āA�������u�Ɓv���}�C�i�X�ɍl���Đ��E�Ɏ�������ȂƋ����邱�Ƃ��Ђ�����Ԃ��āA�u���v�����̐��̐�ΐM���ł��錴���ł����Ă��ꂾ����ڎw���Ƌ�����悤�ɂȂ����̂��Ǝv���܂��B�v��̒m���l�ɂƂ��đT�����͕K���ʂ铹�ł����āA�����̓N�w�ɒm�炸�m�炸�e���������Ƃ͂������Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B
�������ւ̉���ł́A��̓`�̓��e����������Ă���̂ŁA�����Ō�̓`�Z�͂Ɠ`���͂ɂ��ď����q�ׂĂ����܂��B��q�́A�w��w�x�����ǂ�ł���u�o�v��͂ƁA�u�`�v�\�͂ɕ������܂��B�u�o�v�Ŋȗ��ɏ�����Ă��邱�Ƃ��A�u�`�v�ł͏\�͂ɕ������ďڂ����q�ׂ��Ă���A�ƌ����Ă܂��B���W���ɂ���Ƃ���ł����A�����ł���ƌ����Ă��悢�͂ƁA������Ƃ��������߂���Ǝv����͂�����܂��B�i���v�m�ɓ�����`�͂ɂ��ẮA���Ƃ��������̂��U�킵���̂��A�Ƃ݂Ȃ��āA��`���������낷���Ƃ܂ł��܂����B����Ȓ��ŁA�`�Z�͂Ɠ`���͂́A���ӂƐ��S�̂��Ƃ������Ă���Ƃ݂Ȃ����Ƃ͊ԈႢ�ł͂Ȃ��͂ł��B
�`�Z�͂ł́A�u���l�苏���ĕs�P���ׂ��v�Ƃ����L���Ȍ��t���o�Ă��܂��B���̌��t�́A��������Ďg���Ă��܂��B���݂́A�u���l�Ƀq�}��^����Ƃ낭�Ȃ��Ƃ����Ȃ��i�����珬�l�͂��������Z���������g�����ق����悢�j�v�Ƃ����Ӗ��ŁA���Ȃ舫�ӂ������Ďg���܂��B��������w�̌����ł́A�u�N�q���Ձi�ƁA�ЂƂ�j��T�ށv�̌�ƑƂȂ���̂ł��B�u�苏�v�Ƃ́A�u��l�ł��邱�Ɓv�����ӂł��B�u���l�ł��܂Ƃ��Ȃ��Ƃ����邪�A����͑��l�̖ڂ��C�ɂ��Ă��邩��ł���B�������l����l�ł���Ȃ�A�ނ�͖{���������āA�s�P�C�ōs���B�N�q�͂����ł����Ă͂Ȃ炸�A������l�ł���Ƃ��ɁA�S�̈ӂ𐽂ɂ��đP�ɗ��܂葱����̂ł���v�Ƃ����̂��A�w��w�x�̖{���̈Ӗ��ł��B�l�̖ڂ��C�ɂ��Ĉ����Ȃ����P���s���̂́A�{���̑P�ł͂Ȃ��B����́A�������A�e�ɂ������ȓI�ȍs�ׂł����Ȃ��B�N�q������̂́A���̗��v���Ȃ��Ă��A��l�ŐS��P�ɂ��đP���s���̂ł���ƁB�P���D�ݕs�P�ނ��Ƃ��A�F���D�݈��L�������悤�ɍs���B�S���P���D�ݕs�P�ނ��Ƃ������A�Ǝv���Ƃ���܂Ŏ����Ă����A�Ƃ��������ł��B���x���\���܂����A��q�w�ɂ�����P�Ƃ́u���v�ł��B�u���v�ɏ]�����Ƃ������Ǝv���Ƃ���܂Ŏ����Ă����A�Ƃ����̂��C�{�ł���Ƃ������Ƃł��B
�`���͂́A���S�̏͂ł��B�����ŁA���W���̌��t��������Ă��܂��B�C�J���E�I�\���E�����R�r�E�E���C������ƁA�S���������Ȃ�Ȃ��B�S���݂炴��A����ǂ��������A�����ǂ��������A�H���ǂ����̖���m�炸�B�w�Ԏ҂́A���̂悤�ȋɒ[�Ȋ�����������A�������S��ۂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�ƁB��q�w�́A�w���f�x�̗��_�ƌ��т��āA�u�S�𐳂��v���߂ɏ�𐧌䂷��C�{������A�ƌ����܂��B
�ɓ��m�ւ́A�w��w�x�̂��̂悤�ȋ�����ᔻ���܂��B�m�ւ́u��w�͍E���̈⏑�ɔ�̕��v�́A�ނ��Ǝ��̎咣���n�߂��ŏ����ɁA����̏m�œ��X�ɔ��\���ꂽ���ł���܂����B�w��w�x�Ƃ������́A��q�w�͂������̂��ƁA����ɑΗ�����z���w�ɂ����Ă��ŏd�v�̐��T�Ƃ݂Ȃ���A�E�q�Ўq�̐^�ӂ͂����ɂ���A�Ƃ��ꂼ�����������œǂ܂�Ă������̂ł����B�m�ւ������Łw��w�x�M����ɑ��炸�A�ƕ\���������Ƃ́A��q�w�Ɨz���w�̗����Ɍ���U��グ�����Ƃł���A�ނ��v�z�ƂƂ��Ĉ�{�������邱�Ƃ̎n�܂�̐錾�Ƃ����ׂ����̂ł����B
�m�ւ́u��̕فv�Ō����܂��B�_��̒��ŁA�E�q�͒Q���A����A�������ĉ��Y��Ă���ł͂Ȃ����B�w��w�x�́A���������Ȃƌ����B����������Ƃ͐S�́u�p�v�ł����āA�S����������K�R�I�ɋN������̂ł���B�Ўq�́A�u�m�������ĐS�𑶂��A��������ĐS�𑶂��v�i���K�͋剺�j�ƌ����Ă��邪�A�w��w�x�̂悤�Ɋ����}������A�Ƃ͌����Ă��Ȃ��B����āw��w�x�͍E�q�E�Ўq�̂��Ƃ��킩���Ă��Ȃ��㐢�̎�҂̍�ɂ����Ȃ��A�Ɣᔻ�������̂ł��B
�m�ւ́A���N����Ɂw��w�x��ǂ�Ŋ������A���ꂩ�璷�����ԉƋƂ̏����������ɏ���ǂݑ����A��q�w�̊��߂�C�{�������͂����ɒB������ׂ����A��q�w�Ɨ��ێR�E���z���̊w�Ƃ̑����������ɂȂ��ׂ����A�ɂ��Ďv�����ċꂵ�ޔ����ł������B�O�\�㔼�ɂȂ��āA�悤�₭�m�ւ͎���̌�����`����ׂ��m�����s�x��ɊJ���܂����B�m�ւ̊w�́A�ނ̐��U��ʂ��Ēz���グ��ꂽ���̂ł����B���̌��_�́A�E�q������w����ō��̐��l�ł���B���̌��t��^�����w�_��x���A�ł����Ԃׂ��ō����T�ł���B�����āw�Ўq�x�́A�E�q�̌����𐳂����p�����ĉ�����邱�Ƃ��ł����B��̏��ł���B���́w�_��x�w�Ўq�x�ɑ����āA�E�Ђ́u�����v��ǂݎ�邱�Ƃ��A�㐢�̉�X�̂Ȃ��ׂ��w��Ȃ̂ł���B�w��w�x�ق��̌㐢�̎A���邢�͎�q�w�E�z���w�́A�E�Ђ́u�����v�𐳂����ǂݎ���Ă��Ȃ����䂦�ɕs���S�ł���A����ɑS�ʓI�Ɉˋ�����킯�ɂ͂������A���ꂩ�痣��āw�_��x�w�Ўq�x�̐^�ӂ�ǂݎ��Ȃ�������Ȃ��B���̐m�ւ̊w��͌Êw�A���邢�͌Ë`�w�ƌĂ��悤�ɂȂ�܂����B�m�ւ͎�q�w���l�Ԃ͐l�~�������āu���v�u���v�Ɉˋ�����ׂ��Ɛ������Ƃ�ᔻ���A���퐶���ł̓��s�𗣂�č����ȗ��z�����߂ďC�{���邱�Ƃ́A�E�Ђ́u�����v���痣��Ă���Ɣᔻ���܂����B�������Đm�ւ͎�q�w�������A��q�w�ɔY�݁A��q�w�Ɨz���w�̑����������ɂȂ��ׂ����ɔY�݁A���ɍE�q�ƖЎq�̌�̎���ɐςݏd�Ȃ������w����苎���čE�q�ƖЎq�ɖ߂�ׂ����Ƃ��咣�����̂ł����B����́A��q�w�ł��z���w�ł��Ȃ��A���{��w�̃I���W�i���ȓW�J�̂ЂƂ̂͂��܂�ł����B���̐���̉����h�q�́A�m�ւ̊w�Ɋ������č]�˂���m�ւɌ����Ď莆�������܂����B���ꂪ�m�ւ��a�C���������炩�ǂ��Ȃ̂��A�Ԏ��������ɐm�ւ͖v�����B���ꂪ�h�q�̃v���C�h���������悤�ŁA���ɜh�q�͐m�ւ̊w����ᔻ���āA�E�q�����������������Ƃ͐m�ւ̂悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�͂邩�Ñ�̒����̐��l�̐^�ӂ��㐢�̓����ő����Ă͂����Ȃ��A�Ƃ����Õ����w���n�߂��̂ł����B�h�q�ɂ��ẮA�����̘b�̒��S�ł͂Ȃ��̂ł���ȏ�͂�߂Ă��������Ǝv���܂��B
���{�̎�w�̑傫�ȓ����́A�x�z�҂łȂ����l���w�┭�W�̎���ł��������Ƃł����B�����◛�����N�ł́A��w���w�ԂƂ������Ƃ͉ȋ��̋y���ڎw���Ƃ������Ƃł��B�Љ���w������ׂ��G���[�g�ɂȂ邽�߂ɁA��w���w�B��q�₻�̐�B�̑v���҂����́A�m��v�ƌĂ��X�[�p�[�G���[�g�����ł����B
���������{�ł́A�ɓ��m�ւł������h�q�ł��Γc�~��ł����̉������̐l�X�ł��A�g���͒��l�ł����B��w���ɂ߂��Ƃ���ŁA�喼�͂��납���{��Ɛl�ɂȂ��킯�ł��Ȃ��B���{�̎�w�҂́A�x�z�K�w�̈���ƂȂ�Ƃ����ڕW�Ȃ��ɁA�w����ɂ߂Ė������߂Ɍ��r�����B�����ɁA�����E���͂Ɗw��E���������т����ɂ͂����Ȃ������E���N�ƁA�����E���͂Ɗw��E�������ʁX�̕����Ɍ������ē������Ƃ�����{�Ƃ̈Ⴂ������̂́A�����������ł��傤���B���̓��{�ŁA�{��x�⑺��t���A���c�h��Y�Ȃǂ̕����l�͐��E���Œm���Ĉ�����Ă��閼�O�ł��B���������{�̐����Ƃ́A�N�����ۓI�ɒm���Ă��Ȃ��B�ނ���m����ׂ����l����Ȃ��A�Ƃ����̂����ۓI����ł��B����͓��{�����̓������痈�Ă���̂��낤�A�Ǝv���Ƃ���ł��B
��Ў��`�@���E��{�͍E���̈⏑�ɔ�̙��i�����j
|
�s�ǂ݉����t
��w�ɞH���A�g���C�ނ邱�Ƃ͑��̐S�𐳂��イ����ɍ݂�Ƃ́A�g�i�ނ���j�|懥�i�ӂj���鏊�L��Ƃ��́A�������̐��������Ƃ��B���鏊�L��Ƃ��́A�������̐��������Ƃ��B�D�y���鏊�L��Ƃ��́A�������̐��������Ƃ��B�J�����鏊�L��Ƃ��́A�������̐��������Ƃ��B�v��S�𑶂���̓��́A�|懥�E����E�D�y�E�J�����鏊�����҂��v�Ȃ�͔�����B���ɞH���A����ȂĐS�𐧂��B�Ўq�̞H���A�N�q�͐m���ȂĐS�𑶂��A����ȂĐS�𑶂��A���H���A�m�ɋ���`�ɗR��A��l�̎������B��w�T�������Ȃėv�Ƃ������āA�k�i��������j�ɜ|懥�E����E�D�y�E�J�����鏊�������Ɨ~����́A������B�v�ꍟ�̎l�̎҂́A�S�̗p�Ȃ�B�}���l�A�z�̌`�L��Ƃ��́A�����z�̐S�L��B�z�̐S�L��Ƃ��́A�����|懥�E����E�D�y�E�J���������Ɣ\�킸�B䑁i���₵���j���m���ȂĐS�𑶂��A����ȂĐS�𑶂���Ƃ��́A�������̎l�̎҂́A�����m�E��̒��i����j���ɂ��āA�V���̒B���Ȃ�B���̈��������Ƃ��V��L���B��w�T������V�����炸���āA�k�ɜ|懥�E����E�D�y�E�J��������Ƃ�~���B���ꑦ���E�Ђ̌��������炴�邪�̂Ȃ�B
���H���A�S�݂炴��A����ǂ��������A�����ǂ��������A�H�i����j���ǂ����̖���m�炸�B�����Q���邱�Ɩށi�����Ɓj�����r�i�͂Ȃ́j�����ƈ������B�ҁi���j���E�Ђ̌��������炴��݂̂ɔA�W�i�����j���E�q��M�������āA����Ȃ̊w���ȂĐ��ɍ��i�����j��Ɨ~����҂Ȃ�B��ɞH���A�q�Ăɍ݁i���܁j������i���傤�j���B�O�����̖���m�炸�A���H���A���i�����ǂ��j����ĐH��Y��A���H���A�畣�����B�q�V��L�i�����j���Ĝԁi�ǂ��j���B�]�҂̞H���A�q�Ԃ��B�H���A�Ԃ��邱�ƗL�邩�B�v�i���j�̐l�̔V�i����j�ׁi���߁j�ɜԂ�����āA�N�����߂ɂ���B��i���j����w���ȂĔV���ς�Ƃ��́A�����E�q�������S��Ƃꂸ�ƈ������B�v���w����ҁA�{�i���Ɓj�a�R�ɂ��đR��ɔA���Ӌ`�L���đ��ʂ���ɔB���̊w�{�m�`�̗ǂ��������āA���i���j���đ��̐S�𐧂��Ƃ�~���B�W�����q�̗��̂݁B
���H���A���S�̓A���Ўq�Ɍ�������B�R��ǂ����i�Ȃ��j���i�܂��j�ɔV���c���ׂ��җL��B�Ўq�̞H���A�䖒�l�S�𐳂��イ���A�א��𑧁i��j�߁A?�s�i�Ђ����j�����i�ӂ��j���A����������A�ȂĎO���҂ɏ��i���j���Ƃ�~���B�����i������j�l�S�𐳂��イ���Ƃ����҂́A�֖��̔�S���ւ��āA�V�����Ďא��E�\�s�̐r�����������炵�ނ�������B��w�̈ӂƎ�������قȂ�B�Ўq�̈ӂ̎Ⴋ�A���S�̓A���ɔV�Ɏ{���ׂ����āA�V���ȂɎ{�����炸�B�̂ɕ����l���q�i�����j����A���͐S�𑶂��ƞH���A���͐S��{���ƞH���A�������ĐS�𐳂��ƌ��킸�B���̈ӌ����̂݁B�S�𑶂��Ɖ]���҂́A���̖S�т���Ƃ�~����Ȃ�B�S��{���Ɖ]���҂́A���̒����Ƃ�~����Ȃ�B���i�������j���đ�w�Ȉׁi�����j���炭�A�l�̐S�𐧂���A���Ɋ함�邪�Ⴍ�A���̌`�����E�[���A��肵�ς����炴��ׂ��ƁB����毂ɐS������҂Ȃ���B
|
|
�s�������t
�܂��w��w�x�ɂ́A�u�g���C�ނ邱�Ƃ͑��̐S�𐳂��イ����ɍ݂�Ƃ́A�g�i�ނ���j�|懥�i�ӂj���鏊�L��Ƃ��́A�������̐��������Ƃ��B���鏊�L��Ƃ��́A�������̐��������Ƃ��B�D�y���鏊�L��Ƃ��́A�������̐��������Ƃ��B�J�����鏊�L��Ƃ��́A�������̐��������Ƃ��v�Ƃ���i�`���́j�i��1�j�B�������������u�S�𑶂��v�i��2�j�铹�́A�|懥�i�{�邱�Ɓj�E����i����邱�Ɓj�E�D�y�i�D���Ċy���ނ��Ɓj�E�J���i�J���Y�ނ��Ɓj���邱�Ƃ������ƈȏ�ɏd�v�Ȃ��̂͂Ȃ��A�Ƃ����̂ł��낤���H�w���o�x�ɂ́A�u��������ĐS�𐧂��v�i��虺�V�t�сj�Ƃ����i��3�j�B�w�Ўq�x�ɂ́A�u�N�q�͐m�������ĐS�𑶂��A��������ĐS�𑶂��v�i���K�͋剺�j�Ƃ���A�܂��u�m�ɐS���Z�܂킹�ċ`�ɐS�����点��B��l�i��������j�̂Ȃ����Ƃ́A����ŏ\���ł���v�iᶐS�͋��j�Ƃ���B�Ȃ̂Ɂw��w�x�͂����̂��Ƃ��d�v�Ƃ����ɁA�Ƃɂ����|懥�E����E�D�y�E�J�����Ȃ����Ƃ��������߂�̂́A�ǂ��������Ƃł��낤���B�����������̎l�̂��Ƃ́A���ׂāu�S�̗p�v�i�S�̖{�̂���o����p�j�ł����i��4�j�B���悻�l������́A�l�̌`�����Ă������͐S������B�S���������́A���Ȃ킿�|懥�E����E�D�y�E�J�����Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B�������₵����������m�������ĐS�𑶂��A��������ĐS�𑶂���Ȃ�A�|懥�E����E�D�y�E�J���Ƃ����ǂ��m�E��̔����ł���A�V���̒B���i��5�j�Ƃ����ׂ��ł��낤�B���̈������Ƃ����邾�낤���H�w��w�x�͂܂��������̂��Ƃ������ł��Ă��炸�A�Ƃɂ����|懥�E����E�D�y�E�J�����Ȃ����Ƃ��������߂�̂��B���ꂷ�Ȃ킿�A�E�Ђ̌����𗝉����Ă��Ȃ����䂦�̂��Ƃł���B
�܂��w��w�x�ɂ́u�S�݂炴��A����ǂ��������A�����ǂ��������A�H���ǂ����̖���m�炸�v�Ƃ���i�`���́j�B���ꂱ�������Q���邱�ƍł��͂Ȃ͂������ƌ����ׂ��ł���B���̌��t�����A�����ɍE�Ђ̌����𗝉����Ă��Ȃ������ɂƂǂ܂炸�A�����炭�E�q��M�����ɁA��������ȉ䗬�̊w�������Đ��Ԃɐ������悤�Ɩ]��ł�����̂ł���B�w�_��x�ɂ́A�u�搶�i�E�q�j�́A�Ăɂ���ꂽ�Ƃ���i���傤�B�w�̉��y�j���ꂽ�B���ꂩ��O�J���A�M�����ē��̖�����킩��Ȃ������v�i�q���сj�Ƃ���B�܂��u�i���́j�������āA�H�����Y���l���v�i���сj�Ƃ���B�܂��u�畣�i��6�j�����B�搶�͔ނ̂��߂ɚL�i�����j�̗���s���A�ԁi�ǂ��B�勃���j���Ă��܂����B�]���҂��w�搶�ł��Ԃ����̂ł����I�H�x�ƕ������B�搶�́A�w�ނ����̂��B���̂��߂ɜԂ������āA�N�̂��߂ɜԂ���Ƃ����̂��I�x�ƌ���ꂽ�v�i��i�сj�Ƃ����i��7�j�B�����w��w�x�̌��n���炱���̂��Ƃ�����Ȃ�A���Ȃ킿�E�q���܂����S��Ƃ�Ȃ������Ƃ����ׂ��ł��낤�B�w��w�x���������҂́A�E�q�ւ̗������a�R���������炠�̂悤�ɏ����Ă��܂����킯�ł͂Ȃ��B�܂��A�{���͐^�ӂ������čE�q�̌��t�Ƒ��ʂ���Ӗ����B����Ă���킯�ł��Ȃ��B�ނ��낻�̊w�͂��Ƃ��m�`�̗ǂ��������ɁA�S��͂Â��Ő��䂵�悤�Ɩ]��ł���̂ł���B����́A�v���ɍ��q�i��8�j�̗��V�ł���B
�܂��w��w�x�ɂ���u���S�i�S�𐳂��j�v�i�`���́j�̓́A�w�Ўq�x�ɂ�������B�������Ȃ���A����ɂ��Ă��_����ׂ��_������B�w�Ўq�x�ɂ́A�u�����܂��l�S�𐳂��A�א���łڂ��A������������t��ނ��Ⴍ����ȕ�����˂��A�Z�E�����E�E�q�̎O���l�̓����p�����Ɩ]�ނ̂��v�i�앶���͋剺�j�Ƃ���B�����ł����u�l�S�𐳁v���Ƃ����̂́A���O�̈��S���ւ��āA�͂Ȃ͂������א��Ɩ\�s�������Ƃ��w���B����́w��w�x�́u���S�v�ƑS���Ӗ����قȂ��Ă���B�Ўq�́u���S�v�̈Ӗ��́A���O�ɂ�����{�����̂ł����āA�������g�Ɏ{���ׂ����̂ł͂Ȃ��B������Ўq�͒ʏ�l�ɋ�����Ƃ��ɂ́u�S�𑶂��v�i���̒�2�Q�Ɓj�ƌ������邢�́u�S��{���v�iᶐS�͋剺�j�ƌ����̂ł����āA��x���u�S�𐳂��v�Ƃ͌���Ȃ������B���̈Ӑ}���A�悭������ł��낤�B�u�S�𑶂��v�Ƃ����̂́A�P�Ȃ�S���S�тȂ����Ƃ�~����̂ł���B�u�S��{���v�Ƃ����̂́A�P�Ȃ�S���������邱�Ƃ�~����̂ł���B�Ȃ̂Ɂw��w�x�͂ǂ����l�̐S�𐧌䂷�邱�Ƃ��܂�Ŋ함�邩�̂悤�ɁA�����̋������Ȃ���������͂܂����^�ɒ�߂ĕς��Ȃ����̂ɂł���͂����A�Ǝv���Ă���悤�ł���B����́A�S�Ƃ������̂𗝉����Ă���Ƃ����邾�낤���H
|
�i��1�j�ȉ��́w��w�x�̈��p�́A���ׂāw���{�v�z��n�x�̓ǂ݉����ɏ]���B��{�����́u�g�v���Ɂu���v�Ƒ��肪�Ȃ�t���Ă���B��q�͒��q�̐�������āA�u�g�v�����u�S�v�̌��Ƃ݂Ȃ��B�`���͎Q�ƁB��{�����̑��肪�Ȃ́u�ނ���v�A���邢�́u������v�̗��҂̉\��������B
�i��2�j�w�Ўq�x���K�͋剺�Ɂu�m�������ĐS�𑶂��A��������ĐS�𑶂��v�Ƃ���A�܂�ᶐS�͋��Ɂu�S�𑶂��A����{���v�Ƃ���B�m�ւ́A�w��Ў��`�x�u�S�v�̏͂Łu�S�Ƃ́A�l�̎v���^�p���鏊�A�{�i���Ɓj�M���ɔA���˂����ɔv�ƒ�`����B����͐m�ւ��_��E�Ўq�̌��t�ɂ�����u�S�v���̗p�@���瓱���o������`�ł���B�܂��������u��v�̏͂ɂ����Ắu��v���u���̗~�v�ƒ�`���āA�u�݁i���j���v�����鏊�������ē��������Ƃ��͑����Łi�܂��Ɓj�ɔV����ƈ������A㘁i�킸�j���Ɏv���ɏ�Ƃ��͑����V����ƈ������炸�v�ƌ����B�m�ւɂ��A�l���v�������ē������̂́u�S�v�ł���A�l�̐����v���Ȃ��ɔ��I������̂́u��v�ł���B�m�ւ͖Ўq�́u�S�𑶂��A����{���v�̌��t�������ɂ��āA�u�S�v�i=�l�Ԃ��v�����čs���̈�j�Ɓu���v�i=�l�Ԃ����܂���Ė{���I�Ɏ��̈�j�Ƃ̗��҂͂��ꂼ��ʂɗ{����������A�Ƃ݂Ȃ��B
�i��3�j�㐢�ɓ`����Ă���w���o�x��虺�V�t�т́A�c�O�Ȃ���U�Õ������ɑ�����B����āA�����m�ւ̂悤�ɐ�`����̌Êw�̘_���Ƃ��邱�Ƃ͂��͂�ł��Ȃ��B�m�ւ͋U�Õ��������㐢�̎v�z�ŏ�����Ă��Ă��ɂ����̕��͂Ƃ͌����Ȃ��͂����A�Ƌ^�������A���ꂪ�����ƌ㐢��鰐W��ɝs�����ꂽ���S�ȋU��ł���A�Ƃ�������̒���܂œ��ݍ��ނ܂ł͎���Ȃ������B
�i��4�j�u�S�̗p�v�Ƃ́A��w�͋�`���͂̎�q�������p�������̂ł���B�u�W�����̎l�҂́A�F�S�̗p�ɂ��āA�l�̖����Ҕ\�킴�鏊�̎҂Ȃ�B�v��q�̂��̒��͂�����̗p���ɗ��������̂ł���A�|懥�E����E�D�y�E�J����S�̖{�̂���o��K�R�I�ȍ�p�ł����Ĕ������Ȃ����̂ł��邪�A����͂悩��ʍ�p�ł���̂Ŏ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl����B�`���̗͂p�������Q�ƁB�m�ւ͂����Ŏ�q�̗̑p���ɏ���āA���̏�Ŕᔻ���s���Ă���B
�i��5�j�u�V���̒B���v�Ƃ�����́A�����Ɂw���f�x�i���\�́j��z�N������B�����A�����Őm�ւ��V���̒B���Ƃ����Ă�����e�́A���f�̓��e�Ƃ͊W���Ȃ��B
�i��6�j���i�����j�̂��ƁB�_��ł͎�������Ċ畣�i����j�ŕ\���B�E�q�ň��̒�q�ŁA�_��̒��ōE�q����ؔᔻ�̌��t��^�����ɂЂ�����̂���B��̒�q�ł���B
�i��7�j�L�Ƃ́A�Ñ�̑���ŁA���҂𓉂�Ő����グ�ċ����V��B���̂Ƃ��E�q�͌`�ǂ���̚L��ɂƂǂ܂炸�A�ł��ڂ��|���Ă����畣�����߂����̂��܂�x���O���đ勃�����Ă��܂����A�Ɖ��߂����B
�i��8�j���q�i�������j�́A�w�Ўq�x�̒��ŖЎq�Ƙ_�����铯����ْ̈[�҂Ƃ��ĕ\���B���̎咣�͍��q�͋�ɂ��ΐl�Ԃ̐��͑P�ł��s�P�ł��Ȃ������I�Ȃ��̂ł���A�Ƃ����咣�ł����āA�Ўq�̐��P���ɔ�����B�����Őm�ւ����q�̗��V�Ɣᔻ����̂́A�����N��͋�ɕ\���u����m��v���@�ɂ��Ă̖Ўq�ƍ��q�Ƃ̑�����w���Ă���B�Ўq�͍_�R�̋C��{���Ă���̂ŐS�����t����ɗ����ł����Ԃɂ��邪�A���q�͂����Ɏ���Ȃ��䂦�Ɍ��t�𗝉��ł��Ȃ��Ƃ�������Ƃ��ɂ͂ǂ�����ׂ�����_����A�ƌ����̂ł���B
�۔��F�E�q���i���̎��ɉ��Y�ꂽ�Ȃǁj�l�ԓI�ȑΉ��������A�i�m�ւ́j��w���i�E�q�̂��Ƃ��������Ă��Ȃ��j�Ɣᔻ���Ă���Ƃ̂��Ƃł����A�E�q�ɂ͎������N�q�Ƃ������o�͂Ȃ��B�N�q�ƂȂ肽���l�͂������Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ݂Ă͂ǂ��ł��傤�B
���c�F�_��́A�E�q�̎����ł͂���܂���B�����������E�q������������ɂ���G�s�\�[�h�ɂ��āA��q�̒��ɂ͂����������Ƃ������c���ׂ��ł͂Ȃ��ƍl�����҂�������������܂���B����ł��A�����Ďc���Ă���B�l�ԂȂ̂����犴������͎̂��R�Ȃ��ƂŁA���̂Ƃ��ė�ɏ]���������Ă�����ꂪ�̑�Ȃ̂��A�Ƃ����l���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�۔��F�w��Ŗ��������A�����ł͊w���������ƌ��т��Ƃ̍l�����ŁA���{�ł͐m�ւ�h�q�Ȃǒ��l���w�Ƃ̂��Ƃł����A���{�ł͎��q�����J���ȂǁA���l��������x�N�g�����Ⴄ�����ɓ����Ă��܂��B�w��Ŗ��������ł͂Ȃ��A�l�Ƃ��Ă������������A���w�D�̎q���ɂ��A���q���Ől�Ƃ��Ă̓����L�߂˂Ȃ�Ȃ��Ƃ����悤�Ȃ��ƂƎv���܂��B���{�l�̊i�D�̂悢�������ł͂Ȃ��ł����B
���c�F���{�Ŏ�w���L�܂����͓̂������|����ł��B���y���R����A�x�z�҂̕��m�͂��܂�ɖ��w�őe�\�ł������A�G�g�͑���Œ߂������Ă��āA���ꂪ�������B�鉺�ŕS���������߂܂����ƂƂ���A�G�g�͓{���Ĉꑰ�F�E���ɂ����Ƃ����悤�Șb�����\����ɂ͓`����Ă��܂����B�x�z�҂�����ȗl�q�ł͓V���͎��܂�Ȃ��A�����Ɖ��₩�ɓ������邱�Ƃ����߂Ď�w���L�߂悤�Ƃ����̂��A�������|�ł����B�]�ˎ���ɓ���A�m���ɜ��|�̒�q�̗ё�w�����{�������̎�҂ƂȂ�܂����B����������Ŏ�q�w�����m�ɍL�܂����킯�ł͂Ȃ������B�]�ˎ���̎�w�̕��y�́A�����琷���������̂ł����B���l������グ�A���m�͂��̌�ɑ������B������M�͑��̏��l�ɂ��������̒���|�R�A���䗚�����Ɋw��ł���B�]�ˎ���̌�������N�ԂɂȂ��āA�悤�₭�e�˂̕��m�����͔ˍZ�Ŏ�w���w�Ԃ��Ƃ��K�{�Ƃ����悤�ɂȂ�܂����B���̑O�̌��\����܂ł́A��w�̌����͒��l���哱�������̂ł��B
�۔��F���m�����\�ł���A�痘�x�������n�߂��̂͐��_�C�{�̈�ł������Ƃ����b�������̐搶���畷�������Ƃ�����܂��B
���c�F�퍑�̕��m�́A���͂ɂ��x�z�������ς�Ƃ��Ă����B����͜��|���w��q�w�ł̌N�q�̂Ȃ��ׂ������Ƃ͂������ꂽ���̂ł����B
�۔��F�v�[�`����C�X���G���̏��ƂɁA������������q���B���g�������h����낤�Ƃ���B���݂��c���Ă��܂��B���{�ł͉��ݑ�����Ƃ������ƂɂȂ�Ȃ��A����͍]�ˎ��ォ��̐m�̋����ɂ���Ǝv���܂��B���͔픚���܂������A��w���u���AABCC�i�������Q�����ψ���j�ɓ���܂����B�픚�������Ƃň�w��ڎw�����ƂɂȂ����Ƃ����܂��A�����G�Ƃ��w���Ƃ�ȂǂƎv��Ȃ��͕̂��̍l�������痈�Ă��܂��B���{�l���L�̎~�ߕ�������܂��B�l�I�ɂ͋T���̐l�Œ��t�������u�Ζ�S�w�v���L�߂��Γc�~�₪�D���ł��B
���c�F���{�͊C�Ɉ͂܂��n���ŁA�嗤�̑s��ȎE�C�̗��j���Ȃ������B���{�ł͏��s����ȂǂƒQ�����čς܂��܂����A�嗤�ł͈�Ȃ̐l�����܂邲�Ə��ł���悤�ȎE�����邱�Ƃ��N����A�Q���čς܂��邱�ƂȂǂł��Ȃ��B�����A���V�A�A�����Ƃ������嗤���Ƃ̐푈��ٖ����ɂ�鈳���́A���{�̗��j���o���������Ƃ��Ȃ����̂ł��B����𐅂ɗ����Ƃ����̂́A������Ɠ���̂�������܂���B
�۔��F�؍��������ł��ˁB���݂��c��܂��B
�����F�]�˂̕����l�����͂ƌ��т��Ȃ��Ƃ������Ƃł����A���l�b�T���X�̃C�^���A�������ł��B���l�b�T���X�̕����l�͏��l�ł��B��������܂����悤�ȏ��l�B�L���X�g���ł͏����͐l���x���Ėׂ��Ă���悤�Ȃ��ƂƂȂ�A�q���ɂ͂�点�����Ȃ��B�M���V�A��[�}�̌ÓT���������܂����A���Љ�ɂ͗p���Ȃ����A�d���p�����邱�Ƃ��Ȃ��A�����ƌ��т��Ȃ������l���炿�܂����B
���{�F�]�˂����l�b�T���X���o�ŋƂ�����ł��������Ƃ��ꏏ�B
�����F���[���b�p�ł́A�N���̎�͐��т������Ă����Ȃ��B��w�ł����т̓r�����琔�������������B�T�|�[�g����l�ɗL�\�Ȑl��p����悢�Ƃ����鉤�w������܂��B�����ł͉ȋ��Ńg�b�v�ɂȂ�҂������Ɍg���B�g�b�v�łȂ���ΐ����I�e���͂��Ȃ��B
�۔��F������{�����Ȃ��B
�����F���[���b�p�l�͂����ł͂Ȃ��B���͂ƌ��т��Ȃ��B���l�b�T���X�̎Љ�Ǝ��Ă���B
�۔��F���[���b�p�̕����A�����╗��������ł���ˁB�]�˂̒��l�̕����╗�����L���ɂȂ�̂������BNHK�̃X�y�V�����V���[�Y�u��]�˂̐��E�v���ƂĂ��ʔ��������B
�����F�m���ɖʔ����ԑg�ł����BNHK���h���́u�����������v�̂����̕�����w�҂ł����B
�۔��F���͒N�ɂ��ւ��ĂȂ�������Ζ�S�w�̐Γc�~�₪�D���ł��A���s�̏��Ƃł͂��������`��������č�����w�������Ă���Ƃ��낪����܂��B
���{�F�Γc�~��͉����̐l�ł����B
�۔��F�T���̐l�ł��B���t�������̏��l�B�N�ɂ�����Ղ������܂����i���l�͉������Y�����A���蔃�������ŘJ�������ė��v��ƕ̎�����Ă����B�������A���E�Ƃ������������Ƃ肢��A���l�ɂƂ��Ă̗������A���m�̕�\�Ɠ����悤�ɐ����Ȃ��̂Ƃ����j�B
���c�F�������͑��̒��l�ɂ��n�݂��ꂽ�w�⏊�Œ���|�R�E�����Z��A�x�i����E�R��崓��Ȃǂ�y�o�����B���̉e���͂͑傫���A������M�̊����̉��v�ɉe����^�����B��M�͏����s�̋��t�ɁA��₩���҂������Ă��܂��B���̒��ɂ́A�������̖剺��������Ă��܂����B
�����F�j�g�̎�w�D���́A���ꂳ���i�j���@�G�剜�ʼnƌ��̖ڂɗ��܂�A�j�g���Y�j�̉e�����ȁB���ꂳ��͋��s�̐����̖��B
���c�F�h�q�͖���g�ۂɎd�����̂ł����A�j�g���^���Ă��܂��B��������{�̒鉤�ł���ƁB
�����F�u���ޗ���݂̗߁v�͕]���������̂ł����A�����̎Љ�ł́A���l���쌴���ɕ��u����Ă��܂����B���͍̂����ł���A�Α�����ɂ͐d�̔�p�������Ăł����A�����������ƂɂȂ��Ă���A���u�����y�ɖ��߂Ă��Ȃ����Ƃ�����̂ł��������i�̂Ďq��a�l�A����ҁA�����̕ی��ړI�Ƃ������́j�B
���{�F�d�̉ł͔R����Ȃ��B
�����F�M���V�A�ł������ł͉Α����ł����A���l�̉Α��ɕ֏悷��҂��������B
���c�F�j�g�̋ߔN�̕]���́A����܂ł̕��f�̐������v���ĕ�������������Ƃ������̂ł��B�O�̎���܂ł́A�����̗���R�䐳��̗��Ȃǂ�����A���{���܂��Ր�Ԑ��ł������B�������j�g�̕��j�́A���Ƃ��������w��ŕ����𐄐i����Ƃ������̂ł����B
�����F���R���͊����č����������A�o�ϓI�����������߂��鎞��ƂȂ�A���̐S�̌��Ԃ��悭������̂Ƃ��ē������ꂽ�̂ł��傤�B
�۔��F�����Ɂu�����v�Ƃ������t�͖��������Ɖ]���Ă܂��ˁB
�����F�����̃I�����_�l���炷������Ȃǂ��Ă��Ȃ��B
�۔��F4�ɊJ����Ă����B
�����F�I�����_�A�����A�������N�A�����Ƃ͌��Ղ��s���Ă����B�u�����v�Ƃ������t�͖����ɗ��w�҂����{�Ɋւ��鏑�̃I�����_��ł�|�鎞�Ɂu�����_�v�Ƃ������Ƃɂ��܂��i���\2�N�`4�N�؍݂����h�C�c�l��t�̃A�W�A�ɂ��Ă̑̌n�I�Ȓ��q�̓��{�Ɋւ��镔���Ɂu���{���ɂ����Ď����l�̏o���A�O���l�̓������ւ��A�������̐��E�����Ƃ̌�ʂ��֎~����ɂ���߂ē��R�Ȃ闝�v�Ƃ���^�C�g���̉ӏ�������A����𗖊w�҂ł���u�}���Y���u�����_�v�ƒZ�k���Ė�o�������Ƃɂ��B1801�N�̂��Ɓj�B
��c�F���l���苏����Ɩ{�����o�ĕs�P���Ȃ��Ƃ��邪�A��q�I�ɂ͖{�����ł�ΑP���Ȃ��̂ł��肱�̂܂܂ł͂悭�Ȃ��B
���c�F���ɂ͖{�R�̐��ƋC���̐�������A���̏ꍇ�͋C���̐����w���B
��c�F�u�g�i������j�|懥�i�ӂj�v�Őg���u������v�Ɠǂ܂��Ă��邪�g�̂������قǂ̌������S�̏�Ԃ��w���̂ł��낤���A�u�S�݂炴��v�͐S�������Ă����ۂ�^����B�u�S�����̏�Ԃł͎��Ă������v�A�u�S������ׂ���ԁ�����S���łȂ���Ύ��Ă������v�Ǝv����B
���c�F����͓`���̂Ƃ���Ō������܂��傤�B
2025�N8��9���i�y�j��w�͋�
�{���́A�Z�c����A���{����A�۔�����A���c����A��c����̌ܐl
���c��������W���i�o-07�j�A���W���i��w\�ߘa���N��������T�v�j
�u�`�͂�����youtube�@
|
�ԑ厚�F��L��w�т̌���
�Ώ����F��q�̒�
���厚�F��q�̏������낵��
���厚�F�������ւ̉��
|
|
���̈ӂ𐽂ɂ��܂��~����҂́A��Ñ��̒m��v�i�����j���B
�v�́A�����ɂނ�Ȃ�B�m�́A�P�i�ȁj�����̂��Ƃ��Ȃ�B��̒m���𐄂��ɂ߂āA���̒m�鏊ᶁi�j�������閳����~����Ȃ�B
|
�m�́A�S�̒m�����������ˊo�Ȃ�|�i�Ƃ���j�Ȃ�B�m���́A���Ɨ��ɂ����āA���炸�Ɖ]���ƂȂ��B����ǂ��w�тĂ���𖾂ɂ�����A���̒m�Ђ炯���B�v���Ƃ́A�����łɒm�鏊���A���܂��m�炴��������v���āA�킪�m���̑S�[�i�����j�����͂߁A�V���̗��ɂ����āA�m��������Ɖ]���ƁA�Ȃ��炵�ނ���]�B�W�i�������j�ӔO�̂��܂��܂��ƂȂ炴��́A���P����m�邱�ƁA���܂����������Ȃ�ʌ̂Ȃ�A�ӂ𐽂ɂ���Ƃ���ɂ́A�K�܂Ñ��̒m�����͂߂����Ȃ�B��w�̔����ڂɋߐڂ��錾�t�́A�w�Ўq�x�̒��Ɍ����܂��B�������w�Ўq�x�̒��ł́A���ɂ́u�����v�ł���A�ƂȂ��Ă��܂��B
|
�m��v�����Ƃ͕��i���Ɓj�Ɋi�i�����j��ɍ݂�B
�i�́A����Ȃ�B���́A�P�����̂��Ƃ��Ȃ�B�����̗��������i���イ���j���āA���̋ɂނ�|�i�Ƃ���j���炴�閳����~����Ȃ�B���̔��҂́A��{�̞��ځi���傤�����j�Ȃ�B
|
���Ƃ́A叓�i���Ɓj�Ɖ]���@���B叓�ƂȂ��ĉ]���́A���͂��̂Â��瑴�̒��ɂ���B��叓���i���Ԃj�̗��������ĉ]�Ȃ�B����Ɋi��Ƃ́A�����Ƃ̓������̂��̐��e�\���i�������ւ���j�́A���͂܂�鏊����B���ɂ��āA�������͂ނ�ҁA���Ƃ��Ƃ����̋Ɂi���͂܁j���|�ɁA���͂߂����邱�Ƃ��]�B�W���ɂ��闝�ƁA�S�ɒm�闝�ƁA���ƈ�Ȃ�B�S�̒m���́A���̗������͂ނ�ɂ��ĂЂ炯�A���̓����́A�S�̂��Âʂ�ɂ��Ă���͂�B���̌̂ɁA�킪�m��v�����Ƃ́A���̗������͂ނ�ɂ���B����ǂ��m��v�����Ƃ́A�m���̑S�[���͂������A���͂߂������ƂȂ�B���Ɋi��́A�ЂƂтƂɂ��͂߂āA���̌����ނ��ƂȂ�B�������͂ނ邱�ƁA�����ɂ������ЂāA�m�̂Ă炷���ƁA���悢��Ђ낵�B
���e�\���F��q�w�p��B�����ׂ̍����Ƃ��납���Â��݂ȂƂ���܂ŁA������Ƃ��납��w��ɉB��Ă���Ƃ���܂ŁB��q�w�͐l�Ԃ̑P���͖{���I�ɂ��̐��E�̗������ׂė����ł��闝��������Ă���Ƃ݂Ȃ��B�������̑P����s�����Đ��e�\��������߂邱�Ƃ͑�ϓ���A���ꂪ�ł����̂͗��j��ł��E�q�ق��̐��l�������炢�ł���B����ł��w�Ԑl�͐��l��ڎw���Ċi���v�m�𑱂��A���̐��E�̗������ߑ����Ȃ�����Ȃ��B��q�͖Ўq�́u���l�w��Ŏ���ׂ��v�̗���ɗ����A���l�͉����̑n�n�ҁ������̐v�҂����̓����ł���Ƃ�����������Ȃ��i�����h�q�͌�҂̗�������j�B
�ȏ�̔����A��w�̓��̞��ځi���傤����/���傤�ڂ��j�Ƃ��B�̞��킩��A�Ԃ̖ڂ̂܂��܂��Ȃ邪�@���Ȃ�Ȃ�B���ׂČ��ҁi�݂����j��A���Ɋi��A�m��v���́A�S���ȂāA���������͂ނ邱�ƂȂ�B�ӂ𐽁i�܂����j��ɂ��A�S�𐳂����A�g������́A�g���ȂāA�����ɑ́i�����j����̂��ƂȂ�B�Ƃ�ꎁi�ƂƂ́j�ցA�������߁A�V���i�����炩�j�ɂ���́A���͂��Ȃč����𐄂��Ђ�ނ�̂��ƂȂ�B���͞��̌���p����A�܂��Ƃɑ����ł��݂���ׂ��炸�B�����ނƍ��Ƃ��A�Ƃ荇���ĂȂ���ɂ��A��Ȃ�͕K�i���Ȃ炸�j��ɂ��A��Ȃ�͕K��ɂ��B����ɂ������ЂāA��߂������ނ邱�Ƃ́A�p�Đ��ɂ����͂炸�A�K��߂̌�����āA�㎟��߂�����ɂ͂��炴��Ȃ�B
���̌��F�����ڂ̍H�v�B�������E�V���E�~���P�̎O�j�̂�B�����邽�߂ɁA�i���E�v�m�E���ӁE���S�E���g�E�ĉƁE�����E���V���̔����ڂ��C�{����A���̏C�{�̂����B
����ɂ����ЂāA�ȉ��F�i���v�m���ł���ł��邱�Ƃ�O���ɒu���Ȃ�������Ȃ����A�i���v�m����������܂����g���ĉƂ������Ɉ����������Ă��ċ��������̂ł͂Ȃ��B�����ڂ͑S�Ă��K�v�Ȃ̂ł��邩��A��ɂ���Ԏu���Ȃ�������Ȃ��B
|
���i���Ɓj�i�i�����j��Ď��i�������j���č@�i�̂��j�ɒm����B�m����Ď����č@�ɈӐ��i�܂��Ɓj����B�Ӑ��ɂ��Ď����č@�ɐS�����B�S���������Ď����č@�ɐg���i�����j�܂�B�g���܂�Ď����č@�ɉ�ꎁi�ƂƂ́j�ӁB��ꎂقĎ����č@�ɚ��i���Ɂj���܂�B�����܂�Ď����č@�ɓV�����i������j���Ȃ�B
���͋��߁i���傹���j�A��i�̂��j�����i����j�ɕ��i�Ȃ�j���B
���i�i�����j��Ƃ́A���̗��i��j�̋ɂ܂�|�i�Ƃ���j�ɂ��ē��炴�閳���Ȃ�B�m����Ƃ́A�Ⴊ�S�̒m�鏊�Aᶁi�j�������閳���Ȃ�B�m?�i���Łj��ᶂ����A�����ӓ��ě��i���j�ɂ��i�ׁj���B��?�ɛ��Ȃ�A�����S���Đ����������B�g���܂邱�Ƃ��ȏ�́A�����𖾁i������j���ɂ���̎��Ȃ�B��ꎂ��邱�Ƃ��ȉ��́A����V�i���炽�j�ɂ���̎��Ȃ�B���i��m����A���~�܂鏊��m��B�Ӑ��Ȃ邱�ƈȉ��́A�����F�~�܂鏊��̏��Ȃ�B
|
|
�V�q�i�Ăj���i��j��Ȃď��l�i���傶��j�Ɏ���܂ŁA�㐥�i�����j�ɊF�Ȑg�����ނ���ȂĖ{��ਁi�ȁj���B
�㐥�́A��Ȃ�B�S������������ȏ�́A�F�g�����ނ鏊�ȁi�䂦��j�Ȃ�B��ꎂ����Ƃ��ȉ��́A�������i����j�𝨁i���j���ĔV�i�����j�ɍ��i���j���̂݁B
|
�u�`
����́A����ڂ̍Ō�A�i���v�m�ł��B�i���v�m�̒����v�z�j�ɂ�����c�_�ł́A�K����q�̉��߂Ɖ��z���̉��߂̈Ⴂ���o�Ă��܂��B��q�́u���Ɋi�i�����j��v�Ɖ��߂���B���ĉ��z���́u�����i�i�����j���v�Ɖ��߂���B�u�i�v�̎��̈Ӗ��Ƃ��ẮA�×����痼������܂��B���̈Ӗ��̎����̈Ⴂ����A��q�w�Ɨz���w�͑�Q���J����킯�ł��B��q�́A�O�E���悭�����ŗ������āA�����ł���u���v�Ɋi�i�����j��A�ƌ����B�����ۂ����z���́A�S�̒��ɂ͂��łɁu���v�������āu�ǒm�v������̂�����A������ĊO�E���u�i�i�����j�v���A�ƌ����B��q�̕����ł����A�l�Ԃ͂������������āu���v�̂���ǂ�����l���Ȃ����A�ƂȂ�B���z���̕����ł����A�S���Ђ����珃���ɂ��āA���̐��̑P�������Ĉ���@����A�ƂȂ�B���́u�i�v�̎��̉��߂͎v�z�j�I�ɂ���قǏd�v�Ȃ̂ł����A�����͂���ȏ゠�܂�[���肵�Ȃ����Ƃɂ��܂��B
�w��w�x�́A���Ɓw��L�x�̈�тł����B���̓����w��L�x�̒��ɁA�w�L�т�����܂��B�w��w�x�̒��ł́A�i���v�m�̐�������Ȃ��B�����Ŏo���тƂ����ׂ��w�L�т�ǂ�ł݂�ƁA�ǂ�������Ă��邩�B�i���v�m�Ƃ����p��͎g���Ă��܂���B�����ɏ�����Ă���w�т̃J���L�������́A���W���̂Ƃ���ƂȂ��Ă��܂��B�Ђ��傤�ɂ킩��₷���B���̂悤�ɏ�����Ă���A�i���v�m���w���Ƃ���͉��ł��邩���A�悭�C���[�W�ł��܂��B�������Ȃ���A���̃J���L�������Ŋw�Ԏ҂́A�V�q����̎q��ł���̂��낤���B�w��w�x�ł́A���̌�ɓV�q���珎�l�Ɏ���܂ŁA�g���C�ނ��{�Ȃ��A�Ƃ���܂��B�V�q���g���C�߂āA�Ƃ�Ă��A�������߂�̂͂킩��B�������i���v�m���w�L�т̂��Ƃ��c�_�ƒT���̊w�тł���Ƃ���Ȃ�A����͓V�q����̉��ɏA�������̋���Ȃ̂ł͂Ȃ����B�������ǂ����������藈�܂���B�w��w�x�͋���̈�ʘ_�Ƃ��Ċi���v�m��u���������Ȃ̂��낤���B������w��w�x�ɂ͊i���v�m�̋�̓I�ȓ��e����؏����Ă��Ȃ��̂��낤���B�����͎�q���^��Ɏv���Ƃ��낾�����̂ł��傤�B�w��w����x�ŁA�z��ⓚ�������Ă��܂��B�V�q����łȂ��҂��������V�����l����K�v�͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�_��ɂ��A���̈ʂɂ��炴����̐���d�炸�A�Ƃ���B��q�̓����́A�N�q�͂ǂ�ȋ����ɂ����Ă��V�q��w�ƂȂ�����w�̖��Ƃ���p�ӂ������Ȃ�������Ȃ��A�Ƃ������̂ł����B���̎�q�̌����́A�V�q����̉��ɂ���m��v�̐S���Ƃ����ׂ����̂ł��B�m��v���i���v�m�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����̂͂킩��܂��B��q�͂���ɉ����āA�m��v������̏�ɓV�����Ƃ̑傫�Ȃ��Ƃ܂ōl���Ă����A�ƌ����킯�ł��B���Ȃ�J��������̍l���ł���Ǝv���܂����A���ꂪ�w��w�x�������ꂽ�Ñ�̊����ɂ����Ă͂܂�̂��ǂ����A������Ƃ킩��܂���B�܂��Ă�V�q���i���v�m�̒T�����s���ē�������A�Ƃ����C���[�W���킫�ɂ����Ƃ���ł��B�Ñ�̒����v�z�ł́A�N�傪�q�b�������Đb���̎d���Ɍ��o������͈̂Ë��̏ł���A�Ƃ݂Ȃ���܂����B����͐b����M�p���Ă��Ȃ��Ƃ����؋��ł���A�����ЂƂ�ō����^�c�ł���Ƃ����v�����������S�̂�����ł���B�������ČN��̕s�M�����ɉ��ɓ`�d���Ă����āA����j�ł�������ƂƂȂ�Ƃ������̂ł��B�N��͐M�p�ł���l�Ԃ�M�C���āA�������܂�����̂��d���ł���B�M�p�ł���l�Ԃ�I�Ԗڂ����̂͊i���v�m��������܂��A�w�L�тɕ\������Ă���w�тƂ͂�����ƈႤ�̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���Ƃ���ł��B
�w�L�тɏ�����Ă���J���L�������́A䤎q�̋���v�z�Ƃ悭�Ή����Ă��܂��B�i���v�m���d�����邱�ƁA�o�T�̈ËL����n�܂��Ď��Ẳ��p�ɐi�ނ��ƁA�t�ɂ��Ċw�Ԃ��Ƃ��d�v�ł��邱�ƁB䤎q�ƈقȂ�_�́A�w�L�тł͊w�ԓ��e���u��v�ł���Ƃ͖��L����Ă��Ȃ��Ƃ���ł��B䤎q�ł́A�w�K�̊�b���牞�p�܂ŁA�u��v�̊w�K�ł���Ə�����Ă��܂��B䤎q�̂��Ƃ���Ǝv�z�ɓ����I�ȓ_�́A������d������Ƃ���ł��B�������A���̏��q�S�Ƃɂ͂Ȃ��Ď�Ǝv�z�ɂ͂������Ƃ���ł��B
��A�@�Ǝv�z�Ɖ��V���@�l���̊w�҂ɂ�钆���v�z�̊v�V
�����́A����Ɏ�Ǝv�z�������������j�̗���ɂ��āA���̎v�z�̕������݂ƂƂ��ɘb�������Ǝv���܂��B���W���̐}�͐퍑�������̎v�z�E�̉e���̗���ł��B�͍m��I�Ɍp���A���F�͈ꕔ�ᔻ�E�ꕔ�p���A�Ԃ͔ᔻ�ł��B���������ォ�牺�Ɍ����Ă��A���ԓI����ł��B�}�̉E�E�����E���͂������������̒n���I�z�u�ɑ������Ă��܂��B���̃y�[�W�ɎO�̉~��`���Ă����܂������A�E���^����n�܂����v�z�A�����O��A鰁E��E����n�܂����v�z�A�����Ē����������̎v�z�E�̒��S�ł������Ă̎v�z�ŁA���̐Ăő^�ƎO��̎v�z�Ƃ��Z�����Ē����v�z�ɐV�������ꂪ�N����܂����B���̓����o�ꂵ���v�z���A�����܂����B��́A�@�Ǝv�z�B������́A���V���B�܂��͉��V�̏p�Ƃ��Ă�A�㐢�̌����ł͉��V�v�z�Ƃ��Ă�܂��B���̓�̎v�z�́A�ĂŔ��W���܂����B
�퍑����̐Ă̓s�ɂ́A�l���̊w�҂ƌĂ��w�ҏW�c�������e�n����W�܂��Ă��܂����B�Ўq�͏����̊w�҂̈�l�ł���A䤎q�͌���̑�\�I�Ȋw�҂ł����B�l���̊w�҂́A����܂ł̖Ўq�E�n�Ƃ̎v�z�����z����V���������v�z�̍\�z�Ɏ��g�݂܂����B�Ўq��n�Ƃ́A�m�`�̌N�傪�P�Ȃ閽�߂��o���ΓV���͎��܂�A�Ƃ����f�p�ȍl���ɂƂǂ܂��Ă����B�������Ȃ���A�����ł��낤���B�����������炷���߂ɂ́A�����I�ȍ��ƃV�X�e����v���āA������u�@�v�Ƃ��Č��z���A�N��̌l�I�Ȗ��߂��z���đS�Ă̍������ʂɋK�����邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����B�T���͑�\�I�l���̊w�҂̂ЂƂ�ł����A���̊w�h�̒��ł���w�T�q�x�́A���݈ꕔ�����c���Ă��܂���B���̈핶�ɂ́A�@�x�͌��t�i�͂���j�Ǝڐ��i���̂����j�̂悤�Ȃ��̂ł���A�l������ɕς��邱�Ƃ������Ȃ����̂ł���A�Ə�����Ă��܂��i�u���t����҂́A�y�d���Ȃċ\���ׂ��炸�B�ڐ�����҂́A���Z���Ȃč��i�����j���ׂ��炸�B�@�x����҂́A���U���ȂĂ���ׂ��炸�v�j�B�㐢�ؔ�q���@�Ǝv�z�̑�\�Ƃ݂Ȃ����悤�ɂȂ�܂������A���ƐĂł͂��܂����@�Ǝv�z�́A�ؔ�q�̂悤�Ȑꐧ�N��ɕ�d����Z�p�ł͂Ȃ��A�q�ϓI�Ō����Ȑ������s���Z�p�Ƃ��Č������͂��܂������̂ł���܂����B
�Ƃ���Łw�T�q�x�͊����|���u�Ŗ@�ƂɊ܂܂�Ă���̂ł����A�j�L�ł��l���̊w�҂ł���T���E�ڎq�E�c�w�E���́u�݂ȉ��V�����̏p���w�сA�����Ɉ���Ă��̎w�ӂ������v�Ə����Ă���܂��i�Ўq䤋���`�j�B�i�n�J�́A�ނ�͉��V�����̏p�A�܂肳���قǐĂ̐V�����v�z�Ƃ��Ė@�Ǝv�z�ƕ���ł����ЂƂ������ƌ������A���V�����w��ł�������Ǝ��̘_��W�J�����A�ƕ��ނ��Ă���B���V���Ƃ́A�w�V�q�x����W�J���ꂽ�v�z�ł��B�l���̊w�҂��ǂ����āw�V�q�x�Ɗ֘A������̂��B
1990�N��A�����Łu�s�X�^�ȁv�����@����܂����B�s�X�^�Ȃ͐퍑����̑^�̕悩��o�y���������ł���A������������ɏ]�����������퍑�����A�Ўq���������Ă������̕����ł��B���̒��ɁA�w�V�q�x�̈ꕔ���������ꂽ�B����ǂ���s�X�^�Ȃ��퍑�����̂��̂ł���Ȃ�A�Ўq�̎���Ɂw�V�q�x�Ƃ����{�͏��Ȃ��Ƃ����̏����̕Ҏ[���n�܂����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�������Ўq�́w�V�q�x�Ƃ����{���A�����œW�J����Ă���v�z�ɂ��Ă��A�S�����y���Ă��܂���B�����ۂ��Ўq���Ă�����������l���̊w�҂̌������ʂɂ́A���炩�Ɂw�V�q�x�̎v�z�ƃN���X�I�[�o�[����l����������Ă���B����ŁA�㐢�̎i�n�J���猩��A�T���E�ڎq�E�c�w�E�������݂͂ȉ��V���̌����҂̔��e�ɓ���Ƃ݂Ȃ����ƍl�����܂��i���T��w���V���̐����ƓW�J�x176�y�[�W�j�B�w�V�q�x�̂ǂ��ɁA����ȉe���͂��������̂��B
�w�V�q�x�̎v�z�́A�^����n�܂�܂����B�V�q�Ƃ����v�z�Ƃ̗����́A�`���̖��̌������ł͂����肵�����Ƃ͂킩��܂���B�E�q���V�q�ɉ���Ęb���A��̌�Łu���͗��������B���͉��������Ԃ����Ƃ��ł��Ȃ������v�ƌ������A�Ƃ����b�́w���q�x�Ɍ����܂��B����͂܂������Ȃ��A���q�w�h�̐�`���ł��B�V�q�Ƃ����v�z�Ƃ͐퍑����̐l�ŁA�j�L�ɏ�����Ă������Ƃ��čE�q�̎��������N��i�I���O�O�܁Z�N�j�̋L�^�Ɍ�����l�����V�q�ł���A�Ƃ����L�q�����Ȃ���ۂɋ߂��̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���܂��i�V�q�ؔ��`�j�B�V�q�Ƃ����v�z�Ƃ������Łw�V�q�x�Ƃ����������������̂��ǂ����͂킩��܂��A��w�̎҂�����ɒlj����Č��s�̃e�L�X�g�ɕҎ[����Ă������͂��ł��B�i���T�ꋳ���͕����`�Y���̐����p�����āA�w���q�x�Ɍ�����V�q�̒�q�֛̊��i����j�́A�l���̊w�҂̈�l�ł�����i����j�̂��Ƃł���Ƃ�����������B���A182�y�[�W��4�B�j
�Ƃ������w�V�q�x�ɓW�J�����v�z�́A�퍑���㒆������ȍ~�A�Ă��l���̊w�҂̎v�z�̕ω��ƕ��s���Ē����v�z�ɐV�����v�f���������݂܂����B�w�V�q�x�́A�����v�z�j�ł͂��߂Č`����w��W�J���������ł����B�w�V�q�x�́A�u���v���V�n�����̎�Ɏ҂ł���ƌ����B�u���v�Ƃ������̂́A�V�n�����ɂ��܂Ȃ��s���킽���Ă��镁�ՓI�����ł���A�l�Ԃ����O������ȑO�ɑ��݂��A�ŗL�̉^�����s�����̂ł���B�א��҂́A�m�`�Ƃ����l�Ԃ����t�����T�O�������Đ������s���̂łȂ��A�������ՓI�����I�ȁu���v�Ɉˋ����Đ������s��Ȃ���A�K�����s����B�����ƌ����A�u���v�Ƃ������t�͖��O��t���邱�Ƃ��{���s�\�Ȃ��̂����t�Ő������Ȃ�������Ȃ��̂ʼn��Ɂu���v�ƌ����Ă��邾���ł���A�����m�邽�߂ɂ͐m�`�E��E�@�ȂǂƂ�������̓I�p�������ʂ̓��@���K�v�ł���B
�w��₽�ΗJ���S�����B�B�i���j���d�i���j�ƁA�����邱�Ɗi�������j���B���ƈ��ƁA�����邱�Ɖ���i������j�B
�i�s�X�V�q���Ȃ��B���s�w�V�q�x�㊪�ɂ���B�j
���́w�V�q�x�̍l���́A���ۂ̔w��ɕ��ՓI�ȑ��݂��B��Ă��āA�N��͂���@���Ȃ�������Ȃ��Ƃ����l���ŁA�`����w���̂��̂ł����B�l���̊w�҂̌������w�V�q�x�Ɛڋ߂���n�_�́A���҂����ՓI�Ȍ����Ƃ��āu���v�����Ƃ���ł����B����͒����v�z�̐V�����W�J�ł����B�����v�z�́A�^����u���v�̌`����w���L����A�O��ƌĂꂽ鰁E��E����u�@�p�v�̓����_���L����A���̗��҂��Ăł��ݍ������B���́A�����ŐĂ̂��Ƃ���̓`���ł������E�q�ȗ��`�����铹���N�w�A����ъǒ��E��d���d�������x���̓����p�����o�ώv�z�Ƃ��Z���������ʂ��A�l���̊w�ł������ƍl�������Ǝv���܂��B�����l���̊w�̐��ʂ̈���@�Ǝv�z�A����������V���ł����B
�w�ǎq�x�́A�t�H����̈̑�Ȑ����Ɗǒ��̏��ł���ƌÂ�����݂Ȃ���Ă��܂����B�������Ȃ���A���Ƃ������ǒ��̎��ゲ�납��̓`�������̒��Ɋ܂܂�Ă���Ƃ��Ă��A���̑啔���͌㐢�ɒlj����ꂽ���̂ł���Ɛ��肳��܂��B�w�ǎq�x�i?�q�j�Ƃ������́A�����|���u�ł͓��Ƃɕ��ނ���Ă��܂��B����@���o�Ўu�ł́A�w�ǎq�x�͖@�Ƃɕ��ނ�������Ă��܂��B���Ȃ킿�w�ǎq�x�Ƃ������ɂ͖@�ƓI�v�f�Ɠ��ƓI�v�f���Ƃ��ɑ��݂��Ă���B����Ɍ�ŏq�ׂ锭�@�����́w����l�o�x�̒��ɂ́A�w�ǎq�x�Ɨގ�����\�����������邱�Ƃ��킩�����B����ŁA�w�ǎq�x�w����l�o�x����сw�T�q�x�͂Ƃ��ɐ퍑���㒆�����l���̊w�҂̌�������b�ƂȂ��Ă��āA�w�V�q�x�̌��s�łƂƂ��ɂ��̎���̌����̐��ʂł��낤�Ƃ����������ł��o����Ă��܂��iMasayuki
Sato �gThe Confucian Quest for Order:The Origin and
Formation of the Political Thought of Xun Zi�h,
p70�j�B
�����̏��ɂ����ẮA�u�N��͓��ɏ]���A�@�𐧒肷��v�ׂ����Ƃ�������Ă��܂��B�w�ǎq�x�w�T�q�x�w����l�o�x�ɂ�����邻�̈����A���W���ɔ������Ă����܂����B�����Ɂu�@�v�̕K�v���q�ׂ�̂ł͂Ȃ��āA�u�@�v�̐���҂ł���N��͏�ʂ́u���v�ɏ]���Ă�����������������A�Ƃ����v�z�ł��B�������l���̊w�ł͘V�q�́u���v�̌`����w�Ɓu�@�v�̎v�z���������A�u�N��͓��ɏ]���A�@�𐧒肷��v�Ƃ����������ł��o���ꂽ���Ƃ��ǂݎ��܂��B�N��͕��ՓI�Ȍ����ł���u���v���悭���@���A������u�@�v�ɐ��肵�āA�q�ϓI�������ɓ�������B�����̑P�ɂȂ�s�ׂ͕K�����A�����̈��ɂȂ�s�ׂ͕K���������A���������ꂪ�N��̋C�܂���ȑP�ӂ�ʂ��������ʍP��I�ɍs���邱�ƁB���ꂪ�A�l���̊w�ł̖@�Ǝv�z�̐����ł����B
1980�N�ゲ����O�̌Ñ㒆���v�z�j�ł́A�w�T�q�x�Ɂw�ǎq�x�A���ꂩ��w�ؔ�q�x�̉�V�тȂǂœ��Ǝv�z�Ɩ@�Ǝv�z�̗����̖ʂ������āA���̓�̎v�z�������ɂȂ����Ă���̂��A���̋c�_���s���邱�ƂȂ��A�P�Ɂu���ƂƖ@�ƁA���ꂩ�玞�Ɏ�Ƃ̎v�z��ܒ����������̘_�v�Ƃ������ɂ݂Ȃ���Ă��܂����B����́A�����R������V�����̓��Ǝv�z�Ɩ@�̌������K�p������ؔ�q���̖@�Ǝv�z�Ƃ̊Ԃɂǂ��ɂ��A�ւ����o���Â炩��������ł��B�������Ȃ���n���͊���̔��@�A����Ɋs�X�^�Ȃ̔��@�ɂ���āA�l���̊w�҂����͌����ɂ���Ă͓��Ǝv�z�ɂ������Ė@�Ǝv�z�ɂ������邪�A���̂ǂ���Ƃ�����������ʂȎv�z�W�����Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����l������o����n�߂��̂ł��i���J���w��`�ɂ�����@�v�z�̓W�J�x�ł́A������u���@�v�z�v�ƌĂ�ł���j�B
�������N�傪�u���v�ɏ]�����߂ɂ́A���������ǂ��������H���s���悢�̂��B���̖��͖@�Ǝv�z�̍ő�̎�_�ŁA�v�z�Ƃ����̊Ԃł��イ�Ԃ�ɐ����I�Ȍ������o���ꂽ�Ƃ͂����������B���m�ŗގ��̎v�z�Ƃ��ẮA�u���R�@�v������ƍl���܂��B�u���R�@�v�̎v�z�́A�Ñ�M���V���Ŏn�܂����B
�M���V���l�́A����@�ipositive
laws�j�̂��܂�ɂ����l�Ȃ̂ɑł���āA���`�Ƃ������Ƃ���������̂́A����Ǝ���ƂƂ��ɕς���Ă䂭���R�̂Ƃ肫�߂ɂ����Ȃ��̂��A����Ƃ����̎G�R�Ƃ������l���̔w�i�ɂ́A���ƎׁA���`�ƕs���`(right
and wrong, justice and
injustice)�Ɋւ���i�v�I�ϔO�����݂�����̂ł��邩�ǂ������A���Ƃ���悤�ɂȂ����B�\�t�B�X�g����^�w�h�͑��̌������Ƃ����̂ɔ����āA�\�N���e�X�A�v���g���A�A���X�g�e���X�̎���ȍ~�̊ϔO�_�I�N�w�҂͑��̗�����咣�����B�ނ�́A�ڂ�ς���Ă䂭����@�K�͂ɑΗ�������̂Ƃ��āA�l�̐S�̂Ȃ��ɐ����������Ă���s���̖@(unwritten
law)�A��X�̖����ɂ��肩����������鋤�ʂ̖@(a
common
law)�A�����I���ݎ҂ł���l�Ԃ������Ȃ�Ƃ���ɂ����Ă��F�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ����R�@(a
law of
nature)�Ƃ������̂�������̂ł����āA�N�Z�m�t�H���́u�\�N���e�X�̎v���o�v�̂����ɂ́A�v�w�A�e�q�Ƃ������Ƒ��I�W���A���̂悤�ɂ��肩�������肩����������鎩�R�@�I�K�͂̋�̓I����Ƃ��Ĉ��p����Ă���̂��݂邱�Ƃ��ł���B
�iP.G.���B�m�O���h�t�w�@�ɂ�����펯�x���͎��R�@�A��g���ɂ��B�p��͈��p�҂��p�ꌴ������lj��j
�u���R�@�v�̓M���V���v�z���烍�[�}�@�w�A�����_�w�Ɍp������āA����ɋߑ�Љ�v�z�Ɏ���܂ő����̘_�҂����Ƃ̖@�́u���R�@�v�Ɉ���̂����`�ł���A�Ƙ_���܂����B�������̐S�́u���R�@�v�Ƃ͉����A�ɂ��Ę_�҂̊Ԃňӌ�����v���܂���B����̖@�w�ł́A�u���R�@�v�Ƃ͎��ゲ�ƂɃ������ՓI�i���I�ł���Ƒz�肳���A���ゲ�Ƃɒ�Ă����ۑ�ł���A�q�ϓI�B��I�ȁu���R�@�v�͑��݂��Ȃ��A�Ƃ����������ł������Ȃ��̂ł���Ƃ�����ł��傤�i���B�m�O���h�t�A���́j�B
�Ñ㒆���v�z�ɂ����Ă��A�u���v�Ȃ鎩�R�@�ɂ����ɑ����āu�@�v�𐧒肷��悢�̂��A�ɂ��āA����͏o���Ȃ������B����v�z�ł͎Љ�Œʗp���Ă��銵�K�@�𐬕��@�ɒ�߂�ׂ��ł���ƌ������i�w�T�q�x�j�A�܂�����v�z�ł͌N�傪���Â̐S��ۂ��Đ���ς���菜���A�u���v�ɏ]���q�b�Ɏ���̂ł���ƌ����i�w�ǎq�x�S�p�я�ق��j�B�܂�����v�z�ł́A�����������炷���������ł���u��v�Ɍ����I�Ȏ��R�@�̋ߎ��������߂悤�Ƃ���B
��Ȃ�҂͖@�̑啪�i�����Ԃ�j�Ȃ�B�i�w䤎q�x���w�сj
�@�͗���o�āA��͎����o�ÁB����͓��Ȃ�B�i�w�ǎq�x�����сj
�����ɁA�ؔ�q�������ꂽ�B�ؔ�q�́u�@�v�̋Z�p���������o���A�N�傪�u���v�ɏ]���ׂ��Ƃ��������ʂ���艺�����B�N�傪�u�@�v�𐧒肷��Z�p�𑀂�A����̈ӎv��b���ɗ͂ŋ��������镐��������Ƃ��ł���B�ؔ�q�̓o��ɂ���āA�ȍ~�̖@�Ǝv�z�͐ꐧ�N�傪���͂��s�g����Z�p���M�Ԏv�z�ɕς���Ă��܂��܂����B�������ؔ�q�̖@�Ǝv�z�͖@�p�v�z�ƌĂԂׂ����̂ł���A�ĂœW�J����Ă������Ƃ��Ƃ̖@�Ǝv�z�Ƃ͎��Ĕ�Ȃ���̂ł���܂����B
�w�V�q�x�́u���v���l���̊w�Ō����������́A���Ȃ킿���V���ł����B���V���́A�j�L�⊿���ɂ����Ċ��㏉���ɗ��s�����Ə�����Ă�����̂́A���̐��̂͋ߔN�܂ł悭�킩��܂���ł����B������1970�N��n���͊���̔��@���������B�������犿�㏉���́w�V�q�x���Q�Z�b�g�o�y���܂����B���̂P�Z�b�g�́w�V�q�x�̑O�ɂ́A�ЂƂȂ��ŏ�����Ă����V�����̃e�L�X�g������܂����i�n���͘V�q���{���O�ØÏ��j�B���̃e�L�X�g��ǂނƁA�������҂ɂȂ��炦�����ł���A���ꂪ�w�V�q�x�ƃZ�b�g�ƂȂ������̂����V���Ȃ̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������肪�s��ꂽ�B�e�L�X�g�̉�͂��i��ł���ƁA����́w�V�q�x�Ɠ����u���v�v�z�ɑ�������̐����_�ł������B�V�����̃e�L�X�g�������ւ̉��p�ł���A�w�V�q�x�����̗��t���ƂȂ�N�w�Ƃ����W�ł��B���݁A���̏��́w�����x�|���u�Ɍ����邪�U�킵�Ă��܂����w����l�o�x�ł��낤�Ɛ��肳��Ă��āA����������������Ă��܂��B�w����l�o�x�Ɓw�V�q�x�̓Ɉˋ������̂ʼn��V���ł���A�ƌ��������ł��B���܂������ɏ]���A���̏����w����l�o�x�ƌĂт܂��B
�������V�����̘_����Ƃ���ɂ��A���́w����l�o�x���l���w�h���w�V�q�x�Ƒ��݂ɉe���������W�ɐi�߂������̐��ʂ����Ȃ�x������ɂ܂Ƃ߂����ł��낤�A�Ƃ������̂ł��B���R�́A�w����o�x�Ƃ������������V���A���V�̏p�Ƃ����v�z�����A�퍑����̌������鏑���Ɍ������A����ɂȂ��Ďg���邱�ƂɂȂ�������ł��iSato,
pp70-71�j�B�w����l�o�x�̓��e�́A�l���̊w�̐��ʂł���w�ǎq�x�w�T�q�x�Ǝv�z�I�E�p��I�ɋ��ʂ���_�����������o����Ă��܂��B�������A��ŏq�ׂ�悤�ɁA���̎v�z������̐����ƁE�����ɉ��p���ꂽ���ʍs��ꂽ�����́A�@�Ǝv�z�̂���Ƃ̓j���A���X���قȂ������̂ł���܂����B���́w����l�o�x�̉�͂�ʂ��āA���㏉����?�h������̎v�z�ł��������V���̋�̓I�ȓ��e���𖾂��錤�������W�����̂ł����B
�w����l�o�x�̎v�z�́A�w�T�q�x�w�ǎq�x�Ƃ������l���̊w�҂̌����̐��ʂƁA���ʂ���_�����������܂��B�N��̖�ڂƂ��āA�����ȁu�@�v�𗧂ĂĒ������鐭�����s�����Ƃ���������܂��B�����I�Ȏv�z�́A�V�n�l�́u���v�ɑ���O��I�ɏ�������������s���ׂ��Ɛ������Ƃł��B�N��͓V�n�́u���v�ɏ]���āA���̉A�z�̏����ɉ������͈͂Ŕ_���A�ېł��s��Ȃ�������Ȃ��B�����ČN��͐l�́u���v�ɏ]���Č����Ȗ@�𗧂āA���̏�ɉ������͈͂Ő������s���悤�C���g��Ȃ�������Ȃ��A�Ɛ����Ƃ���ł��B���̓N�w�I���t���Ɂw�V�q�x���u����āA�V�q�̖��ׂ̐���������Ƃ��錴������A�V�n�l�̎��R�ȗ���ɋt��킸���������������s�����Ƃ����肵�������������炷�A�Ɛ����Ƃ���ł��B
�w����l�o�x�ɏ��������e�͐��{�ȂǕK�v�Ȃ��Ƃ����A�i�[�L�Y���ł͂Ȃ��A������������O�ȗ��@�Ɠ������s���A�ƌ����Ă��邾���̂��̂ł��B�ؔ�q�̖@�Ǝv�z���A�l�ԂƂ͗��ȐS���������Ȃ������ł���ƒ�`�Â��āA�N��̗��@�͕K�����̐l��ɋt�炤���̂ł���Ɛ����p���Ƃ́A�����̂��̂ł��B��Ǝv�z�́A�����~�ς�����Ƃ���ł́w����l�o�x�Ƃ͈�v���Ă��܂��B��Ǝv�z�ɕt��������Ă�����̂́A�l�̏�ɗ��ׂ��͓����̍����N�q�łȂ�������Ȃ��A�Ƃ����������𗦐悵�ċ����w�����ׂ��ł���Ƃ����������ڂ̎v�z�ł��B�w����l�o�x�́A�ނ���N��ɓV�n���R�Ɩ��́u���v�ɏ������ċt����Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ǝ��������߂�Ƃ��낪����Ă���ƌ�����ł��傤�B�w����l�o�x�́A�@�Ǝv�z���Ǝv�z�̂悤�ɑI�ꂽ�l������ȐӔC���Đ��������Ȃ�������Ȃ��A�Ƃ����C�����͑S�������܂���B�ނ��됭��������҂͏펯���o�ɏ]���A���R�̏����ɏ]���A���̖]�܂Ȃ��ł�J���͍s�킸�A���̖{�S���t�Ȃł���悤�Ȑ��������Ă͂Ȃ�Ȃ��A�ƌ����ɗ��܂���̂ł��B�������A��������s���邱�Ƃ����͓���Ƃ����̂��A�����v�z����䂦��Ȃ̂ł��傤�B
�w����l�o�x�Ɍ����鉩�V���̎v�z�́A�ꌩ����Ɛ��m�v�z�ł̃A�_���E�X�~�X��n�C�G�N�̎��R��`�v�z�ɁA���Ȃ�ڋ߂��Ă���Ƃ��낪����܂��B���������҂̎v�z�I�����ɂ́A���m�ȈႢ������܂��B���V���́A�V�n�l�́u���v�ւ̈،h�����{�v�z�ł���Ƃ���ŁA���m�̎��R��`�v�z�͎s���̎��R�Ȋ����͂ւ̐M�������{�v�z�ł���Ƃ���ł��B�܂����m�̎��R��`�v�z�A�Ƃ�킯�n�C�G�N�̎v�z�ɂ͍��ƌ��͂̒m�b�ɑ���O��I�ȕs�M������܂����A���V���ł͌N��͗��@�҂Ƃ��Ă̖��m�Ȗ���������A�����V�n�l�́u���v�����߂鎞���������Ƃ��ɂ͉ʊ��ɐ�������s���A���ꂪ�ς�Ăѐ��Â̎p���ɖ߂鍂�x�ȏ���f�͂Ǝ����S�����߂��܂��B
�۔��F�l�����l�͂ǂ������Ӗ��ł����B
���c�F�l���͐Ă̓s�̗�淄�̊w�ҊX�̒n���ł��B�i�s���l��̉��ɂ������B�j
��c�F���̎n�c���@�l�Ɖ]���A�l�͍����̂��ƂŁA�@�l�͍����_�B
���c�F�l���̊w��70�N���炢�����Ă���A�Ўq����䤎q�܂ł̎���̊w�ҊX�ł����B
�۔��F�o�g�n�̈قȂ�l�X���e�n����W�����Ƃ������Ƃł����B
���c�F�Ўq��羂̏o�g�A䤎q����̏o�g�ł��B
�۔��F�Ă̌N�傪�Ăъw�ҊX��������Ƃ������Ƃł����B�i�Ă̈Љ��̍��A��淄�̐����l��̉��Ɋw�������āA�w�҂ɓ@���^���ċc�_���������B�Ўq�͐��\��̎ԁA���S�l�̒�q�Ő����A�ꖜ�߁u50��د�ق̍����v���x�����ꂽ�B�Ўq�͖{���Ȃ�10���ߎx������ׂ��Ƃ����j
���c�F�l���Ɋw�҂��W�߂��ĉ��͍E�q�̎���̐ĉ��̌n���̉��ł͂Ȃ��A������Ő������������c���̌n���ʼn������قȂ�܂��B���͂Ő�����D�悵�����Ƃ�����A�`���I�Ȑ��������Ȃ����Ƃ�����A�w�҂��W�߂Đ����������`�Ԃɂ��ċc�_�������A�퍑����̎v�z��ϊv�������B���q���l���̊w�̉e�����邱�ƂɂȂ�܂����B
|
���ۂ͌N��B���̑��͎G���Ȑb���A���B�}1�ł͌N�傪�b���A���ƎG�R�ƑΛ������[�����Ȃ��l�B�}2�͌N��𒆐S�Ƀ��[����~������ԁB�}3�̓��[���̖������߁A�K�ޓK���ɐl���z�u���s������ԁB�l���̊w�͐}3�̋c�_�B
|
�}1

|
�}2
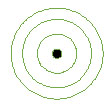
|
�}3
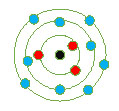
|
�Z�c�F���̉~�͉��ŁA�ǂ����Ă��̉~���g�����̂��B���̐������K�v�B
���c�F������Ղ��Ǝv��������ŁA���S�͖k�ɐ��̃C���[�W�ł��B�E�q���k�C�Ƃ��Đ������������B�V�̐��͖k�ɐ��𒆐S�Ƃ��Ē����������^��������B�V�ɂ͓V�̒���������A�n�ɂ͒n�̒���������l�̎Љ�ɂ͎Љ�̒���������A���̂��Ƃɂ��Љ���肷��B���S�ɌN�傪����A���߂⊯���▯�̃��[�����߁A���[���Ԃɏ��i�A�~�i������V�X�e���̃C���[�W�ł��B
|
��c�F�i�n�J�̓V�����ł͓V�̒����͐����Ɍ����Ă���Ƃ��A�V��͖k�l�����Ŏw���������đS�̂��^�p���Ă���Ƃ���B���̎��ł�����i�{���͎����Ŏ���͊���̊w�҂��^�C�g����ύX�������́j�ł͊����͓V���i�����j�A�n���i�i�k�j�A�~���i�i��j�A�t���i�@���j�A�Ċ��i�i�n�j�A�H���i�i���j�ƓV�̒�����n��Ɏ�������Ƃ����v�l������A�Ñ㒆���̓`���I�Ȃ��́B
�Z�c�F�����̂Ƃ���̐����������Ă���Ǝ�|���`���Ȃ��B
�۔��F�O�������܂��Ă���Ƃ������Ƃ́A���݂����������Ƃ������ƂɂȂ�܂��ˁB
|
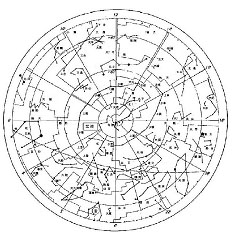
tenmonzu.jpg
�@�V�����̓V���}�͍��n�ɔ��i��p)
|
���c�F������邱�Ƃ�����܂����A��������Ώ��i���A�߂�������~�i���܂��B�N��͒����ɓ������A�@�����Ă�B���Ў�`�̍��ł͌N�傪�@�����肵�A�ォ�牺�ւƍ~�낵��������B�����`�̍������Ƃ������@�����߂�_�ł͓��l�ŁA�������c�m���I��č���Ŗ@�����Ƃ����_���قȂ邾���ł��B�����ł͐`�̎n�c�邩��2246�N�Ԍ��Ў�`�̃X�^�C���ł��B�����A��p�ł͑�c�m���@������Ă��āA���̗��j�ł���܂łȂ��������Ƃ�����Ă��܂��B�@�Ǝv�z�Ƃ����Ε��ʒN���v�������ׂ܂����B
��c�F�ؔ�q�Ƃ������Ƃł��ˁB
���c�F�ؔ�q�͖@�Ƃ̑�\�̂悤�ɂ݂Ȃ���܂����A�ؔ�q�̊w�͐ꐧ�N��ɕ�d����Z�p�ł����āA�@�p�v�z�Ƃ����@�Ǝv�z�̓���Ȉ��ƌĂԂׂ����̂ł��B����́A�l���ŋc�_���ꂽ�@�Ǝv�z�Ƃ͑S���قȂ�܂��B�w�ǎq�x�́A�l���̊w�̖@�Ǝv�z�������Ă���B�����̊��w�҂̈��䑧���́A�ǎq�̎v�z���疋�ˑ̐����z���铝���_�����o�����Ƃ��Ē��߂�������B
��c�F�ǎq���ǒ����炭��̂ł���A�@�����邱�ƂȂ���炪�D�悳��܂��B
���c�F���Ƃ�����d������Ă��āA��Ɩ@�̕��p�Ƃ����ׂ����̂ł��B�w�ǎq�x�̑啔���͊ǒ��̎���̏��Ƃ͂������A�l���̊w�ɂ��Ҏ[���ꂽ���̂ł��B
�۔��F�ؔ�q�ɂ��ẮA�����ł���Ƃ��������܂��B�e���Â��āA���҂ɂ���A�߂𒅂���ꎩ�E�ɒǂ����܂ꂽ�̂ł͂Ȃ������ł����B
���c�F�j�L�̘b�͂ǂ��܂Ŏ������킩�肩�˂�Ƃ��낪����܂��B䤎q�Ɗؔ�q�́A�݂��ɔF���������Ă����̂����₵���Ƃ��낪����B�j�L�̌����ʂ�ؔ�q��䤎q�̒�q�ł������Ƃ�����A�ؔ�q�̒���̒���䤎q���S���o�Ă��Ȃ��̂͂ǂ����Ăł��邩�B
�۔��F���������Ă���Ƃ������Ƃł����B
���c�F�j�L�ł͍��H�Ɨ��M���݂��̏邩��l�荇�������Ƃ�������Ă��܂����A��̊Ԃ͑傫������Ă��āA����Ȃ��Ƃ������͂�������܂���B�������̂ق����ʔ�������r�F�����̂ł��傤�B
��c�F����l�o�̎l�o�Ƃ͂ǂ������o�ł����B
���c�F�w�o�@�A�o�A�́A�����x�̎l�тł��B�ǂ����ĉ��邩�Ƃ����A���̒��ʼn��邪�o�ށi���䂤�j�Ɛ�����Ƃ��̌��t��������Ă��邩��ł��B����ŁA���̐V�����̏��͉���l�o�ł��낤�Ƃ�������������Ă��܂��B
��c�F����̂ǂ̉��̎��ɉ���l�o���݂������̂ł����B�n���Ƃ͒N�ł����B
���c�F�����̔n���͊���ŁA���n�l���n���̕�ƌ����`�����Ă������̂ŁA���ۂ̖����҂͑O���̒����������ƍȂł����B�����́A�O���鍑�ŗB�ꐶ���c�������ƈȊO�̏��ł��B1970�N��ɔ��@����A��i���ʁj�ɏ����ꂽ�e�L�X�g�������ǍD�ȏ�ԂŌ��������B�w�V�q�x�̊��S�ȃe�L�X�g����ʑ��݂��āA���̈�ʂ̑O�Ɍ��݉���l�o�Ɩڂ���Ă���e�L�X�g���u����Ă����B����l�o�́A�V�q�̐����N�w�Ɋ�Â��ċ�̓I�ȓ����_���W�J����Ă���Ƃ����W�ł������B����ŁA���e���s���ł������O���̉��V�v�z�Ƃ́A����l�o�ƘV�q�Ɋ�Â��������_�ł��낤�Ƃ��������L�͂ƂȂ����B�V�q��q�͐l���N�w�̂悤�ɂ݂Ȃ���Ă��܂����A�����ǂ܂��悤�ɂȂ����͕̂�����k������ƂȂ���鰐W�ォ��̂��ƂŁA�퍑����ł͐����N�w�ł����B
�۔��F���͘V�q���D���ŁA�̂̓Ǐ���̎��A���c���V�q�͐����I�Ȃ��̂Ɖ]���ċ��������Ƃ�z���o���܂��B
���c�F����l�o�͘V�q�N�w�œW�J����Ă��āA�N��͌N��͖@�𗧂Ăē�������̂ł��邪�A������������悤�Ȗ@�͂悭�Ȃ��B���R�Ɩ��̐l��ɏ]���A���ɋt�炤���ƂȂ��A�T�d�ɐ����������Ȃ��Ȃ����Ƃ������̂ł��B
��c�F�ՂƊ֘A������܂����B
���c�F���ڂ̊W�͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�۔��F�s�X�^�ȂƂ́B
���c�F1990�N��ɌΖk�ȂŔ�������܂����B�퍑����̑^�̕�Œ|�Ȃ��o�y�����B���̒n���`�ɐ�̂����O�̕�ł���Ƃ��������L�͂ŁA�����ł���Ζ������ꂽ�e�L�X�g�͂�����������퍑���㒆���A�Ўq�̍��̃e�L�X�g�ł��낤�Ɛ��������B�w�V�q�x��1/3�Ă��ǂ���������o�y�����B�����̘V�q�̃e�L�X�g�ŁA�V�q�̎v�z���^����n�܂����̂͂�肩�����������B�V�q�̎v�z���l���̊w�҂ɒm��ꂽ���ƂŁA�u���v�̋c�_������ɂȂ�܂����B�O���̉��V���́A���ŁA�@���ɂ�����A�ΊO�푈�i�Ι��z�j�������Ƃ������e�ŁA���ł����������R�Ȍo�ς��D���ł������ĐŎ����������܂����B�����n�x�̍��͑傫���Ȃ����B����l�o���������ꂽ���ƂŁA���̎���̎v�z�I�w�i�����炩�ɂȂ����킯�ł��B���̌�̕���̎��ɂ́A�����ɒ�����������p���A�Ŏ����̍�����X�ł��o�����B����S��ꔄ���A����ȐŎ����������B����͑ΊO�푈�̂��߂̍������K�v����������ł����B����̑剓���ɂ��A�鍑�̍��y�͑傫���g�債�܂����B�������A����Ȑ��x�o�ɂ������j�]�������܂����B
��c�F�i�n�J�̉ݐB��`�ɑ����݂���l�X�̂��Ƃ��L����Ă��܂��B
���c�F�i�n�J�́A���R���C���D��ł��܂����B��Ǝv�z�Ɖ��V���̐ܒ��I�v�z�������Ă����悤�ł��B
�i���v�m�A���A�@�̌ꌹ
�i��c�j
2025�N9��6���i�y�j��w�͋�
�{���́A���䂳��A���{����A�۔�����A���c����A��c����̌ܐl
���c��������W���i�o-08�j�A�j
�u�`�͂�����youtube�@
|
�ԑ厚�F��L��w�т̌���
�Ώ����F��q�̒�
���厚�F��q�̏������낵��
���厚�F�������ւ̉��
|
|
���i���Ɓj�i�i�����j��Ď��i�������j���č@�i�̂��j�ɒm����B�m����Ď����č@�ɈӐ��i�܂��Ɓj����B�Ӑ��ɂ��Ď����č@�ɐS�����B�S���������Ď����č@�ɐg���i�����j�܂�B�g���܂�Ď����č@�ɉ�ꎁi�ƂƂ́j�ӁB��ꎂقĎ����č@�ɚ��i���Ɂj���܂�B�����܂�Ď����č@�ɓV�����i������j���Ȃ�B
���͋��߁i���傹���j�A��i�̂��j�����i����j�ɕ��i�Ȃ�j���B
���i�i�����j��Ƃ́A���̗��i��j�̋ɂ܂�|�i�Ƃ���j�ɂ��ē��炴�閳���Ȃ�B�m����Ƃ́A�Ⴊ�S�̒m�鏊�Aᶁi�j�������閳���Ȃ�B�m���i���Łj��ᶂ����A�����ӓ��ě��i�܂��Ɓj�ɂ��i�ׁj���B�ӊ��ɛ��Ȃ�A�����S���Đ����������B�g���܂邱�Ƃ��ȏ�́A�����𖾁i������j���ɂ���̎��Ȃ�B��ꎂ��邱�Ƃ��ȉ��́A����V�i���炽�j�ɂ���̎��Ȃ�B���i��m����A�����~�܂鏊��m��B�Ӑ��Ȃ邱�ƈȉ��́A�����F�~�܂鏊��̏��Ȃ�B
|
���̈�i�́A�㕶�𐄂����ւ��āA�{�����̂��ŁA�K�i���Ȃ炸�j�݂���ׂ��炴�邱�Ƃ��A�˂�ɂƂ���B���i��Ƃ́A���̗��̋�
�܂�鏈�ɁA���͂߂����炸�Ɖ]���ƂȂ����B�m����Ƃ́A�킪�m��v������āA�����鏊�������Ɖ]���ƂȂ����B�V�����Ȃ�Ƃ́A�l����
�\�͂Ă��܂ŁA�l�����̂��̕��ۂ̂˂����āA���܂˂����ςȂ邱�Ƃ��]�B�傲�Ƃ̎��i�������j���č@�i�̂��j�̎��́A��i�X�̐�̎�
�̋`������͂��B�]�ӂ́A�����̔@���ɂ��܂��~����҂́A��Â����̔@���ɂ���Ɖ]�́A�K�����̔@������Ď����Č�ɂ悭�����̔@������
���ƂȂ�B�E��Ղ̞��ڂ̐��A���̍H�v���Ȃĉ]���́A���Ɋi��A�m��v���A�ӂ𐽂ɂ��A�S�𐳂����A�g������́A�����𖾂ɂ���̂���
�Ȃ�B�Ƃ�ꎁi�ƂƂ́j�ցA�������߁A�V���i�����炩�j�ɂ���́A����V�ɂ���̂��ƂȂ�B���������Ȃĉ]���́A���i��A�m����́A��
�𖾂ɂ��A����V�ɂ��邪�A���̎��P�Ɏ~�܂邱�Ƃ�m��Ȃ�B�Ӑ�����A�S�������A�g����́A���𖾂ɂ��邪�A���P�Ɏ~�邱�Ƃ�Ȃ�B��ꎂق�A�����܂�A�V�����Ȃ�́A����V�ɂ��邪�A���P�Ɏ~�邱�Ƃ�Ȃ�B
�V�����Ȃ�Ƃ́A�l�����\�͂Ă��܂ŁA�l�����̂��̕��ۂ̂˂����āA���܂˂����ςȂ邱�Ƃ��]�B�F�w��w�x�̓`�\�͂��u���V���v�ɓ�����Ɖ��߂���邪�A�����ŏ�
����Ă��邱�Ƃ͖��̐��������肳����o�ϐ���ł���B���������q�́w��w�x�̕��V���̈Ӗ��͎����̍ŏI�I�Ȉ���A�̈Ӗ��ł���Ɖ��߂���B���Ȃ킿�w��w�x��
�͓V���������ł���B�����ۂ��w���f�x�ł́A�����͐l�Ԃ��z���ēV�n���R�����ɋy�сA�З߂͒����O�̔ؑ��ɂ܂ŋy�Ԃׂ����Ƃ���������Ă���B
|
�V�q�i�Ăj���i��j��Ȃď��l�i���傶��j�Ɏ���܂ŁA�㐥�i�����j�ɊF�Ȑg�����ނ���ȂĖ{��ਁi�ȁj���B
�㐥�́A��Ȃ�B�S������������ȏ�́A�F�g�����ނ鏊�ȁi�䂦��j�Ȃ�B��ꎂ����Ƃ��ȉ��́A�������i����j�𝨁i���j���ĔV�i�����j�ɍ��i���j���̂݁B
|
����艺�O�i�́A��̞��ڂ̋`�����ԁB�V�q��菎�l�܂łƉ]�́A��ɓV���ɂ���܂ł��A��w�̋K�͂Ƃ��āA�Ƃ���������ɂ��āA�����ɖ������̔@���]�ЂāA��w�̓��㉺�ɒʂ��邱�Ƃ�������B�㐥�Ƃ́A��i�������j�̋`�Ȃ�B�i�v�Ӑ��͊F�g���������叓�i���Ɓj�Aꎎ������A���F�ƚ��V���̐l�����āA�e�i���̂��́j���̐g�����߂��ނ�ɂ������A���̌̂ɁA�g�����ނ���ȂĖ{�Ƃ���Ȃ�B�W�ю�̖������V�����łɖ{�������ȂĂ�������ԁB���ɖ��V�̞��ڂ����łāA�����ɖ����̖{�̂��鏊�������A����p��ȗv��������B����ǂ������g�̓A�i�v���������āA������ȂĖ{�Ƃ��鎞�́A�����Ƃ���҂́Aꎎ�����?�Ȃ�B�R��Ώ�̌���ɁA��������{�Ƃ��A�V���Ƃ���`�ƕL��i�Ђ����Ⴄ�j��r�i�����Áj�ɋA����Ȃ�B
�K�́F��q�w�p��B�킭���݁A���i�B
|
���̖{���i�݂��j��Ė��i�����j���܂�҂͔ہi����j���B
�{�́A�g�����i���j���Ȃ�B
|
���̖{�̎��́A�㕶�������ė���ǂ��A����͑��g�̈ꎚ�ɂ�����āA�{����Ɖ]�́A�g�����܂�ʂȂ�B������Ƃ́A��ꎂق荑���܂�V�������炩�Ȃ邱�Ƃ��]�B�ۂƂ́A�����Ȃ��Ƃ��B
|
���̌������鏊�̎Ҕ������āA���̔������鏊�̎Ҍ������ƁA���i���܁j���V�i����j�L�炸�B
�{�́A�g�����i���j���Ȃ�B�������鏊�́A�Ƃ������Ȃ�B���̙_�߁i��傤���j�́A�㕶�i���傤�Ԃ�j�_�߂̈ӂ����ԁB
|
�������鏊�Ƃ́A�Ƃ������B�������鏊�́A���V���Ȃ�B����ǂ����V�������������ׂ�������āA�����]�ɂ��炸�B�����Ƃɛ����āA�������ȂĂ��Ђ킭��݂̂Ȃ�B�]�ӂ́A�܂Ñ��̉Ƃ�ꎂւ���A���ꂷ�łɉƂɔ����B�R��ɋp�č������ߓV���ɂ��āA������������ƁA���܂������߂����炴��ƂȂ�B����̖����܂���ɂ��āA�����̐��̂��ł��邱�Ƃ������B����ɂ��Đ����͂���A���ƓV���̉��߂ɂ������̂��ł��邱�ƒm����Ȃ�B
|
����{��m��ƈ����B
���q�i�Ă����j�H���A�����i����Ԃ�j�Ȃ�ƁB
����m�̎��i������j�ƈ����Ȃ�B
���̋�̏�ɁA�ʂ�荕��i���Ԃ�j�L��B����͓��i�����j���̌���Ȃ�̂݁B
|
����q�́A���q�̐����ď�̓��㔼�̎c�Ȃ��܂��ꍞ���̂Ƃ݂Ȃ��āA���̓`�͂ɑ���o���B
|
�E�S�i�����j��͂́A�W�i�����j���E�q�̌��i���Ɓj�ɂ��āA�\�q�i�������j�V���q�ԁB
�}�i����j����S���B
|
�����F�r�U���c�����w�ł͑̌n�I�ɍl���s�Ȃ�ꂽ�̂ł����A��q���s�Ȃ����l���̌n�I�Ȃ��̂ł����A���o�I�Ȃ��̂ł����H
���c�F��q�͌܌o�̏��o�ɂ��āA���̐^�����ɑ����ȋ^��������Ă������Ƃ��w��q��ށx���猩�邱�Ƃ��ł��܂��B����ł��k�v�̐�B���������o���^���Ă������j�d���āA�����^���̐��T�Ƃ��Ď�闧����т����Ƃ���ł��B������Õ������A����ɕt�������E�������ɂ��āA���̕��̂��㊿��`鰐W��̂��̂ł͂Ȃ����Ƌ^���Ă����B�C���́A�w�U�i�ׂ�ꂢ�j�́A�傪�p�����Ă��āA�Â�����̊����Ƃ͎v���Ȃ��B����ł���q�́A��Ƃ̐^���̐��T�Ƃ݂Ȃ��܂����B�����w�I�ȋ^������A�v�z�I�ȈӋ`��D�悳�������ʂł����B��q�́A���o�̕��͂͌Â����セ�̂��̂ł͂Ȃ���������Ȃ����A�����ɏ�����Ă���ϗ����M�Ԃׂ��Ƃ�������ł����B
�����F�����l�؊w�ł͏��o�͂ǂ��ᔻ����܂������B
���c�F����A���o�ɑ��ēO��I�ȃe�L�X�g�ᔻ���s���āA�Õ�������鰐W��̋U��ł���Ƃ������_���o����܂����B�w��w�x�ɂ��ẮA���{�̈ɓ��m�ւ��E�q�̈⏑�ł͂Ȃ��Ɣᔻ���܂����B���̔ᔻ�̓��e�͕����w�I�Ƃ������͎v�z�j�I�Ȃ��̂ł����B��w�ł͌o�ϐ���Ɂu���v�������B�������E�q�Ўq�ł���u���v�����킸�u�`�v�����������͂��ł���A�Ȃǂł��B
���o�́A�܂��O����O���ɓ����̎�Ƃ��`���������u���������v�����������B���̌�A�O���㒆���ɍE�q�̋���̕ǂ���o�y�����Õ�����ǂ������ʁA�����ɏ��o���܂܂�Ă��āA���������m�̕т������������B���̔������ꂽ�т��܂��@�{���u�Õ������v�ƌĂꂽ�B������鰐W��Ɂu�Õ������v�͎U�킵�Ă��܂����B���W��ɔ~賾�i�������j���u�Õ������v���������ꂽ�ƌ����Ă�������サ���B�@����ȍ~�A�u�Õ������v�́u���������v�ƕ���Ō܌o�̐��T�Ɉʒu�t����ꂽ�B�v��ł́A�Õ������Ƃ��ɐ��T�ł���A�k�v��̎�҂����ɍ����]�����Ă����B��q�́A�Õ������ɂ��Ȃ�̋^��������Ă��܂������A����܂ł̕]���d���闧������܂����B���������オ����ɂ�ČÕ������͋U���ł���Ƃ����^�₪��o����A���݂ł�鰐W��̋U���ł���Ƃ�������������ƂȂ��Ă��܂��B
�����F���͂��邪�A�V���͂܂��Ȃ��B�V���Ƃ����T�O�͉���������o�Ă��܂����B
���c�F�퍑�������ł��傤�B�܂������͓��ꂳ��Ă��܂���ł������A���̎���ɂȂ�ƍ��͈���Ă��Ă��������������L���Ă���Ƃ����ӎ������łɐ������Ă����B�s�X�^�Ȃ͖Ўq�̎���ƍl�����Ă��܂����A�^�̕�Ɂu�V�q�v�ƕ���Ŏ�Ƃ̃e�L�X�g�����߂��Ă����B����ٕ̈����̍��ł������^�ɂ����Ă���A���łɎ�Ƃ̎v�z�͑��d����ǂ܂�Ă������Ƃ�������܂��B���̂悤�ȕ����I��̐����������������E�́A�₪�ē��ꂵ�Ď��߂���ׂ��ł���Ƃ����l�������オ�i�ނɂ�ď�������Ă����܂����B�E�q�͂����ƑO�̎���ɁA�����̘D�𗣂�ď���������܂����B�E�q�������́u�����͘D�l�Ƃ��������z���������S�̂ɑ�����҂��v�ƍl���Ă�����������܂���B�������E�q�̐���������ł́A�܂��܂����̂悤�ȓV���Ƃ����l���͂Ȃ������͂��ł��B
�����F���{�̐퍑����ł��V���͓��{�ł͂Ȃ��A���s�ł���A���s���S�̊T�O�A�]�ˎ���ɂȂ�L�܂�܂����B�V���̉��߂͎���ɂ��قȂ�܂��B�����̗������錾�t�ŗ�������Ă����̂ł��傤�B���ꍑ�Ƒg�D���Ȃ��A�O���W�ł����ꂪ�Ȃ���ԂŁA�ǂ͈̔͂œV���Ƃ��Ă����̂����l����B
���c�F�퍑����ƂȂ�ƁA�����S�͓̂V���ł���Ƃ����v�z�͕��y���Ă��܂����B
���{�F�t�H����ł́A���������̂���ł͂Ȃ������B
���c�F�����́u�����v�Ƃ����l�����͂������B�����������̈ӎ��ł��B���]����͓�ŁA�`�Ȃǂ͐��^�ŁA�����Ƃ͈Ⴄ�������Ƃ݂Ȃ���Ă����B�������퍑����ɂȂ�ƁA����̑^�͖k���ƌ��t���S�R�Ⴂ�܂������A�����͓������̂��ǂ܂�A�ϗ��͓������̂������悤�ɂȂ����B���[���b�p�ɚg����Ȃ�A�p�ƕ��͌��t�͈قȂ�܂��B���������e���ꂪ���ʌ���Ƃ��Ēʗp���A�L���X�g�����@���������Ƃ��Ĉ�̐���^���Ă����B�[�֎���ɂȂ�ƁA�t�����X�v���̗��O�͍����z���ĕ��ՓI���`�Ƃ��Ċe�����Ɋ��}����Ă������B�퍑����̒��������l�ŁA���t�͂��ł����Ă������I�ϗ��I�ɂ͑��ʂ��钆�ؐ��E�ł���A�Ƃ����l���͂��łɐ������Ă��܂����B���Ƃ͂����鍑���܂Ƃ߂邾���ł����B
���c����̍u�`: �`���̏p youtube
�t�H�퍑����A������̎���ɂ����ć@������A�A�ォ��A��̕������݂��܂����B
�@������A�Ƃ����̂́A�E�q�̎�ƏW�c�̓����ł��B������̎���ɂ����Ď�N�ׂ̈ɓ����B��N�ɑ��Đ����ł���A�����œƗ���������A�d�����N�����Ƃ��Ȃ��B
�A�ォ��A�Ƃ����̂͐퍑�N�傪�A�Ɛb���{���Ɏd�������Ă��邩���ēA�č����铮���ł��B�Y���̏p�ł��B�������K�p���邱�Ƃ��]���̂��u�@�Ɓv�A�ɂ₩�ɓK�p���邱�Ƃ��]���̂��u���Ɓv�ł��B
�j�L���m��`�ɐĂ̈Љ��̈�b������܂��B�Љ��͒n�������߂钷���i��v�j���d�������Ă��邩�A�����ɑ��߂������������܂����B
���Ɏ��т������Ă���ƕ]���̒����̏��ł́A�l�X�͕n�����A���̑��߂ɘd�G���Ă��邱�Ƃ��������܂����B���ɕ]���̈��������̏��ł́A�悭���܂�A�l�X���n�����Ȃ��A���̑��߂ɘd�G�邱�Ƃ�����܂���ł����B���͕]���̗ǂ������������ώE���A�d�G�����߂����Y���A�]���̈������������˂̗W�ɕ����܂����B�Ɛb�̕]���͈��ɂȂ�Ȃ��A�ēA�č����K�v�Ƃ������Ƃł��B���߂̐��x�ł́u��j��v�A�����̊Ď@�@�ւƂȂ�܂��B���{�ł́u�e����v�A�M���́u�e�����v�ł����B
�����F���S�Ɋ�����`�A�n���̗L�͎ҁA���̌����W�҂������A��������߂邱�Ƃ��n�������߂邱�ƂɂȂ�B�����W�҂ɂ͐M�p�ł��Ȃ��҂�����B�ꑰ�̎҂ɎE����邱�Ƃ�����B�ēA�č����ǂ��܂Ŗ{���ɂł������͋^��ŁA�`�n�c�邭�炢�����o���Ȃ������̂ł͂Ȃ����B
���c�F�@�Ǝ�`�A������`�͐��̐`�����ۂɌR�������ŋ�����ċ����ƂȂ�܂����B�����ۂ����̐ẮA�l���̊w�҂��v�z�Ƃ��Ė@�Ǝ�`�𗝘_�����Ă����܂����B�Ă͎��ۂ̐����ł́A�Ō�܂ʼn��̎�`���̂Ă邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂ł����B
����F�`�ł��������n���̗L�͎҂Ƃ��Ă����B���S�ȃr���[���N���V�[���ѓO���Ă����̂ł��낤���B
���c�F�`�́A�R�ɂ����Ė@�Ǝ�`������`��O�ꂵ�āA���̔h���Ƃ��čs���̖@�Ǝ�`������`����������Ă����܂����B�n�c��͂���𒆍��S�̂ɊѓO�����悤�Ƃ����̂ł����A���������肷�����B����œŖŖS�����B�Â�����́A�ŏ������̏����������`����炴������Ȃ������B������������ł͊�����`���ǂ�ǂ����āA�l�ނ́i���O��͏��Ȃ��Ƃ��j���̂łȂ��\�͂Ɛl���őI�����ׂ��Ƃ������O�����Ă�ꂽ�B�n�c��ȗ��̊�����`�́A�����ƏՓ˂��Ȃ�����A�㐢�ɒ��ؒ鍑�̗��O�Ƃ��Ďp����Đ����܂����B
���{�F�t�H����̓M���V�A�s�s���Ǝ���A�퍑����̓w���j�Y������A�`����̓��[�}����B
�����F�ǂ̒n��̘C���A�Ƃ̃����L���O�̉e���͂��قȂ�B�����̏o�̒N�ʼne���͂��قȂ�A���������ǂ��܂ŋ@�\�������̂��B
���{�F�������̕����x�z�I�A�v�z�Ƃ��Ċ������Ă����Ƃ��Ă��B
�����F���[���b�p�̐�Ύ�`�́A����������Ă���B��ΌN��̉��̊������ƌ����Ă������A�n�v�X�u���N�Ƃ̍c��͓����Ɋe���̉��E����E�������˂Ă��āA����������x�z����Ƃ������͊e���̖��]�ƂɎx����ꂽ�����I�x�z�\���ł����B
���c�F�����ł́A�퍑����ɎY�܂ꂽ�������̗��O���㐢�܂ő����A�ŏI�I�ɉȋ��Ƃ��Č��������ƌ������Ƃ��ł��܂��B����ł́A�n���̐��E���ł������B����ł̓R�l��r���ł��Ȃ��B�\�Ȍ�������Ɏ�������ׂ��A�Ƃ����l�����ȋ��ݏo�����B
�����F�ŏI�͎����������������B�c�鎩�g���������Č��߂˂Ȃ�Ȃ��Ȃ�B
���c�F�����ł́A���̕���͂ǂ��ł���ȋ��Ɋւ��Ă͕s���������Ȃ��悤�Ɍ������^�c����܂����B�v��A�҂���o�������ẮA�㏑�W�ɓn����ĕM�ʂ���܂����B���Ă̕M�Ղ���A�N�̓��Ă�������Ύ������̏�������肩�˂Ȃ��B���������邽�߂ł��B��q�̃��C�o���ł��������ێR�́A���łɏG�˂Ƃ��ėL���ł�������ɉȋ��������B���̓��ẮA�㏑����ĒN�����������������Ď������ɓn���ꂽ�B���̎������́A�ЂƂ�����铚�Ă̕��͂����āA����͂��̗��ێR�̓��ĂɈႢ�Ȃ��ƌ��j�����ƌ����B
�۔��F�����Ɍ����ɂ��悤�Ƃ����B
���c�F�����͌��i�ł��B�y�悷��A�i�m�̈ꑰ���������ƂɂȂ�B������S���ŕK���ƂȂ��Ĉꑰ�̗D�G�Ȏq����ȋ��ɑ��荞�����Ƃ����B����قǂ̒��ڂ���鎎���ŕs���┃���Ȃǂ���A���Ƃւ̐M��������Ă��܂��B�Ȃ̂ŗ�㉤���́A�ȋ��Ɋւ��Ă����͌����ł��낤�Ƃ��܂����B
���{�F�Љ�̃R�X�g�͑�ł����A�����b�g�͏��B
�����F���������܂��B�g�b�v�N���X�̂ݒ����ŗp�����܂��B���̕��ł͕s�̗p�B
�۔��F���[���b�p�ł͉ȋ��́H
���c�F�t�����X�̍������������́A�����̉ȋ������f���Ƃ������̂ł��B�t�����X�v���ŋM�������E����Ǖ����ꂽ�B�M���ɑウ�āA�\�͂��銯���𐭕{�̒����ɒu�����Ƃ������ƂɂȂ����B���̂Ƃ��Q�l�Ƃ��ꂽ�̂��A�����̉ȋ��ł����B�[�֎v�z�Ƃ̓��[���b�p�̋M��������s�����ł���Ƃ��˂Ă���ᔻ���Ă��āA�����̉ȋ���L�\�҂����{�̒����ɑI������鐧�x�Ƃ��ď^���Ă��܂����B���݂ł��t�����X�̍������������̓t�����X�哝�̂̍��ւ̓��}���ŁA����ւł��B
�����F�C�G�Y�X��ȋ����x���Љ���B
���{�F�J�g���b�N�̑m�����I�������B
�����F�m���̓��e���ꂪ�ł����B
�۔��F���{�ł����V���p����ꂽ�B
��c�F�����͏@����������A���x�������ɍ���Ă��A�ꑰ�厖�ŏ�����݂̐l���ƂȂ�B�l�ɂ��Љ�_�Ȃ��Ɩ����B
|
�@�@�@�@�@