論語読書会 その9e漢字使用
メンバー
稲垣裕史(京都大学院卒:立命館大学講師)
成田健太郎(京都大学院)
高津友明(劉鵬)
上田啓之(国際会議場/定年退職)
安澤英治(行政書士)
川那辺恵津子(主婦、韓国文化研究会より)
中村典子(作曲家:京都市立芸術大学専任講師)
小田光男(あじあのとうふ)
大川沙織(京都府立南陽高等学校)
北澤正敏(プラントビジネス退職)
早川太基(京都大学院)
鄭墡謨(京都大学博士卒中国海洋大学副教授)
張崑将(台湾師範大学教授)
田世民(京都大学院卒)
高井龍(立命館大学/中国留学/帰国/広島大学院)
童嶺(南京大学文学部、京都大学留学/南京大学講師)
林月恵(台湾大学中央研究所)
沈相德(京都大学卒/トクソー理研)
津布良春輝(彦根東高校教諭)
岸本史子(立命館大学院日文)
林子博(京都大学院留学生)
李芝映(京都大学院留学生)
姚嘉音(京都大学院留学生)
大西保(国際会議場)
角☆掛奈奈子(精神科医)
稲冨雄亮(京都大学院中文)
川津康弘(フリー)
張伯承(仏教大学留学)
寺澤一美(病院言語聴覚士)
2012年3月17日
≫ 2012年3月24日
≫ 2012年4月7日
≫ 2012年4月14日
≫ 2012年4月21日
≫ 2012年4月28日
≫ 2012年5月12日
≫ 2012年5月19日
≫ 2012年5月26日
≫ 2012年6月2日
≫ 2012年6月9日
≫ 2012年6月16日
≫ 2012年6月23日
≫ 2012年6月30日
≫ 2012年7月7日
≫ 2012年7月14日
≫ 2012年7月21日
≫ 2012年7月28日
≫ 2012年8月4日
≫ 2012年8月11日
≫ 2012年8月25日
≫
2012年3月3日
≫
(論語為政篇)
2012年3月10日
≫
2(論語為政篇)
(孟子公孫丑章句下)
(孟子公孫丑章句下)
(論語為政篇)
(論語為政篇)
(論語為政篇)
(孟子公孫丑章句下)
(論語為政篇)
(論語為政篇)
(論語八佾篇)
(泉屋博古館、黒谷、八佾篇)
(論語八佾篇)
(論語八佾篇)
(論語八佾篇)
(孟子梁恵王章句下)
(孟子梁恵王章句下)
(孟子梁恵王章句下)
(論語八佾篇)
(論語八佾篇)
(論語八佾篇)
(論語八佾篇)
(孟子梁恵王章句下)
(記録は記憶によったもので、上田さんがあらましを記し、小田さんが推敲したもの。参加者の確認をとったものではない。) 後藤点では漢字の肩に○印があり、平、上、去、入聲の指定がされている。論語での一覧表がありますのでそれをみて、指定された聲と合う方を正しい読み方としていただければOKです。 阿弥陀仏になる前に修行中に名乗った名前で、法蔵菩薩は衆生を救うために五劫という時間をかけて四十八の願を完成され、極楽浄土をつくり、阿弥陀仏になられたそうです。衆を救うため、髪が伸びたままで、結局アフロヘヤーのごときことになったというのですが、劫と云う時間は、天女が3年に一度羽衣で岩を撫で、岩がすりきれる時間、一説43億2000万年、五劫なら216億年となります。そんな仏像が安置されているとは、確かに黒谷はただものではありません。パワースポットです。
2012年3月3日(土)論語為政篇
本日、成田君、北澤さん、小田さん、上田さんの四人。
成田君のリードで為政篇の音読。本日の所、北澤さんお願いします。
子の曰はく、君子は器ならず。
器は、各(おのおの)其の用に適(かな)ひ、相通ずること能はず。成德の士は、體具ふざること無し。故に用周(あま)ねからざる無し。特(ただ)に一材一藝を爲すのみに非ず。
先生がおっしゃいました。君子というものは、その器ではありません。決して単なる専門家ではいけないものです。
器は、それぞれの利用法に適応していて、相通ずることはない(小田:たとえば、しゃもじはしゃもじ、箸は箸で、一つのことしか使えないようなもの)。德のある人は、體を備えていないことはない(実体を持っている)。だから、利用法は、周(あま)ねからざることはない(何にでも使える)。ただ、一材一藝をなすだけではない。
小田:この章も有名な言葉です。この章は後の公冶長篇と併せると面白いです。そこの4で、孔子が子貢に「汝は器なり」と評しています。
北澤:「子貢、問ひて曰く、賜は何如。子の曰はく、女は器なり。曰く、何の器なりや。曰はく、瑚璉なり」ですね。要は子貢は専門家ということですか。
小田:瑚璉は、お供えに用いる上等の器です。孔子に「お前は器にすぎない(つまりこの章の言葉の定義により、君子ではない)」と言われて、子貢はむっとして「では、何の器ですか?」と聞くと、「上等の器だ」と先生がフォローした、という話です。孔子は、子貢ですら君子でないと言ったわけです。
成田:ここはもう少し深く読める。孔子が子貢を「君子でない」と思っているかは分からない。孔子と子貢の間には、あうんの呼吸がある。孔子が、「お前は器だ」と言うと、子貢は、「器とならば、何の器ぞ」と返すところが子貢のうまい所。孔子は、「それは瑚璉なり」と答えさせるのが子貢のもってゆきかたのうまい所。先生と弟子とが互いの呼吸が判っていてあえてこんな問答をしてみた、一種の出来レースとして捉えたいです。
小田:師弟ともども、名人芸ということですかね。
北澤:子貢も自分は器と思っていたのですか?
成田:孔子が亡くなった後に、弟子たちは親の喪ではないが、心喪、つまり心の中で喪に服することを三年行った。それが終わっても、子貢だけは孔子の墓前に庵をたてて更に三年暮らし、結局六年喪に服して暮らした。子貢は生き残っている弟子のなかでの古株、一番の先輩であり、孔子の学団をまとめるのにうってつけの立場にあったが、それを拒否して喪に服していた。もしかしたら子貢には計算もあって、自分は学団を率いるリーダーの器でないことが分かっていて、あえてそういう行動にでたのかもしれない。史記や孟子の記述にありますが、弟子たちが有子(有若)を孔子の後継者に立てようとしたときのエピソードで、子貢の名が出てきません。それは、子貢は喪を口実にしてそれに関与しなかったのかもしれませんね。上田さんどう思いますか?
上田:そう思います。喪を口実にした、成程、子貢はそういう人だと思う。
成田:子貢は先を読むことがうまかった。
小田:孔子のあとのまとめ役には有子がよいとされた理由は、孟子などの記述によれば有子が孔子の面影を残していたことにだったらしいです。しかし、曾子だけが反対した。彼は、「孔子は長江・漢水で身を潔め、秋の強い陽に身を晒し(大変な辛酸を経験され)汚れがなく、その潔白なさまは、有若に比すべくもない」などと言いました。つまり、有子ごときに孔子の真似ができるわけがない、と曾子は拒絶したということです。このエピソードの中には確かに子貢はおらず、若い弟子達が孔子の後釜を決める談合の中心となっていました。
北澤:では、その後、誰がリーダーとなったのですか。
成田:その後はリーダーはない。
小田:各々の弟子が、それぞれの儒家教団を作っていきました。魯に残ったのは曾参のグループで、そこから後に子思、孟子が出ました。
北澤:曾参がまとめたということですか。
成田:全体を曾参がまとめたものではない。
小田:たとえば、子夏と彼の一派は黄河の向こうの魏に移って行きました。
成田:子張篇で、子張と子夏の弟子達の論争がある。それぞれが弟子を持ち、必ずしも仲が良かったわけではない。
小田:子張篇では、子貢も出てきますね。「子貢仲尼に賢(まさ)れり」、など。子貢の方が孔子より優秀であるという評価が、いろいろな人の口から言われています。子貢は、それらにいちいち気の利いた言葉で否定した。
成田:子張篇の子貢に関するエピソード群は、孔子の死後の話だったでしょうか?生前だったかもしれません。叔孫武叔がそう言ったのでしたが、もしかしたら孔子の晩年ぐらいのエピソードかもしれません。
上田:季康子のもとで冉求や子貢が内政、外交をしており孔子の存命中、子貢は六年の喪ですから、六年何もしなければなかなか復帰はむつかしい。子貢は、孔子あってこそ自分の能力が発揮できると思っていたように思える。喪を理由にして子貢が距離を保ったという成田君の考えは、確かに子貢らしい。
小田:子貢は、孔子がまだ大して有名でない時代からの弟子で、孔子と非常に近い関係だったのでしょう。
上田:孔子が亡くなる前に、子貢が会いに来るのが遅いとするところがある。顔回、子路はおらず、一番の話し相手は子貢であった。
小田:孔子は、春秋時代の後期に活躍して、晩年の頃にはすでに時代は戦国時代の直前の空気に突入していました。晩年の孔子は、もう時代についてゆけなくなっていたのではないでしょうか?若い世代からは才気走って弁の立つ者がどんどん現れて、昔の時代の質朴な気風がどんどん失せていった。そんな晩年の孔子と昔ながらの話が通じるのは、もはや子貢しかいなかったのかもしれませんね。
成田:「先進は野人、後進は君子」と孔子は言いました。生き残った先進は、もはや子貢のみ。ゆえに子貢は野人であるから、君子でない。こういう脈絡で「器」と孔子は彼に言ったでしょうか。後進はよりしっかりとした弟子で、孔子は彼らを君子と評価します。君子ではあるが、だけど孔子が愛情を持つのは先進の野人の方であった。
小田:孔子はまた「中庸を得ることができなければ、狂狷」を選びたいと言うぐらいです。洗練されているよりは、偏屈でも骨のある人物が好きだったのでしょう。
成田:孔子がまさに「狂狷」ですからね。
小田:この章の言葉は、昔はよく引用されたものでしてね。要は、上に立つ者はスペシャリストであるよりもジェネラリストであるべしという、組織理念を示す言葉として引用されていました。私もかつて役人でしたが、キャリア組の役人は、若い時にいろんな部署を短期間でたらい回しさせられます。それは、下働きのときに色々な組織の部署を経験させて、一つの器にしないための人事政策のためでした。だから、各部署の込み入った仕事は、長年同じ部署で仕事をしているノンキャリアたちがよく知っています。キャリアは、上っ面しか知らない。しかし、それでよい。キャリアは君子であり、ノンキャリアは小人である、などというと労働組合に叱られますけれどね。
次にゆきましょう。小田さん、お願いします。
子貢、君子を問ふ。子の曰はく、先ず其の言(こと)を行ふて、而して後に之に從ふ。
周氏の曰く、先ず其の言を行ふは、之を未だ言はざる前に行ふ。而して後に之に從ふは、之を?に行ふ後に言ふ。○范氏の曰く、子貢の患は、言の難きに非ずして、之を行ふこと難し。故に之に告ぐるに此を以てす。
子貢が、君子について質問した。先生がおっしゃった、「まず言うべき事を実行し、それから後に行いに従って発言するのだ」と。
周氏が言うに、「『先ずその言を行う』というのは、まだ発言しない前に行動することである。そして『後に之に從う』というのは、行動した後に発言することである」と。○范氏が言うに、「子貢の欠点は、弁舌の難にあるのではなく、行動に難があった。だからこのように子貢に言ったのだ」と。
小田:つまり、不言実行ですね。
北澤:周氏と范氏というのは?
小田:周敦頤(周濂渓、1017-1073)と范祖禹(1041-1098)でしょう。二人とも北宋の人で、朱子の100年ほど前の人です。
成田:朱熹は、自分一人で儒学の体系を編み出したのではありません。宋代の彼の先行者たちは「周・張・二程」と呼ばれます。つまり周敦頤、張戴(張横渠、1020-1077)、程顥(程明道、1032-1085)、程頤(程伊川、1033-1107)のことです。中でも二程子は朱熹の体系に強い影響を与えたために、朱子学のことを「程朱学」とも言います。また周・張・二程に朱熹は宋代の人なので、彼らの学問体系のことを「宋学」とも言います。
小田:朱子は、儒学の道統は孔子から子思、孟子につながり、その後絶えて長い暗黒が続いたと評します。ようやく唐代に韓愈が現れて絶えていた道統を復古させ、宋代の周敦頤以降に継がれた、と言います。朱子は、自らをその末端に位置づけているのです。
北澤:韓愈は詩人じゃないですか。
小田:文学者でもあります。
成田:政治家として重要な仕事をしています。当時、仏教と道教が流行っていました。税金を逃れるために僧侶や道士になる人が後を絶たなかった。国としては、そんな税金逃れは困る。韓愈は、仏教・道教を中国の異端であると見なして正統は儒教である、と彼は上奏した(『論仏骨義』)。仏教、道教を排する過激な上奏を奉って、当人はうまくいかず左遷させられてしまいましたが、後世の者たちによって、儒教を復興した人として称えられるようになりました。
小田:当時、仏教に入門することを口実にして、税金を逃れようとする実利を求める人間が後を絶たなかった。これは国として困る。それで、儒教を正当化する韓愈の主張には、政策的効果も期待されたのです。中国では仏教は唐代が全盛期で、その後は次第にふるわなくなっていきます。(韓愈死後の唐代末期に会昌の排仏(えしょうのはいぶつ)が起こり、寺の破壊、僧の還俗、寺領の没収が行われて中国の仏教は大打撃を受けます。)
北澤:儒教者も無税ですか。
成田:儒教に入信するとは、実際には役人となること。それには、論語、詩経、書経等々を勉強しなければならない。役人となれば非課税。仏教者は勉強せずとも入信してしまえば税金はただとなる。必死で勉強している者にすれば、不満があった。
小田:しかも勉強するだけではダメで、科挙に受かってはじめて非課税ですから。
成田:皇帝が仏教にのめり込んでいた状況では、まず仏教信者の貴族階級から説得しなければならなかった。これは困難で、こうなれば、政争に巻き込まれ排斥されることにもなる。韓愈は、皇帝の怒りを買って左遷させられてしまいました。これに比べれば同時代の白居易は仏教を好み、つまり時代の主流に乗ったわけで唐代の官僚としては失敗なく生涯を送ることができました。
上田:范氏は子貢の患は言を行うに難があるとしているが、子貢は弁舌のみの人ではなく、行動の人であり、ピンとこない。君子不器にこれがあるのがおもしろい。子貢の質問に孔子は不器とはいわず、不器とは何かと頭をひねらず、まず、やってみろ、みたいなもってゆきかたに思える。
成田:子貢が質問している意味、君子はどうですかという語があり、それに並べて、まず、その言を行う、君子のことを行う、まあ、やってみろ、やってみれば、言葉がついてくる、ということでしょうね。范氏の言はどうかと思います。子貢はむしろ出来る人だと思う。
北澤:「巧言令色、鮮いかな仁」ですかね。子貢がこのようであると?
小田:その言葉は有子に対する評価かもしれない、とこの読書会で話していました。
北澤:孔子の後を継いだという有子のことですか。
成田:有子は孔子とやり合うほど弁がたつということはない。
小田:有子は、学而篇で出てきますが、それ以外に論語ではほとんど現れません。意図的に排斥されているようにも思われます。孔子の後継者事件のことがあって、有子については無視する傾向が弟子たちにあったのでしょうかね?
成田:有子は若輩(孔子より43歳若い)であり、孔子というより、先輩とのやりとりが多い。
小田:まあ、先進篇の18と19で孔子は高柴・曾参・子張・子路のことをボロカスにけなしていますが、顔回と子貢だけは褒めています。子貢は、孔子が褒めるのに躊躇しなかった数少ない弟子であったでしょう。評価が低いはずがない。
北澤:しかし先進篇のようなことを先生から言われたら、ショックですなあ。
では、次にゆきましょう。北澤さんよろしく。
子の曰はく、君子は周して比せず、小人は比して周せず。
比は必二の反。○周は普偏なり。比は偏黨なり。皆人と親厚するの意。伹し周は公にして比は私しのみ。○君子小人に爲す所同じからず、陰陽晝夜の毎毎相反するが如し。然れども其の分るる所以を究むれば、則ち公私の際、毫釐の差に在るのみ。故に聖人の周比・和同・驕泰の屬(たぐひ)に於て、常に對し擧げて互に之を言ふ。學者、兩閒を察して其の取舍の幾(わずかなきざし)を審らかにせんと欲すなり。
先生が言われた、「君子は周して比せず、小人は比して周せず(貝塚先生は、君子は親しみ合うが狎れ合わない。小人は狎れ合うが親しみ合わない、としておられる)」と。
比は必と二の反切。(「ひつhitu」と「にni」から「ひhi」となる、と小田さん)○周は普偏で、比は偏黨、片寄ること。皆(周も比も)人と親厚するということ。ただし、周は公のもの、比は私のものというだけである。○君子と小人のやることは同じではない、陰陽や昼夜がことごとく相反するようなもの(別ものである)。だが両者が分かれるゆえんをよく見ると、それは公と私の境目にあるわけで、毫釐(わずか)の差があるのみだ。だから聖人は「周・比」「和・同」「驕・泰」といったたぐいの比較において、常に対にして取り上げて、互に言及するのだ。聖人は学ぶ者に対して、これら二つの間にある境目を察して、取るか取らないかの機微をよくよく理解せよ、と望んでいるのである。
小田:両者は似ているがわずかに違う。そのわずかな違いが大きな差になる、というわけです。
北澤:周と比を貝塚先生は親しみ合う、狎れ合うとしておられる。
小田:貝塚先生の読み方は、「和して同ぜず」という言葉に引き寄せて解釈しているようです。しかし、朱子はここでやや違った意味で解釈しているのではありませんか?
北澤:両方とも人と仲良くする、周は普遍、比は片寄るとしている。
小田:人と付き合うことは、人間として君子も小人も変わらない。だからわずかの差でしかない。付き合いを好き嫌いでやると、小人の道となる。相手の人物に留意して、自分にとっての親疎好悪を抜きにして人物としての価値を尊重して付き合うのが、君子の道でしょう。
北澤:和して同ぜずと同じ意味ですか。
小田:貝塚先生はそうとっておられるようですが、ちょっと違うのではないでしょうか?
成田:周は「あまねし」、普遍、まんべんなこと。自分と違う性格の人とも付き合う。比は「並べる」、つまり似たものを並べる、同じ種類の器を並べることです。君子は器ではない。同じ種類のものが一緒に並んでいるのではなくて、違う人とも私心なく付き合う。いっぽう「和して同ぜず」とは、音楽だと「和」つまり和音であり、違う音階が調和して美しく響く様を言っている。しかし「同」とは同じ音を皆で一斉に歌うようなもので合うのは当然。だけど、調和の美しさはない。美しさは、異なった音階が調和することにあり、そこが両者の似て非なるところです。
小田:この章の言葉の反対が、「類は友を呼ぶ」という言葉でしょうかね。類は友を呼ぶのは、人情として致し方のないところです。だけど、類の友だけで集まるのは「比」であって「周」でなく、小人の道だとこの章は言います。
成田:器は同じことしか知らない。器でなくば、他の専門の人とも話せる。
上田:周は国名ですが、周密に装飾された美しい盾の象形、行き届いて、あまねく、公平な、天命を受けた周のイメージ。比は人が並んでいる象形、二人を並べると主従の関係が生まれやすく、また相互を比較することになりがち。周は音楽でうまく喩えられたように、個々をあるがままにみて対応することを言う。君子というのは周の文王のような人がモデルで小人は支配される側の人間、民であり、君子は、小人(民)の安寧を考えるべき立場にあった。それが時代が下ると、貴族、大夫、士へと適用され、同じレベルで比較するときに、あいつは君子、こいつは小人と対立概念となった。孔子は、下級の士であっても君子となれば、大夫や貴族にひけをとることはないというあり方を示された。
小田:孔子もまた、時代の子です。孔子の時代には下剋上があり、そういう機運がありました。学を積めば身分など突破して「士」になれる、そのよな「士」こそが国を動かす君子なのだ、というのが孔子の私塾に集まった生徒たちのテーマだったでしょう。孔子の下に弟子がわっと集まったのは、すでに君子と小人の差が生まれつきの身分では決められない実力優先時代に突入した、という時代が背景にあります。
北澤:必と二の反切というのは。
成田:中古音では、必の聲母はP清音、韻母はit、二の聲母はにゃににゅにぇにょに当る音(ny)韻母はiで去聲、反切でP清音+i去聲ですから、biの四聲bìとなります。
上田:二erとの関係は?
成田:niからri、iがとれてr、これでは発音しにくいのでeを入れてerとなった。
小田:現代北京音では消失していますが、かつての中国語の発音において入声(語尾がk
t
p)の語末の子音は、中古音つまり唐代前期の音でははっきり発音されていました。だから、「必」は現代北京音では"bi"ですが、かつては"pit"と発音されていたはずです。日本人も韓国人も唐代の音を聞いて、これを自分たちの言葉に転写しようとした。日本人は、"pit"を転写して、「ぴつ」と読みました。上代にパピプペポで読まれていた音は、時代が下るとハヒフヘホに変化して、現在は「ひつ」と読んでいます。いっぽう現代韓国語では「必」の字は"pil"と読みます。韓国語では、後世にt→lの音韻遷移が起こったのです。(必要ピリョ、必然ピリョン、必勝ピルスン)
成田:反切で指定されるのは、二つ以上読み方があって、あまり一般的でない場合に指定をすることになる。
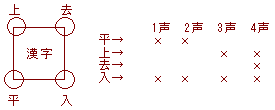
北澤:今の中国人もそういう風に読んでいますか。
成田:そういう区別がなくなってきている。
北澤:周と比の漢字について、当時の人は分かっていましたか。
成田:今の人には周と比は分かりにくいが、当時の人はピンときたのでしょうね。
小田:昔の時代ならば、すでに聞いたときにピンときたのではないでしょうか。なぜならば昔の時代はテキストを読むのではなくて暗誦するのが学ぶことだったのですから。この章くらいの短い語句は、暗誦すべき課題だったでしょう。
北澤:当時、孔子が言ったことをメモすることはあったのですか。
成田:衛霊公篇に孔子が言ったことを「子張これを紳に書す」とあります。紳は帯の垂れ下がった所です。
北澤:墨はあったのですか。
成田:顔薬と筆はありました。役人は刀と筆が必需品で、役人のことを「刀筆の吏」と云いました。かつては木簡・竹簡が記録用紙であり、役人は字を間違えたら刀で誤字を削ったのです。砂漠地帯で、過去の時代の役人が刀で文書を削った削りカスが出土したりします。
小田:漢代には、砂漠地帯まで駐屯地があって役人がいましたからね。乾燥しているから、削りカスが腐らずに現代まで残った。
さて、器の話しは昔はよく行われたものです。器が大きいとか小さいとか、とらわれてはダメで偉い人は器を使う人、どんな器でも使いこなせる。しかし、平成の世では、国会において専門的なことも知らないで大臣になるなどとんでもないと批判を買う始末。何も知りませんではひんしゅく者と大臣の椅子から引きづり下される。では、論語の時代は、どうであったのだろう。孔子の述べるごとく、君子は不器が通用していたのであろうか?となると疑わしい。戦国の世には、色々と能力を持ったものがのし上がってきた。儒家は禮のプロとみなされており、決してジェネラリストとして評価をえていたものではない。戦争、外交、経済とそれぞれのプロが諸子百家として存在意義を競った。魯においても哀公の時代、大夫の季康子はもっぱら冉求や子貢を用い、孔子を遠ざけた。国政を一人の人格ある者に預けるより、専門家を登用する方向にあった。平成の世においても、孔子のごとき主張をすれば、政権に就けるかと言えば、煙たがられること、かの時代と変わりありますまい。
平成の国会において、政治家は不器。まず、言を行え、さすれば政治家たりえる。政治家は周し比することなかれと言えば、マスコミを含め、なにをとぼけたことを、江戸時代じゃあるまいに、時代錯誤ですな、民主主義の政治の現実を知らぬこと甚だしいと揶揄されよう。
孔子も揶揄をされ、その言は政治の現実の場では採用されず、空を切ることが多かった。しかし、若輩諸子になんと酷評されようと、踏ん張って直言された。それ故、今もってその言を聞くことが出来る。
2012年3月10日(土)論語為政篇
本日、成田君、北澤さん、小田さん、早川君、高津君、上田さんの六人。
成田君のリードで為政篇の音読。本日の所、北澤さん、私がやりましょう。
子の曰はく、學びて思はざれば、則ち罔(くら)し。思ひて學びざれば則ち殆(あやう)し。
諸を心に求めず、故に昏(くら)くして得(う)ること無し。其の事を習はず、故に危くして安からず。○程子の曰く、博學・審問・愼思・明辨・篤行。五つの者、其の一を廢(す)つれば學に非ず。
先生がいわれた、「学んで習っているだけで、自分で考えないと、ぼんやりとして、はっきりしない。逆に、考えるだけで学ばないと、(貝塚先生の訳に従うと、)『疑いがでてくる』」と。
心で反省してみない。だから、得ることが無く昏迷である。いろいろなことを学習しない。だから、危なっかしく不安定である。程子が云う、「博く学び、審(つまびら)かに問い、愼(つつし)んで思い、明確に分析し、ていねいに行うこと。この五つのうち、一つでもなければ学んだことにならない」と。
北澤:「博學・審問・愼思・明辨・篤行」は『中庸』二十章に記されていると注されています。(「博くこれを學び、審かにこれを問い、愼みてこれを思い、明らかにこれを辨じ、篤くこれを行う。」)朱子は、「殆」を「危くして不安」としているが、貝塚先生はこの説を疑わしいとしておられる。
小田:貝塚先生は、王引之に従って「殆」の意味を「疑う」と解釈しています。いっぽう朱子は「不安」と読みました。古注はさらに別の解釈です。
北澤:「殆」は古注では「怠る」とあるのですか?
成田:朱子の「不安」は現代日本語の意味としての「心理的な不安」というものではなく、基礎がしっかりしないと安定しないという「不安定」という意味の「不安」で、もともとの原義です。王引之の説は、多くの例で「疑」の字と「殆」の字がセットで使われている点に根拠を求めています。為政篇のここから三章の後、子張が禄を求める条で、「多く聞き疑はしきを闕き、愼みて其の餘りを言へば、則ち尤(とがめ)寡し。多く見て殆きを闕き、愼みて其の餘りを行へば、則ち悔い寡し」とあります。ここで「疑」と「殆」が対になっていて、意味は「疑わしい」です。王引之は、つまり考えるだけで学習しない人の言うことは「疑わしい」と解釈するのです。いっぽう古注は何晏が、「学ばずして思う、終に卒して得ず」。いたずらに人の精神を疲れさせる。思うだけで学ばないと「疲れる」。自分が疲れるだけで得ることが無い、という解釈です。
北澤:自分で考えるより人に聞いた方が手っ取り早いみたいなものですか。
成田:思うだけでは、苦労したほど効果はないということです。
小田:その古注の解釈は、私に泰伯篇の2章を思い起こさせます。そこには「恭にして禮無くば則ち勞す」とあります。つまり、恭謙な意図を持っていても、礼を学んでこれに従わないと、労あって無駄骨である、ということです。古注の「疲れる」という解釈は、たとえ意図が善良であっても、学習することを抜かせば労あって益なきことだ、という点で、為政篇のこの章に泰伯篇の2章のような意味を読み込んでいるのでしょうかね。
成田:泰伯篇の2章は礼を学ぶことを言っているので、学ぶという側面から引きつけて読むことは、確かに可能です。だがこの章は、学ぶことと思うことのバランスを言うことが主題です。何晏が言うように「学ばず思うだけでは得ることが無い」という解釈では、では学びさえすればいいのか。どうも何晏の解釈のいう「思うだけでは無駄に疲れる」という読み方は、前の部分とうまく合わないように見えます。
小田:泰伯篇も、その真意は礼だけ学んでいいということではないでしょう。善意がまず必要です。しかし、善意だけで礼を学ばなければ、無駄骨だと言っているわけです。為政篇のこの章は、学と思の両者のバランスを格言のように短く言ったもので、泰伯篇はもっと長い言葉で応用したものではないでしょうか。論語の中のどこだったかな、「一日食わず寝ずで思ったが益がなかった。学ぶ方がよい」という章があったはずですが、、、いま探しています。
成田:探している間に・・・古注は前半部分について包咸の説で、「学びて其の義を尋ね思はざる、則ち罔然として得る所無し」とあります。何晏の後半部分の解釈は、学ばずして思うことはいたずらに精神を疲れさす、とあります。何晏の解釈は学と思の順番を入れ替えて、「学ばずして思うと疲れる」と解釈しますが、しかし思ってから学んではいけないのか?思ってさんざん疲れた果てに、本を学んでそこに正解が書いてあって分かることなどがある。しかしこの過程が一概にいけないとは、思わないですね。
小田:ありました。衛霊公篇に、「吾嘗て終日食らわず、終夜寝ねず、以て思う、益なし。学ぶに如かざるなり」です。
成田:学があるから、まず思考してみる。これは真面目な勉強家のパターンです。何晏の解釈は、学ぶ方向に片寄りがちです。
小田:とにかく思考してみるということを、孔子はかつて実験したわけですね。で、それだけではだめだと分かった上で、本章の言葉となる。
成田:孔子は一回実験してみて学問の大切さが身にしみた。「竹にも理が有る」という話は、誰だっけ。
早川:王陽明です。
成田:そうですね。朱子は万物各々に理があり、それぞれの理を観察により窮めることができると言いました(格物致知)。それで王陽明は竹にも理があるはずだろうと、七日間竹を見つめた。だが、竹の理がわからない。
早川:それで病気になった。
成田:病気になった後で、朱子の主張は嘘っぱちではないか、と考えるようになりました。それで朱子学から離れて自分の一派を立てました。陽明学です。
小田:ヒヨコを観察するとヒヨコの仁が分かる、と言ったのは程明道でしたっけ。二程子の兄のほうですが、彼の哲学には万物に「仁」や「理」があるという自然哲学的な傾向があったといいます。「竹にも理がある」とかいう主張は、このへんから来ているのでしょうかね。
早川:程明道には、こんなエピソードがあります。彼の自宅の窓辺から、草がぼうぼうと生えていました。弟子がそれを見て、刈ったらどうですかと聞いた。明道は、いやいやこの窓外の草から、それが生育していく理が見えるのだ、と言ったとか。
小田:どうも朱子学は、「思いて」の方に傾いているようですね。
成田:朱子学は、古い儒教に対して「思う」方を重視した。それまでの儒学は、書物の丸覚えからスタートしていました。それに対して宋学は思惟することが特徴でした。
小田:昔の読書は、丸暗記ですよね。あれだけ膨大なテキストを丸暗記するなどは大変だ。
成田:いちおう、できるとされているんです。五経の丸暗記は、一経を三年で行うとされています。だから全体で15年です。だから十五にして学に志せば、三十にして五経の暗記が完了して学者として立つことができるという計算です。
小田:相当早い子供時代から入門しないと、とても無理ですね。子路なんかはいい歳になってからの入門ですから、暗記なんかは無理だったでしょうね。それで優秀な後輩たちに馬鹿にされた?
北澤:中国は今でも暗記を重視しているのではないですか。学生たちの物覚えはいいが応用に欠けるという印象がありましたがね。
小田:中国では、何を覚えるのですか?毛沢東語録?
高津:いやそれは今時!
小田:冗談です。
早川:文革世代は、丸暗記していましたが。今ならば、論語や孟子の有名な部分とか、漢詩かな。小学校の一学年のカリキュラムで漢詩十首を覚えるようです。
高津:覚えさせられましたね。
小田:日本人も、昔の子供は百人一首とか諳んじていましたが、今の子供はダメですね。昔の日本人は、丸暗記が好きだった。子供は教育勅語、軍隊に入れば軍人勅諭。それに天皇の歴代の名前。戦後の教育は、反動から丸暗記が避けられるようになりました。よいことなのか、悪いことなのか。
成田:学んでも、思っているかが問題です。
早川:内藤湖南の親父さん(祖父?)あたりまでは、日本人でも論語が暗誦できたといいます。その後の世代は、もう京大の学者でもできなくなりました。
上田:罔を「くらし」、殆を「あやうし」と訓じているが昏や暗、危とせず罔、殆としたことを考えねば。罔は捕えられることで罔(な)し、無いことでもある。殆の歹は残骨、悪人、死に近いイメージ、台は怠慢、なまける喜び、みたいなものでそういうものをひっくるめたものがあるのでは。
成田:「罔」の字は古典であまり使われないが、「殆」の字は珍しくありません。朱子は「危うく安からず」、王引之は「疑わしい」と解しています。いっぽう「罔」の字の原義は網(あみ)のことです。簡体字で「網」は「网」ですが、これは「罔」の古い字体を復活させたものです。読みは「wăng」。もともと「网」だったのですが、これに「亡」を足して「罔」となりました。「亡」は声符で、発音(wáng)を示す符号です。「网」に「亡」をくっつけることにより、より読み方をはっきりさせたのです。しかし、なぜこの字から「くらい」という意味が派生したのかは、よく分からないのですが、おそらく目の前で網をかけられて見えにくくなる状態を示唆したのでしょう。
上田:学んだことに囚われる、自分の考えることが罔(な)い。
北澤:朱子注で「五つのうち一つを欠く」とは何が言いたいのですか。
成田:おそらくこの程子の言葉は、論語のこの章について言ったことではないはずで、『中庸』の言葉について述べたものでしょう。『中庸』のこの部分には学問の大切さが書いてあり、程子はこの五つを兼備して初めて学問である、と述べました。朱子は、程子のこの言葉をあえて論語のこの章の解説として引用したのです。本を読んで学ぶだけでなく、考え、行動で示すべきだという解釈の補強としてです。
小田:以前に成田さんからの解説にありましたが、そもそも朱子注で「程子曰く、、、」「周氏曰く、、、」など先人の学者たちの言葉が引用されている場合、それらは必ずしも学者たちが論語の各章のために言った言葉ではない。朱子が、論語の注を書くに当たって、先人の学者たちの言葉をピックアップして各章に引用し、論語の解釈を宋代学者たちの思想によって体系化しようと試みたものです。言葉は先人たちのものですが、どの章にどの言葉を引用するか、という選択は朱子のオリジナルです。
成田:そうすることによって、論語を体系的に解釈して、朱子学の書としたのです。
上田:誰に向かって孔子は言ったものか。学んだいうがとらわれて身についたものがない、ひとりよがりのぬかよろこびだな、相当きつい言われ方で、こたえたのではないか。
成田:誰かに向かって言うなら、この章の前半か後半か、どっちかだけ言ったでしょうね。ふたつとなれば、格言となって、残されることになる。
小田:入門した若者たちに、まずこれを教えたのではありませんか?
早川:以前見たドラマ(?)の、門の柱聨に「學地不思則罔」「思而不學則殆」が対で書かれていました。
小田:「思いて学ばざれば則ち殆し」を言う相手をあえて考えるならば、子路になるかな。
上田:子路は一つ聞けば実践できるまで次を聞かないようにした人ですから、学んで思った人でしょう。
小田:ちょっと後の章で孔子は子路に、「之を知るを之を知るとし、知らざるを知らずとせよ」といってますね。子路に思而不學の傾向を孔子は感じたから、このように忠告したのではないでしょうか。
異端となれば、小田さん、よろしく。
子の曰はく、異端を攻(おさ)むるは、斯れ害なるのみ。
范氏の曰く、攻は專ら治むなり。故に木石金玉を治む工を攻と曰ふ。異端は、聖人の道に非ずして別に一端を爲す。楊・墨が如き是れなり。其の天下を率いて父無く君無きに至らしむ。專ら治めて之に精せんと欲せば、害を爲すこと甚だし。○程子の曰く、佛氏の言、之を楊・墨に比すれば、尤も理に近きと爲す。所以(だから)、其の害尤も甚だしきと爲す。學者、當に淫聲美色の如く以て之を遠ざくべし。爾らずんば、則ち駸駸然として其の中に入る。
先生がおっしゃいました、「異端(朱子の解釈にあえて従うならば、儒学以外の教え)を学ぶことは、害しかない」と。
范氏が言った、「攻はもっぱら習得することである。だから木石金玉を加工する職人を攻と言う。異端とは、聖人の道でなくて別に一つの学派をなすことである。楊朱・墨翟のたぐいがこれである。これらは天下を治める原理として、父も君主もない主張にまで至る。このような学問に専念して習得しようとすれば、害が非常に大きい」と。○程子が言った、「仏陀の言葉は、楊・墨に比べればとりわけ理に近い。だから、その害はとりわけ甚だしい。学ぶ者は、仏陀の言葉を淫らな音楽や美しい女色のように、遠ざけるべし。そうしないと、あっという間に心が取り込まれて、支配されてしまう」と。
小田:朱子は范氏・程子を引用して、仏教を主たる敵と見ています。
成田:類似品が一番やばい。仏教は、それだけ宋学に近い点があった。
小田:しかし孔子の時代には楊朱も墨翟もいなかった。孔子にとって、これらが異端ではありえません。
高津:では、孔子の時代の異端とは何ですか。
小田:この章については、徂徠もまた楊・墨が孔子の時代に異端であるはずがない、として朱子の解釈に反対しています。
北澤:貝塚先生は、織物の両端から一度に巻くと中途半端になって害しかない、と読んでいる。
小田:呉服の反物は、両方から巻いては反物にならないということですね。清の戴震(たいしん)の説ということです。いっぽう徂徠は、攻はそのまま「攻撃する」という意味であり、異端は異心とか二心の意味であって、この章は「内心に異心のある人間を攻めると寝返えるからやめておけ」という意味だと言っています。徂徠の読み方は、しかしながらもう一つよく分からないですね。
上田:攻は攻学、攻究で学び究めること、孔子はまず詩と礼を学び究めよ、それをせず他のことを攻究するのは善くない。孔子は何でも学んだ人で、異端を学ぶなということではない。
小田:つまり、学ぶ際には基礎から段階を踏んで進んでいけと。いきなりあっちもこっちも応用をつまんでいては、学ぶことに害があるだけだ。
早川:古注では、異端は悪いもの。善い道は有統(忠孝仁義がある)、だから、殊塗(しゅと)して(詩や書や礼など道が違っていても)同じく歸す。異端は同じく歸さず、つまり帰するところがない。糸の切れた凧であり、善道に帰さずに悪となる、と言います。
小田:しかしその古注もまた、異端について善道でない道を学ぶ者という解釈を取っていて、諸子百家が並び立った時代を通り過ぎた段階を前提としているようです。孔子の時代とは、前提が違うでしょう。
早川:皇侃になれば、異端は雑書、(儒学の)正典ではなく諸子百家の書となる。集解ではそういう対比ではない。帰する所が無い。茶道には表千家と裏千家と武者小路千家がありますが、学ぶ者がそれらを最初からいっぺんに学べば、害しかないでしょうね。
高津:子罕篇に、「共に学ぶを得ても共に道をゆくは難しく、共に
道をゆくも共に立つは難しく、共に立つを得たとしても、共に 権
( はか )
るは難しい」とあります。孔子は、共に学んで進んでも、各人が同じところに辿りつくとは限らない、と言っています。異端と言うが、同じことを学んでも孔子はこうして同じ意見になるとは限らないと言っていて、朱子とかの読み方はどうでしょうか。この章は、前の章の「学ぶだけで考えない、思うだけで学ばない」という言葉に付け加える意味で言っているのではないですか。
成田:異端は両端みたいなものですかね。
小田:私は大学時代の専攻が経済学でしたが、経済学には近代経済学とマルクス経済学がある。近代経済学にとってマルクス経済学はまさに異端であり、またマルクス経済学にとっては近代経済学は異端でした。どちらも経済を説明するための体系として筋道を立てていますが、経済に対する両者の解釈を突き合わせると、矛盾していて相容れません。私は大学初年の頃に両方勉強しようと試みたことがありましたが、じつに無駄でしたね。反省することしきりです。まず、近代経済学でもマルクス経済学でもいいから、どちらかをきちんと勉強すべきでした。
成田:この章は、むしろ中庸が大事ということではないでしょうか。異端とは両方の端であって、道を究めても究めすぎると道の端まで行ってしまい、極論に行き着くものです。そこまでゆくとダメで、中間に中庸がある。
小田:なるほど、やりすぎはいけないと。
成田:トコトン突き詰めると、もともと意図していたものの正反対の害となる。
高津:それでは「器」になるでしょう。孔子はいつも、足らざるところを指摘される。成田さんの言う中庸の解釈がよく分かる。
成田:この章は、次の子路への言葉と併せて読むのがいいでしょう。何でもつきつめて分かるまで突き詰める、これはいけない。分かっていることと、分からないこととを分けるくらいがいい。人知の限界を知ることが、肝要です。
小田:自然科学ならば、そのように「宇宙にはまだ人間が解明できない謎がある」といって自重することもできます。しかし経済学は人間のやっていることの解明なものですから、経済学によって全部説明ができないといけない。解明できない、分からないなどという逃げは、経済学では許されません。近代経済学もマルクス経済学も、だから全ての経済現象について、もっともらしい説明を用意しています。しかし、現実の経済にはどうも理論と合わないことがある。そんな場合に指摘されると、それはお前の解釈が悪いだけだといって、理論を修正したりはしません。経済学では、自学派から見た異端は罵る対称です。それこそ「異端を攻めるのは害あるのみ」と両側が言います。
成田:経済というのも、:うまく行っているときは万事が中庸のあたりにあるのではないでしょうか?
高津:孔子の時代も一つのことをやってはいけないと言います。農法については老農に聞いてくれ、知らないとして、自らは政治に特化している。だが朱子のように、どれか一つの学問しかないということではない。前の章は、学ぶのみでなく、核心がわからないと意味がないとしていた。この章は、むしろ何も考えない事が異端ではないかという風に思えます。
早川:『論語補疏』には別の解釈が置かれていまして、「攻」を「秩序立てる」と解釈して、「斯害也已矣」は通常「それ害あるのみ」と読みますが、これを「それ害や已(や)まん」と読みます。つまりこの章は「異端を秩序立て(て整理す)ると、害はなくなるだろう」と解釈するのです。違うと思うけれど、面白い解釈だなと思いました。この解釈は、異端つまり異なった考え方を比較して、それぞれの関係をあれこれ考えて整理した結果、相矛盾しない総合ができる。もともとあった敵対関係が無くなるだろう、という読み方です。
小田:学者の研究姿勢はかくあるべし。それに引き寄せた読み方ですね。
早川:まだ別の解釈として「攻」をそのまま「攻める」と解釈して、「異端を攻撃するのは害あるのみ」と解釈する説もあります。孔子は、自分と異なる思想であっても、それを攻撃したことは見当たらない。この章は、異端であってもそれを攻撃することなどは害しかない、という孔子の戒めだとか。
小田:その解釈ならば、孟子は一番害があるでしょうね。彼は異端に対して徹底的に論争したわけだから。
早川:更に別の解釈として、さきの二つの読み方を組み合わせて、「異端を攻撃することで、異端の害がなくなるだろう」という解釈まであります。
小田:それを聞いたら、孟子が喜ぶでしょうね。
成田:しかしいずれも異端を儒教以外の思想ととらえるならば、古注・新注のパラダイムからは出ていないです。孔子の時代に異端はあったかどうか?という疑問がない。
高津:孔子は自分と意見が違う人にも聞きに行った。むしろ討論をしたいと望み、自分と違う考えの人を害とは思わなかった。
小田:伝説では、孔子はライバルの老子にすら礼を学んだと言いますね。
成田:孔子は常の師なしの人ですから。
高津:老子は存在しない、ただの老人だと成田さんは昔おっしゃってましたね。孔子はだから老人に学んだ。
成田:今もそうです。
北澤:楊・墨とはなんですか?
小田:楊朱は、いちおう道家の一派とみなされています。ただ自分の著作がなくて、後世の『列子』の中に若干まとまったエピソードが収められています。孟子にとって、楊朱と墨翟は最大の異端でした。
高津:孔子と墨子は似ているという人がいますが。
成田:墨家は、過激派の代名詞ともなった。今でいうところのアルカイダみたいなものかな。確かに墨家は敵を攻めることはないが、敵から守るためには何でもやりました。エゲツナイ防衛手段を用いたりもします。「墨守」という言葉が現在でも使われるように、堅く守るのが彼らでした。
早川:墨家は、さらに薄葬論を展開して、音楽を否定します。儒家の反対です。
高津:孔子も葬式を贅沢にせよとは言っていない。心の問題としている。
成田:戦国時代の儒家と孔子とは違います。戦国時代の儒家は礼楽の専門家で、礼楽には金がかかります。それに比べれば墨家は薄葬で安上がり、おまけに城も守る。そういって諸侯に売り込みました。
小田:そのうえ墨家は兼愛を主張して、赤の他人でも利害抜きで働こうとしました。儒家は身内優先で、行動はより実利的です。
成田:身内も他人も関係なく愛するという墨家の兼愛の行き着く先は、儒家の孝の否定につながります。親の葬式を立派にすることも根拠を失い、儒家の行為が否定される。
小田:墨家の思想は、キリスト教に近いとも言われます。キリスト教もまた赤の他人を愛する隣人愛を主張し、無償の愛を主張します。
早川:だけど墨子の本だけを読むと、どうして生計をたてていたのか。また孔子が弟子を引き連れてどうして学派の糧を得ていたのか。謎です。
小田:墨家は職人集団が主な担い手だったから、各国で城作りとか土木工事とかの職を得ていたのではないでしょうか。孔子放浪時代については、きっと子貢が金を工面していたのでは?
高津:墨子のことは「墨攻」の映画を見るまで知らなかった。日本に来てからはじめて墨家を知った。日本では墨家が重視されている。
成田:そうでもないですが、、、中国では、もう墨家はいません。朱子学の前の時代、唐代くらいまでは、墨子は一定の評価を得ていました。墨家は孔子と並べられて、両者は不遇な賢人として慕われていました。
高津:墨子のことは日本の漫画「墨攻」で知りました。
早川:墨子と孔子は、賢人で不遇でした。かつては「墨子の家の煙突は黒くならず、孔子の席は暖まることがなかった」(炊事をする暇もなく、座っている暇もないほど忙しかった)と並び称されていました。(「墨突不黔、孔席不煖」と成田君)
小田:その二者に脛の毛がすりきれるまで働いた禹を加えれば、生涯忙しく働いて疲れ果てた三人ですね。
成田:禹は孔子・墨子と違って、成果を挙げましたがね。
小田:『列子』の中の楊朱の言葉では、禹と孔子が他人のために働きつめた者の例として、セットで挙げられています。この『列子』は晋代の著作で、中に書かれている楊朱の言葉とされているエピソードがどこまでオリジナルであるか、ちょっと分からないです。その中には、たとえば子貢の子孫の端木叔が一代で己の快楽のために先祖の財を食い潰したことを、貶すどころか称えたりしています。他人の為に何かをして何か益があるなどというのは愚かな幻想で馬鹿げたことであり、本当は他人のための行為などは、苦痛なだけで何も残らない。だから人は短い一生のうちに己の快楽だけを求めるのが真の道である、などというのです。
早川:『列子』には晋代の仏教色が濃いと言われていますので、中に入っている楊朱の説にも、仏教の色が見えます。ところで子貢の子孫「端木」氏は今でも続いていまして、当世の端木さんはなかなかの美人です。
北澤:仏陀の言葉を「淫聲美色」とありますが?
成田:仏教の禅と朱子学は、かなり近いものを持っています。だから学ぶ者は仏教を耳に心地よい音楽や見かけだけ美しい女性のように、表面の美に惑わされずに遠ざけなければ、取り込まれやすいと言うのです。
早川:じつは、朱子学の理気論や体用論などは、先行する仏教の中にすでに理論の枠組みが見られたりします。
成田:つまり、朱子学は仏教理論をパクったといえます。
早川:それで朱子学は、口を極めて仏教を罵ります。
成田:なまじい近いから、危うい。
小田:声を大にして批判する者は、内心不安なのです。内心で相手に対して自信がなくて、負けるかもしれないと思っているから、声を荒げて罵るのです。
北澤:普通には、仏教はそう見られていたのですか。
成田:儒家にとっては、見た目がよいので取り込まれるから注意せよ、と言われるほどでした。
北澤:取り込まれると、どこが悪いのですか。
小田:儒家が仏教徒に信徒を取られるわけですから、商売あがったりでしょう。この宋代に儒学が盛んでしたが、同時代に中国に渡った日本人は、栄西とか道元とか、もっぱら仏教を学んでいました。少なくとも同時代の日本人にとって、宋代の中国は仏教の国、禅の国で、儒学の国ではなかった。日本人が宋代の儒学を学ぶようになったのは、ずっと後の江戸時代になってからです。
高津:仏教は唐では保護されていたが、宋になってダメになった。
成田:唐代で仏教を保護し過ぎて、危機を感じた儒家が挽回を図りました。
早川:仏教を保護すると、税金を納める人が少なくなります。
小田:僧侶は無税だし、寺に土地を寄進するようなこともあって、ますます税金がとれなくなりました。
北澤:当時の時代には、普通の人々の生活は仏教だったのでしょうか、儒教だったのでしょうか。葬式とか、、、
早川:基本的には儒教がベースですが、時代により色合いが異なり、唐代は仏教が濃かった。宋代でも葬儀は仏式が基本でした。儒家たちが、それに代わって儒家式で葬儀を執り行ったことが、記録に残されています。記録に残されているということは、もの珍しかったからです。
小田:周囲から見れば、けったいなことをする奴らだ、と思われていたということでしょうね。当時の儒家たちは仏教を排して奇行を行う連中だった。
高津:葬儀で白い服を着て、泣き、お札を燃やす。これは儒式ですか?
成田:道教と儒教の折衷じゃないですかね。
早川:ややこしいことに、時代が下ると三教帰一の思想が現れてきます。つまり道教、儒教、仏教はその根本は同じなのだ、という考えです。こうして、なんでも有りがたいものは一緒に混交してしまいました。
成田:台湾の道観でも、孔子の横に老子が堂々と祭られています。何でもありです。
小田:香港の道観では、中に入ると観音菩薩が置いていました。なんだこりゃ、仏教寺院じゃないか、と思いましたね。
北澤:香港は関帝を祀るのではないですか?
小田:そうですね。関帝廟があります。しかし関帝は道教の神ですが儒教にとっても帝号を追贈される偉人の一人であり、確か仏教の菩薩の号も持っていたはずです。これもありがたかったらなんでも祀る、という多神教的発想のうちにあって、日本とその辺は事情は同じです。西洋のように、キリストやアラー以外は異端として殲滅するような激しい一神教は、東アジアの宗教観ではないということでしょう。朱子学の仏教排斥の激しさは、東アジアの宗教観とはずれていると思いますね。
早川:中国の山奥のお婆さんが、毛沢東の塑像を祀っていたという話がありました。それを恭しく礼拝して、自分は一番の共産主義者だ、と自慢なさっていたとか。毛沢東もまた、ご利益がある神と化しました。
高津:戦国時代の儒家は、孔子にとっては異端じゃないですか?孔子の本来の考えは、もっと広い。
小田:墨子もまた、人から儒家を批判するのにどうして孔子を称えるのか?と聞かれたとき、「是れ其の当にして易(か)うるべからざる者なり、、、今翟曽(およ)そ孔子を称えること無からんか。」(それは、彼の言っていることが理にかなっていて変えられないからだ。それがしが孔子を称えなかったことなど、全くありません。)と答えたといいます(『墨子』公孟篇)。墨子はもと儒家の門徒であり、それに飽き足らずに去って自派を始めた人です。きっと墨子は、自分こそが孔子の正しい後継者だと思っていたのかもしれませんね。孔子の言葉として現在残っているのは、あくまでも後世の儒家にとって都合のよかった孔子像に適合した言葉です。実際は孔子はもっと多くのことを言っていたのかもしれず、その中には墨子の主張に取り込まれた内容もまた含まれていたのかもしれません。それが、後世になると儒家と墨家として、相容れない対立思想となってしまった。
早川:『荘子』の中にも孔子が出てきますが、そこでは顔回が大活躍するのが面白いです。きっと顔回が夭折せずに大成していたならば孔子を超える人物となっていたに違いない、という願望があって、彼の回りにいろいろな伝説が作られて、荘子のエピソードのように後世発展したのでしょう。
時間となりました。今週も一杯なし、「一揆」のマスターも首をかしげておられるでしょう。
2012年3月17日(土)孟子公孫丑章句下
本日、小田さん、高津君、上田さんの三人。
本日部分の音読。小田さんお願いします。
孟子臣爲ることを致(かえ)して歸る。王、就(ゆ)きて孟子を見て曰はく、前日見んことを願(のぞ)んで得可からず。侍することを得て同朝甚だ喜ぶ。今又寡人を棄てて歸る。識らず、以て此れに繼いで見ることを得可き。對へて曰く、敢へて請はざるのみ。固より願ふ所なり。他日、王、時子に謂りて曰はく、我中國にして孟子に室を授け、弟子を養ふに萬鍾を以てし、諸大夫、國人(くにたみ)をして皆矜式(きょうしょく)する所有らしめむと欲す。子盍ぞ我が爲に之を言はざる。時子、陳子に因りて以て孟子に告げしむ。陳子、時子が言を以て孟子に告ぐ。孟子の曰く、然り。夫(か)の時子、惡んぞ其の不可を知らん。如(も)し予をして富を欲せしむれば、十萬を辭して萬を受く。是れ富を欲すとせんや。季孫曰く、異(あや)しいかな子叔疑。己をして政を為さしめ、用ゐられずば、則ち亦已(や)まん。又其の子弟をして卿爲らしむ。人も亦孰か富貴を欲せざらん。而れども富貴の中に於て獨し、龍斷を私すること有り。古の市をするは、其の有る所を以て其の無き所に易ふるは、有司の者、之を治むるのみ。賤丈夫有り、必ず龍斷を求めて之に登り、以て左右に望みて市の利を罔(あみ)す。人皆以爲へらく、賤し。故に從ひて之を征す。商を征すること、此の賤丈夫より始まれり。
孟子は臣たることを辞して帰った。斉王が、行って孟子に会見して言った、「先日それがしはあなたに会見しようとしたが、出来なかった。だが今朝廷で会えて、うれしいです。ところが先生はそれがしを捨てて帰ろうとしている。どうでしょうか、これからも継続してお会いできないでしょうか?」と。孟子は答えた、「こちらからお願いしないだけで、私も元よりそれを願うところです」と。後日、斉王は家臣の時子にこう言った、「私は、斉の国の中で孟子に屋敷を与えて、弟子を養うために一万鍾の俸禄を与え、諸大夫・国人に先生を敬うようにさせたい。君は、私のためにこのことを告げてください」と。時子は陳子に依頼して、孟子に伝えさせた。陳子は、時子のことばを孟子にとりついだ。孟子は言った、「そうか。あの時子は、そんなことは不可能だということを知らない。もし私が富をほしいとするなら、十万の禄を辞退して何で一万を受けようか。これで富をほしいというか(決して欲していない)。季孫は言った、『子叔疑は奇っ怪な奴だ!(ここで出てくる季孫と子叔疑について、朱子は「何れの時の人を知らず」としている。季孫は、孔子と同時代の魯の季孫氏だという説もある。)そもそも君主が自分に政治をさせようとして、政策が用いられなければ辞職すべきである。それにもかかわらず、彼はまた自分の子を大臣に就かせている。人たるもの、どうして富貴を欲せないでいられよう。しかし、彼は一人富貴の中に居て、龍斷して私で独り占めしている』と。いにしえの市場では、余っているもので足りないものを交易するのであって、役人は、裁判をしていただけであった。ここに賤しい男が現れて、この男は必ず小高い場所に登り、龍斷(ろうだん、原義は高い所に登ること)して左と右を見比べて、市の利益をさらった。人は皆、この男を賤しいと考えた。だからこの者に対して税をかけた。商売に税をかけるのは、この賤しい男から始まったのだ」と。
小田:この章は、「壟断(龍斷)」の語の出典です。「断」は崖・高い所で、「壟(龍)」は登るという意味です。これまでの章で斉は燕の出兵に失敗して、この章から孟子が斉を去る話となります。ここで斉王は孟子を引き留めようとしていたといいます。これは、しかし王が賢者を引きとめようとする演出を行ったのかもしれませんね。
上田:卿を辞退したんですね。
小田:そうです。
上田:誰かを通じて王に辞任を告げ、王は孟子に会って、これからも会えないかと言うと、孟子は、本当はそうしたいが私の方から請うことはできないとした。それで、後日、王は時子に、孟子を家臣ではなく、師として禄を与え、斉に置くという提案をし、時子はこれを孟子の弟子、陳子を通じて伝えた、このようなやり方で双方の関係が噛み合わない・・・
小田:いや、これは朝廷として通常ではないですか。現代でも大臣が内閣を辞任するとき、直接首相に告げることもありますが、通常は辞表を事務官に提出して役所的手続きを踏みます。孟子は、辞表を役人に提出して、斉王が受理したのでしょう。それで、後日に会見の場をセッティングして直接意見交換をした。
高津君が参加、これまでのまとめを小田さんが説明。また、高津君のリードで本日分再度音読。
小田:この章ですが、私は改めていま読み返してみると、斉王と孟子とが事前に打ち合わせて演出したのかもしれない、と思ってしまいます。双方が、互いの面子を潰さないように引いている。ここまでの叙述では明言されていませんが、孟子が辞職した原因は、ぜったいに燕侵攻の失敗の責任を取ったのでしょう。しかし、孟子は勇退するという名誉ある形で去ることにした。斉王は、孟子が留まらないことを知っていながら、あえて賢人が惜しいという姿勢を取って、引きとめた。それに対して、孟子は金のために斉にいたのではないという言葉を残して去った。孟子は、去る前にきれいな言葉を残して去る必要があったのでしょう。それに斉王が応じて、斉王としては賢者を惜しむ仁君だという演出を行った。ふたりの間では、打ち合わせどおりだったのではないですか。斉の家臣には、孟子に責任をとらせて処罰せよとする意見もまたあったでしょう。しかし、斉王はこの時まだ仁君として本気であり、賢者の孟子に対して失礼をしないように心がけた。しかし、もはや斉に置くことも出来ない以上、孟子の面目を立てて、かつ斉王が孟子を追い払ったのではないというきれいな形で終わらせたのではないでしょうか。
告子章句下の六で、孟子と淳于髠(じゅんうこん)との問答があります。淳于髠は稷下の学士の一人で、孟子に厭味たっぷりに言う。「先生は斉の三卿(さんけい。大臣職)に名を連ねておきながら、名声も実績もいまだに上の国君から下の人民までの間に増したとはいえない。それで今、この斉を去ろうとしておられる。仁の人とは、元来このようなことをするものなのですか?」とか。これに孟子が反論するという展開ですが、きっと斉の国の中では、彼に代表されるような孟子への批判が相当にあったのでしょう。淳于髠は史記の滑稽列伝にも出て来る著名人です。そこでは斉王をユーモアで説得した人として、高く司馬遷の評価を得ています。おそらく、賢人だったのでしょう。しかし、斉王は孟子の面子を崩すようなことを、行わなかった。斉王は天下を望む君主であり、天下の賢者の孟子は、私利私欲で斉にいたのではなく、天下を安らげる策を授けるためにいた。そのような後味を残したかったのでしょう。孟子だけを読むと斉王はただの暗君のように見えますが、ここで孟子を勇退させたところなどを見ると、まるっきりの阿呆ではなかったでしょう。
高津:斉は燕を攻めたが約束を破った。太子(平)との約束を破り、内乱の首謀者を殺すだけでなく、太子が屈辱を受け、後に宣王が攻められるのいうやつですね。この前の章で、「昔の君子は、過ちがあると改めるが今の人は言い訳をする」と孟子は言っています。子貢の言葉にも「君子は日月のごとくその過ちを隠さず、改めるところを誰もが見てそれを仰いだ」(子張篇)というものがあった。また論語には、斉の王が家臣に弑されたとき、孔子が斉を攻めなさいと進言した。燕の場合もそういうことがあって、斉が攻めるべきとしたのでしょうが、内乱を治めた後に、太子を輔佐しておればよかったんですがね。
小田:内乱を鎮めた後すぐに撤退するのが、最も斉にとってよかったでしょう。正義の戦争をすべきであり、孟子もそのつもりで進言したのでしょう。史記では、孟子が斉王に攻めるべきだと進言した、と明言しています。ところが、斉は撤退せず併合を企んだ。怒った太子が斉に対する反乱軍を組織して、諸外国も斉を討伐すべきだという意見が高まって、斉は追い詰められて怨まれ、撤退しました。その後、孟子は斉の大臣を辞して去っています。
高津:歴史に"もし"はないが、内乱を助け、撤退していれば歴史は変わったでしょうね。
小田:なぜ斉が燕を併合しようとしたか、については歴史書にはっきり書かれていません。
高津:当時は皆、虎視眈々として覇者になることを狙っていた。秦は金を使って、斉と燕を戦わせたと言います。秦の思惑どおりになったのではないですか。
小田:戦国時代の外交戦は虚虚実実で、歴史書に書かれていることの裏側では、えげつないやり取りが飛び交っていたはずでしょう。当時、斉と秦が一番覇者に近いところにいて、東西の二大大国でした。燕の太子平は斉の撤退後に即位して燕の昭王となりますが、彼はこの30年後に将軍楽毅を登用して斉を攻めて、斉は一時領地のほとんどを失い、後に国は復興しましたが、斉の力は衰えてしまいました。斉が攻められたきっかけは、南の宋を併合したことでした。その結果対斉連合軍が成立してしまい、周囲から袋叩きに会って没落します。
高津:孟子は菅仲になれなかった。菅仲は燕を救援し、燕の荘公が感謝し国境を越えて見送ったとき、そこまでを燕の領土としたんですよね。
小田:覇者たるもの、約束は守る。これを実現したことによって、管仲は桓公の名声を高めることに成功しました。損して得取れです。結果、斉のリーダーシップに諸国は従い、斉の出した法度は諸国で守られることになりました。孟子は、自分は菅仲や晏嬰より上だと思っていました。ところが実際の政治では、管仲のように領地を望まず君主の名声を高めることができませんでした。
高津:何故、孟子は菅仲のようにできなかったのでしょう。
小田:政治というのは、奇麗事を奇麗事として通すためには、強力なリーダーシップが必要です。正義の軍という建前だけでは、汗をかく家臣は納得できません。リーダーとしては、家臣をいい目にあわせる必要も考えなければならないこともあります。日本では、武田信玄と上杉謙信とではリーダシップのあり方が違っていました。謙信は戦争をしても、領地を望みませんでした。彼の戦争は領土野心からではなく、秩序を守ることを名目としていました。それでも家臣を率いることができたのは、彼のリーダーとしてのカリスマがあったからでした。いっぽう信玄は、家臣団に恩賞を与える必要があることを分かっていました。だから、領地拡大に熱心であり、家臣たちを実利で引っ張るリーダーシップに巧みでした。戦争には、費用がかかります。戦争に勝てば、負けた国から富を奪って費用をまかない、敵国の土地を家臣への褒章に充てるのは、組織として間違ってはいません。費用も賄わず、褒章もなしで正義の軍を起こすためには、よほどにリーダーの統率力と信念が必要でしょう。
高津:謙信のようなやり方もあるということです。ええっと、誰だったかな、生きている間、秦が恐れをなして攻めて来なかったという人物は。趙が秦に攻められ援軍を出す時に、一人で向かっていった、、、
小田:魏の信陵君無忌ですね。魏王は秦が怖くて兵を出さなかった。それで信陵君は、王の軍隊を盗んで趙の救援に行く。
高津:私はこの人が大好きなんです。肉をさばく人、ええっと、朱亥ですね。朱亥に会いに行って話をしている間、立って待って、知り合いになる。秦が趙を攻めた時、今お返しをする時と、助けになる・・・
小田:信陵君は、門番の侯嬴と肉屋の朱亥を賢人と見抜いていました。彼は両名の低い身分に関わらず厚く礼遇しましたが、二人は感謝すらしませんでした。ときに趙が秦に攻められ、魏王は秦を恐れて趙に援軍を出すことを行いませんでした。信陵君は、わずかな手勢を率いて趙を助けて死にに行こうと決意しました。このとき、ついに二人はこれまでの恩に報いるために立ち上がりました。侯嬴は、信陵君に魏の軍を盗む策を授けました。そして自分は年老いているので、今後の側近として朱亥を連れて行けと言い残しました。
高津:侯嬴は自分のやったことが許されるものでないことを知っており、自害する。軍を動かすには、王と将軍が互いに半分ずつ持つ割り符が必要でした。信陵君は侯嬴の策に従い宮中から割り符を盗み出し、将軍の晋鄙に見せて軍の引き渡しを要求しました。だが晋鄙は名将で、割り符が偽りであると疑い、軍を渡しませんでした。それで朱亥が将軍を殺して軍を動かし、ついにギリギリのところで趙を救いました。
小田:しかし、信陵君は魏王を偽った罪で趙に亡命しました。今度は、魏が秦に攻められました。魏王は信陵君に出馬を要請しましたが、信陵君はこれまで自分を罪人して扱ってきた王の命に応じようとしません。そのとき彼の側近が、あなたは魏あっての存在ではないか、魏が滅んで宗廟が壊されたら、どこに立つ瀬があろうか、と説きました。ここに信陵君は翻意し、魏を救援する軍をもって故国に駆けつけ、秦を撤退させることに成功したということです。
高津:信陵君は戦国の四君の一人。
小田:魏の信陵君、斉の孟嘗君、趙の平原君、楚の春申君ですね。
高津:一番素晴らしいのは信陵君。宣王の場合は、結果的に欲にかられて、うまくゆかなかった。
小田:横にいた孟子は、菅仲はたいしたことはないとまで豪語していたんですがね。
高津:管仲は、桓公の絶対的信頼を得ていた。成し得たことは孟子は菅仲の下です。燕を討つ時、孟子は誰が討つべきかを聞いてくれなかった、聞かれたら「天吏なら討ってよい」と言ったはずだ、と書いています。孟子は、言い訳はたつが、重要なところで、言葉が足りないようです。
小田:後から言ったように書いているのは、言い訳でしょう。実際は、孟子は正義の軍としてはっきり出兵を進言したはずです。だが斉王にすれば、先生のお墨付きをもらったと解して出兵した。孟子は、斉軍が本当に正義の軍として撤退できるか、斉国とはそのようなことができる組織であるかまで考えて、進言したのでしょうか。
高津:孟子は言うだけで実際には戦場には行っていない。菅仲は現場にいて指揮をとっていた。孟子は菅仲より知恵はあったかもしれないが、現場を知らなかった。
小田:孟子は、王の前での弁舌を行う才はありました。だが、実際の政治や軍隊において、適宜政策的な判断ができたかといえば、どうだったでしょうかね。彼は思想家として原則を述べることには巧みでしたが、政治家ならば、現場の動静をよく掴み、流動的な情勢の変化に対して的確な判断ができなければなりません。管仲はそれができたけれど、孟子にはそこはなかったかな。
高津:昔の人は「述べて作らず」という枠、政治家ならここまでしなければならないという大局を見る資質があった。
小田:ただ、管仲の時代と戦国時代では、国家組織の規模が違っていました。かつての時代ならば、一つの邑の運営からそれほど飛躍しない程度の、顔の見える政治ができたことでしょう。しかし戦国時代では人口は激増し、軍隊や朝廷の規模も膨れ上がっており、一人の政治家では全体を把握することはできなくなりました。
高津:論語の中では、武王が"乱臣(治める臣)十人"ともあり、王がすべてを知る必要は無く、正しい方向性を示せばよかった。規模というより、上に立つ人の資質によると思う。
小田:斉王は、そういう君主になりたかったことでしょう。孟子を読むと斉王はたいした君主ではないようにみえるが、そこまで馬鹿じゃなかったはずです。
高津:宣王は、結構国民にも愛されていたのではないですか。
小田:ただ、正義の軍という建前を家臣に押し通すためには、非常のリーダーシップが必要ですが、宣王はそこまでのずば抜けた君主ではなかったでしょう。
高津:孟子は現場に行くべきであって、それが出来ておれば菅仲より上になれた。
小田:宣王だって、文王や武王を目指したはずです。そこまでの資質がなかったといえばそれまでですが、組織が複雑になった時代で、求められる君主の能力が昔よりもはるかにハードル高くなった時代に、ずばぬけた有能さを彼に求めてもいたし方ないことです。
高津:皆、覇者になりたかった。
小田:天下を統一する、記念すべき王になりたかったことでしょう。『孟子』に書かれているような、私利私欲だけの王ではなかったはずです。孟子は彼に仁君になれ、そうすれば天下も取れると説いたのです。
高津:しかし孟子は仁政を行えなかった。
小田:理論通りにはゆかなかったが、理論は後世に残さねばならない。それで、理論を残しました。しかし斉にいた時代には、斉王をたてて天下取りを望んでいたことでしょう。
高津:孔子もそういう人がおれば、もっとできたかもしれない。
小田:君主に愛されるという点では、孟子は孔子を凌駕していたと思います。
高津:王様の思いを見抜いている。衛霊公篇で、子貢が仁を為すを聞いている。その国で、「其の大夫の賢なる者に事へ、其の士の仁なる者を友とす」、それに合わせていればよい、自分のやりたいことを分かってくれないと力が発揮できない、自分を後押ししてくれる人を求めた。
小田:孔子は、自分に合う君主を求めてさ迷い歩いたと言えるでしょうか。いっぽう孟子は自分の領域に君主を引きずり込んで、相手を合わせてしまいます。宣王たち君主はすっかり信者とすることができましたが、しかし実際に政治を行うと、理論どおりにいきませんでした。
高津:孟子が孔子を受け継ぐのであれば、斉の宣王にやったことはダメであり、理想とする政治は行えなかった。
小田:孟子は、後に、宋や滕という小国へ行きます。孟子の思想家としての意地を感じますね。斉という大国だけで自分の思想が行われるわけでない。斉の後に、それに比べれば芥子粒ほどの小さな国に行って、持論を説きました。金のために遊説しているのではない、理論を広めるためなのだ、という姿勢を行動で示したのです。孟子は、思想家としては立派でした。
高津:孔子と一緒で時代を読み切れなかった。実質は、秦が統一したようなものであった。
小田:結局、戦国時代は王道ではなくて、武力による統一で終わりました。しかし、孟子や宣王の時期には、まだまだ一国が武力で統一できるほど強大な存在はありませんでした。
高津:秦には地の利があったとされてますね。函谷関を越えて攻めきることはできない。破れることはあっても秦を追い詰めるところまではゆけない。
小田:秦は蜀を手に入れて、豊かな土地を増やして強大化しました。西から攻撃されることもなく、東は函谷関で守られて、守るに易く、攻められるに難い地勢でした。
高津:孟子にはチャンスがあったと思います。
小田:二大強国の一方の国の王に気に入られ、孔子よりよほど天下の権力の中心に近い所にいました。もしうまくやれば、もっと実績を残せたかもしれませんね。孟子は世渡りはうまかった。結果的に、斉からは勇退の形で帰還しました。そのあたりの手抜かりはなかったですね。死んじゃった韓非子とは、明暗を分けています。
高津:韓非子は失脚というよりは、どうしようもなかった。
小田:韓非子は、始皇帝にその思想をいたく気に入られていました。そこだけは、孟子と同じです。
高津:李斯と韓非子の師は荀子でしたね。
小田:李斯は、韓非子が秦の朝廷に採用されれば自分はかなわないと思い、韓非子は韓のスパイであると始皇帝に讒言したとか。始皇帝は騙されて韓非子を投獄し、韓非子は毒を渡されて死ぬ。それが、公式の歴史書に書かれていることです。
高津:韓非子が死んだとき、始皇帝は驚きました。
小田:しかし、李斯を断罪していません。
高津:韓非子の書物を手に入れた。
小田:始皇帝は、韓非子の思想を重視しました。しかし、韓非子は韓の一族であり、彼の立場は韓を存続させるところにありました。それで、政治家として始皇帝はこれを野に放ってはいけない、と判断したのではないでしょうか。だから、毒殺されたのも規定路線だったのではないでしょうか。しかし斉王は、孟子のことを野に放っても危うくないと考えたのでしょう。孟子に対して、「あんまり悪口を言わんでくれ」ぐらい言っておいたでしょうかね。
高津:稷下の臨淄に諸子を集めたのは宣王ですか?
小田:歴代の斉王の政策ですね。孟子から半世紀ほど後の荀子もまた、斉の都で研究活動を行いました。
高津:孔子が戦国時代であれば、どうなったでしょうか。
小田:孟子はご本人にはカリスマがありましたが、いい弟子がいませんでした。孔子はご本人は君主に取り入るのがうまくありませんでしたが、弟子は多士済々で、才人勇士が揃っていました。もしかしたら、弟子たちで斉の政治を乗っ取ってしまったかもしれませんね。
よもや話に脱線し時間となりました。久方振りに三人で一揆で一杯。上田さんはウーロン茶一杯。君子と小人について、高津君、熱く持論を語るの夕べとなりました。
2012年3月24日(土)孟子公孫丑章句下
本日、小田さん、高津君、上田さんの三人。
高津君のリードで本日部分の音読。訓読と訳を小田さんお願いします。
孟子齊を去りて、晝(ちう)に宿す。王の爲に行くを留めんと欲する者有り、坐(ざし)て言ふ。應へず、几に隱(よ)つて臥せり。客悦びずして曰く、弟子齊宿して而して後に敢へて言ふ。夫子臥して聽かず。請う、復敢へて見ること勿けん。曰く、坐せよ。我明らかに子に語(つ)げん。昔者魯の繆公(ぼくこう:穆公)子思の側に人無んば、則ち子思に安んずること能はず。泄柳(せつりゅう)・申詳(しんしょう)、繆公の側に人無けれは、則ち其の身を安んずること能はず。子長者の爲に慮りて、子思に及ばず。子長者を絶つか。長者子を絶つか。
孟子は斉国を去って、昼(ちゅう)の街に宿泊していた。斉王のために、孟子が行くのを引き留めようと望んだ者がいた。彼は坐って、孟子に話をした。孟子は応えず、「几(き)」にもたれ寄りかかったままでいた。客は喜ばずに言った、「それがし、謹んで敢えて申し上げる。先生はねそべって私の話を聞こうともなさならない。もう二度と会いたくありません!」と。孟子が答えた、「坐りなさい、私が君にはっきりと語ってやろう。昔、魯の繆公(ぼくこう)は子思(孔子の孫)の側に誰かがいなければ、子思を安んじて引き留めることはできないと思った。泄柳・申詳(せつりゅう・しんしょう。同時代の魯の賢人らしい)は、繆公の側に誰かがいなければ、己の身を安んずることができなかった。君がこの長者(年長者、つまり孟子が自称している)のために配慮していることは、繆公が子思に対して行った配慮にすら及ばない。君がこの長者を絶交するのだろうか?それともこの長者が君を絶交するのだろうか?」と。
小田:「几」とは、ブーメラン状の板に足をつけた肘掛けで、三国時代の遺跡から本物が出土しています。古代の中国は、日本同様に板の間にムシロを敷いて正座していました。正座は正しい座り方であり、家臣や年少者、弟子の座り方です。これに対して諸侯や年長者、師匠は、くつろいで足をほどき、この「几」に肘をかけて体を横たえることが許されていました。しかし中国では唐代あたり以降は椅子が用いられるようになって正座の習慣が滅び、それと同時に「几」は中国で使用されなくなりました。ところが日本は古代中国の風習が古い時代におそらく導入されて、そのままずっと後世まで残りました。つまり正しい座り方は畳の上に正座することであり、「几」と同じ形の肘掛けは、江戸時代の殿様がくつろいで家臣と謁見する際に用いられていました。次に本章で孟子が言う「坐せよ。子に明らかに語(つ)げん」という言葉ですが、これはしばしば古典に表れます。師匠が弟子に対して説教を行うときの決まり文句です。論語、陽貨篇1の「來れ、予爾と言はん」も同様です。つまり、孟子はここで客に対して、師匠が弟子に説教する態度で発言していたのです。
上田:王の為に孟子を引き留めるとし、孟子が会っている所を見れば、本来は孟子も王もよく知っている名の分かった人物だろう、王の意向を受けていたのかもしれないのでは。
小田:私は、この章の内容から解釈して、この客は単なる点数稼ぎを行おうとして独断した家臣にすぎない、と考えるしかないと思います。ここで孟子を引き戻すことができれば、斉王に感謝してもらえると思ったのでしょう。朱子は、「齊王、子をして來らしめず、而るを子自ら王の爲に我を留んとす」と注しています。朱子はこの客は王命で孟子の下に来たのではないと考えています。
高津:魯の穆公の側に人無ければ・・・とは?
小田:公は、子思のそばに彼を引き留める人を常に置いておかなければ、安心して子思を引き留めておくことができなかった、ということです。
高津:泄柳と申詳とは?
小田:当時の魯の賢者らしいですね。
高津:二人が穆公の側に人無ければとは?
小田:人とは、子思のことです。穆公の側に子思がいなければ、自らが公に用いられるかどうか不安であった、ということです。子思と穆公については、萬章章句下六、七にも出てきます。それによると、子思は穆公について高く評価していません。子思の本音は、公は仕えるに足る君主ではなかったというのです。そんな穆公は、子思を引き留めるために、そばに常に人を付けておりました。このことを引き合いに出して、孟子は斉王も本来なら自分を引き止めるための役割の人間を派遣しなければ、私を引き止めることなどできない。なのに王は人を派遣せず、この章で訪れた客は単なる独断でやって来たにすぎない。なんだい、斉王の私に対する姿勢は、あの穆公が子思に行った姿勢にすら劣るではありませんか。ならば去るしかない、というのが本章の言い分です。
高津:穆公に斉王は及ばない、ということですか。
小田:そう言いたかったのでしょうね。斉王は私への引き留め方が足りない。点数稼ぎに来た奴なんぞに一切応じる必要はない。お前は斉王の命で来たのじゃないだろう、と。
上田:この客は孟子が斉に残りたいという気持ちをもっていたことをよくよく知っていたのだろう。しかし、孟子が「王の意志として」を重要視していることを見誤っていた。
小田:孟子は斉に残りたかったとしても、斉王にとっては孟子を残したいとしてもできない事情があったと思います。孟子の中では明言されていませんが、私はおそらく孟子は責任をとって卿を辞職せざるを得なかったのだと思います。
高津:責任とは燕のことですか?
小田:前回言いましたように、孟子の進言によって斉は燕の内乱に介入しました。
高津:まずは、一応成功しましたね。
小田:内乱平定に成功した後、結局斉は不名誉な撤退となりました。
高津:燕を属国にした。
小田:斉は燕を併合しようとして、燕は反乱を起こしました。斉は占領が続けられず撤退に追い込まれ、隣国に怨みだけを残しました。
高津:孟子は属国にするのは間違いだと主張して、斉がいさぎよくそうしなかったから、自分の主張が容れられないので卿を辞任したのではなかったのですか?
小田:孟子を読むと、そういう風に読めます。しかし、孟子はじじつ斉が燕を占領している際に批判をしていますが、まだ卿のままです。ようやく燕で反乱が起こって斉の作戦が全面的失敗に終わってから、孟子は卿を辞任しています。卿という家臣の最高位で進言した作戦が失敗に終わったのだから、本人はどう言おうが責任を取って辞職したと考えるべきだと私は思います。(『孟子』では斉にいた時の自分に発言の責任はなかったのだ、と主張する伏線まで置かれていたのは、これまでに読んだところです。しかし、卿の立場でそんなことありえません。)斉王はどれだけ孟子を気に入っていたとしても、斉の朝廷ではおそらく孟子を引き留めることに反対する人の方が、多かったのでしょう。斉王が断固として家臣の意見を聞かず、孟子を引き留めてくれれば孟子は残ったでしょう。しかし、斉王はさすがにそこまで孟子を弁護できなかった。それで、孟子は去りました。
高津:去る際の問答は、歴史的背景が分からないと難しいです。
小田:孟子も、はっきり辞める理由を語っていません。孟子は、斉では理想がかなえられないので去ったというストーリーに仕立てて、自分には責任は無いといいたいのです。しかし、この時期にどうして辞めなければならなかったという背景の事情は、孟子を読んでもはっきり書かれていません。というか、書かなかったのだと思います。
上田:孟子はここでは、自分は残りたいが王が直接その意思を示さなかったことにあるとし、この後では、斉王がいい王になる可能性はまだあると、自分はなんとかして王を輔佐したかった、と自分から見限ったものではないという言い訳をする。
小田:斉王は卿としては無理であるが、大夫や士を教える師として斉に残ってほしい、と前の章で言っていました。斉王としてはこの辺が孟子へのギリギリの好意だったでしょう。しかし孟子としては、斉には政治を行いに来たのであり、道徳の先生をしに来たのではない、卿のままででなければ残る価値がない。しかし、斉王にはそれは出来ない相談であったでしょう。政治で失敗した卿をそのまま引き留めるなど、とてもできなかった。それで、前の章のような残ってくれ、いや残らない、といった問答が行われたのだと思います。
上田:孟子は、いわば礼を尽くして王の輔佐足らんと最後まで努力したということを次に言い、その後ではまた、違ったことも言う。
小田:孟子は礼を尽くしたが、斉王は賢者への礼を尽くしていない。だから去った。そのストーリーで孟子は書かれていて、孟子はその見方で読ませようとしています。おそらく孟子の同時代人にとって、孟子が斉を去った経緯は、周知の有名事だったでしょう。それは、司馬遷の記述のとおり、孟子の進言により斉王が正義の軍を起こしたが失敗に終わり、結果として孟子は斉を去らねばならなかったという経緯です。それが同時代人にとってあまりに有名であったために、孟子は本当はこういう事情だったんだ、去る時にも十分礼を尽くしていたんだ、やむを得なかったのだという言葉を残す必要があったのでしょう。
上田:原発事故では、議事録が残されていなかった。後で、菅さんは回顧録で実はこうであったとやるんでしょうね。
高津:斉には史官が居て、その経緯は記録で残されていたのではないんですか。
上田:あったでしょうが、残っていない。
小田:始皇帝は、六国を滅ぼした際に各国の資料を首都の咸陽に集めました。秦が滅びた時に、項羽が咸陽を焼き打ちしました。そのときに、六国の資料もまた焼失してしまいました。戦国時代の歴史は、漢代になって残された記録から再編されたものです。だが、六国の公式な資料が焼かれたせいで良く分からない点が多くあります。かえってその前の春秋時代の方がよく分かるぐらいです。
上田:孔子が魯を去ったのも、三桓氏の武装解除に失敗し、魯におれなくなったという政治的背景がある。
小田:孟子は、「孔子は魯で道が行われないから去った」ということを意識して、自分もまた斉で道が行われないから斉を去ったのだ、私は孔子と同じ進退をした、というストーリーにしたかったのだと思います。
続いて次を高津君のリードで音読、訓読と訳は小田さん。
孟子齊を去る。尹士人に語げて曰く、王の以て湯武爲る可からざることを識らざるは、則ち是れ不明なり。其の不可を識りて、然して且つ至るは、則ち是れ澤を干(もと)むるなり。千里にして王に見る、遇せられざるが故に去る。三宿して而して後に晝を出づ。是れ何ぞ濡滯(じゅたい)なる。士は則ち茲に悦びず。高子以て告ぐ。曰く、夫(か)の尹士惡んぞ予を知らんや。千里にして王を見るは、是れ予が欲する所なり。遇せられざるが故に去る。豈に予が欲する所ならんや。予れ已むことを得ざる。予三宿して晝を出づ。予が心に於て猶以て速やかなりとす。王庶幾(こひねが)はくは之を改めんことを。王如し諸を改めば、則ち必ず予を反さん。夫れ晝を出でて王予(われ)を追はず。予(われ)然して後に浩然として歸る志有り。予然りと雖も、豈に王を舍てんや。王、由(なを)用(も)て善をすること足れり。王、如し予を用ゐせば、則ち豈に徒(ただ)齊の民安からんや。天下の民舉(みな)安からん。王庶幾はくは之を改めんことを。予日々に之を望む。予豈に是の小丈夫の若く然らんや。其の君を諫めて受けざれば、則ち怒り悻悻(こうこう)然として、其の面に見(あら)はれ、去れば則ち日の力を竆(つくし)て、而して後に宿せんや。尹士之を聞きて曰く、士は誠に小人なり。
孟子は斉を去った。斉の家臣の尹士が、ある人に告げて言った、「斉王が湯王や武王のようになることができないと知っていなかったとすれば、孟子の不明である。斉王が湯・武になれないと知りながら斉にやってきたのであれば、恩澤(=俸禄)を求めるためであったということになる。孟子は千里の道を越えて斉王に謁見し、いま冷遇されて去ろうとしている。その彼は、昼(ちゅう)の街に三日も宿泊してから、去った。なんとまあ、(未練がましく)ぐずぐずしたことか!それがしは、彼のこんな態度が気に食わないですなあ」と。孟子の弟子の高子が、彼の言葉を孟子に告げた。孟子が言った、「何であの尹士に、私のことが分かろうか?千里を越えて王に会見したのは、私が望んだことである。冷遇されて去るのは、なんで私が望むことであろうか。やむをえず、去るのである。私は、昼の街に三日宿泊して去った。私の心の中では、これでも速く去ったと考えている。私は、王がなんとか態度を改めてほしいと願っていたのだ。王がもし態度を改めるなら、私を呼び返すはずだ(と思って、三日も滞在したのだ)。しかし、昼の街を出たが王は私を追わなかった。私はこのとき、心さっぱりと帰る決心がついた。たとえその時でも、何で私は斉王を見捨てるだろうか。斉王はあれでも、善を為すことができる人だ。王がもし私を登用すれば、ただ斉の民ばかりが安らかになるのではなく、天下の民皆が安らかとなるだろう。王がなんとか態度を改めることを、私は毎日望んでいるですぞ。私が、何で小人物のようなことをするだろうか?小人物とは、君主を諫めて受け入れられなければ、怒りの表情をムラムラと顔に出す。そして去る時には、太陽が出ている間できるかぎり進んで、日が暮れてようやく宿泊する(ぐらい、さっさと去る態度をするものだ。私は違うだろう?)」と。尹士は孟子のこの言葉を聞いて、言った、「それがしは、誠につまらない人間である」と。
小田:この章の、豆知識です。中国の元末に、張士誠(1321-1367)という群雄がいました。彼の名は、この章の「士誠小人也(士は誠に小人なり)」から取ったものです。士とはこの章で登場する尹士の名で、自分で自分の名を言って謙遜し、「それがしは誠につまらない人物である」と言ったわけです。人の名前の由来がこんなひどい言葉から出ているのは、おかしいと思いませんか?
高津:士誠というのは、悪い意味とは思えませんが。
小田:そうです。一見すると、よい字に見えます。背景があります。元末には中国の各地でモンゴルに抑圧された漢族の不満が爆発しました。南部の中国人は「蛮子」と言われて、とりわけ体制の中で蔑視されていました。その蛮子の中から、モンゴルへの反乱を起こす群雄が現れて乱世となりました。その中で最後に立った両雄が、朱元璋と張士誠でした。最終的には、朱元璋が勝って明朝を起こしました。張士誠は塩の商いをしていた人物で、力を持っていたが自らは学がありませんでした。それで、蘇州の士大夫たちをブレーンとして雇いました。中国で天下を取るためには、自分は馬の骨であったとしても、中国社会でステータスとして確立している読書人のインテリたちに支持されることが、ぜひとも必要だったのです。彼は読書人のインテリたちに、かっこいい名前を付けてほしいと望んで、士誠という名前をもらいました。本人は、死ぬまでいい名だと喜んでいたといいます。だが、実はその由来は、孟子のこの章でした。彼らインテリたちは、表で張士誠閣下を敬い、陰では小人だと嘲笑っていたのです。朱元璋は皇帝になってから、このエピソードを知りました。朱元璋もまたヤクザの親玉から皇帝に成り上がった人物であり、自分の下で平伏している士大夫たちが本心では自分を嘲笑していることを知って、心が冷えました。それで、彼の治世は中国史上最大級の官僚への大粛清に血塗られることとなりました。
さて、本章で言うには、孟子は三日間昼の街で待ったが、王は来なかったので魯に帰ったということです。
上田:孟子は斉に居たかった。斉王にはまだまだ可能性があり、補佐を続けたかったとくどくどと述べている、そういう印象を定着させたかった。
小田:孟子が斉にやって来た時期は、斉の宣王が即位した直後のことです。まだ若く、場数を踏んでいない君主でした。その君主をすっかりその気にさせて、国家の一大事である戦争までやって、支離滅裂な失敗で終わった。周囲の家臣たちから見れば、孟子は未熟な我が君になんてことをさせるんだ、と冷ややかであったことでしょう。
上田:尹士のような見解が家臣の大勢であったのだろう。それでも、いや宣王は湯王にも武王にもなれると孟子は言うのですから、いい加減にしてもらいたいという気があったと思える。
小田:斉の家臣から見れば、そこまで王を乗せたのならば、孟子は側近としてもっと政治への的確なフォローをしろよ、孟子はそれが出来ていないじゃないか、という思いがあったかもしれませんね。家臣にすれば、孟子は道徳顧問程度の自覚で、自制して欲しかったことでしょう。とても戦争のような国家の一大事にまで、口を挟んでほしくなかったことでしょう。
上田:尹士は孟子の言葉を聞いて納得したとしている。話の組み立てとしては、家臣を納得させたようになっているが、実際の多くの家臣はそうではなかったのだろう。
高津:最近の政治を見ると、大局で見たらその場その時の政治家の決断が、後から回顧すると間違っていた、ということもまたあるようです。それを後から、政治家の当時の決断に対して足を引っ張っている。しかし後付けならば、何とでも批判できます。大事なのは、その時その場でしっかり方向修正できるように諌めることができる人が、決断する政治家の側にいなければいけないのに。
小田:残念ながら、近年の政治では、決断力に欠けるトップ、それから的確にトップを諌める側近が乏しいのかもしれません。
高津:批判するだけですか。
小田:私が思うに、近年で最後に決断力に富む政治をできた日本の政治家は、小泉首相くらいでしょうか。彼は、株価が下がろうが、国際情勢が急変しようが、政治家としてやりたいことの筋を変えたりしませんでした。「株価に一喜一憂しない」と言って経済政策に対して殺到する批判を受け流したのは、政治家の姿勢として偉大だったと思います。彼の政策を評価しているわけでは、ありませんよ。政治家の姿勢としての、評価です。その後の安倍さんも麻生さんも民主党の面々も、そこまでの決意は見えません。思うに、斉王は孟子に乗せられていたのであって、家臣からの批判を撥ね退けてでも孟子を信任するまでの断固とした決断力は、なかったのでしょう。本当にそう思うのならば、家臣が何と言っても引き留めたでしょう。劉備玄徳はどんな批判を受けても、若造の諸葛孔明を信任しました。漢の劉邦は、張良と蕭何のやることには全幅の信任を与えました。孟子にすれば、宣王がどんな批判もはねのけて、自分を押し立てて欲しかったのでしょう。ところが、とても引き留めてはおけないほど、孟子の評判は悪くなっていた。そんな雑音など聞かずに私を信じて留めて欲しい、そうすれば天下をとらせる、と孟子は言いたかったのでしょう。孟子を引き留めておけば果たして斉が天下を取れたかどうか、あるいは少なくとも国としてよい方向に向かったかどうかは、別の話ですがね。
高津:斉では、菅仲が絶対的な存在でした。菅仲の政策のおかげで、斉という国はその後数百年間の繁栄の基礎が作られたぐらいです。
小田:孟子はその菅仲など、何ほどでもないと豪語しました。孟子は、自分は菅仲に出来ない事が出来る、と自負していました。それはつまり、天下取りです。孟子は、自分は斉に天下取りを行わせることができるから菅仲などものの数ではない、と豪語したのです。それが本当に孟子先生の理論と力量で可能だったかどうかは、別の話ですがね。
高津:直感ですが、孟子では出来そうもないでしょう。菅仲を孟子が越えるには、燕への出兵をあんな形にしてはならなかったでしょう。出兵すれば何が起こるか、どういう結果になるという見通しを、菅仲ならば持って戦争もしたはずです。それを後付けで、誰が攻めるべきかと聞かれなかったとか、天吏であればよいと答えたであろうなどという言い訳を孟子はしています。菅仲ならば、しなかったでしょう。
小田:孟子は、天下平定という着地点を見ていました。これは間違いない。そこから彼の全ての発言が出ています。ただ、その着地点が遠大でした。今、斉の政治に携わっていて、自分の最終的な着地点に向けたステップとして、小さいことながら何をすべきか?そんな細かい配慮を、孟子先生は真剣に考えていたでしょうか。その辺が、政治家でなくて思想家だったのでしょう。
高津:孟子が孔子の後継者なのであれば、燕を併合などせず、兵を引く助言をすべきであった。孔子は、魯公に正義の軍を起こす進言をした。
小田:孟子としては、そのつもりだったはずですけれどね。国がいったん戦争となればどのような経緯をたどるかについて、見通しが甘かったのでしょう。
高津:その時、諌めねばならなかった。過ちを改めないのが過ちだと、孔子も言っています。
小田:結果として、燕で反乱が起きて諸外国を敵に回して、やむなく撤退しました。最悪の撤退で、斉にとってこの戦争は、何も得るものがありませんでした。
高津:楽毅の方が上です。彼は諸国を味方にする策を打つことができました。
小田:楽毅は、燕人ではありませんでした。反乱した太子平は即位して昭王となりましたが、昭王は楽毅を魏国から礼を厚くして招き、彼が生きていた三十年間、楽毅を信任し続けました。昭王の方が、斉王よりも上手でした。士を遇する態度も、国に役に立つ士を選ぶ人選力も。
高津:楽毅は昭王の死後、息子(恵王)に疑われて亡命しました。上下の信頼関係が大切です。孟子は、楽毅と比較すると、斉王に引き留められていません。孔子は峡谷での斉公と魯公との会盟で、自ら先頭に立って、斉の威嚇行動を阻止して魯の立場を守りました。孟子には、そんな孔子のように陣頭に立って兵すら指揮するような点に欠けていたのではないでしょうか?
小田:孟子は滕の文公が「わが国は小国で大国の斉と楚にはさまれています。わが国は斉に付くべきか、楚につくべきか教えてください」と聞かれたとき、「私はそういった謀(はかりごと)は分かりません!」などと答えました。(梁恵王章句下、十三)。孟子先生は、外交について何のアドバイスもできなかった。先生、あんた何のために君主の顧問として来たんだ!と突っ込みたくなりますね。
高津:それに比べると、鄭の子産は小国を守るために必死にやっていました。
小田:福沢諭吉も、さすがにこんな孟子の態度にはあきれています。たとえば19世紀後半の開国したばかりの日本という国がこれからどのような外交をしなければいけないのか、という問いは切実であるのに、儒教の孟子先生は何一つ策を言うことができない。政治を取ることに熱心でありながら、外交について何も知らない。こんな役立たずはない、と。他にも孟子は、梁の恵王が太子を戦場に出して戦死させたことについて、不仁だと罵っています(尽心章句下、一)。太子は大事な身内で真っ先に愛しなければならないのに、戦場に出して死なせるなどは、愛すべきものを愛しない不仁の行為でけしからん、と。しかし、私は思うのですが、太子ならば戦場での場数も必要だと王は思ったのかもしれません。政治や軍隊での訓練を受けなければ、為政者は育ちません。たまたま死んでしまったのは残念だが、後継者を戦場に出してはいけない、と言う孟子の言葉は、私はおかしいと読んで思いました。
高津:始皇帝も、太子の扶蘇を軍隊の現場に送りました。教育のためだったのでしょう。
小田:史書では、太子が始皇帝に諫言したので皇帝の怒りに触れて、匈奴防衛の軍隊に左遷された、と記されています。しかし、私は思うに高津さんの意見と同様で、始皇帝は太子を軍隊にあえて送ったのだと思います。その始皇帝の死後、扶蘇は趙高の奸策に陥れられて死に、胡亥が二世皇帝となりました。胡亥は単に始皇帝に気に入られて側にいただけの子で、政治も軍事も何も知らない愚者でした。秦帝国は、胡亥が二世皇帝となった途端に、あっという間に滅亡してしまいました。これが何も知らない後継者の末路です。高津:だいたい歴史でも会社でも二代目は、ダメなのが多いですね。
小田:劉禅とかね。父親のような生涯場数を踏んだ君主とは、大違いでした。孟子は、やっぱり思想家であり、現場での政治や軍事のことには、向いていなかったのでしょうね。
2012年4月7日(土)論語為政篇
本日、早川君、北澤さん、小田さん、成田君、高津君、上田さんの六人。
早川君のリードで為政篇の音読。訓読と訳を北澤さんお願いします。
子の曰はく、由、女(なんじ)に之を知ることを誨へんか。之を知るを之を知るとし、知らざるを知らずと、是れ知れるなり。
女の音は汝。○由は孔子の弟子、姓は仲、字は子路。子路勇を好む。蓋し其の知らざる所を強いて以て知るとなす者有り。故に夫子之に告げて曰く、我女に敎ふるに之を知るの道を以てせんか。但知る所の者は、則ち以て知るとし、知らざる所の者は、則ち以て知らずとす。此の如くんば、則ち或は盡く知ること能はずと雖も、而して自ら欺くの蔽無く、亦其の知るとするを害せず。況や此に由りて之を求めば、又知る可きの理有るをや。
先生が言った。「由よ、なんじに知るということを教えよう。知ることを知るとなし、知らないことを知らないとなすことが、知るということなのだ」と。
「女」の字は(女[じょ、おんな]ではなくて、汝(じょ、なんじ)である。由は孔子の弟子で姓は仲、字は子路。子路は勇を好んだ。つまり、知らないことを敢えて知っているとするところがあった。ゆえに孔子は子路に忠告して、「私がお前に知ると言うことの道を敎えよう。ただ知っていることを知っているとし、知らないことは知らないとする。このようにすれば、ことごとくを知ることができないとしても、自らを欺く弊害はなくなるし、(新たに)知ることを妨げない。いわんや、この原則によって知を求めてゆけば、そこにこそ知ることの理があることは、いうまでもない」と(言ったのである)。
北澤:本文とおなじことを二度言っているだけですね。
成田:本文のことをくどくど言って、本文の方がむしろ分かり易いですね。
小田:この章は、いわば「無知の知」。例の野田首相が、田中防衛大臣を擁護したところですね。
成田:しかし、本当に無知の知と理解して行動しているのかが、あの大臣の疑問点です。
北澤:何も知らないですか?
成田:大臣が何を分かっていて、何を分かっていないかが分からないとすれば、危険でしょうね。
小田:何を知っていて何を知らないのかも、忘れてしまった。もはやそうなれば忘我の境地ですかね。
早川:道家の統治思想は、それが理想だったりしますけれど。
小田:道家は、自由放任無為自然ですから。
成田:朱熹は子路の性格を、「知らないところを強いて知るところがあり、勇猛でありながら知らぬことでも突き進む」ので、知らない事を知らないとせよとしたのだ、と解釈しています。だが、皆様の子路像と重ねてみると、どうですか?
北澤:子路は知らないことは知らないとするような性格だと思います。知ったかぶりをするようにはみえない。
小田:私が思うに、『論語』の編集方針として、子路をボケ担当というかコミックリリーフというか、外した発言をしてたしなめられる立ち位置に置いているのではないでしょうか。文学作品では、誰か笑いを取る担当を置いて物語を活性化するというのは、よくある仕掛けです。孔子学校が賢い者ばかりではおもしろくないので、子路をわざと失敗役として振り当てているのではないでしょうか。子路の実像は置いておいて、伝説の中で彼はそういった損な役回りになっているところがあるのではないでしょうか。為政篇で顔淵や子貢がでてくるるなかで、子路はあまりぱっとしない役割を演じさせられているのでしょう。
早川:会津藩の儒学者の安部井帽山は、子路が「知らないことを知るとなす」例を二つ挙げています。一つは、孔子が南子(衛霊公夫人)に会見をするのを、子路が止めようとしたとき。南子が帯珠をじゃらんと鳴らせた(帯と解いた)と記されており、それで子路が止めようとしたが、孔子はやましい思いで会見したのではない、もしそうであれば天が私を罰すると言った。ここで子路が孔子を邪推したのがその例としています。
成田:孔子が女に会った、けしからんと子路は思った。しかしそれは孔子の真意を知らないからだ、いうわけ。
早川:もう一つは、謀反を起こす人(公山不狃)に二つ返事で加わろうとしたのを、孔子の本意を知らずに子路が止めたことです。
小田:しかし論語中をひっくり返しても、そんな二つの例しか見つけることができなかった。それにそれらの例は、朱子が言っている子路の害とは、ちょっと違うように思えますがね。孔子先生の真意を取り違えたとかうんぬんの話を、朱子は言っていないでしょう。
成田:子路はことごとくなんでも知ってやろうとし、勇猛にあふれていた。それに比べて若い弟子たちは就職予備軍で、ともかく就職できればよくて学問に対して知らなければ別に構わないと突き放していました。だが子路はそれではダメで、孔子からすべてを知ろうと望み、失敗する。それで孔子は、子路に対してほどほどにわきまえることを学習せよ、と言ったのでしょうか。
小田:子貢のようにすらすらと理解できないが、勇を好むので、なにくそと奮起してしまうのでしょう。それで勇み足となる。
成田:もし「知らざるを知らずとなす」をできたならば、それこそ顔淵なみ、孔子なみにもなれるでしょう。だから難しい。
小田:孔子ですら、「我生まれながらにしてこれを知る者に非ず」(述而篇)と言っています。この境地に至るまでに、長い修練と経験が必要だったのです。
成田:子路は弟子の古参で、古株で年齢も孔子と離れていない。若いころは勉強もしていないので知識では劣っていた。
北澤:この章の言葉は、いつごろ言ったものですか。
早川:荀子によれば、子路が入門した時に孔子が言ったと記載されています。しかし、それはどうかと思いますね。
成田:史記ではどうですか。子路が入門のころは、鶏の羽根を頭に差した勇の無頼の徒でしたね。
早川:史記には、この言葉は書いていないです。
成田:この言葉が入門時のものならば、孔子は一目で子路の性格を見抜いていたと考えたことになる。すごい眼力だ。
北澤:入門早々であれば、このことを反省していたとなりますね。
成田:反省して、このあたりを慎んだのでしょうか?
高津:孔子は、冉求よりは子路の方が上であると言ってますね。
成田:任される部門が異なる。
小田:孟子は、子路を結構高く評価しています。彼は回想として、曾参の子孫の曾西が「あなたと子路とでは、どちらが勝っていますか?」と聞かれたとき、「私の先人ですら畏怖していた方なのに、私などとてもとても」などと言ったとか述べています。その曾西が「あなたと菅仲とでは、どちらが勝っていますか?」と聞かれたら、激怒して自分と管仲ごときを比較するな、汚らわしい!と言ったとか。つまり、孟子の学派の中では、子路は管仲よりも上の評価がされていたということです。孟子の学派の中での評価と、論語の中での叙述は、子路への評価が違いますね。
上田:衛の霊公の後継者問題で、子路は孔子に出公を選ばせたかったが、孔子は動かず、「君子は其の知らざる所に蓋闕如(がいけつじょ)たり」、わからないところは欠けたままにしておけと戒めている。子路は出公を補佐し死ぬことになる。子路は北澤さんがおっしゃるように、一つのことをマスターしなければ、次にゆかないという性格であり、知ったかぶりをするタイプではないと思う。南子の件や、公山不狃や??に加担するのを止めて、政治判断では孔子にないものを持っていた。ただ、この件では、勇み足となった。
早川:荀子では、論語のこの章の問答を引き伸ばして、言葉と行いの両面の戒めとなっています。言葉では知ったかぶりを、行いでは出来ない事をできるとすることを、子路に戒めたというのです。もしこれが入門のとき、最初のときとすれば、孔子の眼力はすごすぎる。孔子が戯れに「筏に乗りて海に浮かばん。我に従う者はそれ由か」(公冶長篇)と言いました。孔子は、彼の率直さを喜んでいました。それを子路は真に受けて、筏の材木まで調達しかねないようなところがあった。そこで、この章の言葉となります。
上田:この言葉は、入門時ではなく、出公のことがあって以降の方が話があう。
成田:それじゃ、子路の遺骸(なきがら)に向かって言ったことになりますね。
上田:そうなりますか・・・
成田:子路は衛で討たれ、醢、死体を塩漬けにされた。醢にされれば、食われたことになるだろう。子路が醢にされたのを聞いて、孔子は家の中の醢の肉を全部捨てさせたといいます。つまり孔子の家にも醢があったのですが、これが文革時の批林批孔運動の時には孔子が人肉の醢を食っていた証拠だ、と言って人肉食孔子の非難が起こりました。
小田:なるほど、つまり普段から人肉の醢を食っていたのだが、身内が醢にされたのを聞いて、やっと人肉を食べるのが気持ち悪くなって捨てたのだ、という非難ですか。漢王朝の建国の功臣彭越は、呂后に殺されてその醢が漢の家臣たちに配られたとか。あれも、食われたんでしょうかね。
しばし、人肉談義。
中国では英雄の肉を食うと、そのエネルギーを得ると考えられていたようである。子路が衛で醢されたということは衛人に食われたことになる。子路は英雄とみなされていたようであるから、話は合致する。マサイ族は、動物も親戚とみており殺して食う事は無い。ただ。牛の乳と同じく、血を抜き取って飲み、この栄養価が高く肉を食う必要はないと言う。中国で死刑囚の血をマントウに着けて食べる風習があったことは、魯迅の小説にも芥川龍之介の中国紀行にも出てくる。中国では、諸侯が会盟するとき、牛の耳を切って互いに血を飲んだ。「牛耳を執る」のいわれである。牛の血が最も上等で、豚、羊と下等になり、最も下等なのはスッポンの血であった。台湾では、豬血糕という豚の血を固めた餅が普通に売っていて、血を食べるのは普通。ドイツなんかでも、ブラッドソーセージとして食べる。両者とも肉食文化で、家畜は血まで残さず食べる文化。
成田:子路は衛の出公に仕えて、内乱で死ぬ。史記にはそう記されているが、論語にはその話は無い。孔子が放浪から魯に帰って来てから、子路も魯にいたようです。孔子は衛にいたこともあったが、そのときにも子路は衛にいたわけで、子路が衛で死んでいるならば子路は行ったり来たりし過ぎている。史記は、子路の英雄譚として記述しています。英雄だから食われたことにもなるでしょう。しかし、子路の死は論語に言及がなく、論語を読むに当たっては、史記のような子路の死の話は除いて考えたほうがよいでしょう。
上田:左伝にも記されているではないですか。
成田:論語の中での子路像を考えるべきであり、論語の中では、子路の死という大事なことであれば言及されてしかるべきですが、何も書かれていません。
小田:顔回も、曾参も、論語の中で死んでいます。伯牛は、論語の中でもうすぐ死にます(笑)。そういう人々は死にざまを記録しているのに、確かに子路についてはそんなに劇的な死に方をしたのならばどうして『論語』に何も言及がないのかが、変といえば変ですね。
早川:先進篇に「由の若きや其の死然るを得ず」とあります。これを孔子が生前に言ったこととすれば、あまりに子路の死にざまをピタリと予言しすぎる。
成田:これも、まさか入門直後の言葉だったりして?
小田:どうも、史記仲尼弟子列伝の有若のくだりなどを見ると、孔子死後の弟子たちは、孔子を予言者か何かの超能力を持った人間のように神格化する傾向があったようですね。『論語』の中にも、その傾向が入っているのかもしれません。
成田:「百世知るべし」とは、過去のことを再現できるのか、それとも未来を予知できるというのか。ひょっとしたら、後世の者は孔子が百世後の未来まで予知できた全知全能だったと考えていたのかも、しれません。
上田:子路は人が言えば即反応する。この率直さには孔子もあわてて、冗談だと訂正せざるをえない。片方の言を聴いても、率直に対応されると嘘が通じなくなり、本当のことが分かるというのが子路。
小田:子路は、孔子の弟子の中でも特に意図の純粋なところがありました。心中の純粋さを重んじる孟子などは、その点について子路を好んだかもしれませんね。「子路は人これに告ぐるにその過ちをもってすれば、則ち喜べり」(公孫丑章句上)。この章では、子路・禹・舜を列挙して、三者を称えています。いにしえの聖王たちと並べられるとは、大した評価だ。
成田:子路は、「下問を恥じず」、つまり目下の者に教えを乞うことを厭わなかった人です。
じゃあそろそろ本日のメインエベントにゆきますか、小田さんよろしく。
子張祿を干(もと)めんことを學ぶ。子の曰はく、多く聞き疑はしきを闕き、愼みて其の餘りを言へば、則ち尤(とがめ)寡し。多く見て殆きを闕き、愼みて其の餘りを行へば、則ち悔い寡し。言(こと)尤寡く、行悔い寡ければ、祿其の中に在り。
子張、孔子の弟子、姓は顓孫(せんそん)、名は師。干は求なり。祿は仕る者の奉なり。行寡の行は去聲。○呂氏の曰く、疑は、未だ信ぜざる所。殆きは、未だ安からざる所。程子の曰く、尤は罪外より至る者、悔は理内より出づる者なり。愚謂へらく、聞見多き者は學ぶこと博、疑殆を闕く者は擇ぶこと精、言行を愼む者は守ること約。凡て其の中に在りと言ふは、皆求めずして自ら至るの辭なり。此を言ひて以て子張の失を救ひて、之を進むなり。○程子の曰く、天爵を修まば則ち人爵至る。君子の言行能く謹むは、祿を得るの道なり。子張祿を干むるを學ぶ、故に之に告ぐるに此を以てす。其の心を定めて利祿に動ざらしむ。顏・閔の若きは則ち此の問ひ無し。或ひとの疑ふ、此の如くして亦祿を得ざる者有ると。孔子蓋し曰(のたま)ふに、耕すや餒其の中に在り。惟理の爲す可きは、之を爲すのみ。
子張が、祿を求めることを問うた。先生が言われた、「いろいろと聞いて疑わしきを取り除き、慎んでその残りのことだけを言えば、尤(とがめ)は少ない。いろいろ見てあやふやなことを取り除き、慎んでその残りのことだけを行えば、悔いが少ない。言に尤が少なく、行に悔いが少ければ、祿はおのずからその中に在るのだ」と。
子張は孔子の弟子で、姓は顓孫(せんそん)、名は師。「干」は求めることである。「祿」は仕える者の俸給である。「行寡」の「行」は去聲で読め。○呂氏が言った、「疑わしいのは、確信していないことだ。あやふやとは、安定していないことだ」と。程子が言った、「尤は罪が外より押し寄せるものだ。悔いは正しい道理が内からでるのでくやむことだ」と。それがし(朱子)が思うに、聞見の多い者は広く学ぶことができ、疑わしいこととあやふやなことを取り除く者は精密に選択できる。言行を愼む者はきっちりと守ることができる。結論として「その中に在る」というのは、全てが求めずして自ら至ることを言っているのである。孔子はこう言って子張の欠点を救い、もっと前に進ませようとしたのだ。○程子が言った、「天爵を修めれば、人爵に至る。君子が言行をよく謹しむのが、祿を得る道である。子張は祿を求める方法を問うたので、孔子は彼にこの章のように告げたのだ。子張の心を定めて、利祿に動かないようにさせたのだ。顏淵・閔子騫のごときは、(利祿に心を動かさないので)このような質問をしない。このように疑う人もいるだろう、『この章のようにしても、祿を得ることができない人もいるではないか?』と。孔子はこう言われた、『耕しても餒えることはある』と。心中の理から為すべきことを、ただただするのみだ。(祿を得る道はそれしかないのだから、いたしかたがない。)」と。
小田:あらかじめ、レジメを切らせていただきました。
早川:衛霊公篇に、「君子は道を謀りて食を謀らず。耕やすなり、餒、其の中に在り。學ぶなり、祿、其の中に在り。君子は道を憂へ貧を憂へず。」とあります。程子はここから引用したのです。
小田:朱子は、どうやら正しく進んで行っても成功しないことがありうることを、認めざるをえなかったようですね。だから、末尾のような言い方となる。
成田:だけど他に方法は無いからそうしなさいとなる。
小田:天爵・人爵は、孟子の言葉です。君子は正しく射ることが大事であって、射た矢が的に当るか外れるか、そんな結果はどうでもよい。朱子は、この章を孟子に引き付けて読んで、君子にとって成功するかどうかなのは二の次の問題なのだ、と解説しています。子張のごとく若くて出世に燃える弟子に対して、孔子は慎重になれと言いました。顔淵や閔子騫はそんなにガツガツしていないから、こんな問いをしないだろう、と朱子は言います。
成田:最初の「學」の字について、朱子は「問う」という意味で読んでいます。「学問」という言葉があるから、この解釈は穏当です。つまり、子張が問うて孔子が答えた、問答の章として読んでいるわけです。しかし別の読み方があって、文字通りに学んでいたと解釈して、子張が禄を得るための就職の勉強を学んでいた。それを孔子が見とがめて、正すために言葉をかけた、という解釈も可能です。
早川:対話なのか、孔子の語りかけか。子張が禄を求めているのを見て語りかけているならば、ちょっと言葉が具体的すぎるように見えますが。
成田:かつての時代の学問とは、弟子が質問を問うことにより行われました。子張は「干祿」とは何ですか?と問うた。弟子はそれに対する先生の返答を記録した。そんな時代の学問は、学ぶことと問うことは同じでした。
上田:「学」とあり干祿について学んだとみる説に賛成。干祿は詩、文王の「豈弟君子、干祿豈弟・・・」のことで、文王に天の祿が降りたことについて子張が学び、それに関する質問をしたのではないか。
早川:古注にも、この章は詩の章句についての問答である、というのがあるが、それについての注釈はしていない。
成田:子張はガツガツではない。
上田:子張は非常に若いが、孔子家語によれば、孔子は子貢が最近自分より優れた人物より下の人物と過ごしているが、子張は自分より優れた人物と付き合っているという風なものがあり、就職にガツガツしていたとは思えない。
小田:それはどうでしょうかね。先進篇で、「師や辟」と言われています。辟とは「かざる」ことで、つまり子張はうわべを飾るだけの軽薄者だ、という厳しい批評です。
上田:文王は殷の紂の治世で、慎重に処し、人心が彼に集まり、天の禄が文王に降りたという故事であるが、孔子の時代に本当にそういうことが通用するのか?今の世ではどう理解すべきかを聞いたのではないか。
成田:詩の解釈ではなくて、孔子の意見を聞きたいということですね。
小田:孔子の時代において、「干祿」の道を孔子はこのように解釈しました。しかし、私はレジメに書かせていただきましたが、現代の「干祿」は、すでに本章の孔子のアドバイスは通用しないのじゃないか、と思うのです。むしろ、「巧遅は拙速に如かず」が、現代の「干祿」なのじゃないだろうか。
高津:石原都知事のことを、言っているのですか?
成田:いや、レジメで言及しているのは、橋下大阪市長です。
小田:私は役所文化というものを知っている人間ですが、役所はまさに孔子のこの章の言葉が幅を利かせるところです。法律か条例を広く学んであやふやな点を取り除き、法の条文に書かれていないことは言ってはならず、行ってはならない。その原理を、新入りは叩き込まれます。「言尤寡く、行悔い寡ければ、祿其の中に在り。」まさにこれは役所文化です。この原理を忠実に果たす輩が、碌を得て出世できる仕組みとなっていたのです。少なくとも、最近までは。
北澤:役所なら、この言葉を壁に貼ってでもしているものですか?
小田:いや、さすがに貼ってはいませんが、でもこの言葉を貼っておいてもよいぐらいですよ。上に行けば行くほど保守的となって、法の条文から外れず、拙速なチャレンジを行わない。ところが橋下さんは、こんな役所文化に真っ向から対立します。彼は、失言も拙速な行動も恐れず、アクションを起こします。慎みなど糞くらえで、アクションを起こすことから前に進んでいくと考えています。役所の中は、市長の役所としてあるまじき行為を突きつけられて、大変です。
高津:レジメの中で、「初心正しければ、拙速なるもその中に禄あるべし。」とあります。初心正しければ、が肝心です。孔子は過ちを否定しない。過ちを改めることが大事とします。孔子は決して役所みたいなことをしなさい、とは言っていないんじゃないですか。
成田:孔子は、言うべき時に言わないのが過ちともします。
高津:言わないというのは、冉求が諌めるべき時に諌めないのはいけないとした話ですね。
成田:孔子は役人気質ではない。また、見て見ぬふりをするのはダメとした。
高津:古賀さんは左遷されましたね。
小田:とはいうものの、言うべきことを言わない方向に、保守的な組織は流れるのです。出世の道として言うべきことを言わないのが最も安全なのに、なんで言う必要があるか。
成田:孔子には、言うべきときに言わなければ後悔する、という考えまでが含まれています。
小田:今の時代は、そっちの方を強調すべきなのです。批判上等くらいの心構えでないと、政治家はいけません。
成田:孔子はその方向。
小田:政治のトップは、批判があっても初心を変えてはいけません。「尤寡し」などを気にしてはいけないと思います。
早川:小田さんのレジメで、歴史上の例を挙げていますが、いずれも乱世ですね。大阪市は、乱世ではないのでは?
小田:しかし、今の大阪市は財政的に火の車です。税収は下がるわ、生活保護受給は増える一方だわ、このままでは自治体として破産するでしょう。今は非常事態で、非常の策を取るべき乱世といってもよいかと私は思います。
高津:亀井さんを見ておれば、まさに乱世でしょうかね。ところでレジメの「巧遅は拙速に如かず」ですが、孫子の言葉のように言われていますが、実は孫子の中ではこの言葉はありません。必ずしもこのように孫子は言っていないのではないですか?
小田:おっしゃるとおりです。孫子の中には、「兵は未だ拙速なるを聞くも、巧久なるを睹(み)ざるなり。」(作戦篇)と書かれています。「巧遅は拙速に如かず」という言い方とは、ちょっと違います。だが孫子は、「勢」を重視します。「善く戦う者は、これを勢(せい)に求めて人に責(もと)めず。(勢篇)」つまり、勝利の条件は優秀な人間を求めるところになく、「勢」を有効に活用するところにある。「勢」は天の時を得たならば一気に転がり落とすところに生まれる。孔子には、このような「勢」についての認識は、見られないようです。
成田:「勢」について、私は一論を書いたことがあります。『文心雕龍』に、坂に球体と立方体を置くことを論じています。立方体は坂に止まったままだが、球体は坂を転げ落ちる。立方体は静、球体は動で、形と位置から動静は分かれます。この静と動の両方が、「勢」です。「勢」という字の意味はすがた、かたちであり、国勢調査の「勢」は国の勢いを調査する意味でなく、国のすがたが現在どうなっているかを調べるものです。
兵法でたとえれば、川の上流にダムを作り水を溜めると、「勢」が生じます。そうすると、下流の軍隊が洪水を恐れて逃げます。これが「勢」を利用した戦いです。孔子は「勢」を言いません。「勢」は兵家の発想であり、兵家は国家間のパワーバランスを見て現在がどのような「勢」であるかを見極め、「勢」を利用しようとします。しかし孔子は、社会が安定した状態を求めます。たとえるならば、坂の上の球体が動きそうになれば、兵家ならばそのまま転がって下流が踏み潰されることを考えますが、孔子はそれを平らなところに移動して動かないようにしようとするでしょう。
孫子の教えは、国家間の優劣の状況を捉えてどのような「勢」があるかを見極め、勝ち馬に乗ることが大事だということです。そのためには、人の数や地勢状況などを正しく見ることができねばならない。こういう流れに逆らうのが孟子で、彼は転がって来るものを押さえようとして失敗したわけです。孔子の時代は、まだ「勢」を考えなくてもよかった。しかし孟子の時代には、「勢」を考えないといけない時代でした。しかし、孟子はあえてそうしなかった。
小田:戦国時代になれば、「勢」を考えないと、いくら正しいことを言っていても負ける側についていたら弾き飛ばされておしまいの時代でした。
高津:孔子は兵家や戦争は好きでなかった。
成田:むしろ戦わないことを理想としました。孔子は、いにしえの静的な「勢」の配置に社会を引き戻すことを望みました。静的な「勢」の配置が復活したならば、争いもなくなる。
高津:孫子も、なにがなんでも戦争というものではなかったはずです。
小田:そうですね。孫子は、戦わずして屈服させる作戦を最上と考え、城攻めを最低の作戦と批判しました。自国の圧倒的な勢力を見せ付けて、外交で脅して相手を屈服させるのが国力を浪費しないので最良の作戦だと考えました。だが、ひとたび戦争となれば、勝つために躊躇せず戦うべきだと考え、勝つための方法を考察しました。
成田:戦争は、勝者と敗者を生みます。勝者と敗者が生まれれば怨みが残り、国際情勢の不安材料を新たに生みます。それを避けようとした。
上田:平時と戦時のもう一つ異なる点は、戦時は何をしても時間内に出来ることが重要で、「巧遅は拙速に如かず」となる。
早川:乱世になれば、国民の批判の対象を外の敵に誘導することができます。しかし平時ではそれができないため、全て批判は国内の政治家へ向かいます。そう考えると、私の専攻の宋代の王安石を思い起こします。彼は乱世でなかった時代に大改革を試みて、激しい批判を受けた人物でした。
高津:王安石の評価はどうですか。
早川:今から百年前には、悪人と言われました。それ以降は、大政治家として高い評価を受けているようです。彼にとって致命的だったのは、死後40年で宋が滅びてしまったことです。それで、宋が滅んだのは王安石の政治のせいだ、という悪評が立ってしまいました。まるで日本陸軍に戦争責任を全ておっかぶせるようなものです。
小田:中国で平時に大改革をやった政治家といえば、他に誰がいるかな。明で財政改革をやった、張居正とかでしょうか。あるいは漢の霍光とか、、、新の王莽も、主観的には政治改革者でした。中国の王朝は、平時でもときどき改革者が現れますね。
早川:清ならば、雍正帝でしょうか。
成田:あるいは、つぶされましたが清末の変法自強運動とか。
小田:同時代人には、王安石はどう評価されていたのでしょうか。
早川:変わったことをする人という評価。
成田:革命を好む人は評価する。宋は、新法派と旧法派の泥試合となりました。最終的には政策の対立としてはあいまいになり、単に二つの派閥が私怨で争う様相となりました。そんな政治の乱れで、宋は倒れてしまいました。
王安石の胆力はすばらしものがあり、文筆にも優れた才があったようです。「巧遅は拙速に如かず」という改革断行する政治家が求められているのか、「言尤寡く、行悔い寡くして」天の祿が降りる政治家が求められているのか、議論は尽きません。
2012年4月14日(土)論語為政篇
本日、早川君、小田さん、成田君、高津君、上田さんの五人。
早川君のリードで為政篇の音読。
章は戻るが、為政篇2で「思無邪」について、この思は詩経においては「これ」と読んでsīの発音に当る。しかし論語において孔子は「思い邪無し」と「思い」と読ませているので、sìとなるべきか。(現代ではこの区別はない)朱熹はテキストで何の指示もしておらず、ここはsīと読ませているのでしょう、と成田君。
訓読と訳を小田さんお願いします。
哀公問ひて曰く、何をしてか則ち民服せん。孔子對へて曰はく、直きを擧げて諸(もろもろ)の枉(まが)れるを錯(お)けば、則ち民服す。枉れるを擧げて諸の直きを錯けば、則ち民服さず。
哀公は魯君、名は蒋。凡そ君の問に皆孔子對へて曰くと稱するは、君を尊ぶなり。錯(そ)は捨て置くなり。諸は衆なり。程子の曰く、擧錯(きょそ)義を得れば、則ち人心服す。○謝氏の曰く、直きを好みて枉れるを惡むは、天下の至情なり。之に順へば則ち服し、之に逆へば則ち去る、必然の理なり。然れども、或は道を以て之を照らすこと無んば、則ち直きを以て枉れると爲し、枉れるを以て直きと爲す者多し。是(ここ)を以て君子敬に居るを大となし、理を窮むるを貴ぶ。
哀公が質問をされた、「どうすれば人民が心服するだろうか?」と。孔子が答えて申された、「正しい者を採用して多くの曲がったものを捨て置けば、民は心服します。曲がった者を採用して多くの正しい者を捨て置けば、民は心服しません」と。
哀公は魯の君主で、名を?という。一般的に君主が質問したときに「孔子對えて曰く」とあるのは、君主を尊んでいるのである。「錯(そ)」は捨て置くことであり、「諸」は多くの人のことである。程子が言う、「擧錯(きょそ)が義を得ていれば、人は心服するものである」と。○謝氏が言う、「正しい者を好み曲がれる者を憎むのは、天下の至情である。これに従えば服し、これに逆らえば民が去ってゆくのは、必然の理(ことわり)である。だが道によってこれを照らさなければ、正しい者を曲がっているとし、曲がっている者を正しいとする者が多くあろう。だから君子は敬に居ることを偉大とみなし、理を窮めることを貴ぶのだ」と。
成田:「凡そ君の問に皆孔子對へて曰く」とは、この章だけではなくて、一般に君主を尊んで言うときには、「孔子応えて曰く」という表現となる。これから先もそういうことだから心得ておけ、と指摘しているのです。
小田:目上の君主と孔子との対話だから、通例の「子」ではなくて「孔子」と姓を付けて、へりくだる書き方になります。
早川:「凡そ」は日本語では意味がなくなり、「そもそも」くらいのもの。
小田:顔淵篇22では、「子の曰はく、直きを舉げ諸の枉れるに錯けば、能く枉れる者をして直からしむ。樊遲、退きて子夏を見て曰く、鄕に吾、夫子に見へて知を問ふに、子の曰はく、直きを舉げ諸の枉れるに錯けば、能く枉れる者をして直からしむ、何の謂ひなりや。子夏が曰く、富かな言ふや。舜、天下を有ち衆に選びて皐陶を舉ぐるに不仁者遠のく、湯、天下を有つや衆に選びて伊尹を舉ぐるに不仁者遠のきぬ。」とあります。この為政篇の章と同じ言葉を樊遲が聞いて、よく分からなかったので子夏が解説しています。
成田:子夏がえらくしゃべっており、しゃべりすぎですね。
小田:子夏の解説はこの章よりももっと具体的で、分かりやすいです。つまり皐陶とか伊尹のような賢臣を高位に採用すれば、政治がよくなると。
成田:哀公がそう思ってくれれば成功したことになるんですがね。
小田:孔子は哀公に、具体例を挙げて言わなかったのでしょうか。ぜんぶ言ってしまうと、賢臣を刺激するから?
成田:それはどうか分からない。
上田:この問答のとき、哀公に民が心服していなかった。季康子が実権を握っており、季康子は冉求を用いていた。孔子は、季康子や冉求が枉れる者と言ったことになる。それでは民は心服しない。
成田:哀公は、そう思っていましたかね。では、直きとは誰のことになりますか?
上田:自分(孔子)のことでしょう。
成田:孔子世家では、「終ひに孔子を用いること能はずして、孔子も亦た仕ふるを求めず」とあります。つまり魯では晩年の孔子を登用することができず、孔子も仕官しようとしなかった、ということです。史記では、哀公時代の孔子はあえて仕官せず教育に専念していたと。だが、上田さんの推測が正しければ、そうでもなかった。孔子は、再登板してやる気が満々だったということですか。
上田:孔子を用いようとしたが、魯の公之魚が前回孔子を使って失敗し、諸侯の失笑を買った二の舞になりますよとして、冉求を用いたという経緯があった。
成田:では、なぜ孔子に質問をしたのでしょう。
早川:枉れる者は誰を指すかというと、三桓氏(季孫氏、叔孫氏、孟孫氏)でしょう。八佾篇21で、哀公が宰我に国の社(神木)を尋ねたとき、宰我がしゃれこんで「周人は栗」、つまり周の神木は栗の木の栗であり、これには「慄然」の意味がある、とひっかけた。だが孔子はこれを聞いて、「成事は説かず、遂事は諫めず、既往は咎めず」と答えました。
上田:その話は陽貨が哀公の父、定公のとき、三桓氏を牛耳り、定公ともども周社で誓を立てさせたことで、本来君主が家臣を慄然とさせる場で、逆に家臣に君主が慄然とさせられたことを宰我が持ち出したもの。その事を知っていて当然の哀公が知らずに質問したとなれば、君主としてはお粗末なところがあったのだろう。
早川:哀公は、どうすれば民が心服するかを孔子に尋ねた。孔子の答えは、エビで鯛を釣るような方法です。哀公が出した質問に、哀公の手腕では及ばないことを分かって孔子は言ったのでしょうか。
小田:この公の「哀」は、だいたい王朝末期の君主に付けられるような悪い諡ですが。
成田:何故、哀公と名付けられたのか。
小田:魯は哀公の代以降に滅亡したわけではないです。かえって隣の斉や晋が、この後に家臣に国を乗っ取られました。しかし魯はこの後三桓氏が国を乗っ取ったわけでもなく、細々ながら戦国時代まで残りました。孔子の危惧は、後から振り返ってみればとりこし苦労だった?
早川:麒麟だって出てましたね。
上田:孔子が亡くなった時、ああ哀かな、と歎いたことから哀公となったのではないか。
早川:諡の由来を調べてみましょう。
成田:哀公の質問の仕方からすれば、民が心服していなかったことになる。
上田:季康子の康という諡は民を安んじたことを表しており、当時としては民は季康子や冉求の政治を支持していたと思われ、哀公には心を寄せていなかったし、孔子の言葉にも耳を貸すような状態ではなかった。
成田:季孫氏が実権を握っていました。孔子はその季孫氏を排してもっとよい良い政治家に取り替えよ、と勧めたというよりは、いま季孫氏が曲がった人材を登用しているから殿様はその逆をすれば声望を取り戻せるだろう、と勧めたのではないでしょうか。
小田:曲がっているとか、真直ぐというとき政治家のどんな性質を想定しているのでしょうかね。能力なのか、人徳なのか。それとも別の何かか。
成田:季孫氏じたいが曲がっているかどうかは、問題にならない。季孫氏がどういう人材を登用するかが、問題です。君主ができることは人材を登用することで、その人材の良し悪しにより下々に政治を明らかにすることができる。孔子は季孫氏と敵対していたというわけではなく、冉有と決別していたわけでもない。哀公とも季孫氏とも双方に関係があったのは孔子くらいだった。
上田:この頃は、冉求や子貢が孔子より政治、外交において大きな役割を果たしており、孔子の影響力はあまりなかった。
小田:子貢の外交的活躍がなければ、魯は滅んでいたかもしれない。そんな国難の時代に国を保ったのは、政治的手腕だったでしょう。政治的手腕で国を保った子貢とか季康子とかに人民の声望が集まるのは、当然なのではないでしょうか。次の章で、季康子に孔子はもっと具体的なことを言っています。ここでは、季康子に人民の操縦法に踏み込んで言っている。これは、季康子が実際に国を動かしているから、ここまで言ったのでしょう。季康子は、魯国の国威を発揚させるために軍事的行動が必要だと考えて、そのために民を上手に徴発させる手段を孔子に聞いたのではないでしょうか。
成田:季康子は魯の家臣だから、実際に民を動員させる立場にもとよりありました。魯公はもとより直接に民と対するわけではないので、この章と次の章との孔子の発言の違いは、通常です。
このあたりからは次と一緒に考えるべしとなり、成田君が訓読と訳。
季康子問ふ、民をして敬忠にして勸ましめんこと、これを如何。子の曰はく、之に臨むに莊を以てすれば則ち敬す、孝慈なれば則ち忠なり。善を擧げて不能を敎ゆれば、則ち勸む。
季康子は魯の大夫、季孫氏、名は肥。莊は、容貌端嚴なるを謂ふ。民に臨むに莊を以てすれば、則ち民己を敬す。親に孝、衆に慈あるは、則ち民己に忠。善者は之を擧げて、不能者は之を敎ゆれば、則ち民勸む所有りて、善をするを樂しむ。○張敬夫の曰く、此れ皆我に在りて當に為す所なり。民を敬忠して以て勸めしむを欲するが爲に之を為すに非ず。然れども能く是の如くなれば、則ち其の應、蓋し然るを期せずして然る者有り。
季康子が問うた、「民に自分の仕事に一生懸命になり、それによって進歩をさせるにはどうすればいいでしょうか」と。先生が言った、「これに臨むときに莊厳(おごそかさ)で威厳のある感じで臨めば、民はすべきことに一生懸命になります。親類に孝にして、多くの人に慈しみの心をもってなすべきことをすれば、民は一生懸命になります。よくできる者を積極的に使い、出来ないものも教えるならば、民は積極的に取り組んで進歩します」と。
季康子は魯の大夫、季孫氏、名は肥。「莊」は、容貌は端正で威厳あることをいう。民に威厳をもって臨めば民はすべきことに一生懸命になる。親類に孝にして多くの人に慈しみの心をもってなすべきことをすれば、民は一生懸命になる。善くできる者を積極的に使い、出来ないものを教えるなら、積極的に取り組んで来ることになり、善いことを自発的にするようになる。○張敬夫の言うには、「これは皆自分においてやるべきことであり、民に対して一生懸命に働かせたいからやるようなことではない。そういうことであるからこういう風にやれば、その効果は期待していなくてもそうなるものだ」と。
小田:つまり、朱注によると、政治家たるもの人民を使役したいがために善行に励むのはよくない。善行はそれ自体が自分のための目的であり、政治家が自己目的として善行に励めば、結果的に自然と人民が付いて来るのだ、と言いたいわけですか。
成田:だから、季康子のような政治目的の質問の仕方はいけない。
早川:偉い人との問答には、パターンがあるのかな。
小田:孔子は、季康子を嫌っていた訳ではないでしょう。この章のように、季康子の問いを尊重して答えています。
成田:孔子は、季康子に呼ばれればちゃんと出掛けて、下問に答える。それが礼です。質問するかしないかの選択権は、季康子の側にあります。
小田:季康子も、孔子の言うことをいちおう参考にしようと思って、ここでこんなことを聞いたのではないでしょうか。
上田:季康子は自分なりには上手くやっており、民の支持も得ていると思い、自慢したくて言ったのではないですか。しかし、孔子は、その敬忠は荘、孝慈に欠け、教育することもないとした。
早川:季康子は本当に分かっていたのでしょうかね。
上田:教訓にしたかは疑問。言われたことをあまり気にしていなかったのではないか。
早川:「康」は結構いい諡です。
成田:そうかな。お手盛りの諡でもっとよい評価を付けるならば、「文」などにするでしょう。
高津:この章は、民に敬忠を「勸」(quan)のやり方で仕向けるのはどうか、とい季康子が孔子に聞いたのではないでしょうか?季康子は、そのやり方を自慢したかった。しかし孔子は、「之に臨むに莊を以てすれば則ち敬す、孝慈なれば則ち忠なり。善を擧げて不能を敎ゆ」と答えて、それを先に行って、それでもだめだったら「則ち勧」、「勧」という最後の手段を取るがよい、と言ったのではないでしょうか。
成田:なるほど、季康子は民に敬忠を「勸」して、ダメだったら罰する方針で行こうとした。そう読みましたか。
高津さんは、中国語のニュアンスで「勧」の字を読んだのですね。「勧」は日本語ではススメルと読み、やわらかく推奨するニュアンスがありますが、中国語の「勧」(quan)は勧告というか、もっと上からきつく下す命令に近いニュアンスがあります。
高津:だから、前の章の「直きを擧げて諸(もろもろ)の枉(まが)れるを錯(お)けば、則ち民服す」に近い。
成田:哀公との問答は、君主が家臣を登用する内容です。この章は、季康子が民を統治する内容です。
高津:上に立つ人がしっかりしておれば大丈夫、そうでないと大変なことになる。直と曲の人の問題。
成田:高津さんの読み方は、「勧」の字を他動詞とみなして敬忠を「勧」する、と読んでいます。だが、私はやはりこの「勧」は自動詞だと思います。民が積極的になるにはどうすればよいか、という意味で、善を挙げて不能つまり出来ない者でも教えて出来るように仕向ければ、積極的に働くようになるのだ、という意味で読むべきだと思います。
小田:この章での季康子の問題意識は、民を国のために奉仕させるにはどうすればよいか、ということです。昔の時代ならば戦争は士大夫以上の仕事であって、民はほうっておいてよい。しかし新しい時代では、民を戦争に動員して働かせる必要が現れ、大量動員の時代になりつつあった。だからこの章の問いとなったのではないでしょうか。
高津:孔子は、君子とは単に偉ぶるだけではなく、民を安定させる責務がまず最初にあると考えました。孔子は士大夫のためでなく、民のために政治をすることを、ずっと重視していました。
成田:孔子としての理想は、民が難しいことを考えずとも、君主がいい政治をするから民がそれに従う姿です。学而篇に、「子の曰はく、千乘の國を道(をさ)むるに、事を敬みて信、用を節して人を愛し、民を使ふに時を以てす」とあります。これは民を「時」つまりタイミングをみて使えということで、具体的には農繁期に徴用してはいけない、ということです。
小田:子路篇では、「子の曰はく、教へざる民を以て戰ふ、是れこれを棄つると謂ふ」とあります。ここで孔子の言っていることを裏返せば、民を教えてから戦場に出すのは認められる、ということではないでしょうか?
成田:徴発は土木工事もありますが、戦争のための徴発もありました。春秋時代でも、民を戦争に徴発しました。戦わなくても荷役などの人手が要るからです。だから戦争は春先の農閑期にするのが決まりでした。
ここで春秋時代の戦争や青銅器について脱線。春秋時代の戦争では、布陣を右翼と左翼に分ける。右翼に強い兵を置き、左翼に弱い兵を置くことが中原諸国の決まりだった。交戦すれば、双方の右翼がまず左翼に勝ち、次に右翼どうしの戦いとなった。ところが楚や呉などは違っていた。楚の布陣は左翼が強く、中原諸国との戦争はいきなり強兵と強兵との戦いとなった。それで、むちゃくちゃな乱戦となった。また、春秋時代には布陣や兵站の優劣によって、戦場で戦う前に勝敗を決することも多かった。楚の青銅器が周より優れているとする話がある。元来、青銅器については殷が優れていて、青銅器を使って酒を飲むのが礼儀であった。周が殷を倒したので、殷人の飲酒の礼儀を必要以上に悪く言って、酒池肉林など飲酒で滅んだイメージを後世に植え付けた。周が殷を滅ぼしたことにより、殷の青銅器職人はいなくなって、周では飲酒を戒めて青銅器つくりの技術は落ちた。楚の隣の越の製品では、越王勾践の剣が近年出土した。その合金技術は高度なもので、中原の合金よりも優れていた。辺境といえども、侮るべからざる技術を南方諸国は持っていたようだ。
成田:「擧直錯諸枉」ですが、通説では諸を「もろもろ」の意味に取り、また朱熹は錯を「捨て置く」、物を捨て置くという意味にとっている。しかし、諸を「これを」と読む説が別にあります。諸zhūは之zhī乎hūをつづめてzhūとした意味もあり、これに従って読めば「擧直錯之乎枉」は「直きを挙げて之を枉れるの上に錯く」と読めます。つまり、曲がっているものの上に真直ぐなものを置くと、曲がっているものが真直ぐになってゆく。そのようなイメージとなる。
小田:つまり後の読み方では、真直ぐな人材を上に登用して、曲がった人の上に置く。上から教え諭して、曲がったものを矯正する、という意味ですね。通説の読み方は、曲がった人はそもそも登用しないで、捨て置く。
成田:曲がったものの上に真直ぐな人を置くと、真直ぐになる。
小田:これは、組織の道理ですね。曲がった人材を上に置けば、下は去っていきます。
早川:明清代以降には、「之乎」のほうがが正しいとする読み方が、台頭しました。孔子の考え方からすれば、曲がっている人を捨てて排斥するのは、正しい捉え方ではないという考えです。
成田:日本では、徂徠が「諸」を「これを」と読み始めて、以降日本ではわりかし主流となっています。
小田:江戸時代は家禄は世襲で、つまらぬ家臣といえども辞めさせることは出来ませんでしたからね。
成田:吉川幸次郎先生の注釈では、最初為政篇のこの章で徂徠を引いて、徂徠説を採用しました。ところが後の顔淵篇22では一転して、前の為政篇では徂徠の考えを採用したが、いまいちど考え直してみる必要がある。徂徠の解釈はどうも窮屈に思える、と同じ本の中で変心しておられる。何が窮屈なんでしょうか?
小田:曲がっている者は全部矯正しなければならない、という解釈が、窮屈なのではないですか。曲がった者は曲がったままで、別段役所に登用されなくてもいいじゃないか。人それぞれの道があるのだから、なにがなんでも矯正というのは窮屈だ、といった感じでしょうか。
早川:孫応時は陸象山の弟子ですが、この人が「諸」を「之乎」と読み始めた最初の人です。
小田:徂徠では皆真直ぐにならなければならないが、朱子説では曲がっている奴はほっておけとなります。
成田:働きアリは、すべてのアリが働いているように思うが、その10%は働いていないと言います。だが巣からその働かない10%を取り除くと、やはりそのうちの10%が働かなくなる。働かないアリばかりを集めると、一転して働かなかったアリのうち90%が働くようになるとか。働くか働かないかの比率は、組織全体によって一定となる習性があるそうです。
小田:それは、人間の組織も同じです。組織の中では2割はよく働き、2割は働かず、あとの6割は働くふりをしていると言われます。この比率は、どんな組織でも変わらない。
成田:朱子の論では、働かないアリは除いてしまえとなるが、組織の法則としてこれで問題は解決しないようです。除いた後には、また新たに働かないアリが出てくる。むしろ徂徠のように、働くアリを組織の上に置いて、下をコントロールさせたほうが効果的でしょう。
小田:組織の中で開き直って明らかに働かないでいるのは、針のムシロですよ。そういう者は、他の者たちから必ず後ろで陰口を言われています。だから、働かないのは少数派なのです。圧倒的多数派は、体を動かしてさも働くふりをしています。それがいちばん精神的に楽だ。
成田:働かない人を働かせようとするのは無駄だから、働く有能な人を上に置いて管理させたほうがいい。上がきっちりしていれば、組織はいいのです。
小田:ゼークト(ドイツの軍人)は、有能な働き者は最もよく、無能な怠け者はまだマシだが、無能な働き者は最悪だ、と言ったとか。けだし、組織の名言です。(後注:正確には、「有能な怠け者は司令官となし[有能で他人に仕事を任せるから]、有能な働き者は参謀となし[有能で自分から仕事をするから]、無能な怠け者は連絡将校か下級兵士となし[自分で行動せず命令に従うから]、無能な働き者は銃殺刑に処せ[働くこと自体が害となるから]」と言ったといいます。)
高津:映画などで見るのですが、よいリーダーは徳がある。賢くて徳があるのに越したことはないが、賢くなくても徳があれば、リーダーとしてはよい。よくないのは、賢くて徳が無い人です。賢いから、賢さを悪事に用いることができるからです。
小田:有能で働く人間は、あまり得られない人材です。組織としては、無能で働かない人間でもそういう人は部下に任せて自分は何もしないから、まだましです。リーダー面して的外れなことを行う、無能な働き者は最悪ですね。
成田:この章の言葉は、能力と徳に優れた人材を上に置くべきだといっているのか、それとも能力が無くても徳があって心根が真直ぐな人を置くべし、と言っているのでしょうか。
小田:後者は、中国の組織論ですね。上に立つ人は、能力よりも人徳ある善人でなくてはならない。
高津:ところが中国では、子供でもお金と権力が上に立つ条件だと当たり前に思っています。どうしたことでしょうね。
早川:正直者は馬鹿を見る。
高津:真直ぐな人を置きたいが、それが出来ない。
小田:中国社会はそういった実情であったから、孔子が逆のことが正しいのだ、と声を大にして言ったとも考えられませんかね。
成田:今の中国では、共産主義理論に詳しいことが出世の条件ではありません。むしろ誰からも嫌われずに敵を作らないのが、偉く昇進するためによい。敵を作らないのも、まあ徳と言えば徳ですか。
早川:香港ではモメているようですね。
成田:中国では、徳があるから結果的にお金と権力が集まるのだ、と考えて、だからお金と権力がある人は徳があるのだ、とみなされます。そんな徳のある人だからお金と権力を任せてよいとなって、お金と権力が集まります。そんな人が汚職をしたり殺人をしたりすると、手のひらを返して袋叩きにします。
高津:もとは素直な善人であったのに、政治に入って権力と金を得る状況に入ると悪いことに走る。アメリカでもよくあることです。
小田:徳あるリーダーというのは、近年の日本ではあんまり見かけませんなあ。たとえば村山富一首相は、日本国内では評判が悪いが、外国の首脳間ではわりかし人気があったそうです。東洋人のご老体の風貌で、何か周囲の人々から尊重させる雰囲気があり、好感を与えたようですね。
成田:中国では、鄧小平がそういう雰囲気で称えられます。中国で鄧小平を悪く言う話は、まず聞きません。特に深圳では、鄧小平さまさまです。彼無くして深圳なし。
小田:深圳なんて、もとは何もない田舎でしたからね。香港側は今でもど田舎で、山一つ隔てた向こうの深?側にはビルが林立しています。
上田:日本人には擧直錯之乎枉の方がわかりやすい。錯が措cuòに通じ、捨て置くになるのでしょうが、錯は砥石で研くこと、曲がったものを直す感覚がわかりやすい。
成田:「錯」は、ものをまず取り上げてそこから下に置く、という意味ですが、ポイと置いたところにゴミ箱があれば、捨て置いたことになります。置いたところに曲がった人たちがあれば、曲がったものを矯正するということになります。
時間となりました。
2012年4月21日(土)論語為政篇
本日、早川君、小田さん、成田君、北澤さん、上田さんの五人。
月曜日のBS日本TVで夕方6時から孔子のドラマ(1時間もの40回)が放映されていて、陽貨から声をかけられたところあたりが先週のところ、と北澤さん。詩巻第二十(朱熹集傳)の「思無邪 思馬斯徂」で朱熹は読み方について指定をしていない。意味は「これ」、と早川君。思うと動詞ならsì 名詞ならsīとなる、と成田君。思うと思う事の区別がつきがたいものがある。王姫之車については、朱熹は斤於の反jūと尺奢の反chēと両方を記している、と早川君。現代中国語では一般的に車を指す場合chēと発音するが、将棋の駒の「車(俥)」だけはjūと読む、と成田君。元代に編纂された「孔子論語年譜」には、「孔子二十四歳母卒合葬於防」とある。「孔子の母は二十四歳で死んだ」ということだが、その根拠出典は分からない。しかし元代には孔子家語の年譜に記されるようになったらしい、と早川君。
早川君のリードで為政篇の音読。訓読と訳、今日はやはり小田さんでしょう。
或ひと孔子に謂ひて曰く、子奚ぞ政をせざる。子の曰はく、書に孝を云へりや。惟れ孝に、兄弟に友に、政有るに施すと。是れ亦政をするなり。奚(なん)ぞ其れ政をするとせん。
定公の初年、孔子仕へず。故に或人其の政をせざるを疑ふ。書は周書、君陳篇。書に孝を云へりやは、書に孝を言ふは此の如し。兄弟に善きを友と曰ふ。書に言ふ君陳能く親に孝に、兄弟に友あり。又能く此の心を推し廣め、以て一家の政を爲す。孔子之を引きて、言ふこころは、此の如くんば、則ち是れも亦政をなす。何ぞ必ずしも位に居りて乃ち政をするとせんや。蓋し孔子の仕へざるは、以て或人に語げ難き者有り。故に此に託し以て之を告ぐ。之を要するに至理亦是に外ならず。
或ひとが孔子に語りかけた、「先生はなぜ政治をしないのですか?」と。孔子が言った、「書経に孝についてこう云っている。『そもそも孝とは、年上・年下と仲良くして、その政(家政、身内への心配り)をさらに外にふりむける』と。これもまた政治をすることである。何で具体的に政治をする必要があろうか?」と。
定公の初年、孔子は仕えなかった。ゆえににある人が孔子が政治をしないことを疑った。「書」は周書君陳篇である。書に孝を云へりや、とは、周書に孝についてこのように言っている、ということである。年長者と年下とよい関係を持つことを友という。周書には、君陳が親に孝であり、兄弟と仲良くして、この心を推し廣めて一家の経営した、とある。孔子はこれを引用した。その意味は、このようにすれば、これもまた政治をしている。何で朝廷の位にいることだけが政治というべきか、ということである。孔子が仕えなかった理由は、この人に対して言いにくいことがあった。それで、周書に託してこれを告げた。つまりは、理の極致もまたこのことである(近いことから始めるのが、理に適っているのだ)。
小田:レジメを切らせていただきました。論語や孟子の中では、「なぜ仕えないか」というテーマがよくでてきます。孟子でもこのことがえんえんと述べられています。孟子は、「向こうから頭を下げてこないから」と繰り返して答えます。なぜここまで孟子がこだわるかに、私はこだわります。思うに、孟子は墨家からの批判を念頭に置いて、言っているのではないか。墨家は、儒家に対してレジメに引用したみたいに、滅多打ちに批判しています。いわく、儒家は進んで善をしようとしない。自分に利益が無いと見れば、国家の存亡の緊急事態であっても手をこまねいて何もしない卑怯者、と。孔子自身は、為政篇の後で出てくる「義をみてせざるは勇なきなり」と言っているくらいで、違うかもしれません。墨家が批判しているのは孔子そのものというよりは、それを継いだ戦国時代の儒家に対する批判であり、当時の儒家には墨家が言うようなところがあったのでしょう。為政篇のこの章は、そういった批判に対抗する意味で、孔子もまたこのようなことを言っているのだ、と弟子たちに示して暗誦させるために時代の師たちがテキストの中に置いた、いわば弟子たちへの思想的締め付けが目的で置かれた章ではないか、と思うのです。真の勇気は匹夫の勇じゃない。時と状況により打って出ないこともあるのだ。そういう孔子の後継者たちが弟子たちに言い訳をする声が、この章から聞こえてくるような気がします。たとえるならば、なぜ目の前にゴミが落ちているのにゴミ拾いをしないのか?と詰め寄られて、そのような行為は君子のたしなみではない、と答えようとしたのです。
成田:墨家と同時代の儒家ならば、孟子。その頃の儒家の実態は墨子に書いてあるようなものだったのでしょう。しかし、それと孔子とは違っていた。孔子は若いころは呼ばれると出て行く、あぶなっかしい人でもあった。孟子などからすれば、この章のような孔子像のほうが都合がよかった。朱子はこの章のことを定公の初年としているが、どうですか。
上田:孔子が斉から魯に戻って、陽貨から声をかけられ、何故参加しないというあたりの時代と朱熹はみているのでしょう。
成田:中都の宰とか司寇に出世する前ですね。
小田:貝塚先生は、ここの「あるひと」を陽貨と見なしています。
成田:私は話のムードが違うと思う。陽貨のときには孔子は反論できず、仕えましょうなどと言ってまるめこまれていた。しかし、ここでは、ドンと構えている、書経を読みなさい、孝行について書いてある、と質問者より上の立場で言っている感じがする。孔子が放浪を終えて魯に帰ってからとするほうが、しっくりくる。
小田:ならば、「あるひと」は陽貨ではないということになります。
成田:前の章の哀公や季康子と同じ時期ということになります。
小田:確かに史記にも、孔子は哀公の時期にも仕えなかったとは書いています。
早川:哀公の時、孔子は大夫だったのでしょう。
成田:官職ではなく、顧問の立場。
早川:「あるひと」の言い方は、皮肉っぽい言い方になっています。なんで仕えないのか?と。
成田:為政の意味合いを考えねばならない。「あるひと」が想定する為政は、政治の実務を掌ること。孔子が答えた為政は、実務を行うことではなくて為政の根本である人格の内容について言っています。孔子は晩年大夫であっても、実務は掌っていなかった。
早川:孔子は無理とわかっていても、大夫である以上言わざるをえないと諫言をしている。そういう立場にある孔子にこういう言い方は皮肉っぽいところがある。
小田:最初にこの章が定公の初年のこととみなしたのは、古注からですか?史記には、定公初年に孔子が仕えていなかったと書いてあるだけで、別にこの章の言葉が定公の時期の話とてい引用されているわけではありません。
早川:古注かどうか探していますが、分からない。定公の九年に孔子は司寇になっています。
成田:定公初年とみなしたのは、朱子オリジナルの可能性がある。
小田:朱子は、だったらなんでこの章のことを哀公末年に結びつけなかったのでしょうか。
成田:魯に帰ってからの孔子は高い地位にあったはずとだという考えがあったのでしょう。
小田:しかし、晩年の孔子をこの章のように上から目線で問いかけることができる人など、誰かいましたか。
成田:「あるひと孔子に謂ひて曰く」と、「孔子」と言っており、これは孔子より高い地位にある人の発言のはずです。それに対する答えとして「孔子応えて曰く」とあればこれは君主レベルであるが、「子の曰はく」なので、そうじゃないということになります。
小田:大夫の地位にある晩年の孔子に、ここまで上から目線で問いかけることができる人がいたのか。そこに朱子はひっかかって、もっと若い定公初年のこととしたのではないでしょうか。
上田:前の条、次の条を考えれば、晩年の方がしっくりする。
成田:学而、為政篇を通じて、晩年の発言として読めないものはない。ここだけ若いころにするのは不自然。
上田:為政の根本には孝や友があり、それを欠いては政治にならないと孔子はするが、それに耳を傾けるものがいない。
成田:孔子以外の役人の為政の概念と、書経に言う為政の概念とのズレがありました。
小田:そのズレを、孟子は無理やり結び付ける論理を展開したわけです。これで王たちを催眠術にかけました。
早川:書経は、「有政に施すと」とあるだけです。これを孔子が為政と結びつけるのは、我田引水ですね。
成田:書経の言葉は、孝と友が「有政に施す」。ここまでしか言ってません。
早川:孝と友が政治にプラスになる、施すところがある、それだけですからね。
上田:これは文王の政治のことを言っているのでしょう。孔子はそういう政治をいいたい。
成田:今ある君陳篇は、擬古文です。『論語』のここから後世の者が君陳篇を偽作したと言われています。擬古文は晋の梅賾(ばいさく)が「こんなテキストが出土しましたけど?」という触れ込みでとつぜん世に現れた代物でして、宋代くらいからあやしいという声があったのですが、清朝になって偽作と考証されました。その中に君陳篇も含まれています。
早川:偽作はたいてい読みやすく、中身はいいことを言っている。君陳篇とかは孟子学派のなぐさめに使える、後世の説に都合がよい中身です。
小田:墨家から、儒家は世のため人のためになぜ天下にうってでない、と批判をされていました。この章とかは、そんな批判に対して君子は時と場合が正しくなければそんなことはしないものだ、という言い訳であり、この章を暗誦させて弟子に対する思想的しめつけの効果を狙ったのではないでしょうか。為政篇の最後は「義を見てせざるは勇なきなり」であり、諸君我々は勇を忘れてはいないのだぞ、しかし墨家の行動は匹夫の勇で、孔子学派は匹夫の勇はしないのだ、、、と時の師たちは言い訳したかったのではないでしょうか。私はそのように、論語編集者の意図を推測します。
成田:ならば孟子が高位に出世して羽振りが良ければ、この章はなかったかも。
小田:しかし孟子は、結局後半生で天下の諸侯を説きに回る旅に出ました。この章とかは、その前の世代の子思あたりが入れたのかもしれないな。孟子は若いころは自重していたが年がいってから、このままでは儒家の存亡の危機だ、と思い立って遊説旅行に乗り出したはずです。
早川:曾参は、敵を見て逃げましたね。
小田:曾参が武城の町にいたころ、南から越が攻めてきた。曾参は、敵がやって来る前に留守番に対して「今から逃げるから、誰も我が家に入れさせるなよ」と言い残して、町を逃げていきました。武城の人々は曾参のまねをして、皆逃げてしまった。その後越軍が去ってから、曾参は悠然と帰ってきた、と『孟子』に書いています(離婁章句下、三十二)。孟子は他のところで、同じ部屋の中で争いごとがあれば髪をざんばらにして冠の紐を付けずに仲裁してもよいが、家の外で隣人に争いごとがあったとしても、髪をざんばらにして冠の紐を付けずに出て行くのは迷いであり、戸を閉ざしていてもよい、などと言っています(同、三十)。吉田松陰は、この章について評価に苦しんだようなコメントをしていますね。
北澤:君子危うきに近寄らず、ですかな。
小田:墨家は、孔子の思想の一部を受け継ぐところがあったと思うのです。孔子の知的で文化的な一面を子思や孟子などの儒家が受け継ぎ、行動的な情熱を墨家が受け継いだ。後世、その違った面を受け継いだ両者が、互いに争うようになった。墨子は儒家を攻撃することはあっても、孔子を認めています。ある人から、「あなたは儒家を攻撃するのに、なんで孔子を称えるのですか?」と聞かれて、「これその当にして易(う)べからざるのところなり」と答えました。孔子じたいの説は墨子にとってもしごく理にかなっているから、私は批判できないよ、と答えたのです。
北澤:行動的な子路とかが、墨家的ではないのでしょうか。
小田:しかし上田さんのお説では、子路は孔子よりも政治的な勘があって、孔子の政治的行動を諌めるようなところがあったということになりますね。子路がいなければ、孔子は政治でもっと失敗していた。
墨家から脱線。小田流にいえば、「存在論では道家にしてやられ、善を為す行動力では墨家に圧倒され、国家統治論では法家の台頭を許すようになった。儒家に残された得意分野は音楽と宮廷儀式だけ」ということだが、儒家にしてみれば、たいへんな集団にさらされ、どう対応してよいものか困ったのであろう。論語が編纂される過程にそういうものが影響を与えたことを考える必要がある。これは孔子の弟子達のおかれた困難。孔子が陽貨に誘われたのは、陽貨が三桓氏そして定公を牛耳って政権を奪取したことへの参加である。公山不狃にも誘われ、東周をなさんと豪語したり、佛肸(ひっきつ)の誘いにも乗ろうとしており、定公の君権を復活させるものと孔子が思ってみても、子路が止めねば、下剋上の片棒をかつがされる結果に巻き込まれていたかもしれない。60年代や70年代の安保闘争において、闘争に参加した学生の姿がダブる。歴史の必然としての資本主義から共産主義革命を教えられた世代には、参加するも参加せぬも苦しい選択を迫られた。自己批判の先に集団リンチの殺人に行き着き、なんと驚いたことか。孔子は子路を使って、三桓氏の武装解除を行い失敗して魯を去る。14年諸国を放浪して、輔佐すべき君主に恵まれず、魯に帰っても、用いられたのは冉求や子貢であり、大夫であり、諫言をすることがあるが、容れられない状況にあった。子貢のあげる外交成果により、孔子より子貢という家臣も結構いたようである。徳知政策よりも、富国強兵策が求められ、孔子の言も教団以外では受け入れられなかったようである。
「子奚ぞ政をせざる。」は政治が出来るというのになぜしない、と言う風に読めば、朱熹がいうごとく、定公初年、陽貨に誘われたというイメージになる。しかし、これ以外の読み方もあるでしょう。
成田:朱熹は、位に居ることだけが為政ではない、位に居なくても為政は可能としている。最後のくだりで、「為為」となっているが、これは文法的に不自然です。ある人の言った「子奚ぞ政をせざる。」の問い全体にひっかけて、「其れなんぞ『為政』とせん」という形で答えている。書経の「為政」にこだわる必要があったのでしょうか。
早川:古いテキストでは、「為為」でなく「為」一文字としているのもあります。この方がわかりやすい。「政をするに德を以てすれば、譬はば、北辰の其の所に居て、衆星之に共(むか)ふが如し」と為政篇の最初にあります。政をするには位に居て、徳をほどこす。
成田:しかるべき地位について政治をしないかになる。
早川:晩年の孔子は大夫という地位にあって、政治顧問の立場にありました。政治をしない、と問われるのは変で、朱子に肩入れしたくなります。
成田:孔子は魯に帰って来て大夫の身分で、特には官職についていなかった。ある人からすると、孔子ほどの大人物ならばしかるべき位につくべきだと考えたのでしょう。
小田:晩年の孔子に上から目線で言えるとなれば、哀公とか季康子くらいしかいなかったのでは?ならば、この章のある人は、どちらかでしょうかね。
成田:それはないでしょう、哀公とか季康子とするでしょう。
早川:どうして貴方は政治をいたさないのですか、はきついニュアンスです。
成田:就こうと思えば就けるのに何故就かないのですか、ですか。
小田:ある人が聞いたのは、現代的なニュアンスの「政」であり、つまりは国の政治です。それについて聞いてきたとき、孔子はわざと昔のテキストから引用して、古い意味の「政」つまり家の中の人間関係のようなことを言って、ある人の質問をはぐらかそうとしました。直接答えたくなかったから、学者流に煙に巻いたように見えます。こうは考えられないでしょうか。じつは、このある人は哀公の使者で、哀公は季康子を取り除く陰謀を企んで、孔子に出馬してくださいよ、と持ちかけた。それを、孔子ははぐらかして断った。重大な出来事だから哀公と明言できないので、ある人と言った、、、
成田:うーん、晩年の孔子の地位ともなれば、哀公とか季康子とか国のトップとの会話は記録されて、公開されて筒抜けとなります。そこで記録されるにはばかれる内容があったならば、ぼやかして書かれることもあったかもしれない。
小田:孔子が動けば、子貢とか冉有とか第一線で活躍している弟子たちも、師匠に従うしかなかったのでは。哀公は、それを期待した。
成田:それはどうですかね。孔子の晩年の頃には、前面に出て働いているのは、弟子たちです。孔子はその後ろにいる。若い世代のリーダーたちから見れば、変なじいさんが妙に皆から尊重されているのが、不審に思われたのかもしれない。それで、そんな尊重されているじいさんならば、なんで政治しないのか?と孔子に問うたのかもしれません。
小田:世代間の、孔子に対する温度差ですかね。野球の話ですが、私のような世代から見れば、長嶋とかがなんで上の世代たちからチヤホヤされているのか、さっぱり分からずにいまいましかった。しかし、私の上の世代は彼の現役時代を知っているわけで、彼のカリスマが焼きついている。長嶋は、人を育てるのはうまかったんですよ。決して凡庸な指導者ではなかった。ただ、実戦での采配が下手だっただけです。
成田:なんか、孔子にも通じますね。孔子の本領は弟子の教育にあって政治になかったから、見た目では孔子の価値は分からなかったし、弟子たちから尊重されている理由が外部の者には分からなかった。
時間となりました。久方振りに一揆で一杯。
2012年4月28日(土)孟子公孫丑章句下
本日、小田さん、上田さんの二人。
本日分音読、訓読と意味を小田さん。
孟子齊を去る。充虞路にして問ふて曰く、夫子不豫の色有るが若く然り。前日虞諸を夫子に聞けり。曰く、君子は天を怨みず、人を尤めず。曰く、彼も一時、此れも一時なり。五百年にして必ず王者興ること有り。其の閒必ず世に名ある者有り。周より來(このかた)、七百有餘歳。其の數を以てすれば則ち過ぎたり。其の時を以て之を考へれば則ち可なり。夫れ天、未だ天下を平治せんと欲せず。如し天下を平治せんとせば、今の世に當りて、我を舍いて其れ誰ぞ。吾何爲れぞ不豫せんや。
孟子が齊を去った。充虞は道中で質問をした、「先生はお顔色がお喜びでないようにみえます。先日それがしは先生からこう聞きました、『君子は天を怨まず、人を尤めず』」と。孟子が言った、「あれはあの時で、今は別の時だ。五百年毎に必ず王者が興るものだ。その時期となれば、必ず世に名を知らしめる者が出る。周が始まって以来、七百年余りが過ぎた。この年数からすれば、王者の出るべき五百年はもう過ぎている。時代を考えたならば、そろそろ王者がでてもよい頃だ。つまり天は、いまだ天下を平らかに治めようと望んでいないのだ。もし天下を平らかに治めようと望むならば、今の世に私以外に誰があろうか。私がどうして不機嫌であろうか(天の意志であるからどうしようもない)」。
小田:五百年ごとに聖王が現れる、という伝説があったようですね。孔子から五百年後に、王莽が現れました。王莽は、きっとその時期に自分が当っていると思い込んで、政権を簒奪して無茶をやらかすことになったのでしょう。
上田:彼も一時、此れも一時とは?
小田:朱注では、「彼」は先日で「此」は今日ということです。充虞が前に聞いた時は、天を怨まず人をとがめずと言ったのは正しかった。しかし今は状況が違うから、しかたないじゃないか。
上田:何が言いたい?
小田:小林先生は朱注は誤っているとされていますね。朱注では、充虞に話した状況と今とは違っているので、今は見た目にやっぱりしょげているのはやむをえない、と孟子も認めているという解釈です。だが心の底の本心は、しょげてなどいない。しかし小林先生は「彼も一時、此れも一時」を、あの時も今も一緒で変わらないと解釈します。つまり、今も全くしょげてなどいない。小林先生の方が、孟子はポジティブに考えていると見ているわけです。朱子は、じつは孟子もショックでしょげているのだが、天のなすことだから怨んでもしようがない、不機嫌になってもしようがない、とあきらめの境地である解釈です。結論としては、両者の解釈とも孟子はしょげてはいないという最後の言葉となります。ただ、孟子の心境が違います。
上田:「天を怨みず、人を尤めず」と言って不機嫌な顔つき。どういう風に見えようが、次の章のことが言いたいための前置き。
小田:こんな言葉を、孟子があえてここに入れようとした意図は、何だったのでしょうか。こんな失敗者の愚痴のような言葉、思想だけを語るのであれば入れなければよかった。それは、自分は斉でうまくいかなったが、それは自分の責任じゃないぞ、天の時が悪かっただけなのだ、という弁明の意図があったに違いない。政治でしくじった戦犯が「意図は正しかったんだ、ただ時代と状況が悪かったんだ」などと弁明する、典型的な姿ですね。孟子が斉で失敗したことは、この時代天下周知のことです。だから、著作で決して孟子は悪くなかったのだ、と言い訳しておかないと、儒家の親玉として面子が立たない。親玉の死後にも活動していく公孫丑とかの弟子が、諸国で相手にしてもらえない。そのために儒家のアンチョコの中に言い訳を書いたのでしょう。
上田:いきなり五百年説にゆけないので、弟子の疑問に応えるという導入としたのでしょう。
小田:今の乱世、王者が出てそれを輔佐するものがでていい時期である。斉王をたてて王者とするために斉にいたが、いられなくなったのは天がそれを求めていなかったからである。こう総括したのですね。
上田:そこで終わっておけばいいのに、その後に余計なことを言ってしまった。
小田:この章は、尽心篇の最後の章と連動しているのです。「孟子は言う。『堯・舜から湯王に至るまでの間は、五百余年であった。禹や皋陶(こうよう)のごときは、堯・舜のなすことを見て知っていた。後の世の湯王は、堯・舜の事跡を聞いて知った。湯王から文王に至るまでの間は、やはり五百余年であった。伊尹や莱朱(らいしゅ)のごときは、湯王のなすことを見て知っていた。後の世の文王は、湯王の事跡を聞いて知った。文王から孔子に至るまでの間は、やはり五百余年であった。太公望呂尚や散宜生(さんぎせい)のごときは、文王のなすことを見て知っていた。後の世の孔子は、文王の事跡を聞いて知った。孔子から現代に至るまでの間は、百余年しか経っていない。このように聖人が世を去ってから、それほど遠く隔たっていないのだ。そして余が生を受けた鄒(すう)は、聖人の故国の魯からこんなにも近いところにあったのだ。ならば、余が孔子の事跡を伝え聞いたことを残さなければ、後世に聖人の道を聞いて知る者はとうとういなくなってしまうだろう。』」(尽心章句下、最終章)とあります。孟子は、この章で自分の位置付けを言います。孔子は即位して世を変えることはできなかったが、堯・舜・禹・湯・文・武・周公を継いだ聖人であった。孔子を継ぐのは私であり、ここで私が何かをしないとダメになる。孟子は結局天下平定に失敗したので、後世の読者に私が何のためにいたのかを、ここで訴えようとしたのです。天下平定はできなかったが、せめて聖人孔子の言葉を後世に伝える使命だけは果たしたのだ、と。この最終章の前の章は、自分の思い通りにならない世の中に怒り、自分の考えを容れない世の中を呪う、とても暗い章です。
上田:五百年説は司馬遷も取り入れていますね。
小田:当時ではポピュラーな説だったのではないですか。孟子がはじめて言い出した、というものではなかったでしょう。
上田:文王は何時くらいの人でしたか。
小田:殷周革命の時期は、いくつか説がありますが紀元前11世紀ごろです。文王はその頃に死に、孔子は紀元前552年の生まれとされているので、文王の死後だいたい500年後に世に現れた計算です。(小田後記:この計算はちょっと合いすぎているので、私は500年説は孔子死後の儒家が孔子を文王・武王・周公の後継者の聖人として祀り上げるために作ったと思っています。堯舜から殷が500年であり、殷から周が500年であったという孟子の説は、だから私は儒家が孔子を聖人に祀り上げるために作った、さしたる根拠のない年数だろうと思います。)
上田:この章句の出だしは、天の時、地の利、人の和の話から始まっており、天の時も人の和もなく実現しなかったで終われば、それなりにすっきりするが、最後に余計なことを二言言ってしまい、ぶちこわしになっている。
小田:それは、さきほど申しましたとおり、言い訳しておかなければならない事情があったからでしょう。
ということで次も小田さんが訓読と訳。
孟子齊を去りて休に居る。公孫丑問ひて曰く、仕へて祿を受けざるは、古の道か。曰く、非なり。崇に於て吾王を見ることを得たり。退きて去る志有り。變ずることを欲せず。故に受けざるなり。繼いで師命有り、以て請ふ可からず。齊に久しきは、我が志に非ず。
孟子が斉を去って、休という所にいた。弟子の公孫丑が質問し、「仕官して祿を受けないのは、古の道ですか?」と。孟子が答えた、「そうじゃない。崇という所で私が斉王に初めて謁見することができた。謁見から退いたときには、もう去ろうと思っていた。その気持ちを変えたくなかったので、祿を受けなかっただけである。続いて戦争の諸事が起こって、退官を請うことができなくなった。斉に長くいたのは、私の志ではなかったのだ」と。
上田:なんとまあ、すてぜりふみたいなことで・・・
小田:後世に残すために、こう書かざるを得なかったのでしょう。禄を受けないのは礼に反することだが、心中の義を偽ることができなかったので、禄を受けなかった。戦争が起こり、図らずも長くいることになったのだ、と。実際は、斉王に会った最初のときから去るつもりであったはずがないでしょう。もっと乗り気だったはずです。史記にも記されているように、斉の燕侵略の音頭を取ったのは孟子のはずで、それが大失敗に終わった。こうして政治家として失敗者であるという孟子への評価が、世間には固まっていたのでしょう。それを放置しておいては儒家として困るので、このテキストを作って自分に続く儒家のために残したのでしょう。孟子は決してまちがってはおらず、儒家の論理は正しい。斉で失敗したのは、孟子の責任ではない。斉の国が悪いのであり、あるいは天の時が悪かったのだ。斉に長くいたのは、じつは孟子の本意じゃなかった。そう言いたいのです。
上田:はじめと、終りの落差にがっかりする。言い訳となるとは思えない。
小田:公孫丑章句の最初で、斉に天下を取らせるのは手のひらを返すように簡単だ、と自信満々の出だしでした。それが、末尾ではしょぼくれてしまいました。
上田:しかし、朱熹なんかはそういうことは言わない。
小田:朱子に限らず、王陽明だろうが伊藤仁斎だろうが、孟子が実際に諸国で行った行動を全体として追って読むようなことはしません。一コマ一コマを読むように、各章ごとにその思想を読み取ろうとします。朱注では、孔氏を引いて、「仕へて祿を受くるは、禮なり。齊の祿を受けざるは、義なり。義の在る所、禮時有りて變ず。公孫丑一端を以て之を裁せんとするは、亦誤りならずや。」とあります。礼の正しさと義の正しさがあって、ここで孟子は義に従って礼をはずしたのだ。こういうことも許されることが公孫丑は分かっていない、と。このように、孟子のこの章から思想を抜き取ろうとして、孟子の斉時代の行動が全体としてどのようであったか、といったことは、わりかしどうでもいい。彼ら注釈者にとって孟子は思想書であって、歴史書でないのです。
上田:言い訳として成功しているようには思えない。
小田:当時の儒家が置かれていた心境を考えなければ、分からない事があるでしょう。孟子は失敗した政治家であるとする評判を、否定しなければいけなかった。孟子の説は政治として失敗であり、儒家の主張は政治のために役立たない、といった批判の芽は何としても摘まなければいけない。だから、孟子が失敗したのはたまたま時が悪かった、本意は別にあった、孟子は正しいのだ、と反論しなければいけなかったでしょう。
上田:小林先生はそういうことになにかコメントをされていますか。
小田:そこまで踏み込んではおられない。孟子の思想が大事であって、孟子の業績を問うことはしないというのが伝統的な読み方です。孟子の政治活動について批判的な読み方をしているといえば、福沢諭吉とかはそうですね。儒学を勉強するには、孟子について言われている思想を読み取らなければならず、孟子の歴史的な活動の是非を詮索する読み方などしてはいけない。それが、読書の掟でした。伊藤仁斎は、だから孟子のことを論語の必読の解説書として位置づけ、孟子を読むことによって論語の言いたいことが体系立って理解できるのだ、と推奨します。仁斎は思想書として、孟子を読むのです。しかし荻生徂徠は、仁斎とはだいぶん孟子への評価が違います。徂徠は孟子のことを、孔子本来の業績を論争で用いる抽象的な議論によってねじまげてしまった、儒学が堕落した張本人のように批判します。徂徠は孟子を間違った思想家として批判しています。
上田:先週の論語でも、小田さんから、戦国時代の儒家は、墨家や法家から攻撃をうけており、思想家として、孔子が置かれていた立場とは異なる。朱熹の時代にも儒家も厳しい立場に置かれていた。しかし、我々はそういうものとは違った状況にあり、そういう眼で読みなおしてみる必要がある。
小田:孔子にはライバルというものがなかったが、孟子の場合には強力な論敵がいました。先週見たように儒家は墨家から、進んで善を行なおうとしない卑怯者だと痛烈な批判を受けていました。孟子はその批判を打ち消すためか、儒家だって行動をすることを身をもって示し、また大国の梁(魏)や斉ばかりでなく宋や滕やという小国へも行ったのは、墨家を意識していたのではなかったでしょうか。墨家は、すすんで小国の味方となって、大国の侵略から実力をもって防衛戦を戦っていたわけですから。孟子もまた、それに対抗したのか小国を見捨てるわけではない意気を示しました。
上田:燕への出兵に関して、菅仲ならできたことが孟子にはできなかった。もし、孟子がそれを自覚して、そういうことが出来る者と連携できておれば、事態は違ったかもしれない。戦争をはじめてしまうとそれを統御することは孟子としても如何ともすることができなかった。
小田:思想家は真面目すぎて妥協ができず、思想家であって政治家であるということは非常にむつかしいということでしょう。両立させたのは、レーニンくらいですかね?プラトンだって一時政治に関わりましたが、結果はさっぱりでした。
上田:孟子の場合、思想と実際起こったことが分かり、実際の難しさを考えさせてくれます。それは、孔子の場合もそうですが、老子の場合は、その人となりが分からないので、その思想だけでは、なんとでも考えられしっくりこない。言い訳をせざるを得ない孟子がいる、あの孟子をそこへ追い込んだ戦争への対応のむつかしさを改めて考えさせられる。アメリカがイラクのクエート侵攻に軍を派遣したこと、フセイン政権を打倒したこと、これが中東の安定化をもたらし、アメリカの名声を高めることになったかといえば、そうでない。
小田:イラク戦争の時期のアメリカは、自国の力を過信している時期でした。大国というのは、世界の隅でじっとしていることは許されず、必ず諸国の標的にされます。だから力があれば時には平定の軍を起こすことも、やむをえない。しかしイラク戦争は、アメリカの力に過ぎたものだったかもしれない。フセインを倒したことで隣のイランを調子付かせて、今また対応に苦慮しています。今やアメリカの国力はかつてより衰えてしまい、とても極東に積極的に手を伸ばす余力がない。それを見越している国もあります。外交や戦争は、思想から導かれる理想とは、違う原理も見なければならないようです。かといってエジプトやリビアでは民衆が独裁政権を倒したわけで、民をないがしろにした政権は倒される運命だという孟子の放伐論が正しいことを示しました。だから、必ずしも思想のとおりに政治が動かないとは言えず、極東だって今後どうなるか分かりません。ともかくこれで公孫丑章句は終わりで、次はもう一度戻って梁恵王章句下からです。これまで読んだことの繰り返しの部分もありますが、後で出てくる滕のエピソードへの予習にもなりますし、いろいろと面白い章もある箇所です。
2012年5月12日(土)為政篇
本日、成田君、小田さん、上田さんの三人。
成田君のリードで為政篇音読、訓読と意味を小田さん。
子の曰はく、人として信無くんば、其の可なることを知らず。大車輗(げい)無く、小車軏(げつ)無くんば、其れ何を以てか行(やら)んや。
輗は五兮の反。軏は音月。○大車は、平地任載の車を謂ふ。輗は、轅(えん)の端に橫木をし、軛(やく)に縛りて以て牛を駕する者。小車は、田車・兵車・乘車を謂ふ。軏(げつ)は、轅の端、上曲し、衡(こう)を鉤(こう、ひっかける)して以て馬を駕する者。車に此の二つの者無くんば、則ち以て行く可からず。人にして信無くんば、亦猶是のごとし。
孔子が言われた、「人としてもし信が無ければ、その人が可であることすら分からない。大車に輗が無く、小車に軏が無ければ、どうして前に進むことができようか」と。
輗(げい)は五(ご)兮(けい)の反切。軏(げつ)は音月(げつ)。○大車は、平地で荷物を載せる車を言う。輗は、轅(ながえ)の端に橫木をし、軛(くびき)に縛って牛を御するものである。小車は、田車(耕作用)・兵車(軍隊用)・乘車(乗用)を言う。軏(よこがみ)は、轅の端にあって上り曲がり、衡(こう)を鉤(ひっかけ)て馬を御するもの。車にこの二つのものが無ければ、進むことが出来ない。人にして信が無ければ、車と同じことになる。
成田:朱熹は車についてあまり詳しくない。朱子は大車を輗、小車を軏としているが、清朝考証学によれば、春秋時代においては両者は同じようなもので、轅(ながえ、車を前から引っ張る腕の部分)が1本しかなかった。1本の轅の車は2本の轅の車に比べると牽引する能率が非に悪くて、中国ではどうして長らく1本の轅を採用していたのかというのも、興味深い問題です。
上田:1本の轅は、戦車を小回りを効かせて運転することに優れていたからでしょう。
成田:古代の車は馬の胸あたりに横木があり、Y字で衝に繋がれていた。轅の先は上に曲がって、一か所で衝に接続される箇所が輗または軏と呼ばれていた。後の時代に轅が二本でリヤカーみたいに荷を引く車の接続部が輗、轅が一本の接続部が軏と言われるようになったようです。
上田:輗、軏と信との関係をどうみますか。
小田:車に輗・軏がなく、人に信が無ければ、いずれも役に立たない。そのことは明らかだということではないでしょうか。
成田:車と牛馬の関係を人にたとえているわけですが、車と牛馬は人においてそれぞれ何に当るのでしょうか。どうですか。
小田:この章の「信」は、別段「礼」であってもよいのではないでしょうかね。牛や馬がある。車がある。しかしそれらをつなぐ輗・軏がなければ荷物が運べない。人の場合ならば、その人の能力はあるかどうか分からないが、その人に実際に仕事をさせることが出来るか、任せることができるかどうかは、なにものかが必要だ。それがなければ、能力いかんにかかわらず、何の役にも立たない。名馬であっても、輗、軏が無ければ車を曳かせることはできない。それと同じで、有能な人間であっても、その人に信がなければ仕事をやらせてよいのか判断できない。仕事を誠実にする人だ、という信がなければ、何をしでかすか予測もできず、不気味で仕事を任せることができない。そういうことでしょうか。
成田:信とは何ですか。
小田:信頼というか、信用というか、そういうものでしょうか。
成田:人と人との間のことですか。
小田:もし相手に信用がなければお金を貸すことはできないし、仕事を委任することもできません。ものごとを委任するには、信が必要です。
成田:車が課長で、馬が平社員。信がないといかに有能な社員でも課の仕事はうまくゆかない、そういうものですかね。
小田:仕事というのはなんでもかんでもマニュアルで指図して配下を動かすようなやり方は、本当の仕事じゃない。大なり小なり、相手に自由裁量を認めて、仕事を委任します。それは、相手を信頼信用して行うのです。しかしたとえば支店長が、会社の金を勝手に使ってしまう。これは信用できない人を信用してしまって、組織を危機に陥れる例です。こういった例は、数限りない。しかし、仕事とは相手を信用信頼して委任しなければいけない。仕事を委任されるためには、やっぱり相手に信を与える人間でなければ、仕事もやらせてくれません。配下に全幅の信頼を与えて、大きな仕事をさせる成功例も、やっぱり数多くあります。新米若造の諸葛亮を信頼して重用した、劉備とか。無名の陸遜を信頼して軍の指揮を任せて勝利した、孫権とか。仕事とは、相手を信頼信用して委任するものです。この章は、委任して仕事を行わせるために必要な原理を言っているのではないでしょうか。
上田:輗、軏も信も無ければ、用をなさないという方向もあるが、では輗、軏と信はどう同じかとなる。馬と車を結びつけ機能させるのが輗、軏、人と人がバラバラにならないで結びつけるものが信、その要ということではないか。
成田:私の考えですが、車と馬が一体になる、これを一人の人間でみれば、馬とは人間の志であり、それがあって何かを引っ張っていって、はじめて仕事ができる。信は人と人の間のこともありますが、一人の人間の中でも、志が行動と一致することを信と考えたい。そのような人を、周囲の人たちは信用する。言行一致の信、これがなくて単に志ばかりだと暴走する馬のようなもので、実あることができない。しかし輗・軏でつなげば、車を引っ張らせて走らせることができる。同様に人の志を言行一致の信で繋げば、前に進むことができて人に信用される。それがなければ、実現可能性を考慮しておらず、可であるとは言えない。
小田:その読み方ならば、信とは信念、あるいは信仰でしょうか?
成田:むしろ、誠実さでしょうか。
上田:自分に対して信があるかというのは孔子が問いそうなこと。大事なことです。
では次を小田さんよろしく。
小田:この注は長いです。
子張問ふ、十世知る可しや。子の曰はく、殷は夏の禮に因り、損益する所知る可し。周は殷の禮に因る、損益する所知る可し。其れ或は周に繼ぐ者、百世と雖も知る可し。
陸氏曰く、也は一に乎に作る。○王者姓を易へ、命を受くを一世と爲す。子張問ふ、此より以後、十世の事、前知す可しか。馬氏の曰く、因る所は三綱五常に謂ひ、損益する所は文質三統を謂ふ。愚按ずるに、三綱、君は臣の綱爲(た)り、父は子の綱爲り、夫は妻の綱爲るを謂ふ。五常は、仁義禮智信を謂ふ。文質、夏は忠を?び、商は質を?び、周は文を?ぶを謂ふ。三統、夏の正は寅に建す人統爲り、商の正は丑に建す地統と爲し、周の正は子に建す天統と爲すを謂ふ。三綱五常は禮の大體、三代相繼いて、皆之に因りて變ずること能はず。其の損益する所、文章制度の小過不及の閒に過ぎず。而して其の已に然るの迹は、今皆見る可し。則ち今より以往、或は周に繼ぎて王たること有るは、百世の遠きと雖も、因る所革むる所、亦此に過ぎず。豈但十世のみならんや。聖人の來を知る所以の者は、蓋し此の如く、後世の讖緯(しんい)術數の學の若きに非ず。○胡氏曰く、子張の問ひ、蓋し來を知ることを欲す。而して聖人は、其の?に往く者を言ひて以て之を明らかにす。夫れ修身より以て天下を爲(をさ)むるに至るまで、一日として禮無んばある可からず。天敍天秩は人の共に由る所、禮の本なり。商は夏に改むること能はず、周は商に改むること能はず。所謂、天地の常經なり。乃ち制度文爲の若し、或は太過なれば、則ち當に損すべし。或は足らざれば、則ち當に益すべし。之を益し之を損し、時と之を宜しくして、因る所の者壞れず。是れ古今の通義なり。往に因りて來を推すに、百世の遠きと雖も、此の如きなるに過ぎざるのみ。
子張が質問した、「十世(解釈の分かれるところだが、朱子の解釈では十王朝)先を知ることが出来ますか?」と。孔子が答えられた、「殷の礼は夏の礼に依拠しており、両代で削ったり増やしたりした部分を知ることができる。周の礼は殷の礼に依拠しており、これも両代で削ったり増やしたりした部分を知ることができる。そもそも周を継ぐ王朝があらわれるなら、百世(これも朱子の解釈に従えば、百王朝)先でも知ることができる」と。
陸氏が言った。「『也』の字は『乎』の字に作る例がある」と。(最初の子張の問いは疑問形で、後の孔子の答えは平叙文。陸氏の指摘しているのは、子張の問いの「也」に限っている。)○王者が姓を易え、天命を受けるものを一世とする。子張が質問をした、「これより以後、十王朝先の事を予知できるのでしょうか?」と。馬氏が言った、「『因る』というのは三綱五常を言う。『損益』つまり削ったり増やしたりするのは文質三統を言う」と。それがし(朱熹)が思うに、三綱とは、君主が家臣の綱であり、父が子の綱であり、夫が妻の綱であることを言う。五常とは、仁義禮智信のことである。文質とは、夏王朝が忠を尊び、商(殷)王朝が本質を尊び、周王朝が文化を尊ぶことを言う。三統とは、夏王朝の暦が正月を寅の月(1月)とする「人統」であり、商王朝の暦が正月を丑の月(12月)とする「地統」であり、周王朝の暦が正月を子の月(11月)とする「天統」であること言う。三綱・五常は礼の本質であり、夏・殷・周の三代が相伝えるものであり、すべての王朝はこれに依拠していて変えることができないものである。削ったり増やしたりする部分は、文章制度のちょっとした余計な箇所や足りない箇所の範囲に過ぎない。そして過去にそれらが変遷した痕跡は、今の時代においてもすべて確かめるこができるものだ。つまり、今より以降、あるいは周を継ぐ王者が出現したとして、百王朝先といえども依拠する所と改める所は、これらのことを越えることはない。ただ十王朝の先のみではないのだ(もっと先まで同じである)。聖人(孔子)の未来を予知する根拠とは、以上のようなものである。後世の「讖緯術數の學」(予言)のごときものではないのだ。○胡氏が言うに、「子張の問いは、つまり未来を予知することを望んでいるのだ。しかし聖人(孔子)は、過去の諸王朝の例を出して未来を明らかにする。身を修めることより天下を治めることに至るまで、一日として礼が無いことはない。天の秩序は、人が共に依拠する所であり、礼の本体である。それについて商は夏を改めることはないし、周は商を改めることはない。いわゆる「天地の常經」つまり永久不変の道である。だから制度とか文章のごときは、行き過ぎていれば削り、足らなければ増補すればよい。増補したり削ったりを時宜に合わせて行えばよく、それで依拠する所のものが壊れることはない。これが古今の通義である。過去に依拠して未来を推測するなら、百王朝先といえどもこの通義を越えることはない」と。
成田:お疲れ様です。
小田:朱子の解釈は、非常に理知的な読み方ですね。
成田:解釈としては、理屈しか言っていません。
小田:しかし、孔子は朱子が解釈したような内容が、本当に真意だったのでしょうか。それこそ、朱子が「讖緯術數」として斥けたようなオカルト的な予言こそが、孔子がこの言葉で想定していたのかもしれませんよ。ここで言及されているのは暦の変遷ですが、夏正・商正・周正の変更はなぜ行われたのでしょうか?
上田:太陽の1年と恒星の1年のズレや地球自転のズレによるというものじゃないですか。人間は春夏秋冬と月が一致しないと困るので、季節感にあうように修正した。
成田:そういったズレが暦の変遷の本質ならば、1月の次は2月、2月の次は3月、、、と王朝ごとにずっとズレていってもよい。しかし、漢は時間を遡って夏正を選択しました。
小田:その夏正が漢以降は標準となって、二千年間固定された。もう漢以降はズレなかった。いわゆる、今の時代で言う「旧暦」ですね。
成田:衛霊公篇に、顔回が邦を治めるについて質問したときに、孔子が「夏の時を行ひ、殷の輅に乘り、周の冕を服し・・・」と述べています。暦は夏、輅(車)は殷、服装は周を採用すればよい、と孔子は答えています。子は冬至の頃で、陽の力が一番弱まっている時期です。暦としては正月から春が始まるとみなされるわけですが、冬至の頃では春にしては寒すぎる。中国人の季節感からすれば、寅の月(いわゆる旧暦1月)を正月として新春とする夏正が一番ピッタリしているといえます。だから、漢以降は動かなかった。動かして周王朝の暦にこだわったのは、王莽と則天武后が周正を採用したくらいです。いずれも現実離れした暦を採用したわけで、長続きしませんでしたが。
小田:たしか、秦と漢は違った暦だったと思いますが。秦は秦で、今度は10月を正月としていた暦だったのではなかったでしたっけ?
成田:一時期のみでしょう。
小田:また項羽は一時的に西楚覇王と称し、楚王朝がわずかの期間あった。その楚王朝もまた夏正とは違った暦を用いていたはずです。
成田:楚のような南蛮は、中華の制度に縛られなかった。孔子は、さきほどの衛霊公篇のように、暦としては夏のものが、工芸品・実用品は殷のものが、礼楽は周のものがよいと評価していました。
小田:孔子は当然周の制度の時代に生きていたわけで、しかし孔子はさっきの衛霊公篇のように周の制度にこだわらずに夏や殷のおいしいところもつまみ食いしようとしていた。とすると、既存の制度を変更するべきだと考えていたわけでしょうか。つまり、孔子は衰退していく周代の遺した制度にすでに見切りを付けて、来るべき理想の新王朝のシステムを構想していた、とでも言えるのでしょうか?
成田:孔子は、周について礼楽を称え、他の点で殷と夏を称えた。中国の文明は、殷も夏も周もみな大事に引き継ぐべきであり、そういう文明の継承者を孔子は自認していたのです。だから、過去の王朝の制度のよい点をそれぞれ評価しました。
小田:しかし、周の時代なのですから、当時の暦は周正であり、子の月を正月とするのが年中行事として行われていたはずです。その時代に孔子は夏正のほうが合理的でよい、と言ったというのは、まるで旧暦で動いていた江戸時代に新暦のほうがいいから私は新暦を採用する、などと言っているのと変わらない、、、それでは、孔子は時代の慣習に反抗して新制度を提唱したように見えます。それは、いささか奇妙だ。
成田:新暦は珍奇な新制度ですが、夏正は過去の制度の復活という点が、違いますけれど。
小田:しかし、当時の新年の行事は周正で行われていたはずですよね。その時代に夏正の暦を用いたのでしょうか。『春秋』は夏正の正月を採用して書かれていたのでしょうか?
成田:どちらだったかな、、、調べないといけない。ともあれ春秋時代には実際にどの暦が使われていたのか、調べておきましょう。
(周王朝にあって周が天文観測をして暦を作り、諸侯を集めてこれを発布し、各国に置いて史官がそれに基づいて記述をし、共通の祭祀などの行事が行われたと思われるが、春秋時代となると必ずしもそうではないという。月をずらすだけで、換算が可能らしい。)
(成田:昨日の周正・夏正と『春秋』の暦については、当サイトをご参照下さい。簡単にまとめると、孔子の時代には夏の時代から継承された(と信じられた)伝統的な暦が普通に使われていて、「周正」はそもそも存在しなかった、ということです。)
(小田後記:成田さんから紹介されたホームページの叙述によると、この三代の暦が一ヶ月ずつずれているという議論は、根幹から疑う必要があるということです。結局、時代に関わりなく現代の「旧暦」と同じ夏正(の原型となるような暦)が中国では常識的に採用されていたのであり、周正という暦は紀元前四世紀 -つまりだいたい孟子のいた戦国時代前半期のことですが-に帝王の制度としての暦が定められた時期に成立した(そして過去に遡って投影された)、フィクションの暦にすぎないということになるでしょうか。書物に書かれた夏・殷・周三代の制度は後世に理想化された多分に架空の産物であり、実際の三代に行われていた制度とにはズレがあると言うべきなのかもしれません。)
上田:朱熹は一世を一王朝とするが、夏や殷は数百年続いており、十王朝なら数千年、百王朝なら数万年であり非現実的。
成田:たとえとしての言い回しとしてなら、可能でしょう。
上田:夏の前に堯舜の世とか伝説の王に遡れるが、数千年くらいのもので、数万年というものが孔子の頭にあったのだろうか。
小田:孟子では、「一世」を30年とみなしています。
成田:「一世」は30年という意味が普通です。だから十世ならば300年。これならば、先でも後でも推測が可能な範囲でしょうね。
上田:季氏篇に、「孔子の曰はく、天下道有れば則ち禮樂征伐は天子より出ず。天下道無ければ則ち禮樂征伐は諸侯より出ず。諸侯より出ずれば蓋(けだ)し十世にして失(う)せざること希(すく)なし。大夫より出ずれば五世にして失せざること希なし。陪臣が國命を執り三世にして失せざるは希なし。天下道有れば則ち政は大夫に在らず。天下道有れば則ち庶人議(ぎ)せず」とある。子張はこの十世で、諸侯の時代も続かないと疑問を呈した。孔子は、天下に道が行われば、十世どころか百世先も分かる、夏、殷、周を引き継ぐものだとした。
成田:子張は、「今の世はまずいことになっていますよね、300年後にはいったいどうなっているのでしょうか?」という意味で問うたのでしょうか。しかしそれに対して孔子は、「300年どころじゃなくて3000年先だって見通せる。それと比べれば、300年などなんてことはない」とはぐらかした。へっちゃらだ、と。
上田:ここでは二つの事がいわれている。王朝の根本はかわらず制度に多少のズレがある。朱熹は根本を三綱五常、ズレは文質三統の範囲ということ。もう一つは、過去を知ることで未来を推測できる。
成田:子張は未来のことを心配して問いました。しかし孔子は、過去も未来も併せて答えました。過去も未来も、どっちも言わなければならない。夏殷周以前から百世後に至り受け継ぐべき伝統がある、と孔子は自覚していたから、こう答えたのでしょう。
時間となりました。
2012年5月19日(土)為政篇
本日、成田君、小田さん、上田さんの三人。
周正に関する「新城の『春秋』年始早晩図(『春秋』暦日にもとづく正月朔と冬至)」について基礎的なことを解説いただく。ここでの「春秋」とは春秋経のことで、魯国の史書(魯の隠公元年<紀元前722年>から下は哀公十四年<紀元前481年>)。その春秋経に書かれた期間の正月と冬至の関係を、グラフに落としたもの。その結果、孔子の時代ごろにはほぼ冬至近くが新年に選ばれていたことが分かる。冬至が新年に選ばれる理由は、太陽が一番短い日であり、太陽が一番弱いところから復活するところに神聖性を見出したのであろう。これはキリスト教でも復活と関連付けられ、人類共通の認識と言える。しかし、冬至の日を前もって予測することは、古代ではむつかしかった。結果、日が短くなる日が尽きて長くなり始める日=冬至が来てから、初めてその年の冬至の日を確定できたという時代があったはずだ。つまり、日が一番短かった冬至の日を観測して、その一月後を正月とする時代があった。前722から前650年くらいまではそういう形で冬至後に正月がおかれていた。だが前650年から前600年くらいになると天文観測のデータが蓄積されて、毎年の冬至の日を前もって予測することが可能になった。この時期以降になると、冬至のある月を正月とすることになったと思われる。したがって、周初から冬至を正月とするという周正は成立しておらず、周代に天文観測をして暦を定めて諸侯に配布していた、という説も成立しないことになる。
春秋経は、魯の記録である。これは周の暦を拝領していたのか、魯が自分で暦を観測して用いていたのかは、定かでない。
春秋経の伝の一つである『春秋左氏伝』(左伝)について。平セ氏は左伝での正月を点線グラフで記しておられる。それによると、左伝は正月を立春を含む月に設定していて、春秋経と異なっている。これは、冬至では年初=春の始まりとしては季節的に寒すぎるので、春夏秋冬の季節感に合わせた暦を採用したものであろうか。この立春の月を正月とする暦は、夏正と言われる(要は現代における「旧暦」)。伝説では夏の時代に天文観測をして定めたと言われているが、夏の暦とは思われない。むしろ季節感と合うことから、用いられるようになったものとみるべきである。
春秋経は叙述が簡潔すぎて、詳細な注釈をほどこした「伝」がある。現存するのは『春秋左氏伝』『春秋公羊伝』『春秋穀梁伝』の三伝。公羊伝および穀梁伝は春秋経に沿って、魯の記録に合わせて注釈されている。だが左氏伝は、独自の記事を挟み込んでおり、とりわけ晋の記事が多く書かれている点で異質である。左氏伝は左丘明の著作だと伝えられている。だが左丘明は孔子と同時代あるいは孔子以前の時代の人と思われ、その左丘明が左伝で孔子死後のことまで記述している、となると年代的に合わない。左伝は漢代の古文学者によって春秋経の注釈として広められた。だが、実際にはもとから春秋経の注釈だったと決めてかかることはできない。左伝は晋との関係の記述が多く、おそらく戦国時代に三晋(晋の後継国家)、とりわけ魏あるいは韓で編纂された書である可能性が高い。その本来春秋経とは無関係な歴史書を、後世の古文学派が春秋経の注釈書として当てはめたと見ることもできる。だから、左伝は戦国時代の三晋の暦で編纂されている可能性もあり、ゆえに当時広まっていた夏正が採用されている可能性がある。
成田君のリードで為政篇音読、訓読と意味を小田さん。
子の曰はく、其の鬼に非ずして之を祭るは諂ひなり。義を見て為(せ)ざるは勇無きなり。
其の鬼に非ずは、其の當に祭るべき所の鬼に非ざるを謂ふ。諂ふは求めて媚るなり。
知りて為ざるは、是れ勇無きなり。
孔子が言われた、「自分の先祖の霊でないのに、これを祭るのは諂いである。義を見ながら行わないのは、勇がないことである」と。
「其の鬼に非ず」というのは、自分が祭るべき霊でないことを言う。「諂」は媚びることである。知っていて為さないのは、勇のないことである。
小田:この章は、前半と後半で内容が違いすぎるように見えます。なぜこの二つが繋がるのか?二つの章であってよいと思うのですが。
成田:もし、間に「子曰」があれば、二章となるでしょうが。
小田:それがないから、一つにしていると。
成田:しかし、これでも読者は違和感を持たなかったからこそ、古来繋げて一章として読まれてきたのです。
小田:しかし、今読んでみると、やはり違和感があります。前半と後半がどこで繋がっているのか?
成田:前半を、不義を見てするのは諂うこと、と逆にすれば、諂うは勇の逆であると言えます。
小田:「鬼」と「義」で語呂合わせをして並べた、ということではないようですね。音が違う。
成田:guiとyiですから、それはなりません。
上田:次の八佾篇とつながり、季氏が八佾の舞をしたことや泰山の旅することを、義ではないとして、冉求にやめさせようとしたが、しなかったことを勇なきとした。ただ、魯公が八佾を行う樂人をかかえておらず、人々も実権をにぎっていた季氏が行うことを善しとしていおり、冉求が諌めてやまるものではなかった。「義をみてしないのは勇がない」といわれても実行は難しい。
成田:季氏の祭りが間違っていると分かっているのに、止めさせられない。
上田:斉でも家臣が実権を握る時代であり、孔子のいうことは実現される見込みはなく、勇なきといわれてもどうしようもなかった。言われた冉求も困り果てた。
成田:きついことを言うのが孔子の仕事。
小田:皇帝ナポレオンに、ローマ教皇に従いなさいというようなものですかね。ナポレオンは皇帝として、ローマ教皇から戴冠を受けるというカール大帝以来の儀式を行ったわけで、形式的にはローマ教皇の臣下だったりしました。当時、もちろんそんなことは誰も問題にしていませんでしたが。
上田:この言葉は、孔子が魯に帰ってから、晩年のものでしょう。
成田:為政篇までは、どれも魯に帰ってからのものと読める。
小田:魯公に力が無くなっており、力ある季氏が八佾を行ったということですか。
成田:この条を八佾とつなげるのはいいが、八佾は祭祀と直接関係は無い。季氏の不遜を言うが、魯の殿様に為り代わってやっているとまでは言っていない。季氏の不遜に限定することもない。有力者に取入るために、有力者の祖先を祭ることがあったのかもしれない。季氏に諂うということも考えられる。有力者に諂うのであれば、魯の殿様より実権を持つ季氏に諂った方が実入りもよい。
小田:しかし季氏とて、一族以外のものが祖先の祭儀に参加したりしたら、怒るのではないですか。
成田:貢物、お供えを持ってくるとか、位牌を別に作って勝手に祭るとか・・・
小田:季氏に諂うために、季氏の祭りに付け届けをするということですか。それは、季氏に媚びるということですね。
成田:季氏側も大きなホールをしつらえて、来るなら来い、ということかもしれない。
小田:他家なのに季氏の祖先を称え、それに諂うなら、この章は一般的なものとなるでしょう。本来は家で厳粛にやるべきものを政治的に利用し、そこに他人が便乗することを許す。それはけしからん、と。
上田:鄭玄は、「人神を鬼と曰ふ。其の祖考(祖先)に非ずしてこれを祭るは、是れ諂ひて福を求む」としており、お二人の話のごとく、諂って福をもらうとみているのでしょう。
成田:おこぼれを頂戴しようとする。
小田:季氏が八佾をするとき、誰を祭っているのでしょうか?文王まで遡るのでしょうか?
成田:文王ではない。季孫氏は、季孫氏の開祖でしょう。
上田:桓公の子、荘公の三人の弟(慶父、叔牙、季友)が孟孫氏、叔孫氏、季孫氏のはじめであり、元々は王族、季氏の家来の陽貨とは異なる。
小田:つまり、分家のはじまりを祭っていたと。魯公の祖は周公だから、魯公は周公ですか。以前に台湾の孔子廟を尋ねましたが、そこでは毎年孔子を祀る「釋奠礼」を行います。その儀式での舞踊は、たしか六佾でした。
成田:六佾は諸侯のもの。八佾は「霊廟の祭り」としてますから、魯公であれば周公以来の魯公、周公にはじまるから魯は(諸侯であるが)八佾となる、季氏の場合は季氏の祖先を祭る(大夫は四佾)。
小田:それなら季氏が八佾をするのは、非常に僭越です。しかしなぜ季氏が八佾を行ったのでしょうか?
成田:豪勢だったのでしょう。身近に八佾が行われていたからやった。
小田:季氏が季氏の祖先を祭っているなら、それは諂うことにはならない。魯の君主になるという野心でもありましたか?
成田:季氏が魯公にとってかわるという批判は、なされていません。そういう野心ではないでしょう。そもそもは身内です。
小田:徳川御三家が将軍家にとってかわる、というようなものではなかったと。
成田:それを考える必要はないでしょう。
上田:貝塚先生は当時魯公は八佾を行うに足る樂人と舞人をかかえておらず、季氏にはその財力があったとしておられる。また、魯では昭公が斉に亡命してから、空位の時代がつづいており、その時政治の実権を持っていた季氏が、八佾を執り行うというような事情があったのではないですか。その季氏も陽貨に牛耳られており、政治がガタガタしていた。
小田:季氏が主家を僭越する風潮を作ったから、陽貨はそれを見て下克上の時代が始まった、力があるものが権力を握ってよいのだ、と思ったのでしょう。
成田:若い頃の孔子は、それに乗ったわけです。彼も下克上だった。しかしうまくいかず、晩年にはやっぱり秩序を守ることが正しいのだ、と思い直すようになりました。
為政篇は終了。
2012年5月26日(土)八佾篇
本日も、成田君、小田さん、上田さんの三田人。成田君のリードで八佾篇音読。訓読と意味を小田さん。
孔子季氏を謂(のたま)はく、八佾庭に舞はす、是をも忍ぶ可くんば、孰れをか忍ぶ可からざらんや。
佾の音は逸。○季氏は魯の大夫、季孫氏なり。佾は舞の列なり。天子は八、諸侯は六、大夫は四、士は二、佾毎に人數は、其の佾の數の如し。或ひと曰く、佾毎に八人、未だ孰れが是か詳らかならず。季氏大夫を以て僭して天子の禮樂を用ふ。孔子言ふこころは、其れ此の事尚之を爲るを忍べば、則ち何れ事を忍ぶ可からざらんとす。或ひと曰く、忍は容忍なり。蓋し深く之を疾(にく)むの辭。○范氏の曰く、樂舞の數、上よりして下り、降殺に兩を以てするのみ。故に兩の閒、毫髪を以て僭(せん)し差(たが)ふ可からざるなり。孔子政をして、先ず禮樂を正せば、則ち季氏の罪、誅に容れず。謝氏の曰く、君子其の當に爲すべからざる所に於けるを、敢へて須臾(しゅゆ)も處(を)るをせざるは、忍びざるが故なり。而して季氏此を忍ぶ。則ち父と君とを弑すと雖も、亦何ぞ憚る所せざるや。
孔子が季氏について言われた、「八佾を庭で舞わすと聞いた。これを許することができるなら、何を許さないことがあろう(いやない)」と。
佾(いつ)の音は逸(いつ)。○季氏は魯の大夫、季孫氏のこと。佾は舞の列のこと。天子は八、諸侯は六、大夫は四、士は二であり、佾ごとの人数は、その佾の数と同じである。ある人は、佾ごとの人数は八人(に固定)だと言っている。いまだどちらが正しいのか、はっきりしない。季氏は大夫でありながら僭越にも天子の礼楽を用いた。孔子が言わんとすることは、このことを許可するならば、一体世の中に何が許可できないことがあろうか、ということである。ある人が言うには、忍は容忍のことである。つまり、深くこれを疾(にく)むという言葉である。○范氏が言うに、楽舞の数は、上から下に順々に二つづつ減る。その二つの間は、ほんの少しも違っていることはできない。孔子は政治をするに、まず礼楽を正すことから始めた。ゆえに季氏の罪は誅殺に値する、と。謝氏が言うに、君子はそれをやってはいけない所においては、ほんの少しもその立場にいないのは、耐え難いからである。ところが季氏はこれを許した。つまり父と君とを弑すことについても、どうしてはばかってしないことがあろうか(いやするだろう)、と。
小田:「忍びず」の意味は、許せないではなく耐えられない、でしょうか。
成田:「忍びず」は耐えられないという意味です。謝氏は孔子は耐えられないが季氏は耐えられる。季氏は平気で耐えられから、何であってもやるだろう、と。朱子の注では、「忍ぶ」の主語は誰でしょうか。孔子か季氏か。私は孔子と思ってきたが、朱子はどうやら季氏が主語であると言っているようだ。古注は詳しく書いておらず、単に「孔子これを誹る」としているだけです。
小田:朱子の注は、孔子は礼の先生のような見方で、季氏が「忍ぶ」ことはいけない、と批評している、ということでしょうか。いっぽう成田さんの読み方では、孔子が「忍ぶ」ことができずに怒りを顕わにしている、主体的な孔子像と言うべきでしょうかね。
成田:別の人が注していて、「忍」には、「敢忍」と「容認」の二つがある、とあります。
小田:容認は許容することでしょう。敢忍は怒りをこらえること?
成田:いや、敢忍は悪いと思っていても敢えてやってしまうことです。
小田:つまり、あえて悪に手を染める、と?
成田:そこまで極端ではないでしょう。朱子は「或る人曰く、容認」としています。つまり、これは朱子の意見ではないということです。つまり朱子は本章の「忍」の字を敢忍と捉えているわけで、季氏がこんなことを平気でできるなら、何でもやってしまうだろう、と。この場合「忍」の主語は季氏です。一方ある人の説を取って「容認」と解せば、主語は孔子であって、孔子が季氏の行為を深く憎んだ、ということになるでしょう。
小田:だが当時、季孫氏が八佾をすることに人々はショックを受けていたのでしょうか?
成田:それはなかったのではないでしょうか。
小田:確かに昔はしきたりとしてこだわった時代もあったかもしれないが、今どきはもうこだわらなくなっていた。それを、礼楽とか意識して学んだ孔子がこだわって文句を言ったのでしょうか。
成田:孔子がそうすることで、季氏をより悪者に仕立てあげることになった。上田さんどうですか。
上田:忍ぶの主語は孔子と思いこんでいたので、頭が混乱して議論についてゆけなかった。季氏が八佾を行ったのは、前回も言ったのですが、昭公が亡命をして空位であった時に実権を有していた季氏が代わりに行ったのではないかと思う。貝塚先生はその後も魯公は少数の樂人舞人しか抱えられず、財力のある季氏が八佾を行うことができたとされ、それがその後も既成事実化したものと思う。この言葉は孔子が魯に帰ってからの晩年という気がする。
成田:この章が孔子が魯を出る前の言葉なのか、魯に帰ってからの言葉なのかで既成事実化の度合いが異なる。その度合いが高まっている魯に帰国してから後の方がうまく読めるのではないでしょうか。
小田:つまり、季氏が行うのがあたりまえのことになっていた時期の発言が、この章であると。
成田:季氏が八佾を行った時期ですが、清朝の程樹徳らはこれを季平子の昭公二十五年のことである、と考証しました。根拠は、この年の左伝の注に「季氏八佾を舞わしむ」とあり、また漢書劉向伝にあります。この説は清朝の管同あたりから始まりました。古注の馬融は、季平子の次の代である季桓子の時と見ています。(故昭二十五年《公羊傳》稱昭公謂子家駒曰:"吾何僭哉?"答曰:"朱幹玉戚以舞《大夏》、八佾以舞《大武》、此皆天子之禮也。"是昭公之時、僭用他廟也。雲"季桓子僭於家廟舞之、故孔子譏之"者)孔子の晩年ならばすでに季桓子の次の季康子の代ですが、それを採用した説はないようです。
小田:季桓子の時と見なすならば、このとき孔子は権力に就いていていたわけであり、礼のプロとしてこの言を政治的に言ったということになるでしょう。しかし季平子の時代であったならば、孔子はまだ駆け出しで何の権力もなく、単にはねっかえりの学者が文句を言ったことにすぎなくなって、重みがないですね。
上田:季平子は昭公の時、季桓子は定公の時、この時は陽貨に牛耳られ、魯公や季氏の祭祀はガタガタになったと思われる。季康子は哀公の時、冉求が季氏の宰となっており、孔子が魯に帰国してからんこと。
小田:季平子の乱の予兆があって、季平子が八佾を行うのは魯公にとってかわるという意思表示だったのでは?
成田:いやそういうことではなく、人数が揃う財力があればやってみよう、豪勢でいいじゃないか、くらいの軽い意図だったでしょう。
小田:金があれば、豪華な祭りでもできる時代になった。昔のみんな貧しい時代は、身分に応じた祭りをすることしかできなかったが、富を蓄える者が出てくる時代には、諸侯を超える財力を持つ者すら出てくる。富が礼楽を崩していく時代に、孔子はいたということでしょうか。
成田:礼楽は、序列を守り争いを少なくするところに効能があって、時代が変われば新しい時代に応じて礼楽も変えていけばよい。それが、季氏などの感覚でしょう。季氏が八佾を舞わせたのは、金と力のある季氏が豪華な儀式を行うほうが現実に即している、という考えがあったのでしょう。
小田:だから、何も魯君にとって代わるということではなかったと。
成田:それを孔子は、季氏に土地も含めて本家に還せと迫った。
小田:孔子は、いにしえの時代の状態に富の分布までも引き戻して、礼楽の秩序を守ろうとしたのですか。それでは誰も時代の人は従わないでしょうね。
三家の者、雍を以て徹す。子の曰はく、相(たす)くる維れ辟公。天子穆穆として、奚ぞ三家の堂に取らん。
徹は直列の反。相は去聲。○三家は、魯の大夫、孟孫・叔孫・季孫の家なり。雍は周頌の篇の名。徹は、祭畢はりて其の俎を收むなり。天子宗廟の祭は、則ち雍を歌ひて以て徹す。是の時三家僭すは、之を用ひ、相は助、辟公は諸侯なり。穆穆は深遠の意、天子の容なり。此れ雍詩の辭なり。孔子之を引きて、三家の堂、此の事有るに非らず、亦何ぞ此の義に取りて之を歌はんと言へり。其の無知妄作、以て僭竊(せんせつ)の罪を取るを譏る。○程子の曰く、周公の功、固より大なり。皆臣子の分當に爲すべき所。魯、安んぞ獨り天子の禮樂を用ふるを得んや。成王の賜ふ、伯禽の受る、皆非なり。其の因襲の弊、遂に季氏をして八佾を僭し、三家をして雍徹を僭せしむ。故に仲尼之を譏る。
三桓氏が、雍を歌って撤収した。先生が言われた、「『輔弼するのはこれ辟公(諸侯)/天子は奥ゆかしく遠くにおられる』と。どうして、これを三家の堂(ホール)で用いるのか?」と。
徹は直(ちょく)・列(れつ)の反切。相は去聲。○三家は、魯の大夫、孟孫・叔孫・季孫の家である。雍は周頌の篇の名である。徹は、祭を終えて供物を撤収することである。天子宗廟の祭は、雍を歌って撤収する。この時三家は、僭越してこの歌を用いた。相は助であり、辟公は諸侯のことである。穆穆とは深く遠いことであり、天子の姿である。これは、雍の詩の中の言葉である。孔子はこれを引用して、三家の堂(ホール)ではこれをやってはならない、果たしてこの意味を分かって歌っているのか、と言っているである。その無知と妄りな行い、竊(ひそ)かに僭越する罪をそしっているのである。○程子が言った、「周公の功は、もとより大きい。しかしそれは、すべて家臣であり子である分際でやった範囲のことであった。魯だけがどうして、天子の礼楽を用いることができるのか。成王が授け、伯禽が受けたことまで、すべておかしい。その因襲の弊があったから、ついに季氏が八佾を僭し、三家が雍徹を僭したのだ。だから孔子がそしったのだ」と。
成田:「相(たす)くる維れ辟公。天子穆穆として、奚ぞ三家の堂に取らん」と、後藤点は「として」と読ませているがこれはおかしい。
小田:天子穆穆たり、と終わるべきでしょうね。
上田:雍の詩はそこで終わっている。
小田:程子は昔のしきたりまで批判していますね。
成田:しかし、文王や周公は批判せず、成王や伯禽が悪いとする。
小田:三家がこの儀式を行っていた、ということは、すでにそれが魯の文化となっていたのでしょう。魯人としては、それを自慢していたことでしょう。魯は天子からの伝統を伝えている特別な国だ、だから我々三家も誇らしく文化を継承しよう、とか。しかし孔子はそれをいけないと言った。
成田:仮に魯の本家の殿様が雍を撤すれば、孔子はどう言うでしょう。天子じゃないのに止めておけとするのか、特別許されたのであるからいいとするのか。
小田:程子風に言えば、孔子は魯公から批判すべきなのでしょう。
成田:最初に例外を認めてしまったから、後々こんな乱れが出てしまった、と考えるのが程子です。
小田:三家の人は、おそらく詩の意味なんか考えていなかったでしょう。ただの伝統的な儀式の歌、程度の認識だったでしょう。しかし孔子は物知りで、礼楽を意識して学んでいたから、詩の意味を取り上げてその本義を指摘し、軽々しく用いるべきでない儀式なのだ、と苦言を呈する。この言葉は、いつの頃になりますか?
成田:さきの八佾は、古注では季桓子です。
小田:清朝の学者は、季平子という考証でしたね。
成田:だがこの章の雍徹のことは、いつの頃かは分かりません。
上田:雍の詩の朱子注によれば、武王が文王を祭り、諸侯が武王の所の来て祭事を助け、武王の姿が穆穆としていることをいうようである。孔子がどう思っているか分からないが、魯公が周公を祭って、諸侯が来るわけでなし、雍の趣旨からははずれることを程子が言っている。三家も雍の詩の意味が分からない訳はないと思う。ただ、儀式化して深く考えるようなものではなかったのではないか。
小田:たとえば日本で「君が代」を歌っているとき、歌詞の意味なんて意識しません。そこにやって来て、君らは歌詞の意味が分かっているのか、天皇陛下の世が千代に八千代に、さざれ石が岩となりて、苔が蒸すまで続くことを祈る歌なのだぞ、などと割り込み、お前は歌詞の意味のとおりに天皇陛下に祈りながら歌っているのか!ちゃんと祈って歌え!などと言ったら、どうでしょうね。孔子は、そのようなことを言っているように見えたかもしれない。昔からの儀式だからそれでいいではないですかとする者に、ちゃんと意味があるのだから意味を汲み取れ、と言った。しきたりの意味を改めて問うという斬新さは、あったのかもしれない。ただ、歌なんて楽しめばいいのに、いちいち理屈付けて野暮なことを言う嫌味なオッサンだなあ、と顔をしかめられて当然でしょう。
成田:この条については、何時のことか、議論されてはきていない。そういう意味では手掛かりがない。前後を続けて読んで判断すべきであろう。編集の意図があるのかもしれない。
小田:八佾をやり始めたのは季平子で、孔子が批判したのは季桓子の頃という説が主流でした。これが季康子となれば、いまだにやりつづけていたので孔子が文句を言ったというべきでしょう。
ここからは脱線気味。
朱子学では孔子が誹るとするのであるが、どうも、儀式が形骸化をしており、季氏が財力の無い魯公の代わって儀式を豪華に行っていることにあまり違和感がなくなっている社会変化があり、それは小田さんが君が代に喩えたごとく、サッカーやボクシングの試合でも、慣行として歌われるもので、その意味をよく分かって歌い、また、聞きなさいと説いても、馬耳東風、野暮なことをいう人だとおもわれるがごときものである。徳川家康に仕えたブレーンたちは、きっと論語とか礼記とかをよく読んでいたに違いない。江戸時代は格式の時代で、上下の身分関係を細かく礼儀によって規定する制度だった。諸侯には家格があって、江戸城に詰める伺候席(しこうせき)が家格によって厳格に差別されていた。礼儀によって諸侯をコントロールする制度は、儒学の言う周の制度からヒントを得たのではないだろうか。
日本人は儒学の文化が血肉にまで入っていないが、朝鮮では文化の根幹まで儒学が入っていて、朱子学の解釈が文化の隅々に行き渡っている。なので、朱子学を日本人のように距離を置いて批評することが難しい。日本の面白いところは、江戸期になって初めて真剣に朱子学を受容してから、たった100年で仁斎・徂徠のような朱子学批判が現れてしまったところにある。朝鮮では朱子学を磨き上げて精緻化したが、その後の発展がなかった。朝鮮通信使が来日したとき、日本人は清朝の考証学なども読んでいて、その批判的研究成果を通信使にぶつけたりした。朝鮮にとって清朝は夷狄に乗っ取られた国であり、儒学の正統を保持する小中華を誇る国としては、そんな国の研究など汚らわしくて相手にもしない。それで、日本側と朝鮮側で喧嘩になったりもした。両者の違いは、儒学を文化として血肉に入れたか否かの違いであろう。
江戸期の雨森芳洲は対馬藩に仕えた儒者で、対馬藩は釜山に広大な倭館を持っていて、対朝鮮外交の窓口を受け持っていた。雨森芳洲もまた倭館にいて朝鮮語を学び、朝鮮の官民と長く交渉していた。その彼は、日本と朝鮮との文化がずいぶん違うことを指摘して、相互の違いをよく認識して外交(雨森芳洲は「交隣」という言葉を使った)することが相互に誤解を生まないために必要だ、と対馬藩主に説いた。朝鮮では、葬式で儒礼に基づいて大泣きする。雨森芳洲は、朝鮮人は日本人もきっと感激しているだろうと思い込んでいるが、日本人は変な奴らだと笑っている。そのような文化の違いが両国にある、と指摘している。(小田が)韓国に住んで妻が韓国人である日本人に聞いたのであるが、彼は韓国で妻の親族の葬儀に参列して、大泣きする人々に会った。それを初めて見たとき彼は、親族の死に対してここまで悲しむ、なんと情の厚い人々であるか、といったんは感激してしまった。ところがそのすぐ後に、親族の人たちはケロッとして酒盛りをして大笑いしていた。日本人の彼はそれを目撃して、いったいさっきの悲しみはどこに行ったのだ、と今度は首をかしげてしまったという。日本人の葬式には、儒礼が入っていない。朝鮮は、儒礼に完全に基づいて行うから、儀式として大泣きするのだ。それを見て日本人が不審に思うことこそが、日本人が儒学を文化として血肉に入れていない一例である。(他には長幼の序がおそろしく厳格なこと、祖先の祭儀が最も重大な行事であること、祖先を同じくする同姓の者は何十世代前に分かれていても親族扱いすることなど、韓国朝鮮の文化は儒礼に基づいている。)
2012年6月2日(土)泉屋博古館、黒谷、八佾篇
午後から泉屋博古館(HP)を見学。川那辺さん、成田君、小田さん、北澤さん、上田さん。黒谷より早川君合流。
狙いは殷代の青銅器。ボランティアの解説員に熱が入るほど聞き手も質問を発す。殷代の青銅器に込められた思いと技術には圧倒される。酒器であっという間に一時間、書の解説がありますとのことで、中断して、書展に急ぐ。この解説も一時間、解説員がおられ、成田君の解説が聞けないのは残念なことでした。立ち疲れてロビーの習字コーナーで一服。八大山人の、安晩帖を手本に水墨で書く。成田君、川那辺さんは達筆。成田君が篆書で「有顔回者好学不幸短命死矣」を書くを消えないうちにと川那辺さんが撮影。
青銅器に戻り、西周時代、春秋戦国時代、漢・唐時代まで観ると、足腰ぐったり。天気予報では雨が懸念されていたが、雨は降らず。岡崎神社の横道から黒谷の金戒光明寺(HP)に向かい、そこで早川君と合流。HPにある熊谷直実が鎧を掛けた松の二世は立派でした。会津藩の墓所を探して歩く。犬が歩けば棒に当る。早川歩けば碑に当る。研究に関連する内容が記されているそうです。道中毀れた墓石、ひっくり返った墓石、積み上げられた墓石、放置された大きな墓は始末に困る。大きな墓は、後世の大きな迷惑。
早川君、成田君の執念の成果
小田さんは、海保青陵(徂徠学派の学者で経世家、宝暦五年-文化十四年)の墓を見かけ、早川君が池玉蘭(池大雅[享保
八年-安永五年]の妻で、夫と同じく画家)、竹内栖鳳(日本画家、元治元年-昭和十七年)の墓所があるという碑を見かけた、と新たな収穫があったようです。見つからないのが山崎闇斎先生の墓所。早川君が東十歩の碑を見つけるが十歩内に該当するものがない。東数十歩の所に成田君が発見。ところが奥さんや娘さんの墓石は分かるが先生の墓石がわからない。一番奥の真ん中の一番小さな墓石が先生の墓石なら、なんと奥ゆかしい先生かと噂するに、早川君が成田君に闇斎先生の名をネットで検索を依頼。名は嘉、
字は敬義、通称嘉右衛門。何と入口の一番立派な墓石が先生のもの。灯篭まであり、やっぱりねと川那辺さん。手を合わせてお参りをせんとすると、垂加神道ですからと早川君、柏手に変えました。朱子学者で神道家。東大路まで歩いてバスで西陣小学校へ。冷えたビールで一息入れて読書会。小田さん、企画ありがとうございました。
成田君のリードで八佾篇音読。訓読と意味を早川君。
子の曰はく、人として仁ならずんば、禮を如何。人として仁ならずんば、樂を如何。
游氏の曰く、人として仁ならずんば、則ち人心亡ぶ。其れ禮樂を如何せんとや。言ふこころは、之を用いんと欲すと雖も、禮樂、之が用を爲さず。○程子の曰く、仁は天下の正理。正理失するは、則ち序無くして和せず。李氏の曰く、禮樂人を待ちて而して後行はる。苟も其の人に非ざれば、則ち玉帛交錯(こうさく)、鐘鼓鏗鏘(こうそう)と雖も、亦將(はた)之を如何せん。然れども記者此を八佾、雍徹の後に序するは、疑ふらくは其れ禮樂を僭する者の爲に發するならん。
孔子がおっしゃった、「その人となりに仁がなければ、礼があってもどうすることができよう。その人となりに仁がなければ、楽があってもどうすることができよう」と。
游氏が言った、「人として仁がなければ、人の心がなくなる。禮樂(れいがく)をどうすることができよう」と。その意味は、禮樂を用いようとしても、禮樂が役に立たないということである。○程子が言った、「仁は天下の正しき理である。正理が失われば、秩序が無くなり調和しなくなる」と。李氏が言うに、「禮樂は人があって行われる。かりそめにも、それに適した人でなければ、立派な玉帛を交錯しても、立派な鐘鼓を鏗鏘しても、どうすることもできない。しかしながらこの条を八佾、雍徹の後に位置づけたのは、疑うに禮樂を犯すものを啓発(または告発)するためにおいたのであろう」と。
小田:礼シリーズの三番目です。この章では、形式が完備していてもだめだ、というわけですか。
成田:最後の李氏のコメントは、この章は礼を身分を越えて用いることへの批判である、と位置づけています。
早川:つまり、これも季氏シリーズの章の一つだ、と読んでいる。
成田:要は、季氏は不仁であるということですか。
小田:前の二つの章では、季氏が礼の規則に外れていることを歎じていました。八佾や雍徹はおかしいと。
成田:八佾、雍徹は、季氏は技術的には礼に従っていたが運用が間違っている。順番からすると、この章は前の二章を受けて、礼を無茶苦茶にしているのはけしからん、仁ではない、という批判の意図を込めてここに置かれているのは確かなことですが、それは編集者がそう読ませようとしてここに配列したわけで、この言葉を孔子が季氏のようなことを批判する目的で発言していたのかは、ちょっと疑問です。季氏の礼違反を孔子は歎ずるわけですが、季氏に対してこの章のように、そういうことをする者は人として不仁である、とまで考えていたかどうかは微妙なところです。
早川:この最後の言葉には、薀蓄がある。
成田:どう「薀蓄」がありますか?
早川:最初の二章で、そんなことをするならばどんなことでもできる、という批判をしていました。この章は一方直接的な批判ではないが、相手への説き方に違いがあります。
成田:主語を季氏にすれば、非礼は不仁であり、下剋上の乗っ取りに繋がる、と読めます。
早川:この並べ方には、論語を編纂した人の意図が感じられる。礼楽に対する批判が並んでいます。
小田:論語の編纂者だから、とうぜん孔子の後の時代です。要は、戦国時代の編集者の意図ということになります。春秋時代ならば、まだ衰えたとはいえ周の天子の秩序を礼で取り戻す、という孔子の望みにはいくぶんかリアリティーがあったかもしれない。しかし、戦国時代になったら周王朝などどこかに飛んでしまって、守るべき礼の秩序もへったくれもなく、王たちが新たに秩序を作ることが正義となりました。そんな時代に、論語の編集者は何を言いたかったのでしょうか。礼楽を使うときに、どういう心を入れるべきと説きたかったのでしょうか。礼楽など、もはや時代遅れの秩序感を今さら孔子の言葉として強調して、どんな理想を描いていたのでしょうか。礼の僭越も身分に応じた礼楽も問題でなくなっていたはずの戦国時代になって、この章を編集した人々は礼楽にどんな利用価値を見出していたのでしょうか?
成田:仁を盛り込むのが、この章の大事なところ。孟子が仁を言ってどこまで浸透したかは不明。孟子の頃には、まだ仁より宮廷儀式としての礼楽の方が、必需品として受けが良かったことでしょう。だから、まず礼楽で君主に売り込む。それから、礼楽に通じた人には仁が必要だと隠していたことを言って、仁を売り込む。そして仁が欲しければまた礼の授業を受ける必要がある、ということになって、儒家の商売がうまく回っていきます。
小田:まず受けのよい礼楽から売りこんで、礼楽には中味が必要だ、と言って核心に迫る、という戦略ですか。
早川:八佾も、雍徹も、戦国時代の王には耳が痛かったでしょう。
成田:しかし王を名乗ったならば、八佾をやってもいい。
小田:梁恵王章句下の冒頭で、斉王と孟子が問答します。家臣が言うに、王は古の礼楽は好きでなく、最近の流行りがお好みだと言う。孟子はそれを聞いて、王に古の文化も今の文化も一緒であり、王がそれを楽しんで皆もまた楽しむならばいいのだ、と言いました。私はこの章が非常に好きなのですが、何も格調高いクラシックを聴かなければ君子じゃない、というのではないのだ、ヒット曲やディスコソングが好きでもかまわない。要は、偕(みな)と楽しむという仁の心が王にあれば、それでいいのだと孟子は言いました。孟子にとって、礼楽はしょせん宮廷儀式を売り込むという、商売道具にすぎませんでした。別に王が退屈な礼楽に感動してくれなくても、構わない。それよりも、大事なのは仁と説きました。孟子は、礼楽に本気で感動していなかったと、私なんかは思いますね。
早川:孔子には、何々という曲の作者である、などの伝説が豊富にあります。ところが、孟子にはぜんぜんありません。その辺もまた、両者の礼楽に対する打ち込み方の差が、伝説の差となったのでしょうかね。
上田:編纂者の意図は孔子が季氏の政治を批判をしていることになり、朱熹らもその点を強調しているが、成田君が孔子がその目的で発言をしたかは疑問というのは頷ける。前回もみたように、当時は季氏のやっていることが当たり前のごとくなっており、耳を傾けるものはあまり居なかった。
成田:為政者への批判というよりは、弟子に言った言葉でしょう。お前たちに単なる礼楽の技術を教えるのではなくて、その心を教えるのだ、という意図でこの章の言葉を弟子に言った、ということはありえると思います。この章は、だから世相批判というより、弟子に対する教えと読みたい。
小田:孔子の時代では、礼楽は宮廷に就職するための必須科目だったのでしょう。弁護氏になるために、法律学校で法律を学ぶのは必須です。その学校で先生が、法律の条文だけ知っていれば人としてよいのではないぞ、法の精神つまりリーガルマインドを養わなければいけないよ、と言ったりする。孔子の弟子への言葉を、そんな風に取りたいですね。そして、法律を学ぶ者は必ずしも皆が法の精神まで学ぶことはなく、むしろ技術あって精神のない専門家が多く生まれるのも、事実です。
上田:孔子は批判をするが、このことを言っても分かってもらえないと、歎いている感がある。前回、小田さんが「君が代」の意味が分かって歌っているのかと歎く人、というのと同じような状況でしょう。
成田:「人として仁ならずんば、禮を如何。人として仁ならずんば、樂を如何。」言葉としてははっきりとしており、歎くというものではなくスッキリした文章。感情的に「~かな」で締めたり、倒置法を使っているわけでもない。淡々としている。やはり、弟子に対する教訓でしょう。
早川:この章は口調が美しくて韻もふんでいます。礼や樂に直結しており、弟子によく考えろと諭したのでしょう。
小田:私が思いますに、孔子は日本で言えば戦前の人というべきではないでしょうか。それに対して戦国時代の孟子は戦後人。戦前に生きた人ならば、しだいに古きよきものが崩れ去っていくことを感じ、それを慈しんでなんとか時の流れを引きとめようと試みるのも分かります。孔子は守るべき古い秩序があることを肌で知っていた、いわば戦前人の世代なのであろうな、と私は論語を読んで感じたりします。いっぽう戦後になれば、古い文化や感覚などは吹き飛んでしまい、何の未練も感じようがない。そんな時代には、新しい世界を作ってやろうという意気込みが現れます。孟子は、もはや古い文化など壊れてしまった時代に生きて、新思想で天下を革命しようと意気込んだ戦後人ではないでしょうか。
さて、古注は、魯卿の季氏が禮樂の事を僭用したことを孔子が批判をしたとし、新注は、それは元来魯公が周公に許されたことをいいことに、天子の禮樂を行ったことに起因しており、聖人孔子はそのことまで視野にいれて批判するものとした。伝統的に批判者としての孔子像が定着している。しかしながら、季氏の祭事が常態化しており、孔子の言葉は当時の政権、おそらくは一般の人々にとっても、今更周公の政治に戻れというのは、現実離れしたものと映っていたものと思われる。政権担当者にも一般にも通じず、孔子は弟子にその思いを継承させるしかなかった。政治を通じてその思いを実現することができず、それでも通用する政治思想を求め、己自身を偽らずに生きる姿勢は、有教無類、地位も身分もなく、人として如何にあるべきかに迫るものとなった。「人として仁ならずんば、禮を如何。人として仁ならずんば、樂を如何。」は、逆境のなかにあって、それを貫こうとする孔子の姿を弟子が伝えようとしたものではなかったか。
2012年6月9日(土)八佾篇
本日、北澤さん、早川君、小田さん、成田君、上田さんの五人。
黒谷の墓には色々楽しいものがあったようです。帰りの階段の途中に、アフロ姿の仏像があり、川那辺さんが写真をとって興じておられたが、早川君によれば、滅多にみつからない仏像で、法蔵菩薩という。
(小田:衆生を救う菩薩への信仰は後から北インド地方で起こった大乗仏教の新教義で、日本や中国の仏教はこの大乗仏教の教義が伝わったものです。菩薩信仰は他力本願であり、解脱ではなくて救済を求める点で、釈迦本来の教義ではなかったはずです。仏教古来の姿を留めているタイなどの南伝仏教は、今でも個人の解脱が教義の中心にあります。タイの人々が老年期になったら僧院に入って解脱を求めるのは、その教義のためです。南伝仏教では、在家の衆生は出家者を経済的に支えるのが義務とされています。また大乗仏教でも禅宗は、仏教本来の解脱の教義を中国で取り戻そうとした宗派といえるもので、菩薩に救われるよりも自分が悟って自力で救われることを目指しました。)
小田さんによれば、衆生を救いたいというのもまた煩悩であり、成仏せず煩悩に留まるのが菩薩ということのようです。京都には地蔵盆があり、地蔵菩薩が安置されます。親より先に死んだ子は地獄に落とされるそうです。その子を救うために地獄へ赴いて守ってくださるという民間信仰によるとのこと、仏教は元来自らを救う、悟ることで、衆生を救うというのは、後付けのようです。
早川君のリードで八佾篇音読。本日最初の部分の訓読と意味を北澤さん。
林放禮の本を問ふ。子の曰はく、大なるかな問ふこと。禮は其の奢(おご)らんよりは寧ろ儉せよ。喪は其の易(をさ)めんよりは寧ろ戚(いた)めよ。
林放は魯の人。世の禮を爲す者、專ら繁文を事とするを見て、其の本、是に在らざるを疑ふ。故に以て問いを爲す。孔子、時(とき)方(まさ)に末を逐ふに、放(林放)、獨り本に志有るを以て、故に其の問ひを大とす。蓋し其の本を得れば、則ち禮の全體、其の中に在らざること無し。易は去聲。○易は治なり。孟子の曰く、其の田疇を易むと、喪禮に在りて、則ち節文習熟して、哀痛慘怛の實無き者なり。戚は、則ち哀を一にして、文足らざるのみ。禮は中を得るを貴ぶ。奢り易るは則ち文に過ぐ、儉し戚すは則ち及ばずして質なり。二つの者は皆未だ禮に合はず、然れども凡て物の理は、必ず先に質有り而して後に文有り、則ち質は乃ち禮の本なり。○范氏の曰く、夫れ祭は其の敬足らずして禮餘り有らんよりは、禮足らずして敬餘り有るに若かず。喪は其の哀足らずして禮餘り有らんよりは、禮足らずして哀餘り有るに若かず。禮これを奢に失し、喪これを易に失するは、皆本に反(かえ)ること能はずして、其の末に隨ふ故なり。禮奢りて備はるは、儉にして備はざるの愈(まさ)るに若かず。喪易めて文なるは、戚みて文ならざるの愈るに若かず。儉は物の質、戚は心の誠。故に禮の本爲り。楊氏の曰く、禮は諸(これ)飮食より始まる。故に汙尊(うそん)して抔飮(ほういん)し、之に簠簋(ほき)・籩豆(へんとう)・罍爵(らいしゃく)の飾を爲るは、之を文(かざ)る所以なり。則ち其の本は儉のみ。喪は以て情を徑して直に行ふべからず。之が為に衰麻(さいま)・哭踊(こくよう)の數(すう)をするは、之を節する所以なり。則ち其の本は戚のみ。周衰へて、世方に文を以て質を滅す。而して林放獨り能く禮の本を問ふ。故に夫子之を大なるとして、之に告ぐるに此に以てす。
林放が、禮の基本を質問した。先生がおっしゃった、「大いなる質問だな。禮は豪勢なものより、つつましやかにせよ。喪は儀式をきちっとするより、悼む気持ちを大切にせよ」と。
本文より解説の方がむつかしい。同じことを難しく繰り返しているのであるが、皆さんの助け舟もあって、訳がすすみました。
林放は魯の人。世間で禮をなす者が枝葉末節にこだわるのをみて、その基本はそこにはないのではないかと疑って質問した。孔子は、その当時が末節を追っているのに、林放がひとり基本に志したので、よい質問であるとした。つまり、その基本を習得すれば、禮の全体がその中にないことはない、二重否定で必ずある、とした。易は去聲で、「易」は治めることである。孟子が(尽心篇上で)「其の田疇を易む(田畑の畔を整える)」と言っている(易=治の例として引用されている)。「易」とは、葬式の禮に関して節文(葬儀の細かな次第)を習熟しているが、哀痛慘怛(悲しみ悼む)気持ちが無い者のことである。「戚」とは、哀悼をもっぱらにして、文(節文)が足りないことである。禮は中(奢・易と儉・戚の中間)を貴いとする。奢や易は文に過ぎ、儉や戚は及ばずして質であり、両方とも禮には合致していない。しかし、すべて物の理は、必ず先に質があって後に文がある。質はだから禮の基本である。○范氏が言うに、(祖先の)祭は敬が足らず禮に余りあることは、禮が足らず敬に余りあることに劣る。喪は哀が足らず禮に余りあることは、禮が足らず哀にあ余りあることに劣る。禮が奢に失し(派手にする)、喪が易に失す(形式ばる)ことは、すべて基本に返ることができず末節にとらわれるからである。禮が派手に準備できているのは、つつましやかで準備できていないが勝っていることに劣る。喪がよく整って文(飾る)あるのは、悼んで文でないことが勝っていることに劣る。つつましさは物の質で、悼むは心の誠である。だから禮の基本となる。楊氏が言うに、禮は飲食より始まる。だから汙尊(うそん)して抔飮(ほういん)する。(禮記、禮運の言葉で、太古まだ器がないから、窪みを掘って水を溜め、手ですくって飲むこと)。簠簋(ほき)・籩豆(へんとう)・罍爵(らいしゃく)の器を使うようになり、これを飾るることになった。[先週泉屋博古館の見学が早速役に立った。殷の青銅器では、簠簋は穀物を盛って供える器、豆は食物を盛る高杯(籩も同様)、酒を供える器が尊、酒を溜めておくのが罍、持ち運ぶ器が卣(ゆう)、酒を温める器が爵、酒を飲む器が觚(こ)と言った。爵を飲む器と考えるのは、誤解ということである。]つまり、その基本はつつましやかなものであった。喪は直情径行、感情のままに行ってはならない。ゆえに衰麻(さいま、喪服を定め)・哭踊(こくよう、泣き、立ち居振る舞い)の數(すう、秩序だったやり方)を定め、これを分節するようにした。その基本は、戚である。周が衰え、世の中がまさに文により質が滅びていった。だが林放がひとりよく禮の基本を質問した。だから、先生は、これをよいこととして、林放にこう告げたのだ。
長い説明ですね。
小田:殷の青銅器の素晴らしさを先週観ましたが、(周の青銅器よりはるかに殷が精巧であり)、殷の方が文が盛んであったことになりませんか。
成田:周が礼の本質を重視した、と孔子なら言うかもしれません。朱熹の注は、文質については詳しいが、林放についてはえらく簡単なものです。
北澤:林放は孔子の弟子だったのですか。
成田:孔子には三千人の弟子があるとされますが、レギュラーの弟子とたまにしか出てこない弟子、そのまた弟子というのがありますから、ピンキリがある。林放はレギュラーの弟子ではないようです。
小田:史記の仲尼弟子列伝には、林放は入っていないのでしょうかね。(後注:入っていない。)司馬遷は、孔子旧宅から出土した古文資料に基づいて、裏づけの取れた弟子について取り上げた、と言っていますが。
成田:朱熹は魯の人とするだけで、弟子と見ているようではないようだ。
早川:闕里文献考(清・孔継汾)には、林放は字(あざな)を、子丘と記している。漢書には、林放の名があります。
成田:漢書は人物を9ランクに分けて記している。林放は、5ランクで中の中。
早川:漢書のランキングでは昔の時代には堯舜とか周公とか上の上にランクされている人が多いですが、孔子の時代になると上の上は孔子だけになります。下の下は、桀とか紂です。
北澤:林放は、ここと次の次くらいのものですか。
成田:そうです。
上田:この条が、林放が時流に流されず礼の本を聞いたことを孔子がほめたとするが、朱熹がうがちすぎではないか。大哉は、なんと大仰なという印象が強い。林放がいきなり礼の本を聞く、なんと物のわからない男かとあきれたのではないか。
成田:そうですね、林放ひとり本に志す、林放のみ真剣とまで朱熹がいうのは、おかしい。
上田:「泰山が林放に如かず」の解釈にもかかわる。泰山があの立派な林放に如かずなど、ややこしいことになる。あの横着な林放にも劣るとでもいうのか、という方がピンとくる。
成田:大哉は、えらいことを聞く奴だ、というニュアンスでしょうか。朱熹が言うような林放を高く買っての言葉ではないでしょう。林放の他にも弟子が居る状況があり、なかなかよいことを聞く。他の弟子にも、礼はこうだと言うきっかけになった。衛霊公篇に、「君子は言を以て人を舉げず、人を以て言を廢てず。」とあります。孔子は、言だけで林放を高く評価することもないし、林放が言ったことだからつまらないと捨てるわけでもない。
小田:つまり、この対話は1対1の対話ではなくて弟子たちが臨席する講義の場で、林放がこの質問をした。それを孔子は取り上げて、その質問はとても良い。だから、力を入れて答えよう。そんな問答だったかもしれませんね。
成田:孔子がこう言う前に、弟子が林放の質問にくすっと笑ったかもしれない。それで孔子が、いやなかなかいい質問ではないかとしたかもしれない。
北澤:この発言は何時の頃のことですか。
成田:放浪から帰ってから、となんとなく思える。この篇の最初の三つは放浪から帰ってからのことと読めないものはなかった。
早川:論語で大哉の例は、子罕篇2に、「達巷黨の人曰く、大なる哉、孔子。博く學びて名を成す所無し。子、これを聞きて門弟子に謂ひて曰はく、吾、何を執らむ、御を執らむか、射を執らむか、吾、御を執らむ。」とあり、この大哉は皮肉が込められている。泰伯篇19の、「大なるかな堯の君と爲るなり。巍巍乎として唯だ天大と爲す。唯だ堯これに則る。蕩蕩乎として民能く名づくる無し。巍巍乎として其の成功有るなり。煥乎として其の文章有り」の大哉は、非常に良い意味。
小田:次の次の章で林放について言及されますが、その章は冉有が季氏の下にいた時代の問答なので、この章もまた晩年のものと見たほうが、自然でしょう。
成田:林放が相当に古株の弟子でもなければ、その通りでしょう。
上田:林放が礼の本を質問し、答えは、礼は驕るよりつつましく、喪はきっちりしているより悼む気持ちというのは、林放ならこの程度からマスターしてくれねばという感じにとれる。答えのレベルは低い。
早川:確かに落差は激しい。
成田:林放が根本を尋ねるというほどのものでなく、孔子が林放を低く見ているというものでもない。孔子は、質問に本気で答えている。礼という大きな枠の中では、やり過ぎるより控え目がよい。その具体例として葬式では、きちきちするより、心情が素朴に出ている方がよい。葬式の例は、林放に分かる程度のもの。しかし、それは礼の大きな枠組みでも通用している。その他の弟子への教育的効果も狙っての言葉でしょうか。
小田:この章は、「大なるかな問い」の言葉はなくても、対話は成り立ちます。これは、孔子があえて力を入れたのでしょう。力を入れた相手は、周りの弟子に向けてだったでしょうか。ここは大事なところだよ、ということを弟子たちに伝えるために、「大なるかな、問い」と言った。
成田:弟子たちは、一斉にノートをとろうとする。
小田:弟子にかねがね言おうとしていたことを、いま林放が質問してくれた。それで、弟子の皆に言い聞かせる。そんな情景が浮かびます。
成田:当時、林放以外に、こういう質問をする人がいなかったのかもしれません。弟子たちは、礼のこまごまとしたことを聞く者や、子貢のごとくひねって聞く者はいた。しかし孔子に面とむかって「礼の本は」と聞く者はなかったのでしょう。だが孔子はそういう質問を待っていた。
北澤:弟子が「仁とは何か」という基本を問うようなことは、他にもある。ところが礼は日常のありふれたことであり、基本的な問いはしなかったのでしょうか。
成田:礼の学習は、作法の実習の時間です。その時間に生徒が、「先生、こんな実習をして何の意味があるんですか?」と身も蓋もない質問をするみたいな感じで、林放が礼の基本は何ですか?と聞いたのかもしれません。
次は小田さんよろしく。
子の曰はく、夷狄の君有るは、諸夏の亡きが如くならず。
呉氏の曰く、亡は古の無の字、通用す。程子の曰く、夷狄、且つ君長有り。諸夏の僭亂し、反りて上下の分無きが如くならず。○尹氏の曰く、孔子、時の亂るを傷みて之を歎ず。亡は、實に亡きに非ず。之れ有りと雖も、其の道を盡くすこと能はざるのみ。
先生がおっしゃった、「夷狄ですら君主がいる。それは、中華が君主がいない状態と違っている」と。
呉氏が言うに、「亡は古の無の字に通用する」と。程子が言うに、「夷狄ですら君長がいる。中華王朝が下剋上となって家臣が権力をもち僭越して乱れ、上下の分が無くなっているような状態でない」と。○尹氏が言うに、「孔子は時代の乱れを悲しんで、これを歎じたのである。亡といっても、実際に君主がいないことではない。君主はいるけれども、君主としての道を尽くすことができないだけである」と。
小田:新注は「如かず」ではなく、「如くならず」と読んでいます。驚いた。
成田:そこをどう読むかが大問題です。「如かず」なら、夷狄に君主がいても、君主のいない中華王朝には及ばない、という意味だが、「如くならず」では中華はこんなことではもうだめだ、ということになります。
小田:「如くならず」という読み方は、いつぐらいから出てきましたか?
成田:普通は「如くならず」と読みます。
早川:古注の皇侃の時から、「如くならず」です。
小田:「如かず」は?
成田:ちょっと分からないですが、文法的には「如かず」と読んだほうが正しいはずです。それがここだけ「如くならず」と読み慣わされているのが、謎です。
小田:しかし朱子などは華夷の区別を最も主張した人です。そんな朱子が、どうして「如かず」と読まなかったのでしょうか?
早川:程子の北宋の時には、もう遼とかに圧迫されていました。南宋の朱子の時は金にもっと圧迫されていました。こんな状況では、両者ともに「如かず」などと自己満足して悠長に構えていられなかったのかもしれませんね。
成田:朱子学者としては、中華に君主がいないという想定は、考えてもいけない。だから、中華に君がない状態などは、想定外だった。それで、君主はいるけれど乱れて君主がいないかのような状態に中華がなっている、と解釈したのでしょうか。
北澤:「如かず」と「如くならず」では、どう違いますか。
成田:如かずは、夷狄に王がいても、中華に王がいなくても、中華がよいという意味になります。
早川:如くならず、ならば夷狄の方が上だ、という評価になります。
成田:如くならず、では比較の意味がなくなります。
小田:まあたとえば、モンゴルにはチンギスハンがいて皆がひれ伏している。いっぽう中国にはまともな君主がいない。その状態を考えたとき、「如かず」ならば中華を評価するのです。チンギスハンがいくら名君であろうが、中華の君主がいくら暗君であろうが、中華の文化は野蛮人のモンゴルよりも圧倒してすばらしい。だから、中華の勝ちである。このように、負け惜しみの言葉になります。しかし「如くならず」ならば、野蛮なモンゴルですらチンギスハンがいてよく統治されているが、この中華はまともな君主がいなくて無茶苦茶である、という嘆き節になります。
北澤:孔子はどっちの意味で言ってますか。論語の他の部分の不如はどっちですか。
成田:「如かず」、後に来る方(諸夏)がよいとするのが普通です。ここだけ、「如くならず」というへんてこな読み方が通っています。
上田:朱子の置かれている政治情勢では、王が居なくても中華がいいといえるような呑気なものではなかった。
早川:孔子の頃は乱れているが夷狄に支配されるという状態ではなく、「如かず」と言えたでしょう。
小田:戦国時代の孟子は、はっきり中華文化が夷狄よりも優越している、という考えをしています。彼の立場は、明快に「如かず」のはずです。
成田:清朝考証学者は古い時代に遡って考証するが、この章に関してのみは国の事情があって泣く泣く「如くならず」にしたのでしょうね。満州の王朝の下で、夷狄の王は王がない中華に如かず、などと言えば、どえらいことになりますから。
早川:王船山(明末学者)は、この章を空白にしています。
成田:本人は明人と思っており、清なぞ認めなかった。
小田:それで、清代では朱子が「如くならず」と読んでくれているのをいいことに、昔の朱子の説のままでごまかしたということですか。過去の説を引用しているだけで、私にはこれを書いた責任はありません、と言って逃げた。
早川:もし朱子がこう解釈せず「如かず」と解釈していたならば、清代では発禁ものだったでしょう。北宋の頃、日本の坊さんが皇帝に目通りして、日本には天皇があり、代々続いていると言うと、皇帝は我が国は及ばないと言ったそうです。
小田:徂徠は「如かず」と読んでいますね。「君有りといえども礼儀なくんば、是れ其の禽獣を去ること遠からず」と言っています。
早川:天皇家は夷狄の王となりますが。
成田:徂徠は中国をよしとする人ですから。
小田:徂徠は、「程子の解、『不如』の詁を失す。従うべからず」と言って、程子の解釈を斥けています。
早川:中国人にとってはどっちにしても「不如」であり、あまり気にせず読んでいるでしょう。だが翻訳するときには、どちらで読むべきかかが問題となります。一説には、漢文は中国人、韓国人、日本人、アメリカ人の順で、後者になるほど精密に読んでいるということです。中国人は漢文のままに読んで、意味を詮索しない。韓国人は、ある程度訓点を付けて読むので、中国人より精密である。日本人は、訓点と共に読み方まで詮索するので、韓国人よりもさらに精密である。アメリカ人は、漢字をすべて翻訳しなければならないから、単語の意味まで精密に読みます。
小田:ウエイリーは、どちらで読んでいますかね?
時間となりました。
2012年6月16日(土)八佾篇
本日、早川君、小田さん、成田君、上田さんの四人。早川君のリードで八佾篇を音読。途中から成田君合流。訓読と意味を小田さんお願いします。
季氏泰山に旅す。子、冉有に謂ひて曰はく、女(なんぢ)救ふこと能はざるか。對へて曰く、能はず。子の曰はく、嗚呼、曾(かつ)て泰山、林放に如かずと謂(おも)へんか。
女の音は汝。與は平聲。○旅は祭の名。泰山は山の名、魯の地に在り。禮に、諸侯封内の山川を祭る。季氏之を祭るは僭なり。冉有は孔子の弟子、名は求。時に季氏の宰爲り。救ふは、其の僭竊(せんせつ)の罪に陷るを救ふを謂ふ。嗚呼は歎の辭。言ふこころは、神は非禮を亨(よろこ)ばず。季氏其の益無きを知りて自ら止めんことを欲し、又林放を進め、以て冉有を厲(はげま)す。○范氏の曰く、冉有季氏に從ふ。夫子豈に其の告ぐ可からざるを知らざらんや。然して聖人輕んじて人を絶たず、己の心を盡くす。安んぞ冉有の救ふこと能はず、季氏の諫むべからざることを知らんや。既に正すこと能はざれば、則ち林放を美(よみ)し、以て泰山の誣(し)いるべからざることを明らかにせり。是も亦敎誨の道なり。
季氏が泰山で「旅」の祭りをしようとした。先生は、冉有に質問された、「お前は季氏を非礼から防ぐことができないのか」と。冉有が答えた、「できません」と。先生がおっしゃった、「ああ、それならば、泰山は林放にも劣るとでも思うのか」と。(後藤点は曾を"かつて"と訓じるが、意味はすなわち)
女(じょ)の音は汝(じょ)。與は平聲(~か)。○旅は祭の名で泰山は山の名で、魯の地にある。禮に、諸侯は領地内の山川を祭るとある。季氏が泰山を祭るのは僭越である。冉有は孔子の弟子で、名は求。この時に季氏の宰であった。「救」とは、その僭竊の罪、つまり身分を越えて君主の位を盗むこと、に陥るのを救うことをいう。嗚呼は感嘆のことば。その言わんとすることは、神は非禮をよろんで受けることはない、ということである。季氏がその無益を知って自ら止めることを願って、また林放を称え、冉有をきびしく励ましたのである。○范氏が言った、「冉有は季氏に従っている。先生は、冉有が季氏に告げることができないと知っていたはずである。だが聖人は軽々しく人を絶つことをしないで、己の心を尽くすものである。どうして冉有が救うことができず、季氏を諫めることができないと知るだろうか(知らないのだ)。正すことができないとすれば、林放をほめて、泰山を貶めることができないことを明らかにした。これもまた、教育の道である」と。
上田:范氏は孔子は冉有が季氏に言えなかったのを知っていたのか、知らなかったのか、諌めることが出来ないのを知っていたとするのか、知らないとするのか、よく分からない。
小田:范氏の前半部は、孔子が知っていたはずだと言い、後半部で知らないはずだ、と言う。矛盾しているように見えますが。
成田:前半は、孔子が冉有の立場を知っていた、ということです。後半は、冉有がそれでもやってできない人間だと知るはずもない、知ってあきらめるのは、人を絶つことです。孔子は、それをしないということです。
小田:ならば後半部の「知らない」は、人の力を見切って知ったかぶりしない、という意味ですかね。
成田:泰山に勝る人間がいる、という解釈はおかしい。一人の人間が泰山以上ということはありえない。
小田:林放をどう見なすかで、読み方が変わってきますね。林放が礼を知る大人物だと注のように考えたならば、泰山と人間を比べていることになる。成田さんの疑問のとおりです。しかし林放を大した人物でないと考えるならば、そんな林放ですら礼について問うたではないか。その林放に泰山が劣るわけがあろうか、という泰山を強調する表現となります。こちらのほうが、確かにしっくり来る。
上田:朱熹の読み方には無理がある。林放をほめるのは古注もそうだが、見どころのある林放にも劣ることはない、という解釈はなんともおかしい。
成田:林放が礼の本を問うたことを先にほめた注と、ここでつじつまをあわせたら、こうなるわけです。
上田:先でもほめていたとは思わない。いきなり礼の本を聞く、あきれ返った奴である。
成田:それなら、後ともつじつまが合います。
小田:ここは、やはり林放でも礼を知っているのに季氏はそれ以下の非礼ではないか、と批判することに力点を置いたほうが、分かり易いですね。注は、さきの章で林放を称えるというスタンスに、しばられている。
成田:林放はどちらかというと礼の経験も知識もない人とすれば、季氏が泰山で旅をすれば、林放以下の大馬鹿者になります。古注の包咸は、「神は非禮を享けず。林放尚禮を問うを知る。泰山の神反りて林放に如かずや?誣してこれを祭るを欲す」としています。包咸は、林放は礼を問うを知る程度であると言うわけで、さほどほめているものではない。そんな林放ごときより泰山が下なのか、という非難として読んでいます。
上田:孔子は管仲を評価する一方、この篇の後で、礼を知らないと批判している。その管仲は斉の桓公が泰山を封ぜんとしたのを止めている。礼を任じる孔門が、若き季康子の非禮を止められない。これは孔子にとっては非常に腹立たしいことで冉有をしかりとばしている。林放は弟子というより、魯の人とするのみであり、季氏の泰山での儀式をとりしきっていた人とみてみたい。先に、その林放が孔子に先生の礼の本は何ですか、時代遅れではありませんかとでも言いたかったとでも解釈したい。あの林放に泰山の神が劣るとでも思っているのかと怒った。
成田:そういうことを言う人があったような気がするが、誰だったかな?
小田:この冉有が論語の中でどれぐらい出てくるのか見直したところ、一杯出て来ますね。とりわけ重要な章に、顔を出します。弟子の中でも、かなりおいしいところを取っている。雍也篇では「子の道を説ばずに非ず。力、足らざるなり」と言ったり、季康子に政治力を問われて孔子は、「求や藝、政に從ふに於てか何ぞ有らむ」と評され、先進篇では「政事では、冉有・季路」と十哲の一人に挙げられ、また子路との比較で、「求や退く故に之に進む。由や人を兼ねる、故に之を退く」と言われています。この章で孔子は冉有にはもっとやれと薦め、子路には慎重にせよと抑えたというのです。冉有は、ならば自信のない男だったのでしょうか。「季氏、周公より富めり。而して求やこれが為に聚斂してこれに附益す」とあります。余程に、季氏に気に入られていたのでしょうか。ここまで政治で取り立てられる人物ならば、引っ込み思案とはいえないでしょう。実力は、あったのではないでしょうか。
成田:冉有は慎重派の政治家です。泰山での旅のことも、子路なら季氏がやると言っても身を呈して止めたであろう。だが、冉有は季氏にとっても孔子にとってもまるくおさめようとする調整タイプだった。
小田:政事においては、冉有と子路の二人が優れている、と評されていました。子路篇では、「冉子朝を退く。子の曰はく、何ぞ晏(おそ)きや。對へて曰く、政有り。子の曰はく、其れ事なり。如し政有らば、吾を以ひずと雖も、吾其れ與りこれを聞かむ。」とあります。これなんかを読むと、冉有が季氏の政治に必要以上に取り込まれていていて、それを孔子が苦々しく思っているかのようです。事務は、上手だったのでしょうね。だから与えられた業務を一生懸命やってしまって、大局的な正義を見失うことがあったのかもしれない。こんな人は、役所で出世します。
成田:事務能力はあるが、思想がない、それでは君子ではない。
小田:孔子としては、冉有は弟子の中でも権力にいちばん食い込む立場にいるわけですから、こいつを鍛えてやろうと意気込んでいたのでしょうかね。しかし、季子然が「うちの家では、おたくのお弟子の子路と冉有を雇っていますよ。彼らは大臣クラスの人物ですかね?」と聞いたら、あんなの大したことない、と嫌事を言います。孔子が弟子を褒めるとしたら、やっぱり顔回と言うことでしょう。冉有は孔子学校から季氏に入った先兵のように思っているのでしょうが、季康子に泰山での旅の祭を止めろということを、なぜ自分でも直接言わなかったのでしょうか?
成田:孔子は、当時自分で言う立場にはなかった。下問されれば答えるが孔子のスタンスです。一度、斎戒して直接意見をしたことはあるが、それは非常時のことでした。
小田:つまり、この時は非常時ではなかったと。
成田:魯の殿様ではなく、ここでは季氏です。弟子が仕えているから弟子を通じてやる。冉有がやってくれると思ったが、やってくれない。
小田:孔子は、このことは自分の首をかけても諌めろ、と言いたかったのでしょうか。
成田:そうでしょうね。
小田:孔子としては、本当は自分が冉有の立場にいて、政治を引っ掻き回したかったのではないでしょうか。もしこの時若くて政治の場にいたならば、自分で阻止に動いたはずでしょう。
成田:だから、孔子は使いにくかった。いっぽう冉有は使いやすいので、宰にしたのです。
小田:孔子なら、諌めて即首になっていたでしょうかね。
成田:一度、昔にそうなったわけです。
小田:冉有にしてみれば、先生はそれで失敗したじゃないですか、そんなことをしても首になっておしまいですよ、私は長い目で季氏の政治を正していきたいのです、と言いたかったのかもしれません。ならば冉有の言いたいことも、分かります。一挙には無理だから、少しづつやっている。しかし「季氏、周公より富めり。而して求やこれが為に聚斂してこれに附益す」ということになっています。孔子には、冉有は真面目にやっているが、政治の大道をはずれて季氏にとりこまれている、と見えたのでしょう。
成田:論語からはそういう風にみえてくる。
小田:仕事は出来るが、仕える人に引っ張られる人間で、能吏というべきでしょうか。
成田:季氏のために働き過ぎて、孔子に叱られていた。仕事は出来る人。
小田:学はあるが、いわば仁がないというべきでしょうか。
上田:冉有は腹芸のできる政治家。赤(公西)が斉の使者となったとき、孔子が沢山粟を持たせすぎると冉有を叱ったが、赤の母のためとかなんとか言って、使者にふさわしい出で立ちを整えてやるとか、孔子を魯に呼び返すために、自分の軍功は孔子に学んだと偽り季康子に先生を売りこみ、その先生は一方で、自分は軍のことは知らないと放言しており、この噂が季康子の耳に入る前に、使者と礼物を整えて、さっさと迎え入れている。
早川:泰山での旅祭は止められなかったというのですが、左伝にはそれを行ったという記述は無い。真相は、どうだったのでしょうか。
成田:この問答のあと、冉有が思い切って止めた。ああよかったというわけで(笑)。
早川:徂徠の論語徴では、「然れどもその林放を引くを観るに、則ち孔子の譏(そし)れる、必ず奢に在りて僭に非ず。則ち必ず季氏は魯候の為に旅し者にして、其の礼を行うこと徒(いたずら)に美観を務むるが故のみ」と言っています。つまり、ここで孔子が批判しているのは祭りの豪華さに対してであり、季氏は泰山で主君のために盛大に祭りをしようとしたので、僭越という解釈は誤りだというわけです。季氏がどうして、天子の祭りをしたいのか。八佾なら自分の家の庭でできるが、泰山となれば、そこまで出掛けて祭祀を行うことになる。
小田:つまり、徂徠は季氏は魯公の代理として贅沢にやろうとしただけであり、祭り自体は僭越であったわけでもないし、ましてや簒奪の意図などなかった、と徂徠は見るわけですか。
成田:それでは言葉足らず。
早川:季氏がやろうとした。
成田:季氏がやろうとしたというようなものとはしていない。魯の祭りのためでしょう。
早川:出掛けて祭ったのは、何のためにしたのでしょう。
小田:新注では、季氏が僭竊の罪をして、政権簒奪の一歩手前まできていたと見ているわけです。しかし、そうだったのかな。
成田:八佾と同じく、魯の殿様が。財政的に出来ないから本家に代わって立派に祭る。良かれと思ってやっていることでしょう。孔子は、季氏が礼を知らずに祭りを行おうとしているので、これを止めさせるべきと考えて、冉有に止めさせようとした。季氏が政権を簒奪するというものではない。
早川:葵祭というのは、民間の娘が斎王、内親王となるのですから、僭竊なること大変なものです。泰山の神と林放のとりあわせどころではないですね・・・。泰山を人格ある神と見ているのはおもしろいですね。
小田:泰山の神は、泰山府君でしたっけ。
成田:それは、後世の仏教化した神でしょう。この時代ではランドマークとしての泰山であり、国の守護神とみている。
小田:古信仰では、死者の魂魄が泰山にゆくという話があったと聞きましたが。
成田:その信仰は、もっと後の漢代になってからのことです。この時代の泰山の意義とは違っていたことでしょう。
早川:泰山は名山のひとつで、東岳(中央:嵩山、南:衡山、北:恒山、西:華山)です。詩経では、「崧高篇」で、「崧高 維れ嶽 駿天に極る 維れ嶽神を降し 甫及び申を生む」としている。
成田:優秀な人は山や川の霊気を受けている、という考えがありました。孔子も尼丘の山に祈って生まれた、だから頭の形が山のようだ、などという観念です。
早川:北宋の蘇軾(蘇東坡)・蘇轍の父である蘇洵は我眉山の力を受けて生まれ、そのために生まれたとき我眉山の草木が枯れ落ちた、とか言います。
成田:泰山は魯のパワースポットというべきで、魯は泰山を祭る係として周王から派遣されてきた。秦の始皇帝もまた、泰山のみならず各地の名山を廻りました、泰山では、封禅を行いました。
小田:季氏の祭は、泰山に登ったのでしょうか、それとも麓で行ったのでしょうか?
成田:そこは分かりませんが、麓にも祭祀の出来るところがあります。さて新注では「救う」という意味を非常に道徳者孔子として季氏を救おうとした、と解しています。しかし、「救う」はここまでの意味があったのでしょうか。単に、「やめさせる」とサラッと読むほうがよいのでは。
小田:そういえば、英語のhelpも「救う」と「やめる」の二つの意味がありますね。孔子は冉有に、いわば臣道を尽くせ、君君たらずとも臣臣たれ、首を賭けて諌めよ、と言いたかったのでしょうか。
成田:新注は、孔子を道徳者として読みすぎるから、「救う」をそう解釈してしまうのです。それでは、論語に出てくる皮肉屋の孔子が見えてこない。
小田:孔子は、子貢に「暇あらず」とか非常な嫌事を言うわけで。かなり嫌味な人ですね。
成田:新注としては、林放が前の章で礼の「本」を問うたということを、その思想体系に則って重視している。だから、林放を高く持ち上げざるをえないのです。それで、この章の読みに無理がある。
早川:学而篇しょっぱなの有若の言葉「仁の本」から、思想的解釈をほどこすのが朱子です。
成田:朱子の時代には、礼の具体を学ぶことなどできなくて、「礼の本」を追求することしかできなかった。だから、抽象論になるわけです。
小田:林放も「礼の本」を問うたとか言いますが、古義としてはそんな朱子が考察するほど高度な思想的意味で「本」を問うたのでしょうか。そうには、見えないですが。
成田:朱子は、「本」の字があれば本・末の二分法で読みます。本があるならば末があるはずだ。林放は礼の本を問うたから、これは思想的問いをしたのだ、と読むわけです。
小田:林放は、「本」の字を残したばかりに、後世で哲学者として持ち上げられたわけですか。
早川:この一語で、得をした人というわけですかね。
次は早川君おねがいします。
子の曰はく、君子は爭ふ所無し。必ず射か。揖讓(ゆうじょう)して升り、下(くだ)りて飮ましむ。其の爭いは君子。
飮は去聲。○揖讓して升るは、大射の禮、耦(ぐう)して進み三たび揖(ゆう)して而る後堂に升る。下りて飮ましむは、射畢(を)はり揖して降りて、以て衆?の皆降りるを俟(ま)ち、勝つ者は乃ち勝たざる者に揖し、升りて、觶(し)を取り立ちて飮むを謂ふ。言ふこころは、君子恭遜(きょうしん)、人と爭はず。惟射に於て而して後に爭ふこと有り。然れども其の爭や、雍容(ようよう)揖遜(ゆうしん)乃ち此の如くなるは、則ち其の爭や君子にして、小人の爭若(ごと)きに非ず。
先生がおっしゃった。君子は競い争うことをしない。(だが、競い争うのは)必ず弓射の大会である。お辞儀をしたり讓ったりして(堂に)あがり、位置に就き、(堂を)降りて(酒を)飮ませる。その競い方・争い方は、君子である。
飮は去聲(つまり、飲ましむ)。○お辞儀して讓って升るとあるのは、大射の禮つまり国家における君臣の礼を行う弓矢の大会であり、二人づつ進んで三度お辞儀をして堂に升る。(堂を)降りて酒を飮ましめるのは、弓矢を射終わって、お辞儀をして(堂を)降り、すべての組が皆降りるのを待って、勝った者は勝たなかった者にお辞儀して堂に升り、杯を取り立って飲むことを言う。つまり、君子は恭しくひとにすすめて、人と争わない。ただ、弓矢において争うことがあるけれども、その争いは穏やかであり、お辞儀して人にすすめるものであり、このようにするのは、その争い方が君子のやり方であって、小人の争いのごときものではないからである。
早川:弓の事は、成田さんにおまかせです。
成田:古注は「相飲」、つまりお互い飲ませ合うとしています。
小田:試合の最後は、なごやかなパーティーということでしょうか。
成田:朱熹は、終わると堂を降りて、さらに勝った人が勝たない人にお辞儀をしてまた堂に登って飲む、と読んでいます。
小田:つまり、全部終わった後にまた堂上に登って、皆で飲むというわけですか。試合をお開きにして、堂上がパーティー会場に変わる、ということでしょうかね。
成田:朱子の解釈の理由が分からない。射は、揖讓して、お辞儀をし合ってやる。終わった後飲ませ合う。終わって堂を降りており、そこで飲ませ合えばいいのであるが・・・朱子は本当に射の儀式に通じていたのか。
早川:朱子は、母が亡くなってから葬礼を学んでいるくらいですから。酒壺は、西の柱のところにあったとか。柱が堂上なのか堂下なのかまでは、わかりません。
小田:このように中国の弓の儀式について書いていますが、日本の弓の儀式は、どこから典拠しているのでしょうか。
成田:戦国時代は、弓矢は殺す道具であって儀式ではなかった。それが江戸時代になってから、『儀礼』など古典に基づいて、弓の儀式を作り上げていきました。その儀式が、教養ともなりました。各藩ごとに儀式を研究して、それが弓道の流儀となっていきました。
小田:剣道は?
成田:剣道は中国にはなかったから、典籍から取っていないでしょう。
小田:剣道は、六芸に入っていなかったのでしたっけ。
早川:入ってないです。刀で直接殺すのは、君子ではない。弓は遠くから射て殺すので、君子のたしなみとなることができます。
小田:だから項羽が剣について、「人一人を殺すのみ」の術だとして学ぼうとせず、兵法を学んだのは、君子の道としては正しかったというわけでしょうかね。
成田:兵法は、人に戦わせて自分は殺さない。君子は、自分が知らないところで人が死ぬのはかまわない。弓は、人を殺さずとも的を当てる試合として成立しますからね。だから君子のたしなみとなる。
小田:剣道だと、相手の面とか小手とかを殴りつけなければ、判定できないですしね。
早川:「射不主皮、為力不同科」、力が等しくないからハンディをつける。
成田:力量に差のある人が、対等に対決できるようにする。距離を飛ばす試合ならば力の強い者が有利ですが、的を当てるとなると対等となります。
小田:しかし、射術は後世の中国では、すたれましたね。
早川:もう漢代ぐらいから、あまり聞かれなくなります。すでに戦国時代に弩(いしゆみ)が普及して、弓術の実戦的意義はなくなりました。ライフルの時代に刀が無意味となったようなものです。唐代の柳宗元か誰だったかな、油壺の翁の話があります。立派な士大夫がいて、弓道を自慢していた。翁がいて、油を甕に入れて決してこぼさない術を持っていた。翁は士大夫を笑い、おまえさんの弓道などこのワシの油入れの術に等しい、と言いました。だから、唐代ぐらいにはまだ術としては残っていたようです。
小田:しかし、君子の責務として学んでいたのではなくて、単なる趣味だったのでしょう。
成田:ところが、宋代の「清明上河図」には、弓矢を売っている店が書かれています。あれは、誰が買ったのか。
小田:楽器として使っていたんじゃないですか?バイオリンは、遊牧民がギターを弓で弾いてみたところから始まったといいますし。
成田:いや、武器の形でしたがね。
上田:追儺(ついな)の儀式のように、悪霊を払う儀式として、弓は残ったのではないでしょうか。
成田:日本では、そうですね。
上田:何故ここに射儀のことを置いたのか。
小田:これも、礼の一つです。戦乱の中で、平和な礼を説くのは迂遠です。でも、さっきの話のように、遠い後世の江戸時代に、泰平の世で弓の儀礼が学ばれた。孔子が戦乱の世に平和な儀式について言ったことは、決して無駄なことではなかったのです。
早川:君子は射にも礼がある。左伝では人を殺すにも礼がある。ほしいままに殺すのは小人のごとくであるとしています。
成田:孔子は競争心を否定はしないが、すべてが我先となると、いっせいにおしかけて全ての者がだめになってしまう。そこには譲り合いの精神がなければならない。秩序ある競争です。その礼の実例として、弓矢でそのことを示した。
時間となりました。
2012年6月23日(土)八佾篇
本日、小田さん、成田君、上田さんの三人。成田君のリードで八佾篇を音読。訓読と意味を小田さんお願いします。
子夏問ひて曰く、巧笑倩(せん)たり、美目聁(へん)たり、素(そ)以て絢(あや)を爲すとは、何と謂ふことぞ。子の曰はく、繪の事は素(しろ)きより後にす。曰く、禮は後か。子の曰はく、予(われ)を起こすは商なり。始めて與に詩を言ふ可きのみ。
倩は七練の反。聁は普莧の反。絢は呼縣の反。○此れ逸詩なり。倩は、口輔(こうほ)好(よ)きなり(好き口輔の方が自然)。聁は、目の黑白分かるなり。素は粉地、畫の質なり。絢は、采色、畫の飾なり。言へらくは、人此の倩聁の美質有りて、又加ふるに華采の飾を以てすれば、素地有りて采色を加ふるが如きなり。子夏其れ反りて素を以て飾と爲すと謂うかと疑ふ。故に之を問ふ。繪は胡對の反。○繪の事とは繪畫の事なり。後素とは、素より後にするなり。考工記に曰く、繪畫の事、素功より後にす。謂へらくは、先ず粉地を以て質と爲し、而して後五采を施す。猶人に美質有りて、然る後文飾を加ふ可きがごとし。禮は必ず忠信を以て質と爲す。猶繪の事必ず粉素を以て先と爲すがごとし。起は猶發のごとし。予を起こすは、言へらくは、能く我の志意を起發す。謝氏曰く、子貢は論學に因りて詩を知り、子夏は論詩に因りて學を知る。故に皆與に詩を言ふ可し。○楊氏曰く、甘きは和を受け、白きは采を受く。忠信の人は、以て禮を學ぶ可し。苟も其の質無くんば、禮は虚しく行はれず。此れ繪の事は素より後にするの説なり。孔子の、繪の事は素より後にすと曰ひて、子夏、禮は後かと曰ふは、能く其の志を繼ぐと謂ふ可し。之を言意の表に得る者に非ずんば、之を能くせんや。商・賜、與に詩を言う可きは此を以てなり。夫れ心を章句の末に玩ぶ若きは、則ち其れ詩を爲(おさめ)るや固なるのみ。所謂予を起こすは、則ち又相長ずるの義なり。
子夏が質問した、「『にっこり笑う口元えくぼ、白い目にぱっちりとした黒い瞳、白地をもって彩色がひきたつ』とはどういうことですか?」と。孔子がおっしゃった。「白い下地を先にして、そこに色彩をのせるということだ」と。(朱熹は「繪の事は素より後にす」と読ませて、以上の訳となる。古注は「素を後にす」と読ませて、ここを「先に彩色をして、後から白を入れて仕上げる」と読む)子夏が言った、「礼は後から追うものですか」と。先生がおっしゃった、「私を啓発するのは商(子夏)である。それでこそ一緒に詩を語ることができる」と。
倩(せん)は七(しち)練(れん)の反切。聁(へん)は普(ふ)莧(けん)の反切。絢(けん)は呼(こ)縣(けん)の反切。○これは逸詩である。倩は、口元のきれいなこと。聁は、目の黑白がくっきりしていること。素は粉地(おしろい)、画の質(基本)である。絢は、采色、画の装飾である。その意味は、人の口元のえくぼ、ぱっちりした目の美しさがあって、そこに華采の飾を加えれば、素地があって采色を加えるようなものである。子夏は白地を飾りとするのはどういうことかといぶかって、この質問をした。繪(かい)は胡(こ)對(たい)の反切。○繪の事とは絵画の事である。後素とは、白地より後に色を加えることである。考工記では、「絵画の事、素功より後にす」つまり白地から始めるとする。まず粉地を質として、後に五采を施すことをいう。ちょうど人に美質があって、そこにお化粧を施すようなものである。礼は忠信を質(基本)とする。ちょうど絵画において白地から始めるようなものである。起は敬発することである。「予を起こす」とは、私の意図を啓発できるということである。謝氏がいう、「子貢は学を論じて詩を知り、子夏は詩を論じて学を知る。だから両者とは一緒に詩を語ることが出来る」と。○楊氏が言った、「甘(旨味)は和を受け(つまり味を調和できる)、白(白地)は采(色)を受ける(つまりのせることができる)。忠信の人は、礼を学ばねばならない。もしその質(基本)が無ければ、礼は空しくなって行われない。これが「繪の事は素より後にする」の規則である。孔子が、「繪の事は素より後にす」と言って、子夏が、「禮は後か」と言ったのは、孔子の志を継ぐといってよい。これを言意の表に得る(行間を読むこと)ことができなければ、どうしてこのことができようか。商(子夏)・賜(子貢)と一緒に詩を語ることができるというのは、こういうことである。章句の瑣末なことに囚われるならば、詩を読むときに凝り固まって読むことになる。予を起こすとは、互いに良くなるということである」と。
成田:古注は「素を後にす」という読み方をしていて、そう読むと意味が変わります。
小田:「素を後にす」と読めば、後で白を入れる、となるわけですね。
成田:朱子の解釈では、化粧から絵を類推しているわけです。化粧は確かに「おしろい」が先で、後で頬紅などを塗るのが順番です。絵は朱子の時代はどうしていたか分からないが、しかし孔子の時代では、朱子が言うように全体を白く塗ってから後で色をつけるというものではなくて、まず彩色を施してからその隙間に白を埋めて完成させる、という方法が普通だったはずです。白の絵の具だって安くないわけですから、最初に白を一面に塗るよりもこの方が経済的でもありました。
小田:「絵の事は素きを後にす」と読めば、そう考えるしかない。朱子は、わざわざ「素きから」と読んで反対にしました。
成田:鄭玄は、凡そ絵画はまず布に衆色を描き、その後で素でその隙間を分布するとしていて、おそらくそれが孔子の時代のやり方だったはずです。
小田:その解釈では、礼のニュアンスもまた朱子とは違いますね。
成田:朱子は白を礼と取らず、礼は鮮やかさのほうであり、五色の色の方であると考えます。
小田:つまり白さは忠と信であり、これが「質」。様々な礼の規則は華やかさである、と。しかし、古注ならばたとえれば人間の色々な特質が五色の華やかさであり、人間というものはまず豊かな彩色が置かれるべきである。その後に礼で輪郭をつけることによって、立派な人間になる、と考えるわけですね。この方が人間の多様な美質を認める解釈になって、ふくらみがあるように思えます。
成田:古注では、白が礼です。新注は、色が礼です。
上田:素と白はちがう。口元や目元が美しいのは化粧した顔ではなく素顔、その素(顔)が絢(あや)というフレーズの意味が分からず聞いた。考工記においても、白は五色の一つであり、五色と素は別にしており、「繪畫之事、後素功」とあり素の功(はたらき)としている。
成田:私の印象では、素=白の意味で使われることは、普通だと思います。この章が考工記の定義で使われているかは分からないですが、考工記以外の文脈で素と白を厳密に区別して用いているかは、疑問です。白のかわりに素の字を使うことは、珍しくないです。
上田:義疏では、「素は白。絢は文の貌。白色を用ひ以て間を分つを謂ふ。五采をして文章(あや)を成す」としており、古注では素を白としてますね。以前の読書会で鄭さんは、「下地の悪い所に化粧しても化粧が映えない」、素の質が良くなければの観点でみなくてはいけないと強調しておられた。禮後乎も、禮で仕上げるというものではなく、禮においても素質が大事であることを言っているのではないか。
成田:そういう読み方も、不可能ではないです。だがそれは、新注よりもさらに新しい考え方というか、素顔のままが最も美しいという現代的な美人観で読むとそうなる、と言えるでしょうかね。鄭さんの美人の観念と孔子の美人の観念が同じだったか、どうか?
小田:孔子の美人観と朱子の美人観、そして鄭さんの美人観は、いずれも時代を隔てて違っているでしょうね。ただ鄭さんの読み方を取ると、素顔の素質が美人でない人は帰ってください、となってしまうなあ。
成田:文法的には、「絵の事は素より後にす」とはふつう読みにくい。前の「夷狄の君有るは、諸夏の亡きが如くならず」のように、朱熹は文法どおりに読むことよりも、正しいと考える解釈に沿って読むことを優先するときがあります。文法的には「素を後にす」と読むのが自然です。考工記も、「絵画の事、素功を後にす」としています。
上田:禮後乎は繪事後素と同じく、禮後「素」乎ということではないか。
成田:だがそういう意味ならば、たとえば「禮後之乎」とならねばおかしいです。あるべき目的語が省略されることは、ありません。やはりここは目的語を伴わない、「礼は後か」と読むしかないと思います。
小田:前に成田さんが言われましたが、朱子の時代になればもはや礼の実習などは不可能であって、礼の「本」を考察することしかできなくなっていた。だから、この章も礼を礼だけで終わらせることなく、その質である忠信を下地に置くべし、という解釈に引き付けて読んだのでしょう。
成田:朱子の時代にもなんとか復元しようと望んだのですが、無理であった。礼の具体は、どうしても二の次になってしまう。
小田:礼を抽象的に考えるしかなかったのが、朱子の時代が古代と違っていたところでしょうね。
上田:左伝を読むと、孔子の時代には、礼儀と礼を分け、魯公は挨拶とか贈り物などの礼儀はきちんとしているが、礼が分かっていない。国の在り方が礼にかなっておらず、あれではいずれ成り立ち得なくなるみたいな言い方をしており、国や個人がいかにして存立できるかを問うものとなっていた。
小田:しかし、その言われる「礼」は、孟子の言う「仁義」と何か違っているのでしょうか?表面的な「礼儀」の奥底にあるべき精神を指すのだとすれば、それは左伝では「礼」という字を用いて説明したとしても、その内実は孟子の用法でいう「仁義」と同じなのではないでしょうか?孟子は「礼」を「仁義」とは別の概念として区別しています。私は、孟子の「礼」はやはり形式的な規則に準拠する精神、として捉えていると思います。それはそれ自体が美徳であって、他方別にある人間の美徳として「仁義」がある。どちらも重要である、と孟子は考えたからこそ、両者を並列したのだと思います。
成田:礼は朱子学の基本概念ですが、形式だけではだめで、本質が必要である。朱子の時代には、礼の実践はもはやできなかった。すでに形式を失っていた。形式が得られないから、本質が備わっていればそれでよいのだ、という考えになった。我々は礼を実践できないが、仁があるからいいのだ、と。だが孔子の礼楽には、本質論と形式論がある。形式を、きちんと実践して身に着けていた。むしろそれがカリキュラムの主要課題だった。なので礼楽が形式に傾くのは、仕方が無い。だが、そこに仁が無くなれば終り。子夏の「禮は後か」という問いは、形式を軽んじていることではない。えくぼや目ぱっちりは本質で仁、おしろいで塗るとそれが引き立つ。白が礼であり、形式が本質を引き立てることを言っている。
小田:礼を礼儀だけで終わらせないために、たとえば詩を学ぶ、書を学ぶとか、いろいろな文化を知って仁の心を養うことが、孔子の薦めた教育でしょう。礼は就職の手段であるから学ばないといけない。だが知識ばかりでは、人間としてよろしくない。孔子の時代には、礼の形式を学ぶことは必須であり、しかし礼の形式を学ぶだけでは足りない。それが、孔子の言いたかったことでしょう。
成田:広い意味での礼は、国家システムまで入ります。八佾篇では、楽とならべて用いられる。詩や書はいわば一般教養で、礼楽は専門科目です。礼楽は就職の必須科目だから学ばなければならないが、これだけはなくて教養科目も必要で、情操を涵養しなければならない。
上田:詩に興り、礼に立ち、楽に成る。つまり、礼は自立すること。
成田:「興」とは、自然な感情が起こること。自然に起こる感情、それが仁です。詩を学ばないと、礼楽を学んでも仁が起こらない。
小田:この章の「巧笑倩兮 美目聁兮 素以爲絢兮」は、逸詩と言いますが。
上田:これは詩経、衛風、碩人で、「手如柔荑 膚如凝脂 傾如蝤蠐 齒如瓠犀 螓首蛾眉 巧笑倩兮 美目聁兮」とある。「巧笑倩兮 美目聁兮」が一致しており、この詩を碩人とし、古注は、「素以爲絢兮」が亡逸されたとみてきた。また、古注は、碩人を衛國の美人、莊姜を形容したもので、素顔が美しいのみならず禮を心得た女性であり、絵を白で際立てるごとく、禮で自らを節することができる女性とみていた。衛公は徳を好まず、莊姜はうとまれたようで、それを閔(あはれ)む詩とした。
成田:この子夏の引用が本当に碩人から取ったのかは、確定できません。
小田:後世になって、この論語にある詩の一句を種にして詩経に「碩人」を増補した、という可能性はあるのでしょうか?
成田:それは、考えにくい。詩経はすでに孔子の頃に三百程度になっており、衛風、碩人はすでに成立していました。孔子時代より前に成立していたわけですから、捏造なんかしたら同時代人によってバレてしまいます。しかし、孔子の頃には「素以爲絢兮」があってその後これが亡逸した、と古注は考えているのですが、朱熹はこれに疑問を抱いたようです。だから、全体を逸詩とみなしています。
小田:「巧笑倩兮 美目聁兮」というフレーズは、いわばありふれた決まり文句。たまたまこれが碩人と一致していたから古注は子夏は碩人の原型を引用したのだ、とみなしたのでしょうが、実は別の失われた詩の一部であった可能性を捨てきれない。朱子はここで慎重に懐疑論を取ったのですか。
上田:吉川幸次郎先生は、ここをどう解釈していますか。
成田:この詩は碩人の詩とみなしており、朱子の懐疑は取っていません。古注の「素を後にす」に従い、白を最後に加える、つまり礼で仕上げる。人間も教養を積んで、礼を行う、という読み方を取っています。この章のように論語の解釈と詩経の解釈がダブルで必要になると、解釈する側も難しいです。
小田:ここで孔子と子夏は、いわば色っぽいことを詠んでいる詩について議論しています。ところで子夏は前の学而篇で「賢賢易色」と言っていましたね。これを朱子は「賢を賢として色に易(か)ふ」と読んでいるわけで、つまり子夏はここで「好色などにうつつを抜かす心を改め、賢人を賢人として評価せよ」と言ったということになります。だが朱子のように読むと、この章で孔子と子夏が色っぽい詩について議論していることと、子夏のイメージがいささか合いませんなあ。
成田:古注では、「賢賢易色」はあるいは色を好むように賢人を賢人として評価せよ、と読んだり、目上の人の顔色をうかがうように賢人をよく見て評価せよ、と読んだりしています。これらならば、子夏が色気を退けた堅物とはなりません。
小田:ならば、「賢賢易色」は古注のほうが、この章での子夏と合うかもしれませんね。孔子も子夏も、なかなかの好き者であった、、、
成田:詩をダシにして好色談義を行い、その過程で深い意味もまた論じる。そのような師と弟子の対話があったとしてよいでしょう。
いささかも色めいた話で終り。久方振りに一揆にて一杯。
2012年6月30日(土)孟子梁恵王章句下
本日、小田さん、上田さんの二人。本日分を音読。訓読と意味を小田さんお願いします。
莊暴、孟子を見て曰く、暴、王に見(まみ)ゆ。王、暴に語(つ)ぐるに樂を好むことを以てす。暴、未だ以て對ふること有らず。曰く、樂を好むこと何如。孟子曰く、王の樂を好むこと甚だしくば、則ち齊國は其れ庶幾(ちか)からんか。他日王に見へて曰く、王嘗て莊子に語ぐるに樂を好むことを以てする有りや。王、色を變じて曰く、寡人能く先王の樂を好むに非ず。直(ただ)世俗の樂を好むのみ。曰く、王の樂を好むこと甚だしくば、則ち齊は其れ庶幾(ちか)からんか。今の樂は猶(なを)古への樂のごとし。曰く、聞くことを得可きか。曰く、獨り樂して樂しむと、人と樂して樂しむと、孰れか樂しき。曰く、人と與(とも)にするに若(し)かず。曰く、少と樂して樂しむと、衆と樂して樂しむと、孰れか樂しき。曰く、衆と與(す)るに若かず。
莊暴が、孟子に会って言った。「それがしが王に謁見したとき、王はそれがしに『楽が好きだ』と申された。(楽を音楽とみるか、楽しむこととみるか。朱子は音楽とみており、それでとりあえずは解釈する。)それがしは、何と答えてよいか分からない。音楽が好きという王の言葉について、どう思いますか?」と。孟子が言った。「王がそんなにも音楽が好きであれば、この斉は理想に近いでしょう」と。後日、孟子は王に会見して言った。「王は、以前に莊暴に音楽が好きだとおっしゃったそうですね」と。王は、顔色を変えて言った。「寡人(それがし)は、先王の音楽は嫌いです、世俗の音楽しか好きになれません」と。孟子が言った。「王がそんなにも音楽をお好きなであれば、斉は理想に近いでしょう。今の音楽は、いにしえの音楽と似たようなものです」と。斉王が言った。「もっと詳しく聞かせてほしいです」と。孟子が言った。「王は、ひとりで音楽を演奏して楽しむのと、誰か他人と共に音楽を演奏して楽しむのと、どちらが楽しいですか?」と。王が言った。「それは、誰か他人と一緒にするほうです」と。孟子が言った。「では少人数と共に音楽を演奏して楽しむのと、大人数で音楽を演奏して楽しむのとでは、どちらが楽しいですか?」と。王が言った。「それは、大人数のほうです」と。
小田:朱子は、楽を音楽と解釈しています。しかしそれでは、莊暴がどうして「未だ以て對ふること有らず」と言ったのでしょうか?莊暴は、王が単に「音楽が好きだ」と言ったことに対して、なんで返事に窮したのでしょうか。
上田:莊暴は、王に楽が好きだが、古の楽より今の楽が好きだと言われて、どう返答してよいものか答えに窮したのを、孟子ならどう答えるかを聞きたかった、と朱子はするのでしょう。
小田:「樂」を単に音楽と解釈するのは、なんとも狭い解釈で好きではないですね。小林先生はもっと広く「楽しむこと」としておられる。こっちの方が、より内容の広がりがあると思うのですが。
上田:朱子は樂をyue、音楽の樂とle、楽しむを分けている。すべてleで読めということですか。
小田:小林先生は、陳善・郝氏の説を取って、「楽」を娯楽、歓楽の意と読みました。こう読めば、斉王はいにしえの音楽に限らず、もっと一般的にいにしえの古臭い文化なんかよりも今風の娯楽の方が好きなんだ、と言ったことになります。こちらの方が、斉王の答えとしてより生き生きしていると思います。ところで今改めて朱子の注を読んでみたのですが、この解釈にはがっかりですね。朱子は、結局孟子が「今の樂は猶(なを)古への樂のごとし」と言ったことについて、時を救うため、つまり本来音楽は上下を調和させるために存在しているのだが、斉の国は上下が調和していない。だから、今どきの文化でも今は致し方ないから上下を調和する努力をしなければならない、と斉王に説いたと解釈しています。つまり、孟子が今どきの世俗の音楽(文化)でもかまわない、と斉王に言ったのは、単なる時を救う方便としてこう言っただけだ、本当は孟子もまた孔子と同じように、いにしえの音楽(または文化)しか正しい文化はありえない、と考えていたはずだ、とみなしています。この読み方は、せっかくのこの章の持ち味を殺している、と私は思うのです。朱子は、孟子と孔子の考えは同じであり、そこにズレはないと見なすから、こう解釈するのです。私は、賛同しかねます。
上田:朱子が孔子と孟子は同じ考えであるとは、どういうことですか。
小田:朱子は、「孔子の言は、邦を爲むるの正道、孟子の言は、時を救ふの急務なり」と言います。孔子は、音楽は舜の作った韶はよいがワイセツな鄭声は追放せよ、と言いました。孟子は古の音楽も、今の世俗の音楽も同じようなものだ、と言いました。この両者を、朱子は孔子は正道、孟子は時を救う方便とみなして片付けました。しかし、それでよいのでしょうか。斉王がたとえば舜の韶なんてつまんねえ、今どきの世俗の音楽のほうが楽しいよ、と言ったとき、孟子は斉王を叱らなかった。舜の音楽なぞ、戦国時代にはしょせん古臭くて堅苦しい。斉王が今どきの音楽の方が楽しいのは人情としてもっともであり、だから音楽の内容ではなくて楽しむことの精神を大事にすればいいのですよ、と孟子は説いたのではないでしょうか。そこに、孟子と孔子の違いがあると思うのです。
上田:孔子は正道、孟子は方便としましたね。
小田:私は、孔子と孟子の視点にはズレがあると思うのです。孔子は礼楽を本気で研究して実践し、これに生涯を打ち込みました。孔子の礼楽に対する言葉には、本気があります。しかし孟子が斉王にいにしえの楽でなくても今の楽でもよいと言ったことは、果たして朱子の解釈のように妥協をしたものであったのでしょうか。私は、時代のずれが孔子と孟子にはあり、自分で感動して薦めた人と商売として諸侯に売り付けた人との差があると思うのです。私が思うに、孟子はいにしえの礼楽が戦国時代の人を感動させるとは、思っていなかったのではないでしょうか。舜の音楽に孔子は感動しましたが、孟子は実はこんなもの今どきは通用しないと思っていたのかもしれません。だから、論点をずらした。クラシック音楽とかフォークソングなんか、古臭くてつまらないですよね。王がトランスとかアニソンとかがお好きなのは、当然ですよね。だから、王がどんな音楽が好きかなんかはどうでもよくて、王が楽しんでいる姿を皆が喜んでくれるように心がけるのが、王の勤めとして大事なのですよ、と孟子は時代の人として言ったと私は見たいです。
上田:孟子特有の語り口、ポイントを変え、非常にシンプルに二者択一、誰にでも分かるような喩えを用いる。
小田:斉王が顔色を変えた、という部分がよいですね。孟子に「いにしえの音楽はお気に召さないようですね?」と言われて、若い王が狼狽して先生に本音を漏らした。その言葉を巧みにとらえて、斉王の心をつかんだ。舜の音楽がつまらないとは、どういうことか!とか叱るのではなくて、それはかまわないのです、だから大事なことは別にあるのですよ、と説いた。ここの説き方が、じつによい。
上田:それは孔子にはできない芸当で、孟子は、斉王の性向をよく考えて説得する策をめぐらして会見をしたのでしょう。樂樂を「楽しみを楽しむとする」と読むのは後の鼓樂、鐘鼓の聲、管籥の音への展開では音楽を楽しむとする方が流れがよいと思う。
小田:この章を通して読めば、「楽」を音楽と読んだほうが、自然でしょうね。しかし、それではあまりにもつまらない。「楽」の字を楽しみと読んだほうが、斉王と孟子の言葉が生き生きとします。若い世代と年寄りの楽しいと思うことがずれているのは当然であり、だから孟子は若いあなたが楽しいと思う娯楽は私にさっぱり理解できないが、楽しんでいる姿を喜ばれることが人の上に立つ者の責務だということは、分かるでしょう?と、世代の違いを超えて説いたと読みたいです。
上田:孟子は孔子が諸侯に容れられなかったことをよく考え、諸侯を説得するには孔子風のやり方では無理であると思い、論点を分かり易いポイントで見直し、二者択一で答えられる分かり易い喩えを用意し、ポイントさえ外さねば鷹揚に対応した、これは孔子にはないもので、諸侯の心を捉える点では孔子にはるかに勝った。ただ、もっと長いスパンでみれば、孔子と孟子の影響力の差は歴然としている。
小田:孔子は自分を理解してくれる弟子たちには上手に対話しましたが、会見した諸侯の心を掴むような話術はありませんでした。孔子は、弟子とか貴族とかに対して、多くを語らずに遠まわしに人に悟らせるような対話法を取ります。しかし孟子は、話術で相手を自分のペースに引き込ませるやり方でした。初対面の人でも半信半疑の人でも、説得して納得させる術の持ち主が孟子だったでしょう。
上田:次にゆきますか。
臣請ふ、王の爲に樂を言はん。今王此に鼓樂せんに、百姓王の鐘鼓の聲、管籥(かんやく)の音を聞きて、舉(みな)首を疾(や)ましめ頞(ひたい)を蹙(あつ)めて、相ひ告げて曰はん。吾が王の鼓樂を好む、夫れ何ぞ我をして此の極に至らしむ。父子相ひ見ず、兄弟妻子離散すと。今王此に田獵せんに、百姓王の車馬の音を聞き、羽旄(うぼう)の美を見て、舉、首を疾ましめ頞を蹙めて、相ひ告げて曰はん、吾が王の田獵を好む、夫れ何ぞ我をして此の極に至らしめて、父子相ひ見ず、兄弟妻子離散すと。此れ他無し。民と樂しみを同じふせざればなり。今王此に鼓樂せんに、百姓王の鐘鼓の聲、管籥の音を聞きて、舉、欣欣然とし、喜べる色有りて、相ひ告げて曰はん、吾が王庶幾(ちか)くは疾病無きか。何ぞ以て能く鼓樂する。今王此に田獵せんに、百姓王の車馬の音を聞き、羽旄の美を見て、舉、欣欣然として喜べる色有りて、相ひ告げて曰はん、吾が王庶幾くは疾病無きか。何を以てか能く田獵す。此れ他無し。民と樂しみを同じふせばなり。今王百姓と樂を同じふせば、則ち王たらん。
「臣(それがし)、王様のために音楽について申し上げましょう。今、王様がここで鼓をうつとします、人民が王様の鐘鼓や竹笛の音を聞いて、全員が頭を痛めて、眉間にしわを寄せて(後藤点では「額を寄せあって」と読ませる)、お互いが話し合ってこう言ったとしましょう。『我らの王様は鼓楽が好きだが、一体どうして我々はこのような窮迫になったのか。父子は離れ離れ、兄弟、妻子も離散している』と。また、今王様がここで狩りをするとしましょう。人民が王の車馬の音を聞き、旗の美しさを見て、全員がやはり頭を痛め眉間にしわを寄せ、お互いが話し合ってこう言ったとしましょう。『我らの王様は狩りが好きだが、一体どうして我々はこのような、、、(以下同じ)』と。これは他でもない、民と楽しみを同じくしていないからです。しかし、今王様がここで鼓をうつとします。人民が王様の鐘鼓や竹笛の音を聞いて、全員がうきうきと喜びの表情をあらわしてこう言います。『吾らの王様は最近はご病気でもないのでしょう。そうでなければ、どうして鼓がうてましょうか』と。また、今王様が狩りをするとしましょう。人民が王の車馬の音を聞き、旗の美しさを見て、全員が、うきうきと喜びの表情をあらわし、お互いが話し合ってこう言ったとしましょう。『我らの王様は最近はご病気でもないのでしょう。そうでなくばどうして狩りができましょうか』と。これは他でもない、民と楽しみを同じくするからです。今、王様と人民とが楽しみを同じくするならば、王者となることができましょう。」
小田:「庶幾無疾病」ですが、これをどう読むべきでしょうか。小林先生は庶幾を「幸いにも」と読みます。後藤点は「近くは」と読ませているようです。
上田:「最近は」としているのではないか。
小田:それでは、「庶幾」の読み方がさっきと違うように読まれることになります。つまり、先程は距離的に近い、ここでは時間的に近いということでしょう。とりあえずここは最近と読んでおきますが、「庶幾」に時間的近さの意味があるのかどうか、調べ直してみる必要があります。
上田:後藤点では、「頞(ひたい)を蹙(あつ)めて」と読ませている。朱熹は、「首を疾むは頭痛なり。蹙は聚なり。頞は額なり。人憂戚あるは、則ち其の額を蹙む。」としている。聚とし、額を蹙(しわ)むともしている。
小田:小林先生は、朱子の読み方ですね。ここで、人民は王の音楽とか狩りの中身を見て、王を評価しているわけではありません。王がどんな音楽を聞くか、どんな狩りで楽しむかなどは、人民にとって知ったことではない。ただよい政治をしてくれれば、人民は王の健康を祈ることでしょう。王に人民を思う気持ちがあれば、人民はこの王に倒れてもらっては困ると思うでしょう。王が元気だとありがたいと人民に思われるような王になりなさい、と孟子は言いたいのです。
上田:王と一緒にするということは、後に文王の狩場は文王のみでなく、民もまぐさを刈り、薪を採りに入る、雉や兎などを捕まえに入ることができる、民にとっても都合がいい場所なのでもっと広くてもよいとしたということ。
小田:孟子が「今の樂は、猶古への樂のごとし」と言ったのは、儒家の公式見解からはずれた物言いです。だから、朱子は「若し必ず禮樂を以て天下を治めんと欲すれば、當に孔子の言の如く、必ず韶舞を用ひ、必ず鄭聲を放つべし。蓋し孔子の言は、邦を爲むるの正道、孟子の言は、時を救うの急務なり。」と解説せざるをえなかったのです。しかし私が思うに、孟子のここでの主張は、儒家の公式見解から一歩も二歩も越えていることを指したのではないか、と思うのです。大事なのはいにしえの礼楽そのものではない。礼楽の儀式なんぞはただの宮廷でのタテマエであり、孟子としては儒家の商売道具だから売り込んでいるのにすぎない。君主として最も大事なことはむしろ音楽の精神であり、それは一緒に楽しむことなのだ。一緒に楽しむ精神があれば、今どきの楽しみでも一向にかまわない。孟子は、そこに言いたいところがあったと私は思うのですが。
上田:さっきの箇所は范氏の説ですね。
小田:朱子は范氏を引用しているので、先人の引用をつなげて言いたいことを構成するのは、朱子のスタイルです。つまりこれは朱子の考えでもあります。正道と方便という見方です。孟子の時代になると、宮殿や軍隊が大掛かりとなり、いわば形で威圧して君主の権威を高める時代となっていました。しかし、孟子は。盡心章句下三十四で、「大人に説くに、則ち之を藐(かろん)じて、其の巍巍然たるを視ること勿かれ。堂高きこと數仞、榱題(すいてい)數尺、我志を得るともせじ。食前に方丈、侍妾數百人、我志を得るともせじ。般樂して酒を飮み、驅騁(くへい)して田獵し、後車千乘、我志を得るともせじ。彼に在る者は、皆我のせざる所なり。我に在る者は、皆古の制なり。吾何ぞ彼を畏れんや」と言います。権勢を気にするな、見掛けに惑わされるな、そんなもの私は要らないというのです。宮廷を厳かに飾る礼楽が売りの儒家の親玉である孟子が、大仰な宮廷装飾を軽視するのが面白い。儒家は儀式を商売道具としており、厳かさにより心服させることが売りです。孟子は弟子から聞かれれば、礼楽を厳かに行えと答えたでしょう。だが斉王にはあまりこだわらず、力点をずらした。そういう闊達さは、孟子以前も以後もみられない。後の儒家は荀子でも叔孫通ら漢代儒者でも、儀礼に非常にうるさくなります。礼楽こそが、儒家のオリジナルな売りなわけですから。
上田:この鷹揚さというか、ええかげんさは孔子には無い。孔子以降諸侯を説き宰相となって政治を行うということは、孔子にできなかったことに挑むものであり、孟子も相当の覚悟で挑み、孔子以上の成果をあげた。孔子の時代とは異なり、孟子は独自の方法をとらねばならなかった。
小田:孟子の時代には、孔子の時代にはいなかった論敵がいました。君主に説く集団は儒家だけではありませんでした。ライバルの上手をゆき、王の心をとらえねばならなかった。そのための工夫を孟子はしたので、孔子と置かれた状況が違いました。朱子などは、孟子を孔子の解説者とみなす視点に終始します。孟子が独自の見解をもつとは、見ません。朱子ら宋代学者は、礼楽について孔子と孟子の主張を首尾一貫させて議論するのですが、実のところはいにしえの礼楽についてリアリティーを持って議論できなかったから、抽象的議論を展開せざるをえなかったのでしょう。
上田:前にもその議論があったのですが、朱子の礼楽が抽象論にすぎるということですが、どういうことですか。
小田:礼楽などの古代文化は、漢が滅んで五胡十六国の時代に古代中国がいったん滅亡した時期に、ほとんど断絶してしまいました。後の唐の時代になれば、社会風俗はずいぶん仏教化してしまいました。そこで韓愈が儒学の道統復興を唱えたわけで、続く宋代にしても学者たちは禮記などのテキストを見直しました。しかし、そこに書かれている礼楽はすでに遠い時代の文化であって、その当時の時代ではほとんど実感できるよすがもありませんでした。我々が奈良や平安朝の儀礼にリアリティーが感じられないのと、同じことです。今の日本人の文化は直接は江戸時代の文化を継承しており、その前段階としてせいぜい室町時代の文化ぐらいにしか起源を遡ることができません。だから、平安時代の日記とかに書いてある細々とした儀礼とか習俗とかは、今の日本人にとっては遠い世界の話でしょう。中国では王朝が交代し、周辺異民族が漢族に取って代わっているため、文化的断絶はなおさらです。時代を通じて共通しているのは漢字ぐらいのもので、朱子の頃には禮記を読んでも、もはや実感が湧きづらかったことでしょう。こうだったのかな、ああだったのかなと考えることしかできなかった。なにせ、孔子や孟子の座りかたであった、ゴザの上に正座するというスタイルじたいが、朱子の時代には滅んでいました。いにしえの音楽もまた、滅んでいました。葬礼だって、朱子の頃には仏式だったはずです。それを儒式で行った宋代儒家たちが奇人扱いされたぐらいですから。その後中国では儒学が勢いを盛り返したので、現代ではいくぶん古式に戻っています。中国では王朝交代はときに民族の交代を伴い、前王朝が否定されて文化は一変してしまいます。唐は宋と違い、宋は元と違い、元は明からさらに違い、その明は清と違います。朝鮮では民族は変わりませんが、そこでも王朝が代わると前王朝の文化が全否定されます。李氏朝鮮の文化は、前代の高麗文化が仏教中心であったことを根本から否定して、朱子学一尊を定めて仏教を排斥しました。現代の韓国には、平地の都市にほとんど仏教寺院がありません。李氏朝鮮時代に、廃止されたのです。
上田:そんなに断絶していますか。日本人は日常生活を戒律により行うという習慣はなく、禮記をみてもリアリティーがないのはよく分かるが、朱熹においてもそれほど遠いものという考えはなかった。その時代のリアリティーを知らねばならないというのはまさしくそうですが、なかなかそれは難しい。
小田:朱子は孟子の叙述に、どこまでリアリティーを感じることができたか。朱子の時代には、孟子の時代のように臣下が君主と親しく対話するというようなことは、ほとんどありえないことでした。孟子にとって当たり前のようにできていたことが、朱子の時代には遠い世界であるように見えたと思います。ましてや、皇帝の権力が絶対専制化した明代以降の学者などには、夢のような話であったでしょう。
上田:成程、時代の制約を知ることは重要なことです。
2012年7月7日(土)孟子梁恵王章句下
本日、小田さん、上田さんの二人。本日分を音読。訓読と意味を小田さんお願いします。
齊の宣王問ひて曰く、文王の囿は方七十里、有り諸(や)。孟子對へて曰く、傳に之れ有り。曰く、是の若く其れ大なるか。曰く、民猶を以て小なりとす。曰く、寡人が囿方四十里、民猶を以て大なりとするは何ぞや。曰く、文王の囿は方七十里、芻蕘(すうじょう)の者往き、雉兔の者往く。民と之を同じふす。民以て小なりとす、亦宜(う)べならずや。臣始めて境に至るに、國の大禁を問ふ。然して後に敢へて入る。臣聞く、郊關(こうかん)の内、囿方四十里なる有り、其の麋鹿(びろく)を殺す者は人を殺すの罪の如しと。則ち是れ方四十里、?を國中に爲る。民以て大なりとする、亦宜(うべ)ならずや。
齊の宣王が質問した、「文王の狩場は七十里四方だったといいますが、本当ですか?」と。孟子が答えた、「言い伝えにそうあります」と。宣王が言った、「そんなに大きいものだったのですか」と。孟子が言った、「人民はそれでも小さいとみなしていました」と。宣王が言った、「それがしの狩場は四十里四方ですが、人民はそれでも大きいと言う。これはどういうことでしょうか」と。孟子が言った、「文王の狩場は七十里四方でしたが、草刈りや薪集め、雉や兔を取る者の立ち入りを許し、つまりは人民と狩り場を共有していました。だから人民は、文王の狩場を小さいとみなしたのです。当然ではないですか?それがしが始めて国境に来た時に、斉国の重大な禁令を聞いてから、国に入りました。聞くに、関所の内側に四十里四方の狩場があり、その鹿を殺す者は殺人罪を適用するとのことでした。ならば、これは四十里四方もある落とし穴を国の中に造るようなもので、人民がこれを大きいと言うのは当然ではないですか?」と。
小田:後で出てくる滕文公の、滕国が方五十里です。つまり方四十里は、当時の弱小国並みの大きさというわけですか。一里400mですから方四十里は16km四方です。それで孟子は斉王を批判して文王を称えるのですが、私が思うに周の文王の時代とこの戦国時代とでは、土地の価値がぜんぜん異なっていたことでしょう。文王の頃の中国は、まだまだ未開の状態で原野が多く、七十里の狩り場を設定しても大したことはなかったでしょう。国の法令で森林や沼沢地への立ち入りを禁じたのは、戦国時代には各国でも行われた政策でした。木は戦略物資であり、保護しなければいけない。また沼沢を管理することは、治水政策上の都合もあったはずです。文王の時代と戦国時代を比べると、人口が桁違いに増加しており、土地は開拓され、それに伴う自然破壊の問題もこの時代には現れました。国家としては森林や原野を人民の好き放題に開墾させることは、国家政策上望ましくない点もあったはずだと私は思います。だから、狩場への無断立ち入りを禁止したは、あながち王の私利私欲による暴政とはいえなかったのではないか。私は、そう思うのです。しかし、邪魔をされた人民は当然怨みます。けちな王だと怒るでしょう。韓非子などは、人民の言うことは聞いてはいけない、なぜならば国の利益と人民の利益は相反し、人民は目先の利害しか見えないからだ、と論じます。国全体の利益のためには人民の個別の利害や意見などは無視して進まなければいけないと言うのです。孟子にも幾分か、人民の意見を聞くべきでない場合がある、ということを理解している節があります。鄭の子産の美談で、冬の川を渡れずに困っている人民を哀れんで自分の舟に一緒に乗せてやったという話があります。孟子はこれを批判して、なぜ冬の間に人民を動員して橋をかけないのか、と言いました(離婁章句下、二)。その時は怨まれるかもしれないが、あとで大きな利益が得られる。だから、人民に我慢して働いてもらわなければいけない。また孟子は、「佚道を以て民を使ふは、勞すと雖も怨みず。生道を以て民を殺すは、死すと雖も殺す者を怨みず(「人民の福祉のためにあえて人民を使役するならば、苦労させても怨まれはしないだろう。人民の生存を守るためにあえて死を命じるならば、殺してもその執行者は怨まれないだろう。」)と言いました(尽心章句上、十二)。韓非子と違って、孟子には「一道を以て行」えばそのとき民は喜ばずとも、後に必ず民は喜んで感謝してくれるという楽観論が見えますね。孟子には、天の声は人民の声を通じて現れる、という考えがあります。人民から見放されたら、もはや君主の資格はないと言うのです。しかしそうであるならば、人民から批判される政策は、何もできなくなる。だが孟子は上のような視点を用意して、政治家は民の声を最終的には得ることができるので、目先の批判を受けることを気にせずに長期的によい政策を取れ、というロジックを成立させます。いっぽう韓非子は、一転して人民の理解力に対して悲観的となりました。
上田:子産が農地改革を行った時、民は子産を怨んだ、この苦しさのすべてはあの子産のせいだ、子産を殺すものがおればいいと歎いた。三年たつと生活が豊かになり、子産なくしてはこの生活はないと喜んだ、というような類ですか。
小田:孟子は、その説話のとおり、最終的には民は分かってくれるという信頼感があります。しかし、韓非子にはその信頼はありません。民は目先のことのみで、感謝などしない。だから、人民の意見など聞かず法と力で政策を突き通すべきである、と言うのです。
上田:どうして、そのように意見が変わりましたか?
小田:なぜでしょうかね。韓非子が結論に達したところの中国の民は、為政者に感謝するような殊勝な人々ではないのかもしれませんね。孟子は、民の声は天の声の反映であるとみなすわけですから、人民が怨むようではいけない。しかし他方で人民の意向に逆らっても、目先の利益に反することもしなければならない。ここの兼ね合いが、難しいところですね。
上田:斉に入国するとき、孟子はこの禁令を知り、この話は使えると考えていたのでしょう。
小田:孟子が斉王に言いたかったのは、法をなくせとかいうことではなくて、法の向こうにある精神を大切にせよということではなかったでしょうか。殺人罪を適用するような禁令は、国のためなのか。国のためならば、厳罰もいたしかたない。しかし、法の目的を理解して運用しなければ単なる暴政であり、人民の落とし穴である。孟子は、ここでそんなことを斉王に伝えたかったのではないでしょうか。
上田:王が狩場の話を出したので、よしとばかりにこの話を切り出した。
小田:斉王もまた時代の人で、当時の理想の王であった文王と自分を比較する考えが、ちちらついていたのでしょう。文王や堯や舜のように天下の王となりたいが、自分のやっていることは理想にかなっているのだろうか。それを、孟子に聞きたかった。そこで、待ってましたとばかりに孟子が話したのでしょう。
上田:孟子はこの話を練り上げていたのでしょう。それにしても、四十里四方の落とし穴というイメージづくりもうまい。斉王もギクリとさせられたでしょう。
小田:告子章句上九で、あまり「王」に会見できないことを孟子が歎いています。この章の「王」は、文中からは誰なのかは明確ではないですが、古注も朱子も、おそらく斉王のことだと推測しています。その王に孟子が会見するのはまれであり、せっかく会見して良心を目覚めさせようとしても、会見の後で他の者どもがその心を冷やしてしまう、と。だから、短い会見のチャンスに分かり易い話を用意して、王が面白いと思ってくれるような心に残る話をしよう、と作戦したことででしょう。だから、孟子の斉王への話は簡潔で面白く、しかもためになる。だいたい当時の遊説家の弁舌には、とてもじゃないが王に分かりそうもない弁論を展開する者が多くいました。遊説家たちは、遊説が成功したらその記録を残すのですが、こんな込み入った論理、ちょっと会見して王が聞くだけでは分からないだろう、と思うものが多いです。恐らくは事前に家臣に説明して、家臣が王に説明を加えておいたのでしょう。王は聞き流して「善し」といえばよいだけで、遊説家は俺はこう言ったのを王が「善し」とされた、と記す。そんなところだったろう、と私は思います。しかし孟子に関しては、王の心を捉えることのできる話を持ち出していたと、私は評価できます。
上田:今の国会でも、孟子のように分かり易い論議をして欲しいものである。
小田:私はずっと昔学習塾で講師などしていましたが、そこで言われた大事なことは、まず生徒が授業を面白がってくれなければだめだ、ということ。それから、毎時間に言ったことの99は忘れられてもいいから、1だけを生徒の心に残らせることを、心がけろということ。私はとうていこの芸当はできませんでしたが、孟子は王たちを相手に、うまくやっていたのではないでしょうかね。笑わせて乗らせて、そして分かりやすい話をして、わずかな会見の中でほんのちょっとだけでも王の心に残れば、それでよい。それを積み重ねれば、王はきっとよくなる。もっとも、よくなる前に孟子は斉を去ったのですが。
上田:次にゆきますか。
音読。訓読と意味を小田さん。
齊の宣王問ひて曰く、鄰國に交わるに道有りや。孟子對へて曰く、有り。惟(ただ)仁者は能く大を以て小に事(つか)ふことをす。是の故に湯は葛に事へ、文王は昆夷に事ふ。惟智者は能く小を以て大に事ふことをす。故に大王は獯鬻(くんいく)に事へ、句踐は呉に事ふ。大を以て小に事ふる者は、天を樂しむ者なり。小を以て大に事ふる者は、天を畏るる者なり。天を樂しむ者は天下を保つ。天を畏るる者は其の國を保つ。詩に云く、天の威を畏れて、時(ここ)に之を保つと。王の曰はく、大なるかな言ふこと。寡人疾有り。寡人勇を好む。對へて曰く、王請ふ、小勇を好むこと無かれ。夫れ劍を撫して疾(にく)み視て曰く、彼惡んぞ敢へて我に當たらんや。此れ匹夫の勇、一人に敵する者なり。王請ふ、之を大いにせよ。詩に云く、王赫として斯に怒りて、爰に其の旅を整へて、以て徂(ゆ)く莒(もろもろ)を遏(とど)む。以て周の祜を篤ふして、以て天下に對ふと。此れ文王の勇なり。文王一たび怒りて、天下の民を安んず。書に曰く、天、下民を降して、之が君と作(な)し、之が師と作す。惟(こ)れ其の上帝を助くるを曰ふ、之を四方に寵す。罪有り罪無し、惟(た)だ我在り。天下曷(いづく)んぞ敢へて厥の志を越ゆること有らんや。一人天下に衡行(こうこう、気ままに振る舞ふ)するも、武王之を恥づ。此れ武王の勇なり。而して武王も亦一たび怒りて、天下の民を安んず。今王亦一たび怒りて天下の民を安んぜば、民惟(ただ)恐るらくは王の勇を好まざることを。
斉の宣王が質問した、「隣国との交際に道がありますか?」と。孟子が答えた、「あります。ただ仁者だけが上手に大国でありながら、小国に仕えることができます。ゆえに湯王は葛国に仕え、文王は昆夷に仕えました。また、ただ智者だけが上手に小国でありながら大国に仕えることができます。ゆえに大王(古公亶父)は獯鬻に仕え、越王句踐は呉に仕えました。大国でありながら小国に仕える者は、天を楽しむ者です。小国でありながら大国に仕える者は、天を畏れる者です。天を楽しむ者は天下を保ち、天を畏れる者は自国を保ちます。詩にあります。『天の威を畏れて、ここにこれを保つ』と。それが、このことです」と。斉王が言った、「大したものですな、その言葉は。しかし、寡人(それがし)には欠点があり、勇気が好きです。(これはどうですか)?」と。孟子が答えた、「王よ、どうか小勇を好んではなりません。剣をひっさげて、敵をにらんで、『あいつがどうして俺に敵するものか!』とか言う輩は、匹夫の勇です。たった一人しか、相手にできない者です。王よ、どうかもっと大きく敵対してください。詩にこうあります、『王、かっとして怒り、ここに軍団を整え、行く先々のものを制圧する。こうして周の福(さいわい)を篤くして、天下に対峙する』と。これが、文王の勇気です。文王は一たび怒りて、天下の民を安んじました。書経にあります、『天は、下民を地上に降し、その君をおき、人民の師とした。これ(君主)は上帝(天帝)を助け、四方の人民を慈しめさせるためである。どの者に罪有り罪無しかは、君主の御心にある。天下の誰が、君主の志を越えることが出来ようか』と。つまり、一人でも天下に逆らうものがあれば、武王はこれを恥じたのです。これが、武王の勇気です。武王も一たび怒りて、天下の民を安んじました。今、王も一たび怒りて天下の民を安んじるならば、人民はただただ王が勇気を好まないことを恐れることでしょう」と。
小田:朱注は、理気二元論です。匹夫の勇は気で、文王武王の勇は理。人間といわず宇宙の万物は気と理によって貫かれている。気とは物質であり、人間の身体もまた気から成っています。その気のままに怒るのは、匹夫の勇です。大きな勇とは、当然人間だから気がベースにあるのですが、それを宇宙の法則である理に合わせるところから生まれる。そのためには、理性を高めて体内の感情をコントロールしなければならない。つまり、学問を積んで孔子孟子の正道に自らを沿わせなければ大勇への道は開かれない、というセオリーです。
上田:そうですね。「小勇は、血氣の爲す所、大勇は、義理の發する所」と注しています。
小田:朱子は、血気にはやる人を評価しないような読み方をしました。静的で理性的な為政者が、理想でした。しかし、朱子の解釈は、生の人間の感情から来る生き生きした力を殺す。そのことへの批判から、陽明学が現れました。大塩平八郎は、陽明学徒でした。また吉田松陰は朱子の理性的な読み方を基本に保っていましたが、他方で陽明学に引かれるところがありました。朱子学には、血気ある人に物足りなさを感じさせ、それで陽明学にひかれる人が出たわけです。
上田:書経の解釈ですが、これは武王が孟津を渡河する前に述べた言葉とするなら、いくつか問題がある。天が下民を降ろすは意味をなさない。天が武王を下民に降ろし、君とし師としたとなる。上帝を助けるは、殷の紂王を討つこと、それは私心ではなく、上帝の意向を為すためのもの、四方を寵す(武王が平定する)ことに、罪があるも無いも(諸侯ではなく)、我、武王一人に在る。この志に越える者はあるか。この上帝の命を受けた我に逆らうものを放置することは、我の恥じである、いざ我に従って孟津を渡らんか、というアピールの言葉。
小田:「天、下民を降ろす」はいわば決まり文句で、「天地創造よりこのかた、、、」みたいなもので特に意味もない言葉ではないでしょうか。もし上田さんのような解釈とするならば、「天、我を下民に降ろす」と目的語を入れるでしょう。目的語を抜かすことは、普通ないのではないでしょうか。面白い読み方だとは、思います。
上田:孟子はここでは、得意の詩経と書経を持ち出して、小勇と大勇を喩えた。左伝では、「天が民を生み、君を樹て、民を利す」というフレーズがあり、現存の周書、泰誓でも、「天、下民を佑け、之が君と作し、之が師と作す。惟れ其れ克く上帝を相く」とあり、孟子の天降下民が意味不明で、天佑下民としている。
小田:泰誓のオリジナルは、もはや分からなくなっています。以前にも話がありましたが、今の書経のうち今文尚書と呼ばれるテキストは、晋代に偽作されたものです。朱子は、「引く所と今の書の文、小しき異なり」と言っており、この箇所が偽作だとはみなしていません。泰誓篇の偽作者は、きっと孟子のこの引用から逆算してテキストを作ったのでしょう。そのとき「天降下民」では意味が分からないので、「天佑下民」とテキストに分かりやすく化粧をしたのではないでしょうか。私は文献学的知識はないので、はっきりしたことは言えないですが。
上田:最初の詩は周初、国を保つ例、次の詩は、文王が阮を侵す密人を討つ、天下を保つ例。斉王からすれば、昔のこと。
小田:句踐は昔ではなく、この時代から一世紀ほど前の人です。
上田:仁者か智者でなければダメですよとなる。斉王としては、先生やっぱりその話かとなる。
小田:孟子としては、智者・仁者でないと、大国斉といえども天下を取ることはできないと言いたかったのでしょう。
上田:斉王は疾があるとしたが、これは謙遜のつもり。
小田:前の章は内政で、この章は外交です。斉王は外交について、一番意見を聞きたいところだったでしょう。それで、孟子の意見もまた聞きたかった。その孟子の答えは、智者仁者となって穏当賢明な外交を行えというアドバイスでした。しかし斉王はその答えに対して、自分には勇を好む欠点がある、と言いました。つまり、自分はそんな「ぬるい」外交ではなくて、もっとイケイケで隣国を切り取りたい、と思っていたのでしょう。斉はいま国力が充実しているので、攻めの外交がよい、と思っていたのでしょう。後の燕への介入も、だから行ったのです。そんな斉王に対して、孟子は勇はよいのだと答えました。もし勇はだめだ、と言えば斉王はもうそれ以上孟子を相手にしないでしょう。だから、孟子は勇であっても匹夫の勇ではだめで、文王武王の勇でいきなさい、と言った。これは、斉王の興味を繋ぎとめるために言ったのでしょう。
上田:孟子のこの話は、斉王には不十分であった。
小田:斉王は、だったら私は大勇でゆく、と合点したでしょうね。だから燕に介入した。孟子が乗せて、斉王には逆効果となったようです。
上田:朱子は理気で釈して、斉王は理を理解していないとみるが、そういうことではないだろう。
小田:朱子は学者の読み方をしており、実践者の視点とはちょっと違います。朱子にとって孔子・孟子は思想です。政治的な現場での王との駆け引きや妥協があってこうなった、と読んだりはしません。
上田:我々は二つのことを考えて読んできた。斉王は実際どの程度孟子の言を容れ、何を容れなかったのか。燕への介入に孟子がどうかかわったのか、斉王にどういう影響を与えたのか。
小田:そういうことは、朱子の関心外のことです。ところで、この章で前に論語の林放の章で出た「大なるかな」が出て来ました。この「大なるかな」は、明らかに斉王の皮肉が入っていると思います。
上田:そう思う。自分は孟子の言に納得していないというサインとなっている。四十里四方の落とし穴のイメージはインパクトがあったが、小勇、大勇の話は詩、書の引用として得るところがあるが、斉王としては、「はいそうです」と言えるものではない。これは成功したとはいえない。
小田:斉王は納得していないだろうし、孟子も説得できたとは思っていなかったでしょう。前の公孫丑章句では、孟子は仮病を使って斉王との会見を断り、翌日に堂々と外出して、斉王に私はあんたの僕ではないぞ、という大見得を切りました。孟子はある場合には王を持ち上げ、別の場合には王に厳しい姿勢を見せたりしました。孟子は、積み重ねが大事と思っていたことでしょう。分かり易い話であっても、王がわかってくれるとは限らない。ただそっぽをむかれると、全ておしまいになる。この章でも、斉王はたぶん納得しなかったから説得としては失敗だったでしょうが、孟子はその中でも斉王に勇はいけないと言わず、何とかご機嫌を取りました。面白い話をして好印象を与え、その中でポイントが分かってくれればよい。それが積み重なると必ず変わると期待していたのでしょうね。
2012年7月14日(土)孟子梁恵王章句下
本日も、小田さん、上田さんの二人。本日分を音読。訓読と意味を小田さんお願いします。
齊の宣王、孟子を雪宮に見る。王の曰く、賢者も亦此の樂しみ有りや。孟子對へて曰く、有り。人得ざるときは、則ち其の上(かみ)を非とす。得ずして其の上(かみ)を非とする者は、非なり。民の上と爲りて民と樂しみを同じふせざる者は、亦非なり。民の樂しみを樂しむ者は、民も亦其の樂しみを樂しむ。民の憂ひを憂ふ者は、民も亦其の憂ひを憂ふ。樂しむに天下を以てし、憂ふに天下を以てして、然して王たらざる者は、未だ之れ有らず。昔者(むかし)齊の景公、晏子に問ひて曰く、吾、轉附(てんぷ)・朝儛(ちょうぶ)を觀て、海に遵(したが)ひて南し、琅邪に放(いた)らんと欲す。吾、何を脩めて以て先王の觀(あそび)に比す可き。晏子對へて曰く、善いかな問ふこと。天子の諸侯に適くを巡狩と曰ふ。巡狩は守る所を巡るなり。諸侯の天子に朝するを述職と曰ふ。述職は職とする所を述ぶるなり。事に非ざる者無し。春は耕すを省(み)て足らざるを補ひ、秋は斂(おさ)むるを省て給(た)らざるを助く。夏の諺に曰く、吾が王遊ばずんば、吾何を以てか休(いこ)はん。吾が王豫(たの)しまずんば、吾何を以てか助からん。一遊一豫、諸侯の度爲(た)り。今は然らず。師(もろもろ)行きて糧食す。飢たる者食らはず、勞する者息(いこ)はず。睊睊(けんけん)として胥(あひ)讒る。民乃ち慝(うらみ)を作(な)す。命に方(さか)ひ民を虐ぐ。飮食すること流るるが若し。流連荒亡は、諸侯の憂爲り。流れを從(をふ)て下りて反ることを忘る、之を流と謂ふ。流れを從て上りて反ることを忘る、之を連と謂ふ。獸を從て厭くこと無き、之を荒と謂ふ。酒を樂しみて厭くこと無き、之を亡と謂う。先王流連の樂しみ、荒亡の行無し。惟(ただ)君の行ふ所なり。景公説びて、大いに國に戒(つ)げ、出でて郊に舍(ほどこ)し、是に於て始めて興發(こうはつ)し足らざるを補ふ。大師を召して曰く、我が爲に君臣相説ぶ樂を作れ。蓋し徵招・角招是れなり。其の詩に曰く、君を畜(とど)むるは何ぞ尤(とが)めん。君を畜むるは、君を好(よみ)するなり。
齊の宣王は、孟子を雪宮で謁見した。王が言った、「賢者もまた、この楽しみがあるのでしょうか?」と。孟子が答えた、「あります。およそ人たるもの、得ることができなければ上に立つ者をそしるものです。だが自分が得られないからといって上に立つ者をそしるのは、よくないことです。しかし人民の上に立ちながら人民と楽しみを同じくしない者は、これもまたよくないことです。人民の楽しみを楽しむ者は、人民もまたその楽しみを楽しむものです。人民の憂いを憂う者は、人民もまたその憂いを憂うものです。天下のことを楽しみ、天下のことを憂うならば、このようにして天下の王とならなかった者はこれまでかつてありません。むかし、齊の景公が晏子に質問しました、『私は、轉附・朝儛の山を観光して海沿いに南下し、琅邪に行こうと思う。私は、どんなことをすればいにしえの先王たちのあの旅行に匹敵する功業を成すことができるだろうか?』と。晏子が答えました、『それはとてもよい質問です。そもそも天子が諸侯を訪問することを、《巡狩》といいます。《巡狩》とは、諸侯たちが守護している地域を巡回することです。また諸侯が天子に謁見することを《述職》と言います。《述職》とは、諸侯が己の職務を報告することです。いずれも、国の事業でない旅行はありませんでした。春は耕作を視察して不足があれば補い、秋は収穫を視察して不足があれば助けました。夏の諺に、こういいます、《わが王が巡遊しなければ、われはどうして憩うことができようか。わが王が楽しまなければ、われはどうして助けてもらえようか》と。遊び・喜びのいちいちが、諸侯の模範となったのです。ところが今の時代は、そうでありません。家臣をぞろぞろ連れ合って飲み食いし、その横で飢えた者は食うこともできず、働く者は休むこともできません。人民は王から眼をそむけて、たがいにそしるでしょう。こんなふうに人民は怨み、家臣は王命に逆らって人民を虐げます。その飮食することは、あたかも水が流れるがごとく尽きません。流連荒亡は、諸侯の憂いです。流れを追い下って帰ることを忘れる、これが《流》です。流れを遡って帰ることを忘れる、これが《連》です。野獣を追い狩って飽きることがない、これが《荒》です。酒を楽しんで飽きることがない、これが《亡》です。いにしえの先王は、流連の楽しみも荒亡の行いもありませんでした。今どうなさるかは、王が選ばれることです』と。景公はおおいに喜び、国中にふれを出し、郊に出て喜捨を行い、こうして初めて倉を開き民の不足を補いました。そして音楽の長官を召して、こう言いました、『私のために君臣が相喜ぶ音楽を作りなさい』と。つまり、これが徵招・角招です。その歌詞にこうあります、『君主のお諌めして止めれば、尤(とが)がない』と。君主をお諌めして止める者は、君主を愛する者なのです」と。
上田:畜の読みですが、成田君のテキストはxùとなっていますが、朱子は敕chù六liùの反chùとしています。xùは飼う、養うの義でchùは蓄える、朱子は畜止、とどめるとしており、成田君に聞いてみる必要が有ります。それから、意味がとりにくいところがいくつかあります。まず、「事に非ざる者無し」とはどういうことですか。
小田:天子の巡狩、諸侯の述職はすべて国事つまり国の事業であった、ということでよいのでは?
上田:小林先生はそうされていますが、朱子はどうですか。
小田:「皆、事無くして空しく行く者有ること無し」と書いています。やっぱりそうではないですか。
上田:どういう意味ですか。
小田:つまり、かつての時代、君主や諸侯は無意味に旅行をしていたわけではなくて、国家事業のプログラムの一環として人民の福祉に寄与する意義があったということです。しかし今の時代に君主が家臣と旅行をすることは、人民の利益と相反する私的な浪費でしかなく、人民の患いとなっている。そういうことでしょう。
上田:豫が楽しむと解釈されていますが、何故豫が楽しむことになりますか。
小田:旅行というのは、慣習的に「遊」の字を使うでしょう。今でも「外遊」という言葉があります。首相は国の外交のために外国を訪問するのであって、それは国事として旅行するわけです。しかし、「外遊」と言います。かつての時代においては、旅行は国事でありながら一種の君主の娯楽という捉え方もありました。だから、たとえ国事で行っていたとしても、「遊」「豫」の字を用いて表現するのは、原義に遡ればおかしなことではありません。
上田:豫とは「与える」ことではありませんか?
小田:豫を「与える」と読むのは、この章の意義から外れていると思います。君主の楽しみが、人民にも実利を与える。君主は、そのようにしなければならない。これが、本章の言いたいことです。それゆえに、「豫」は楽しみと読むべきです。「与える」では、この章の意義をぼかしてしまうことになります。孟子は、宣王に楽しいことをするなとは、言うことができません。そこで、人民の楽しみにつながるような楽しみでなければいけませんよ、ということを言いたいのです。もしここで孟子が王に楽しんではならない、自分が苦労して人民に与えなければならない、などと説教すれば、王は聞くことなどないでしょう。
上田:「流連荒亡は、諸侯の憂爲り」というのは誰が流連荒亡するのですか?
小田:景公でしょう。
上田:その場合、「諸侯」とは誰ですか。
小田:「流連荒亡は、諸侯の憂爲り」は決まり文句みたいなもので、晏子がここに引用したのでしょう。一般論として、流連荒亡をするのは悪い君主であり、君主の悪行は国の乱れのもとであり、君主に仕える諸侯の憂いである。もとは夏の桀王とか殷の紂王とか周の幽王・厲王とか、そのような悪王の浪費が諸侯の憂いであった、という言葉だったのでしょう。ひるがえって、晏子が引用したときには、流連荒亡をしようとしているのは景公であり、憂うのは斉の家臣たちでしょう。
上田:「流れを從て下りて反ることを忘る、之を流と謂ふ。流れを從て上りて反ることを忘る、之を連と謂ふ」とはどういうことですか。
小田:川をずっと下ったり、逆にずっと上ったりして遊び、帰らないことでしょう。
上田:一般的なことですか。
小田:獣を追うことや、飲酒の楽しみと続けて、君主の浪費ということです。
上田:このところは晏子春秋にもありますが、内容が違っています。「轉附・朝儛を觀て、海に遵ひて南し、琅邪に放らんと欲す。」ですから、晏子春秋では轉附・朝儛という山に登ること、海を南下する、あるいは川を下る、それに我を忘れてしまうことが流連という展開になっています。
小田:しかし孟子の引用が文の大意まで変えているわけではありません。このくらいの改変は、引用するときにリズムをつけて化粧したぐらいの理解でよいのではないでしょうか?
上田:「君を畜むるは何ぞ尤めん。」の解釈が分かれますが。
小田:朱子は、君主を諌めて止めれば尤(とが)が無くなる、と解釈していますね。他方小林先生は、畜を"よろこぶ"としておられます。朱子注は、自説に引きずられた解釈といえるでしょうか。
上田:成田君によれば、畜には、chùチク(たくはふ)、xùキク(やしなふ、かふ)、xùキウ(家畜)の三つの読み方がある。朱熹はここではチクと読ませ、畜止(とどめる)としていた。尤には咎(とがめる)、と最もっともよい、もっとも)等相反するような意味も含む、色々な意味にとれる字が用いられている。朱熹は尤を過とした。
小田:朱子の「過」は、過失のことでしょう。
上田:音読テキストではxùとなっていた。この読みならば、君を「養う、育てる」となる。
小田:しかし、君主を「養う、育てる」という言い方が、ありえるでしょうか?それは、ちょっと私には納得しかねます。それならば朱子のように「止める」と読むか、いっそ小林先生のように「よろこぶ」と解釈するほうがよい。小林先生の解釈に従うならば、「王の喜びには、過失がない。(なぜならば王の喜びは人民の福祉に合致しているからだ)」という意味になるでしょう。
上田:xùと読ませている意味が分からない。晏子が景公を留めたことを景公が喜んで詩を作らせたという脈絡にある。それが徵招・角招といい、その詩の一部を引用している。この前後が分かれば、もう少し意味がはっきりするのだが。晏子が景公の遊行をとどめたのは、咎めたものではない、それは君主を思ってのこと、だから、孟子が斉王に同じようなことを言うのは、斉王を思ってのこと、と自己弁護にも使ったと思っている。それと「事に非ざる者無し」の事は、大事小の"つかえる"ではありませんか。
小田:この箇所を君主が民に事(つかえる)、などと読めるでしょうか?前の文の内容から、とつぜん飛躍しすぎだと思います。私は、この「事」は国事と解して十分だと思います。
上田:「大を以て小に事ふる者は、天を樂しむ者なり」というのは文王のことであった。天子が巡狩して足らざる補うとか不給を助けるというのは、天子が自らの政治の実態を反省しそれを修正することであり、大事小の延長線上にあるように思う。
小田:君主が民に事(つか)えるという理念がありうることは、否定しません。しかし、この章は君主の楽しみと人民の福祉との関係について述べた章です。私は上田さんの読みは、この章の趣旨から外れていると思います。
上田:さっきおっしゃったように、孟子は斉王の楽しみを否定せず、共に楽しむという所に引っ張り込む。これは孔子の失敗を考えた上での孟子のチャレンジだと思う。
小田:孟子は、この一連の斉王との対話の中で、楽しみはよいが人民と楽しめ、と繰り返し言います。しかし、孟子は特に後半の各章で、仁義を楽しめば物欲は必要ない、それこそが人間の目標であり、いにしえの舜とか文王とかは仁義を楽しんで物欲を超越したのだ、と力説します。孟子は、弟子に対してはきっと物欲などにかまけるな、ただひたすら仁義を磨け、などと教えたことでしょう。しかし、梁恵王とか斉王とかの君主には、そうは言いませんでした。朱子は、孟子を前半の章と後半の章とで、首尾一貫して同じことを言っているのだ、と捉えようとします。だから、孟子は常に人欲を断って天理に従うことを言おうとしている、ところが斉王はそれが理解できず、人欲を断てず天理に従えない、だからだめな君主なのだ、と解釈します。孟子が斉王に本当に言いたかったことは、後半の章のことである。それを遠まわしに、斉王に言ったまでであった。斉王は、本当は孟子の説に従って人欲を捨てて天理に従わなければいけなかった。そうでなければ、文王のような天下の王にはなれない。朱子はこう解釈して、斉王を愚かな君主であるとしてしまいます。だが、孟子が斉王の前で語ったことは、果たして後半の章の内容と、一致しているのであろうか。私は、疑問を持ちます。孟子の持論は、おそらく後半の章のようなものであったでしょう。極めて禁欲的な人間の理想を、掲げたものです。おそらく、孟子の主張がそのようなものであるということは、当時の宮廷人たちは周知していたことなのでしょう。そして斉王に対しても、「孟子はあの理想論を、きっと王にも吹き込もうとするでしょう。しかし、孟子の理想は窮屈すぎて現実の人間離れしており、現代の政治家の現実とかけ離れています。あまり信じないほうがよいですよ」などと進言する者があったことでしょう。斉王もまた、孟子の話の面白さは喜んでも、彼の理想にはちょっとついていけない、と内心距離を置いていたのでは?だから、私には疾がある、勇を好むのだ、金を好むのだ、色を好むのだ、こんなふうに私はあなたの理想に従う人間ではないですよ、こんな私をどのようになさるおつもりですか?と半ば試すように聞いたのではないでしょうかね。その問いに対して、孟子は王の欲を否定せずに、大勇であれとか人民と共にすればいいと言いました。それは朱子の解釈では、孟子の理想的人間像を遠まわしに言っただけで、斉王は孟子の真意を悟り人欲を絶って天理に従わなければいけなかった。しかし従わなかったので斉王は愚かであった、ということになってしまいます。しかし、孟子はじつは、王に対しては人間の理想論からは離れて、もっと妥協的な話をして心を掴もうとしたのではないでしょうか。いわば二枚舌をふるって、王との対話と常の持論とを分けて用いたのではないでしょうかね。だから、王たちとの対話と後半の章の議論とは、必ずしも首尾一貫していないのかもしれない、と私は思います。
上田:人欲と天理ということで朱子が全体に首尾一貫性を持たせたということですが、孟子らしさがそれでは浮かび上がって来ない。先週、孟子は斉王と合う機会が少ない、せっかく上がった熱気がさめてしまうという話があり、孟子は相当話を練って王と会見し、その話しぶりは実に見事というほかない。孔子にはない能力、ただ長い目でみれば孔子のすごさは別にあるが。
小田:孟子は、他の諸子百家の問答には見られないおもしろさがあると思います。さぞかし王と会見する数少ないチャンスに、面白いたとえ話を毎回出すよう心がけたのでしょう。王が、すべてを理解してくれなくてもよい。毎回何かを王の心に残して、それを積み上げてゆく戦略だったのでしょう。だから王の人欲を否定することなくして、その中でより善導しようとした。斉は大国で、孟子の主張を受け入れない家臣が大勢いたことでしょう。孟子はその中で、弟子に語るような厳しい禁欲論にこだわることなく、王の興味をひきながら少しずつ自分の信者にしていこう、と戦略していたのではないでしょうか。しかし、斉王は信者とまではいかなったようです。小国の滕の文公は、孟子にすっかり感化されて信者になりましたが。
上田:全部を通してみて、二枚舌となるが、前篇では梁の恵王とかこの宣王の心を捉えることが先決で、すごいくどきのテクニックを練っていた。今の、国会議員もそれを勉強すればいい。そういう時の話と、いつもおっしゃる燕への介入、それ以降とは立場がちがい、最後はもっぱら上手くゆかなかった言い訳となる。それを人欲と天理ではおさまりきらない。
小田:朱子の読み方は、あくまで人間が個人として君子に完成するためにはどうするべきか?という問いをめぐって孟子を解釈します。だから、孟子の王への発言もまた、人欲を抑えて天理に従う君子への道を言っているのだ、と解釈することになりました。しかし、その読み方からでは、孟子の王との対話の凄みはこぼれ落ちてしまうのではないか。後の章で、斉王に対して紂王を王じゃなくて匹夫とし、これを討つのは王ではなくただの悪人を成敗したまでだ、などと平気で言ってのけた。こんなことは、朱子はおろか歴代中国の思想家の誰ひとりとして、君主の前でやってのけたことはありません。いや、やった人はいましたが、命はありません。朱子は、これは孟子の思想の表明として言ったのだ、とさも当たり前のように解釈しますが、そんなことよりも、孟子がこんなことを斉王にあえて言ってのけたという驚異、しかも討ち首にならなかったというもっと驚異的な内容を読みとったほうがよい。斉王が自らの過激な説を聞く場を、対話の中で積み上げたからできたのでしょう。斉王に気に入られていたはずです。だから燕介入の失敗のあとも、先生の意見をきかなかったからこうなって申し訳ない、と反省していました。
上田:そこのすごさを評価しないのは片手落ち。ただ、宣王が信者ではなかったというとおり、疾があるといいながら不同意であったのでしょう。それと孟子のなかにでてくる詩、書のあつかいが気になる。先程のはなしでも孟子流にアレンジしているように思える。
小田:それは断章取義ですね。詩の全体から一部だけ取り出して、そのフレーズに話の流れに沿った別の解釈をほどこす、というやつです。日本の古典でも、よく行われることです。
本日は宵々々山、土曜日でもあり、人出の多いことでしょう。例年では祇園祭前に梅雨明けとなりますが、本年は九州でとんでもない豪雨、600mmとか800mm、川の氾濫。近年の気候の変動は後世からどう見られることになるのでしょう。
2012年7月21日(土)論語八佾篇
本日は、早川君、小田さん、上田さんの三人でスタート。成田君が途中から合流。早川君は香港での学会の発表が終え、当地で多くの学友と交流。日本人が七弦琴の話をするのは、米国人が尺八の話をするようなものらしい。中国では伝説の王、庖羲(伏羲)、女媧、神農が五弦琴を作成し、黄帝が作曲をしたというような話があり、文王の時に六弦となり武王の時に七弦、孔子は七弦琴を奏し、作曲もされたそうである。庖羲や女媧は人面蛇身といいますから、ギリシア神話の半獣半人、パンみたいなもので、「神明の徳に通じ、万物の情を類す」ことがはじまりで、神と人と万物の間をとりもつもの。これが如何にして日本に伝わり、受容されたか、結構注目をされたとのこと。
八佾篇を早川君のリードで音読。訓読と意味を小田さん。
成田君が合流、奥様、無事に、女児を出産されたとのこと。写真をみると、ふっくらと円満の相。お腹の中でよく動いていた子、元気なお子さんでなによりです。おめでとうございます。
子の曰はく、夏の禮吾能く之を言へども、杞、徴(しるし)するに足らず。殷の禮吾能く之を言へども、宋、徴するに足らず。文獻足らざるが故なり。足らば則ち吾能く之を徴せん。
杞は夏の後。宋は殷の後。徴は證なり。文は典籍なり。獻は賢なり。言ふこころは、二代の禮、我能く之を言ふ。而るに二國は取りて以て證と爲すに足りず。其の文獻足らざるを以て故なり。文獻若し足らば、則ち我能く之を取りて以て吾が言を證とせん。
孔子がおっしゃった、「夏王朝の礼については、私はこれを説明することができるが、その末裔の杞国の制度、文化はそれを証拠とするに足らない。殷王朝の礼についても、私はこれを説明することができるが、その末裔の宋国の制度、文化はそれを証拠とするに足らない。典籍やそれを伝える賢人が足りていないからである。もし足りていれば、これを証拠とすることができるはずだ」と。
杞国は夏王朝の後継。宋国は殷王朝の後継。徴は証拠のことであり、文は典籍のことであり、獻は賢人のことである。つまり、夏、殷の二代の礼について、孔子は説明することができる。しかし、杞・宋の二国の制度や文化はこれを取り上げて証拠とするには不足している。その典籍や賢人が不足しているからである。典籍や賢人がもし足りるなら、孔子はそれを取り上げて自分の説の証拠とすることができるのであるが、と言ったのだ。
小田:朱子の注は、ただの繰り返しです。
早川:一人称で同じことを繰り返しているだけですね。
小田:この章の言っていることなのですが、清代の康有為などは、孔子は「述べて作らず」と自称したのであるが実際には新しい制度を創建した創作者であった、と主張しました。孔子は、新しい制度を作った。しかし孔子の作では、当時の人々が信用しない。だから、孔子はこれらの創作を昔の時代の復古である、と言っただけにすぎなかった。康有為は、こんなことを言っていました。
早川:「孔子教」ですね。次の章でいう「禘」は周の礼制ですが、孔子の代にどこまで完全に伝わっていたかは怪しい。夏や殷の礼については、孔子の代に伝わっていたかどうか。周の礼については、魯に伝わっていたのですが。
小田:次の章以降の「禘」の議論について、朱子と徂徠では見解が大きく違っていますが、両者ともにすでに「禘」の礼が十分伝わっていなかったという視点に立っています。
早川:礼記では夏、殷、周の礼が並列されていますが、内容がかなり違う。孔子は当時の各地の礼制を調べて、整合性が取れない、矛盾している内容に当ったとき、それを周の礼制よりもっと古い代の礼の残存ではないか、と考えて夏・殷の礼に括った可能性があります。土地間の文化の相違を、時代の相違に解釈したのかもしれません。
小田:孔子の時代には、たぶん原『三礼』とか原『書経』のような伝承資料は、あったのでしょう。それを当時の人々は、単なる過去からの伝承として体系的に整理するところがなかった。孔子の業績とは、これらを整理して再構成したところにあるならば、たとえ本人はテキストを追加しなかったとしても、その作業はじっさいには創作というべきものだったのではないでしょうか。これは、朱子の注を読んでいると、そう思うのです。朱子は、周張二程子や謝氏等々の先人の説を引用して再構成したわけで、彼は自分の説は先人の研究の助けを借りて孔子・孟子の説を現代に忠実に再現しただけだ、と固く信じていたことでしょう。しかし後世から見れば、その引用した再構成が、はっきりと朱子のオリジナルな思想体系を作り上げている。主観的には「述べて作らず」と信じていたけれど、その事業を客観的に見ると明らかにオリジナルな作業であった。その朱子の作業に、孔子もまたなぞらえることができるのではないか、と私は思うのです。昔の伝承をただ述べて作らなかったが、だが再構成をしてその背後に体系的な文化と倫理感を見出しているわけで、それは孔子の生きた時代の要請に合ったものであったはずです。だから全くの創作ではないが、再構成自体が創造的行為というべきでないででしょうか。この章の言わんとしていることは、もはや孔子の時代には夏、殷時代の文化は分からなくなっていたので、孔子はそれを再構成したということでしょう。だがその再構成した結果のいにしえの時代は、意図せずに自分の理想とする社会の姿に整形されていた。それが、孔子が時代に先んじていたところではなかったのでしょうか。社会と人間があるべき理想や倫理感を、いにしえの時代を再構成する作業を通じて、初めて取り出してみせたという。
早川:朱熹が古典を読んだとき、それが朱子の哲学となったということですかね。
小田:古代ユダヤ教の話をしたいと思います。伝統的なユダヤ教・キリスト教の解釈では、いわゆる「モーゼ五書(トーラー)」創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記は、シナイ山で神がモーゼに下した契約をそのまま後世に伝えたものである、というものです。現代でも、両教の保守的な信者は頑なにそう信じています。ところが、19世紀以降のヨーロッパでは、リベラル派と呼ばれる聖書の批判的研究が発達しました。リベラル派たちの批判的研究によれば、「モーゼ五書」を初めとする旧約聖書の諸文献が今伝わるような姿となったのは、せいぜいバビロン捕囚(BC586~539)以降の時代である、というのです。孔子(BC557~479)の少し前の時代です。イスラエルの歴史を見れば、紀元前2000年紀のモーゼから下って、ダビデ朝がダビデ・ソロモンの両王の下で全盛期を見ました。しかしソロモン王の後はイスラエル王国とユダ王国に分裂して、衰退していきます。北のイスラエル王国はアッシリアに滅ぼされ、南のユダ王国はアッシリアの圧迫を受けたが辛うじて生き残るも、アッシリアの後に現れたバビロニアに滅ぼされます。バビロン捕囚は、そのときの出来事です。バビロニアはペルシャに滅ぼされて、そこでようやく捕囚の人々はパレスチナに帰ることが許されました。このバビロン捕囚は、民族の危機の時代でした。一神教のユダヤ教は、この時期になって明確に成立したのです。一神教の契約を説いた「モーゼ五書」もまた、この時代に固まったと思われます。アッシリア時代以降、ユダヤ人は民族の危機に際していました。滅ぼされた北のイスラエル王国の民は、周辺諸民族と混合してしまい、民族のアイデンティティを失ってしまいました。彼らはキリストの時代にはサマリア人と呼ばれ、たぶん現代のパレスチナ人の祖先です。アッシリア時代のユダヤ人はバアルとかアシラとかの外国産の農業神を各地で祀っていて、多神教がはびこっていました。イスラエル王国は、アッシリアに滅ぼされて文化的に滅んでしまった。このままでは、ユダヤ人はすべて周辺の文化に解消されてしまう。そんな民族の危機の時代に、民族の伝統を取り戻す運動が起こったのです。それは民族古来の一神教に回帰し、外国産の多神教を根絶する運動でした。この運動の過程で、ただの伝承であった「モーゼ五書」も再発見されて、民族の文化と倫理の根幹に置かれました。バビロン捕囚が起こったとき、国がなくても信仰を保っていれば世界のどこにいてもユダヤ人である、というアイデンティティーがかえって確立されました。このように旧約聖書が現代に続く一神教の聖典となり、ユダヤ教が明確に成立したのは、信じられていることとは異なってかなり新しいはずです。たしかに古い伝承はあったのでしょうが、それを再構成して文化と倫理の根幹に置かれたのは、ずっと後世の危機の時代になってからでした。
早川:古典中国においてはどうなりますか?
小田:私は、旧約聖書にあたるのが五経だと思います。両者とも伝統的に、昔からの伝承そのままである、と堅く信じられてきました。だが、実際には伝承は危機の時代になって倫理観をもって再構成されたものであり、危機の時代に伝統を振り返った作業の成果だったのではないでしょうか。
早川:そうなると、ユダヤ教の成立はキリストの時代からさほど遠くない。
小田:そうですね。明確な倫理的教えの歴史は、意外と新しい。孔子は春秋時代という先の見えない危機の時代に、君子の立つべき根拠として中華の文化と礼楽を見出したのだと私は思います。これは飛躍ですが、もし孔子がいなかったら、中華は一つの文化として成立しなかったかもしれない。楚は楚、越は越、秦は秦で、それぞれに分かれて別の文化のまま発展したとしても、おかしくはなかった。地方的な相違を越えた、統一的な文化と倫理を見出したのは、孔子でした。その作業が、中華文化としての統一に寄与したのではないでしょうか。
上田:夏の礼、殷の礼を説明できるとするが、どう説明していたのか。朱熹は徴を證とし、証明できるとしているが、孔子は証明がしたかったのか。今の学問では証明できれば評価を得るが、孔子が証明できれば事足れりとしたとは思えない。
早川:証拠があれば、証明できる。しかし「証拠がないので私は証明できない」という朱子の読み方を取れば、夏殷の礼は孔子が作ったということになりかねません。古注では、徴を「成」と解します。つまり、杞や宋には夏殷の礼が伝わっているが、それを「成」つまりうまく成り立たせることができない。杞や宋の君主は、それをうまく運営できていない。両国には文献と伝承者が不足しているからだ。だが、私の手元には十分足りている。だから私ならば、夏殷の礼を成り立たせてうまく運営できる。こんなところが、古注の解釈です。
上田:この後に禘の礼がでてくる。夏の禘、殷の禘、周の禘、魯の禘に関して孔子がどう思っていたかが問題になるのであるが、それは次条でみるとして、夏、殷の前に堯や舜の世があり、そこには堯や舜の礼、これは夏、殷とは違って政権をその任に相応しい人物に禅譲するという風なものがあるが、夏や殷の礼とはどう関係するのかが分からない。
早川:堯や舜については、孔子の時代にはまだ多くのことが言及されません。なので、堯舜の礼についても、多く語られません。せいぜい論語では堯曰篇の第一章に展開される「中」の論議程度です。堯舜の礼という言い方もありません。孔子は当時の色々な風俗や生活習慣を比較して、周の礼として括りきれないものについてこれは夏の礼、これは殷の礼だと時代を区分して振り分けたのかもしれません。これは、後漢の鄭玄がやったことです。鄭玄は三礼つまり「礼記」、「儀礼」、「周礼」の三つテキストの間の整合性をつけようと試みたが、さすがの彼をもってしてもうまくゆかなかった。そこで、整合性の取れない箇所について、先代の礼の残存であると整理しました。
小田:杞も宋も、自称では夏殷の後継国家として孔子の代に存続していました。孔子は、実証のために杞や宋の文化を参照ようと試みたのではないでしょうか。孔子は杞や宋に行ったのかもしれないし、あるいは両国の伝承を知る人に会見したのかもしれない。孔子ならば、そのくらいやっただろうと思うのですが。しかし、よく分からなかったというのがこの章の言葉の背景なのでは。
早川:「之杞」と読んで、これを「杞に之(ゆ)きて」と読む読み方をする説もあります。こう読むと、小田さんの言うように孔子は両国に行ったわけですが、ただこの読み方には無理がありますね。
小田:当世の後継国家には、夏礼や殷礼のなごりがなくなっている。だから私の研究の方が正しいという考えが、孔子にあったのではないでしょうか。たとえるならば、現代の鹿児島や山口の人に会ってみたが、明治維新の薩摩や長州の思想や行動の名残を知ることができない。しかし、明治維新の研究をすれば、かつての薩摩人や長州人の姿を再構成できる、というようなものでしょうか。
成田:遅れて今来たのですが、小田さんは徴を「しるし」と読んだわけですか。
小田:いまは朱子注に従って、そう読みました。
成田:上田さんが、証明したところでなんぼのものか、と言われたのは、的を得ていると思います。朱子の時代には礼の実態は失われ実践の対象ではなく、説明するしかなかった。だから、昔はこうであったと証明すればそれで終わった。孔子にあっては、だが正しいやり方で実践されねばならなかった。
小田:そうすると、むしろ成田さんは古注を採るわけですね。両国もいちおうは礼を行っているが、不完全であると。しかし、そうなると何の基準で完全と言えるのか、という問題が出てくるのではないでしょうか。敬虔さか、誠実さか、あるいは美的感覚か。それは、孔子の時代に新しく自覚された倫理観なのかもしれません。
成田:「成」は完成する、立派にするということで、欠けているところが無いようにするということです。杞や宋は夏や殷の礼を引き継いでいるが、欠けているところがある。周の礼であれば当世の礼なので、欠けていても補って実践できる。だが杞や宋の礼は過去の礼であって、欠けているとこれを補うことができず、両国では完成というところまで復元できない。孔子は、だから立派に欠けているところが無いようにすることが、私ならばできると言ったのではないでしょうか。
さてさて、子どもの写真を配る成田君も父親となられました。夫となって半人前、父となって一人前と申します。鄭さんをはるかに越えてしまいました。これからは子を育てるという観点からも論語に向き合っていただくことになります。孔子は弟子を育てることにおいては、異能を発揮されました。
2012年7月28日(土)論語八佾篇
本日は小田さん、上田さん二人。まずは音読をして、訓読と意味を小田さん。
子の曰はく、禘既に灌してより往(のち)は、吾之を觀るを欲せず。
禘は大計の反。○趙伯循曰く、禘は王者の大祭なり。王者禘に始祖の廟を立て、又始祖、自ら出る所の帝を推し、之を始祖の廟に祀りて、始祖を以て之に配すなり。成王、周公の大勲勞有るを以て、魯に重祭を賜ふ。故に周公の廟に禘することを得。文王を以て出づる所の帝と爲して、周公、之に配す。然れども禮に非ず。灌は、方(まさ)に祭る始め、鬱鬯(うっちょう)の酒を用ゐ、地に灌して以て神を降ろす。魯の君臣、此の時に當り、誠意未だ散せず、猶觀る可き有るがごとし。此より以後、則ち浸(やうや)く以て懈怠して、觀るに足る無し。蓋し魯の祭禮に非ず、孔子本より觀るを欲せず。此に至りて禮を失するの中、又禮を失す。故に此の歎を發す。○謝氏が曰く、夫子嘗て曰はく、我夏道を觀んと欲す。是の故に杞に之(ゆ)く、而(しか)れども徴するに足らず。我商の道を觀んと欲す。是の故に宋に之く、而ども徴するに足らず。又曰はく、我周道を觀るに、幽厲之を傷(やぶ)る。吾魯を舍て何くにか適かん。魯の郊?は禮に非ず。周公其れ衰へたり。之を杞・宋に考へるに已に彼の如く、之を當今に考へるに此の如し。孔子の深く歎ずる所以なり。
孔子がおっしゃった、「禘の祭りは、私は灌の儀式が終わってからは見たくない」と。
禘は大と計の反切。○趙伯循が言った、「禘祭は王者の大祭である。王者が始祖の廟を立て、またその始祖の出自の帝を推し挙げ、その帝を始祖の廟に祀り、始祖をその横に配する。周の成王は、魯の始祖である周公の大きな功績を考慮して、魯に重祭を賜った。故に周公の廟においても禘をすることができた。文王を始祖の帝の位置に置き、周公をその脇に配した。しかしながら、これは本来の礼に反する。灌とは、その祭りの最初に鬱鬯酒を使い、大地に灌(そそ)いで神を降ろす儀式である。魯の君臣は、灌の時においては、誠実の心がまだ失われておらず、まだ見るべきものがあったようだ。しかし灌より以降は、だんだんだらけて見るべきものがなかった。つまり、魯の正しい祭礼ではないので、孔子はもとより見ることを欲していなかった。さらにここに至り、そもそも礼を失しているなかで、又礼を失していた。だからこの歎きを発された」と。○謝氏が言った、「孔子はかつてこう言われた。『私は夏の礼道を見ようとして杞国に之(い)った(先週「之杞」を「杞に之(ゆ)く」と読む説がある、と議論したが、ここで謝氏はこの読みを採用しているのである)。しかし、証拠とするに足らなかった。私は商(殷)の礼道を見ようとして宋に之ったが、証拠とするに足らなかった』と。またこうも言われた。『私は周の礼道を見ようとしたが、末期の暴君である幽王・厲王がその道を損なってしまっていた。だから私は魯を捨ててどこに行くことができるだろうか。だが魯の郊禘は、礼にはずれていた。周公も衰えてしまったものだ』と。礼の道を杞国・宋国で考えると、すでに省みる証拠が足りなかった。同様に、魯の今を考えるとかくの如き(周公も衰えた)ものであった。孔子が深く歎ぜられたわけである」と。
小田:朱子は趙伯循と謝氏を引用して、魯の禘は周公の功績を称えて魯に許されたもので、本来の禘の儀式ではない。だが灌の儀式までは魯の君臣はまじめにやっていたが、それ以降はだらけてしまっていたと言っています。魯の禘は本質的に礼にはずれており、孔子はもともと見たくない。さらに灌以降は儀式がだらけていて、ますます見たくないという解釈です。
上田:始祖とは誰で帝とは誰ですか。
小田:周本来の始祖は、文王でしょう。帝は后稷でしょう。魯では始祖を周公とし、帝を文王としている。そこが周の本来の形式からはずれているわけです。
上田:古注はどうなっていますか。
小田:貝塚先生は、位牌の並べ方が礼に反していると解釈されています。魯は四代閔公・五代僖公・六代文公と続きますが、閔公は正妻の子だが年少であり、僖公は庶子だが年長であった。その僖公の子が文公で、位牌は僖公・閔公・文公の順序で配置されていて、祭りの順序をかえていた。それを孔子は見るにしのびず、だが臣下の身分でこの乱れを正すことは出来ないので見て見ぬふりをしていた、という解釈です。これは、古注に従った解釈です。
上田:朱子は古注にあきたらず、魯の禘祭そのものが礼に反すると解釈した。
小田:荻生徂徠は、「孔子の禘に於ける、其の大なる者を見んと欲して、其の小なる者を見ることを欲せず」と言っており、孔子は祭において見るべきものを見れば十分であり、見る必要のないものは見ないと言ったのだ、と解釈しています。灌の儀式について徂徠は『礼記』祭統篇を引用し、「夫れ祭に三重有り、献の属、裸(灌)より重きはなし」とあることを挙げます。つまり祭りの中で神に奉げ物を行う「献」の儀式の属(たぐい)において最も重要なのは「灌」であり、これが禘において最も重要であって後は大したことが無いから見る必要がないと孔子は評したのである。このように徂徠は解釈しています。いつもながら、豊富な知識を援用したアクロバチックな解釈ですね。
上田:魯の公室は荘公のとき非常に乱れ、後継者争い不義密通で、閔公が擁立されたが、二年で殺される始末で何の業績もなく、この混乱を治めるため季友(季氏)が擁立したのが僖公であり、三十二年の在位で大いに業績をあげ、魯では僖公を閔公より上に配することが妥当とされ、魯の賢人とされる藏文仲もこれを支持した。孔子はそれに異を唱えた。古注はそういう歴史的背景で解釈している。昭穆(位牌の配置)でみるべきか、禘祭でみるべきか。
小田:では、次の条にゆきますか。
或ひと禘の説を問ふ。子の曰はく、知らず。其の禘を知る者の天下に於ける、其れ諸れ斯(しか)るを示(み)るが如きか、其の掌を指す。
先王、本に報し遠きを追ふの意、禘より深きは莫し。仁孝誠敬の至りに非ずんば、以て此に與(あづか)るに足りず。或人の及ぶ所に非ず。而して王ならずんば禘せずの法は、又魯の當に諱むべき所の者なり。故に知らざるを以て之に答ふ。示は視と同じ。其の掌を指す。弟子、夫子の此を言ひて自ら其の掌を指すを記す。言ふは、其れ明らかにして且つ易し。蓋し禘の説を知れば、則ち理明らかならざる無く、誠格(いた)らざること無くして、而して天下を治むる難(かた)からず。聖人此に於て、豈に眞に知らざる所有らんや。
ある人が禘の説明を孔子に聞いた。孔子がおっしゃった、「分からない。その説明を知る者が天下に向かえば、これをみるようなものでしょう」と。そう言って、自らの掌を指された。
先王が祖先に報告して遠い先祖を思う心は、禘においてより深いものはない。仁・孝・誠・敬のきわみでなければ、禘にあずかるに足りない。ましてや、「ある人」の及ぶ所ではない。そして、「王でなければ禘せず」の掟は、魯がつつしんで忌むべきものである。だから、孔子は分からないと答えた。「示」は「視」と同じである。「その掌を指す」とは、弟子が、先生がこのように言って、自らその掌を指し示したことを記録したものである。それは、明らかであって簡単なことだと言おうとされたのである。つまり、禘の説明を知っていれば、理において明らかにならないことはなく、誠実さが至らないこともなく、天下を治めることも難しくない。聖人孔子がこれらのことについて、どうして知らないところなどあっただろう。孔子は、知っていたけれど言いたくなかったので、言わなかったのである。
小田:禘は周王朝がやるべきもので、魯がやるのは礼を失している。だから聞かれても言わなかった。禘は王者の誠実のきわみの中で行うべき祭であり、そういうことが分からない者が聞いても意味がない。聞くことは、不遜でもある。帝王にしかできないことであり、そういう帝王が天下を治めることは簡単なはずだ。これが朱子の解釈です。
上田:そういうことですね。
小田:貝塚先生は、古注を受けて、魯国の位牌の逆転をどう思うかと或る人が聞いたとされています。デリケートな問題であるから孔子は言質を取られたくなく、知らないと言って逃げたという読み方です。貝塚先生は、この章の「ある人」は為政篇21の、「或る人、孔子に謂いて・・・」のある人と同人物だとみなしています。孔子から政治的な発言を引き出したかったが、孔子は知らないと逃げたというわけです。これはおもしろい見方です。
上田:具体名はありますか。
小田:貝塚先生は陽貨の時代の「魯のかなり有名な政治家」としておられる。読書会では晩年の季康子の周辺の高位の者ではないかと、解しましたね。いっぽう荻生徂徠は、魯が禘をするのは非礼ではなく、朱子の説は当らないと見ます。周の礼は幽王・厲王の代で衰えてしまい、孔子としては、今の禘が本来の禘ではないことを知っていたというのです。今の時代、周の禘祭がくずれて復元できないから「知らない」と言い、それができていたいにしえの周の時代の王ならば天下を治めることも難なくできていた、と言ったというのが、徂徠のこの章の解釈です。
上田:禮運に、「孔子の曰はく・・・魯の郊禘(こうてい)禮に非ざるなり。周公、其れ衰へたる。杞(き)の郊なるは禹なり。宋の郊なるは契なり。是れ天子の事守(じしゅ)なり。故に、天子は天地を祭り、諸侯は社稷(しゃしょく)を祭る」とある。朱熹はこういうことから魯の郊禘は礼に非ずとしたのだろう。「其の禘を知る者の天下に於ける」以下をみるなら、これは位牌の問題より、天下に王たる者が郊禘の主体という展開の方がしっくりする。歴史的な背景では、孔子は魯として功績ある僖公の位牌を閔公の前に置いたものを善しとしなかった、時流に合わないが礼に非ずと筋を通そうとしたことになる。
小田:ちょっと違うかもしれませんが、閔公と僖公の功績の落差は、七代将軍徳川家継と八代将軍徳川吉宗との業績の差ぐらいあったでしょうかね。家継は幼少で何もせずに夭折し、後を形だけの猶子として吉宗が継いだ。両者の業績の差は、比較にならない。その吉宗の嫡男の徳川家重は先天的に身体的欠陥があり、まともな意思疎通すらできなかった。それで将軍職には疑問視されて、側近は文武に長けた次男の田安宗武を将軍職につけようと運動をしました。しかし吉宗はこれを容れず、家重を次期将軍に就けました。それは、嫡男相続の掟を崩すことを拒んだからで、相続の掟を変えることは後世に乱れを呼ぶと判断したからでした。このように泰平の世では実力よりもルールを遵守することが優先されましたが、戦国の世においては、ルールよりもむしろ一族の中で実力あるものが後を継ぐことが優先されました。そうしなければ他国に滅ぼされるからです。春秋時代もまた、国どうしが争う乱世でした。だから、実力ある家臣たちは心服の出来る、有能な者を君主に立てようと望んだことでしょう。それは、当時の当然の成り行きだったはずです。その中で、孔子は時流に逆らったことを主張していたわけでしょうか。これでは、賛同者は出なかったのもいたしかたなかったでしょう。
本日はここで切り上げて宝が池の花火観賞(京都フォト日記国際会館)。
ライフで飲み物を仕入れ、稲垣夫妻の到着を待つ。PLの花火大会を知る小田さん、物足りないであろうなと思いつつ、乾杯。稲垣君の刺身やなめろうをつつき、花火を見る。
小田さんの感想:取り立てて話題にもならない花火大会だから大したこともないだろう、と高をくくっていましたが、短い時間ながらもなかなかに充実した花火で、堪能させていただきました。観客もあまりおらず、余裕綽綽で見物できました。稲垣さんご夫妻が持ってきてくださったアジの刺身や白子入り卵焼きとか、いつもながら工夫が入った料理。じつに風流の中の珍味を楽しませていただきました。ありがとうございました。
上田さんは二日続きでしばらくダウン。サッカー(なでしこvsスエーデン)が気になりつつ引き上げると、0-0の引き分けでした。阪神は7連敗(ファンはシンデレラ)。
2012年8月4日(土)論語八佾篇
本日は小田さん、上田さん二人で音読、訓読と意味を小田さん。途中から高津君、成田君が合流。
祭ること在(いま)すが如くす。神を祭ること神在すが如くす。子の曰はく、吾祭に與(あづか)らずんば、祭らざるが如し。
程子の曰く、祭は、先祖を祭るなり。神を祭るは、外神を祭るなり。先を祭るは孝を主とし、神を祭るは敬を主とす。愚謂へらく、此れ門人の、孔子の祭祀の誠意を記す。與は、去聲。
又孔子の言を記して以て之を明らかにす。言ふこころは、己れ、祭る時に當り、或は故有りて與るを得ずして、他人をして之を攝せしめれば、則ち其の在すが如くする誠を致すことを得ず。故に已に祭ると雖も、而れども此の心缺然として未だ嘗て祭らざるが如し。○范氏の曰く、君子の祭は、七日戒し、三日齊し、必ず祭る所の者を見る。誠の至りなり。是の故に郊すれば則ち天神格り、廟すれば則ち人鬼享(う)く。皆己に由りて以て之を致す。其の誠有れば則ち其の神有り、其の誠無くんば則ち其の神無し。謹まざる可けんや。吾祭に與らざれば、祭らざるが如し。誠は實爲り、禮は虚爲り。
孔子は先祖を祭るとき、先祖の霊がそこにいるかのように祭られた。先祖でない神々を祭るときには、神々がそこにいるかのように祭られた。孔子がおっしゃった、「私は祭に参加しないと、祭った気がしない」と。(以上は朱子の解釈からの訳。このように「祭如在、祭神如神在」を朱子は孔子の行動を記したものと解するが、荻生徂徠は「古経の言なり」つまり昔の経典からの引用である、と解している。徂徠の解釈を取るならば最初の文は、(古言に言う、)「先祖を祭るときには、先祖の霊がそこにいるかのように祭れ。先祖でない神々を祭るときには、神々がそこにいるかのように祭れ。」ぐらいになるだろう。)
程子が言った、「祭は、先祖を祭ることである。神を祭るとは、先祖でない神を祭ることである。先祖を祭るには孝を主とし、先祖でない神を祭るには敬を主とする」と。それがし(朱子)が思うに、この言葉は門人が孔子の祭祀の誠意を記録したものであろう。與は、去聲である。
(後半の言葉も)また孔子の言葉を記録して、以上ことを明らかにしたのである。つまり自己が祭りに当って、場合によってやむを得ず参加できず他人に代理させたなら、その人は在(いま)すがごとくする誠意をつきつめることができない。だからすでに祭りを行ったとしても、その者の心に欠けた感じが残り、祭っていないような気になるものだ。○范氏が言った、「君子の祭は、七日戒し、三日齊し、必ず祭る対象を見る。これが誠意の至りである。だから郊の祭りをすれば天の神々がおり、宗廟の祭りをすれば、先祖が降臨する。みな自分の中から発して、これらをつきつめるのである。その誠意があれば神々がやって来るし、その誠意が無ければ神々はやって来ない。だからどうして、謹まないでおられよう。『私は祭に参加しなければ、祭りをした気にならない』。誠意が実であり、礼は外面的なものなのであるにすぎない」と。
上田:徂徠が「祭如在祭神如神在」を「古経の言なり」とした根拠はありますか。
小田:徂徠は、郷党篇(27章)の「色みて斯に挙がり、翔びて後に集まる」についても古言の引用であると解釈して、この章の前半はこれと同じだ、と言っています。徂徠は、論語の言葉が何でも孔子のオリジナルの発言だと考えるのは誤りで、論語には当時の詩やことわざなどの引用もあって、それがむしろ孔子の文化継承者としての立場としての本来なのだ、と言わんとしているのだと思います。
上田:孔子が祭りに與らないを、古注は病気や出掛ける用事があり代理をたてるとし、朱熹はそれを踏襲しているが、呼ばれなかったのではないか。孔子が呼ばれたのは、司寇、大司寇に就任して以降のことだろうし、恐らくはこれは晩年のこと。「祭らざるが如し」は祭った気がしないとしているが、祭りの呈をなしていない、ご先祖様がきちんともてなしてもらっていない、孔子はそういう説教をするのでうとまれて呼ばれなかったのではないか。
小田:私が参加していないと祭りじゃない、と。孔子の大変な自信を示した発言ということですか。
上田:私が祭らないと、降りて来られたご先祖様が満足できない。
小田:前の禘の議論から言えば、祭は魯公が主宰するべきものですが、主催者はやる気がなくて家臣もだらけていた。それで孔子はカツを入れて説教をしようとしたが、煙たがられて追い出された。それで私が行かないと祭りにならない、と言ったというわけですかね。
上田:「灌してより往(のち)は、吾之を觀るを欲せず」と考え合わせるとそういう風に思えて来る。
小田:それはそうかもしれませんが、孔子の祭と孔子以外の祭との間の真剣さとは、どこがどう違っていたのでしょうかね。当時の祭のことがよくわからないので、何とも言いようがない。魯の朝廷だって、形式的にはきちんと行っていたのだろうとは思うのですが、、、孔子先生は、どこがお気に召さなかったのか?本当に孔子がやれば、納得できるほどに立派な儀式となったんでしょうか?
ここで高津君、成田君が合流、これまでの経緯を説明。
成田:最初の箇所が荻生徂徠の見解であるべきか朱子の見解であるべきかは、それ自体が検討すべき重要なことです。次の「與らずんば」ですが、古注・新注ともほぼ同じ解釈で他方上田さんが別の意見をお持ちだということですが、両者は本質的には変わらないのではないでしょうか。祭りに参加しないことを、古注では病気とか他の用事として、朱熹もやむを得ない事情で代理をたてることとしています。いっぽう上田さんは疎まれたためと考えますが、理由はともかく孔子自身が参加していないことは一致しているわけです。孔子が参加していないので何らかの欠落がある、ということが共通しています。下の句の主語については、古注も朱注も孔子としており、孔子がこんなことでは祭った気分にならないとする。上田さんはご先祖様が満足されないと言います。しかし私の意見では、いかに孔子といえどもご先祖様の気持ちまで推し量ることはしないのではないでしょうか?先進篇に「季路、鬼神に事つるを問ふ。子の曰はく、未だ能く人に事へず、焉ぞ能く鬼に事つる。敢へて死を問ふ。曰はく、未だ生を知らず、焉ぞ死を知る」とあり、生きている人間に仕えることもできないのに、死んだ人間が祭られた気になっているかを推し量るなどは、自ら戒めていたはず。だから、私は従来の解釈を取りたいです。
小田:昔の日本では、村の一人が代表としてお伊勢さんに旅行して村民全員の代参をするなど、代参の習慣が広く行われていました。そんな代参では、孔子は心が納得しないというのでしょうか?
成田:孔子は代参がだめだとは言っておらず、自分が祭った気持ちにならない、気持ちがスッキリしないと言ったまでです。礼は儀式を行うのが基本だが、孔子は心がこもっていないが気になるのです。
小田:前の章で子夏が「礼は後」と言っていましたね。心中の誠実が先にあって、形式は後から整えるものであると。だから、心中をおろそかにした形式はよくない、ということになるわけですかね。
成田:儒家はそうです。宗教において、儀式と心中の義との兼ね合いは、いつも問題となります。今はイスラムでラマダンの時期ですが、オリンピックで大問題となっています。
小田:選手によっては、飲食しなければ試合ができないから自分はラマダンに従わない、と言う人もいますね。
成田:あるいは、選手については後日断食月を持つことで代用してよい、と公式見解が出されたりしています。さて「祭如在祭神如神在」が孔子の行動か、あるいは古経の言であるかは重要な議論です。その後の孔子の科白との関係が重要ですが、どう思いますか。
小田:上田さんは、本来の祭りの姿であらねばならないが、魯公も家臣も形式に流れている。「灌してより往(のち)は、吾之を觀るを欲せず」、灌以降は観る気がしないと連動して読めるが、代理の祭りでは心が落ち着かない。心をこめて在ますがごとくせねばならない。朱子も范氏を引用して、誠意は實があり、禮は虚、外面的としている。
成田:それには賛成します。礼はかくあらねばならないという言葉で、ところが今の礼はそうなっていない。この章を晩年の孔子の言葉だとすれば、晩年の孔子の御意見番としての意見であり、具体的に祭祀には参加していなかった。祭りに与る人間ではなくて、祭りの本来の精神が失われている、祭りの精神が一番重要だと辛口の批評をしたということになるが、ありそうなことです。
小田:たとえば「郊」の祭りに参加できるのは、どのクラスまでですか。
成田:大夫まででしょう。その下の士は、無理でしょう。
小田:ならば、晩年の孔子は参加できる地位にあったのではないですか?
成田:末席に参加はできたでしょうが、孔子としては、自分が仕切ってやりたかった。単に列席して見ているだけでは、孔子として関与したことには入らないと考えたでしょう。しかし、それはできなかったでしょう。
小田:禘の祭りには、孔子は参加していますね。
成田:参加していますが、礼を行う側ではなくて、いわばVIP席で観客としていただけでしょう。
小田:宰主は魯公ですから、祭を仕切るは儀式の進行役がいたのでしょうか。
成田:孔子は、MC(Master
of Ceremony)をこそやりたかったのでしょう。
小田:その職務となると、、、
成田:周制でのMC相当は大宗師ですが、これは周の役職であり、魯がそれぞれの職務に相当する大臣を置いていたかどうかは、分かりません。しかし、それに相当する担当者はいたでしょう。
上田:八佾篇では礼の基本が失われること、魯においては、魯公が自立していない、魯公がすべき礼を家臣が行う、軍事や財政、儀式においてそれが続いており、礼が失われており魯公自滅の危機的な状況にあると孔子が憂いているが通じない。
成田:礼の乱れが政治の乱れに関係していると孔子が考えていたのは、その通りでしょう。しかし、礼の乱れは、魯国に限ったことではないと考えていたでしょう。諸国を放浪していたとき、どの国においても礼が乱れていることを孔子は発見した。礼は魯国のみならず各国においても重要なことであり、孔子は礼を正すことで、天下の政治の安定をはかることを目指したはずです。
小田:八佾篇では、最初の章では礼の形式の乱れを批判していましたね。しかしその後で子夏との問答で「礼は後か」と言い、形式よりも心情の誠実が優先だ、と論じています。形式を守らなければならないが、形式だけ守っていても中身がなければよくない、と一見して矛盾したことを言っているようです。この孔子の主張は、なかなか分かってもらえないでしょうね。
成田:孔子の時代の人もそこが分かりにくかったでしょう。本当に心がこもっていればいいのだが、やっている本人からすれば、よく分からない。
高津:行動に余裕が有れば学べ、と孔子は言いました(学而篇六)。まず孔子は弟子を観察して、この人物は学問を学ぶべきかどうかを見極めたでしょう。余力があったところで学ばせ、行動を礼で約させた。こういう教育のやり方は、当時も今も変わらないと思います。孔子は昔のことを言うが、今にでも通用することを言っているはずです。
成田:孔子が怒っているのは、祭る立場であるから祭っているだけというおざなりな態度であり、祭の本来の精神を考えねばならないということです。いつの時代でもこれは一緒で、形式を守ることについてそう考える人は少ない。
小田:孔子の時代の礼の議論をあえて今の時代の例に引き寄せれば、敬語を使うべきかどうかという議論になるでしょうかね。大人が若い人に、そんな乱れた言葉を使うなと叱る。若者は反論して、「言葉なんか心がこもってたらイージャン、タルいこと言ってんじゃねーよオッサン」と答える。それに対して大人は、どう反論するべきか。「もし相手を思いやる心がこもっているならば、そもそもそんな言葉を相手の私に言わないだろう?」と答えるでしょう。しかしこれで言われた若者が納得するとは、思えませんね。形式に従うことを心中で納得して学ばせるには、説教を越えたなにものかがなくてはならないでしょう。
高津:それは大人にも責任がある。やっている姿を見せないといけない。孔子は弟子にそれを見せている。身分や立場に関係なく、その人に合わせ、その立場になって、対応をしている。自分がしているからそれを押しつけるでは、子供たちは従わない。
小田:口先だけの説教で行動が伴っていない場合、子供は見破りますね。子供は聡いですから。
高津:孔子が魯だけのことを思っている訳ではないという成田さんの意見には、賛成。孔子は諸侯が自分を信じてくれれば、必ず力を発揮すると言っていました。当時の諸侯はいかにして戦争に勝てるかを聞くが、孔子はもっと広い立場で考えた。この後の章で「其れ奧に媚びんより、寧ろ竈に媚びよ」と言われたことに対しても、「罪を天に獲れば、祷る所なきなり」と答えて、何か天にやましいことをしてしまうと、もはや修復はできないと言いました。
成田:礼の乱れ、政治の乱れを放置すれば、天から罰が下されるということです。最終的には天が出てくる。天の罰とは、あるいは天変地異が起きるとか、そういう脅しみたいにまとめることもあります。こういう強い言葉は、孔子が怒っているときにだけ発するのですが。
小田:それが荀子になると、天変地異は自然現象であって天罰などではない、と言います。また祭での祈りは、単に祭るふりをしているだけで具体的な効果などない、と断じてしまいます。荀子になると、ここまで合理的になってしまいます。それで荀子は、ならばどうしてわざわざ礼に従わなければいけないのか?という問いに対して、礼には実利があるから従ったほうが得するのだ、と答えるしかありませんでした。礼に従えば人から評価されて、長期的に見れば成功が得られて利益がある、と荀子は言う。こう言うしかないのです。荀子になると、孔子にはあった天からの恐れを取っ払ってしまった。孔子にはあった秩序の乱れに対する恐れの感覚が、荀子には消えている。荀子の時代でもう非常に現代的な醒めた感覚となっていて、秩序に外れたことをするとどこかからバチが当る、という畏怖感が消し飛んでいるから、結局荀子は礼に従わないと人生長い目で見て損しますよ、といった実利的な説得をするのです。孔子に比べるとなんとも醒めていて、どうも味気ないです。
高津:日本のこの20年の変化には驚きます。世の中がどんどん進むと、こう言う風に変わるのでしょうか。今までうまく行っていたからといって、そのまま成り行きで放置すると、いつか間に合わなくなるのではないでしょうか。
小田:20年も昔、私は塾で中学生を教えていました。そのとき、こいつらが大人になるとどうなるんだろうか、などと思ったものです。しかし、その彼らも今や30代のはずです。あの時代の子供には、もう親とか先生とか年長者とか、ひっくるめて世間を恐れるということが、なくなっていました。そんな子に怒鳴って怒っても、聞きませんでした。その子たちが大人になった今の時代、さらに下の世代の子に対して、彼らが説得できるはずがありません。今の時代、教える人々は大変です。
高津:西門豹は、いつの頃のことでしたか?
小田:子夏が孔子の死後に魏に行きましたが、その頃魏にいた人です。だから、孔子よりやや後の時代の人ですね。
高津:私は封建主義はよくないものと思っていたが、西門豹の伝記を読んだとき、考えを改めざるをえませんでした。政治のよしあしは封建主義とか民主主義とかのシステムではなくて、上に立つ人のよしあしの問題です。塩野七生は、民主主義がよいのではなくて、上に立つ人のよしあしに依存すると言いました。ギリシアはペリクレースのとき30年間繁栄しました。アテネの民主主義では大衆が指導者を選ぶことができるが、それでは衆愚政治に陥る危険があった。ペリクレースはそれを知っていて、大衆に受けをよくしながら背後でしっかり手綱を締めていました。そして、その事実をバレないようにしていました。ペリクレースが上にいたからアテネの民主主義はよかったので、彼の死後短期間でアテネは衆愚政治になってしまいました。
小田:ペリクレースの後にアルキビアーデスが支持されたぐらいです。アルキビアーデスが悪質なデマゴーグであることを、アテネの民衆は見抜けなかった。それで、アテネは彼の愚策に乗ってしまってわずかの期間で没落してしまいました。
高津:西門豹は、河伯に犠牲をささげる祭の迷信を打ち破りました。祭を行う人のよしあしによって、祭がとんでもないものになっていた。西門豹は祭が巫女と役人の私服を肥やす道具となっていて、しかも民衆に信じられていることを見ました。それで恭しく祭りを行うためには犠牲となる女性の器量が悪いと言って、代わりに巫女を川に沈めてしまいました。それで何の答えも返ってこないのは河伯が物足りないと思っているのだろう、と言って次に巫女の弟子を沈めました。それでも何の答えもないから河伯が納得していないのだろうと言って、今度はこの儀式で私腹を肥やしている連中を沈め、次に金銭を得ていた役人を沈めるように命じました。ここに来てとうとう役人たちは降服し、この儀式を取り止めることにしました。西門豹の素晴らしさが、これを読んで分かった。孔子がここで言ったことは、自分の私利私欲のために祭りを利用するならば世の中はこわれてゆくということでしょう。その憤りが強調されていると思います。
小田:超自然的なもの、人間を越えた者への畏敬の気持ちが、孔子の時代ですら人々に薄れていったのでしょう。しかし伝統を破ること、つまり自分で作ったものではないものを自分の一存で変えることに、孔子は畏れの感覚を持たなければいけないと考えていたのだと思います。しかし西門豹の頃には、その畏れをむしろ打ち破るべきことが、正義となりました。荀子では、とうとう神無しとなりました。
高津:西門豹は迷信を打ち破っただけでなく、大規模な灌漑工事を行った。工事への反対も多かったが、彼は今は評価されなくとも、そうする必要があるとして行った(魏の農業生産を高め、魏は強国となった)。彼は、今の政治の見本となるようなことをしています。西門豹を封建主義でひとくくりにしていた自分が、恥ずかしかったです。
成田:史記の中の話ですね。
小田:「河渠書」でしたっけ。「河渠書」は、先秦時代の各国が行なった治水灌漑工事が列挙されています。(後注:「河渠書」には西門豹の業績は簡潔な叙述しかなくて、上の高津さんの言及したエピソードは史記「滑稽列伝」のもの。ただし前漢の褚少孫が補筆した箇所である。)
高津:政治には「人ありき」を言いたかった。
小田:その史記ですが、司馬遷は縦横家の張儀を非常に悪し様に酷評しています。私は読んだとき、これはどうしたことだろうか、と不審に思いました。思うに、司馬遷は後世に役立つことをした人が好きであって、孔子も評価するし孟子も評価するし老子も荘子も評価する。思想的には節操がなく、思想という後世につながる業績を残した点で、評価しているかのようです。しかしながら張儀は酷評する。張儀のような縦横家は各国を渡り歩いて一時的な勢力均衡を試みただけで、後世の役に立っていないと考えたのでしょうか。
成田:縦横家は、考え方のスケールが小さいと言えましょうか。一国一国のことのみで、天下全体のことを考える諸子に比較すると志が落ちる。そう考えたのでしょう。法家ですら、漢代の視点からみれば誤った議論ではあったが、天下を構想した。縦横家には、それすらなかった。
高津:私は司馬遷が史記を書いたことは評価しますが、彼以降本を残すこと自体が目的となって、自分が活動しなくても書いたものを残せばよいのだという考えを始めたのは、よくない前例であったと思っています。本を残すことが目的となってはならず、やっぱり生きているうちに行動しなければいけない。
成田:孔子は諸侯に受け入れられず、文献を整理して残した。文献は、仕方がないから残したのです。諸々の失敗がなくて最初から文献整理をしている孔子であれば、重みもないことでしょう。伯夷や叔斉は、失敗して餓死してしまった。しかし司馬遷以降は、死ななくても後世に書物を残せば人生十分だ、という安心感が生まれました。それで、後世の人々は伯夷みたいに死ぬ道を選ばなかったという効能が、司馬遷にはあったのではないでしょうか。
さて、次に行くのも中途半な時間帯で、関連する話題に脱線。サッカーは帰宅すると3-0でエジプトに快勝。ベスト4に進出、次はメキシコ戦となりました。
2012年8月11日(土)論語八佾篇
北澤さんは8月末に中国に発たれ日本語教師となられる。読書会は本日が最終。弘法市で論語、孟子、大学など明治十四年発刊の後藤点10冊を入手。成田君に聞けば、そういうものは結構出回っているそうですが、時代を感じさせてくれました。高津君、小田さん、成田君、上田さんの五人。成田君のリードで音読、訓読と意味を北澤さんお願いします。
王孫賈問ひて曰く、其の奧に媚びるよりは、寧ろ竈に媚びよとは、何と謂ふことぞ。
王孫賈は衛の大夫。媚は、親順なり。室の西南の隅を奥と爲す。竈は、五祀の一、夏に祭る所なり。凡そ五祀を祭り、皆先づ主を設け其の所に祭り、然して後尸を迎へ奥に祭る。略(およ)そ宗廟を祭る儀の如し。竈を祀る如きは、則ち主を竈陘(そうけい)に設け、祭畢はりて更に饌を奥に設け、以て尸を迎ふ。故に時俗の語、因りて奥は常の尊有るも、而れども祭の主に非ず、竈は卑賤と雖も時に當りて事を用ふるを以てす。自ら君に結ぶは、權臣に阿附するに如かざるに喩ふ。賈は衛の權臣。故に此を以て孔子を諷す。
王孫賈が問うた、「『その奧に媚びるよりは、寧ろ竈に媚びなさい』とは、どういうことですか?」と。
王孫賈は衛の大夫。媚は、親しみ従うこと。室の西南の隅を奥という。竈は、五祀(戸、竈、中霤、門、行)の一つで、夏に祭るもの。そもそも五祀を祭るには、皆まず主を設けて祭り、その後尸(位牌のようなもので、霊を降ろす依り代)を迎えて奥に祭る。だいたい宗廟を祭る儀式は、このようなものである。竈を祀るには、主を竈陘(そうけい、かまどのまわりの器)に設け、祭が終わってから供物を奥に設けて尸を迎える。だから当時の俗諺で、「奥には常の尊位があるが、祭の主ではない。竈は卑賤なものであるが祭の時には事に用いられる」と言ったのである。つまり自ら君主に結ぶよりは、権臣におもねりへつらうほうがよい、というたとえなのである。賈は衛の権臣であり、だからこの言葉で孔子を遠回しにあてこすったのだ。(孔子は奥の衛公に会う前に、竈の実力者に会うべきだということ。)
子の曰はく、然らず。罪を天に獲れば、祷(いの)る所無し。
天は即ち理なり。其の尊對す無し。奥・竈の比す可きに非ず。理に逆へば、則ち罪を天に獲る。豈に奥・竈に媚び、能く祷て免る所か。言ふこころは、但理に順ふに當りて、特(ただ)竈に媚ぶに當らざるに非ず、亦奥に媚ぶ可からざる。○謝氏の曰く、聖人の言は、遜して迫らず。王孫賈をして此の意を知らしめば、益無しと爲さず、其の知らしめざるも、亦以て禍を取る所に非ず。
先生がおっしゃった、「そうじゃない。(どちらも道をはずれている。道理に違って)罪を天にうけるなら、祈っても罪をのがれることはできない」と。
天とは正しい道理である。その尊さは比較する対象がない。奥や竈に比較すべきものではない。理に逆えば罪を天にうける。奥や竈に媚びて、よく祈ったからとてどうして免れることができようか。つまり、理に従うとは、竈に媚びることでもなく、奥に媚びることでもない。○謝氏が言った、「聖人孔子の言葉は、慎んで奥ゆかしく迫らない。王孫賈にこの意を知らしめることができれば、益が無いものではないし、知らしめることができなくとも、禍となることもない」と。
小田:王孫賈が孔子に近づいて、何で挨拶に来ないのか、とたとえ話を使って嫌味を言った。これは現実的な力関係です。だが孔子は天を恐れて、正しい道、正しい理でしか行えないと答えた。孔子は天の理に従って考えたということでしょう。
北澤:衛に初めて行ったときのことですか。
成田:竈にたとえられたのが、誰のことか。これを王孫賈と考えた場合には、いつのことかはわかりません。これを南子と考えることもできて、そう考えれば、孔子が南子に会った時ときです。別説では王孫賈は権臣などではなくて、権臣は彌子瑕(びしか)のことであると考えます。その説では、南子が奥で彌子瑕が竈ということになります。王孫賈が単なる伝達係であるという考えに立てば、彼の主人は彌子瑕であったかもしれないし、南子だったかもしれない。うちの主人にまず会いなさい、と言ったことになります。
高津:孔子は各国を回って、たとえその国の殿様が孔子を採用したいと考えても、家臣たちは孔子に国を取られることになる、と反対された。だからここで孔子が政治をやりたいのなら、下の家臣から攻めろみたいなことを、成功していない孔子に言った。私はこの言葉で、福島のことを思い出しました。朝日新聞の7月5日に黒川報告が載っていた。それによると、規制する側の委員会が、規制される側の企業の言いなりになってしまっていた。両者の立場が逆転していた。竈とは、今権力を持っている者で、いわば皆の前で祭りを行っている所が電力会社であった。会社は自己の利益を図ろうとして、規制する側を操った。黒川先生が指摘されたのは、電力会社の東電が規制する側を押さえつけて危険性の指摘を無視していたことで、だからこれは天災ではなく人災である、とみなしたことです。「天に罪を獲れば祷る所無し」と孔子は言いましたが、福島のことは本末転倒で規制側が事業側にとりこまれていて、そのようなことがあれば結果として取り返しがつかないことになる。
小田:朱子の解釈では、天の理が唯一であって奥も竈も比較にならない、と言います。これでは王に媚びるのも、権臣に媚びるのも、どちらもやりたくないということになります。しかし、孔子としては王にストレートに接近することは、望ましいのではなかったのでしょうか。それを、両方ともに斥けるという解釈は、どういう真意でしょうか。
成田:孔子が怒っているのは、宗教儀式を「媚びる」と俗語を引いて表現したところです。孔子が王に媚びるとか竈に媚びるとかとたとえ、孔子をまるで媚びる人とみなした物言いをされた。孔子が気に入らないのは、そこです。
小田:つまり、問いそのものを退けた。
成田:「其の奧に媚びるよりは、寧ろ竈に媚びよ」は時俗の言で、当時の俗語です。こんな言葉は、書経にも詩経にもない。孔子としては、そのような俗語にたとえられたことに答えられない。
高津:どの国も各人それぞれ役割があって、かみあっているはず。なのに、権臣たちは自分の権力を誇示するばかり。己の立場をわきまえておれば、孔子を推挙すべきだった。
小田:王孫賈は、孔子に政治の常識を言ったのでしょう。上手く取り入った方が結果が出せるからよい、という次元で言われた。しかし孔子としては、たかだか目先のことで自分は衛に来たわけでない、もっと大きなテーマの実現のため、天下の理想追及のためにここにいる、と言いたかったのでしょう。
成田:しかし王孫賈が本当に政治を推進できるのであれば、あんなことを言う必要はない。政治を儀礼にたとえて両者を媚びることなどと言ったから、その姿勢に孔子は激怒したのです。
上田:孔子は天命を実現しようと諸侯を求めて衛に来た。天に罪を獲るとは、夏の桀、殷の紂のこと、民の安寧を図らず天に罪を得た。祷るとは長寿を祈ることで、桀や紂の命運の尽きたことを言うのではないか。
成田:天とか神に対して媚びるような心情は、結局天に対する罪を導くでしょう。殷の紂王時代には、神を祀る儀式は壮麗で立派なものであった。だが、その片方で民を虐げる政治を行っていた。このように天の道に逆らっていては、罰を受けてから天に祈ってみても、もはや手遅れで意味がない。このような祭りは形式でしかなく、内実が備わっていないと言うしかありません。
上田:古注では、道の成否は君主が決めることで家臣の決めることではないとしており、朱熹はそれでは飽き足らず、天は理であり、媚びる対象じゃない、次元が違うとした。しかし、天に罪を獲るについては説明をしていない。
小田:古注は、単に家臣の分際を越えることはしてはいけない、と解釈するだけで、あまり突っ込んだ解釈ではありません。朱子は、もっと思想的な解釈です。神に媚びるような心根には、神の道、天の理に対する真摯さが足りない。だから、表面上の祭りよりも心中の理に従って生きて行かねばならない、と思想化します。
高津:王孫賈は現実に権力のある者で、いつでも自分を最高としていた。だから政治を実際に行っているのは自分だと思っていた。魯では、魯公ではなく季氏が実権を持ち、竈が前に出ている時代だった。孔子はそんな時代のなかで、周公が成王を補佐したような政治を目指し、秩序を乱すような権臣を目指さなかった。そんなことをすれば、時代の権臣と同じことになる。孔子は自分に力があっても、役割を果たして人が支え合うことを目指していました。
小田:成田さんが指摘したように、竈が具体的に誰を指すのかはいろいろ説があるようですが、いずれにせよその者たちは今ここの衛国の政治に視点を集中していたのでしょう。孔子は、そんな人々に対して思想的に、今ここの衛という国を越える視座を持とうと望んでいたのでしょう。だから今ここにある課題と直面していた権臣たちの状況とは視点がずれていたので、話が噛み合わないのはいたし方なかったでしょうね。
高津:王孫賈は自分のことしか考えていなくて、王孫賈が考えるべきは孔子を推薦することだった。
成田:しかし、王孫賈たちが本当はどう考えていたかは、分からないです。
ここで話は福島の原発事故のことに、しばし、脱線。
小田:孔子の頃には戦争の規模が大きな衝突に変化して、あっちこっちの国で下克上が起こり、大きな変化の時期にありました。孔子は、そんな時代に対して、このままではどうなってしまうのであろうかと懸念を抱いていたのでしょう。それで、大きく網を掛けるような統一的秩序の思想を持つようになったのでしょう。
北澤:他のレベルが低いということですか。
高津:公西華の所で、孔子が原思を宰にして粟九百を与えると原思が断った。そのとき孔子は原思に対して、もらって他の人に与えよと言いました。与えてもらったものは他に施せと、ただ自分の清廉さをアピールするばかりではなくて、他人のことも考えよと諭したのです。
ここで話は管仲に飛ぶ。これは管仲のところで繰り返しになる可能性があり、割愛。高津君、管仲を批判する孔子に、「成事は説かず、遂事は諫めず、既往(きおう)は咎めず」ではなかったですかねと不満。孔子は管仲をけなしているばかりではなく、後の憲問篇では、その功績を評価している。管仲は孔子の時代には誰もが高く評価していた人物であって、八佾篇の孔子の言葉は、だからといって管仲は完璧ではない、礼を知っていたとはいえないという孔子の軽い人物批評程度を記録したものかもしれない、と成田君。武内義雄先生の考証に従えば、八佾篇などの論語上篇は魯学派の編纂であるに違いない。ならば八佾篇の管仲のくだりなどは、たとえば孔子が弟子に対して軽い批評としてボソボソ話した記録を、後に魯学派が管仲をけなすためにあえて取り上げて、収録したものかもしれない。魯学派の末裔である孟子は、公孫丑上篇で弟子の公孫丑が管仲を称えたことを叱り飛ばして、菅仲などは私にはるかに及ばないと強烈にくさしている。いっぽう憲問篇などの論語下篇は武内先生によれば主に斉学派の伝承である可能性があり、そこで管仲を誉めたのは斉で大きな業績を残した政治家としてポジティブにとらえていたことの表れではないだろうか、と小田さん。いずれにせよ、歴史上の人物をけなすのはいかがなものか、と高津君。
成田:歴史上の人物の議論は重要です。文王、武王、周公、堯、舜、晋の文公、斉の管仲など、功績と人格は分けて考えられない傾向がありました。
上田:春秋の筆法ということですか。
高津:私が聞いた話を言いますと、銀行マンは入社5年を越すと、会社を辞めるかあるいは会社に残って目が死ぬかという分かれ目になるそうです。組織に長くいると、守りに入ります。優秀な人でも、そうなってしまう。これは現代でも、当時でも同じことです。孔子の時代は馬車が大事で、顔回の父が顔回の棺槨のために馬車を所望したが、孔子は大夫が馬車無しでは礼に反すると断った。それくらい馬が大切なのに、馬舎が焼けた時、馬のことを言わずに、孔子は怪我人の心配をしました。孔子は、礼に適うべき状況と緊急の状況との場合で、それぞれに何が一番重要かということを押さえていたからこのような対処ができたのだろう、と思うのです。
小田:最近の福島原発事故から数日の現場と東電本社とのやり取りのVTRが一部公開されました。そこで、炉に海水を入れなければいけないと現場が主張した時に、本社側から「もったいない」という言葉が洩れました。あれは、官僚的発想ですね。高津さんが言われる、組織に居ついた者が自然に陥る発想です。組織というものは面白いもので、私もまた役所にいましたが、人が組織に慣れると誰もが組織を優先する発想になるのです。市役所ならば、市民よりも役所のことを考えるようになり、役所よりも局のことを考えるようになり、局よりも課のことを、課よりも係のことを、、、とムラ重視の発想に陥ってしまいます。大きな団体ではどこでもそうであるのが、面白いといえば面白い。あのとき東電本社側が「もったいない」とうめいたのは、今起こっている恐ろしい状況よりも組織のことが先に思い浮かんでしまったことの表れだと思うのです。決して東電社員たちが無能だったからではなくて、組織とはそういうものなのです。あれで海水を入れることにもったいないという発想は、距離を置いた目から見ればありえない。
成田:海水を入れると炉が使えなくなる、という発想ですね。
小田:組織にあると、何が起こっているかの想像力が、働かなくなるです。そういった正気を保つことは、簡単なようで難しい。孔子の天の罪への意識は、大事なことでそしてなかなか難しいことです。
原発事故においても、理に逆らえば、取り返しがつかないことになる。「天に罪を獲れば、祷る所無し」。よくよく考えてみなければなりません。
北澤さんの送別、成田君のお祝い、一揆は盆休みで、久方ぶりに白木屋へ。竹島問題、北方領土、北朝鮮と中国関係、海洋資源にからんだ国益の激突。与党内ですら政策を統一できない隙をつかれ揺さぶり続けられても、最優先すべきことに焦点が絞れない政治。論語は仁を原点に置いた、と終電ギリギリまで歓談。
2012年8月25日(土)孟子梁恵王章句
本日は孟子、小田さん、成田君、上田さんでスタート。成田君にリードで本日分音読、訓読と意味は小田さん。帰省の早川君が合流。
齊の宣王、問ひて曰く、人皆我に明堂を毀(こぼ)てと謂ふ。毀たんや、已みなんや。孟子對へて曰く、夫れ明堂は、王者の堂なり。王王政を行はんと欲せば、則ち之を毀つこと勿かれ。王の曰く、王政聞くこと得可べしや。對へて曰く、昔者(むかし)文王の岐を治る、耕す者九が一、仕ふる者祿を世々にす。關市譏(き)して征せず、澤梁禁無し。人を罪すること孥(ど)までせず。老いて妻無きを鰥(かん)と曰ふ。老いて夫無きを寡(か)と曰ふ。老いて子無きを獨と曰ふ。幼にして父無きを孤と曰ふ。此の四つの者は、天下の窮民にして告ぐること無き者。文王政を發(おこ)し仁を施し、必ず斯の四つ者を先にす。詩に云く、哿(か)なるかな富める人、哀しきかな此の煢獨(けいどく)。王の曰く、善いかな言ふこと。曰く、王如し之を善しとせば、則ち何爲(なんす)れぞ行はざる。王の曰く、寡人疾有り。寡人貨を好む。對へて曰く、昔者公劉貨を好む。詩に云く、乃ち積し乃ち倉す。乃ち餱糧(こうりょう)を裹(つつ)む。槖(たく)に囊(のう)に。戢(あつ)めて用(も)て光(をほひ)にせんことを思ふ。弓矢斯れ張り、干戈戚揚(かんかせきよう)までに。爰(ここ)に方(はじ)めて行(みち)を啓く。故に居る者積倉有り、行く者裹糧(かりょう)有り。然る後に以て爰に方めて行を啓く可し。王如し貨を好んで、百姓と之を同じふせば、王たるに於て何にか有らん。王の曰く、寡人疾有り。寡人色を好む。對へて曰く、昔者大王色を好んで、厥の妃を愛す。詩に云く、古公亶甫、來りて朝(つと)に馬を走めて、西水の滸(ほとり)に率(したがつ)て、岐の下(ふもと)に至る。爰に姜女と、聿(つひ)に來りて胥(あひ)宇(を)る。是の時に當りて、内に怨女無く、外に曠夫無し。王如し色を好むこと、百姓と之を同ふせば、王たるに於て何か有らん。
齊の宣王が質問をした、「周囲の者たちが皆、私に明堂を壊せと薦めます。これを壊すべきでしょうか、やめたほうがいいでしょうか?」と。孟子が答えて言った、「明堂は、王者の建物です。王が王政を行おうと思われるなら、壊してはいけません」と。王が言った、「その王政について、聞かせていただけますか?」と。孟子が答えて言った、「昔、文王が岐の地を治めたときには、耕す者には九区画の一区画を税とする井田法を取り、仕える者の禄を世襲としました。関所や市場では、検査するだけで税をかけませんでした。沼や川での漁は、禁じられませんでした。人を罪するに、妻子に連座させることはありませんでした。老いて妻のないことを鰥といいます。老いて夫のないことを寡といいます。老いて子のないことを獨といいます。幼くして父のないことを孤といいます。この四者は天下の窮民であり、誰にも窮状を訴える相手がおりません。そこで文王が政令を発して仁を施し、必ずまっさきにこの四者を救いました。詩にこういいます、『よろしきかな富める人、哀しきかな一人暮らしの苦しきさびしさ』と。王が言った、「それはとてもよい言葉ですな」と。孟子が言った、「王よ。もしこれをよいと思われるのならば、どうしてそれを実行しないのですか?」と。王が言った、「それがしには悪いくせがあり、財貨(たから)が好きなのです」と。孟子が言った、「昔、周の公劉も財貨を好みました。詩経に言います、『糧(かて)積みて/穀(ぞく)を倉に収め/乾食(ほしい)を包み/小袋に包み大袋に包む。人民(たみ)和らぎて/国の誉あらんことを欲す。弓矢張り/干戈を掲げ/かくしてついに軍(いくさ)進めり』と。つまり、残る者には積んだ穀物と倉の穀物があり、行く者には乾かした糧食がある。こうして初めて、行軍を開始することができたというのです。王がもし財貨を好んで、それを人民と一緒に好まれるならば、どうして天下の王にならないことがありましょうか?」と。王が言った、「しかしそれがしにはまた悪い癖があり、好色なのです」と。孟子が言った、「昔、大王(古公亶甫)も好色で、その妃を愛しました。詩経に言います、『古公亶甫/朝(つと)に馬駆け/西水のほとりに従い/岐山の麓に至る。かくして姜女と/ついに添い遂げたり』と。この時に至って、内には伴侶のいない女はいなくなり、外には伴侶の無い夫もいなくなりました。王がもし好色であり、人民と共にあるならば、どうして天下の王とならないことがあるでしょうか?」と。
上田:毀諸已乎は毀たんや諸れ已まんやと読みませんか。
成田:諸は之乎のことで前にかかりますので、「これを毀つか?」です。しかし後藤点ではしばしば「諸」の字を黙字として読まないことがあります。それならば、「毀たんか、已まんか」と読めるでしょう。
小田:この章の朱注は、哲学的概念を連ねて難解ですね。
成田:楊氏が曰く以下ですね。
小田:楊氏の引用の中で、「情」と「人欲」とを別概念として捉えています。勇を好み、貨を好み、色を好む心は「皆天理の有する所」であり、「人情の無みするあたわざる所」だと言う。しかし「孟子、時君の問いに因りて、幾微の際を剖析す。皆、人欲を遏(あっ)して天理に存する所以なり」と言います。つまり、勇を好み、貨を好み、色を好む心は人情であって天理に従っているから、消すことはできない。なのに、人欲は抑えることができるし、抑えなければならない。これは、矛盾していないでしょうか?
成田:「情」は、「性」とセットになっている概念です。人間の本来の性質であり、だからそれそのものは善であると考えます。しかしそれは人欲とは違うものだ、と考えているようです。
小田:人欲は押さえよと言い、しかし情は天理であるからなくすことができないなどと言うのは、詭弁に聞こえますね。朱子の概念操作は、よく分からないなあ。それならば、キリスト教みたいに情も欲も天理に外れた罪であるから、抑えるべき悪である、と言い切ったほうが、そのよしあしは別として一貫すると思うのですがね。
成田:情は押さえるか押さえないの概念ではなくて、人間として必然的に持っているものです。だから、それを聖人はよく用いて小人は悪く用いる、という考えなのです。
小田:斉王が「勇を好み、貨を好み、色を好む」のは情のゆえに仕方がないと考えて、しかしそれならばどんどん勇を好み貨を好み色を好め、とは言わない。結局、人欲を抑えるというのは、情を自由に発揮させずに理性で抑えることであって、それでは情を肯定していることにはならないと見えるのですがね。
成田:人により、情は異なります。聖人の情はよいが、小人の情はよくない。「聖賢の其の性を盡くす所以なり。欲を縱(ほしいまま)にして一己に私するは、衆人の其の天を滅ぼす所以なり。二つの者の閒は、髮を以てすること能はずして、其の是非得失の歸は、相去ること遠し」と朱子は言います。聖人は、持てる情を最善に尽くすから、聖人であるというのが朱子の見方です。
小田:しかし、孔子もまた人間であり小人もまた人間である以上、持って生まれた情の本質は両者で同じでないと、人間は仁義礼智のための四端を必ず持っているという儒学の根本に外れるでしょう。宋代学者の孔子のイメージとしては、孔子は人間の情をきれいに発揮する人であり、いっぽう小人には情の使い方にノイズが入っているからいけない。孔子だけを超人として一般人と違う性質の持ち主であった、という見方は、彼らは取っていなかったはずです。もしそうであれば、普通の人間が聖人を目指すのは無理だということになってしまいます。だが、孔子が情を完全に発揮したから聖人だ、という点は、やっぱり私には分からないですね。理性は、情を伸ばすというよりも制御して抑圧する点のほうが大きいのではないか、、、孟子の章の内容に映りますが、「斉王が貨を好む」ことがどうして「公劉が貨を好む」ことと通じると孟子は言ったのでしょうかね。斉王は私欲で貨が好きだ、と言っているわけで、いっぽう公劉は国の財政を豊かにしたいと望んでいたわけです。まるで次元が違っていることで、孟子は斉王の冷やかしの問いかけを言葉でごまかしただけのように、私はここを最初読んだときに思いました。
成田:根本的なところでは一緒ではないでしょうか。誰でも聖人になれるという立場から、斉王の情でも好転させることができる、と言いたいのでしょう。
小田:しかし、国の財政を富ませることと、己の私財を蓄えることは、まるで動機が違うのではないでしょうか。
成田:まあ斉王の現状では、私財の欲を国の財政を富ませる政治に広げることはないでしょう。
小田:ここで斉王は孟子をからかって、「私はケチな性質で、私利私欲のある人間ですよ。これでも、あなたはいいというのですか?」と問うたわけです。それに孟子は公劉も財貨を溜め込んだからいいのだ、と答えました。しかし、公劉はどう見てもケチではなく、国を思って政策を立てたはずです。これと斉王の問いには、飛躍どころではない論点のすりかえがあると思うのですが。まあ古公亶甫の例は、分からなくもありません。斉王に対して、「人民の模範となるような恋愛をすれば、人民も倣ってよい家庭を作ることでしょう。だから恋愛大いに結構。だけど模範的恋愛をどうぞ」と言うわけで、これは何とか筋が通るかもしれませんがね。しかし公劉の例は、納得がいきません。
成田:公劉は性格として物を蓄えるのが好きで、それを見習って国民も蓄えるようになり、結果として国が強くなったと、言いたいのではないでしょうか。これが孟子のレトリックです。君主のよい性格が光源となって、国民に広がることで善政が成り立つという論理なのです。
小田:確かに、前のところで斉王が牛を可哀そうだと思う心を孟子は取り上げて、それを伸ばすだけで仁政につながるのだ、というのが孟子の論理です。しかし、この章の貨を好むことは、公私を混同した論理ではないか。
成田:当時の王には、プライベートはないということです。ぜんぶが私で、ぜんぶが公であった。貨を集めることも、公私の境はあいまいであった。
小田:もとより、昔の国家とは家産制国家だから、事情は言われるとおりでしょう。国の税収と王の収入との間に区別はないのが、古代国家でした。孟子は集めた税を福祉のために使えと薦めるわけで、回りくどく言えば国が困れば自分の立場も苦しくなるのだから、税の使い方はよくよく考えなさいよ、と遠まわしに王に言おうとした?しかしこれは情を推し進めた先に至る結論ではなくて、理性により情とか欲を自制した結果見える道だと、私は思うのですがね、、、
成田:話は変わりますが、最初の明堂に関する質問ですが、孟子の答えはずいぶんあっさりしています。王が王政をするなら残しておきなさい、と。これだけです。もっと重要な問題だと思うわけですが。
小田:いつ頃まで遺跡があったのですかね、漢の時にはあったようですが。
成田:朱注を読むと「趙氏が曰く、明堂は、泰山の明堂。周の天子東に巡守して、諸侯を朝する處なり。漢の時遺址尚在り」としてますね。
小田:後漢の趙岐の注を見ましょうか。「泰山の下の明堂を謂う。本(も)と周の天子、東して巡狩す。諸侯に朝(ちょう)するの処(ところ)なり。斉、地を侵してこれ有るを得る。人宣王に勧む。諸侯明堂を用いず、毀壊べし、、、」どうも、趙岐の注を見ると、漢代に明堂の遺跡があったとは書いていない。すると、朱子のいた宋代に漢代の明堂の遺跡が残っていた、という報告を朱子がしたのでしょうかね。
上田:周の天子が巡守し諸侯を朝すとなれば、各々の諸侯に部屋というか館というか、宿泊することもあるとするなら相当広大な施設となる。それを使わないままであるなら、浪費であると思う家臣も民も多かったことであろう。
小田:子貢ではないですが、明堂などという過去の遺跡を役に立たないのに維持することなどは、維持費がもったいない。それで、廃止しようという意見が出たのは当然でしょう。
成田:だが孟子は、王政を行うにはメリットになり得るから残したほうがいい、と言いました。
小田:王政を行うときには、あなたが使うようになるだろうと。将来を見据えて残せ、というわけです。
成田:孟子が望むような王になるなら、周王のように諸侯を明堂に集めて、そこから天下に号令することができるでしょう。
小田:しかし、明堂は元来は周の制度であって、斉とは関係ないですね。孟子には孔子と違い、周を復興させようという考えはないはずです。どうも孟子には、孔子のような周代の制度への固執がすでにないように思われます。孟子の意図は、明堂を宣伝材料に使えということでしょう。斉王は志が小さい。かつての周王のように諸侯を集めて天下の王となる気概を持ちなさい、と。
上田:孟子は呼ばれた時に明堂を維持すべきかどうか聞かれることが分かっていたのだろう。それで孟子は詩経を引用して、王たる心構えを説いて維持すべきとしたが、斉王はそれに関心をもたなかった。
小田:この梁恵王章句が、時系列に沿って並んでいるかどうかは分かりません。しかし編集者の意図は、読み取ることができます。斉王の最初の会見から始まって、この章になると斉王は孟子の言うことにだんだん関心をなくし、疑いを持ち始めている。斉王は孟子に対して自分は悪い癖がある人間であり、あなたが教える聖人はどうも嘘臭くて、信憑性が乏しいと疑い始めた。この次の章では、斉王は孟子の言葉を聞かず、横を向いてしまいます。斉王もだんだん本性をあらわしてきたので、孟子はついに紂王のことを持ち出して、悪王は滅ぶべしとまで言って暗に斉王を批判した。それから燕の事件が起きて、結局斉王は天下の王の資格がなかったという落ちになっています。この並べ方は、意図的でしょう。
上田:孟子の言うことは、当時の斉の政策とは合わないのでしょう。
成田:孟子の主張が時代に合っていたかといえば、そうとはいえなかったでしょう。かなり時代錯誤の荒唐無稽な政策を、主張しています。当時は商業が発達して貨幣経済が進んだ時代であり、税についても関税や取引税が増えて富国強兵策が採用されていました。それを昔のように関税や市場税を取るな、というのは非現実的な献策です。
小田:関税や市場税を取らないので、孟子はもっぱら農民から税収を取ることを理想としました。それがいわゆる井田法で、これは土地に農民を縛り付けて画一的に割り当てて直接税を取る、農奴制です。孟子の言うことは、だんだん社会が活発になってきた戦国時代においては、時代遅れでした。後の漢代でも、銭による徴税が当たり前でした。関税や市場税は要所に役人を配置するだけで銭を簡単に徴収できるので、盛んに用いられました。
上田:であれば、この親爺さん、いまだにこんなことを言うとはと云う反応になる。
小田:孟子と斉王の回りには、国政をあずかる専門家たちも臨席していたはずでしょう。関税や市場税を撤廃するなどできるわけがないと、彼らは孟子の説を内心せせら笑っていたのではないでしょうかね。
成田:斉は隣国もあるわけで、人や物資の往来もあります。国際社会の中にあって一国のみ特殊な税制を採用することは、やりづらいものでしょう。日本も諸外国にならって消費税を取り入れました。
小田:他国にさきがけて関税や市場税を撤廃すれば、商工業者たちが仕事がやりやすいからと集まってくるという楽市楽座の政策ビジョンはありえます。しかし、孟子が楽市楽座を目指して関税市場税の撤廃を主張していたかといえば、そうではないでしょう。井田法に見られるように、孟子は商工業を抑えて農業社会に逆行させることを理想としていたはずです。
上田:ちょっと脱線ですが、消費税についてはどう思われますか。
成田:増税を好む人はいない。しかし経済は生産と消費によって成り立っており、消費に税をかけないのは、税収のバランスからすれば片寄りすぎるのではないでしょうか。
小田:そもそも所得税とか法人税とかの直接税というのは、戸籍を作って人民を管理する行政制度が前提です。ヨーロッパでも19世紀になるまで税はワインとか茶とか砂糖とかへの消費税と、輸入品への関税が主流でした。国にとって、これらがいちばん手っ取り早い税金収集法でした。19世紀以降、国民一人一人を能率的に管理して税金を集める管理社会が成立して以降、法人税と所得税が国家の税収の主役となりました。しかし孟子の時代では能率的な官僚制度など望むべくもなく、だから国家が手っ取り早く税収を得るためには、関税や市場税はむしろ最適解だったかもしれません。孟子は商工業を嫌い、素朴でお上を慕う農民主体の社会を理想としていたはずですが、現物税を全国から徴収するためには、必要な官僚制度を整備するコストは膨大であり、そしてその政策により配置した役人が清廉公正である保証はおそらくない。それならば、街道とか市場に担当者を置くだけで税収が得られる関税や市場税のほうが、公正は置いといて税収のための役人の数もずっと少なくて能率的ではないか、という見方もありえるでしょう。孟子は、たぶん農民からの現物徴収制度に必要な行政コストの問題を、無視しているのではないでしょうか。ずっと古代の素朴な時代を理想とするあまり、税収の能率を無視し、そして商工業が発達した戦国時代の社会の現実から意図的に目をそむけています。直接税の先進国であったヨーロッパでは、今や消費税に力点を移しています。文化を共有し、人も企業もさっさと隣国に移動することが当たり前となった現代のヨーロッパ諸国では、自国だけが高い直接税を採用したら速やかに人と企業が隣国に逃げます。だから、消費税に力点を置かざるをえず、どうしてもその比率が高まらずにはいられません。いっぽう、日本ではヨーロッパのように隣国と文化を共有いしているわけではなくて、日本の企業や国民がおいそれと香港やニューヨークに逃げるようなことはまずないわけで、その点でヨーロッパのように消費税を取らなければならない事情とは、わけが違う。今の日本の消費税増税は、別の必要性から見るべきです。私は、これは、これから急増する高齢者の社会福祉の支出増を、金を持っている高齢者の支出から負担してもらうシステムとみるべきだと思うのです。今の日本の若者は金を持っていないが、高齢者は持っている。支出は結局持てる財産に比例するわけだから、若者に低く高齢者に高い徴税をするために、消費税が適切であるという視点があるはずです。さて孟子に戻りますが、たぶん孟子は具体的な政策うんぬんについて細かいことを考えていたわけではなく、また王に進言したいことは、そういう具体的な政策内容ではなかったのではないでしょうか。むしろ、天下に王たることの心掛けを説き、王の性根を改めることに絞って説得を試みたのではないでしょうか。王がよき心がけをもてば、それが家臣と人民を感化して、天下が治まる。具体的な政策は、有能なテクノクラートにやらせればよい。その有能な人材を集める人徳を持つことが王のつとめであり、孟子は王にそれを目指せと言いたかったのでしょう。関税をどうの、市場税をどうのといった具体的なことは、その筋の専門家にやらせればよろしい。
成田:朱熹は、孟子を思想の書とみている。政治活動の記録として読んでいるわけではない。しかしこの書を残した孟子の気持ちがどうであったかと考えるならば、自分がやりたかったこと、こうすればうまくゆくはずだったという主張を残そうとしたのでしょう。だから、どの記録も微妙に言い訳じみている。しかしそれを朱熹は思想的に捉えるので、理路整然とした思想体系を王たちに述べた、と読み取ったのです。
小田:孟子は、当時の有名人でした。彼が斉で失敗したことは、皆が知っていたはずです。だから孟子としては、自分が言ったことやったことは間違っておらず、ただ時が悪かっただけだと主張しなければいけなかった。それは自分のための言い訳だけではなくて、儒家の親玉として儒家の体面を保つために、弁明をしておく必要があったから著作を残したのでしょう。孟子の後に出た儒家の荀子は、孟子の失敗を批判する立場にありました。だから孟子とは違って、儒家としての具体的な制度論を、詳しく述べました。孟子には、それが欠けていた。孟子は王の心を捉えることが戦略の主眼であって、体系的な政治システムを主張するのではなくて王を善人に導くという頂点からの改造に特化したと言えるでしょう。しかしそれではうまくいかなかったので、荀子はもっと具体的な理想の制度を儒家として説明することに努力しました。
上田:斉王が色を好む、というのはどうみますか。
小田:色を好むというのはネガティブな面で、人間としては褒められたことではない。斉王は、孟子から文王とかの聖王の昔話を聞かされたが、そんな「まんが中国昔ばなし」のような王様など、本当にいたのかと疑わずにはいられなかったのでしょう。先生は文王をやたらと称えるが、そんなのは「まんが中国昔ばなし」の登場人物であって、本当にそんな王が存在できるのですか?私は欲もある人間で、先生の言われる文王のような人間離れした存在ではありえませんよ、とからかいたかったのでしょう。そのからかいに対して、孟子は「いやいや、昔ばなしの王様もまた欲がある人だったけれど、ただその欲をうまく使っていたのですよ」と補足しました。
上田:論語に斉が歌舞音曲に秀でた美女達を魯に送り、季氏や定公が朝廷をさぼり、孔子は魯を出たという話があるが、この当時の斉にはそういう美女を揃えた遊戯場とか、女郎館はありましたか。
成田:あったでしょうが、王はわざわざ遊郭に行く必要などなくて、召せばよいわけです。
小田:趙の邯鄲とかは、歓楽都市として著名でしたね。各国の都市には、大なり小なり遊郭とかあったでしょうね。
上田:明堂を壊すか、維持するか当時懸案事項で皆が壊せとしていた。孟子は「王が王政をおこなうならば」と条件をつけて壊すなと回答した。皆の意見と違ったことになる。しかし、斉王は孟子の王政をからかっているようであり、孟子は、これでは王政の実現はおぼつかないと思っただろう。このままでは、孟子は壊さないことを助言してくれたになる。
成田:だから、斉で明堂を壊すか壊さないかについての議論において、私はこう言ったのだと記録を残したのです。
小田:孟子の著作は、斉の人々が最大の仮想読者だったのではないでしょうか。自分が深く関わっていた斉の朝廷人に向けて、自分の行為を記録して、正当性を主張した。趙岐によれば孟子は晩年に弟子たちと自著を編纂したということですが、孟子の晩年は、斉が最大勢力として盛んに侵略活動を行っていた頃です。孟子の死後まもなく、燕の楽毅が斉を滅亡寸前にまで追い込むわけですが、孟子の晩年にはまだひょっとすれば斉が天下を統一するかもしれない、という展望すらありえた。そんな時代の著作だと考えると、また別の見方もできるでしょう。
成田:天下統一した時には、仁徳をもって政治をしてください。それが遺言だった。
小田:孟子は斉の後に、宋や滕といった斉に侵略される側にも行って自説を主張しました。それは、自分の主張は斉のような超大国だけで通用するものではなくて、吹けば飛ぶような弱小国でも変わらず通用するものなのだ、ということを行動で示したのだと私は思います。強いが自説を容れなかった斉への、一種の当て付けでしょう。
上田:結果が分かって書くのと、分からない状態で書くのは大違い。孟子も思案しもって書いたのであろう。
小田:滕のような極小国は、孟子以外の文献ではどこにも出てきません。それをデカデカと書いて、斉とバランスを取っているかのようです。これは、思想的意地というべきものでしょうね。孟子は自分がこければ儒家がこけるため、自分への世間の悪い評判に対して、私のやったことには間違いないと主張しなければいけなかった。それが、彼の生前の精一杯の後世への弁明だったことでしょう。
上田:孔子の場合は弟子が編纂しており、そういうことはない。
小田:孔子の場合は、対立する思想家というものがいない時代でした。だから、孔子は思ったことをしゃべくれば、それでよかった。しかし孟子の時代は諸子百家の時代で、孟子の主張を挫こうとする敵がいっぱいいた。彼らとの論争で、孟子は負けるわけにはゆかなかった。
早川:遅れて来たのですが、久しぶりに今日はバスで孟子を読んでいました。この章などの孟子の話の組み立て方は、じつに見事ですね。しかし、実際の場で話したことをそのまま記したとは限らない。キケロというローマの雄弁家が、ある人の弁護をしたがうまくゆかなかった。後でその弁明を文章にして発表し、名声を得た。その文章を敗訴した当事者が読んだとき、「あのときにも、このように弁護してくれれば負けなかっただろうに」と言ったとか。斉王も、孟子の書を読んだらそう感想したかもしれませんね。「こんなふうにちゃんと言ってくれたら、よかったのに」と。
小田:孟子は、いろいろと論争していますが、有名人はあまりいない。有名どころでは、斉の淳于髠ぐらいでしょうかね。いちおう淳于髠には孟子が論争で勝ったことになっていますが、本当かどうかは分からない。孟子がやたらライバル視している告子などは、荀子の非十二子篇で主要な邪説家一覧の中に挙げられていない。告子をこんなに取り上げているのは、孟子だけです。ひょっとしたら、告子に限らず、孟子が論争して勝った敵は、大した人物がいなかったのかもしれませんなあ。
早川:というか、勝った記録だけ残したのでしょう。
小田:孟子と同じ時代の荘子とか恵施とかは、孟子がせっかく彼らの本拠であった宋にも行ったのに、触れられていません。彼らは論争するには手ごわ過ぎて、避けたのかもしれませんが。
久方振りに一揆へ。竹島、尖閣列島問題の遠因から将来まで。ビールに泡をふかせて終電まで。
岩倉紙芝居館 古典館 論語読書会 上田 啓之
.