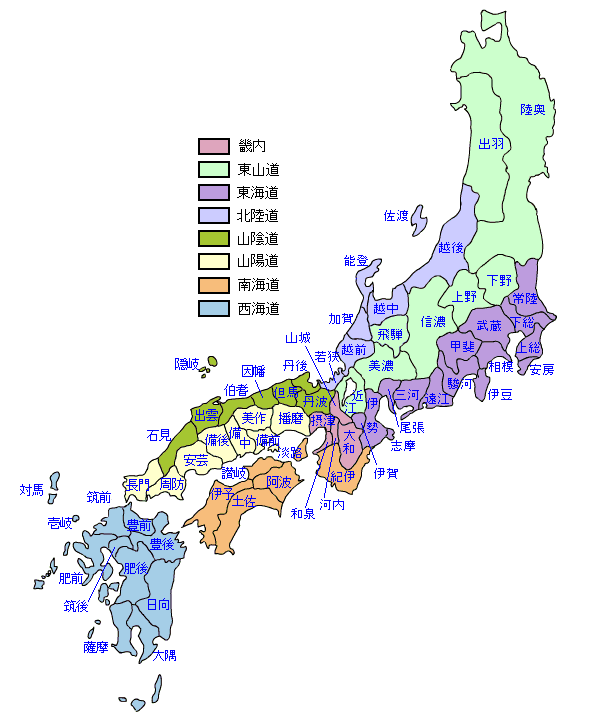![]()
橘豐日天皇 用明天皇
元年春正月壬子朔(586.01.01) ≫≫
二年夏四月乙巳朔丙午(587.04.02) ≫≫
泊瀨部天皇 崇峻天皇 ≫≫
元年春三月(588.03) ≫≫
二年秋七月壬辰朔(589.07.01) ≫≫
三年春三月(590.03) ≫≫
四年夏四月壬子朔甲子(591.04.13) ≫≫
五年冬十月癸酉朔丙子(592.10.04) ≫≫)
(岩波文庫 日本書紀 坂本太郎・家永三郎・井上光禎・大野晋 校注 を読む。)
橘豐日天皇(たちばなのとよひのすめらみこと) 用明天皇(ようめいてんわう)
橘豐日天皇 天國排開廣庭天皇第四子也 母曰堅鹽媛 天皇信佛法尊神道 十四年秋八月 渟中倉太珠敷天皇崩
九月甲寅朔戊午 天皇卽天皇位 宮於磐余 名曰池邊雙槻宮 以蘇我馬子宿禰爲大臣 物部弓削守屋連爲大連、並如故 壬申 詔曰 云々 以酢香手姬皇女 拜伊勢神宮 奉日神祀【是皇女 自此天皇時 逮乎炊屋姬天皇之世 奉日神祀 自退葛城而薨 見炊屋姬天皇紀 或本云 卅七年間 奉日神祀 自退而薨】
橘豊日天皇は、天国排開広庭天皇(あめくにおしはらきひろにはのすめらみこと)の第四子(よはしらにあたりたまふみこ)なり。母(いろは)をば堅塩媛(きたしひめ)と曰(まうす)す。天皇(すめらみこと)、仏法(ほとけのみのり)を信(う)けたまひ神道(かみのみち)を尊(たふと)びたまふ。十四年の秋八月(はつき)(585.08)に、渟中倉太珠敷天皇(ぬなくらのふとたましきのすめらみこと)崩(かむあが)りましぬ。
九月(ながつき)の甲寅(きのえとら)の朔(ついたち)戊午(つちのえうまのひ)(09.05)に、天皇、即天皇位(あまつひつぎしろしめす)す。磐余(いはれ)に宮つくる。名(なづ)けて池辺双槻宮(いけへのなみつきのみや)と曰(い)ふ。蘇我馬子宿禰(そがのうまこのすくね)を以(も)て大臣(おほおみ)とし、物部弓削守屋連(もののべのゆげのもりやのむらじ)をもて大連(おほむらじ)とすること、並(ならび)に故(もと)の如(ごと)し。壬申(みづのえさるのひ)(09.19)に、詔(みことのり)して曰(のたま)へらく、云々(しかしかのたまへり)、「酢香手姫皇女(すかてひめのみこ)を以て、伊勢神宮(いせのおほみかみのみや)に拜(め)して、日神(ひのかみ)の祀(まつり)に奉(つかへまつ)らしむ【是の皇女(ひめみこ)、此(こ)の天皇の時(みとき)より炊屋姫天皇(かしきやひめのすめらみこと)の世(みよ)に逮(およ)ぶまでに、日神の祀に奉る。自(みづか)ら葛城(かづらき)に退(しりぞ)きて薨(みう)せましぬ。炊屋姫天皇紀(みまき)に見ゆ。或本(あるふみ)に云(い)はく、三十七年(みそとせあまりななとせ)の間、日神の祀に奉る。自ら退きて薨せましぬといふ】。
渟中倉太珠敷天皇が崩御されたのが八月十五日、殯宮での馬子と守屋の嘲笑のやりとり、穴穗部皇子の天下取りの発言と物々しい展開であったはず。九月五日に橘豊日皇子が即位、その経緯について何等の説明もない。渟中倉太珠敷天皇(敏達天皇)の意中は、押坂彦人大兄皇子であったらう。押坂彦人大兄皇子にとっての不幸は、神か仏かいづれの祟りによるか判然とせぬ伝染病により、後継指名ができなく病死されたこと、また、母の広姫が既に他界され、皇后が堅塩媛の女(むすめ)、豊御食炊屋姫であられたこと。殯宮の儀式の主宰者が記されていないが、渟中倉太珠敷天皇との間に二男五女をもうけておられた皇后が主導されていたやうに思はれる。これは、後の事件からも想像される。それを政治的にバックアップしたのが、馬子であり、帯刀して弔辞をのべる馬子を守屋がこれを罵倒したのは、事の成り行きに異を唱へたものであらう。押坂彦人大兄皇子、竹田皇子の双方の可能性が封印され、天国排開広庭天皇と堅塩媛の子、豊御食炊屋姫の兄、橘豊日皇子を後継となし、馬子が大臣、守屋が大連といふ体制とすることで、合意が成立したのであらうか。
また、後の記述から想像すれば、橘豊日皇子は蘇我稲目の女(むすめ)、石寸名(いしきな)を娶っておられ、馬子の義理の弟の立場にあり、また、稲目の女(むすめ)堅塩媛の妹、小姉君の子、泥部穴穗部皇女も娶っておられ、天国排開広庭天皇と蘇我氏に深い姻戚関係を有しておられた。腹の虫が治まらないのが、堅塩媛の妹、小姉君の子、泥部穴穗部皇子であった。
天国排開広庭天皇(欽明天皇)
石姫
渟中倉太珠敷尊
→ 敏達天皇
堅塩媛
蘇我大臣稻目宿禰の女大兄皇子
豐御食炊屋姫
→ 用明天皇
→ 推古天皇
小姉君
堅塩媛の弟泥部穴穗部皇女
泥部穴穗部皇子
泊瀬部皇子→ 崇峻天皇
石寸名
蘇我大臣稻目宿禰の女渟中倉太珠敷天皇
(敏達天皇)広姫
(息長真手王の女)押坂彦人大兄皇子
*押坂彦人
大兄皇子の妃菟名子夫人
(伊勢大鹿首小熊が女)糠手姫皇女*
豐御食炊屋姫尊
竹田皇子
小墾田皇女*
尾張皇子
櫻井弓張皇女*大兄皇子
[橘豐日天皇]
(用明天皇)石寸名
蘇我大臣稻目宿禰の女田目皇子
広子
葛城直磐村が女麻呂子皇子
酢香手姬皇女當麻公の先
伊勢神宮に拝す穴穗部間人皇女
廐戸皇子
來目皇子
殖栗皇子
茨田皇子
神道が仏法に対応する語として用ゐられた。易経、観の卦の彖伝の、「盥(てあら)いて薦(すす)めず、孚(まこと)ありて顒若(ぎょうじゃく;うやうやしい)たりとは、下観て化するなり。天の神道を観るに四時忒(たが)はず、聖人神道をもって教を設けて、天下服す」によると注される。天の神道(霊妙なる働き、力)とは、天帝が四季をめぐらせ万物をはぐくむことの形容、聖人がその道によって万民を導くなら、万民はそれに感化され、天下は服す。この借り物の二文字、神道が日本人の神道となるのは、随分先のこと。書紀が編纂された頃には、編纂者周辺のみが知っていた言葉、”ほとけのみのり”に対する”かみのみち”とした。渟中倉太珠敷天皇は仏法を信けず、文史(しるしふみ)を愛(この)まれたが、橘豊日天皇は仏法を信け、神道を尊ばれた、と記した。
葦原中国は、「多くの蛍火かがやく神及びさばへなす邪し神、また、草木ことごとくよくものいふことあり(書紀巻2)」といふ状態にあり、それを平定したのが、大己貴神(大国主命)と海から来たその幸魂奇魂、大物主神、これを助けたのが高皇産霊尊の不肖の子、少彦名命。高皇産霊尊は、大己貴神に国譲りを迫り、予知力のある事代主神が大己貴神にそれが不可避であることを告げ、天神と国神の合意が成立した。大己貴神は幽界に去り、出雲に大社を建て祭られ、三輪の大物主神の妻に高皇産霊尊の女(むすめ)三穗津姫を配し手綱を締め、天孫を葦原中国に降ろし、この国の政の基本が定まった。”あまつかみ”と”くにつかみ”なら分かるが、それらの神々を畏敬することはあっても、そこに道dăoがあるといわれても、何のことか分からない。道といふは中国ではdăoで導の意味となり、神のお導きに従ふこと、ひたすら崇敬すればよろしい。神のお告げがあれば、大願成就せん。ならば、仏も崇敬すればよろしい、仏を崇敬すればご褒美に如意、なんでも思ふがままになるといふ功徳があるらしい、などと優劣を噂していたのかもしれない。
渟中倉太珠敷天皇の「百済大井に宮つくる」は、時と場所の両面で不確かなものがあった。四年の譯語田の幸玉宮が本格的な遷都であったらう。この譯語田については、巻向説と磐余説とがあった。池辺双槻宮の池辺は、和名抄の大和国十市郡の四郷(飯富、川辺、池上、神戸)の池上郷、大和志に十市郡の安部長門邑(桜井市阿部;地図)とする。双槻は槻(ケヤキの木)が並び立つ様で地名ではない、と注される。池辺は磐余池の池上の義であり、磐余池の場所は特定されていないが、その地名から、現在の桜井市南西部の池之内、橋本、阿部から橿原市の東池尻町を含む地域にあったとみなされている。2011年12月15日に、橿原市教育委員会は、「磐余池」とみられる人工池の堤の遺構と大型建物跡などが出土したと発表した。詳細は、現地説明会記録(橿原市~明日香村(磐余池堤跡~額田王墓)探訪(2011-12-17)②磐余池堤跡;長生きも芸のうち日記)に詳しい。推古天皇紀に、聖徳太子を「宮の南の上殿に居らしたまふ」とあり、上宮太子とも称されており、上宮は十市郡上宮村(桜井市上之宮)とされ、池辺宮はこの北に位置させねばならない。
さて、酢香手姫皇女を「伊勢神宮に拜して、日神の祀に奉らしむ」とある。橘豊日皇子と葛城直磐村女広子の間の皇女であり、すでに宮に事(つこうまつ)る年齢に達しておられたことになり、石寸名と同じく、即位前から娶っておられたことになる。天照大神とせず日神とするは、すでにみたごとく、仏に対するものとして、家臣も崇敬可能な古来の広い概念、日神をもって対応したものと思はれる。渟中倉太珠敷天皇七年に池辺皇子が伊勢の祠の菟道皇女を奸したとあった(書紀巻20)。池辺皇子を橘豊日皇子とみる説が有った。六年に設置した日祀部の権威を損ねる事件であった。斎の宮の皇女の振る舞いが問題を起こすことが時に記述されてきた。酢香手姫皇女が三十七年に及び無事に日神に事られたことは、日神に対する崇敬を高めることになったのであらう。その功が記された。
元年春正月壬子朔 立穴穗部間人皇女爲皇后 是生四男 其一曰廐戸皇子【更名豐耳聰聖德 或名豐聰耳法大王 或云法主王】 是皇子初居上宮 後移斑鳩 於豐御食炊屋姬天皇世 位居東宮 總攝萬機 行天皇事 語見豐御食炊屋姬天皇紀 其二曰來目皇子 其三曰殖栗皇子 其四曰茨田皇子 立蘇我大臣稻目宿禰女石寸名爲嬪 是生田目皇子【更名豐浦皇子】 葛城直磐村女廣子 生一男一女 男曰麻呂子皇子 此當麻公之先也 女曰酢香手姬皇女 歷三代以奉日神
元年(はじめのとし)の春正月(むつき)の壬子(みづのえね)の朔(ついたちのひ)(586.01.01)に、穴穗部間人皇女(あなほべのはしひとのひめみこ)を立て皇后(きさき)とす。是(これ)四(よたり)の男(ひこみこ)を生(あ)れます。其(そ)の一(ひとり)を廐戸皇子(うまやとのみこ)と曰(まう)す【更(また)は名(な)づけて豊耳聡聖徳(とよみみとしやうとく)といふ。或(ある)いは豊聰耳法大王(とよとみみののりのおほきみ)と名(な)づく。或いは法主王(のりのうしのおほきみ)と云(まう)す】。是の皇子(みこ)、初め上宮(かみつみや)に居(ましま)しき。後に斑鳩(いかるが)に移りたまふ。豊御食炊屋姫天皇(とよみけかしきやのひめのすめらみこと)の世(みよ)にして、東宮(みこのみや)に位居(ましま)す。万機(よろづのまつりごと)を総摂(ふさねかは)りて、天皇(みかど)事(わざ)行(し)たまふ。語(こと)は豊御食炊屋姫天皇の紀(みまき)に見ゆ。其の二(ふたり)を来目皇子(くめのみこ)と曰(まう)す。其の三(みたり)を殖栗皇子(ゑくりのみこ)と曰す。其の四(よたり)を茨田皇子(まむたのみこ)と曰す。蘇我大臣稲目宿禰(そがのおほおみいねめのすくね)の女(むすめ)石寸名(いしきな)を立てて嬪(みめ)とす。是(これ)田目皇子(ためのみこ)を生(う)めり【更(また)の名(みな)は豐浦皇子(とゆらのみこ)】。葛城直磐村(かづらきのあたひいはむら)が女(むすめ)広子(ひろこ)、一(ひとり)の男(ひこみこ)一(ひとり)の女(ひめみこ)を生めり。男をば麻呂子皇子(まろこのみこ)と曰す。此れ当麻公(たぎまのきみ)の先(おや)なり。女をば酢香手姫皇女(すかてひめのみこ)と曰す。三代(みつのよ)を歷(へ)て日神(ひのかみ)に奉(つかへまつ)る。
穴穗部間人皇女は、天国排開広庭天皇(欽明天皇)と小姉君の間の泥部穴穗部皇女のこと。穴穗部は、大泊瀬幼武天皇(雄略天皇)十九年(書紀巻14)に、大草香皇子の妻、眉輪王の母、穴穗天皇の皇后、妻、母、皇后のすべてを亡くす運命を辿られた中蒂姫に対して、大泊瀬幼武天皇がその名を残すために設置されたもの。蘇我氏がこの部を吸収していたことになるのか?間人は、皇女が蘇我氏と物部氏の争いの難を逃れて、蘇我氏の領地であったとも穴穂部の領地であったもされる丹後の「大浜の里」と呼ばれた今の 「後ケ浜」に避難され、お帰りに間人の名を賜はれ、畏れ多く、退座されことから、間人(たいざ、丹後町間人)と称するやうになったといふ伝承を残している(丹後半島独自の伝説ー「穴穂部間人皇后」伝説の真実)。
先に、今昔物語巻十一第一で、「八歳になった聖徳太子がひそかに日羅をみるために難波の館に出かけた」話をみた。太子の年齢はともかく、橘豊日皇子は、すでに穴穗部間人皇女を娶り、廐戸皇子等の御子を生んでおられたことになる。廐戸(うまやと)は元興寺露盤銘の「有麻移刀」、元興寺縁起の「馬屋門」「馬屋戸」、豊御食炊屋姫天皇(推古天皇)紀に、「皇后(穴穗部間人皇后)、懷姙開胎(みこあれま)さむとする日に、禁中に巡行(おはしま)して、諸司(つかさつかさ)監察(み)たまふ。馬官(うまのつかさ)に至りたまひて、乃ち廐(うまや)の戸に當りて、勞(なや)みたまはずして忽(たちまち)に産(あ)れませり」としている。生誕の場所による。豊耳聡聖徳の豊耳聡は、同上で、「一(ひとたび)に十人(とたり)の訴を聞きたまひて、失(あやま)ちたまはずして能く辨(わきま)へたまふ。」としており、豊耳(とよみみ)、豊は美称、よき耳、聡(と)のトは鋭の意、つまり聞き分ける鋭い耳(耳は人名にも用ゐられる、神渟名川耳)。天寿国繍帳銘では、「等巳刀弥々乃弥己等(とみとみみのみこと)」、元興寺丈六光背銘では、「等与刀弥々大王(とよとみみ大王)」と記され、豊聡耳ともされた。聖徳は、法起寺塔露盤銘の「上宮太子聖徳皇」、帝説の「聖徳王」「聖徳法王」「上宮聖徳法王」により、太子死後の諡号。法大王は、596年作の道後湯岡碑銘(釈紀所引伊予國風土記逸文中)の「法王大王(のりのおほきみ)」により、太子生前の名号。法主(のりのうし)は、仏典で、仏陀、説法者を意味する、と注される。
豊御食炊屋姫天皇(推古天皇)九年条に、「皇太子、初めて宮室を斑鳩に興(た)てたまふ」とある。斑鳩は、大和国平群郡(生駒郡斑鳩町)、現法隆寺東院(地図)が斑鳩宮の旧址と注される。豊御食炊屋姫天皇の時に、何故、廐戸皇子が東宮となり、天皇の摂政となられたかは、豊御食炊屋姫天皇紀をご覧あれとしている。
石寸名を嬪としたのは、蘇我大臣稻目宿禰の女であったこと、皇子をなしておられたことによらう。上宮記、帝説によれば田目皇子は橘豊日天皇崩御の後、穴穗部間人皇后を娶り、佐富女王を生んだ、豊浦は地名(高市郡明日香村豊浦)と注されており、相当早い時期に娶っておられたことにならう。
葛城直磐村が女広子については、古事記は、「當麻(たぎま)の倉首(くらのおびと)比呂(ひろ)の女(むすめ)、飯女(いひめ)の子(こ)を娶して、生みませる御子、當麻(たぎまの)王。次に妹須賀志呂古(すがしろこの)郎女(岩波文庫)」としている。原文は「比呂之女飯女之子」であり、比呂の女(むすめ)が飯女、その子を橘豊日皇子が娶ったといふ解釈になる。飯女之子(ひめしこ)と読めないことも無い。帝説は、葛木當麻倉首(かづらきのたぎまのくらのおびと)比里古女子(ひろこがむすめのこ)伊比古郎女(いひこのいらつめ)としている。理は乙類の”ろ”呂でもある。つまり飯子と釈した。当麻は地名(北葛城郡當麻村當麻、当麻都比古神社の地)。天国排開広庭天皇(欽明天皇)十七年条に、蘇我稲目が葛城山田直瑞子を児嶋郡の屯倉の田令に抜擢していた。同二十二年条に、葛城直が難波の大郡で賓客応接に従事しており、同三十一年条で、越に漂着した高句麗の使を迎へるために派遣されており、稲目の下で葛城氏が活用されていた。葛城山田直瑞子の系統は租税システム構築に貢献しており、当麻倉首の比呂(広)はこの線上にありさうだ。書紀は葛城直を磐村とし、その女(むすめ)を広子、つまり、当麻公は磐村の後であり、当麻倉首の比呂の後ではないとした、豊御食炊屋姫天皇十一年条に、来目皇子に代わって新羅を征(う)つ将軍となられた当麻皇子は、磐村の後であるしたことになる。蘇我氏の下で復権を図る葛城氏がそこをはっきりとさせやうとでもしたのであらうか。
夏五月 穴穗部皇子 欲姧炊屋姬皇后 而自强入於殯宮 寵臣三輪君逆 乃喚兵衞 重璅宮門 拒而勿入 穴穗部皇子問曰 何人在此 兵衞答曰 三輪君逆在焉 七呼開門 遂不聽入 於是 穴穗部皇子 謂大臣與大連曰 逆頻無禮矣 於殯庭誄曰 不荒朝庭 淨如鏡面 臣治平奉仕 卽是無禮 方今天皇子弟多在 兩大臣侍 詎得恣情 專言奉仕 又余觀殯內 拒不聽入 自呼開門 七𢌞不應 願欲斬之 兩大臣曰 隨命 於是 穴穗部皇子 陰謀王天下之事 而口詐在於殺逆君 遂與物部守屋大連 率兵圍繞磐余池邊 逆君知之 隱於三諸之岳 是日夜半 潛自山出 隱於後宮【謂炊屋姬皇后之別業 是名海石榴市宮也】 逆之同姓白堤與横山 言逆君在處 穴穗部皇子 卽遣守屋大連 【或本云 穴穗部皇子與泊瀨部皇子 相計而遣守屋大連】 曰 汝應往討逆君幷其二子 大連遂率兵去 蘇我馬子宿禰 外聞斯計 詣皇子所 卽逢門底【謂皇子家門也】 將之大連所 時諫曰 王者不近刑人 不可自往 皇子不聽而行 馬子宿禰 卽便隨去到於磐余【行至於池邊】 而切諫之 皇子乃從諫止 仍於此處 踞坐胡床 待大連焉 大連良久而至 率衆報命曰 斬逆等訖【或本云 穴穗部皇子、自行射殺】 於是 馬子宿禰 惻然頽歎曰 天下之亂不久矣 大連聞而答曰 汝小之所不識也【此三輪君逆者 譯語田天皇之所寵愛 悉委內外之事焉 由是炊屋姬皇后與馬子宿禰 倶發恨於穴穗部皇子】 是年也 太歲丙午
夏五月(さつき)に、穴穗部皇子(あなほべのみこ)、炊屋姫皇后(かしきやひめのきさき)を姧(をか)さむとして、而自(みづか)ら強(し)ひて殯宮(もがりのみや)に入る。寵臣(めぐみたまふまへつきみ)三輪君逆(みわのきみさかふ)、乃(すなは)ち兵衞(つはものとねり)を喚(め)して、宮門(みかど)を重璅(さしかた)めて、拒(ふせ)きて入れず。穴穗部皇子問ひて曰(い)はく、「何人か此(ここ)に在(はべ)る」といふ。兵衞答へて曰はく、「三輪君逆在り」といふ。七(ななた)び「門(みかど)開け」と呼(よば)ふ。遂に聴(ゆる)し入れず。是(ここ)に、穴穗部皇子、大臣(おほおみ)と大連(おほむらじ)とに謂(かた)りて曰はく、「逆(さかふ)、頻(しきり)に礼(ゐや)無し。殯庭(もがりのみや)にして誄(しのびごとたてまつ)りて曰(まう)さく、『朝庭(みかど)荒さずして、淨(きよ)めつかへまつること鏡の面(おもて)の如(ごと)くにして、臣(やつかれ)、治(をさ)め平(む)け奉仕(つかへまつ)らむ』とまうす。即(すなは)ち是礼(ゐや)無し。方(まさ)に今、天皇の子弟(みやから)、多(さは)に在(ま)す。両(ふたり)の大臣(おほまへつきみ)侍(はべ)り。詎(たれ)か情(こころ)の恣(ほしきまま)に、専(たくめ)奉仕らむと言ふことを得む。又余(われ)、殯内(もがりのみやのうち)を観むとおもへども、拒きて聴し入れず。自ら『門を開けよ』と呼(よば)へども、七回(ななたび)応(こた)へず。願はくは斬らむと欲(おも)ふ」といふ。両の大臣の曰(まう)さく、「命(みこと)の隨(まま)に」とまうす。是に、穴穗部皇子、陰(ひそか)に天下(あめのした)に王(きみ)たらむ事を謀(はか)りて、口に詐(いつは)りて逆君(さかふのきみ)を殺さむといふことを在(たも)てり。遂に物部守屋大連と、兵(いくさ)を率(ゐ)て磐余(いはれ)の池辺(いけのへ)を囲繞(かく)む。逆君知りて、三諸岳(みもろのをか)に隠(かく)れぬ。是(こ)の日の夜半(よなか)に、潜(ひそか)に山より出でて、後宮(さきのみや)に隠る。【炊屋姫皇后の別業(なりどころ)を謂(い)ふ。是を海石榴市宮(つばきいちのみや)と名(なづ)く】。逆(さかふ)の同姓(うがら)白堤(しらつつみ)と横山(よこやま)と、逆君が在(あ)る処(ところ)を言(つげまう)す。穴穗部皇子、即ち守屋大連を遣(や)りて 【或本(あるふみ)に云(い)はく、穴穗部皇子と泊瀬部皇子(はつせべのみこ)と、相計(あひたばか)りて守屋大連を遣るといふ】。曰(い)はく、「汝(いまし)往(ゆ)きて逆君と幷(あはせ)て其の二(ふたり)の子(こ)を討(ころ)すべし」といふ。大連、遂(つひ)に兵(いくさ)を率(ゐ)て去(ゆ)く。蘇我馬子宿禰(そがのうまこのすくね)、外(ほか)にして斯(こ)の計(はかりごと)を聞きて、皇子の所(みもと)に詣(まう)でしかば、即ち門底(かどもと)に逢ひぬ。【皇子の家(いへ)の門(かど)を謂ふ】。大連の所に之(ゆ)かむとす。時に諫(あさ)めて曰(まう)さく、「王(きみ)たる者(ひと)は刑人(つみびと)を近つけず。自(みづか)ら往(いでま)すべからず」とまうす。皇子、聴(き)かずして行(ゆ)く。馬子宿禰、即便(すなは)ち隨(したが)ひて去(ゆ)きて磐余(いはれ)に到りて、【行(ゆ)きて池辺に至るぞ】。切(たしか)に諫(いさ)む。皇子、乃ち諫(いさめこと)に從ひて止(や)みぬ。仍(よ)りて此の処(ところ)にして、胡床(あぐら)に踞坐(しりうた)げて、大連を待つ。大連、良(やや)久(ひさ)しくして至れり。衆(いくさ)を率て報命(かへりごとまう)して曰(まう)さく、「逆等を斬(ころ)し訖(をは)りぬ」とまうす。【或本に云はく、穴穗部皇子、自ら行きて射殺すといふ】。是(ここ)に、馬子宿禰、惻然(いた)み頽歎(なげ)きて曰(い)はく、「天下(あめのした)の乱(みだれ)は久しからじ」といふ。大連、聞きて答へて曰(い)はく、「汝(いまし)小臣臣(こまへつきみ)が識(し)らざる所なり」といふ。【此の三輪君逆は、譯語田天皇(をさだのすめらみこと)の寵愛(めぐ)みたまひし所なり。悉(ことごとく)に内外(うちと)の事を委(ゆだ)ねたまひき。是(これ)に由(よ)りて、炊屋姫皇后と馬子宿禰と、倶(とも)に穴穗部皇子を発恨(うら)む】。是年(ことし)、太歳丙午(ひのえうま)。
渟中倉太珠敷天皇(敏達天皇)十四年八月条で、「三輪君逆は、隼人をして殯の庭に相距かしむ。」とあった。三輪君逆は穴穗部皇子が炊屋姫皇后を奸して自分のものとする下心ありとみてとり、皇子が殯宮に入ることができぬやうに、近衛兵たる隼人で厳重に殯宮を警護し、自らもそこに籠った。しかし、最初から皇子が炊屋姫皇后を奸さうとしていたものではなかった。
皇子が五月にお参りをしやうとすると、入れてもらふことが出来なかった。誰がさういふ無礼なことを命じたかを聞くと、三輪君逆であるといふ。七度、門を開けるやうに大声を出しても開けない。穴穗部皇子が蘇我大臣と守屋大連に三輪君逆のこの無礼な行為を糾弾した。天皇の子弟が多くおられ、今大臣と大連もおられるといふに、誰だが自分勝手に門を閉じて平穏を保つと言ひ張る。だうして殯の内を観ることを許さないのか。七度申し入れて返答がない、殺してしまいたい、と言ふと、大臣と大連も「命の隨に」と言ふ。
渟中倉太珠敷天皇の寵臣であり、両者とも三輪君逆に何か腹にすえかねるところでもあったものか、この反応をみた穴穗部皇子は、大臣と大連も私の命に従うといふ、ならば渟中倉太珠敷天皇(敏達天皇)の皇后であった炊屋姫を自分のものとしてしまえば、天下に王たることができるのではないか、と踏んだやうである。
無礼者、三輪君逆を討つといふ口実をもって、何と守屋大連の兵とともに磐余の池辺を囲んだ。磐余の池辺は橘豊日天皇(用明天皇)の宮の地である、いかな皇子と守屋大連とはいへ、天皇の宮を囲むことはできまい。穴穗部皇子は蘇我系である、馬子が動かぬなか、物部守屋が加担するといふは一体だういふことか。逆君を討たうと思ふていた守屋に穴穗部皇子が乗せられたのか?頭が混乱する。
大臣と大連に見放され、大連の兵に攻められるとなれば、三輪君逆は、殯宮に居てはひとたまりもない。顛末を橘豊日天皇に報告し、根拠地の三輪山に隠れた。それを皇子と守屋大連が追ったのであらうか。三輪に辿りついてみると、もはや居なかった。白堤は延喜神名式の山辺郡白堤神社(延喜式神社の調査)の地、金屋から6km北であり、かなり広範囲な勢力を保つ族であったと思はれる。同族の白堤と横山が脅され居場所を告げたのであらう。三輪君逆は後宮、炊屋姫の別荘の地、海石榴市宮(桜井市金屋)に逃れていた。皇子は守屋大連を派遣して逆君とその子二人を殺させた。
これには異説があった。穴穗部皇子の弟の泊瀬部皇子と共に守屋大連を派遣したとするものがあった。穴穗部皇子と泊瀬部皇子の姉が穴穗部間人皇女、つまり、橘豊日天皇の皇后であり、蘇我馬子にとっては頭痛のする問題と化していた。渟中倉太珠敷天皇そして炊屋姫皇后の寵臣を、現皇后の兄が物部守屋に頼って殺させる、それに泊瀬部皇子まで同調しているとなれば、単なる跳ね上がりの暴挙ではすまない、蘇我一門の内紛となりかねない。ましてや、自らの手で逆君を殺すとなれば、怨みが蘇我一門にも及ぶ。
馬子は焦って穴穗部皇子を止めやうとした。皇子の家にゆくと、丁度皇子は守屋のところへ出向くところであった。馬子は皇子の自尊心をくすぐり、「王たる者は刑人を近づけず。自ら往すべからず」と説いた。これは、春秋公羊伝、襄公二十九年条、「君子は刑人に近づかず、刑人に近づくは則ち死を軽んず道なり」また、礼記、曲礼の、「刑人は君側に在(ま)さず」によると注される。儒家の考へ方を馬子が引用するとは考へがたく、かう修飾したのであらう。皇子は聴かず守屋と磐余に兵を進めており、馬子はそこまで出向いて、今度は、一転して、前天皇、皇后の側近を殺せば、お前の天皇への目は無くなるどころか、怨みは今度はお前に向かひ、お前を討たねばならなくなる、いい加減に目を覚ませとでも厳しく諌めたのであらう。
皇子は行かず、守屋が殺したとも、皇子が射殺したともいふ。大臣馬子の歎きに対して、守屋は、「汝小臣が識らざる所なり」、肝っ玉の小さいお前に分かってたまるものか、と誹った。馬子と炊屋姫が、守屋に利用され、一門に亀裂を走らせた穴穗部皇子に恨みを抱いたのは当然である。
二年夏四月乙巳朔丙午 御新嘗於磐余河上 是日 天皇得病 還入於宮 群臣侍焉 天皇詔群臣曰 朕思欲歸三寶 卿等議之 群臣入朝而議 物部守屋大連與中臣勝海連 違詔議曰 何背國神 敬他神也 由來 不識若斯事矣 蘇我馬子宿禰大臣曰 可隨詔而奉助 詎生異計 於是 皇弟皇子 【皇弟皇子者 穴穗部皇子 卽天皇庶弟】 引豐國法師 【闕名也】 入於內裏 物部守屋大連 邪睨大怒 是時 押坂部史毛屎急來 密語大連曰 今群臣圖卿 復將斷路 大連聞之、卽退於阿都、【阿都大連之別業所在地名也】 集聚人焉。中臣勝海連 於家集衆 隨助大連
二年の夏四月(うづき)の乙巳(きのとのみ)の朔(ついたち)丙午(ひのえうまのひ)(587.04.02)に、磐余(いはれ)の河上(かはかみ)に御新嘗(にひなへきこしめ)す。是の日に、天皇(すめらみこと)、得病(おほみここちそこな)ひたまひて、宮(みや)に還入(かへりおは)します。群臣(まへつきみたち)侍(はべ)り。天皇、群臣に詔(みことのり)して曰(のたま)はく、「朕(われ)、三宝(さむぽう)に帰(よ)らむと思(おも)ふ。卿等(いましたち)議(はか)れ」とのたまふ。群臣、入朝(まゐい)りて議る。物部守屋大連(もののべのもりやのおほむらじ)と中臣勝海連(なかとみのかつみのむらじ)と、詔の議(はからひ)に違(たが)ひて曰(まう)さく、「何(なに)ぞ国神(くにつかみ)を背(そむ)きて、他神(あたしかみ)を敬(ゐや)びむ。由来(もとより)、斯(かく)の若(ごと)き事を識(し)らず」とまうす。蘇我馬子宿禰大臣(そがのうまこのすくねのおほおみ)、曰(まう)さく、「詔に隨(したが)ひて助(ゐたす)け奉(まつ)るべし。詎(たれ)か異(け)なる計(はかりこと)を生(な)さむ」とまうす。是(ここ)に、皇弟皇子(すめいろどのみこ)【皇弟皇子といふは、穴穗部皇子(あなほべのみこ)、即(すなは)ち天皇の庶弟(はらから)なり。】豊国法師(とよくにのほうし)【名(な)を闕(もら)せり。】を引(ゐ)て、内裏(おほうち)に入(まゐい)る。物部守屋大連、邪睨(にら)みて大(おほ)きに怒(いか)る。是(こ)の時に、押坂部史毛屎(おしさかべのふびとけくそ)、急(あわ)て来(き)て、密(しのび)に大連に語(かた)りて曰(い)はく、「今群臣(まへつきみたち)、卿(うし)を図(はか)る。復(また)将(まさ)に路(みち)をたゐ)ちてむ」といふ。大連聞きて、即ち阿都(あと)に退(しりぞ)きて、【阿都は大連の別業(なりどころ)の在(あ)る所(ところ)の地(ところ)の名なり。】人を集聚(あつ)む。中臣勝海連、家(おのがいへ)に衆(いくさ)を集(つど)へて、大連を隨助(ゐたす)く。
大嘗祭式に、「凡て天皇十月下旬、川上に臨幸して禊を為す」とあり、三輪君逆を討つといふ事件の余波で昨年の秋には執り行うことができなかったと注される。天皇の得病は、このことと関係があるのかもしれない。「仏法を信けたまひ神道を尊びたまふ」天皇は、だういふことか、「三宝に帰らむ」とされ卿等に検討をさせられた。しかし、物部守屋大連と中臣勝海連は、天皇が国神に背かれるなど聞いたことがないとその詔を違へた。
ただ、穴穗部皇子は守屋の助けを得ていたが、馬子の意見に従ひ、豊国法師を連れ内裏に入った。豊国法師について、名をもらせりとしており、豊国は名前でなく、国名とみられるやうで、日本霊異記に、「客神の像(仏像)を豊国に棄流す」とあることから、昔から、豊前豊後の豊国、あるいは豊かな国=韓国=百済国とみる説がある。元興寺縁起に出て来ないので、豊国法師を創作とする説もある。書紀では、「眼炎の金・銀・彩色、多に其の国に在り。是を栲衾新羅国と謂ふ(足仲彦天皇「仲哀天皇」八年九月条)」とあり、後で丈六仏像と寺がでてくることからすれば、新羅国といふこともありえやう。天皇の詔を実現させるための三宝(仏、法、僧)の僧であり、当時は名の知れた僧であったはずで、何か名を伏せねばならない事情でもあったのかもしれない。
豊国法師を連れ込んだ穴穗部皇子に対して、守屋は激怒したやうである。ところが、今度は馬子は守屋が僧を捕へてしまうことを恐れ、そのやうな場合に、守屋の退路を断つための準備をしていた。これを守屋に伝へたのが、押坂部史毛屎であった。押坂は和名抄の大和城上郡恩坂(於佐加)郷、押坂部は刑部、誉田天皇(応神天皇)の時に帰化した七姓の漢人のうち李姓が刑部史の祖と注される。刑部(忍坂部)は、雄朝津間稚子宿禰天皇(允恭天皇)の皇后、忍坂大中姫命の為に定められた部であった。息長氏系の名門であり、押坂彦人大兄皇子の押坂もここからくるのであらう。押坂部史とはその部の史とならう。押坂彦人大兄皇子は渟中倉太珠敷天皇(敏達天皇)の嫡男であり、皇后の広姫が御存命であれば、次期天皇に最も近い立場であらせられたが、皇后となっておられた豊御食炊屋姫尊、馬子の政治力により、それが果たせなかった悲運の皇子である。毛屎といふ異臭を放つ名前であるが、強烈な臭気が邪霊災厄払いにつながるところから命名されたともいふ。ぷんぷんにおいのする情報を守屋にもたらした。一体だういふ意図で守屋にこの情報を秘かに伝へたものか。
守屋は別荘地の阿都、河内国渋川郡跡部郷(大阪府八尾市跡部:地図)に退いた。阿都は館を作り日羅を住まわせた阿斗桑市、河内国渋川郡跡部(阿止倍)郷(大阪府八尾市植松付近:地図)の地でもあり、渡来人が多い交通の要衝でもあった。守屋はここで兵を集めた。中臣勝海連はこれには合流せず、兵を集めて、守屋に従ひ助けたやうである。
遂作太子彦人皇子像與竹田皇子像厭之。俄而知事難濟、歸附彦人皇子於水派宮 【水派、此云美麻多】 舍人迹見赤檮 伺勝海連自彦人皇子所退 拔刀而殺 【迹見姓也 赤檮名也 赤檮、此云伊知毗】 大連 從阿都家、使物部八坂、大市造小坂、漆部造兄 謂馬子大臣曰 吾 聞群臣謀我 我 故退焉 馬子大臣 乃使土師八嶋連於大伴毗羅夫連所 具述大連之語 由是 毗羅夫連 手執弓箭皮楯 就槻曲家 不離晝夜、守護大臣 【槻曲家者 大臣家也】 天皇之瘡轉盛 將欲終時 鞍部多須奈 【司馬達等子也】 進而奏曰 臣 奉爲天皇 出家修道 又奉造丈六佛像及寺 天皇爲之悲慟 今南淵坂田寺木丈六佛像・挾侍菩薩是也。癸丑 天皇崩于大殿
秋七月甲戌朔甲午、葬于磐余池上陵。
遂(つひ)に太子(ひつぎのみこ)彦人皇子(ひとひこのみこ)の像(みかた)と竹田皇子(たけだのみこ)の像とを作りて厭(まじな)ふ。俄(しばらく)ありて事の済(な)り難からむことを知りて、帰(かへ)りて彦人皇子に水派宮(みまたのみや)に附(つ)く。【水派、此をば美麻多(みまた)と云ふ】。舍人(とねり)迹見赤檮(とみのいちひ)、勝海連の彦人皇子の所(みもと)より退くを伺(うかが)ひて、刀(たち)を拔(ぬ)きて殺しつ。【迹見(とみ)は姓(うぢ)なり。赤檮(いちひ)は名なり。赤檮、此をば伊知毗(いちひ)と云ふ】。大連、阿都の家(いへ)より、物部八坂(もののべのやさか)、大市造小坂(おほちのみやつこをさか)、漆部造兄(ぬりべのみやつこあに)を使(つかは)して、馬子大臣(うまこのおほおみ)に謂(かた)らしめて曰(い)はく、「吾(やつかれ)、群臣(まへつきみたち)我(おのれ)を謀(はか)ると聞けり。我、故(このゆゑ)に退く」といふ。馬子大臣、乃ち土師八嶋連(はじのやしまのむらじ)を大伴毗羅夫連(おほとものひらぶのむらじ)の所(もと)に使して、具(つぶさに)に大連の語(こと)を述べしむ。是(これ)に由りて、毗羅夫連、手に弓箭(ゆみや)、皮楯(かはたて)を執(と)りて、槻曲(つきくま)の家に就(ゆ)きて、昼夜(ひるよる)離(さ)らず、大臣を守護(まも)る。【槻曲の家は、大臣の家なり】。天皇の瘡(みやまひ)轉盛(いよいよさかん)なり。終(う)せたまひなむとする時に、鞍部多須奈(くらつくりのたすな)、【司馬達等(しめだちと)が子なり】。進みて奏(まう)して曰(まう)さく、「臣(やつかれ)、天皇の奉爲(おほみため)に、出家(いへで)して修道(おこな)はむ。又丈六(ぢやうろく)の仏像(ほとけのみかた)及び寺を造り奉(まつ)らむ」とまうす。天皇、爲(ため)に悲び慟(まど)ひたまふ。今南淵(みなぶち)の坂田寺(さかたでら)の木の丈六の仏像、挾侍(けふじ)の菩薩(ぼさち)、是なり。癸丑(みづのとのうしのひ)(04.09)に、天皇、大殿(おほとの)に崩(かむあが)りましぬ。
秋七月(ふみづき)の甲戌(きのえいぬ)の朔(ついたち)甲午(きのえうまのひ)(07.21)に、磐余池上陵(いはれのいけのへのみさざき)に葬(はぶ)りまつる。
厭(まじなふ)については、二人の像を傷つけて死を祈ると注されるがさうであらうか。事ならずとあり、勝海が殺すつもりであった「彦人皇子に帰附す(心を寄せる)」となる。呪い殺す者が殺す相手に帰附するといふは唐突であり、そのことで、守屋側でなく、馬子側の刺客により殺されており、解釈に苦しむ。
厭は祓ふことで、呪い殺す呪詛は道教や密教の呪符のごときものが入って以降のことと思はれる。厭は、「夫(かの)大己貴命、少彦名命(すくなびこなのみこと)と力を一心に戮(あは)せ、天下(あめのした)を經營(つく)る。復、顯見蒼生(うつしきあをひとくさ)及び畜産(けもの)を爲す。則ち病(やまひ)の方(みち)を定其療(をさむ)。又鳥獸(とりけだもの)昆蟲(はふむし)の災異(わざはひ)を攘(はら)ふ。則ち其の禁厭(まじなひやむ)の法(のり)を定む。是れを以て百姓(おほみたから)今に至り、咸(ことごとく)恩頼(みたまのふゆ)を蒙(かが)ふ」による。禁厭法は”まじなひ”し、害が”やむ”止む法。牲を供へて祀り、祈って禍害を圧服すること。「多くの蛍火かがやく神及びさばへなす邪し神、また、草木ことごとくよくものいふことあり(書紀巻2)」と自然界の邪神、邪精霊、害虫等を祓ふことであった。ここでは像を作って厭ふ、憑依した邪神、邪霊を祓ふやうな秘儀を中臣氏は心得ていたのであらう。
「遂に」とは、こうしなければならなくなって厭ふことになったといふことであらう。書紀は、ここで突如、太子彦人皇子と記した。書紀によくあるどんでん返しである。彦人皇子が太子となったことで厭を行った。病状の天皇が彦人皇子を太子にしたとは記されておらず、この状況で、彦人皇子を太子といふ立場に置くことが出来る者があるとすれば、先帝皇后の豊御食炊屋姫尊であり、馬子の意向を汲むものとみるほかあるまい。これは、あくまで非公式なものであり、また、虚報、敵を欺く流言の可能性もあり、信じ難い面があった。
押坂彦人大兄皇子がこれまで太子となれなかったのは、この二人に原因があったことはすでにみた。ところで、だういふことか太子であり、竹田皇子もそれに従っている。何故かういふことになったのか?
後継天皇問題で馬子は、穴穗部皇子と守屋と勝海の分断を謀った。彦人皇子を太子とするといふ噂をながしたのであらう。竹田皇子も同調させた。一方、穴穗部皇子にも後継者の可能性ありとし、守屋との関係を自制することを求め、天皇の病治癒で法師を同道することを求め、守屋との離反を策している。
馬子は押坂部史毛屎を用ひ、守屋に秘かに告げた情報は、守屋と勝海を分断する作戦とみえる。守屋は阿都に引き下がった。勝海は孤立し、心配となり、彦人皇子が本当に太子となり、次期天皇となり竹田皇子が太子となるようなことを止める事が出来るのか、厭ってみたが、止めることは難しいとでた。
勝海は考へ直してみた。押坂部史毛屎が守屋に秘かに告げた情報は、馬子と押坂彦人大兄皇子が示し合はせたものでなかったか。つまり、守屋と勝海を分断する作戦であったかもしれない。もし、彦人皇子が次期天皇となるなら、自分が道を誤ったかもしれない。守屋が阿都に入ったままでは自分は孤立する。勝海は穴穗部皇子次期天皇の可能性はないとみて、太子彦人皇子に帰附すべく水派宮に入った。
水派邑は、小泊瀬稚鷦鷯天皇(武烈天皇)三年条の「十一月に、大伴室屋大連に詔す、『信濃国の男丁を發して、城の像を水派邑に作れ。』 仍りて城上と曰ふ(書紀巻16)」にあるごとく、石組の施された城もどきの地、大和国広瀬郡城戸郷(北葛城郡広陵町、地図)と注される。しかし、この勝海の行動は読まれていた。勝海が水派宮から出たところで、迹見赤檮が勝海を斬り殺した。中臣勝海は後の中臣鎌足とは系統が異なり、気長足姫尊(神功皇后)時代の中臣烏賊津使主の子孫、山背国の葛野の歌荒樔田や磐余の田を与へ定着させられた壱岐や對馬の卜占者(弘計天皇:顯宗天皇三年条、書紀巻15)の卜占を継いだ氏族と思はれる。由緒のある神官が暗殺されたやうなものであり、その衝撃は大きかった。恐らく最初は誰に殺されたか分からなかったのであるまいか。下手人が分かれば、政権としてこれを捕縛し、罪を問はねばならない。
迹見赤檮は穴穗部間人皇后の子、廐戸皇子(後の聖徳太子)の舎人であった(迹見赤檮を彦人皇子の舎人とする説があるが、宮を出た所で暗殺するのは不自然、伝暦により廐戸皇子の舎人とする)。廐戸皇子は渟中倉太珠敷天皇(敏達天皇)三年(574年)生まれとされ、数えで14歳、まだ政治の現実にはかかはりなく、この皇子の舎人が殺したとはなかなか思ひつくまい。守屋との戦いに勝利したからこそ、迹見赤檮と名を明かすことが出来たが、成り行きによっては捨て駒にされたかもしれない。守屋は河内の阿都から、物部八坂(未詳)、大市造小坂(未詳)、漆部造兄(未詳)を、馬子のもとに使者として送り、かう意向を伝えた。河内に退き兵を集めていると私を非難しているやうであるが、「吾は、群臣が我を謀ると聞いた。我は、だから阿都に退いた」。勝海は暗殺された、お前達の仕業に相違あるまい(黙って見過ごすことはない)。書紀における物部氏は、石上神社の地、布留川の扇状地に拠を構へ、全国的な広がりを有する武の氏族である。河内の阿都と倭の石上の両方から攻められては、蘇我氏としては対応が難しい。
馬子は、土師八嶋連を大伴毗羅夫連の所に遣はし事の顛末を話し協力を求めた。武門の大伴氏の動向が鍵を握る。勝海が暗殺され、馬子等がかかはっていると疑はれる状況において、大伴氏を説得することは容易なことではない。馬子は土師八嶋連にこの役割を託した。土師八嶋連は今様の祖とされており、難波の宿館(鴻腫館)に出入りしていたやうである。「土師氏は、喪葬儀礼に深く携わり、葬歌の起源にも関与していたことが指摘されている。さらに楯伏舞を奉仕していたことも知られ、芸能・歌謡との関わりの深い氏族であった。そうした氏族から、歌の名手が出ることは故無しとしないが、さらに土師連その人が、ある公的な場所に宿泊していたー先の推測が正しいとすれば、外交の職掌をもって鴻腫館に出入りしていたーとすることによって、土師連の置かれた立場を重いものとし、今様の祖としての権威を持だせようとしたのではないだろうか(植木朝子氏、「今様起源譚の展開(HP)」)。」土師八嶋連は、『聖徳太子伝暦』 『梁塵秘抄口伝集』にとりあげられた人物であり、この世ならざるものをつき動かす今様の力を有していた。「土師連(八嶋)という歌の名手の身に起こった怪異現象に対して、聖徳太子のみせた能力を賞賛することに重点があり、螢惑星(火星)の精の出現が何か事の起こる予兆であると太子が見破ったことをこそ述べる『伝暦』に対し、『口伝集』は、今様の起こり・を土師連に求め、螢惑星の精が出現したのは、歌を愛でたためだとして、この世ならざるものをつき動かす今様の力を強調しており、聖徳太子の名をあわせて出すことで今様を権威づけようとする意図が明確である(前掲書)」。
おそらく決まり手となったのは、槻曲の家(場所未詳)に馬子が居り、太子彦人皇子を馬子が奉じていたことであらう、大伴氏の天皇家に対する篤い心を動かした。大伴毗羅夫は自ら弓箭、皮楯を執り、馬子を守護したとある。槻曲の家とは、三人の乙女尼に、邸宅の東に仏殿を造り、石の弥勒菩薩像を安置し、礼拝させた地である、仏法により天皇のご病状快癒祈願くらいのことは行はしめていたことであらう、「三宝に帰(よ)らむと思ふ」といふ天皇の御心に沿ふ行ひを妨害させてはならない、と毗羅夫が考へたとしてもおかしくない。それは、毗羅夫が陣営に加わったと同じ効果をもたらした。いづれにせよ、病床の橘豊日天皇(用明天皇)の穴穗部間人皇后と皇子も、馬子と豊御食炊屋姫尊の戦略に組み込まれていた。馬子は彦人皇子を取り込み、蘇我一門の離反者を守屋に推された穴穗部皇子に限定し、守屋の側から中臣氏を切り崩し、大伴氏の協力も取り付けることに成功した。
天皇の瘡(かさ、はれもの)とあり、天然痘とみられるやうである。馬子の意を受けてのことであらう、司馬達等の子、鞍部多須奈が、天皇の奉爲(おほみため)に、出家して修道し、丈六の仏及び寺を造りたいと申し出た。司馬達等については渟中倉太珠敷天皇(敏達天皇)十三年条是歳条(書紀巻20)でみた。鞍部多須奈が造ったものが南淵の坂田寺の木の丈六の仏像、挾侍の菩薩であるといふ。鞍部であり木工技術に長けており、木造の仏像、その脇に配される木造の菩薩像を造ることとなった。坂田寺は奈良県高市郡明日香村坂田(地図)の地にあり、以下に詳しい(仏教伝来の頃の飛鳥、両槻会事務局作製事策用資料、HP)。これらの甲斐虚しく、天皇は薨去された。磐余の池辺双槻宮の近く、磐余池上陵に葬られた。しかし、これは後に、河内に移されることになる。
結局、彦人皇子を太子とする詔は出ることがなかった。
泊瀨部天皇(はつせべのすめらみこと) 崇峻天皇(すしゆんてんわう)
泊瀨部天皇 天國排開廣庭天皇 第十二子也 母曰小姉君 【稻目宿禰女也 已見上文 也】 二年夏四月 橘豐日天皇 崩
五月 物部大連 軍衆 三度 驚駭 大連元欲去餘皇子等 而立穴穗部皇子爲天皇 及至於今 望因遊獵 而謀替立、密使人於穴穗部皇子曰 願與皇子 將馳獵於淡路 謀泄
六月甲辰朔庚戌 蘇我馬子宿禰等 奉炊屋姬尊 詔佐伯連丹經手、土師連磐村、的臣眞嚙曰 汝 嚴兵速往 誅殺穴穗部皇子與宅部皇子 是日夜半 佐伯連丹經手等 圍穴穗部皇子宮 於是 衞士 先登樓上 擊穴穗部皇子肩 皇子落於樓下 走入偏室 衞士等舉燭而誅 辛亥 誅宅部皇子【宅部皇子 檜隈天皇之子、上女王之父也 未詳】 善穴穗部皇子 故誅 甲子 善信阿尼等 謂大臣曰 出家之途 以戒爲本 願向百濟 學受戒法
是月 百濟調使來朝 大臣謂使人曰、率此尼等、將渡汝國 令學戒法 了時發遣 使人答曰 臣等歸蕃、先噵國主。而後發遣、亦不遲也
泊瀬部天皇は、天国排開広庭天皇(あめくにおしはらきひろにわのすめらみこと)の第十二子(とはしらあまりふたはしらにあたりたまふみこ) なり。母(いろは) をば小姉君(をあねのきみ)と曰(まう )す【稻目宿禰(いなめのすくね) の女(むすめ) なり。已(すで )に上文(かみのくだり)に見えたり】。二年の夏四月(うづき)に、橘豊日天皇(たちばなのとよひのすめらみこと)崩(かむあが) りましぬ。
五月(さつき)に、物部大連(もののべのおほむらじ)が軍衆(いくさ)、三度(みより)驚駭(とよ)む。大連(おほむらじ) 、元(もと) より余皇子等(あたしみこたち) を去てて、穴穗部皇子(あなほべのみこ) を立てて天皇とせむとす。今に至るに及びて、遊獵(かり) するに因(よ )りて、替(か )へ立つることを謀らむと望(おも)ひて、密(しのび) に人を穴穗部皇子のもとに使(つかひ )して曰(まう )さく、「願はくは皇子と、将(まさ )に淡路(あはぢ)に馳猟(かり)せむ」とまうす。謀(はかりこと) 泄(も)りぬ。
六月(みなづき)の甲辰(きのえたつ)の朔(ついたち)庚戌(かのえいぬのひ)(06.07)に、蘇我馬子宿禰(そがのうまこのすくね)等(たち)、炊屋姬尊(かしきやひめのみこと)を奉(あがめたてまつ)りて、佐伯連丹経手(さへきのむらじにふて)、土師連磐村(はじのむらじいはむら)、的臣真嚙(いくはのおみまくひ)に詔(みことのり)して曰(のたま)はく、「汝等等(いましら)、兵(いくさ)を厳(よそ)ひて速(すみやか)に往(ゆ)きて、穴穗部皇子と宅部皇子(やかべのみこ)とを誅殺(ころ)せ」とのたまふ。是(こ)の日の夜半(よなか)に、佐伯連丹経手等、穴穗部皇子の宮を囲(かく)む。是(ここ)に、衞士(いくさびと)、先(ま)づ楼(たかどの)の上(うへ)に登りて、穴穗部皇子の肩(みかた)を撃(う)つ。皇子、楼の下(しも)に落ちて、偏(かたはら)の室(や)に走(に)げ入(い)れり。衞士等(いくさびとら)、挙燭(ひとも)して誅(ころ)す。辛亥(かのとのゐのひ)(06.08)に、宅部皇子を誅す。【宅部皇子は、檜隈天皇(ひのくまのすめらみこと)の子(みこ)、上女王(かみつひめのおほきみ)の父(かぞ)なり。未(いま)だ詳(つばひらか)ならず】。穴穗部皇子に善(うるは)し。故(これ)誅(ころ)す。甲子(きのえねのひ)(06.21)に、善信阿尼(ぜんしんのあま)等(たち)、大臣(おほおみ)に謂(かた)りて曰はく、「出家(いへで)の途(みち)は、戒(い)むことを以(も)て本(もと)とす。願はくは、百済に向(まか)りて、戒(い)むことの法(のり)を学(なら)ひ受(う)けむ」といふ。
是(こ)の月に、百済の調(みつき)使(つかひ)来朝(まうけ)り。大臣、使人(つかひ)に謂(かた)りて曰(い)はく、「此(こ)の尼等(あまたち)を率(ゐ)て、汝(いまし)が国(くに)に将(ゐ)て渡(わた)りて、戒むことの法を学(なら)はしめよ。了(をは)りなむ時に発(た)て遣(まだ)せ」といふ。使人答へて曰(い)はく、「臣等(やつかれら)、蕃(くに)に歸(かへ)りて、先づ国主(くにのきみ)に噵(まう)さむ。而(しか)る後に発て遣(つかは)すとも、亦(また)遅(おそ)からじ」といふ。
泊瀬部天皇紀に入ったものの、まずは、橘豊日天皇崩御後の経緯を語る内容となっている。泊瀬部皇子(泊瀬部天皇)は穴穗部皇子の弟にあたる。結果からみれば、まことに皮肉な巡り合はせ、何故さやうなことになったのか。
驚駭(きょうがい)は驚愕と同じで、驚き恐れることであるが、”とよむ”と訓じている。鳴り響く、騒動することであるが、物部大連が何を三度何の為に驚駭したのか、当時の人はこれで分かったかもしれないが。通釈は上宮太子拾遺記に引く元興寺縁起に、「三度驚駭天皇喪」とあることから、天皇喪を補って解釈すると注される。四月の二日に天皇は崩御され、穴穗部皇子が豊国法師を連れて供養をしやうとされたことを守屋が怒って睨みつけた時、押坂部史毛屎が包囲されており逃げなさいとと秘かに告げたとあった。河内の阿都に撤退するに際して、三度驚駭したのかもしれない。
後継に該当する皇子は沢山おられる。天国排開広庭天皇(欽明天皇)、渟中倉太珠敷天皇(敏達天皇)の皇子達(書紀巻20)は多い。去は捨てる義である、他の皇子をすべて殺すとみるは行き過ぎであらう。守屋が穴穗部皇子を最有力候補として、安全を守るために、皇子を阿都に迎へるため秘かに、淡路(天皇のお狩場)に遊猟(かり)することを求めた。しかし、謀り事は漏れたとあり、うまくゆかなかった。五月のことであった。
六月早々に、馬子が炊屋姫尊を奉じて詔をしたといふ。炊屋姫尊は、渟中倉太珠敷天皇の皇后、橘豊日天皇の妹といふお立場であり、影響力がおおきいとしても、その意向であるとして馬子が発した言葉が詔となるものではない。「穴穗部皇子と宅部皇子とを誅殺(ころ)せ」といふを、正当化するために詔と記したのであらう。
【宅部皇子(やかべのみこ)は、檜隈天皇の子、上女王の父なり。未だ詳ならず】とある。檜隈天皇は、都を檜隈廬入野に移した武小広国押盾天皇(宣化天皇)であり、檜隈坂合陵に葬られた天国排開広庭天皇とするのは誤りと注される。しかし、武小広国押盾天皇の子としてはここ以外には記されておらず、上女王もみえない。むしろ、広国押武金日天皇(安閑天皇)が物部木蓮子(いたび)大連の女(むすめ)、宅媛(やかひめ)を妃としていた(書紀巻18)。宅部皇子は、この系統の、物部系であったとみてはいかがなものか。宅部皇子は穴穗部皇子と仲が良かったとあり、刺客から守る意味でも、手勢を率ゐてその宮に入っていたものであらう。そのことは双方に分かっていたやうである。厳兵となれば、刺客ではなく、厳重に宮を囲んで討ち果たす規模の兵力であり、一気に事を決する構へである。穴穗部皇子を救援しやうとする奈良盆地の勢力、阿都の守屋が動き出す前に勝負を終へてしまはねばならない。穴穗部皇子と宅部皇子はそこまでやるとは思っていなかったかもしれない。百済の調使来朝のこともあり、その前に決着をつけねばならないといふ政治日程もあった。
佐伯部の祖は、日本武尊が連れ帰った蝦夷、本来は隼人同様に、宮中の警護、警備を担当させるつもりであったが、熱田神宮で騒ぎ、三輪山に移されそこでも騒ぎ、播磨・讃岐・伊豫・安藝・阿波に移された者がこの五国の佐伯部の祖となった(書紀巻7)。大泊瀬幼武天皇(雄略天皇)前紀における市辺押磐皇子の従者、佐伯部売輪(さへきべのうるわ)、更名仲手子(なかちこ)がみえる。仲手子は平成時代でいへばSP(要人警護)のやうな役割であった。白髮武広国押稚日本根子天皇(清寧天皇)二年(書紀巻15)に、大伴室屋は、白髮部舎人・白髮部膳夫・白髮部靭負の設置を命じられた。主として東国国造の子弟から白髮天皇に仕へる舎人をとり、膳夫は料理関係、靭負は靫を負うて宮廷諸門を警護する集団である。かくて、大伴氏が抜刀人(武官)の長となった。室屋の子の談(かたり)は半島で戦死するのであるが、その子の歌(うたふ)が佐伯部を統轄する役割を以て大伴氏からわかれ、それを引き継いで中央の佐伯連となったとみられている。
大伴毗羅夫は警備、警護はしたが、動かなかった。佐伯連丹経手は、未詳であるが、炊屋姫尊の命で動く立場にあったのかもしれない。
土師連磐村は土師八嶋連の弟(米子・山陰の古代史)、土師八嶋連は文人であり馬子が大伴毗羅夫への使者としており、土師連磐村は武人として、馬子の意を受けて動いていたと思はれる。
的臣は葛城襲津彦の子孫、葛城の武人の系譜である。馬子が全体の枠組みをつくり、炊屋姫尊を表にたてて、佐伯連丹経手に統括させていたやうである。馬子と守屋であれば、同レベルとなるが、炊屋姫尊と穴穗部皇子となれば、格があまりに違ふ。馬子の構想力、政治力は守屋をはるかに越えていた。ここで、穴穗部皇子を失へば、守屋は賊軍となる、味方する勢力を結集する旗頭を失ふことになる、まさか、馬子が穴穗部皇子を殺すとは思っていなかったのであらう。
馬子の父、稲目の女(むすめ)、小姉君の子であり、橘豊日天皇の皇后、穴穗部間人皇女の弟である穴穗部皇子である。捕へて監禁することはあっても、殺すことはないであらう。馬子の妻は守屋の妹であり、元来は二人で政権を運営すべきものであった。その歯車が狂って、ここまできてしまった。
結果からすれば、守屋がその背景になければ、穴穗部皇子は命を失ふことはなかった。穴穗部皇子と宅部皇子は「誅殺」されたとあり、賊として殺され、守屋も賊となった。
百済の調使来朝の儀を馬子は、天皇不在のところ、炊屋姫尊をたてたのであらう、滞りなく済ませたやうである。善信阿尼等が、この機をとらえて、百済において戒(律)を学びたいと申し出たこと、百済側は帰って国主の意向を伺ってから返答をするとしたことを記している。調使一行は阿都近辺を通って来たであらうし、危険であるから帰国を控えたといふこともなささうである。日本(やまと)は平穏であって、馬子が大臣として、大連なしに治まっていたかのごとき印象を残した。最早、この時点で、守屋は追い込まれていた。
秋七月 蘇我馬子宿禰大臣 勸諸皇子與群臣 謀滅物部守屋大連 泊瀨部皇子、竹田皇子、廐戸皇子、難波皇子、春日皇子、蘇我馬子宿禰大臣、紀男麻呂宿禰、巨勢臣比良夫、膳臣賀拕夫、葛城臣烏那羅、倶率軍旅、進討大連 大伴連嚙、阿倍臣人、平群臣神手、坂本臣糠手、春日臣、【闕名字】 倶率軍兵 從志紀郡 到澁河家 大連親率子弟與奴軍 築稻城而戰 於是 大連昇衣揩朴枝間 臨射如雨 其軍强盛、塡家溢野 皇子等軍與群臣衆(いくさ)、怯弱恐怖 三𢌞却還
秋七月(ふみづき)に、蘇我馬子宿禰大臣(そがのうまこのすくねのおほおみ)、諸皇子(もろもろのみこたち)と群臣(まへつきみたち)を勧(すす)めて、物部守屋大連(もののべのもりやのおほむらじ)を滅(ほろぼ)さむことを謀(はか)る。泊瀬部皇子(はつせべのみこ)・竹田皇子(たけだのみこ)・廐戸皇子(うまやとのみこ)・難波皇子(なにはのみこ)・春日皇子(かすがのみこ)・蘇我馬子宿禰大臣・紀男麻呂宿禰(きのをまろのすくね)・巨勢臣比良夫(こせのおみひらぶ)・膳臣賀拕夫(かしはでのおみかだぶ)・葛城臣烏那羅(かづらきのおみをなら)、倶(もろとも)に軍旅(いくさ)を率(ゐ)て、進みて大連を討つ。大伴連嚙(おほとものむらじくひ)・阿倍臣人(あへのおみひと)・平群臣神手(へぐりのおみかむて)・坂本臣糠手(さかもとのおみあらて)・春日臣(かすがのおみ)【名字(な)を闕(も)らせり】、倶に軍兵(いくさ)を率て、志紀郡(しきのこほり)より、渋河(しぶのかは)の家(いへ)に到る。大連、親(みづか)ら子弟(やから)と奴軍(やつこいくさ)とを率て、稲城(いなき)を築(つ)きて戦ふ。是(ここ)に、大連、衣揩(きぬすり)の朴(えのき)の枝間(また)に昇りて、臨(のぞ)み射ること雨の如(ごと)し。其の軍(いくさ)、強(こは)く盛(さかり)にして、家に塡(みち)ち野に溢(あふ)れたり。皇子等(みこたち)の軍と群臣(まへつきみたち)の衆(いくさ)と、怯弱(よわ)くして恐怖(おそ)りて、三𢌞(みたび)却還(しりぞ)く。
七月に入り、馬子は守屋討伐を謀った。泊瀬部皇子を筆頭に記している。穴穗部皇子の弟を後継者の筆頭としたことを意味している。馬子と炊屋姫尊の間でさう決まったのであらうか。しかし、五月時点では、泊瀬部皇子は穴穗部皇子と一緒に逆君を守屋に討たしめていた。その疑ひを晴らす必要があり、その器量を示さねばならない。また、戦闘のなかでは何が起こるか分からない。守屋との戦いに勝利して、後継者と認知されねばならなかった。
竹田皇子は渟中倉太珠敷天皇(敏達天皇)と炊屋姫尊の子、廐戸皇子(後の聖徳太子)は、橘豊日天皇(用明天皇)と穴穗部間人皇女の子、難波皇子・春日皇子は、渟中倉太珠敷天皇と春日臣仲君の女(むすめ)、老女子夫人との子である。
不可解なのは、渟中倉太珠敷天皇の嫡男、息長真手王の女、広姫との子、押坂彦人大兄皇子である。「遂に太子彦人皇子の像と竹田皇子の像とを作りて厭ふ。」とされたはずの押坂彦人大兄皇子が筆頭であるべきだが、除外されている。太子彦人皇子といふは謀略であったとしか思はれない。
馬子は、紀氏、巨勢氏、膳氏、葛城氏、大伴氏、阿倍氏、平群氏、坂本氏、春日氏、また、佐伯氏、土師氏、的氏も含まれているのであるから、多数の豪族を参加せしめている。中臣氏は勝海が討たれていた。石川氏は蘇我系であり、畿内で残る有力豪族といえば穂積氏、息長氏、三輪氏、日下部氏くらいのものである。
紀男麻呂宿禰は天国排開広庭天皇(欽明天皇)二十三年(562年)七月に新羅を討つために百済に派遣された大将軍であったが、25年前のことであり年齢的には高齢であり、実戦の指揮をとるといふよりは、象徴的な存在であらう。
圧倒的多数の軍勢であるが、実戦の作戦を立て、指揮をとる核に難があったやうである。志紀郡は河内国志紀郡(八尾市志紀町;地図)あたり、渋河はその西北約3kmの地。物部氏は子弟(やから)と奴軍(やつこいくさ)の軍、子(こ)や族(やから)、家来(やつこ)、奴を守屋が私有する奴隷と注されるが、奴隷から戦闘員に抜擢された者はあらうが、奴隷を軍事訓練し武器をもたせ、軍団とするといふは非現実的である。物部氏は全国的に分布する氏族であり、子と族だけでも相当であり、これに家来(やつこ)として組み込まれた地方氏族ではないか。
守屋自らが先頭に立つ物部軍の気迫が勝っていた。稲城は、弓矢の攻撃から身を守るものであらう。守屋は衣揩(東大阪市衣揩:地図)に誘い込み、高い位置から雨の如く矢を射かけた。盾以外に矢を遮るものがなかったとみえ、稲城から放たれる矢に苦しんだのであらう、三度攻めて三度怯んで退却を余儀なくされた。
是時 廐戸皇子 束髮於額 【古俗、年少兒年 十五六間 束髮於額 十七八間 分爲角子 今亦然之】 而隨軍後 自忖度曰 將無見敗 非願難成 乃斮取白膠木 疾作四天王像、置於頂髮、而發誓言、【白膠木 此云農利泥】。今若使我勝敵、必當奉爲護世四王 起立寺塔。蘇我馬子大臣 又發誓言 凡諸天王、大神王等 助衞於我 使獲利益 願當奉爲諸天與大神王 起立寺塔 流通三寶 誓已嚴種種兵 而進討伐 爰有迹見首赤檮 射墮大連於枝下、而誅大連幷其子等 由是 大連之軍 忽然自敗 合軍悉被皁衣、馳獵廣瀨勾原而散之 是役 大連兒息與眷屬 或有逃匿葦原 改姓換名者 或有逃亡不知所向者。時人相謂曰 蘇我大臣之妻 是物部守屋大連之妹也 大臣妄用妻計、而殺大連矣 平亂之後 於攝津國、造四天王寺。分大連奴半與宅 爲大寺奴、田荘 以田一萬頃 賜迹見首赤檮 蘇我大臣 亦依本願、於飛鳥地 起法興寺
是の時に、廐戸皇子、束髮於額(ひさごはな)して【古(いにしへ)の俗(ひと)、年少兒(わらは)の年、十五六(とをあまりいつつむつ)の間(あひだ)は、束髮於額(ひさごはな)す。十七八(とをあまりななつやつ)の間は、分(わ)けて角子(あげまき)にす。今亦(また)然(しか)り】 軍(いくさ)の後(うしろ)に隨(したが)へり。自(みづか)ら忖度(はか)りて曰(のたま)はく、「将(はた)、敗(やぶ)らるること無(な)からむや。願(ちかひこと)に非(あら)ずは成し難(がた)けむ」とのたまふ。乃(すなは)ち白膠木(ぬりで)を斮(き)り取りて、疾(と)く四天王(してんわう)の像(みかた)に作りて、頂髮(たきふさ)に置きて、誓(ちかひ)を発(た)てて言(のたま)はく、【白膠木、此をば農利泥(ぬりで)といふ】 「今若(も)し我(われ)をして敵(あた)に勝たしめたまはば、必ず護世四王(ごせしわう)の奉爲(みため)に、寺塔(てら)を起立(た)てむ」とのたまふ。蘇我馬子大臣(そがのうまこのおほおみ)、又誓(ちかひ)を発てて言(い)はく、「凡(おほよ)そ諸天王(しよてんわう)、大神王等(だいじんわうたち)、我を助け衞(まも)りて、利益(か)つこと獲(え)しめたまはば、願(ねが)はくは当(まさ)に諸天と大神王との奉爲(みため)に、寺塔を起立てて、三宝(さむほう)を流通(つた)へむ」といふ。誓(ちか)ひ已(をは)りて種種(くさぐさ)の兵(いくさ)を厳(よそ)ひて、進みて討伐(う)つ。爰(ここ)に迹見首(とみのおびと)赤檮(いちひ)有りて、大連を枝(え)の下(もと)に射墮(いおと)して、大連幷(あはせ)て其(そ)の子等(こども)を誅(ころす)す。是(これ)に由(よ)りて、大連の軍(いくさ)、忽然(たちまち)に自(おの)づからに敗(やぶ)れぬ。軍(いくさ)合(こぞ)りて悉(ことごとく)に皁衣(くろきぬ)を被(き)て、広瀬(ひろせ)の勾原(まがりのはら)に馳獵(かりするまね)して散(あか)れぬ。是(こ)の役(えだち)に、大連の児息(こ)と眷属(やから)と、或(ある)いは葦原(あしはら)に逃げ匿(かく)れて、姓(うぢ)を改め名を換(かた)ふる者有り。或いは逃(に)げ亡(う)せて向(い)にけむ所を知らざる者有り。時の人、相謂(あひかた)りて曰(い)はく、「蘇我大臣の妻(つま)は、是(これ)物部守屋大連の妹(いりも)なり。大臣、妄(みだり)に妻の計(はかりこと)を用(もち)ゐて、大連を殺せり」といふ。乱(みだれ)を平(しづ)めて後(のち)に、攝津国(つのくに)にして、四天王寺(してんおうじ)を造る。大連の奴(やつこ)の半(なかば)と宅(いへ)とを分けて、大寺(おほでら)の奴、田荘(たどころ)とす。田一万頃(たよろずしろ)を以(も)て、迹見首赤檮に賜ふ。蘇我大臣、亦(また)本願(もとのねがひ)の依(まま)に、飛鳥(あすか)の地(ところ)にして、法興寺(ほふこうじ)を起(た)つ。
廐戸皇子が、束髮於額(ひさごはな)してとあり、まだ髪を両方に分けて角子(あげまき)にしない前の年齢のときに、従軍していた。十五、六歳とみなされたことになる。廐戸皇子は形勢が不利、人力では勝つことは難しいと発言された。この前後の戦いの様子は、太子伝補闕記、伝暦に詳しく記されるが、多くは後世の潤色で、骨子は書紀以上に出ないと注される。物部軍に追われた廐戸皇子が椋の木の下で念ずると大木が二つに割れて太子の身を隠した(大聖勝軍寺 大阪府八尾市)とあり、命からがら逃げ延びたとする伝承があったのだらう。磐余彦尊(神武天皇)が孔舎衞之戰で、大きなる樹に於て隱れて難を免がれた故事になぞらへたのであらう(書紀巻3)。一旦奈良盆地まで退却せざるを得なかったやうである。
束髮於額の具体的な格好は分からないが、髪を束にして、一旦、頭のてっぺんでくくり、いくつかに分け、丸めて再度くくり直して、瓢(ひさご)の花(はな)びらのやうにみせたのかもしれない(例;公家童子、那些充?童趣的文物)。年少児の格好、十五、六歳までとされた。髪が十分長くなると左右に分けて、耳のあたりで巻き上げこんもりまとめた(あげまき)。角子、角髪、総角などと記される(例;みずら祭)。いわば青年、大人(十七、八歳)とみなされ、”みずら”とも称され、スタイルは色々工夫され競はれた。束髮於額で従軍されることは、普通ではなく、また、その取られた行動にも、年少のものとは思へないものがあった。非常、非凡なる資質を暗示している。(左掲載写真;瓢の花)
白膠木を切り取って、素早く四天王(東方持国天、南方増長天、西方広目天、北方多聞天)の像を作り、束髮於額の前後左右に置き、敵に勝たしめば、護世四王の寺を建立すると発願された。白膠木は勝軍木とも称された。この木の乳液で修法の壇が塗られ、仏像の心木に用ゐられた霊木、と釈紀述義に注され、民俗に、この木で刀を作り戸口に置くと邪気を払うと注される。馬子は、諸天と大神王(大弁天神、尼連河神、鬼子母神、地神堅牢大梵尊天、三十三天、大神竜王)に発誓をして(利益とは仏教用語で他を利すること、ここでは勝つことができると訓じている)、寺を建立し三宝を伝道するとした。
仏法の威力かくの如しと思はせるが、これは混成軍の動揺を鎮め、ひとつにするための出直し祈願。この戦を分けたものは、馬子の妻、守屋の妹の助言であった。妹は、守屋一人を倒せば、全軍が総崩れになると進言したのであらう。馬子は守屋の居場所を探り、刺客を放った。中臣勝海連を暗殺した廐戸皇子の舎人、迹見首赤檮であった。廐戸皇子は、仏法に発願する一方で、中臣勝海連、物部守屋大連に刺客を放つといふ、恐るべき年少児であったかもしれない。赤檮は、馬子の妻、守屋の妹の手の者を通じて守屋の陣内に潜り込んだのであらうか、木の上から矢を射かける守屋の姿とその子等の居る場所の近くから、守屋を射落し、子等を斬り、とどめを刺し、あっといふまに逃亡したものか(守屋の首をはねたのが秦河勝ともいふ、赤檮単独ではなかった)。(逆臣を)誅すとあり、これは暗殺ではないとした。
総崩れとなった物部軍は皁衣を纏った、黒衣であり、家人、奴婢の衣であり、卑賤の者に身をやつす、あるいは狩のふりをして逃げた。児息(子)と眷属(親族、配下)が散り散りとなり、姓(うじ)名(な)を変へた。或はどこに逃げ込んだか分からない者もいたとするから、守屋の所領、河内国弓削、鞍作、祖父間、衣揩、虵艸、足代、御立、葦原(四天王寺御手縁起)から駆逐されたとみえる。
馬子は、飛鳥の地に、法興寺を建立した。これが普通である、何故、攝津国に、四天王寺を造ったのか。守屋の宅を大寺にし、半分の奴を大寺の奴とし、半分を田荘の奴としたといふことか。宅とは、次にある捕鳥部万の守っていた守屋の難波宅にあたり、当初は、物部氏を弔ふためのものであったとする説をとりたい。仏法嫌いの守屋の宅を寺に見立て供養するとはみせしめのやうなものである。場所は、摂津の玉造(大阪城の東南角の岸)と見られている。豊御食炊屋姫天皇(推古天皇)元年条に、「始めて四天王寺を難波の御陵に造る」、三十一年条に、新羅からの「舎利、金塔、観頂幡等を以て、皆四天王寺に納る」とある。難波の御陵とあり、豊御食炊屋姫天皇時代になってから、太子がその御陵のところに新たに寺(荒陵寺)、後の四天王寺を建立したとならうか。田一万頃を以て、迹見首赤檮に賜った。頃は、中国の地績の単位で百畝と注される。百畝は9917平米(約百メートル四方)、一万頃は約10km四方となる土地(中国的スケールで非現実的、広大の義か)。赤檮が押坂彦人大兄皇子の舎人であるなら、押坂彦人大兄皇子の存在がここでクローズアップされるべきであるが、全く言及がない。伝暦が赤檮を廐戸皇子の舎人とする説をとりたい。
物部守屋大連資人捕鳥部萬 【萬名也】 將一百人 守難波宅 而聞大連滅 騎馬夜逃 向茅渟縣有眞香邑。仍過婦宅 而遂匿山。朝庭議曰 萬懷逆心 故隱此山中 早須滅族 可不怠歟 萬 衣裳幣垢 形色憔悴 持弓帶劒、獨自出來 有司遣數百衞士圍萬 萬卽驚匿篁藂 以繩繋竹 引動令他惑己所入 衞士等被詐 指搖竹馳言、萬在此 萬卽發箭 一無不中 衞士以繩繋等恐不敢近 萬便弛弓挾腋 向山走去 衞士等卽夾河追射 皆不能中 於是 有一衞士 疾馳先萬。而伏河側 擬射中膝 萬卽拔箭 張弓發箭 伏地而號曰 萬爲天皇之楯 將效其勇 而不推問 翻致逼迫於此窮矣 可共語者來 願聞殺虜之際 衞士等競馳射萬 萬便拂捍飛矢 殺三十餘人 仍以持劒 三截其弓 還屈其劒 投河水裏 別以刀子 刺頸死焉 河內國司 以萬死狀 牒上朝庭 朝庭下苻稱 斬之八段 散梟八國 河內國司 卽依苻旨 臨斬梟時 雷鳴大雨
爰有萬養白犬 俯仰𢌞吠於其屍側 遂嚙舉頭 收置古冢 横臥枕側 飢死於前 河內國司 尤異其犬 牒上朝庭 朝庭哀不忍聽 下苻稱曰 此犬世所希聞 可觀於後 須使萬族 作墓而葬 由是 萬族 雙起墓於有眞香邑 葬萬與犬焉 河內國司言 於餌香川原 有被斬人 計將數百 頭身既爛 姓字難知 但以衣色 收取身者 爰有櫻井田部連膽渟所養之犬 嚙續身頭 伏側固守 使收己主、乃起行之
物部守屋大連(もののべのもりやのおほむらじ)の資人(つかひびと)捕鳥部万(ととりべのよろず)【万(よろず)は名なり】、一百人(ももたりのひと)を将(ひきゐ)て、難波(なには)の宅(いへ)を守る。而(しかう)して大連滅びぬと聞きて、馬に騎(の)りて夜(よる)逃げて、茅渟県(ちぬまのあがた)の有真香邑(ありまかむら)に向(ゆ)く。仍(よ)りて婦(め)が宅(いへ)を過ぎて、遂(つひ)に山に匿(かく)る。朝庭(みかど)議(はか)りて曰(い)はく、「万、逆心(さかしまなるこころ)を懐けり。故、此の山の中に隱る。早(すみやか)に族(やから)を滅すべし。な怠りそ」といふ。万、衣裳(きもの)幣(や)れ垢(あか)つき、形色(かほ)憔悴(かし)けて、弓を持ち剣(つるぎ)を帯(は)きて、独(ひと)り自(みづか)ら出(い)で来(きた」)れり。有司(つかさ)、数百(ももあまり)の衛士(いくさびと)を遣(つかは)して万を囲(かく)む。万、即(すなは)ち驚きて篁藂(たかぶる)に匿(かく)る。縄(なは)を以て竹に繋(つ)けて、引き動(うごか)して他(ひと)をして己(おの)が入(い)る所を惑(まど)はしむ。衛士等、詐(あざむ)かれて、搖(あゆ)く竹を指(さ)して馳(は)せて言(い)はく、「万、此(ここ)に在り」といふ。万、即ち箭(や)を発(はな)つ。一(ひと)つとして中(あた)らざること無し。衛士等(いくさびとら)恐りて敢(あ)へて近つかず。万、便(すなは)ち弓を弛(はづ)して腋(わき)に挾(かきはさ)みて、山に向ひて走(に)げ去(ゆ)く。衞士等、即ち河(かは)を夾(はさ)みて追ひて射る。皆中(あ)つること能(あた)はず。是に、一(ひとり)の衛士有りて、疾(と)く馳せて万に先(さきだ)ちぬ。而(しかう)して河の側(かたはら)に伏(ふ)して、擬(さしまかな)ひて膝に射中(いあ)てつ。万、即ち箭(や)を抜(ぬ)く。弓を張りて箭を発(はな)つ。地(つち)に伏して号(よば)ひて曰(い)はく、「万は天皇(すめらみこと)の楯(みたて)として、其の勇(いさみ)を效(あらは)さむとすれども、推問(と)ひたまはず。翻(かへ)りて此(こ)の窮(きはまり)に逼迫(せ)めらるることを致しつ。共に語るべき者(ひと)来れ。願はくは殺し虜(とら)ふることの際(わきだめ)を聞かむ」といふ。衛士等、競(きほ)ひ馳(は)せて万を射る。万、便(たちまち)に飛ぶ矢を払(はら)ひ捍(ふせ)きて、三十余(みそあまり)人を殺す。仍(なほ)、持たる剣(つるぎ)を以(も)て、三(みきだ)に其の弓を截(うちき)る。還(また)、其の剣を屈(おしま)げて、河水裏(かはなか)に投(なげい)る。別(こと)に刀子(かたな)を以て、頸(くび)を刺して死ぬ。河内国司(かふちのくにのみこともち)、万の死ぬる状(ありさま)を以て、朝庭(みかど)に牒(まう)し上(あ)ぐ。朝庭、苻(おしてふみ)を下(くだ)したまひて称(のたま)はく、「八段(やきだ)に斬(き)りて、八(や)つの国に散(ちら)し梟(くしさ)せ」とのたまふ。河内国司、即ち苻旨(おしてふみのむね)に依りて、斬り梟す時に臨(のぞ)みて、雷(いかづち)鳴り大雨(ひちさめ)ふる。
爰(ここ)に万が養(か)へる白犬(しらいぬ)有り。俯(ふ)し仰(あふ)ぎては其の屍(かばね)の側(ほとり)を廻(めぐ)り吠(ほ)ゆ。遂(つひ)に頭を嚙(く)ひ挙(あ)げて、古冢(ふるはか)に收(をさ)め置く。横(よこさま)に枕の側(かたはら)に臥(ふ)して、前(まへ)に飢ゑ死ぬ。河内国司、其の犬を尤(とが)め異(あやし)びて、朝庭(みかど)に牒(まう)し上ぐ。朝庭、哀不忍聴(いとほしが)りたまふ。苻(おしてふみ)を下したまひて称(ほ)めて曰(のたま)はく、「此の犬、世に希聞(めづ)らしき所なり。後に観(しめ)すべし。万が族(やから)をして、墓を作りて葬(かく)さしめよ」とのたまふ。是(これ)に由(よ)りて、万が族、墓を有真香邑(ありまかのさと)に双(なら)べ起(つく)りて、万と犬とを葬(かく)しぬ。河内国司言(まう)さく、「餌香川原(ゑがのかはら)に、斬(ころ)されたる人(ひと)有り。計(かぞ)ふるに将(まさ)に数百(ももあまりばかり)なり。頭身(かしらむくろ)既に爛(ただ)れて、姓(かばね)字(な)知り難(かた)し。但(ただ)衣(きもの)の色を以て、身(むくろ)を收め取る。爰に桜井田部連(さくらゐのたべのむらじ)胆渟(いぬ)が養(か)へる犬有り。身頭(むくろ)を嚙ひ続けて、側(かたはら)に伏して固く守る。己(おの)が主(あるじ)を收めしめて、乃(すなは)ち起(た)ちて行(ゆ)く」とまうす。
資人は、近侍者、捕鳥部は鳥取部。難波宅については、四天王寺御手印縁起に居宅三箇所とあり、摂津志、東生郡の条に「森村に守屋大連の難波の第址有り」とみえるが確かでない。有真香(ありまか)邑は、延喜神名式、和泉郡条にみえる阿理莫(ありまか)神社(延喜式内神社)の所在地(貝塚市久保)と注される。万(よろづ)は有真香邑の出身で婦がそこに居たのであらう。阿里莫神社の祭神は饒速日命、継体天皇元年に神社を創立した阿理莫公であり、物部系の豪族であった。婦に別れを告げて山に隠れた。万は天皇の楯となって仕へた勇士であり、弓の名手であり、怪力の持ち主であり、忠誠心も旺盛であったと思はれる。逆賊とされたことが信じられない気持があり、心が揺れていた。反逆の心は無かったため、戦わずして有真香邑に帰った。山に隠れたものの、忠誠心に変はりはない。それをあきらかにせんと、申し出やうとしたところ、朝廷は山に隠れたことに逆心ありと数百人の衛士を送り込んできていた。驚いた万は篁藂(たかぶる=たかむら、竹群、竹やぶ)に隠れた。竹に縄を結びあちこちの竹を揺らし、居場所をくらませ、矢を射かけた。百発百中の腕前で衞士等は恐れて近づくことが出来なかった。
万は弓の弦をゆるめ腋に抱へて、河を渡り、河に沿って山に向かって逃げた。衞士等が矢を放ったが当たらなかった。一人の衛士が先回りして河の側に伏せて矢をつがえて万の膝を射当てた。万は矢を抜き、弓の弦を張り、応戦し、地に伏せて叫んだ。万が天皇の楯として、勇を奮おうとしたことをだうして聞かないのか。まるで逆に追い詰められることをしたといふ。話の分かる者はいないのか。殺さうといふのか、捕へて調べやうとするのか、だうなんだ。追ひついてきた衛士等は問答無用と射かけてきた。万は、飛んでくる矢を払い防いで、逆に三十人を殺した。竹やぶで多くを殺め、ここでは三十人、これでは、もはや申し開きは出来ない。万は我に返り、手にしていた剣で弓を三つに切り、剣を曲げるといふから怪力である、河の中に投げ入れ、ここで戦ったことは本意ではないことを示し、別の小刀で首を刺した。かくなることに勇を奮った運命を呪ったことであらう。
牒は、この場合国司から朝廷に提出した文書、苻は朝廷から国司に出した文書、八段に斬りとある、手足四段、腰、腹、胸、頭四段とでもなるのか、八国に送って串刺しにしてさらせといふ残忍なものであった。あまりに多くの衛士等を殺したことか、不忠きわまりなしとしたのか?河内で万を斬り梟(くしさ)すと、雷が鳴り大雨がふった。天が声を荒げて涙を流した。
だうやら八段斬りには及ばなかったやうである。万の飼っていた白犬が屍を守り、頭をくはへ古冢に運び入れ、その側らに伏せたまま餓死した。万にしてこの白犬あり、それは天皇の楯たる万の姿そのものであった。犬は主人に似る。これが朝廷を動かした。万の族に墓を造って葬ることを許し、万と犬は有真香邑にならべて葬られた。和泉志、泉南郡阿間河荘の条に、「捕鳥部万の墓は、八田村に在り。狗の墓は万の墓の北に在り」とあるが後世の付会であらう、と注される。このことは、余程印象深い出来事であったやうで、平成の世にも伝へられている(天神山古墳群と捕鳥部万|天璽瑞宝)。
餌香川は、河内国古市郡の恵我川、石川が古市郡で恵我川となり、志紀郡を経て大和川に注ぐ、と注される。この位置であれば、守屋に追いたてられた蘇我連合軍側の兵士とならうか。衣の色でもって遺体を収容せざるを得ないほど腐乱していた。櫻井田部連膽渟(いぬ)の飼っていた犬が数百の遺体を守り続け、遺体がその主に収容されると立ち去ったといふ。忠犬が何故登場してくるのか?この動乱にあって、守屋が逆賊となったが、まさに勝てば官軍の様相、天皇は不在であり、天皇の楯であった万が逆賊とされる世であった。馬子の言が詔と記される危い世であり、犬の忠誠心が際立ってみえたのであらう。守屋といふよりは天皇に忠を尽くさんとした万が逆臣となり自ら首を刺す、そのおどろしく、おぞましき政治の犠牲者であり、政治を私する恐ろしさを暗示するものとなった。
八月癸卯朔甲辰 炊屋姬尊與群臣 勸進天皇 卽天皇之位。以蘇我馬子宿禰爲大臣如故 卿大夫之位亦如故
是月 宮於倉梯
八月(はつき)の癸卯(みづのとのう)の朔(ついたち)甲辰(きのえたつのひ)(08.02)に、炊屋姫尊(かしきやひめのみこと)と群臣(まへつきみたち)と、天皇を勧(すすめる)め進(たてまつ)りて、即天皇之位(あまつひつぎしろしめ)さしむ。蘇我馬子宿禰を以て大臣とすること故(もと)の如し。卿大夫(まへつきみたち)の位、亦故の如し。
是の月に、倉梯に宮つくる。
全く奇妙な文である。天皇とは誰なのか。誰を即位させたのかが記されていない。泊瀨部天皇(崇峻天皇)紀であるから、天皇は泊瀨部天皇であるとならうが、本来は、「即天皇之位(あまつひつぎしろしめ)す」であるが、「即天皇之位(あまつひつぎしろしめ)さしむ」と訓じており、即位させたことになる。(物部守屋大連、中臣勝海連に連なる者を除き)群臣を元の役職に就かしめた、ともあり、炊屋姫尊と群臣とが主語となっているが、これは経緯からすれば馬子と炊屋姫尊とのシナリオ、もっといへば、馬子のシナリオであった。しかし、あくまでも炊屋姫尊と群臣との合意で為さしめたことと記した。
倉梯は、上之宮から多武峰(談山神社の地)に向かう途中の倉橋(桜井市倉橋:地図)とされ、山腹にある。難波、半島を考へれば何故この地に宮をつくったのかが不可解である。政治のための宮ではあるまい。まるで、山中に追いやられた観すら感じさせる。
元年春三月 立大伴糠手連女小手子爲妃 是生蜂子皇子與錦代皇女
是歲 百濟國遣使幷僧惠總、令斤、惠寔等 獻佛舍利 百濟國遣恩率首信、德率蓋文、那率福富味身等 進調幷獻佛舍利 僧聆照律師、令威、惠衆、惠宿、道嚴、令開等 寺工太良未太、文賈古子、鑪盤博士將德白昧淳 瓦博士麻奈文奴、陽貴文、㥄貴文、昔麻帝彌 畫工白加 蘇我馬子宿禰 請百濟僧等 問受戒之法 以善信尼等 付百濟國使恩率首信等 發遣學問 壞飛鳥衣縫造祖樹葉之家 始作法興寺 此地名飛鳥眞神原 亦名飛鳥苫田 是年也 太歲戊申
元年(はじめのとし)の春三月(やよひ)(588.03)に、大伴糠手連(おほとものあらてのむらじ)が女(むすめ)小手子(こてこ)を立てて妃(みめ)とす。是(これ)蜂子皇子(はちのこのみこ)と錦代皇女(にしきてのひめみこ)とを生(う)めり。
是歳(ことし)、百済国(くだらのくに)、使(つかひ)幷(あはせ)て僧(ほふし)惠総(ゑそう)・令斤(りやうこん)・惠寔等(ゑしよくら)を遣(まだ)して、仏(ほとけ)の舍利を獻る。百済国、恩率(おんそち)首信(すしん)・徳率(とくそち)蓋文(かふもん)・那率(なそち)福富味身等(ふくふみしんら)を遣して、調(みつき)進(たてまつ)り、幷て仏の舍利(しやり)、僧、聆照律師(りやうせうりつし)・令威(りやうゐ)・惠衆(ゑしゆ)・惠宿(ゑしゆく)・道嚴(だうごむ)・令開等(りやうけら)、寺工(てらたくみ)太良未太(だらみだ)・文賈古子(もんけこし)・鑪盤博士(ろばんのはかせ)将徳(しやうとく)白昧淳(はくまいじゆん)、瓦博士(かはらのはかせ)麻奈文奴(まなもんむ)・陽貴文(やうくゐもん)・㥄貴文(りようくゐもん)・昔麻帝彌(しやくまたいみ)、畫工(ゑかき)白加(びやくか)を獻る。蘇我馬子宿禰(そがのうまこのすくね)、百済の僧等(ほふしたち)を請(ま)せて、戒(い)むことを受くる法(のり)を問ふ。善信尼等(ぜんしんのあまたち)を以て、百済国の使(つかひ)恩率(おんそち)首信等(すしんら)に付(さづ)けて、學問(ものならひ)に發(た)て遣(つかは)す。飛鳥衣縫造(あすかきぬぬひのみやつこ)が祖(おや)樹葉(このは)の家(いへ)を壊(こぼ)ちて、始めて法興寺(ほふこうじ)を作る。此の地を飛鳥の真神原(まかみのはら)と名(なづ)く。亦は飛鳥の苫田(とまた)と名づく。是年、太歳戊申(つちのえさる)。
大伴糠手連は、渟中倉太珠敷天皇(敏達天皇)十二年(583年)に、日羅を吉備児嶋屯倉に迎へる使者となったことがあった。天皇はその女(むすめ)を「立てて妃とす」とある。普通なら、「立てて皇后とす」となるべきところである。天皇名が言及されず妃といふのが、小手子の立場であった。炊屋姫尊と蘇我馬子は皇后とすることをよしとしなかったのであらうか。ならば、泊瀬部皇子がかねてから妻としておられた女(むすめ)であったかもしれない。いづれにせよ、奇妙な表現である。
物部守屋や中臣勝海が滅ぼされ、仏法の導入に拍車がかかった。百済より官人と僧の混成使節に、寺院建築工2名、露盤博士、瓦博士4名、画工が派遣されてきた。僧を”ほふし:法師”と訓じている。渟中倉太珠敷天皇(敏達天皇)六年条(書紀巻20)に、「百済国の王、還使大別王等に付けて、経論若干卷、幷て律師・禅師・比丘尼・呪禁師・造仏工・造寺工、六人を献る。遂に難波の大別王の寺に安置らしむ」とあった。戒律に詳しい僧侶を律師、禅定修行に長けた者を禅師と云ふ。渟中倉太珠敷天皇主導で行はれたが、大別王の所に留め置かれたやうで、それ以上の進展はなかった。廃仏派の反対を押し切ってまで導入する意志はなかったとみえる。また、馬子との連携もなかった。導入には馬子の政治力を必要とした。同十三年条に、馬子が仏殿を宅の東に作り、石像を安置し、高麗の恵便を師とし、善信尼・禅蔵尼・恵善尼の三尼を以て始めており、尼寺がそのスタートであった。
今回の僧恵総・令斤・恵寔等は、比丘尼ではなく仏法を教える法師であった。恵X、令Xとする門人であらうか、律師も含まれている。百済の冠位は、「佐平は1品、達率は2品、恩率は3品、徳率は4品、玕率は5品、奈率(那率)は6品、將徳は7品、施徳は8品、固徳は9品、季徳は10品、大徳は11品、文督は12品、武督は13品、佐督は14品、振武は15品、克虞は16品」となる。
寺工といふは、寺の全体的な構成、各建築物の構造を設計できる人材であらう。出家であり、まず俗界と隔てる塀が巡らされ、出入り口が限定され、山門が設置される。仏舎利をまつる仏塔と仏を安置する仏殿を如何に構成し、僧や比丘尼の住居、修行する講堂、会堂・食堂・台所・貯蔵室・流し場・便所といふ施設をだう配置し、どのやうな規模、建築法を用いるか、それを指導できる人材である。露盤博士は、塔の相輪を制作する技術者である。本来は日差しが強いインドで釈迦の傘蓋であるが、塔のてっぺんに方形の露盤を設置し、伏鉢、受花の上に輪を積み重ね水煙(火煙)、竜車、宝珠を据え付ける。当時の屋根は板とか萱を葺いたもので、瓦を載せるとなると、瓦を制作する技術もさることながら、その重量に耐える構造の習得を必要とした。瓦の制作には須恵器を造る職人が動員され技術を習得せしめたとされる。画工は絵を描くのみならず、建物や仏像の彩色、顔料や染料に関する技術ももたらしたのであらう。すでに、呪禁師・造仏工・造寺工に言及されており、呪禁師は中臣勝海の厭(まじない)、禁厭法でみたやうなものの中国版で、鬼や魔物、猛獣、毒虫等の害の侵入を阻止し、すでに入っておればそれを追い出し、再度入らぬやうにバリアを張るやうな術であらう。造仏は木造、石造、鋳造とならう、鋳造は後のことであらうが、鋳造技術を取り入れることは、諸々の器具を造るにおいても必要とされた。
馬子は仏道全般を学ばせるために、善信尼等の留学を推し進め、一方、法興寺を建設するといふことで具体的にこれらの人々を用い実をあげやうとした。飛鳥衣縫造は大泊瀬幼武天皇(雄略天皇)十四年条の漢人、衣縫弟媛による漢衣縫部にはじまり、皇室や神職の衣裳を縫ってきたものである。その家を壊して、寺とする、その地を真神原(まかみのはら)といったやうで、これでは、寺は建てにくいので、苫田(とまた)とした(冗談)。法興寺とは仏法を興す寺の義であるが、その地から飛鳥寺(地図)とも称される。万葉集に、
三諸(みもろ)の 神なび山ゆ とのぐもり 雨は降りきぬ 雨霧(き)らひ 風さへ吹きぬ 大口の 真神原(まがみがはら)ゆ 思(しの)びつつ 帰りにし人 家に到りきや
(詠み人しらず 巻一三・三二六八)
三輪山から雲りだし、雨が降ってきた。雨が霧となり、風さえ吹いてきた。大口の真神原から、(私を)思びお帰りになられたあの人は、もう家に着かれただらうか。 妻問いをして帰っていった夫の無事を気遣った歌。大口は開けた河口、真神原は狼の原、あるいは曲瀬の原といひ、この妻の住むところ。
苫田とは茅の生えた荒地のことで、この地は飛鳥川の流れる盆地であり、渡来人が開発をしてきた地でもあった。飛鳥寺の寺域は、南門から伸びる築地塀と東・西・北で発掘された掘立柱塀に囲まれた東西215m、南北293mに及ぶ(奈良県明日香村 飛鳥寺西方遺跡)。馬子がこの荒地に目をつけて、この規模の寺域を持つ仏法の拠点を築くとなれば、ひとつの宮を造営するに等しい。驚くべき構想力と決断、忍耐力の持ち主である。その位置関係については、「古寺巡訪、飛鳥寺」に詳しい。
百済はかねてより北周に朝貢していたのですが、北周の静帝の摂政であった随国公楊堅が581年に静帝から禅譲により隋を建国すると、早々に朝貢したところ、隋文帝(楊堅)は威徳王を上開府・儀同三司・帯方郡公に冊命しています。百済は同じく陳にも朝貢していましたが、589年隋(随から隋に変更)が陳を平定したおり、隋の一戦船が耽牟羅国(済州島)に漂着し、威徳王はこれを援助し、使者を送り、陳を平定したことを祝賀し、文帝はこれを高く評価したとあります。598年に隋が高句麗討伐の軍を起こすと聞くと百済は先導を申し出、百済は高句麗との対抗上隋の支援を必須としていたのでしょう。この際は高句麗が服し戦とはなりませんでしたが、高句麗はこのことを知り、百済の国境を侵掠ています。
楊堅は陝西省(関)・甘粛省(隴)、関隴地方の武川鎮の出身の将軍でした。北魏が平城を首都としていた時、柔然から防衛するため匈奴や鮮卑系の名族を移住させ六鎮が設置され、武川鎮はその一つでした。北魏の孝文帝が武力による防衛から漢化政策に転じ、都を平城から洛陽に遷都したことで、六鎮は見捨てられた形となりました。六では不満が高まり、鎮の乱が起り、北魏は懐朔鎮出身の高歓による東魏(後の北斉)と武川鎮出身の宇文泰による西魏(後の北周)に分裂しました。
宇文泰は、名望ある豪族を「郷帥」とし、郷兵を募り、二十四の郷兵部隊を編成し、その戸籍を軍府(儀同府)に移し府兵としました(府兵制)。これを十二軍に再編し、建国に功名あった八人の将軍(八柱国)に統率させ、楊堅はその一人でした。鮮卑の名族に軍を統率させる一方、農業振興のため漢人儒士を用い均田制を復活させ、租税収入を安定させようとしました。国号を周(北周)と号(なづ)けた如く、周礼による官制改革を目指しました。
静帝から禅定を受けた楊堅(文帝)は陳の併合を目指しました。陳を攻めるには長江を渡らねばならず、兵站を支える強大な輸送船力を力を要し、長江はいわば自然の要塞となっていました。文帝は長安の近くに大興城を建設し、584年に長安と黄河を結ぶ広通渠(運河)を完成させ、中原で生産される食糧輸送の円滑化を図り、更に、587年には、淮水(わいすい)と長江沿いの江都を結ぶ山陽瀆(とく)、別名邗溝(かんこう)を完成させ、物資のみならず、大軍の輸送を可能にしました。これにより、588年に長江の八方面から51万8千の大軍を渡河させ、陳の建康を陥落させることに成功し、南北の分裂を収拾させることになりました。
鮮卑等いわゆる胡人(北方、西方民)と漢人の融合(胡漢融合)の国家を建設する局面となります。胡人、漢人にかかわらず優秀な人材を登用し、中央集権を機能させねばなりません。魏の時に優秀な人材を郷から登用するため、九品中正の制度が採用されました。優秀さに九等級を定め、郷品で二品と定められた者は中央では四等級下の六品から始め二品まで昇進できるという人材登用制度でした。しかし、西晋の頃は「上品に寒門無く、下品に勢族なし」、寒門(貧困層)で上品がなく、下品に勢族(富裕族)なしという門閥貴族偏重に陥っていたとあります。この弊害を取り除くために、儒学経典(易・書・詩・礼・楽・春秋)の学科試験による「科挙」のシステムが採用されました。
中央では、皇帝の詔勅を起案する中書省、それを審議し決定する門下省、それを実施する尚書省とする政策決定と実施のシステムが導入され、る尚書省には六部(吏部・戸部・礼部・兵部・刑部・工部)が置かれる中央集権律令制度が採られ、科挙試験に合格したものを官吏に登用しました。
その一方で文帝は自らを「菩薩戒仏弟子皇帝」と称し、601、602、604年に舎利塔起塔事業を行っています。北斉は仏教治国の政策をとり、都の鄴には4千の寺、8万の僧がおり、、仏教教団を管理する中央の役所である「昭玄寺に大統 一人、統 一人、都維那三人をおいて、功曹 ・主簿員を置きも って諸州、郡、県の沙門曹を管轄する(隋書巻27百官志)」という仏教治国でした。北斉を倒した北周は儒学を主とし、廃仏政策であり、北斉の仏教関係者には不満がありました。文帝は大興城や運河の建設で北斉人を動員したこともあり、舎利塔起塔事業に北斉系の僧侶を優遇しており、統治におけるバランス、多様性を重視したのでしょう。
南北が統一されるということは、半島国にとっては漢や魏により併合された記憶が蘇ります。特に陸伝に攻め込まれる高句麗は警戒心を高めることとなりました。
かやうな情勢の変化は百済から派遣された僧を通じて天皇や側近に伝へられていたことでしょう。蘇我馬子が百済に学問尼、善信等を派遣したのは、仏教の導入はもとより、大陸で起こっていることの実情、百済、新羅、高句麗がどのように動き出すかをさぐるものでもあったと思はれます。百済、新羅、高句麗からすれば、倭(やまと)が大陸と如何なる関係を結ぼうとするかを探ることともなります。
二年秋七月壬辰朔 遣(つかはす)近江臣滿於東山道使 觀蝦夷國境 遣宍人臣鴈於東海道使 觀東方濱海諸國境 遣阿倍臣於北陸道使 觀越等諸國境
二年の秋七月(ふみづき)の壬辰(みづのえたつ)の朔(ついたちのひ)(589.07.01)に、近江臣満(あふみのおみみつ)を東山道(やまのみち)の使に遣(つかは)して、蝦夷(えみし)の国の境(さかひ)を観(み)しむ。宍人臣鴈(ししひとのおみかり)を東海道(うみつみち)の使に遣して、東(あづま)の方(かた)の海に浜(そ)へる諸国(くにぐに)の境を観しむ。阿倍臣(あへのおみ)を北陸道(くるがのみち)の使に遣して、越(こし)等(ら)の諸国の境を観しむ。
東山道を辿り蝦夷の国の境、東海道の沿岸の諸国、北陸道の越等の諸国を視察せしめる。近江臣満、宍人臣鴈、阿倍臣が用ゐられた。しかし、彼等はその後あまり役割を果たしていないとみえ、他にみえずと注される。一体何が目的であったのか?全国的な広がりを持った物部氏はその後だうなったのか。守屋と河内の勢力が滅ぼされたからといって物部氏が一夜で消えてなくなるものではない。
蘇我氏は軍事的な展開力を持たない。大伴氏にはあったが、金村失脚以降は精彩を欠いていた。大伴氏も今や蘇我氏あってのことである。近江臣満、宍人臣鴈、阿倍臣をもって視察せしめたとしても、天皇のもとに再編を行ふことはできまい。結局、国の境を観るといふ差し障りのない表現に終わっている。
馬子は飛鳥にこれまで見たことのないやうな都を築くための遠大な構想に没頭しているかのやうにみえる。天皇はその隙間をみて、自らの勢力を築かうとされたのかもしれない。
三年春三月 學問尼善信等 自百濟還 住櫻井寺
冬十月 入山取寺材
是歲 度尼 大伴狹手彦連女善德、大伴狛夫人、新羅媛善妙、百濟媛妙光 又漢人善聰、善通、妙德、法定照、善智聰、善智惠、善光等 鞍部司馬達等子多須奈 同時出家 名曰德齊法師
三年の春三月(やよひ)(590.03)に、学問尼(ものならひのあま)善信等(ぜんしんら)、百済より還(かへ)りて、桜井寺(さくらゐでら)に住(はべ)り。
冬十月(かむなづき)に、山に入りて寺の材(き)を取る。
是歳(ことし)、度(いへで)せる尼(あま)は、大伴狹手彦連(おほともさでひこのむらじ)が女(むすめ)善徳(ぜんとく)・大伴狛(おほとものこま)の夫人(いろえ)・新羅媛善妙(しらきひめぜんめう)・百済媛妙光(くだらひめめうくわう)、又漢人(あやひと)善聡(あやひとぜんそう)・善通(ぜんつう)・妙徳(めうとく)・法定照(ほふぢやうせう)・善智聡(ぜんちそう)・善智恵(ぜんちゑ)・善光等(ぜんくわうら)。鞍部司馬達等(くらつくりしめだちと)が子(こ)多須奈(たすな)、同時(もろとも)に出家(いへで)す。名(なづ)けて徳齊法師(とくさいほふし)と曰(い)ふ。
桜井寺は向原寺(地図)。天国排開広庭天皇(欽明天皇)十三年条に、蘇我稲目が百済聖明王からの釈迦仏の金銅像を置くために向原の家を浄捨して寺としたとあった。馬子はこの向原寺を尼寺とし、そこから飛鳥川沿いに甘樫丘の北側の麓を回り南上すること200m、そこから東200mくらいに僧寺、飛鳥寺を建設しやうとしていた。十月に材木の調達を始めた。
天国排開広庭天皇(欽明天皇)二十三年八月条に、大将軍大伴連狹手彦が高句麗を討ち、美女(をみな)媛(ひめ:名前)と其の從女(まかだち)吾田子(あたこ)を蘇我稻目に送り、稲目がこれを妻としたとあった。大伴狛の夫人とは高句麗の夫人の義であり、狹手彦は、女(むすめ)と高句麗人の夫人を尼にした。狹手彦は金村の子であり、大伴氏は馬子と歩調を合はせたことになる。これに新羅の媛、百済の媛、漢人の女(むすめ)等が出家した。そして鞍部司馬達等の子が出家し、僧を目指した。馬子は、このことで頭が一杯であったやうにみえる。
かやうな姻戚関係からすれば、百済のみならず、高句麗も新羅も倭の群臣がどのやうな意向であるかを知る意味でも必要なものであったのでしょう。
四年夏四月壬子朔甲子 葬譯語田天皇於磯長陵 是其妣皇后所葬之陵也
秋八月庚戌朔 天皇詔群臣曰 朕思欲建任那 卿等何如 群臣奏言 可建任那官家 皆同陛下所詔
冬十一月己卯朔壬午 差紀男麻呂宿禰、巨勢猿臣、大伴囓連、葛城烏奈良臣 爲大將軍 率氏々臣連 爲裨將、部隊 領二萬餘軍 出居筑紫 遣吉士金於新羅 遣吉士木蓮子於任那問任那事
四年の夏四月(うづき)の壬子(みづのえね)朔(ついたち)甲子(きのえねのひ)(591.04.13)に、訳語田天皇(をさたのすめらみこと)を磯長陵(しながのみさざき)に葬(はぶ)りまつる。是(これ)其の妣皇后(いろはのきさき)の葬られたまひし陵(みはか)なり。
秋八月(はつき)の庚戌(かのえいぬ)の朔(ついたちのひ)(08.01)に、天皇(すめらみこと)、群臣(まへつきみたち)に詔(みことのり)して曰(のたま)はく、「朕(われ)、任那(みまな)を建(た)てむと思ふ。卿等(いましたち)何如(いか)に」とのたまふ。群臣奏(まう)して言(まう)さく、「任那の官家(みやけ)を建つべきこと、皆陛下(きみ)の詔したまふ所に同じ」とまうす。
冬十一月(しもつき)の己卯(つちのとのう)の朔(ついたち)壬午(みづのえうまのひ)(11.04)に、紀男麻呂宿禰(きのをまろのすくね)・巨勢猿臣(こせのさるのおみ)・大伴囓連(おほとものくひのむらじ)・葛城烏奈良臣(かづらきのをならのおみ)を差(さ)して、大将軍(おほきいくさのきみ)とす。氏々(うぢうぢ)の臣連(おみむらじ)を率(ゐ)て、裨将(つぎのいくさのきみ)・部隊(たむろのをさ)として、二万余(ふたよろづあまり)の軍(いくさ)を領(ゐ)て、筑紫(つくし)に出(い)で居(ゐ)る。吉士金(きしのかね)を新羅に遣(つかは)し、吉士木蓮子(きしのいたび)を任那(みまな)に遣して、任那の事を問はしむ。
訳語田天皇とは、渟中倉太珠敷天皇(敏達天皇)のこと、何故、渟中倉太珠敷天皇とせず訳語田天皇とされたのか。十四年(585年)に崩御され、殯宮を広瀬に営まれ、それ以降音沙汰がなかった。また、妣皇后の陵に葬られたといふ異様な状態である。妣皇后とは渟中倉太珠敷天皇の亡くなられた母、石姫。これはまともな話ではあるまい。渟中倉太珠敷天皇を一代の天皇ではなく、石姫の子、訳語田に宮をおかれた天皇として葬った。おそらく、関係者のみで公にされることなく、執り行はれたのであらう。本来なら押坂彦人大兄皇子を立てて陵を造営すべきであるが、その押坂彦人大兄皇子の存在そのものが消えたまま、言及がない。当時の人には周知のことであったらうが、平成の人間には闇の中、書紀の編纂者達はかやうな微妙な表現しか残さなかった。延喜諸陵式に、「河内磯長中尾陵<訳語田宮御宇敏達天皇 在河内国石川郡>」とあり、陵墓要覧では所在地を大阪府南河内郡太子町大字太子奥城(太子町葉室:地図)とする、と注される。馬子ではなく、天皇(泊瀨部天皇:崇峻天皇)が無念の思ひを秘めてこれを執り行はれたのかもしれない。
天皇(天皇のみで、泊瀨部天皇とは記されない)は、一転して、天国排開広庭天皇(欽明天皇)、渟中倉太珠敷天皇(敏達天皇)の意志を継ぐといふことであらう、「朕、任那を建てむと思ふ。卿等何如に」と群臣の反応を試してみた。意外にも群臣が賛同した。馬子のやり方をよしとしない人々にとって、軍事は馬子の弱点であり、軍事を伴ふ外交となれば、その手が及ばない、その意味では天皇は絶妙の選択をされた。
任那を滅ぼした新羅を討つといふことであれば、新羅、高句麗の圧迫を受けていた百済の望むところであり、馬子も反対ができない。紀男麻呂宿禰・巨勢猿臣・大伴囓連・葛城烏奈良臣を大将軍とし、この分野においては、彼等は馬子の指揮下から離れて行動をすることが出来る。八月に発議し、十一月には二万余の軍が筑紫に出ており、新羅と任那に使いを派遣するといふスピードぶりである。馬子はさぞ驚いたことであらう。ただ吉士の派遣は、渟中倉太珠敷天皇四年四月(575.04.)に、「吉士金子を遣して、新羅に使せしむ。吉士木蓮子を任那に使せしむ。吉士譯語彦を百済に使せしむ」とあり、これがそのまま引用されており、実行されたものとは思ひ難い。
591年の時点では、隋が陳を滅ぼし、南北が統一され、威徳王が隋より上開府・儀同三司・帯方郡公に冊命されたことは伝はっていたことでしょう。高句麗平原王は、「王は陳が亡(ほろ)ぶを聞き大きに懼(おそ)る。兵(器)を(修)理し、穀を積み拒守の策を為す。隋高祖は王に璽書(詔書)を賜ひ、責めるに以て藩附(藩屛)を称すと雖も、誠節を未だ盡さず 三國史記卷第十九 高句麗本紀第七 平原王三十二590年年 国会図書館 100/259」と責められ、隋に従はねば一将軍を派遣すれば事足りると脅されたとある。新羅は589年までは陳に高僧を派遣し仏教を導入しており、隋による統一に慌てたことでしょう。594年に新羅の真平王は上開府・楽浪郡公・新羅王に冊命されており、高句麗の状況に鑑み急遽隋に朝貢を重ねたのでしょう。かやうな事態で任那を復す、半島に派兵する二万の兵を筑紫に集結させたとあります。
書紀からすれば、新羅を討ち任那を復興するとならうが、さやうな問題では無い。任那を維持できなかった原因は、雄略天皇が半島進出を為した葛城や吉備の勢力を討ったことで、半島での軍事制圧力が弱体化したことにあった。任那崩壊の発端は、北から高句麗に押し込まれた百済が南下せざるをえず、任那の上哆唎(おこしたり)、下哆唎(あろしたり)、娑陀(さだ)、牟婁(むろ)の四県を自国領とすることを継体政権に要望したことによる。政権基盤が弱く、半島での軍事勢力も劣化しており、継体政権がこれを認めたことが発端であった(書紀巻17)。その地域の安定を百済に委ねることをやむなしとした。これに反発した伴跛(はへ)が己汶(こもん)に攻め込み、百済がその返還を継体政権に求め、継体政権が百済の要望を容れて返還せしめたことで、伴跛が己汶に攻め入り、収拾がつかなくなった。更に伴跛が洛東江方面新羅に面しても城を築き、新羅を攻めたことで、新羅が介入することともなった。
継体政権は百済による事態収拾を求めたが、任那の各勢力は百済に対する反発が強く、任那の日本府では、新羅あるいは高句麗を巻き込み百済を牽制する動きがあり、継体政権は表向きは百済と協調するもいささか傍観的な対応となった。かやうな対応に加羅は新羅により自国を維持しようと梶を切り、新羅の介入が本格化することともなった。政権としては、任那全体の維持よりは、百済を通じて仏教文化や田の管理システム等、統治制度を採り入れることを優先してきた。
その時流に乗っていたのが蘇我氏であった。蘇我馬子にとって、任那の復活などで派兵するなど、実効性はなく、兵力と財を失うばかりであり、百害あって一利なしと映っていたことでしょう。群臣達も半島に派兵して勝利する見通しのないことは分かっていながら賛成し筑紫まで兵をだしており、まるで蘇我氏に対するあてつけのごとき所業にすらみえる。
五年冬十月癸酉朔丙子 有獻山猪 天皇指猪詔曰 何時如斷此猪之頸 斷朕所嫌之人 多設兵仗 有異於常 壬午 蘇我馬子宿禰 聞天皇所詔 恐嫌於己 招聚儻者 謀弑天皇
是月 起大法興寺佛堂與步廊。
十一月癸卯朔乙巳 馬子宿禰 詐於群臣曰 今日進東國之調 乃使東漢直駒 弑于天皇 【或本云 東漢直駒 東漢直磐井子也】 是日 葬天皇于倉梯岡陵 【或本云 大伴嬪小手子 恨寵之衰 使人於蘇我馬子宿禰曰 頃者有獻山猪 天皇指猪而詔曰 如斷猪頸 何時斷朕思人 且於內裏 大作兵仗 於是 馬子宿禰 聽而驚之】 丁未 遣驛使於筑紫將軍所曰(いふ) 依於內亂 莫怠外事
是月 東漢直駒 偸隱蘇我嬪河上娘爲妻) 【河上娘 蘇我馬子宿禰女也】馬子宿禰 忽不知河上娘 爲駒所偸 而謂死去 駒、汙嬪事顯、爲大臣所殺
五年の冬十月(かむなづき)の癸酉(みづのとのとり)朔(ついたち)丙子(ひのえねのひ)(592.10.04)に、山猪(ゐのしし)を献(たてまつ)ること有り。天皇(すめらみこと)、猪(しし)を指(ゆびさ)して詔(みことのり)して曰(のたま)はく、「何(いづれ)の時にか此の猪の頸(くび)を断(き)るが如(ごと)く、朕(わ)が嫌(ねた)しとおもふ所の人を断らむ」とのたまふ。多く兵仗(つはもの)を設(まう)くること、常(つね)よりも異(け)なること有り。壬午(みづのえうまのひ)(10.10)に、蘇我馬子宿禰(そがのうまこのすくね)、天皇の詔したまふ所を聞きて、己(おのれ)を嫌(そね)むらしきことを恐る。儻者(やからひと)を招(を)き聚(あつ)めて、天皇を弑(しい)せまつらむと謀(はか)る。
是(こ)の月に、大法興寺(だいほふこうじ)の仏堂(ぶつだう)と歩廊(ほらう)とを起(た)つ。
十一月(しもつき)の癸卯(みづのとのう)の朔乙巳(きのとのみのひ)(11.03)に、馬子宿禰、群臣(まへつきみたち)を詐(かす)めて曰(い)はく、「今日(けふ)、東国(あづま)の調(みつき)を進(たてまつ)る」といふ。乃ち東漢直駒(やまとのあやのあたひこま)をして、天皇を弑(し)せまつらむ。【或本(あるふみ)に云(い)はく、東漢直駒は、東漢直磐井(やまとのあやのあたひいはゐ)が子(こ)なりといふ】。是(こ)の日に、天皇を倉梯岡陵(くらはしのをかのみさざき)に葬(はぶ)りまつる。【或本に云はく、大伴嬪小手子(おほとものみめこてこ)、寵(めぐみ)の衰(おとろ)へしことを恨(うら)みて、人を蘇我馬子宿禰のもとに使(や)りて曰はく、「頃者(このごろ)山猪を献れること有り。天皇、猪を指して詔して曰はく、『猪の頸を断らむが如く、何の時にか朕が思ふ人を断らむ』とのたまふ。且(また)内裏(おほうち)にして、大きに兵仗(つはもの)を作る」といふ。是(ここ)に、馬子宿禰、聴きて驚くといふ】。丁未(ひのとのひつじのひ)(11.05)に、驛使(はいま)を筑紫将軍(つくしのいくさのきみ)の所(もと)に遣(つかは)して曰はく、「内(うち)の乱(みだれ)に依(よ)りて、外(ほか)の事を莫怠(なおこた)りそ」といふ。
是の月に、東漢直駒、蘇我嬪河上娘(そがのみめかはかみのいらつめ)を偸隠(ぬす)みて妻(めとす。【河上娘は、蘇我馬子宿禰の女(むすめ)なり】。馬子宿禰、忽(たまたま)河上娘が、駒が爲に偸まれしを知らずして、死去(まか)りけむと謂ふ。駒、嬪(みめ)を汙(けが)せる事顕(あらは)れて、大臣の爲に殺されぬ。
実にスピーディーに事が運んでいたといふに、何故か、一年がたった。馬子が何かの遅延工作でも仕掛けたのであらうか。そして、驚くべきことに、「天皇を弑せまつらむと謀る」と大書されている。10月4日の出来事が10日に馬子の耳に入っていた。馬子が先手をうったといふのが公式見解である。
法興寺の仏堂と歩廊を起てた祝いとばかりに、東国の調として天皇を警護すべき武人を進(たてまつ)った。それが馬子の手の内の東漢直駒であった。11月5日に、馬子は「内の亂に依りて、外の事を莫怠りそ」といふ言葉を発している。しかし、推進者であった天皇が崩御されれば派兵はなくなる。11月3日、あるいは4日には、天皇が暗殺されたといふ状況があったのみである。殺された天皇がその日のうちに倉梯岡陵に葬られるといふ異常さであり、一部を除き、周囲では何が起こったのか一切わからない。
天皇の姿が見えず、東漢直駒が姿を消しており、駒に殺されたといふ噂が飛び交う。さうかうしていると馬子の娘、蘇我嬪河上娘が消え、馬子が娘が死んだと騒いでいるといふ話が聞こえて来た。それを追うかの如く、娘は死んでおらず駒に誘拐され汚されていた、怒った馬子が手の者を放って殺したらしい、と噂された。死人に口なし、駒を取り調べることはできなくなった。
将軍達を筑紫に結集させたのは、暗殺を容易にするためであったとする説があると注される。一年の経過は不自然であり、当初からの計画であったとは思へないが、好都合であったことに変はりはない。
或本が何か分からないが、天皇が妃とした大伴の嬪、小手子との破局がこれを招いたとした。しかし、「寵の衰へし」のみでかくなる行動が生まれるものではあるまい。馬子にそれを明かして、小手子に何の益があらう。憎しみ余って馬子に天皇を殺させた、では飛躍がありすぎる。動機が見当たらない。殺すと脅されてさう云ふやうに強要させられたかもしれない。天皇の妃が証人として、馬子が命を狙われたことを証言してくれたといふ記録を残したかったのは、馬子であらう。
駒が「蘇我嬪河上娘を偸隱(ぬす)みて妻とす」とはだういふことか。妻として二人はしばらく一緒に過ごした、と書紀は記した。馬子は「たまたまに娘が偸まれたことを知らず死去した」と云ふ、死体も確認せずに死んだと騒ぎ立てた、妙なことである。そして、娘を汚したとして駒は馬子に殺された。この時代、迹見赤檮といふ暗殺者はその功績を認められ広大な土地を賜はった。駒も馬子にほとぼりが冷めれば悪いやうにしないと言い含められていたかもしれない。
馬子は二人の居場所を知っていた。一夜にして天皇を弑した豪胆な駒を片付けるのは容易なことではない。味方と思っていた者に不意を討たれたのではなからうか。蘇我嬪河上娘の受けた心の傷はいかばかりであったことか。犠牲者である。
馬子を断罪するものはいなかったやうであるが、群臣の心には馬子に対する疑念が渦巻いたことであらう。
2012年10月22日 2025年7月14日更新
岩倉紙芝居館 古典館 日本書紀 21 上田 啓之
.